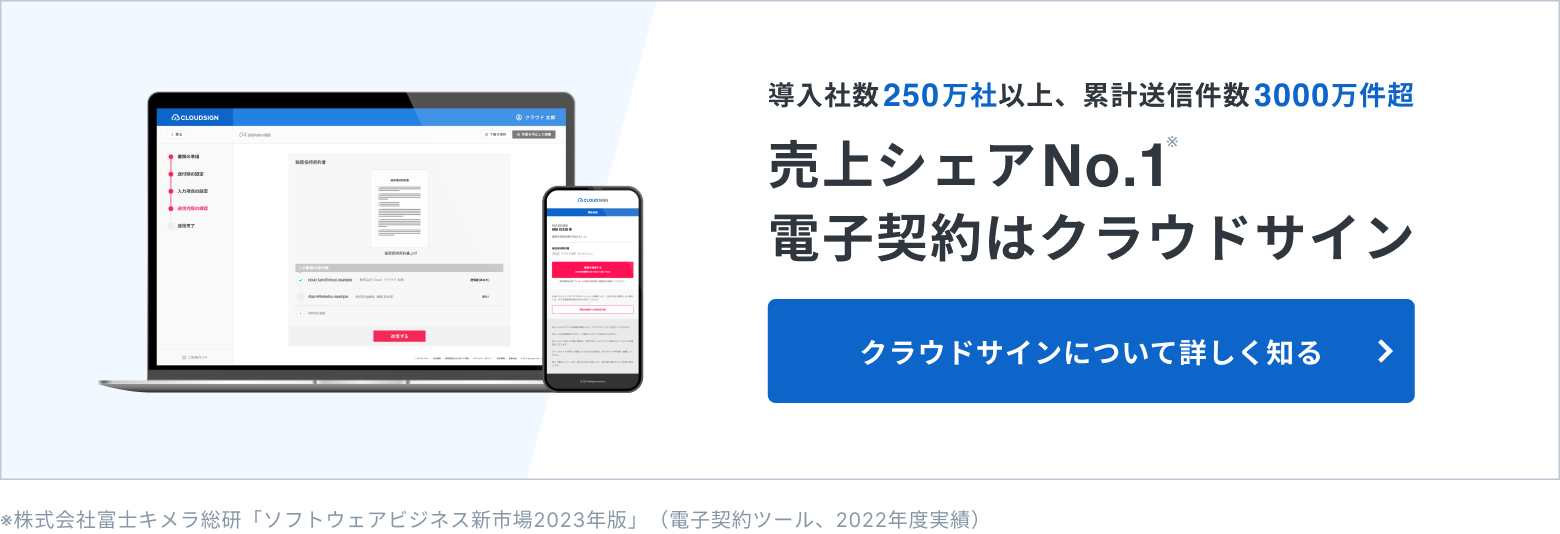ベンチマークとは?初心者向けに徹底解説します

ベンチマークとは、企業や組織が自社の業績やプロセスを他社と比較し、改善点を見つけ出すための手法です。
この記事では、ベンチマークの基本概念から歴史、そしてその活用方法までを初心者向けにわかりやすく、丁寧に解説します。
企業や自治体での運営において、ベンチマークがどのように役立つのかを理解することで、競争力の向上や効率的な業務運営に役立ててください。
なお、クラウドサインでは企業の経営や新規事業に取り組む方に向けて、契約業務のデジタル化によってコスト削減を実現した企業の事例を紹介している資料を無料でご提供しています。
気になる方はぜひ資料ダウンロードのうえ、ご活用ください。
資料ダウンロード


この資料では、「契約書類・事務のデジタル化」によって業務プロセスの無駄をなくし、コスト削減を実現した企業様の事例を紹介しています。原材料価格の高騰や人手不足にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
ダウンロード(無料)目次
ベンチマークの基本概念を解説
この見出しではまず、ベンチマークの基本概念を解説していきます。
ベンチマークとは何か
ベンチマークとは、自社の製品、サービス、プロセス、パフォーマンスなどを、業界のベストプラクティス、競合他社、または他業種の優れた企業と比較し、自社の改善点や目標設定の基準を見つけるプロセスを指します。
簡単に言えば、自分たちの現在地と、目指すべき理想的な地点、あるいは周りの優れた人たちがどこにいるのかを知るための「羅針盤」のようなものです。
これにより、企業は自社の強みや弱みを客観的に把握し、改善策を考えることができます。
ベンチマークの歴史と背景
「ベンチマーク」という言葉の歴史は古く、もともと19世紀の土地測量において「基準点」を表すために使われていたとされます。
さらに、産業革命以降、大量生産が普及するにつれて、製品の品質の均一性や生産効率の向上が企業の競争力に直結するようになったという背景があり、ベンチマークという言葉がビジネス用語として活用されるようになりました。
ベンチマークという概念は今や単なる測量の基準点という意味だけではなく、より広く「比較対象」や「標準」という意味で使われています。
現代ビジネスにおけるベンチマークの意味
ゼロックス社のロバート・C・キャンプ氏によって書かれた書籍『Benchmarking: The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance』(1989年)は現代のビジネスにおけるベンチマークの概念を確立した原典とされています。
キャンプ氏は、1970年代後半から1980年代初頭にかけてゼロックス社が直面していた厳しい競争環境の中で、自社の製品やプロセスを競合他社や業界のベストプラクティスと比較することで、パフォーマンスを向上させる手法として「ベンチマーク」を体系化しました。
この書籍は、ベンチマークが単なる比較だけでなく、「ベストプラクティスを特定し、それを自社に適用することで優位性を獲得する」という戦略的な意味合いを持つことを明確にしました。

ここでのベンチマークは、自社のパフォーマンスを他社と比較し、優れた実践(ベストプラクティス)を学び、それを導入することで自社の改善を図るという、現代のビジネスにおけるベンチマークの核心を形成しています。特に、ゼロックス社が日本の競合他社から多くのことを学んだ経験は、異業種からの学習というベンチマーキングの重要な側面を示しています。
現代は、ITの進化に伴い、ベンチマークはデジタル技術を活用したプロセス改善や新規事業開発の指針としても活用されています。
ベンチマークとKPIの違い
ベンチマークと似た言葉に「KPI(Key Performance Indicator 、重要業績評価指標)」があります。どちらも企業のパフォーマンスを測定し、改善するために不可欠なものですが、その役割には明確な違いがあります。
ベンチマークは、外部との比較に重点を置いた「水準」や「基準点」であり、自社の現状が外部の水準に対してどの位置にあるのかを評価するという役割があります。
一方、KPIは内部の目標達成度を測るための「指標」です。社内目標に対して、どれだけ進捗しているか、達成できているかを数値で表す役割があります。

ベンチマークとKPIは異なる役割を持つ一方で、互いに補完し合う関係にもあります。
たとえば、 「競合他社のコンバージョン率が平均10%であれば、自社のKPIとして12%を目指す」など、業界のベンチマークを参考にKPIを設定することで、より積極的な自社の目標を設定することもできます。
ベンチマークのメリット、重要である理由
インターネットの普及により、顧客はあらゆる情報を簡単に比較検討できるようになりました。中小企業であっても、全国各地、世界中の企業と常に比較され、競争にさらされています。このような状況下で、感覚や経験だけで意思決定を下すのは非常にリスキーです。
ベンチマークを活用することで、主に以下のようなメリットを得られます。
- 客観的な現状認識ができる…自社が業界内でどの位置にいるのかをデータに基づいて把握できます。
- 効率的な改善点の特定ができる…漠然とした課題ではなく、具体的な改善が必要な領域を特定できます。
- 目標設定が明確化できる…達成可能な、かつ競争力のある目標を設定できます。
- 経営リソースの最適配分…限られた予算や人材を、最も効果的な領域に集中させることができます。
ベンチマークの使い方
この見出しでは、ベンチマークを効果的に利用するための具体的なステップを解説します。
1. 情報収集する
ベンチマークを設定するための第一歩は情報収集です。
収集する情報としては、競合他社の業績データや市場動向、技術トレンドなどが含まれます。インターネットや業界レポート、専門家の意見を通じて得ることができます。

情報収集の際には、信頼性のあるソースを選ぶことが重要です。また、収集したデータは、目的に応じて整理し、分析しやすい形にまとめます。これにより、後段の分析段階での効率が向上します。
情報収集は時間を要する作業ですが、効果的なベンチマークの基盤となるため、丁寧に行いましょう。
2. 適切な基準を設定する
収集した情報をもとに、適切な基準を設定しましょう。基準とは、比較対象となる指標や目標のことを指します。たとえば、売上高や利益率、顧客満足度などが考えられます。
基準を設定する際には、自社の現状を正確に把握し、現実的で達成可能な目標を設定することが大切です。
また、基準は一度設定したらずっとそのままでよいものではなく、市況の変化や技術の進化に応じて、柔軟に見直しましょう。
3. 分析結果を活用する
収集したデータをもとに分析を行い、その結果を企業の戦略や改善計画に活用しましょう。
データを分析する際には、まず現状のパフォーマンスを評価し、目標との差異を明確にします。これにより、どの部分に改善が必要か課題を特定することができます。この際、社内の関係者と情報を共有し、共通の課題認識を持つことが重要です。
最後に、分析結果をもとに具体的な改善策を立案します。データの分析結果をもとに改善策を立案することで、施策により納得感を持たせることができます。
知っておきたいベンチマークの具体例
ここでは、ベンチマークの具体的な事例をIT業と製造業を例にあげて紹介します。
いまいちイメージが掴めない方にもわかりやすく解説していきます。
IT業界におけるベンチマーク例
IT業界では、システムのパフォーマンスやセキュリティ対策の基準としてベンチマークが広く活用されています。
たとえば、サーバーの処理速度を測定するためにSPEC(Standard Performance Evaluation Corporation)のベンチマークが使用されることがあります。これにより、異なるシステム間での性能比較が可能となり、最適なITインフラの選定に役立ちます。

また、セキュリティ対策の強化を目的として、情報セキュリティのベンチマークとしてCIS(Center for Internet Security)ベンチマークを参照することが一般的です。これにより、業界標準に基づいたセキュリティ対策が実現できます。
製造業におけるベンチマーク例
製造業におけるベンチマーク例としては、OEE(Overall Equipment Effectiveness)という指標が挙げられます。
これは設備の稼働率、性能、品質を総合的に評価するもので、生産プロセスの最適化に貢献します。
さらに、製品開発のスピードやコストを他社と比較するために、製品ライフサイクル管理(PLM)を用いることがあります。これにより、自社の製品開発プロセスの改善ポイントを明確にし、競争力を高めることが可能です。
ベンチマークのデメリット、知っておきたい落とし穴
ベンチマークは、他社のベストプラクティスを参考にする実践的なアプローチですが、使い方を間違えると逆効果になることがあります。
他社の真似ばかりしていると、自社の独自性がなくなる
他社のやり方をそのまま模倣するだけでは、自社独自の魅力が失われてしまう可能性があります。特に中小企業は大企業との競争に巻き込まれることは避けなければなりません。
また、他社の模倣ばかりしていると、社員も「結局、真似か」と感じて、新しいアイデアを出す気持ちがなくなってしまうかもしれません。
不正確な情報で誤った判断してしまうリスクがある
ベンチマークはデータを見て行われますが、そのデータが間違っていると、誤った判断をしてしまう可能性があります。
他社の詳しい正確な情報は、そう簡単には手に入りません。公開されている情報だけでは、その数字の裏にある背景が分からないことがあります。例えば、「A社の顧客満足度が90%」とあっても、どのような方法で調べたのか、どのようなお客さんを対象にしたのかが分からなければ、単純に比較できません。
時間やコスト、手間がかかる
適切なベンチマークを設定し、活用するには、時間やコスト、手間がかかります。情報収集だけでも時間がかかりますし、信頼できる情報を集めるのにもコストや手間がかかります。
ベンチマークの設定は普段の仕事と並行して行うことが多く、かえって仕事の効率が落ちてしまう可能性もあります。
変化に対応できなくなる可能性
ベンチマークは過去の成功事例や現在のやり方を参考にします。しかし、世の中や技術、顧客の好みは常に変わっています。ベンチマークの結果にこだわりすぎると、新しい流行やチャンスを見逃してしまい、会社の方向転換が遅れることがあります。
「他社がまだやっていないから、うちもやらなくていい」と考えてしまうと、未来の成長のチャンスを逃してしまうかもしれません。

デメリットを避けベンチマークを活用するには
ベンチマーク活用におけるさまざまなデメリットは、ただ「比較」するだけで、その意味を理解せずに進めることで起こります。
ベンチマーク活用のデメリットを避けて会社に役立つツールとして使うためには、まず 「何を、なぜ」ベンチマークするのかをはっきりさせることが大切です。
さらに、他社の成功事例を真似するのではなく、「なぜ成功しているのか?」「その成功の秘訣は、うちの会社でもできるのか?」と深く考えて、「学び」の姿勢で取り組むことが重要です。
また、一つの情報源に頼らず、色々な情報から集めて、批判的な目で分析しましょう。公開されている情報だけでなく、顧客の話や業界の専門家の意見など、可能な範囲で非公開の情報も参考にすることを考えるとよいです。
最後に、ベンチマークは一度やったら終わりではありません。定期的にベンチマークを行い、その結果に基づいて「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)」のサイクルを回し続けることが大切です。
デメリットを恐れず、この記事で得た知識を活かして、自社らしいベンチマークの設定と活用を始めてみてください。
なお、クラウドサインでは「会社全体でDXや業務改善を進めたいけれど、なかなかうまくいかない」と悩む経営者やDX推進担当者に向けて、DX推進が進まない原因や、取り組みのポイントをまとめた資料をご用意しています。
DX推進したい方はもちろんのこと、「周囲の巻き込み力」を高めたい方はぜひ参考にしてみてください。
無料ダウンロード


専門機関による調査レポートを読み解くと、日本企業でDXがなかなか進まない背景には「DXを推進したい経営層」と「どのように推進したら良いかわからない現場」の「目線のズレ」があることがわかりました。この資料では、そのズレを乗り越える3つのポイントついて解説します。
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
高桑清人
中小企業診断士
前職ではBPO企業にて12年間、業務設計・品質管理・人材マネジメントなどの管理業務に従事。独立後は中小企業の経営支援に携わり、新規事業の立ち上げや事業計画策定を伴走型で支援。学習塾講師として16年・1万時間超の授業経験もあり、「聴く・伝える・支える」現場感を大切に活動している。
この記事を書いたライター
業務改善プラスジャーナル編集部
業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。
こちらも合わせて読む
-

中小企業で全体最適を成功させるコツとは?部分最適に陥ってしまう要因と解決策
ペーパーレス化DX業務効率化プロジェクトマネジメント -

レベニューシェア活用のメリット&デメリットとは?
-
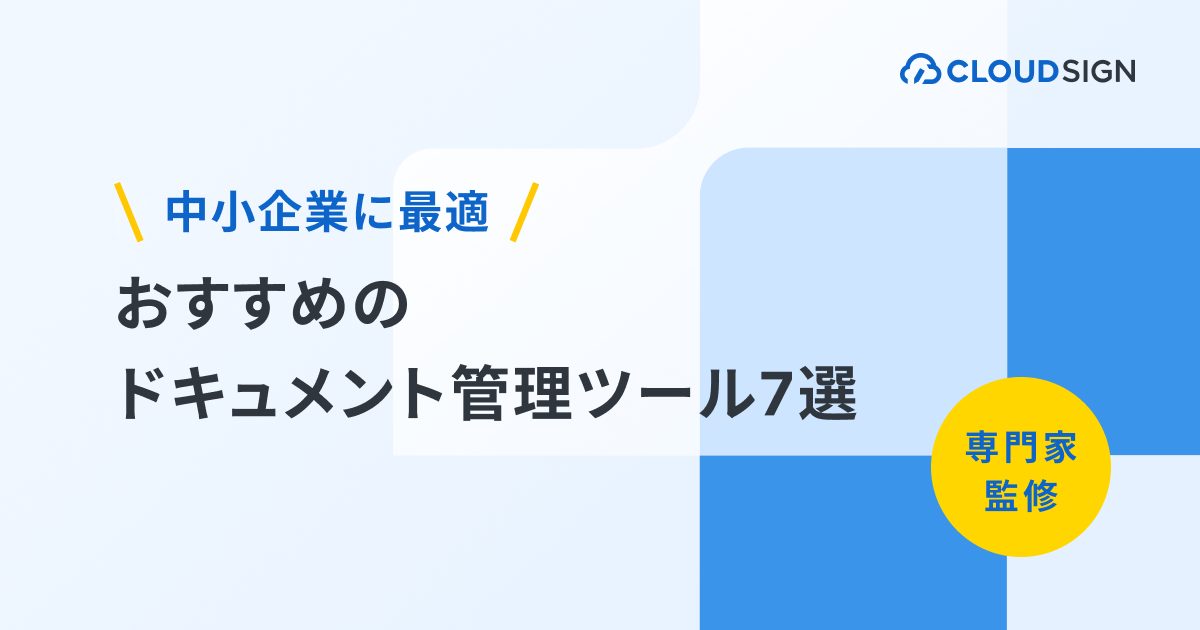
中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選
ペーパーレス化DX業務効率化 -

全体最適とは?今日からできる、中小企業のための実現方法をわかりやすく解説
業務効率化プロジェクトマネジメント -
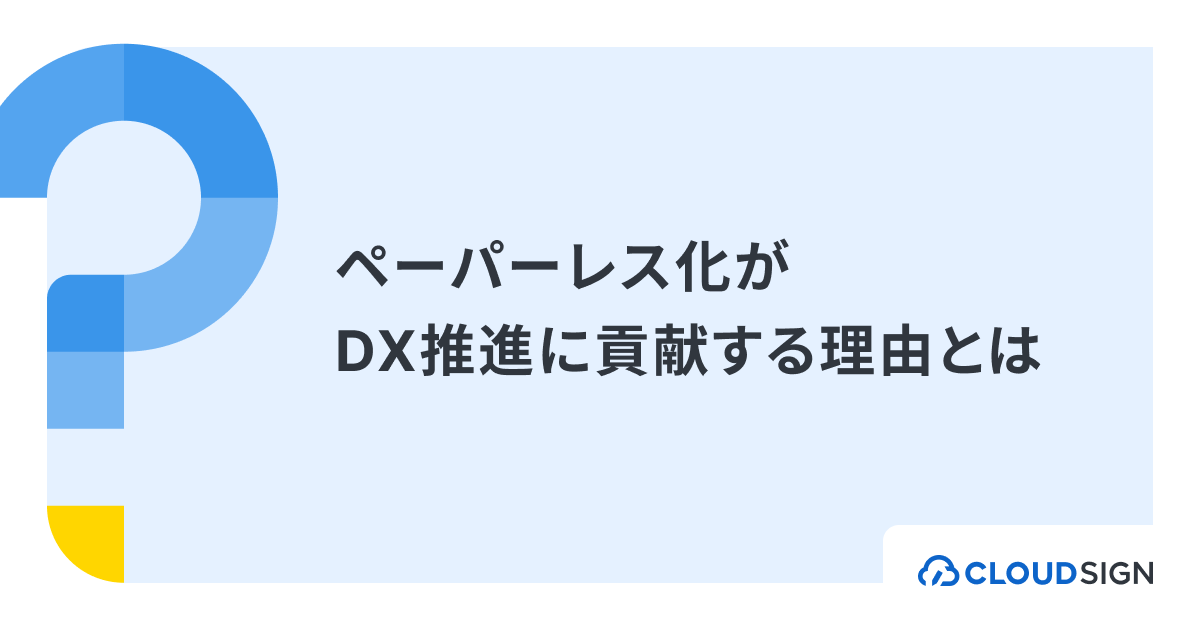
ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説
ペーパーレス化DX -

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説
ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法納品書経理DX -

DXに欠かせない一元管理とは?メリットや利用時のポイントを解説
DX業務効率化プロジェクトマネジメント -

DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説
DX -

API連携とは?仕組みや事例、導入のメリットなどを徹底解説
DX業務効率化API連携 -

【初心者必見】RPAとは何か?今更聞けない基本と導入のポイント
業務効率化RPA