請求書の電子化とは?メリットや注意点などを詳しく解説
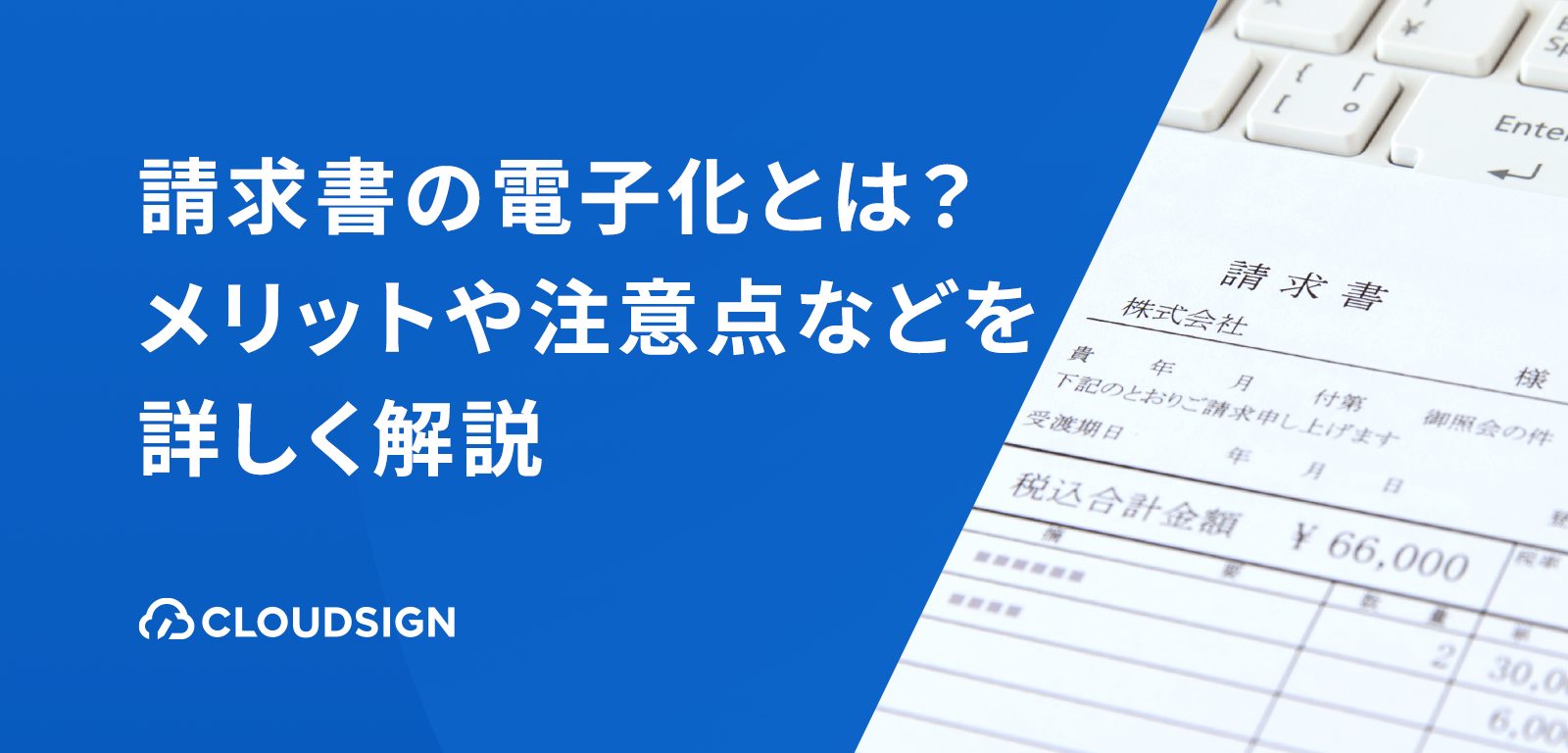
請求書の電子化とは、請求書を紙ではなくPDFなどの電子データで作成、送付を行うことを指します。
近年のDX推進に加えて、電子帳簿保存法の改正によってさまざまな保存要件が緩和されたことから、請求書を含めた紙の書類のペーパーレス化が進めやすくなり注目が高まっています。
特に経理部門で扱う書類は、請求書や納品書など多くの種類があり、経理業務は紙で行うのではなくデータ化することが求められています。
当記事では請求書の電子化やメリット等について初歩的な内容も含めて解説しますので参考にしてみてください。
請求書の電子化とは
請求書の電子化とは、これまでの紙で発行・送付・保管していた請求書をデジタルデータに変換してやり取りすることを指します。
具体的にはPDFなどの電子ファイルで請求書を作成し、メールやクラウドサービスなどを利用して取引先に送付するという流れです。
近年では、電子帳簿保存法の改正により電子取引で受け取った請求書は電子データでの保存が義務化されたため、企業の間で請求書の電子化が進んでいます。
なお、請求書の作成方法について詳しくはこちらの記事もご覧ください。
電子請求書の請求方法・共有方法は大きく分けて3種類
請求書を電子化する方法としては専用のシステムを導入するケースが多いですが、PDFファイルを作成してメールで送付するだけでも電子化といえるでしょう。
ここでは電子請求書の請求・共有方法についてそれぞれ解説します。
一般的な方法の一つで、請求書をPDF形式に変換しメールに添付して送る方法です。PDFはほとんどの環境で閲覧可能というメリットがある一方、改ざんされる懸念もあります。また、そもそもメールを誤送信してしまうといったリスクもあるため、パスワード付きPDFを利用して送信することなどが必要です。
・クラウドストレージや専用のサイトにアップロードし、ダウンロードURLを共有する
大容量のファイルを送付する場合や、複数の関係者と共有する場合に便利です。作成した請求書をクラウドストレージサービス(Google Drive、Dropboxなど)にアップロードし、そのダウンロードURLを取引先に伝える方法です。アクセス権限の設定によりセキュリティを高めることも可能です。・請求書発行システムを利用する
請求書の発行から送付、管理、回収までを一元化し、効率化するために便利なツールです。入金管理機能が搭載されているものや取引先がシステム上で請求書を確認・ダウンロードできるものなど機能はさまざまです。電子帳簿保存法の要件を満たす機能が搭載されているものであれば、法的にも安心です。
電子請求書は法的に有効か?
従来の紙の請求書を電子化する際に気になるテーマとして、電子請求書は法的に問題がないのかという点が挙げられます。ここではその有効性について解説します。
電子請求書は法的に問題がなく有効
まず、請求書をPDFにしてやりとりすることや電子請求書システムを使って発行することは法的に問題はありません。
電子帳簿保存法で定められている要件を満たしていればPDFなどによる電子化した請求書の発行は法的に問題はなく、紙の請求書と同等の効力を持ち、証拠資料としても認められます。
資料ダウンロード


この資料では、電子帳簿保存法改正のポイントや法遵守のコツをまとめています。2022年1月の改正は、企業のデジタルトランスフォーメーションを後押しする規制緩和要素が強い反面、規制強化要素もあり、対応には注意が必要です。気になる方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。
電子請求書には押印が必要?
結論から言うと、電子請求書には押印は必要ありません。そもそも日本の法律上、請求書への押印は必須ではなく、紙の請求書であっても電子請求書であっても同様です。
ビジネスの現場では請求書にハンコを押す習慣が根強く残っており、取引先のルールによっては必要となる可能性もあります。
請求書にハンコが必要かどうかについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
電子請求書の保存期間は?
電子帳簿保存法における帳簿書類の保存期間は、法人の場合、確定申告書の提出期限翌日より7年です。例外として、欠損金が生じている場合には保存期間が10年に延びます。
個人事業主の場合、白色申告と青色申告で異なりますが5年もしくは7年の保存が必要です。
電子帳簿保存法に違反すると罰則を受けるリスクもあるため、定められた期間を過ぎるまで適切に保存しなければなりません。
出典:国税庁「帳簿書類等の保存期間」、国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
請求書の電子化は義務?注意点は?

2024年1月1日より、電子帳簿保存法が改正されたことですべての請求書を電子化しなければならないのかが気になる方もいると思います。ここでは請求書の電子化が義務かどうかを解説します。
紙の請求書発行自体は禁止されていない
電子帳簿保存法により、電子取引で受領した請求書は電子データのまま保存することが義務化されました。つまり、紙で受け取った請求書をスキャンして電子化したものや最初から電子データで受け取った請求書は電子データのままで保存しなければなりません。
しかし、すべての請求書を電子化しなければならないわけではありません。紙で受け取った請求書を紙のまま保存することは可能ですので、紙の請求書の発行自体が禁止されたわけではありません。
ただし、電子取引で受け取った請求書を紙に印刷して保存するだけでは、法律の要件を満たさないので注意が必要です。
電子取引に関する書類は、データでの保存が必須
電子帳簿保存法により、電子データで受け取った請求書を紙に出力した状態で保管することは認められていません。
紙に出力してしまうとそのデータが元の電子データと同一であることの証明が困難になり、データの信頼性を確保できなくなるため、電子データのまま正確に保存する必要があります。
請求書を電子化するメリット
請求書を電子化すると、従来の紙ベースの請求書処理に比べて、業務効率を大幅に向上させることができます。また、印刷や郵送を行う必要がなくなり、送付作業を効率的に行えます。
ここでは請求書の電子化のメリットについて解説します。
これらのメリットを享受することでコア業務に集中し、生産性を向上させることができます。
請求書の処理にかかる時間を短縮できる
請求書の電子化により請求書を作成・印刷・封入・郵送する作業が減り、担当者の負担軽減と業務時間の短縮につながります。
また、送られてきた請求書の確認・承認・仕訳・保管などの作業も、電子化によって効率化ができます。取引先からの問い合わせがあった場合にも、電子データを検索すれば見つかるため、紙で保管している場合よりも素早く対応できます。
コストを削減できる
請求書の電子化によりこれまで必要だった印刷代・用紙代・郵送代などを削減できます。特に、取引先が多い企業にとっては大きなコスト削減効果が見込めます。
さらに、紙の請求書を保管するためのスペースやファイリングにかかる費用も削減できるため全体的なコスト削減につながります。
リスクを軽減できる
紙の請求書は紛失や破損のリスクが常に伴います。しかし、電子請求書であればデータとして保管されるため、これらのリスクを大幅に軽減できます。
紙の請求書の場合、営業担当者が封筒に入れたまま放置したり、紛失してしまったりという不測の事態が起きる可能性があります。そのほかにも、頻度が多いわけではありませんが地震や火災、水害などの災害時に紛失、破損してしまうことも考えられます。
データであれば安全に保管されている可能性が高く、このようなトラブルを回避しリスクを軽減しておくことは事業継続の観点からも重要です。
場所を問わず請求書業務ができる
インターネットに接続できる環境があれば、いつでもどこでも請求書を発行・送付等が可能となります。
リモートワークとの親和性も高いため、リモートワークを導入している企業全体としても、担当者の視点からしても場所を選ばずに請求書を発行できることは大きなメリットです。
請求書を電子化するデメリット
上記のように請求書を電子化することによるメリットについて解説してきましたが、電子化に伴うデメリットについてもここから解説します。
導入費用がかかる
紙の請求書の場合に必要だった印刷代・用紙代・郵送代などを削減できる一方で、電子請求書システムを導入する際には初期費用や月額利用料が発生します。費用はシステムの規模や機能によって大きく異なり、必要な内容によっては追加の費用が発生することもあります。
導入を検討する際には、複数のシステムを比較検討し、自社の予算やニーズに合ったシステムを選びましょう。
請求書発行フローの見直し・周知が必要になる
電子請求書の導入に伴い、請求書の発行フローを大幅に見直すことが必要となるでしょう。従来の紙ベースのフローから電子的なフローへの移行は従業員にとって大きな変化となり、混乱を招く可能性があります。
特に導入初期においては、新しいフローをスムーズに導入するために従業員への十分な説明が必要となること等はデメリットともいえるでしょう。変更点を明確に伝え、必要に応じてマニュアルを作成したり説明会などを開催したりすることで、問い合わせやクレームを減らすことにつながるでしょう。
取引先に電子請求書利用の了承が必要になる
電子請求書を導入する際には、取引先の了承を得る必要があります。取引先によっては、電子請求書に慣れていない、または既存のシステムとの互換性がないなどの理由で紙の請求書を希望する場合があります。
すべての取引先が最初から電子請求書に対応するとは限らないため、紙と電子の両方の請求書発行が必要となることも考えられます。取引先との関係性を考慮しつつ、電子請求書のメリットを丁寧に説明し理解と協力を得ることが重要となるため、これらの労力は一時的なデメリットともいえるでしょう。
請求書を含めた紙の電子化で業務効率向上を
これまで解説してきたように、請求書の電子化によりコスト削減や経理作業の効率化といったメリットを得られます。
請求書の電子化を検討する場合には、それと合わせて契約書などの紙書類のDXを検討することで、社内全体で業務効率の向上が期待できるでしょう。
当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」はアップロードとメール送信のみで契約締結までの作業を完了することができます。書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がないため、取引相手に準備の負担がかかることなく契約締結が可能です。
この機会にぜひ電子契約サービスを導入し、電子化を進めることでペーパーレス化・DX化を推進してみてはいかがでしょうか。
なお、クラウドサインの機能や料金をコンパクトにまとめた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しています。
クラウドサインのサービス詳細について知りたい方は、下記リンクからご入手ください。
無料ダウンロード


クラウドサインは、国内売上シェア、認知度、自治体導入数がいずれもNo.1の電子契約サービスです。この資料では、クラウドサインが多くのお客様に選ばれる理由について取りまとめています。クラウドサインの機能やセキュリティ対策、サポート体制などについて詳しく知りたい方はダウンロードのうえ、ご活用ください。
ダウンロード(無料)この記事を書いたライター
業務改善プラスジャーナル編集部
業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。
こちらも合わせて読む
-
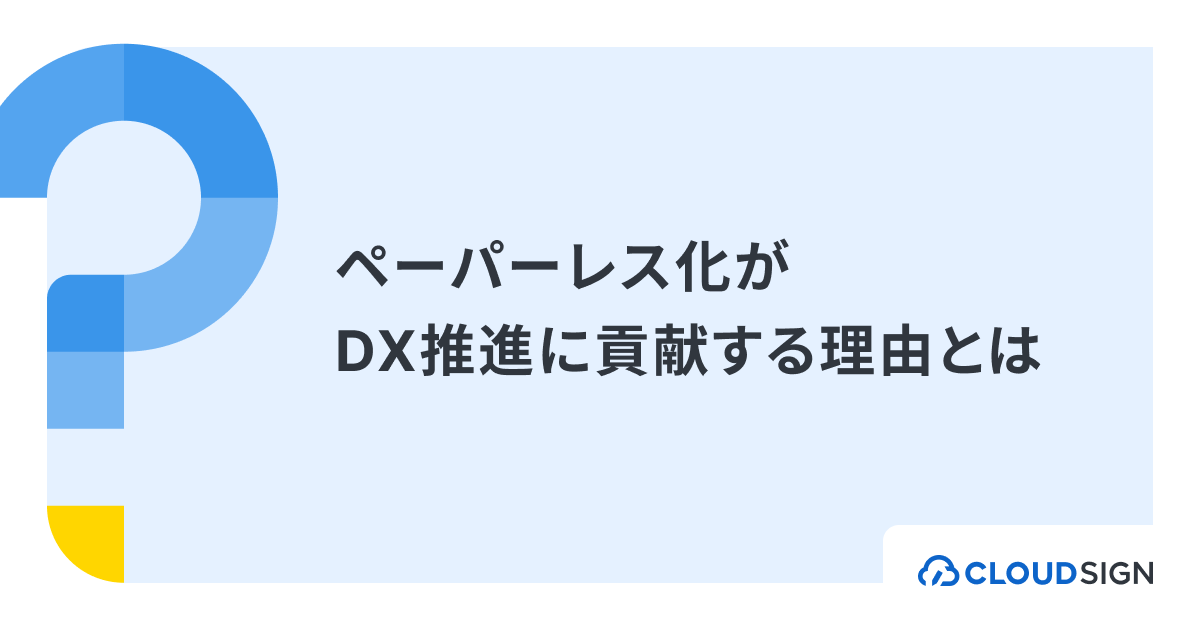
ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説
ペーパーレス化DX -

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説
ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法納品書経理DX -
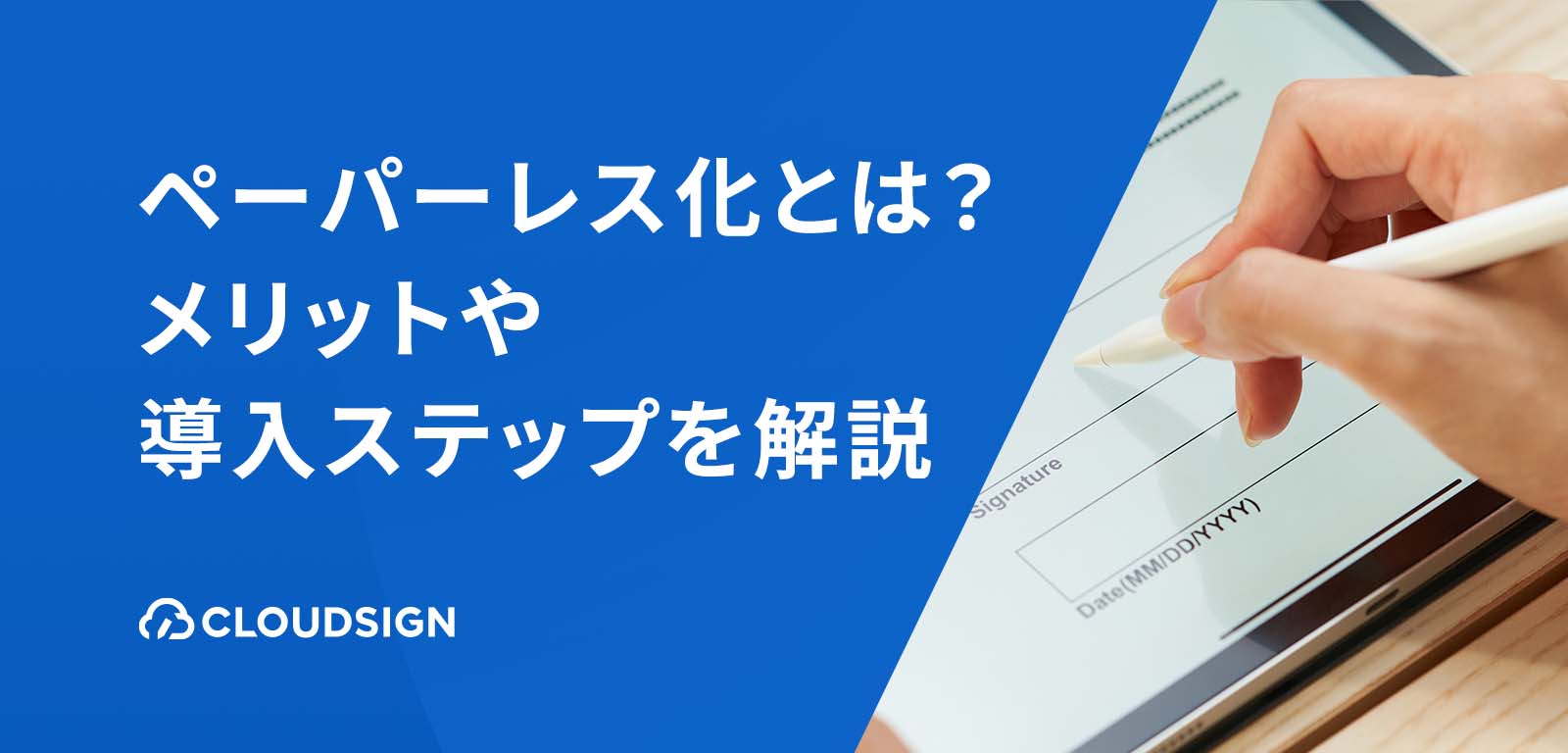
ペーパーレス化とは?メリットと実施までの具体的なステップを解説
ペーパーレス化DX -
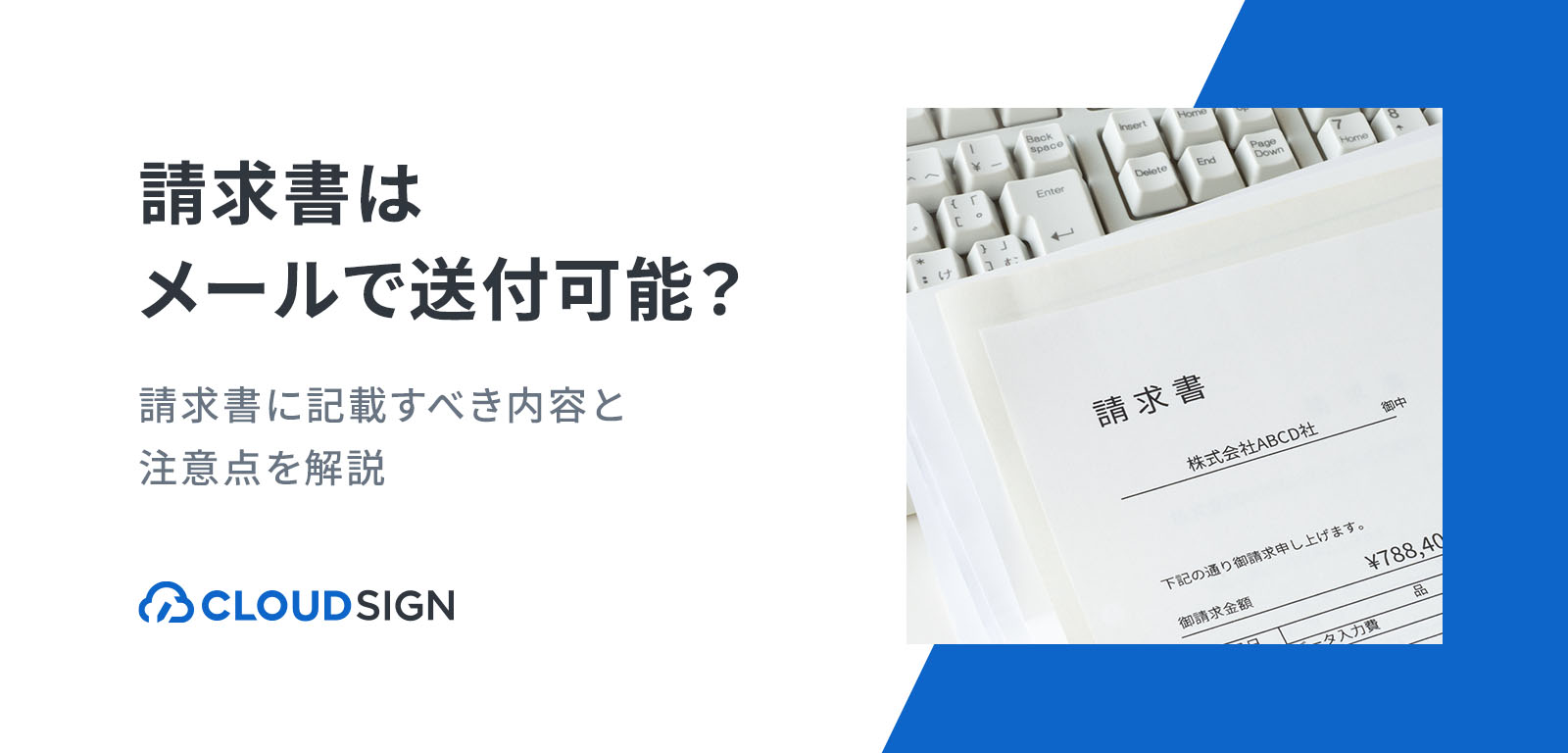
請求書はメールで送付可能?請求書に記載すべき内容と注意点を解説
ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法経理DX -
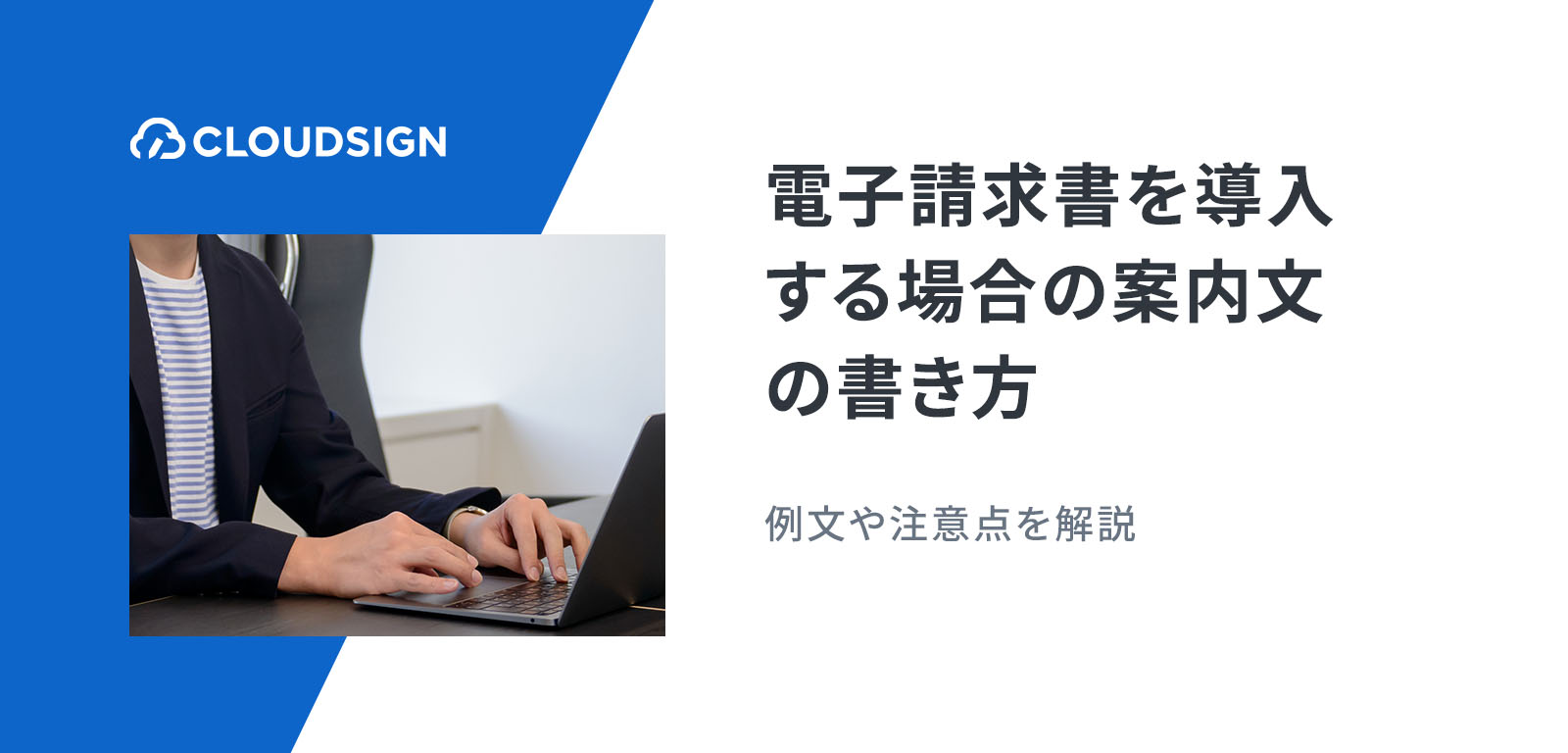
電子請求書を導入する場合の案内文の書き方|例文や注意点を解説
ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法経理DX -
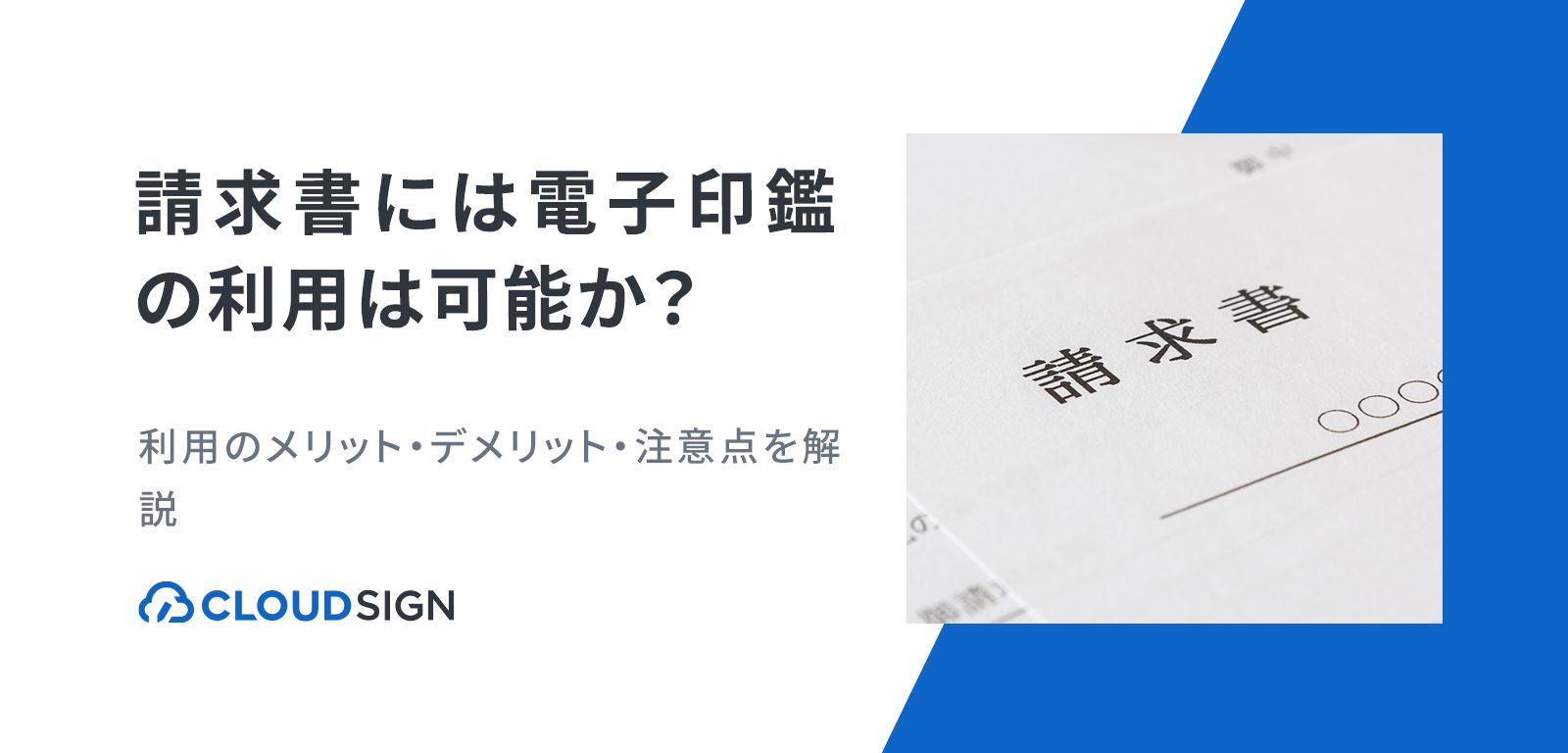
請求書には電子印鑑の利用は可能か?利用のメリット・デメリット・注意点を解説
ペーパーレス化DX業務効率化請求書電子帳簿保存法経理DX -

業務効率化におすすめのツール13選 導入のメリットや利用例を紹介
業務効率化