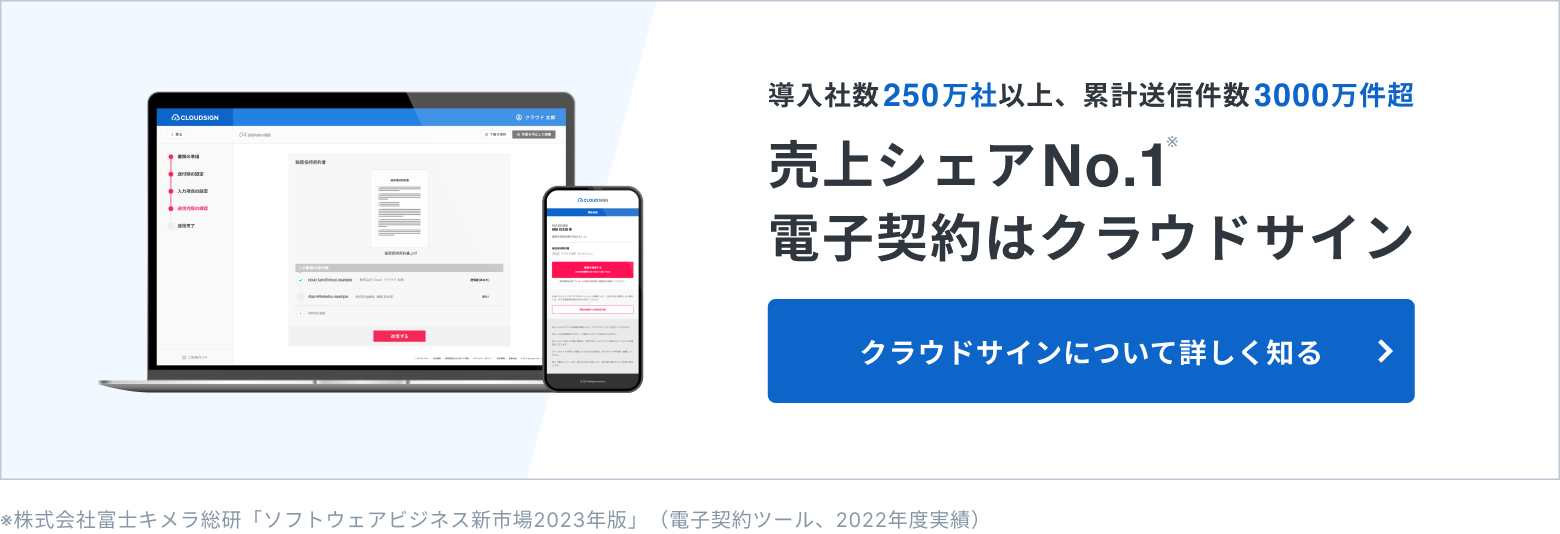レベニューシェア活用のメリット&デメリットとは?

デジタル化の進展によりビジネスの不確実性が高まる中、レベニューシェアという選択肢が注目されています。
レベニューシェアとは、売上の一部をパートナーと分け合うビジネスモデルです。初期コストを抑えつつ、リスク分散できる点が魅力的ですが、一方で利益率の低下や経営の複雑化といった課題も存在します。
この記事では、レベニューシェアのメリットとデメリットを詳しく解説します。レベニューシェアを取り入れるべきかどうか、判断に迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
資料ダウンロード


この資料では、「契約書類・事務のデジタル化」からDXをスタートし、コスト削減を成功させた方法について、実際の企業の事例を交えて紹介しています。原材料価格の高騰や人手不足にお悩みの企業様はぜひ参考にしてみてください。
ダウンロード(無料)目次
レベニューシェアとは?具体例や似た契約形態との違い
ここでは、レベニューシェアの具体例や、似た契約形態である「プロフィットシェア」と「ロイヤリティ」について、その意味や違いを解説します。
レベニューシェアの例
レベニューシェアの具体例として、大阪のランドマークである「あべのハルカス」とパナソニックISの例があります。
「あべのハルカス」は2014年、展望フロアや美術館の入場システムにおいて、システム利用料を入場者数に応じて毎月支払う「レベニューシェア型クラウドサービス」を採用し、注目を集めました。(参考:「レベニューシェア型クラウドサービス」導入とその成果により、近畿日本鉄道(株)が平成26年度「ITビジネス賞」を受賞)

あべのハルカスを運営する近畿日本鉄道にとっては、初期投資コストを抑えられ、万が一入場者数がふるわなかった際の費用負担を軽減できるというメリットがあります。
一方、システムを提供するパナソニックISにとっては、「システムを納入して終わり」ではなく、システム導入後も入場者を伸ばす努力をすることによって自社の売り上げを伸ばせる可能性があり、さまざまなノウハウを得られるメリットがあります。
そのほかの例を挙げると、Youtubeと動画クリエイターも、「レベニューシェア」をしているといえます。Youtube(Google)はプラットフォームを提供し、クリエイターは動画をアップロードすることで、動画の再生中に表示される広告の収益を両者で分け合っています。

このほかにも、
- ECサイトのシステムベンダーと量販店
- 電子書籍ストアと出版社・著者
- ブログ運営者と広告代理店
なども、収益を一定の割合で分け合う「レベニューシェア」型のビジネスモデルであるといえます。
プロフィットシェアとの違い
レベニューシェアとプロフィットシェアは「何を分配の基準とするか」という点に違いがあります。
レベニューシェアは売上そのものを分配しますが、プロフィットシェアは利益、つまり売上から経費を差し引いた後の金額を分配します。
この違いは、ビジネスパートナー間のリスクや報酬の分配方法に大きく影響します。プロフィットシェアでは、報酬を受け取る側のリスクが高く、報酬が不安定になるリスクがあります。
| 項目 | レベニューシェア (Revenue Share) | プロフィットシェア (Profit Share) |
| 分配対象 | 売上(収益) | 利益(売上 - 経費) |
| リスク偏り | 受注側(報酬受領者)のリスクが低い | 受注側(報酬受領者)のリスクが高い |
| 発注側(報酬支払者)のリスクが高い | 発注側(報酬支払者)のリスクが低い | |
| 報酬安定性 | 受注側は比較的安定 | 受注側は不安定になる可能性あり |
| コスト意識 | 受注側は直接的なコスト管理へのイン センティブが低い |
受注側もコスト管理・効率化へ強いイン センティブが働く |
どちらの方式を選ぶかは、事業の性質、パートナーシップの目的、双方のリスク許容度によって慎重に検討する必要があります。
ロイヤリティとの違い
ロイヤリティとレベニューシェアは、「成果の対象」と、それによって生じる「契約の性質」が大きく異なります。
| 項目 | ロイヤリティ (Royalty) | レベニューシェア (Revenue Share) |
| 主な対象 | 知的財産権、ブランド、ノウハウなど の「使用許諾」 |
特定の事業やプロジェクトから得ら れる「売上(収益)」そのもの |
| 契約の性質 | 権利の貸し借り、その対価。事業運営 には直接関与しない場合が多い。 |
共同事業、共同遂行。事業の成功に 向けて協力する意識が強い。 |
| 使われる場面 | フランチャイズ、特許ライセンス、 著作権利用など |
ITサービス開発、プラットフォーム 運営、コンテンツ配信、マーケティ ングなど |
| 主要な目的 | 権利所有者の収益化、権利利用者の効 率的な事業展開 |
発注者のリスク軽減、受注者のコミッ トメント、共同での事業創出と成果分配 |
ロイヤリティは、特許、商標、著作権などの知的財産権、あるいはブランドやノウハウといった無形資産の「使用許諾」を対象とする対価です。
権利を持つ者(ライセンサー)が、その権利を他者(ライセンシー)に一定期間、一定の範囲で使用させることを許可し、その見返りとして、通常はライセンシーの売上や生産量などに応じてロイヤリティが支払われます。

フランチャイズ契約におけるブランド使用料や、書籍・音楽の印税などが代表的な例として挙げられます。
事業の成功に向けて両者が協力し、その収益を分け合うレベニューシェアとは異なり、あくまで権利の貸し借りの対価として報酬を支払うのがロイヤリティです。
レベニューシェアのメリット
ここからはレベニューシェアの具体的なメリットについて解説します。レベニューシェアにはさまざまなメリットがありますが、主なものとしては次の2点が挙げられます。
初期コストを軽減できる
レベニューシェアの大きなメリットの一つは、初期コストの軽減です。
通常、新規プロジェクトやシステム導入には多額の初期投資が必要ですが、レベニューシェアでは売上に応じた費用負担となるため、初期投資を抑えることができます。
先に挙げた「あべのハルカス」の例では、入場管理システムの初期投資を抑え、内装デザインや館内設備などに経営資源を有効活用することができるようになる点が、レベニューシェアモデル採用の決め手になりました。(参考:「あべのハルカス、“レベニューシェア”でITを調達、パナソニックISがクラウドサービスとして提供」:IT Leaders)
こうした柔軟な資金運用は、経営者や新規事業推進担当者にとって、リスクを最小限に抑えながらビジネスを成長させるための戦略的選択肢となるでしょう。

リスク分散できる
レベニューシェアは、リスク分散できるというメリットもあります。
企業は売上に連動して費用を負担するため、売上が低迷した場合にも固定費が重くのしかかるリスクを軽減できます。
この仕組みは、特に市場の変動が激しい分野や新規市場への参入時において、経営の安定性を保つために有効です。また、パートナーとリスクを共有することで、双方のモチベーションが高まり、プロジェクトの成功率が向上する可能性もあります。
無料ダウンロード


DXが進む現代において、「契約DX」の重要性はますます増しています。従来の紙の書面を電子化することで、コスト削減や取引のスピードアップなどさまざまな恩恵を受けられるためです。この資料では、契約DXの課題とその解決策を紹介しているので、業務改善に取り組む企業様はぜひ参考にしてみてください。
ダウンロード(無料)レベニューシェアのデメリット
レベニューシェアは、企業にとって初期コストを抑えることができる反面、いくつかのデメリットも存在します。この見出しでは、レベニューシェアを導入する際に考慮すべき2つのデメリットについて詳しく説明します。
利益率が低下する
レベニューシェアを採用することで、企業はパートナーと収益を分け合うことになります。これにより、自社単独で事業を行う場合に比べて利益率が低下する可能性があります。
利益率が低下すると、企業の成長戦略に影響を及ぼす可能性があります。レベニューシェアを検討する際には、事前に十分なシミュレーションを行いましょう。
レベニューシェアの契約内容によっては、パートナーに支払う割合が高く設定され、企業の利益が圧迫されることがあります。契約交渉の段階で、分配のバランスを慎重に検討する必要があります。
事業運営が複雑になる
レベニューシェアを導入することで、企業の経営は複雑化することがあります。
とくに、複数のパートナーと契約を結ぶ場合、それぞれの契約条件を管理する必要があり、数値の管理やコミュニケーションに手間や時間がかかります。
さらに、レベニューシェアは、契約内容に基づきパートナー間の収益配分を行うため、透明性と信頼性も求められます。契約の解釈や収益配分に関するトラブルが発生すると、企業間の関係が悪化し、プロジェクトの進行に支障をきたすリスクがあります。

成功するレベニューシェア活用のポイント
この見出しでは、こうしたデメリットをできるだけ避け、レベニューシェアを成功させるために必要な2つの要素について解説します。
契約内容を明確にする
レベニューシェアを成功させるためには、契約の明確化が不可欠です。契約書には、収益の分配方法や期間、責任範囲などを詳細に記載しましょう。
レベニューシェアの契約で明確に定義すべきポイント
- 契約の目的
- 事業範囲と役割分担
- レベニューシェアの対象
- 分配比率と計算方法
- 費用負担の範囲
- 報告義務と監査権
- 知的財産権の帰属
- 契約期間と終了条件
契約内容があいまいだと、双方の期待値にズレが生じることがあります。このようなズレを防ぐためにも、具体的な数値や条件を明記しましょう。
さらに、契約には変更時の手続きや条件も含めることが重要です。ビジネス環境は常に変化するため、柔軟に対応できる条項を設定することが、長期的な成功につながります。
信頼できるパートナーを選ぶ
レベニューシェアを効果的に活用するためには、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。パートナー選びでは、相手の実績や信頼性、ビジョンの共有度を確認しましょう。
また、パートナーの選定には、企業文化やビジネススタイルの適合性も考慮するべきです。これは、レベニューシェアが単なる取引ではなく、共同事業に近い性質を持つためです。

レベニューシェアでは、売り上げという共通の目標に向かって、両者が継続的に協力する必要があります。意思決定のスピードやコミュニケーションの頻度、リスクへのとらえ方、費用対効果への価値観、問題発生時の対応方法といった企業文化やビジネススタイルが大きく違っていると、プロジェクトが頓挫してしまうかもしれません。
パートナー選定の際には、時間をかけて相手企業の文化や働く人々の価値観を理解し、自社との相性を確かめるようにしましょう。
よくあるレベニューシェアの疑問とその回答
この見出しでは、企業経営者の方や新規事業推進担当者の方が気になるレベニューシェアによくある疑問とその回答を掲載します。
Q. レベニューシェアの成功例は?
レベニューシェアの成功例として有名なのは「あべのハルカス(近畿日本鉄道株式会社)」と「パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社(パナソニックIS)」の事例で、平成26年度の「ITビジネス賞」も受賞しています。(参考:「レベニューシェア型クラウドサービス」導入とその成果により、 近畿日本鉄道(株)が平成26年度「ITビジネス賞」を受賞:PR TIMES)
この他にも、システムベンダー(かつての日本ユニシス)が小売業者(量販店など)にECサイトの構築から運用までを一貫して提供するケースも成功例として挙げられます。小売店はECサイト開設に関わる初期投資を大幅に抑えられ、ECサイトでの売上の一部をシステムベンダーに支払います。(参考:ショッピングモールサイト構築での共創ビジネスモデルの紹介:UNISYS TECHNOLOGY REVIEW 第 113 号)
システムベンダーはECサイトの売り上げが増えるほど収益が上がるため、単にシステムを作るだけでなく、サイトの機能改善や集客支援、マーケティング戦略の提案など、ECサイトの売り上げを最大化するための共同事業者としてもビジネスに関わることができます。
Q. どのような企業に適している?
レベニューシェアは新規事業の開発を目指す企業や、リソースを効率的に活用したい企業に適しています。例えば、スタートアップ企業や中小企業は、初期投資を抑えつつ新しい市場に参入する手段としてレベニューシェアを活用することができます。また、既存のリソースを活用しつつ、新たな価値を生み出したい大企業にも適しています。
まとめ:レベニューシェアの魅力
レベニューシェアは初期投資コストを慎重に検討する必要がある経営者や新規事業担当者にとって、初期コストを抑えつつリスクを分散できるモデルとして大きな魅力になるでしょう。
利益率の低下や経営の複雑化といったデメリットもありますが、これらは適切な管理と戦略的なパートナーシップによって克服可能です。
こうしたメリットとデメリットを総合的に評価し、自社のニーズに最も適した形でレベニューシェアを活用するとよいでしょう。
この記事の監修者
高桑清人
中小企業診断士
前職ではBPO企業にて12年間、業務設計・品質管理・人材マネジメントなどの管理業務に従事。独立後は中小企業の経営支援に携わり、新規事業の立ち上げや事業計画策定を伴走型で支援。学習塾講師として16年・1万時間超の授業経験もあり、「聴く・伝える・支える」現場感を大切に活動している。
この記事を書いたライター
業務改善プラスジャーナル編集部
業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。
こちらも合わせて読む
-

ベンチマークとは?初心者向けに徹底解説します
新規事業マーケティング -
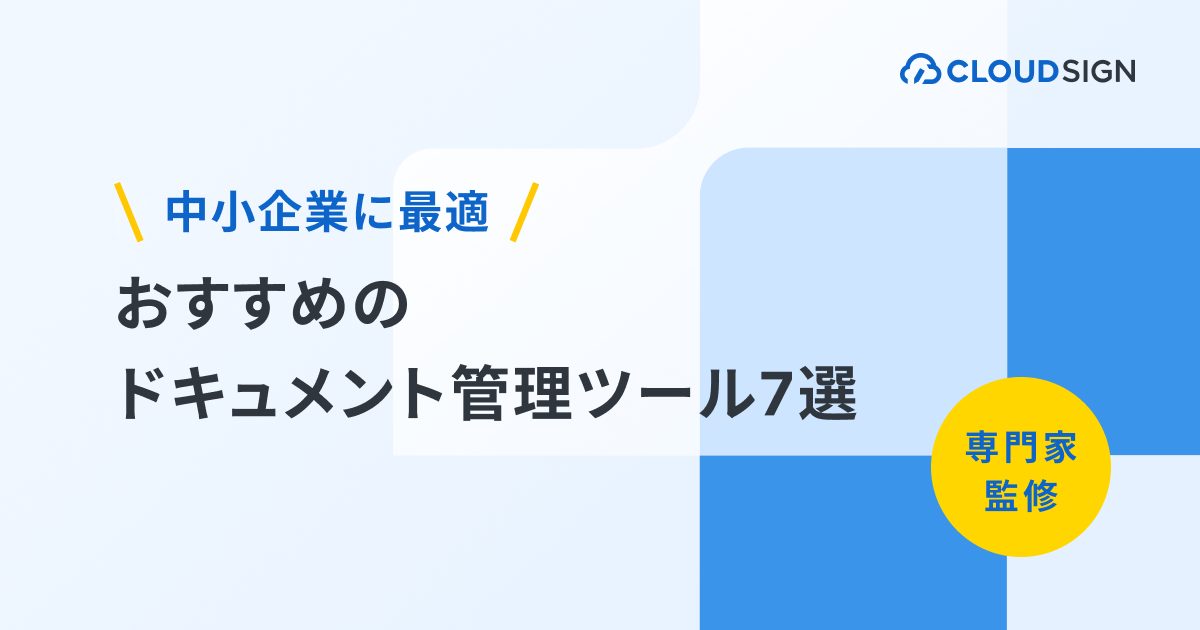
中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選
ペーパーレス化DX業務効率化 -

全体最適とは?今日からできる、中小企業のための実現方法をわかりやすく解説
業務効率化プロジェクトマネジメント -
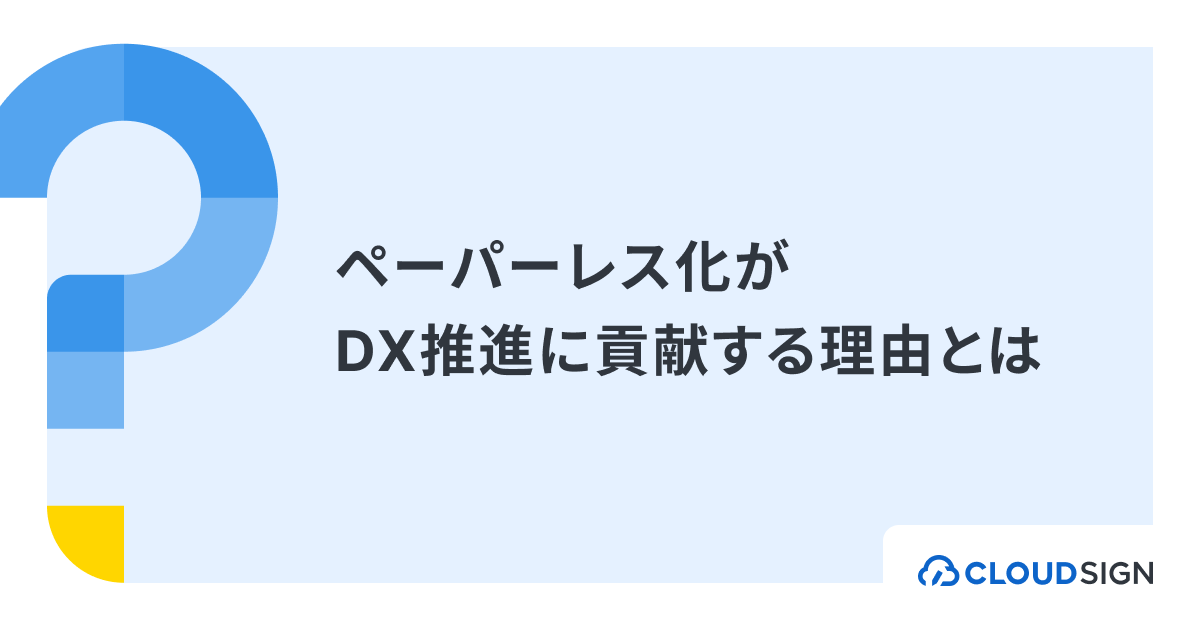
ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説
ペーパーレス化DX -

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説
ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法納品書経理DX -

DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説
DX -

API連携とは?仕組みや事例、導入のメリットなどを徹底解説
DX業務効率化API連携 -

【初心者必見】RPAとは何か?今更聞けない基本と導入のポイント
業務効率化RPA