ASPとは?SaaSとの違い、利用するメリット・デメリットを解説します

インターネットを介してソフトウェアやサービスを提供する事業者、またはそのサービス自体を「ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ、Application Service Provider)」と呼びます。
ASPを利用することで、自社でシステム開発するのに比べてコストや作業負担を軽減できる、リモートでも作業できるといったメリットがあります。
この記事ではASPとは何かを、初心者向けにわかりやすく解説します。コスト削減やワークスタイルの自由化などのメリットをもたらすASPサービスについて、この機会にぜひ覚えていってください。
無料ダウンロード


15の質問に答えるだけで、貴社における「紙業務のムダ度」がわかる診断リストです。「自社の紙文化を変えたいけれど上司や周囲を説得するための材料がなく、進められない」とお悩みの方はぜひ参考にしてください。
ASPとは何か?
ASP(Application Service Provider)とは、インターネットでソフトウェアやアプリケーションを提供している事業者のことを指します。
ASPの意味
ソフトウェアやアプリケーションを「提供している」といっても、パッケージを配布しているわけではありません。ASPのサーバーにインストールされたソフトウェアを、インターネット経由で契約ユーザーに利用させるサービスを提供しているのです。
つまりユーザーは自分のPC・スマートフォンなどにソフトウェアをインストールすることなく、インターネットにつながってさえいれば、どこからでも必要なソフトウェアを利用できるというわけです。

プロバイダ(Provider)という言葉からも分かるとおり、ASPは本来、事業者を指す言葉です。しかしその事業者が提供しているサービス自体をASPと呼ぶこともあるため、本記事では事業者を「ASP事業者」、サービスを「ASPサービス」と書きわけることにします。
他にもある「ASP」
なお、ASPという略語を用いている言葉はいくつもあり、IT関連用語だけでも以下のようものがあります。ASPという言葉が使われるシチュエーション、文脈によって、どういう意味なのかを判断してください。
【その他のASPについて】
●アフィリエイトサービスプロバイダ(Affiliate Service Provider)
ウェブサイトに広告を掲載したい側とウェブサイト運営側を仲介する、いわば広告代理店的な役割を果たす事業者のことです。
●アクティブサーバーページ(Active Server Pages)
マイクロソフト社が開発した、ウェブページの生成に関する技術です。
●情報共有システム、建設ASP(Application Service Provider)
公共工事に関する情報の共有や手続きを効率化する「情報共有システム」のことをASPや建設ASPと呼ぶことがあります。
ASPサービスには、どんなものがあるのか
ASPサービスは、個人向け・企業向けを問わずさまざまな場面で提供されています。
背景としては、インターネットの通信速度・品質が向上し、技術的にインターネットを通じてソフトウェアを動かせる環境が整備されたことが挙げられます。
ここでは、具体例を挙げながらASPサービスについて、より詳しく解説していきます。
ASPサービスの具体例
皆さんが普段利用されているソフトウェアの中にも、ASPサービスがあるかもしれません。たとえば、次のようなものです。
【ASPサービスの一例】
| サービスの種類 | 機能 | 具体例 |
| グループウエア | スケジュールや情報を共有する | GoogleWorkspace サイボウズ Office LINE WORKS など |
| ウェブメールアプリ | ブラウザでメールの送受信、管理を行なう | Gmail Yahoo!メールなど |
| ウェブサイト構築CMS | ウェブサイトの構築・管理・公開を行なう | Wix .com Shopifyなど |
| 勤怠管理・給与管理システム | 事務的な情報の処理・共有などに利用される | 楽楽勤怠 弥生給与Nextなど |
スケジュールや情報を共有するためのグループウェア、ウェブメールアプリ、ウェブサイト構築のためのCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)、財務、人事、販促などに用いられる各種アプリケーションなど、ASPサービスには多種多様なものが存在します。

多くは利用期間やユーザー数によって設定された料金を支払うサブスクリプション契約のもとで提供され、ユーザーはASP事業者が用意した認証システムにログインして、目的のサービスを利用することになります。
クラウドサービス/SaaSとの違い
ASPとクラウドサービスやSaaSは、IT業界においてほぼ同義として用いられており、両者の間に明確な定義の違いはありません。以前はASPと呼ばれていたモデルが発展して、今はSaaSと呼ばれるのが一般的と理解しておくと分かりやすいでしょう。どちらも、クラウド上で提供されるソフトウェアサービスを指す言葉です。
総務省の用語集英字で「SaaS」を調べてみても、次のように記載されています。
SaaS(サース、サーズ)
Software as a Service(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)の略。インターネット経由で、電子メール、グループウェア、顧客管理などのソフトウェア機能の提供を行うサービス。以前は、ASP(Application Service Provider)などと呼ばれていました。引用元:総務省「用語集英字」
ただし、一部のベンダー(提供事業者)においては、ASPとSaaSを以下のように区別するケースも存在するようです。
【ASPとSaaSを区別する場合について】
| ASP | SaaSの「発展形」とされ、シングルテナントとして区分される場合があります。 シングルテナントとは、ユーザー単位でサーバーやソフトウェアを割り当てる仕組みを指します。 つまり、1ユーザーにつき1セットのサーバーやソフトウェアが用意される方式です。 (ただし、厳密には「マルチテナント型」のASPも存在します) |
| SaaS | マルチテナントとして区分される場合があります。 マルチテナントとは、複数のユーザーがサーバーやソフトウェアを共用する仕組みを指します。 |
このように、ベンダーによってはASPを「シングルテナント」、SaaSを「マルチテナント」という技術的な方式の違いで定義づけていることがあります。
厳密な違いはないと理解しておいて問題ありませんが、特定のベンダーとやり取りする際には、そのベンダーがASPとSaaSをどのように定義づけているか、事前に確認してみることをおすすめします。
無料ダウンロード


専門機関による調査レポートを読み解くと、日本企業でDXがなかなか進まない背景には「DXを推進したい経営層」と「どのように推進したら良いかわからない現場」の「目線のズレ」があることがわかりました。この資料では、そのズレを乗り越える3つのポイントついて解説します。
ダウンロードする(無料)ASPサービスを利用するメリット
ASPを利用するメリットはいくつかありますが、主に以下の2点が挙げられます。
コストや作業負担を軽減できる
ASPサービスは、ソフトウェアをライセンス購入よりも安価に導入できる、インストール作業の必要がない、アップデートや保守などはASP事業者側で行なってくれるので手間がかからない…といったメリットを享受できます。
業務用ソフトウェアのライセンスを必要な分だけ購入するには、当然、相応のコストがかかりますし。さらに、ソフトウェアを何台ものデバイスにインストールする作業や、その後の保守・管理には手間と時間を割かれることになります。
リモートワークでも利用できる
ネットワークにつながってさえいれば、どこからでも利用できるというのも、ASPサービスのメリットです。外出先で見積もりをつくったり、リモートワークで仕事をこなせるようになったり、働き方の選択肢が広がります。
しかし社外からASPサービスを利用する際には、さまざまな重要データが詰まった社用パソコンを外に持ち出すのではなく、シンクライアント(データ保存ができないモバイルパソコン)を使い、ASP事業者のサーバーにデータを保存する方法をとるのが安全と言えるでしょう。
ASPサービスのデメリット、導入・利用上の注意点
ASPサービスの利用には次のようなデメリットもあります。
デメリットを理解した上で導入・利用すれば、不用意なトラブルを避けることができるので、リスク対策のために確認しておきましょう。
ネットワークへの接続が必須
ASPサービスは、一部の例外を除いて、ネットワークに接続できない環境では使えません。
接続環境が整っていたとしても、通信障害が発生すればサービス自体が使えなくなってしまいます。

セキュリティリスク
ASPサービスでは、セキュリティ対策の大部分をASP事業者に任せることになります。
このため、ASP事業者が攻撃を受けてしまいサービスが止まったり、自社の情報が漏えいしたりするといったセキュリティリスクがあります。もしASP事業者のセキュリティポリシーが自社にあわない場合は利用を諦めるか、自社のポリシーを変更しなければなりません。
多くのSaaSと同じように、ASPサービスでは複数のユーザーでサーバーやデータベースなどの環境を共用しているケース(マルチテナント型)もあるため、他ユーザーの利用状況によってはパフォーマンスやセキュリティに悪影響が出ることも考えられます。
サービス終了のリスク
ASP事業者の都合により、突然ASPサービスが終了し、使えなくなってしまう可能性もあります。
急にサービスが利用できなくなったときにどうするのか、同等の機能を持つ他のASPサービスやソフトウェアに、スピーディに移行することができるのかも、あらかじめ確かめておいた方が良いでしょう。
まとめ
低コストでスピーディに導入でき、多種多様な用途に応えるASPサービスは、今やビジネスに欠かせない存在と言えます。反面、頼りすぎると思わぬトラブルに巻き込まれてしまう危険性もあります。
ASPを利用する場合、リスクを踏まえた上で、利用契約を結ぶにあたってはできればトライアル期間を設け、安全性や安定性を確かめておくべきでしょう。
またそのASPサービスが本当に必要なのかを吟味、厳選することで、不要なリスクを背負い込まずにすむでしょう。
万が一サービスが止まってしまっても事業を継続できるよう、導入に当たっては予備の手段を用意しておく周到さが必要です。
なお、クラウドサインでは初心者が社内業務のデジタル化を推進するための手順・ツール選定のポイント、ITツールに関する情報収集方法やベンター選定のポイントをまとめた「デジタル化入門ガイド」をご無料でご提供しています。
気になる方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。
「電子契約から始めるデジタル化入門ガイド」


この資料では、IT知識がなくても社内業務のデジタル化を推進する方法を5つのステップに分けてやさしく解説しています。はじめてツールを導入する方やツール・ベンダー選定、導入後の運用・定着に不安のある企業ご担当者様はぜひご活用ください。
ダウンロード(無料)この記事を書いたライター
蔵捨
コピーライター
広告代理店勤務を経て、2001年からフリーランスに。ウェブを中心にIT系、ビジネス系の記事を執筆する他、企業ウェブサイトのコンテンツ制作、製品プロモーション映像の構成台本制作などを手掛ける。
こちらも合わせて読む
-

OEMとは? ODM、EMSとの違いを解説します
業務効率化製造業コスト削減 -

PDMとは? その必要性や導入のメリット、注意点について解説します
ペーパーレス化製造業DX -

データベースとは? 初心者にもわかりやすく解説します
DX業務効率化 -
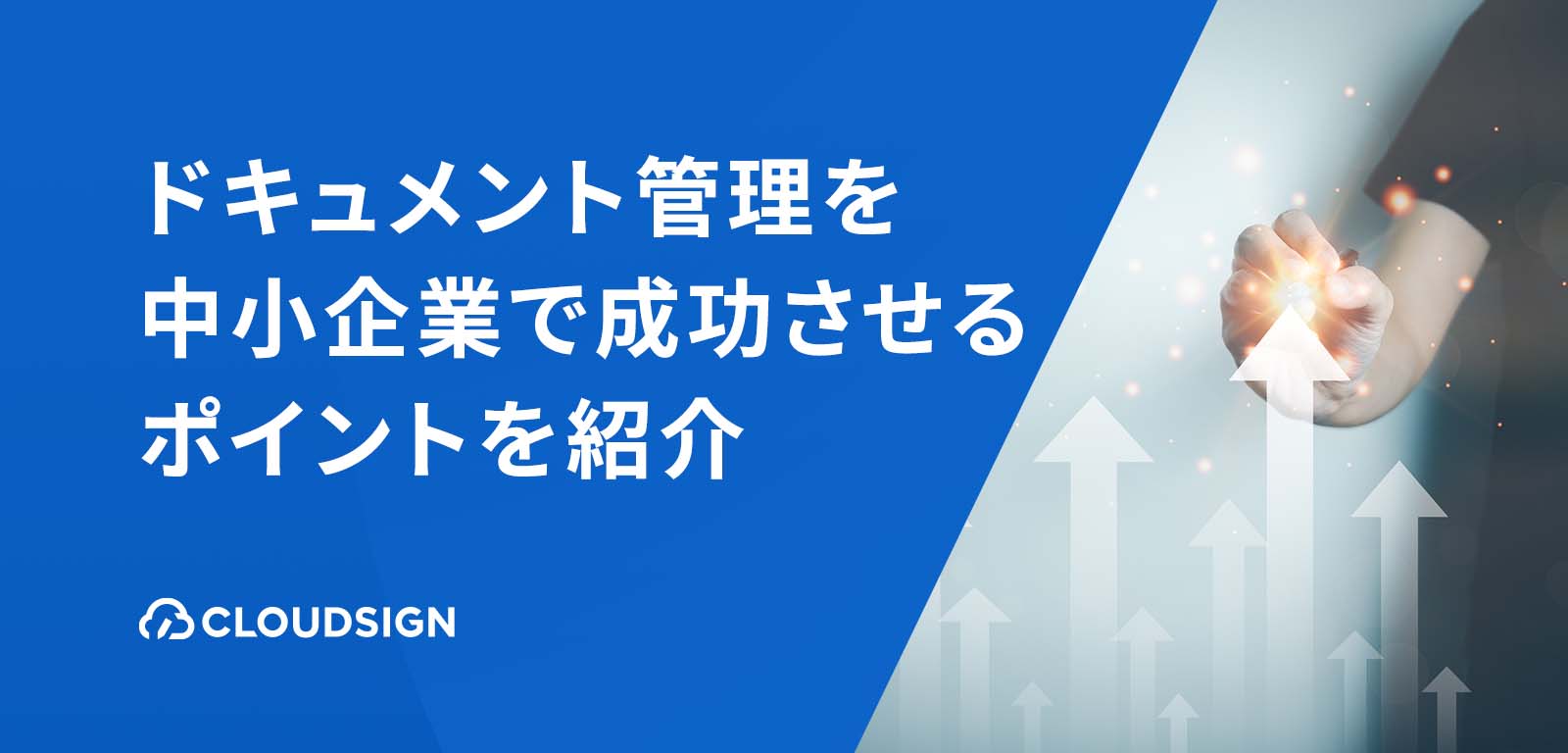
ドキュメント管理は「複利」で効果が現れる長期投資 中小企業が成功させるためのポイントを紹介
ペーパーレス化DX業務効率化電子帳簿保存法 -

IT資産管理ツール 完全ガイド DX時代の選定基準と厳選9選
DX業務効率化 -

シングルサインオン(SSO)とは?認証の仕組みをわかりやすく解説
DX業務効率化 -

ベンチマークとは?初心者向けに徹底解説します
新規事業マーケティング -
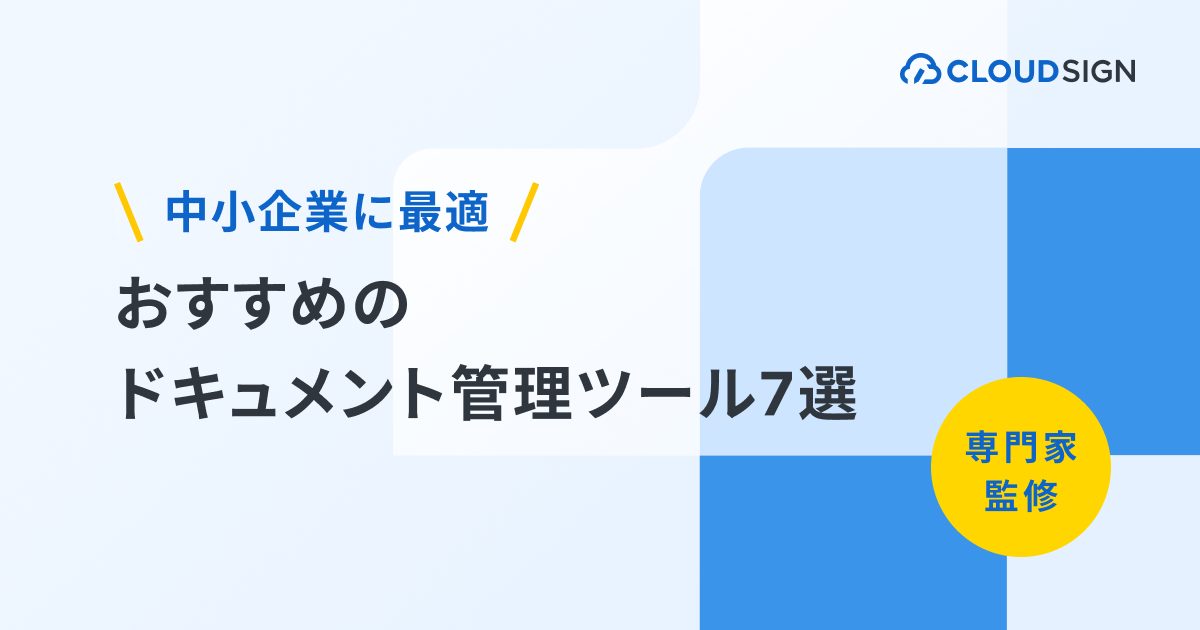
中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選
ペーパーレス化DX業務効率化 -

アドオンとは?その基本的な意味と役割を解説
DX業務効率化 -
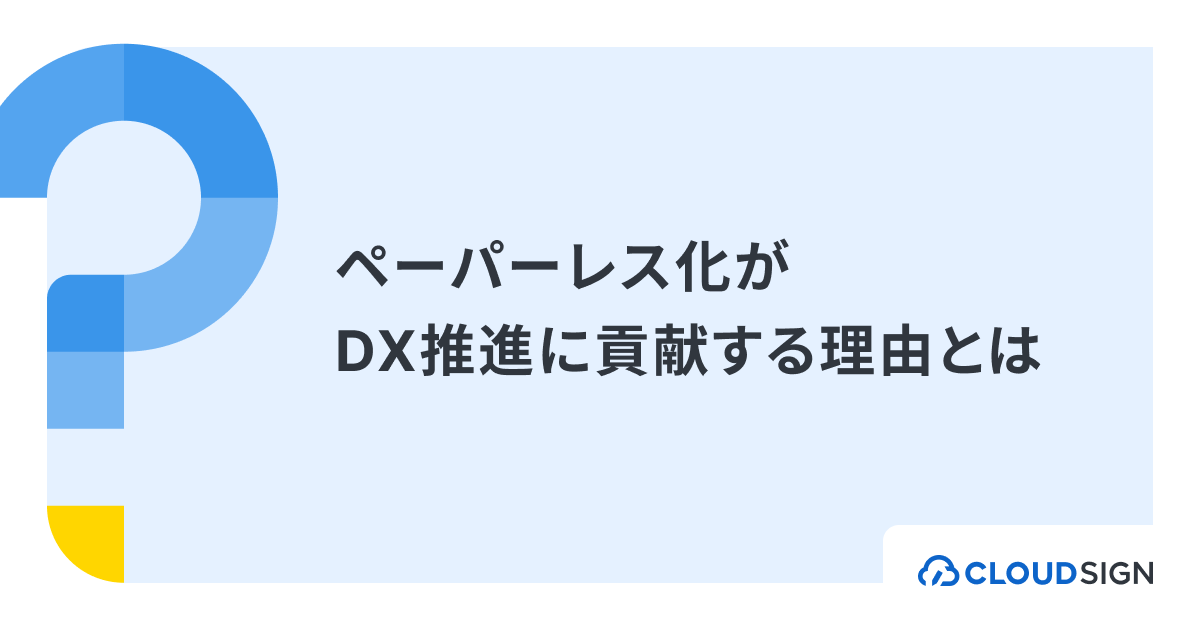
ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説
ペーパーレス化DX -

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説
ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法納品書経理DX -

DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説
DX -

API連携とは?仕組みや事例、導入のメリットなどを徹底解説
DX業務効率化API連携 -

RPA連携で何ができるか?連携の流れや活用事例を解説
業務効率化RPA -

【初心者必見】RPAとは何か?今更聞けない基本と導入のポイント
業務効率化RPA