Zoom議事録をAIで自動作成する方法を徹底解説

オンライン会議の増加に伴い、「会議の内容を正確に残したい」「議事録を効率的にまとめたい」というニーズが急増しています。
そんな中で注目を集めているのが、AIを活用したZoom議事録の自動作成です。
本記事では、ZoomでAIを活用して議事録を作成する方法を、初心者にもわかりやすく解説します。さらに、AI議事録ツール導入時の注意点も紹介します。
無料ダウンロード


契約書のチェックに生成AIを活用することで、法務人材不足・リーガルチェック費用の削減を図る企業様も多いことでしょう。しかし、生成AIを使ったリーガルチェックには4つのリスクが存在します。この資料では、リスクとその解決策について紹介します。
目次
「Zoom議事録をAIで作成する」とは?
AI議事録とは、Zoomなどの会議音声をAIが自動で文字起こし・要約・タスク抽出まで行う仕組みのことです。従来のように手作業で聞き返す必要がなく、記録のスピードと正確性を両立できます。
Zoomの議事録作成でAIを活用するメリット
- 議事録作成にかかる時間を大幅に削減できる
- 会議内容をリアルタイムで共有可能
- 会議後の要約・アクション抽出でタスク漏れ防止
- 複数会議の内容を一元管理できる
AI議事録が注目される背景
AI議事録が注目される背景には、「業務効率化と生産性向上へのニーズの高まり」「音声認識・生成AI技術の飛躍的進化」「働き方の変化と情報共有の重要性」という3点が挙げられます。
業務効率化と生産性向上へのニーズの高まり
従来の議事録作成は、会議中のメモ取りや後の文字起こしに多くの時間と労力を要し、担当者の負担となっていました。AI議事録は、この作業を自動化し、従業員を記録作業から解放することで、本来のコア業務に集中できるようになるため、企業全体の生産性向上に大きく貢献します。
音声認識・生成AI技術の飛躍的進化
近年のディープラーニングによる音声認識技術の向上により、複数話者の識別や専門用語の認識精度が大幅に向上しました。さらに、生成AIの活用により、会議内容の自動要約や重要タスクの抽出が高精度で行えるようになり、議事録の質と利便性が向上しました。
働き方の変化と情報共有の重要性
リモートワークやハイブリッド勤務の普及に伴い、場所を問わず正確かつ迅速に会議情報を共有する必要性が増しています。
テレワークやハイブリッドワークが定着すると、「ちょっと時間いい?」などと声を掛けて仕事を依頼したり、「あれどうなったっけ?」と進捗を確認したりする機会は減ります。そうした対面コミュニケーションの機会が減るに連れ、会議の議事録に「誰が」「何を」「いつまでに」やるのかを正確に記録し、共有することの重要性は増していきます。
AI議事録ツールはクラウドベースで利用できるものが多く、情報共有の迅速化と透明性を確保できるため、新しい働き方のインフラとして不可欠になっています。
Zoom会議をAIで議事録化する手順
Zoom会議の議事録をAIで自動作成するには、いくつかの方法があります。
ここでは、できるだけ手間をかけずに議事録を自動生成できる「Zoom内蔵のAI要約(AI Companion、AIコンパニオン)を使う方法」について詳しく解説します。
Zoom内蔵のAI要約(AI Companion)とは?
Zoomに内蔵されているAI要約(AI Companion、AIコンパニオン)とは、Zoomプラットフォーム全体に組み込まれた生成AI機能の総称です。プロやビジネスなどの有料プランで利用することができます。
AI Companionの中でも「ミーティング要約」機能は、会議中の発言をリアルタイムで文字起こしし、会議終了後には、議論された内容、決定事項、主要な論点、次のステップ(ToDoリスト)を自動的に抽出して要約を生成できるため、とくに注目されています。
生成された要約は、設定しておくことにより、メールやZoom Team Chatを通じて参加者に速やかに共有され、会議に参加できなかった人も簡単に内容をキャッチアップできます。
Zoomに内蔵されているAI要約機能(AI Companionによるミーティング要約)を使用する手順は、主に事前設定(有効化)とミーティング中の操作、ミーティング終了後の確認・共有の3段階に分かれます。各ステップの具体的な手順を確認しておきましょう。
ステップ1:WebポータルでのAI要約機能の有効化(初回のみ)
AI Companionを利用するには、Zoomのウェブポータルで事前に機能を有効化しておく必要があります。
- Zoomウェブポータルにサインインします(Zoomアプリではなくブラウザから)。
- 左側のナビゲーションメニューで [設定] をクリックします。
- 上部のタブから [AI Companion] を選択します。
- [AI Companionによるミーティング要約] の項目を探し、トグルスイッチをクリックして**有効(オン)**にします。
(注意) この設定がグレーアウトしている場合、管理者によってロックされているため、ご自身の組織のZoom管理者に有効化を依頼する必要があります。 - 必要に応じて、「ミーティング開始時に自動的にミーティング要約をオンにする」 などのオプションも設定します。
ステップ2:ミーティング要約の開始と確認(ホスト/参加者)
事前の設定としてステップ1が完了したら、ミーティング中に以下の操作で要約を生成します。
【ホストとして要約を開始する手順】
- Zoomデスクトップアプリまたはモバイルアプリでミーティングを開始します。
- ミーティングの下部ツールバーにある [AI Companion] のアイコンをクリックします。
- 表示されたメニューから [要約を開始] (または [ミーティング要約を開始])を選択します。
- 参加者に要約が開始されたことが通知されます。
- 要約を停止したい場合は、再び [AI Companion] から [要約を停止] をクリックします。
【参加者として要約を確認する/リクエストする手順】
- 確認: ホストが要約を開始すると、参加者には要約がアクティブである旨が通知されます。
- リクエスト: ミーティング中に要約機能が有効になっていない場合、[AI Companion] をクリックし、[要約を開始するようリクエストする] を選択することで、ホストに開始を促すことができます。
ステップ3:要約結果の確認と共有(ミーティング終了後)
ミーティングが終了すると、要約が自動的に生成され、指定された場所に送信されます。
- メールで確認: ホストが設定している場合、ミーティング終了後に要約テキストまたは要約ページへのリンクが記載されたメールが届きます。
- Zoomウェブポータルで確認:
・Zoomウェブポータルにサインインします。
・左側のナビゲーションメニューの [要約] をクリックします。
・過去のミーティング要約のリストから、該当する要約にアクセスして内容を確認、編集、または共有できます。 - Zoom Team Chatで確認: 要約が設定されている場合、対応するTeam Chatグループに要約が自動送信されます。
自動生成された議事録の整形・共有の流れ
何の方法を用いるにしてもAIが生成した議事録はそのまま使うのではなく、
- 不要な発言の削除
- アクションアイテムの整理
- 社内共有フォーマットへの整形
を行うことで、より活用しやすい形に整えましょう。
無料ダウンロード


「生成AIを活用して契約書業務を効率化したい」と考える企業様に知っていただきたい、法務DXにおける生成AI活用のリスクや、契約書業務をうまく進めるコツについて解説資料のセットです。
AI議事録を導入する際の注意点
Zoom AI Companion(AIコンパニオン)を使用する際は、その利便性の裏にある技術的な特性やコンプライアンス上の課題を理解し、慎重に対応する必要があります。
主な注意点を3つのテーマで詳しく説明します。
1. 情報の正確性と「ハルシネーション」への対応
AI Companionは高度な生成AIを活用していますが、その出力の正確性には限界があります。
業界独自の専門用語や固有名詞、あるいは複数の話者が同時に発言する場面では、AIによる文字起こしや要約に誤認識が生じる可能性があります。要約が文脈を誤解釈する「ハルシネーション(嘘の生成)」のリスクも排除できません。
対策としては、AIの出力は「速報版」と位置づけ、特に機密性の高い内容や決定事項については、必ず人間が最終確認・修正を行うようにしましょう。
AI Companionのサイドパネルにも表示される通り、「AIは間違った情報を提供する場合があります。必ず情報の正確性をご確認ください」という認識を持つことが重要です。
2. データプライバシーとコンプライアンスの遵守
ZoomはユーザーデータのAI学習への利用を否定していますが、機密情報の取り扱いには引き続き細心の注意が必要です。
Zoomは、顧客のデータ(オーディオ、ビデオ、チャット、添付ファイルなど)をAIモデルの学習に使用しない方針を明確にしています。(出典:Zoomセキュリティとプライバシー)
ただし、AI Companionが処理するデータが米国などのデータセンターで処理される可能性があるため、特定の地域や業界では、機密情報の取り扱いについて、管轄地域の法令に基づき、自社のコンプライアンス部門と連携して利用を判断する必要があります。
出典:Zoom AI Companionの機能によるデータの取り扱いについて(双日テックイノベーション)
録音や文字起こしが有効化されると、ミーティング画面に「レコーディング・AI文字起こし中」の通知が表示されますが、ホストは事前にAI機能を利用する旨を参加者全員に通知し、同意を得ておくことがトラブル防止の基本です。
3. 機能利用の前提条件と制限事項
AI Companionはすべてのユーザーが常に利用できるわけではなく、いくつかの技術的・契約上の制限があります。
| 機能要件 | 制限事項 |
| 有料プランが必須 | AI要約などの高度なAI Companion機能の多くは、有料ライセンス(プロ、ビジネスなど) を持つユーザーのみが利用可能です。 |
| 管理権限と有効化 | AI Companion機能は、デフォルトで無効になっていることが多く、管理者によるアカウントレベル での有効化が必要です。ユーザー自身が機能を利用できるようになっているか、管理者設定を確認 する必要があります。 |
| 機能上の制限 | ミーティング要約機能は、ブレイクアウトルームでは利用できません。 また、ホスト及び共同ホスト以外はAI Companionの直接的な操作(オン/オフの切り替えなど)が 原則としてできません。 |
AI Companionを導入・利用する際には、「便利だが、万能ではない」という認識を持ち、情報の正確性の確認、プライバシーポリシーの遵守、そして利用条件のクリアを徹底することが、組織における適切な活用に繋がります。
Zoom AI companionが使えない時の代替案
Zoom AI Companionが使えない場合や、セキュリティ上の懸念から利用を避けたい場合にZoom会議の議事録を自動作成する方法として、代替案としては、次のような方法が挙げられます。
| 代替案 | 具体的な方法 | メリットと注意点 |
| Zoomの文字起こし機能を使う | Zoomの自動字幕 +Chat GPTなどの生成AI |
Zoom会議の音声をリアルタイムで文字起こし できます。無料プランでも利用できます。 文字起こしデータの保存はできますが、 議事録作成は自分で生成AIなどを活用して 行なう必要があります。 |
| 外部ツールと連携する | Notta、スマート書記、 Rimo Voiceなど |
AI議事録ツールに録音もしくは録画データを アップロードし、自動で議事録を作成する。 AI搭載で文字起こし精度が高く、話者識別や 要点抽出機能が充実しています。 ただし、多くは有料プランが必要です。 |
| Zoom会議の録画データをもとに 文字起こし・議事録作成する |
Zoomの録画機能 +Chat GPTなどの生成AI |
Zoomでは、コンピュータレコーディングと クラウドレコーディングの2種類が提供され ています。 すべてのZoomアカウントで利用可能なコン ピュータレコーディングは、コンピュータに 直接保存されます。 有料アカウントで利用できるクラウドレコー ディングはZoomクラウドに保存され、 文字起こしデータの自動保存、共有、 ダウンロードが可能です。 議事録作成は自分で生成AIなどを活用して行う 必要があります。 |
| 外部AIの活用 | OpenAI Whisperや ChatGPT(高度な音声モード) |
録音した音声ファイルをアップロードすること で、高精度な文字起こしが可能です。 要約機能も使えますが、機密情報の取り扱いに 注意が必要です。 |
具体的な手順や方法、おすすめのツールについては、次の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
まとめ|AIで議事録作成を自動化して生産性を高めよう
AIを活用すれば、Zoom会議の議事録作成は手間のかかる作業から戦略的な情報活用プロセスへと進化します。
まずは自社に合うAI議事録ツールを見つけるのがおすすめです。
なお、クラウドサインでは「会社全体でDXや業務改善を進めたいけれど、なかなかうまくいかない」と悩む経営者やDX推進担当者に向けて、DX推進が進まない原因や、取り組みのポイントをまとめた資料をご用意しています。
DX推進担当者はもちろんのこと、生成AI活用など全社にまたがる業務改善プロジェクトに共通するポイントが盛りだくさんの内容なので、「周囲の巻き込み力」を高めたい方はぜひ参考にしてみてください。
無料ダウンロード


専門機関による調査レポートを読み解くと、日本企業でDXがなかなか進まない背景には「DXを推進したい経営層」と「どのように推進したら良いかわからない現場」の「目線のズレ」があることがわかりました。この資料では、そのズレを乗り越える3つのポイントついて解説します。
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
橋爪兼続
ライトハウスコンサルタント代表
2013年海上保安大学校本科第Ⅲ群(情報通信課程)卒業。巡視船主任通信士を歴任し、退職後、大手私鉄の鉄道運行の基幹システムの保守に従事。一般社団法人情報処理安全確保支援士会の前身団体である情報処理安全確保支援士会の発起人。情報処理安全確保支援士(第000049号)。
この記事を書いたライター
業務改善プラスジャーナル編集部
業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。
こちらも合わせて読む
-

建設業の後藤組がDXの自走を可能にした「頑張らなくていい」の哲学
DX業務効率化建設業経営建設DX -
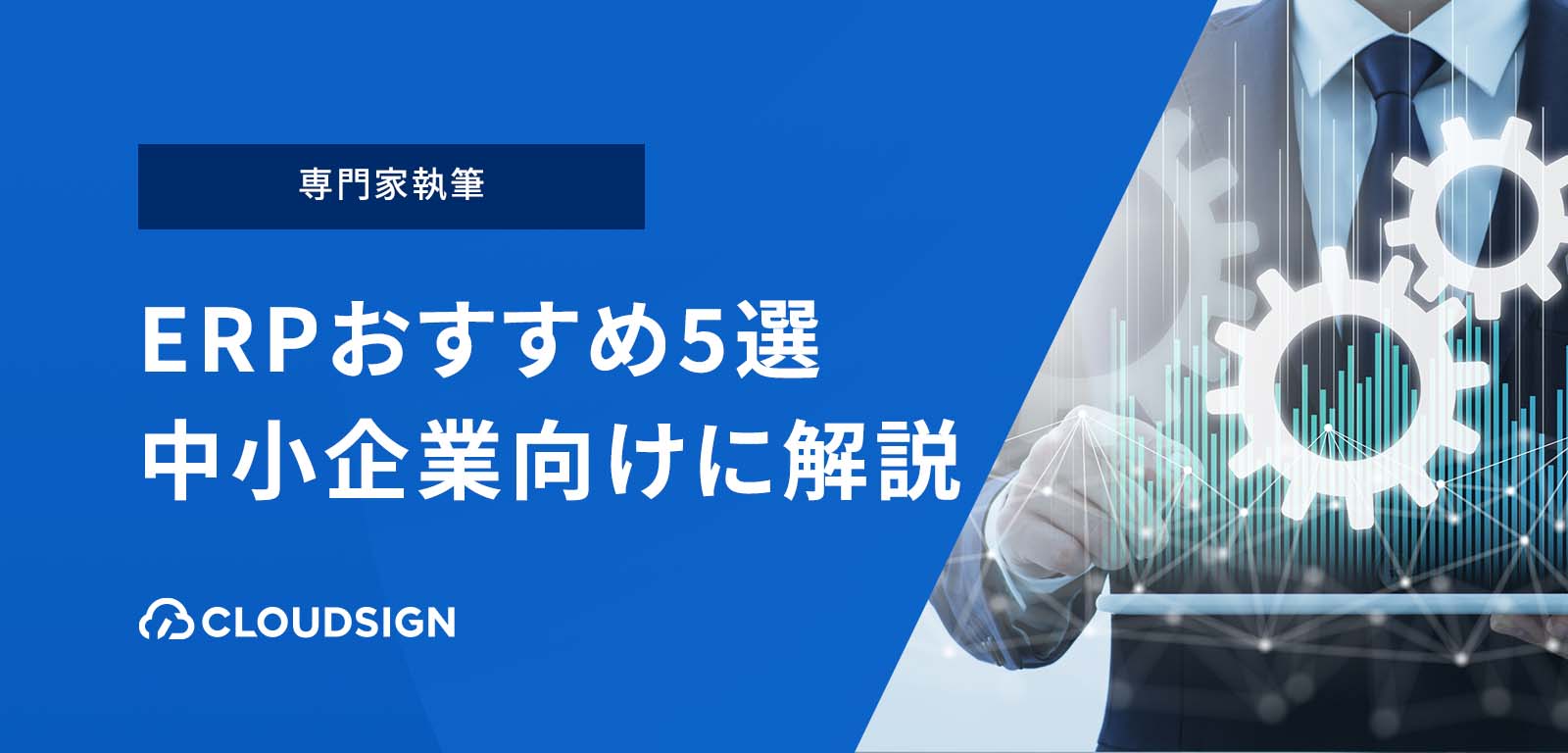
ERPおすすめ5選を徹底比較 中小企業向けに選ぶ際のポイントを解説
ペーパーレス化DX業務効率化経理DX経営 -

データウェアハウス(DWH)とは? データベース、データレイクとの違いや、利用のメリットを解説します
ペーパーレス化DX -
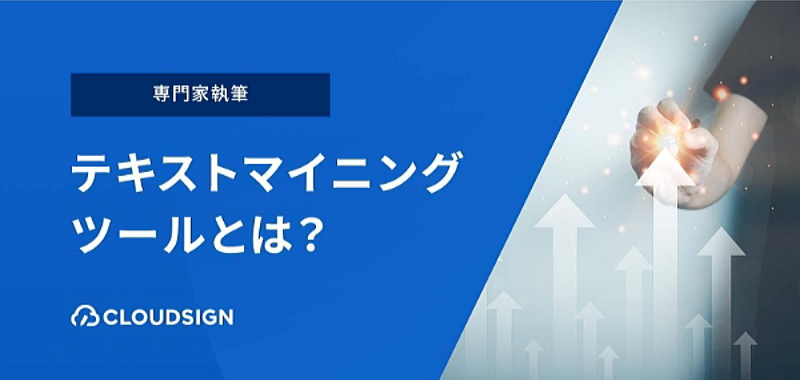
テキストマイニングツール徹底比較 無料で使えるおすすめ5選と選び方ガイド
ペーパーレス化DX業務効率化マーケティング会議DX営業DX -

ノーコード開発とは? 無料で試せるノーコードツール5選と活用法
ペーパーレス化DX業務効率化新規事業 -

Web会議システムとは?選び方や代表的な4つのツールを徹底解説
ペーパーレス化DX業務効率化マーケティング会議DX多様な働き方の実現 -

無料で始めるBIツール徹底比較|おすすめ5選と選び方のポイント
ペーパーレス化DX業務効率化新規事業マーケティング -

OEMとは? ODM、EMSとの違いを解説します
業務効率化製造業コスト削減 -

PDMとは? その必要性や導入のメリット、注意点について解説します
ペーパーレス化製造業DX -

データベースとは? 初心者にもわかりやすく解説します
DX業務効率化 -

中小企業で全体最適を成功させるコツとは?部分最適に陥ってしまう要因と解決策
ペーパーレス化DX業務効率化プロジェクトマネジメント -

ASPとは?SaaSとの違い、利用するメリット・デメリットを解説します
DX業務効率化 -

シングルサインオン(SSO)とは?認証の仕組みをわかりやすく解説
DX業務効率化 -

全体最適とは?今日からできる、中小企業のための実現方法をわかりやすく解説
業務効率化プロジェクトマネジメント -

アドオンとは?その基本的な意味と役割を解説
DX業務効率化 -

業務効率化とは? 生産性アップの秘訣
業務効率化 -

DXに欠かせない一元管理とは?メリットや利用時のポイントを解説
DX業務効率化プロジェクトマネジメント -

API連携とは?仕組みや事例、導入のメリットなどを徹底解説
DX業務効率化API連携 -

RPA連携で何ができるか?連携の流れや活用事例を解説
業務効率化RPA -

業務効率化におすすめのツール13選 導入のメリットや利用例を紹介
業務効率化 -

【初心者必見】RPAとは何か?今更聞けない基本と導入のポイント
業務効率化RPA