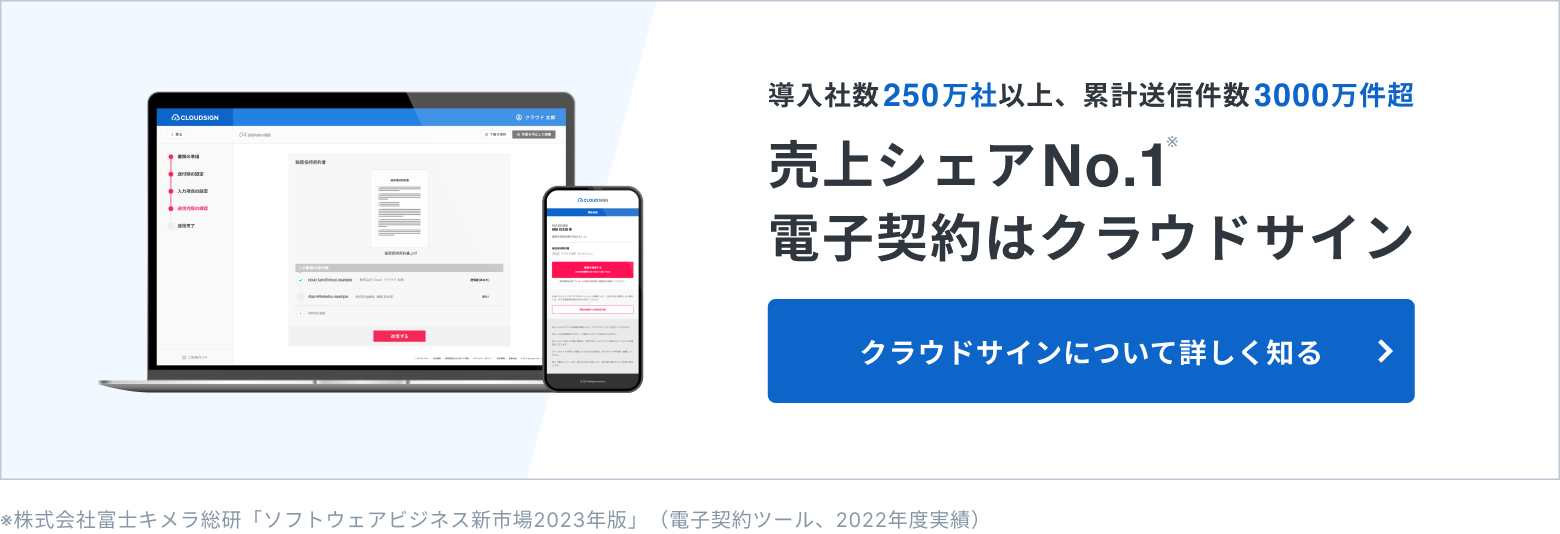請求書の保存方法とは?電子帳簿保存法に対応した方法、原本の保存が必要なケースなどを解説
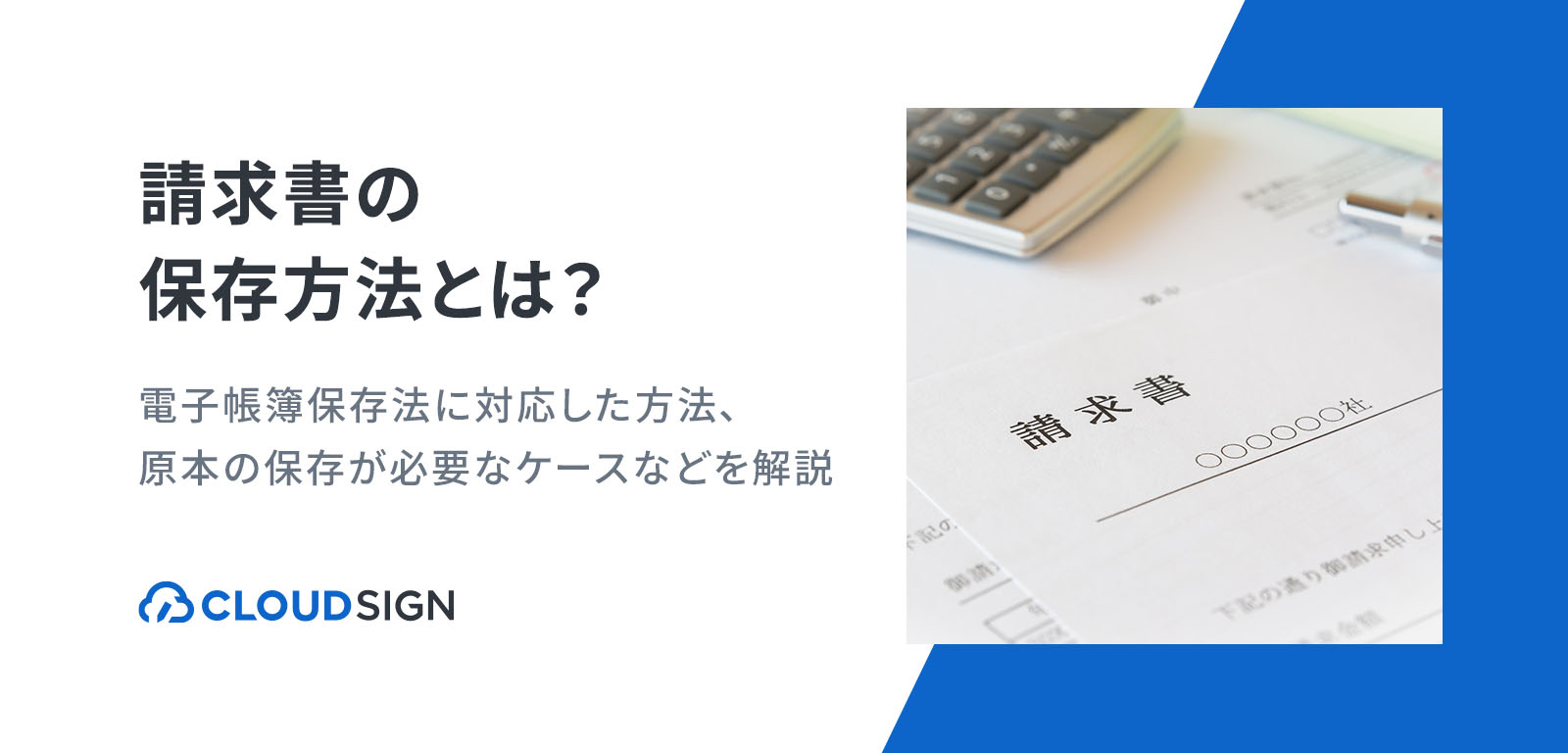
本記事では請求書の保存方法について、電子帳簿保存法に対応した方法や、紙の原本を保管すべきケースなどを詳しく解説します。
請求書の適切な保存は、企業の会計処理や税務対応に欠かせないものですが、電子帳簿保存法の改正により、PDFなどの電子データで受領した請求書の保存ルールが厳格化され、企業は適切な対応を求められています。一方で、紙の請求書は原本の保存が必要なケースもあり、状況に応じた管理が重要です。
本記事を参考にして、適切に請求書を管理し、法令遵守と業務効率化を両立させましょう。
目次
請求書の保存方法とは?
請求書は取引時の発行義務はありませんが、取引の証拠となる大事な証憑書類です。発行された場合は法的効力が発生するため、適切な方法で保存しなくてはいけません。ここでは、電子データおよび紙面で作成・受領した請求書の正しい保存方法について簡単に紹介します。
電子データで作成・受領した請求書の保存方法とは?
電子データで作成・受領した請求書の保存は、電子帳簿保存法に基づいて適切に管理する必要があります。2022年1月の法改正により、電子データで受け取った請求書は、紙に印刷して保存するのではなく、後述する電子取引データの保存要件を満たす形式で、電子データのまま保存することが義務化されました。
具体的な保存方法の例としては、以下のようなものがあります。
- クラウド型の請求書管理システムを利用し、タイムスタンプを付与して保存
- 会計ソフトの電子保存機能を活用し、請求書データを紐付ける
- 社内サーバーにPDFで保存し、検索機能を導入して管理
電子データの請求書は、タイムスタンプやアクセス権限を適切に設定し、データの信頼性を確保するとともに、システム障害に備え、バックアップを定期的に取得することが推奨されます。
電子データの請求書を正しく保存することで、業務の効率化やペーパーレス化を推進できるため、適切な管理体制の構築が重要です。
紙で受領した請求書の保存方法とは?
紙で受領した請求書は、電子データと異なり、従来通り紙の原本を保存する方法と、スキャンして電子データとして保存する方法(スキャナ保存)の2つが考えられます。
原則として、紙で受領した請求書は原本の保管が求められますが、電子帳簿保存法の要件を満たせば、紙の請求書をスキャナ保存し、元本の破棄も可能です。
紙の請求書の管理は、電子データに比べて手間がかかるため、スキャナ保存の活用やペーパーレス化の推進が求められます。
請求書を電子データで保存する際の要件
電子帳簿保存法の改正により、取引先から受領した請求書や、企業内で作成した請求書を電子データとして保存することが認められました。
ただし、元の請求書が電子データか紙面かによって、保存する際の要件が細かく定められています。要件を満たしていないデータは正式な証憑として認められない恐れがあるため、保存要件についてしっかりと理解しておきましょう。
電子データで作成・受領した請求書の場合
電子データで作成・受領した請求書は、電子帳簿保存法に基づき、電子データのまま保存することが義務付けられています。現在(2024年1月以降)は、紙へ印刷して保存することは認められなくなったため注意しましょう。
電子データの請求書の保存については、法改正以降は以下の要件を満たす必要があります。
- 真実性の確保:請求書を誰がいつ発行・受領したかなどの証拠を細かく残すために、タイムスタンプの付与や改ざん防止措置(アクセス制限・履歴管理)を実施する
- 可視性の確保:取引日・金額・取引先などの条件で検索できるように検索機能付きのシステムやファイル名の工夫を実施する、操作用の機器やソフトウェア・ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付けて速やかに出力できるようにする
真実性とは、その電子データが作成された時点から変更・改ざんされていないこと、または訂正や削除が行われた場合にその事実と内容を確認できることを意味します。つまり、記録された情報が正当なものであり、不正な手が加えられていない状態のことをいいます。
可視性とは、保存されている電子データ(電子取引の記録など)を、必要に応じていつでも確認・参照できる状態にしておくことを意味します。また、税務調査に対応するため、請求書を迅速に提示・出力できる体制も整える必要があります。保存するファイル形式は問われず、PDFに変換したものやスクリーンショットでも問題ありません。
実務上は、クラウド型の請求書管理ソフトや会計ソフトと連携し、受領から保存までを一元管理する企業が増えています。保存期間は原則7年(最長10年)のため、期限管理ができるシステムの活用が有効です。
【参考: 電子取引データの保存方法をご確認ください-国税庁】
紙面で作成・受領した請求書の場合
紙で作成・受領した請求書は、これまで通り原本を紙のまま保存することが可能ですが、電子帳簿保存法の要件を満たすことで、スキャナ保存(電子化)も認められます。
紙で受け取った請求書を電子保存する場合には、以下のスキャナ保存要件にのっとる必要があります。
- 真実性の確保:タイムスタンプの付与や訂正・削除履歴の記録など
- 可視性の確保:検索機能により、取引先名・日付・金額などの条件で請求書データを検索できる必要がある
- スキャンの技術要件:解像度200dpi以上・256階調以上など、一定以上の品質でスキャンしなければならない
- 入力期間の期限:原本を受領後、おおむね7営業日以内と速やかにスキャナ保存すること(最長2ヶ月)
これらの要件を満たすには、クラウド型の文書管理システムやスキャナ保存に対応したサービスの利用が推奨されます。
紙の書類からスキャナ保存に切り替える場合は、社内の運用ルール整備や事前準備が必要であり、保存ルールに不備があると経費計上が否認されるリスクもあるので注意しましょう。
紙面の請求書を電子保存した場合は原本は破棄してもよい?
紙面の請求書を電子保存した場合、電子帳簿保存法の要件を満たしていれば、原本を破棄することが可能です。これはスキャナ保存要件に基づくもので、正しい手続きと保存方法を守っていれば、紙のまま保管しておく必要はありません。
スキャナ保存が認められるためには、いくつかの条件があります。まずは請求書をスキャンした際にタイムスタンプを付与すること、そして訂正や削除の履歴が残るシステムで管理することが必要です。
スキャンの際には解像度200dpi以上かつ256階調以上といった技術的な条件も定められています。さらに、請求書を受領してから原則7営業日以内にスキャンを完了させなければなりません。
これらの要件を満たしていない場合は、電子保存は認められず、原本を破棄することはできません。制度の理解不足や保存ルールの不備があると、税務上の問題につながる恐れがあるため、導入時には適切な電子保存システムを活用するなど、慎重に準備を進めることが大切です。
スキャナ保存の要件詳細を確認したい場合は国税庁の公式サイトにある「Ⅱ 適用要件【基本的事項】」を参考にしてください。
請求書を電子保存する際のポイント

請求書を電子保存する際は、制度の改正に適切に対応する必要があります。ここでは、請求書を電子保存する際の4つのポイントについて、わかりやすく解説します。
スキャナ保存に対応しているシステムを導入して効率化する
紙の請求書を電子保存するためには、スキャナ保存に対応しているシステムを導入するのが効果的です。
紙の請求書をスキャンし、適切にデータ化・分類・保存する作業を人手で行なうのは非効率でミスも起こりやすいです。タイムスタンプの自動付与や検索機能、訂正履歴の記録などが備わった電子帳簿保存法対応のクラウドサービスを利用することで、法令遵守と業務効率化の両立が可能になります。
こうしたシステムは自動仕訳や他の会計ソフトとの連携機能も備えていることが多く、請求書の受領から経理処理までを一気通貫で進められます。
なお、当社の提供する電子契約サービス 「クラウドサイン」はスキャナ保存の要件に対応可能な電子契約サービスです。直感的なUIでITツールに不慣れな担当者でも使いやすく、企業内での導入がスムーズに実施しやすいため、請求書以外にも契約書を電子化したい・紙の書類を減らして業務効率化を考えたいという方は検討してみてはいかがでしょうか。
社内マニュアルを整備する
電子保存を確実に運用するためには、社内で統一された運用ルールやマニュアルを整備することが不可欠です。
どの部署が請求書をスキャン・保存するのか、どのようなファイル名・保存形式で管理するのかといった細かいルールを明文化しておきましょう。そうすることで、業務の属人化を防ぎ、誰が対応しても同じ品質で運用が可能になります。
電子帳簿保存法に準拠するには、タイムスタンプの取り扱いや検索機能の活用方法など、専門的な知識が必要な場面もあるため、定期的な社内研修やマニュアルの見直しも重要です。
万一、税務調査が行われた際にも、ルールに従って整然と保存されていることで、スムーズな対応ができ、信頼性の高い業務体制を築けます。
インボイス制度や電子帳簿保存法に対応する
請求書の電子保存を行なう際は、単にPDFなどで保存するだけでなく、「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」の両方に対応することが求められます。
2023年に始まったインボイス制度では、仕入税額控除の要件を満たすために、適格請求書(インボイス)の保存が義務づけられており、その内容を正確に記録・保存する必要があります。
また、電子データで受領した請求書は、電子帳簿保存法に従って、改ざん防止措置(タイムスタンプや履歴の記録)や検索機能の確保が必要です。
これらの法令を正しく理解し、対応可能なシステムや運用体制を整えることが、企業としてのコンプライアンスを維持するうえでも非常に重要です。
電子保存について取引先にも伝える
電子保存を本格的に導入する際は、自社だけでなく、取引先にもその方針や運用方法をしっかり伝えることが重要です。
特に、これまで紙の請求書をやり取りしていた取引先に対しては、電子データでの受領・発行への切り替えを通知したうえで、ファイル形式や送信方法(メール添付やクラウド経由など)を調整する必要があります。
取引先が制度や電子保存に不慣れな場合は、丁寧な説明やマニュアルの共有を行なうと、双方にとってスムーズな移行が可能になるでしょう。情報共有をしっかり行なうことで、誤送信や保存漏れといったリスクも軽減でき、信頼関係の維持にもつながります。
請求書の電子保存についてよくある質問
電子メールで受け取った取引情報はどうやって保存すればいい?
電子メールで受け取った請求書などの取引情報は、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当するため、メール本文や添付ファイル(PDFなど)を電子データのまま保存する必要があります。
紙に印刷して保管するだけでは法令違反になるため注意しましょう。保存にあたっては、改ざん防止のためのタイムスタンプの付与や、訂正・削除履歴が残る仕組みを導入することが求められます。
さらに、取引日・取引先・金額などで検索できる機能を持った保存方法でなければなりません。対応策としては、専用の電子取引保存システムや会計ソフトを利用する方法がおすすめです。
電子請求書は押印しなくてもいい?
法律上、請求書に印鑑を押す義務はなく、特に電子データでのやり取りの場合は、押印の代わりにメール送信履歴や電子署名などで証明できれば問題ありません。
請求書の発行や受領に関しては、印鑑の有無よりも、内容が正確であることや、相手との合意が取れているかが重要といえます。
ただし、取引先によっては慣習として押印を求めるケースもあるため、事前に確認が必要です。どうしても印影が必要な場合は、電子印鑑を請求書に挿入するという方法もあります。
最近では多くの企業がペーパーレス化を進めており、印鑑の有無よりもスムーズで正確な請求処理が重視される傾向にあるといえるでしょう。
紙面で受け取った請求書は電子データで保存するべき?
紙で受け取った請求書も、業務の効率化や保管スペース削減の観点から電子保存することが推奨されます。
ただし、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存として認められるには、いくつかの要件を満たす必要があるため注意しましょう。電子保存の要件を満たしていれば、電子データとして保存後、元本の破棄が可能です。
紙面で受け取った請求書を電子データによって保存すると、検索機能によって請求書が必要な際にすぐに探し出せるため業務の効率化に繋がります。適切なセキュリティが施された電子契約システムを利用すれば、請求書の紛失や情報漏えいなどのリスクも最小限に抑えられるでしょう。
電子請求書は何年間保管しておくべき?
電子請求書の保存期間は、紙の請求書と同様に、原則7年間とされています。これは、法人税法・消費税法における帳簿書類の保存義務に基づくものです。
青色申告を行っている法人で、欠損金の繰越控除などを受けている場合は、最大10年間の保存が必要になるケースもあります。
電子取引として受領した請求書データは、電子帳簿保存法に準じた保存要件を満たした状態で、削除・改ざんができない形での長期保管が求められます。税務調査の際には、速やかに請求書データを提示できるように、整理された状態で保存しておくことも重要です。
保存先には、セキュリティ性の高いクラウドストレージや専用の電子保存システムを利用すると、安心して長期保管ができます。
ペーパーレス化から業務効率化を進めるなら電子帳簿保存法に対応した電子契約サービス「クラウドサイン」の検討を
本記事では、請求書を電子データまたは紙で保存する場合の適切な方法や、請求書を電子保存する際のポイントなどについて詳しく解説しました。
東京都など全国の自治体や企業でペーパーレス化をはじめとした電子化による業務効率化が広がっていくなかで、電子帳簿改正法により、電子データで受領・作成した請求書等の書類はデータのままでの保存が義務付けられました。紙面で受領・作成した請求書も、検索性や紛失リスクなどの観点からスキャナ保存が推奨されますが、紙面の請求書を電子データとして保存する場合は電子帳簿法で定められた要件を満たす必要があります。
適切な形での請求書管理を実現するなら、クラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」の利用をご検討ください。クラウドサインは電子帳簿保存法の電子取引保存に関するシステム要件①〜④を満たすことができる電子契約サービスです。
紙書類の電子化を進めるにあたって電子帳簿保存法への対応を気にされている方は、クラウドサインを導入し、電子帳簿保存法で定められた対応をしていれば、問題なく運用いただけます。
なお、クラウドサインでは書類の電子化を検討している方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター
業務改善プラスジャーナル編集部
業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。
こちらも合わせて読む
-
業務改善に役立つシステム・ツール

中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選
ペーパーレス化DX業務効率化 -
業務改善に役立つシステム・ツール

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説
ペーパーレス化請求書納品書 -
業務改善の進め方
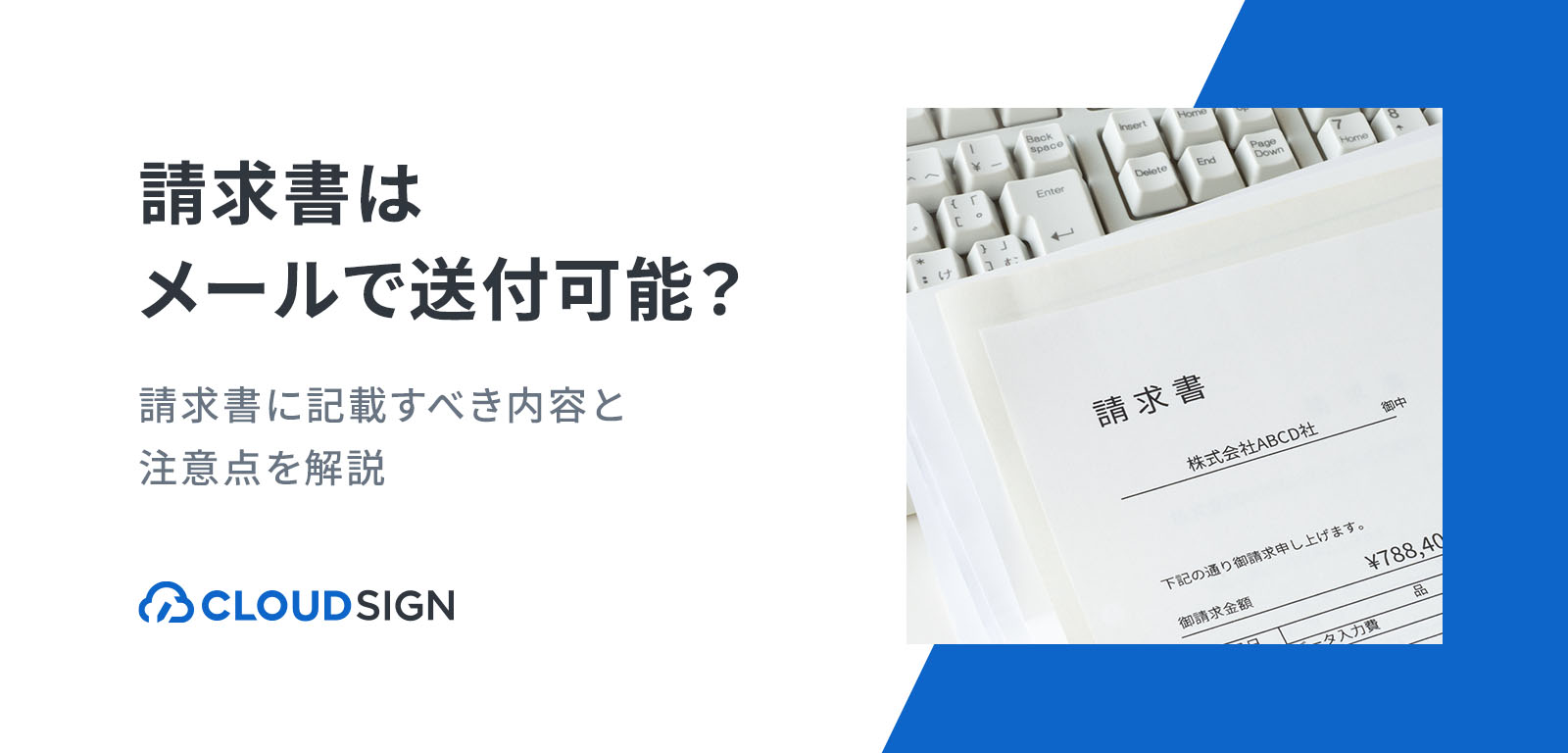
請求書はメールで送付可能?請求書に記載すべき内容と注意点を解説
業務効率化請求書 -
業務改善の進め方
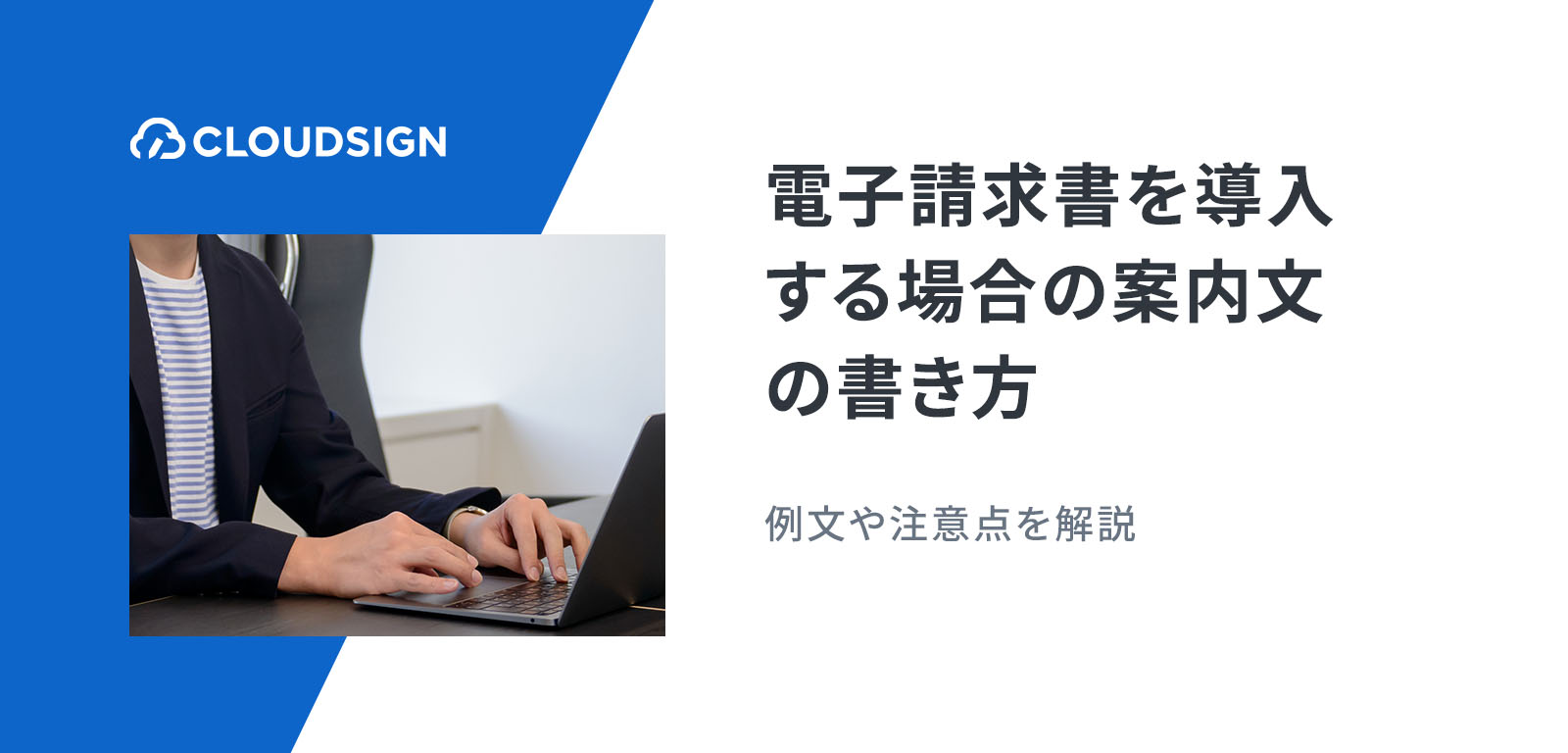
電子請求書を導入する場合の案内文の書き方|例文や注意点を解説
ペーパーレス化業務効率化請求書 -
業務改善の進め方
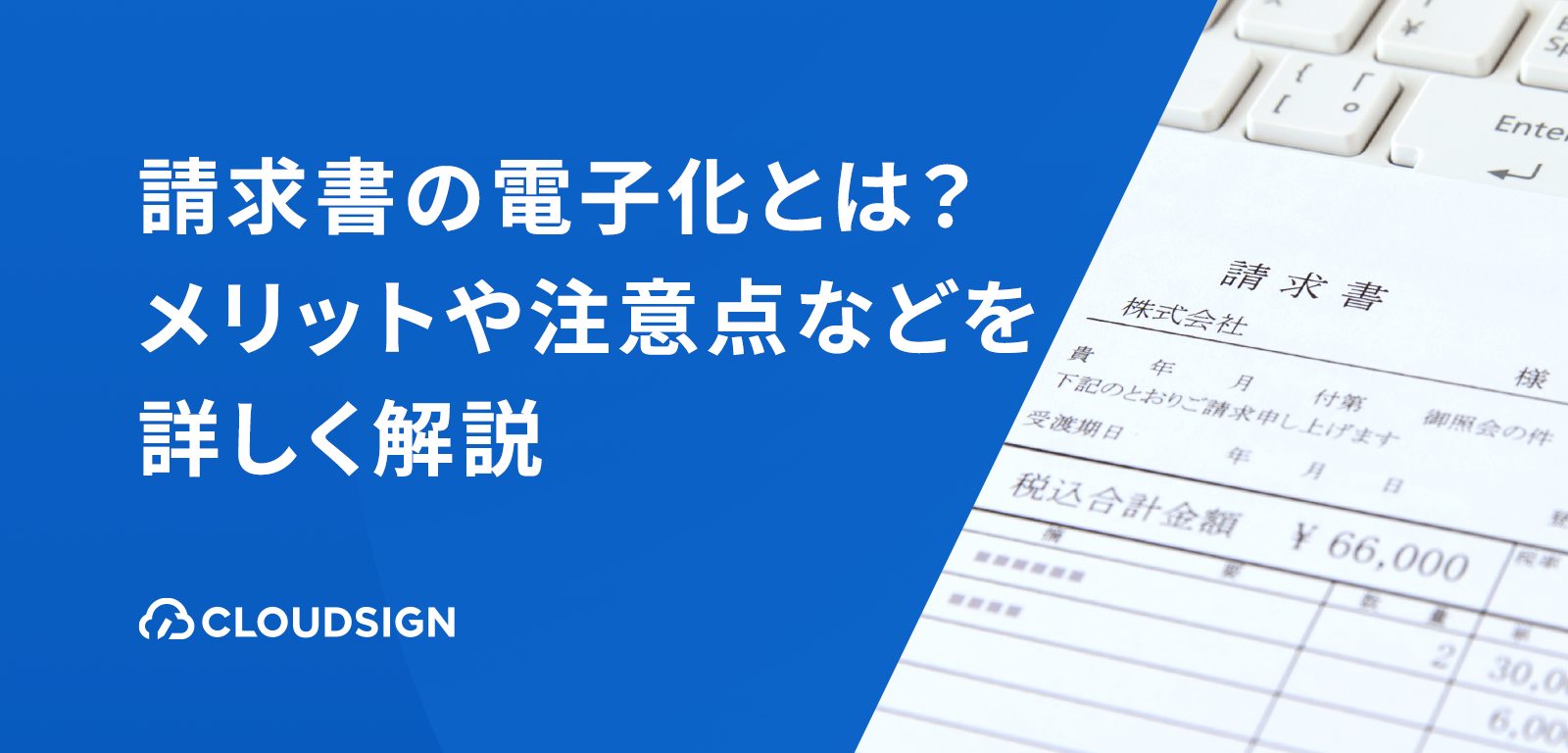
請求書の電子化とは?メリットや注意点などを詳しく解説
請求書電子帳簿保存法 -
業務改善の進め方
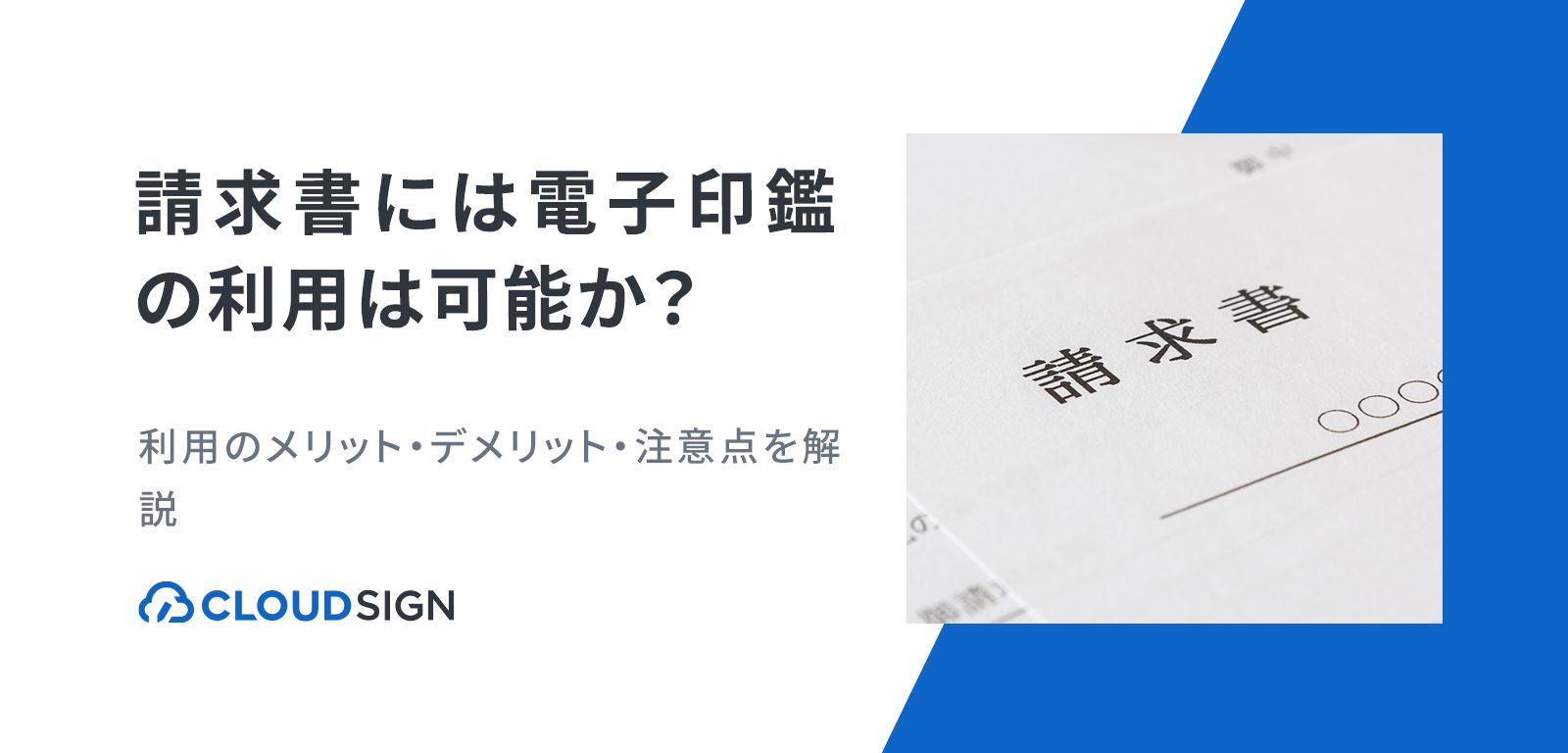
請求書には電子印鑑の利用は可能か?利用のメリット・デメリット・注意点を解説
ペーパーレス化請求書 -
業務改善の進め方

請求書のハンコは必須?押印のメリットや電子化すべき理由を解説
請求書