歩留まりとは?製造業・食品加工業で重要視される理由と計算方法
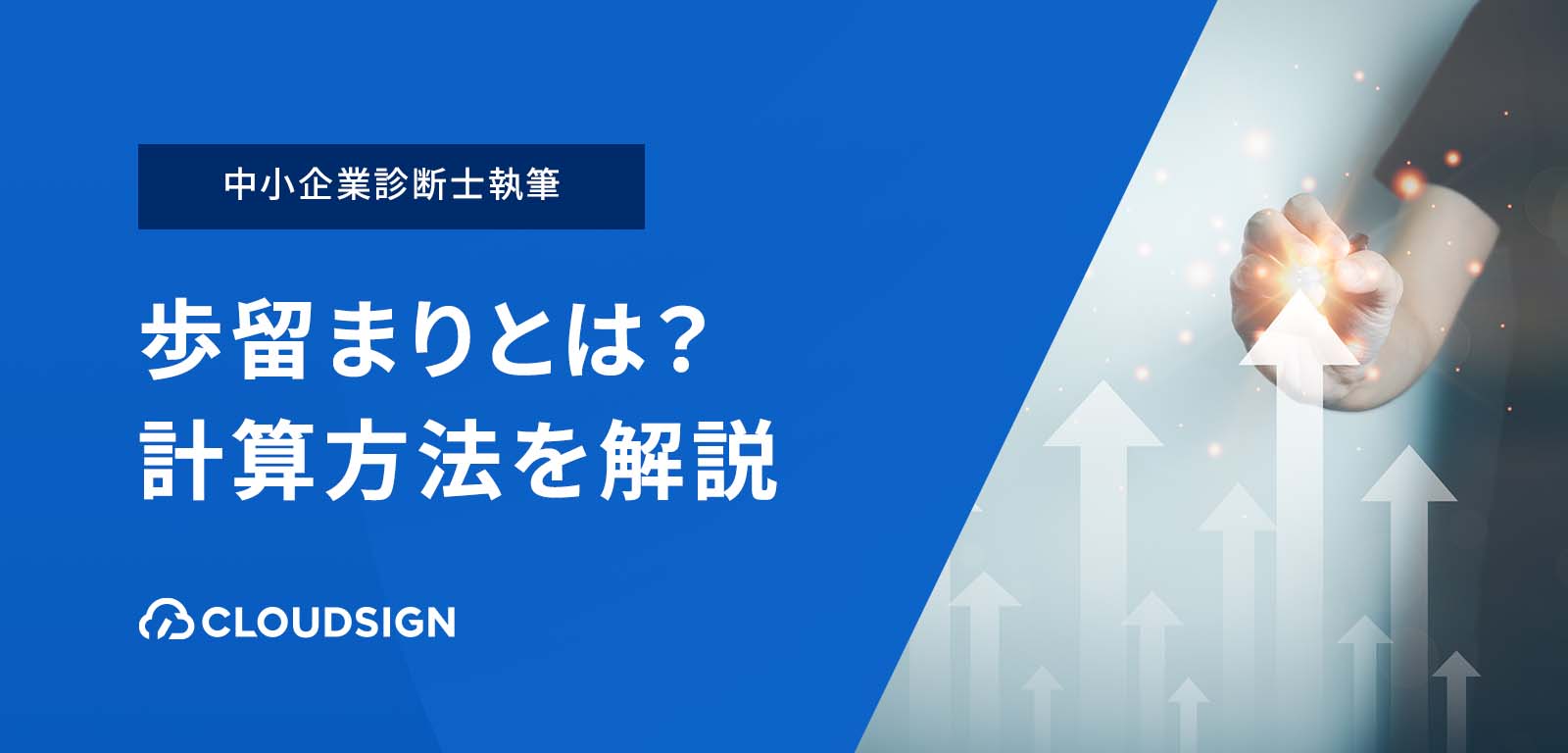
「歩留まり」とは、製造業や食品加工業で重要視される指標のひとつです。製造現場特有の用語であるため、聞いたことがない方も多いかもしれません。
この記事では、材料をどれだけ無駄なく製品化できたかを示す数値である「歩留まり」の基本的な意味や計算方法に加え、歩留まりが低下した際の改善方法を解説します。製造業以外の業種においても非常に有効な考え方ですので一緒に学んでいきましょう。
なお、歩留まりの改善やコストカットに取り組む企業の方に向けて、クラウドサインでは契約業務のデジタル化によってコスト削減を実現した企業の事例を紹介している資料を無料でご提供しています。
契約書のデジタル化は、収入印紙代や郵送費、管理保管場所の削減などコスト削減効果が大きく、成果が短期的にも見えやすい施策です。
気になる方はぜひ資料ダウンロードのうえ、ご活用ください。
「電子契約の導入からスタートする戦略的コスト削減」
資料ダウンロード


この資料では、「契約書類・事務のデジタル化」によって業務プロセスの効率化を成功させ、コスト削減を実現した企業様の事例を紹介しています。原材料価格の高騰や人手不足にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
ダウンロード(無料)歩留まりとは?基本概念を理解しよう
「歩留まり」とは、投入した原材料や部品のうち、最終的に良品として製品化できた数量を指す言葉です。「歩止まり」と表記されることもあり、どちらも「ぶどまり」と読みます。
一般的に、歩留まりは「歩留まり率(%)」として扱われ、製造現場においては、生産効率やコスト管理、品質維持に直結する重要な基準です。
製造業以外でも、人材採用で「応募者数に対して最終的に採用に至った人数」を歩留まりと呼ぶことがあり、採用活動の効率を測る指標として使われています。言い換えれば、「投入に対してどれだけ成果が得られたか」が歩留まりの概念といえるでしょう。
歩留まりの計算方法
ここでは、歩留まりの計算方法を解説します。
歩留まり率の計算式
歩留まり率は次の計算式で求められます。
- 歩留まり率(%)=良品数/投入数×100
上記の計算式で、以下の例における歩留まり率を計算してみましょう。
・自動車部品の製造工程で1,000個の部品を投入
・最終的に良品として出荷できたのが900個
- 歩留まり率=900個/1,000個×100=90%
シンプルな計算式ですが、この数値には大きな意味があります。「歩留まり率90%」=投入した原材料のうち「10%が不良や廃棄」ということです。
もし、歩留まりが95%に改善すれば、1,000個の部品投入で950個が製品化できるため、原材料費や加工コストが5%削減できます。出荷できる製品も増加するため「売上増加+コスト削減」の両面効果を発揮します。
このように歩留まりは、資源効率を数値で捉えるシンプルかつ重要な指標であり、自社の収益性に資するダイレクトな指標として経営判断にも活用可能です。
歩留まり原価の計算方法
食品工場における「歩留まり原価」とは、最終製品を生産するために使用した原材料のコスト指標です。原材料費の数字をそのまま見るのではなく、「実際に製品として残った部分にかかるコスト」を算出することで、より正確に利益率を把握できます。
- 歩留まり原価=原材料費/歩留まり率
ある食品工場で100㎏の魚を1kgあたり1,000円で仕入れたとします。魚には骨や内臓など食べられない部分があり、それを取り除いた80kgが最終製品となりました。この場合、以下のような計算になります。
・原材料費:100kg×1,000円=100,000円
・加工後の最終製品重量:80kg
・歩留まり率:80kg/100kg×100=80%
このときの歩留まり原価は以下のとおりです。
- 歩留まり原価=100,000円/0.8=125,000円
つまり、実際に製品として得られた80kgにかかった原材料コストは125,000円であり、1kgあたりでは1,562.5円/kgとなります。このように、歩留まり原価を把握すれば、仕入価格だけでは見えない「実際の原料コスト構造」を明確にでき、適正な販売価格の設定や利益管理に役立ちます。

歩留まりはなぜ重要か
歩留まりは、製造現場における効率指標としてだけでなく、多くのビジネスシーンで重要です。近年はどの業界も、原材料費の高騰や人手不足、環境配慮など、経営を取り巻く環境が厳しさを増しています。そのため、歩留まり(率)の改善は、収益性や会社の持続可能性に直結する重要なテーマです。
ここからは、生産効率・コスト・品質・環境対応・継続的改善・競争力強化といった観点から、歩留まりが経営にとってなぜ重視されるかを解説します。
生産効率の直接的指標
歩留まりは「投入に対して得られる良品の割合」を示すため、生産効率を直接的に測る指標となります。高い歩留まりは、原材料を無駄なく製品化できている証明であり、低い歩留まりは工程内に非効率やロスが存在する証拠です。
生産現場では多くの改善指標がありますが、歩留まりはもっともシンプルかつ即効性のある効率性のものさしといえるでしょう。歩留まりは、経営者が現場の健全性を判断するうえで欠かせない基準です。
コスト削減と利益率の向上
歩留まりの向上による不良品や廃棄の減少は、追加投入する原材料や再加工にかかる費用を抑制できるため、コスト削減と利益率改善につながります。特に、原材料費の高騰が続く環境において、歩留まりの改善は利益を守るもっとも現実的な対策といえるでしょう。
また、生産能力の増強コストをかけずに、既存設備の効率を最大化できる点も大きな魅力です。歩留まりの改善は固定費を変えずに収益構造を強化できる、経営に直結した施策といえます。
品質管理の基準
歩留まりは、品質を測る客観的な数値としても重要です。歩留まりの安定は、安定した工程が組まれており、それによる製品の質も一定に保てていることを意味します。逆に歩留まりや品質にばらつきが大きい場合は、管理や作業のいずれかに問題があると疑ったほうがよいでしょう。
顧客から信頼される品質を維持するためにも、歩留まりを品質管理の基準として活用し、異常値が出た際は、即座に原因を特定し改善する体制構築が求められます。
環境負荷の低減(フードロス削減)
歩留まりの向上は環境負荷の低減にも直結します。原材料を無駄なく製品化できれば、廃棄量を減らせるため、食品加工業ではフードロス削減に大きく貢献します。これは社会的な責任を果たすだけでなく、企業ブランドの向上や取引先からの信頼確保にもつながるでしょう。
また、昨今では環境配慮への取り組みが評価されるため、歩留まりの改善は、CSRやESG経営の観点からも有効な戦略といえます。歩留まりの改善に取り組めば、経営改善と環境対応を同時に実現できるでしょう。
継続的改善の基準
歩留まりは改善活動の進捗を測るベンチマークとしても有効です。定期的に歩留まりをモニタリングすれば、改善策の効果を数値で確認できるため、PDCAサイクルを回しやすくなります。
各施策による改善が成功しているのか、それとも、新たな課題が生じているのかを明確にできれば、次の施策へ迅速につなげられるでしょう。また、歩留まりを継続的改善の基準・指標にすれば、組織全体における改善文化の醸成も期待できます。
企業の競争力強化
歩留まり改善は企業の競争力UPにつながります。効率的な生産体制と高い品質基準を維持できれば、市場でのコスト競争力維持とブランド力維持の両立が可能です。また、環境対応や持続可能な開発目標(SDGs)を意識した経営を実現できれば、取引先や消費者からの評価も高まり、新規受注や長期的な取引関係構築に有利に働きます。
歩留まりは、単なる現場指標にとどまらず、経営戦略全体を支える柱であり、企業成長の根幹に位置づけるべきテーマといえるでしょう。
無料ダウンロード


企業の競争力強化や環境負荷の低減に取り組む方に向けて、ESG経営の始め方を取りまとめた資料をご用意しました。ESG経営とは何か、そしてESG経営の第一歩として何を始めるべきか悩んでいる方はぜひ本資料を参考にしてください。
ダウンロード(無料)歩留まりが低下する要因
歩留まりの低下には必ず原因があります。設備や材料など目に見える要素だけでなく、人や管理体制、さらには外部環境まで複合的に影響します。ここでは歩留まり低下の主な要因を整理します。
設備に関する要因
老朽化した設備や保全不足は、精度低下や突発的な故障を引き起こし、不良品の発生率を高めます。特に製造業では、設備の安定稼働こそが品質と効率を担保する基盤です。メンテナンスや予防保全が欠けると歩留まりは大きく損なわれます。
定期的な点検や更新を怠ることは、生産効率の低下だけでなく、納期遅延や品質低下といった経営全体のリスクにもつながります。
材料に関する要因
原材料の品質や安定供給は歩留まりに直結します。品質のばらつきや異物混入があると、不良品や廃棄が増加し、投入資源が無駄になります。特に食品工場では、収穫時期や産地の違いで品質差が出やすいため、仕入先管理や原料検査の体制整備は、安定した生産に欠かせません。
材料の品質管理が不十分だと、加工効率や最終製品の品質保証にも悪影響を及ぼし、結果として顧客満足や利益率を大きく損なうリスクをはらんでいます。
人的要因
作業員の熟練度不足や教育不足は、手順ミスや不注意による不良を招きやすく、歩留まり低下の典型的要因です。熟練人材の離職や人手不足が深刻化する中、技能伝承の遅れや人材定着の難しさも影響を強めています。
特に中小企業では、属人的な技能に依存する傾向が強くなりがちです。特定の従業員頼みの状態は、歩留まりの不安定化や不良発生の慢性化を招くため、教育制度の確立や作業標準の整備は、品質維持や効率改善における重要な課題といえます。
作業プロセス要因
作業プロセスが標準化されていないと、作業が属人的になり、歩留まりが安定しません。加えて、複雑すぎる工程や非効率な動線設計も無駄を増やす要因です。また、工程ごとのリスクや不良発生率の分析ができていないのに改善しようとしても、場当たり的な対策しか打ち出せないでしょう。
製品の品質や歩留まりの安定化のためにも、プロセスの標準化やマニュアル整備、定期的な工程分析は欠かせません。
管理・戦略的要因
経営層が歩留まりの改善を現場任せにしていると、持続的な改善は望めません。歩留まりをKPI(重要業績評価指標)に設定せず、指標管理や改善目標も不明確なままでは、現場がいくら努力しても成果が出ずに形骸化する可能性があります。
経営層が歩留まりを経営課題としてしっかり認識し、利益率や競争力向上と直結する目標として位置づけない限り、歩留まりの改善や業績の改善は見込めないでしょう。歩留まりの管理は、戦略的な経営管理の一環として取り扱うべき課題です。
環境要因
食品工場では、温度・湿度などの外的環境が大きな影響を及ぼします。季節や気候条件による変動の軽視は、品質劣化や廃棄増加が発生を招くため、歩留まり低下の原因になるでしょう。こうした衛生管理の不備や保存環境の整備不足も、安全性や品質保証を揺るがす大きな要因です。
環境要因はコントロールが難しく思えるかもしれませんが、近年では、センサー導入やデータ分析によって管理できる領域も広がっています。ロス抑制はもちろん、ブランドの維持や法令遵守のためにも、環境要因の分析と適切な対応による歩留まり向上を目標にしましょう。
歩留まり向上のための具体的な方法
歩留まりを改善するには、原因を正しく把握し、それに応じた具体的な対策を講じることが欠かせません。現場の工夫にとどまらず、経営として戦略的に取り組む必要があります。ここでは、歩留まり向上のためにできる具体的な取り組みを紹介します。
生産不良の記録と原因の究明
歩留まり改善の第一歩は、不良発生の記録と原因の特定です。不良の種類・頻度を数値化・可視化すれば、改善対象が明確になります。原因を突き止められれば、場当たり的な改善策ではなく根本的な解決が可能です。
歩留まりの目標設定
歩留まりの目標を現場任せではなく、経営方針と結びついた目標に設定することが重要です。経営方針の中で、明確な数値目標として設定されていれば、改善活動の方向性も明確になり、従業員の意識も高まるでしょう。また、継続的に進捗を確認し、達成状況を共有すれば、組織的な取り組みとしても促進されていきます。
正しい工程での製造(業務標準化)
歩留まりの安定には、工程の標準化が欠かせません。たとえば、作業手順をマニュアル化し、誰が行っても同じ結果を得られる体制を築けば、不良のばらつきを抑制できます。加えて、教育と現場指導を通じて、標準化された工程を徹底できれば、成果につながりやすくなるでしょう。
機械や道具の整備
設備や道具が適切に整備されていなければ、どれほど工程を改善しても不良は減りません。定期点検や予防保全の徹底により、突発的な不具合を防ぎ、歩留まりの安定化を実現できます。設備投資の判断も含め、経営的視点からの整備戦略が必要です。
原材料の保管状態の安定化
原材料は、仕入れ時の品質だけでなく、保管状態によっても大きく変化します。温度・湿度・衛生状態を適切に管理すれば、劣化やロスを防げるでしょう。特に食品工場ではIoT温度センサーや在庫管理システムの導入が有効的です。
食品加工技術の向上
食品加工において包丁さばきやカット技術など作業者の技能が歩留まりを大きく左右します。最新の設備導入や体系的な従業員教育に投資すれば、無駄を抑えつつ品質を高めることが可能です。技術革新と技能向上の両立ができれば、継続的な歩留まり改善も期待できるでしょう。
可食できる部分の増加
食品加工では、これまで廃棄していた部分を活用する工夫も歩留まり向上につながります。たとえば、皮や骨の加工利用、副産物の商品化など、発想次第で利益源を拡大できるかもしれません。また、廃棄削減は環境負荷の低減にも貢献し、持続可能な生産目標(SDGs)を意識した経営の実現にもつながります。
まとめ
歩留まりは、製造業や食品加工業において収益性や競争力を左右する重要な指標です。歩留まりの改善には、生産管理ソフトによる不良分析や、在庫・原材料管理システムの導入、ラインごとに品質データを収集するツールの利用が効果的です。
近年では中小企業でも導入しやすいクラウド型のソリューションも増えています。こうしたシステムやツールを上手に活用すれば、歩留まり管理を経営戦略と直結させつつ、持続的な成長と利益率向上を実現できるでしょう。
なお、クラウドサインではデジタル化を推進するうえで欠かせないパートナー選定のポイントをまとめた「デジタル化入門ガイド」をご無料でご提供しています。
この資料では、
- デジタル化の5つのステップ
- 伴⾛⽀援の⼿厚さチェックリスト
などをご紹介しています。気になる方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。
「電子契約から始めるデジタル化入門ガイド」
無料ダウンロード


「デジタルツールを使って業務を効率化したいけれど、ITに詳しい人が社内にいない」とお悩みではありませんか? この資料では、IT知識がなくてもできるデジタル化推進方法を5つのステップに分けてやさしく解説しています。「どのようにデジタル化を推進したらよいかわからない」とお悩みの企業ご担当者様はぜひご活用ください。
ダウンロード(無料)この記事を書いたライター
高桑清人
中小企業診断士
前職ではBPO企業にて12年間、業務設計・品質管理・人材マネジメントなどの管理業務に従事。独立後は中小企業の経営支援に携わり、新規事業の立ち上げや事業計画策定を伴走型で支援。学習塾講師として16年・1万時間超の授業経験もあり、「聴く・伝える・支える」現場感を大切に活動している。
こちらも合わせて読む
-

OEMとは? ODM、EMSとの違いを解説します
業務効率化製造業コスト削減 -

PDMとは? その必要性や導入のメリット、注意点について解説します
ペーパーレス化製造業DX -

ベンチマークとは?初心者向けに徹底解説します
新規事業マーケティング -
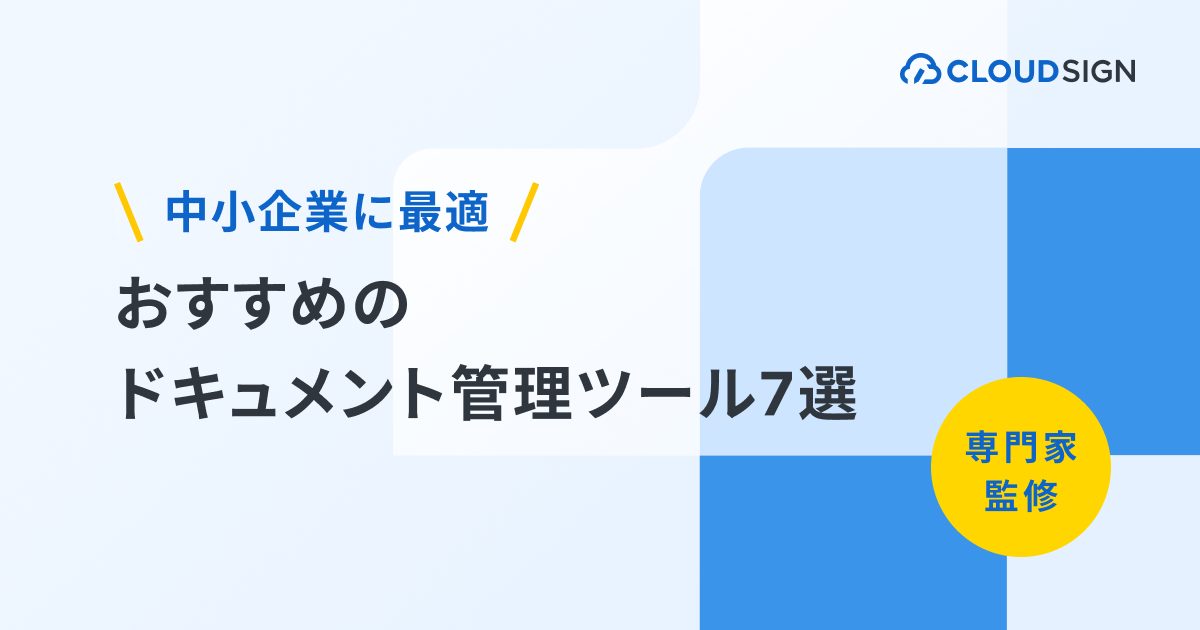
中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選
ペーパーレス化DX業務効率化 -

全体最適とは?今日からできる、中小企業のための実現方法をわかりやすく解説
業務効率化プロジェクトマネジメント -
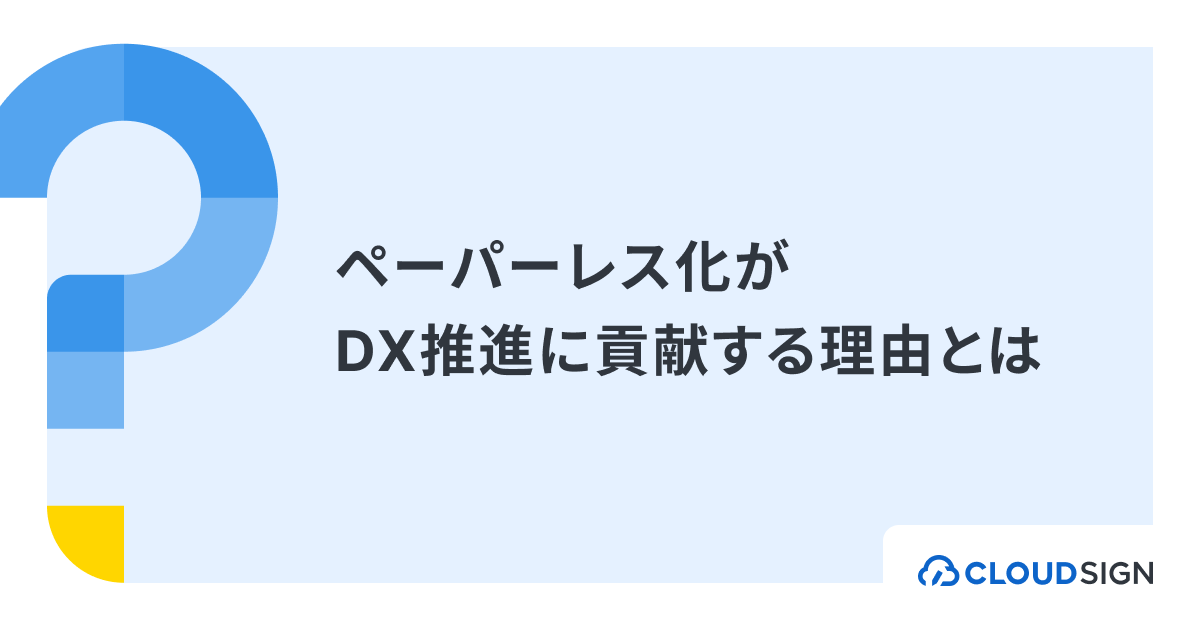
ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説
ペーパーレス化DX -

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説
ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法納品書経理DX -

DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説
DX -

【初心者必見】RPAとは何か?今更聞けない基本と導入のポイント
業務効率化RPA