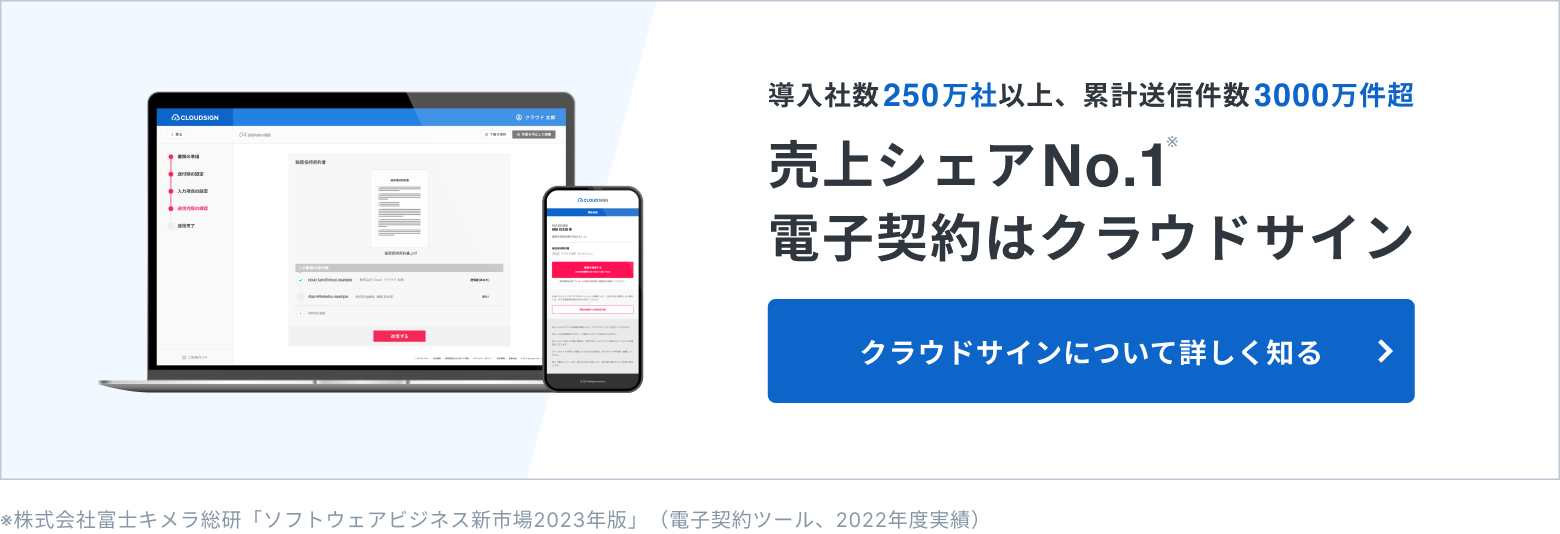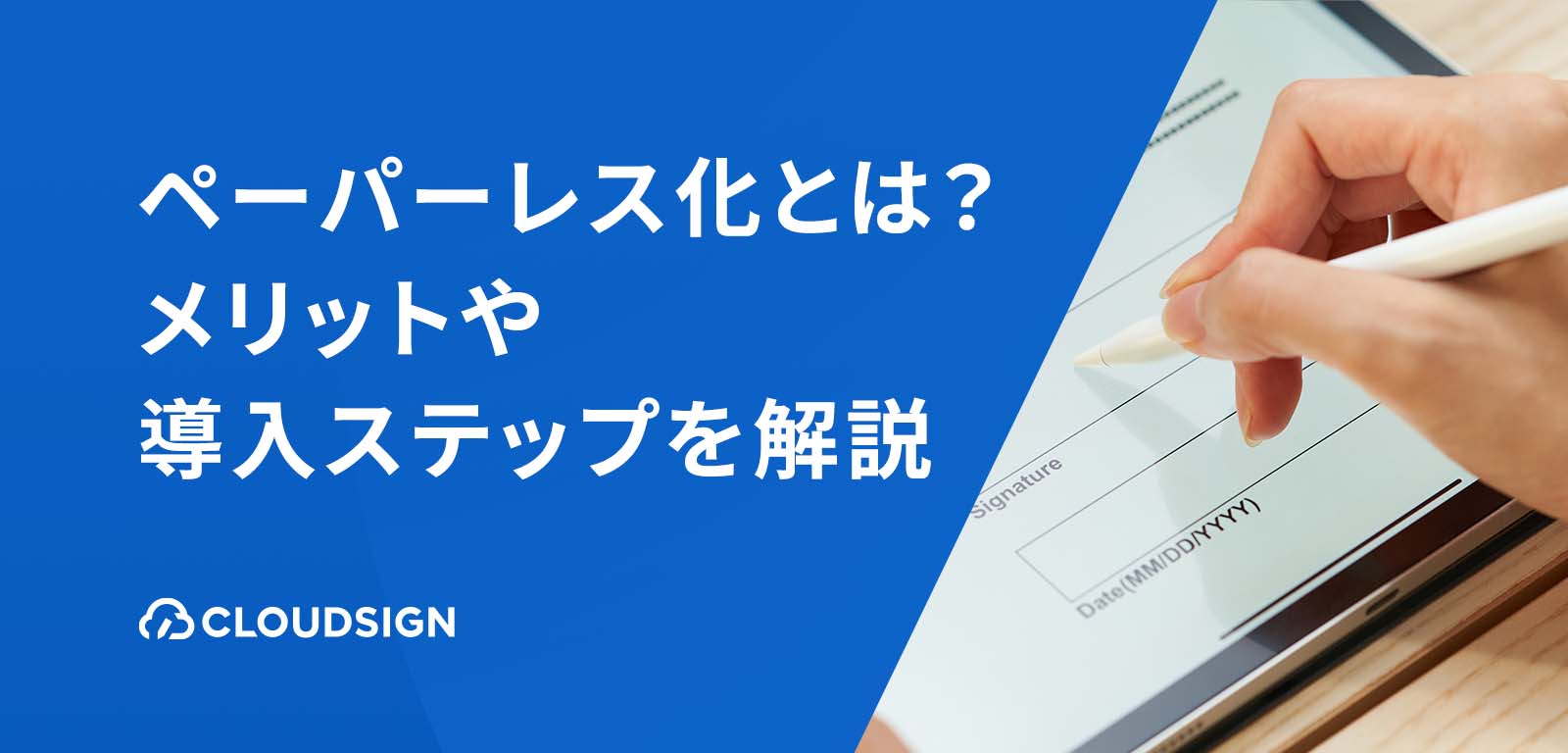API連携とは?仕組みや事例、導入のメリットなどを徹底解説

昨今、API連携は業務効率化やデータ活用を支える重要な要素となり、多くの企業で注目されています。
たとえば、受発注システムやCRMとの連携によって業務の自動化を実現したり、スムーズなフローを構築することにより顧客体験の向上に大きく寄与したりしています。
本記事では、API連携の基本的な仕組みから、具体的な事例、そして導入によるメリットまでを詳しく解説します。
記事後半ではAPI連携導入時の注意点も紹介します。API連携を日頃の業務に生かし、企業の競争力を高める方法を知りたい方はぜひ参考にしてください。
なお、クラウドサインではITが苦手な初心者に向けた「デジタル化入門ガイド」をご無料でご提供しています。
- デジタル化の5つのステップ
- 伴⾛⽀援の⼿厚さチェックリスト
などをご紹介しています。気になる方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。
「電子契約から始めるデジタル化入門ガイド」
無料ダウンロード


「デジタルツールを使って業務を効率化したいけれど、ITに詳しい人が社内にいない」とお悩みではありませんか? この資料では、IT知識がなくてもできるデジタル化推進方法を5つのステップに分けてやさしく解説しています。「どのようにデジタル化を推進したらよいかわからない」とお悩みの企業ご担当者様はぜひご活用ください。
ダウンロード(無料)APIとは
APIとは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(Application Programming Interface)の略で、異なるソフトウェア間でデータや機能をやり取りし、機能やサービスを共有する仕組みのことです。あるソフトウェアが別のソフトウェアにリクエストを送り、相手のソフトウェアがそのリクエストに応じた情報を返したり、処理を行ったりします。
たとえば、ECサイトでクレジットカード決済などの決済処理を行うために、決済代行会社のAPIを利用します。それにより、ECサイトは自社で複雑な決済システムを構築・運用する必要がなくなります。
他にも営業支援システムから契約書を直接作成したり、契約内容をリアルタイムで更新したりすることが可能です。
API連携とは
API連携とは、APIを使って、異なるシステム・アプリケーション同士がデータや機能を共有しお互いに利用できるようにする仕組みを指します。APIがソフトウェア間の橋渡し役として機能し、システム同士がスムーズに情報をやり取りできる環境を整えてくれるということになります。
API連携を適切に業務に導入することによって、業務の大幅な効率化に繋がり、結果として顧客体験の向上にも寄与します。
API連携は、企業のDXを加速させ、競争力を高めるために強力な手段です。
これからのビジネス環境で優位性を確保するために、API連携の導入を検討することは非常に重要といえるでしょう。
こちらの記事では電子契約のAPI活用方法や導入のメリット、クラウドサイン導入のメリットなどについて詳しく知りたい場合はご確認ください。
API連携の仕組み
API連携の仕組みをわかりやすく言うと、「異なる言語を話す人同士の会話をスムーズに進めるために通訳を利用する」ようなものです。
たとえば、ECサイトと在庫管理システムを考えてみましょう。
ECサイトは「お客様が商品を購入した」という情報を持っており、在庫管理システムは「現在の在庫状況」を管理しています。
この2つが直接やり取りしようとしても、異なる形式やルールでデータを扱っているため、意思疎通が難しい場合があります。
そこで、APIが通訳の役割を果たし、データを双方が理解できる形に変換しながら連携を実現します。
具体的には、以下のような流れでAPI連携がはたらきます。
2)データ変換:APIは、リクエストを在庫管理システムが理解できる形式に変換する
3)レスポンスの受信:在庫管理システムが「商品Aの在庫は残り10個」という結果を返し、APIがそれをECサイトに伝える
このように、API連携は基本的にリクエスト(要求)とレスポンス(応答)から成り立っており、異なるシステム同士が円滑に情報をやり取りできる仕組みであるといえます。
企業にとって、API連携はシステム間の連携を効率化し、業務の自動化やデータの正確性向上に役立つ重要な技術です。
API連携の事例を紹介
API連携は、企業内の営業活動や、私たちの生活の周りにおいて、様々な形で活用されています。
API連携の導入事例として、主に以下のものが挙げられます。
Facebook、XなどのSNS
FacebookやXなどのSNSにおけるAPI連携は、マーケティングや顧客対応を効率化するうえで非常に有効です。
たとえば、企業のマーケティングチームは、APIを利用してFacebookやXに自動で投稿をスケジュールしたり、広告キャンペーンを管理したりできます。
これにより、手動投稿の手間を省き、一貫性のあるコンテンツ配信が可能になります。
加えて、SNS上での顧客とのやり取りを効率化するツールとして、カスタマーサポート向けのチャットボットを導入する例もあります。
APIを介して、SNSのメッセージ機能と顧客管理システム(CRM)が連携することで、顧客の問い合わせ内容が自動で記録され、担当者が迅速に対応できるようになります。
以上のように、SNSの運用にAPI連携を活用することで、顧客満足度の向上や対応コストの削減が実現します。
また、Xの閲覧に公式アプリ以外のビューアーアプリを用いたり、SNSアカウントを利用して様々なサービスにログインしたりする仕組みも、API連携が日常生活の中で役立っている一例といえます。
ECサイト
ECサイトにおけるAPI連携は、在庫管理や顧客体験の向上に大きな役割を果たします。
たとえば、ECサイトと在庫管理システムをAPIで連携すると、注文が発生した際に在庫状況がリアルタイムで更新されます。
これにより、在庫切れによる販売ミスを防ぎ、スムーズな運営が可能になります。
また、APIを活用して外部の決済システムと連携するケースも一般的です。顧客が注文を確定すると、APIを介して決済処理が迅速に実行され、注文情報が安全に記録されます。
マイナンバーカード
マイナンバーカードも、API連携が導入されている一例です。
デジタル庁が提供するデジタル認証アプリと連携するAPIを活用することで、マイナンバーカードを使った本人確認・認証や電子申請書類への署名機能を簡単に組み込めるようになっています。
(参考:デジタル庁「デジタル認証アプリ」)。
たとえば、行政サービスでは、マイナンバーカードを用いた本人確認がAPIを介して他のシステムと連携することで、住民票の取得など様々な手続きがオンライン申請が可能になります。
さらに、民間企業でもマイナンバーカードの活用が進んでいます。
銀行や証券会社では、口座開設時の本人確認にマイナンバーカードを利用したAPI連携を導入しています。
API連携により、必要な情報を迅速に照会し、不正を防止しながら手続きの効率化を実現しています。
こちらの記事ではマイナンバーカードで電子署名する方法や注意点を解説しますので参考にしてみてください。
社内業務管理システム
社内業務管理システム同士にAPI連携を用いることで、業務の効率化とデータ活用の向上が図れます。
たとえば、人事システムと勤怠管理システムをAPIで連携すると、社員の出退勤データが自動的に人事システムに反映されます。
これにより、給与計算や労働時間管理が迅速かつ正確におこなえるようになります。
さらに、プロジェクト管理ツールと経費精算システムを連携することで、プロジェクトごとの経費データがリアルタイムで可視化されます。
経費の過剰支出を抑えつつ、予算管理がしやすくなるでしょう。
API連携を導入するメリット

企業がAPI連携を導入するメリットとしては、主に以下の5つが挙げられます。
・公開ソフトウェアを活用できる
・UX・顧客満足度を向上させられる
・セキュリティレベルを向上させられる
・最新情報の取得が容易になる
開発コストを大幅に削減できる
API連携を導入することで、システムの開発コストを大幅に削減できます。
従来、新しい機能やサービスを構築する場合は、全てを一から開発する必要があり、多大な時間と人件費がかかりました。
しかし、API連携を利用すれば、既存のシステムやサービスを活用して必要な機能を迅速に統合することができます。
たとえば、自社サービスに決済や認証機能を実装する際に、自社開発を避けて外部のAPIを利用することで、コストを抑えられます。
また、API提供者が保守・更新を行うため、自社での運用コストも削減できます。
これにより、開発に割いていたリソースを、その他のコアビジネスやマーケティングなどに集中させることが可能になります。
公開ソフトウェアを活用できる
API連携は、外部の公開ソフトウェアやサービスを容易に活用できる点もメリットです。
APIの多くはインターネット上に公開されているため、特別な契約などをせずに活用可能です。
たとえば、Google MapsとのAPI連携により、地図情報を自社のアプリケーションやウェブサイトに活用できます。
これにより、高度な機能を自社でゼロから開発する必要がなくなります。
同様に、SNSやクラウドストレージなどとAPI連携をすることで、これらのサービスを直接的に自社の業務に活用できます。
UX・顧客満足度を向上させられる
API連携を活用することで、シームレスなユーザー体験(UX)を提供でき、顧客満足度の向上に繋がります。
たとえば、ECサイトでは、外部の決済APIを導入することで、複数の支払い方法を簡単に利用可能にし、顧客がより便利に購入できるようになります。チャットボットや顧客サポートのAPIを利用すれば、迅速かつパーソナライズされた対応が可能になり、顧客の不満を軽減できます。
さらに、APIによるリアルタイムデータの提供により、在庫状況や配送状況を即座に確認できるなど、スムーズなサービスが実現可能です。
セキュリティレベルを向上させられる
API連携は、適切に実装されることで、システム全体のセキュリティを向上させることができます。
たとえば、認証やアクセス制御に関するAPIを利用すれば、高度なセキュリティ機能を手軽に導入可能です。
OAuthやOpen ID ConnectといったAPIプロトコルを活用すれば、ユーザー情報の安全な認証や、権限の管理が効率的に行えます。
また、APIプロバイダーがセキュリティ対策や脆弱性の更新を継続的に行うため、自社のリソースを割かずにセキュリティを強化できます。
さらに、データのやり取りが暗号化される仕組みが標準的に用意されているAPIも多く、不正アクセスやデータ漏洩のリスクが低減されます。
最新情報の取得が容易になる
APIを活用することで、最新情報をリアルタイムで取得することが可能です。
たとえば、金融機関のAPIを利用すれば、為替レートや株価などの最新情報を即座にシステムに取り込むことができます。
また、SNSのAPIを通じて、トレンド情報やユーザーの投稿データを収集することで、マーケティング施策の最適化やトレンド分析に役立てることができます。
これらのリアルタイムデータの活用は、迅速な意思決定やビジネスのスピード感の向上に直結します。
さらに、自動更新機能を備えたAPIにより、常に最新の状態を保つことが可能になり、手動での更新作業を削減できる点もメリットです。
API連携導入時の注意点
API連携を業務に導入すれば、外部データとのシームレスな連携が可能となるうえ、一部のシステムやサービスを自社で開発する必要がなくなるなど多くの恩恵が受けられます。
その一方で、API連携には注意しておくこともいくつか存在します。具体的には、API連携を導入する際は、以下の3点に注意しましょう。
・API提供元への依存リスクがあること
・API提供元のトラブル時には対応が必要となること
適切なセキュリティ対策が必要となること
API連携を導入する際、セキュリティ対策が不十分だと、データ漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。
そのため、APIとアプリケーションの間のセキュリティを保護するための重要な情報である「APIキー」や「シークレットキー」を使い回さないなど、適切なセキュリティ対策が必要です。
また、不必要なデータの持ち出しや操作がおこなわれないように、APIには最小限の権限だけを付与するようにしましょう。
API提供元への依存リスクがあること
API連携を導入すると、APIを提供している外部サービスに依存することになります。
これは、APIの仕様変更やサービス終了が発生した場合に、自社システムへの影響が避けられないという課題を生みます。
たとえば、APIの提供元が急に新バージョンをリリースした場合、旧バージョンのサポートが終了すると、それに対応するシステム改修が必要になります。
提供元がサービス停止を決定した場合には、それに代わる別のAPIを導入するためのコストや労力が発生します。
このようなリスクを軽減するために、APIの利用契約内容を事前に確認し、サポート期間やサービス継続性について把握しておくことが重要です。
また、代替手段を用意しておくことで、依存リスクを最小化できます。
API提供元のトラブル時の対応が必要となること
API連携を導入すると、外部のAPI提供元のサーバー障害が自社システムに直接影響を与える場合があります。
たとえば、何らかの障害で一時的に決済用のAPI連携が利用できなくなった場合、ECサイトでは取引が一時停止し、顧客の不満を招く可能性があります。
連携しているSNSや分析ツールが停止した場合などは、リアルタイムデータの取得ができなくなり、業務効率や意思決定に悪影響を与える可能性もあります。
障害発生時のリスクヘッジとして、あらかじめ予備のAPIやサーバーを用意しておくなどの冗長化が必要です。
API連携可能な電子契約サービス「クラウドサイン」で業務効率化を実現
本記事では、API連携の仕組みや導入例と、API連携導入によるメリットや注意点などを詳しく解説しました。
企業活動において、API連携の有効活用は業務効率化や顧客満足度の向上において大きなインパクトがあります。企業の目標やサービスに合わせて適切なAPI連携を用いましょう。
なお、当サイトを運営する電子契約「クラウドサイン」もさまざまなサービスとAPI連携が可能です。
電子契約サービスにおけるAPI連携は、契約業務を効率化するための技術であり、契約書の作成、署名、管理などをシステム間で自動化できるようになります。
クラウドサインを導入するメリットや導入までの流れ、お客様の声などクラウドサインを導入検討するために知っておきたい情報を網羅的に解説しているので、クラウドサインのサービスの詳細について知りたい方は、下記リンクからご入手ください。
無料ダウンロード


クラウドサインは、国内売上シェアNo.1(※)の電子契約サービスです。この資料では、クラウドサインが多くのお客様に選ばれる理由について取りまとめています。クラウドサインの機能やセキュリティ対策、サポート体制などについて詳しく知りたい方はダウンロードのうえ、ご活用ください。
この記事を書いたライター
業務改善プラスジャーナル編集部
業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。