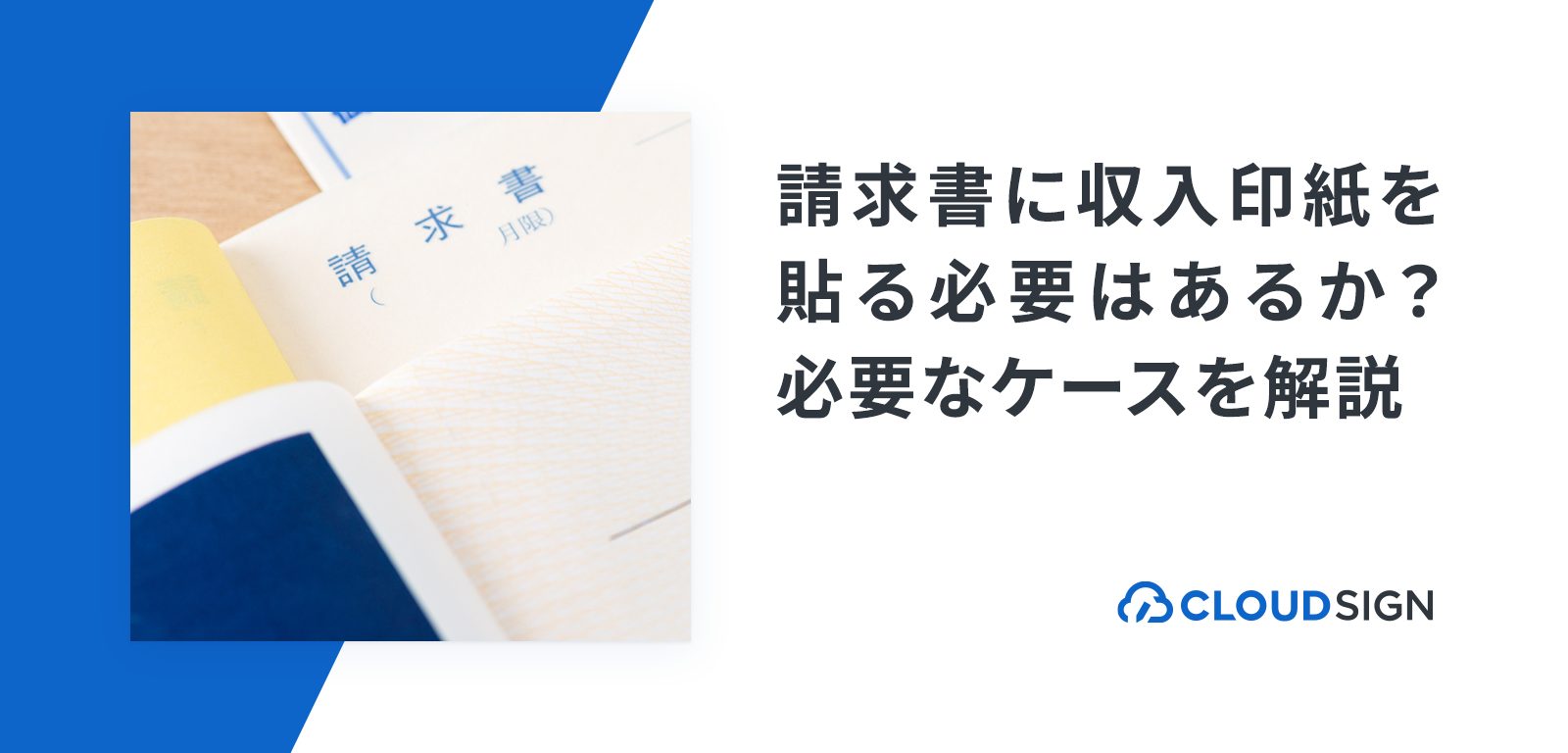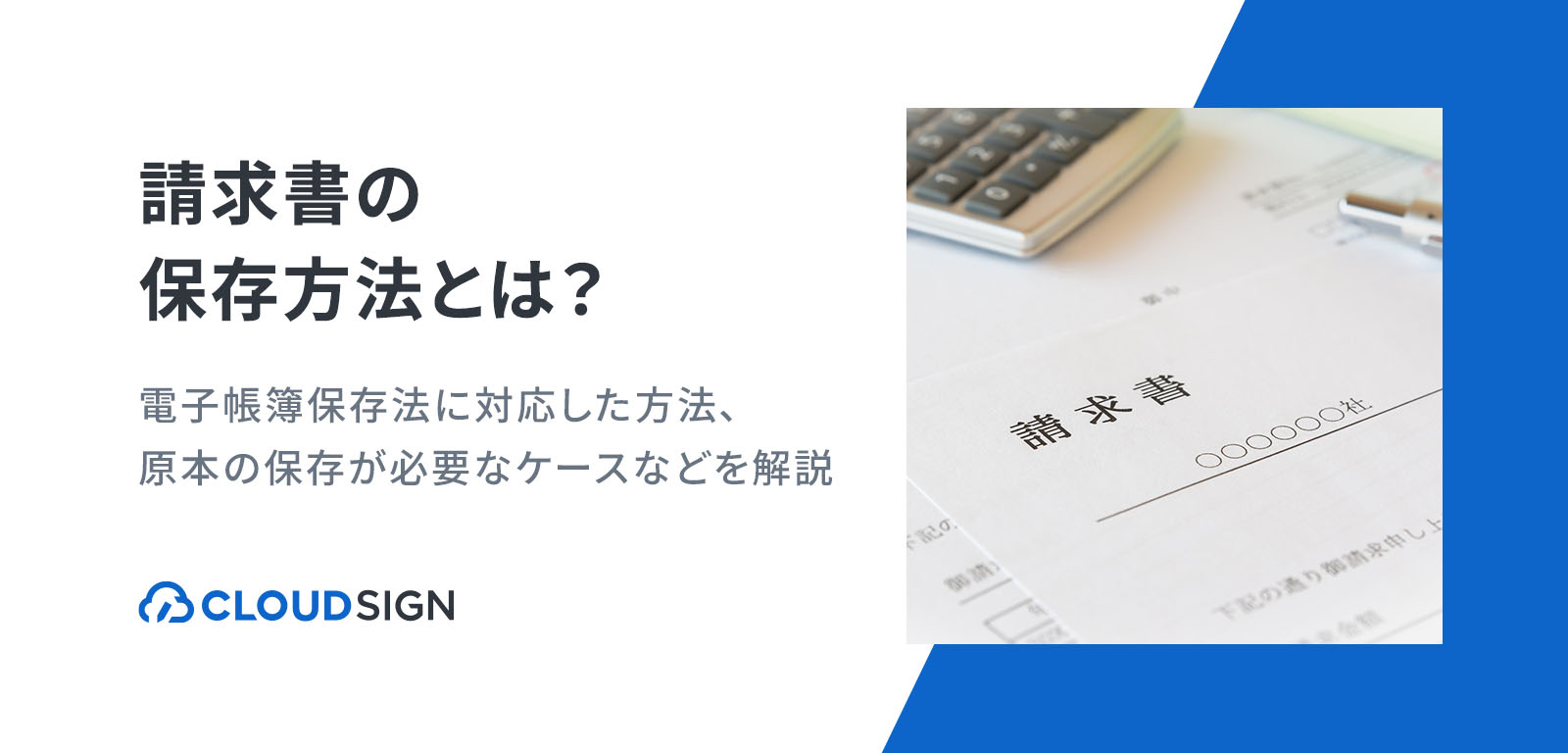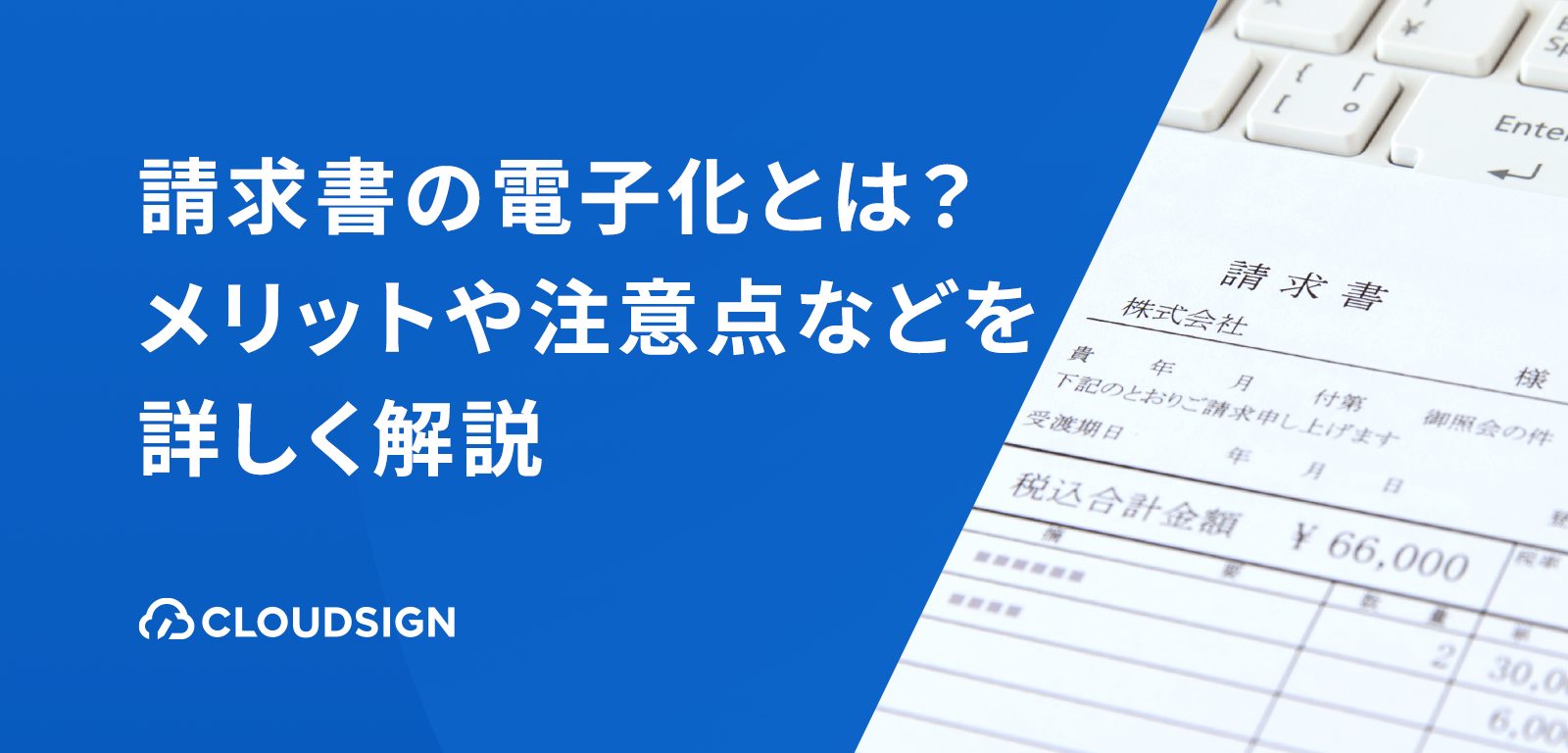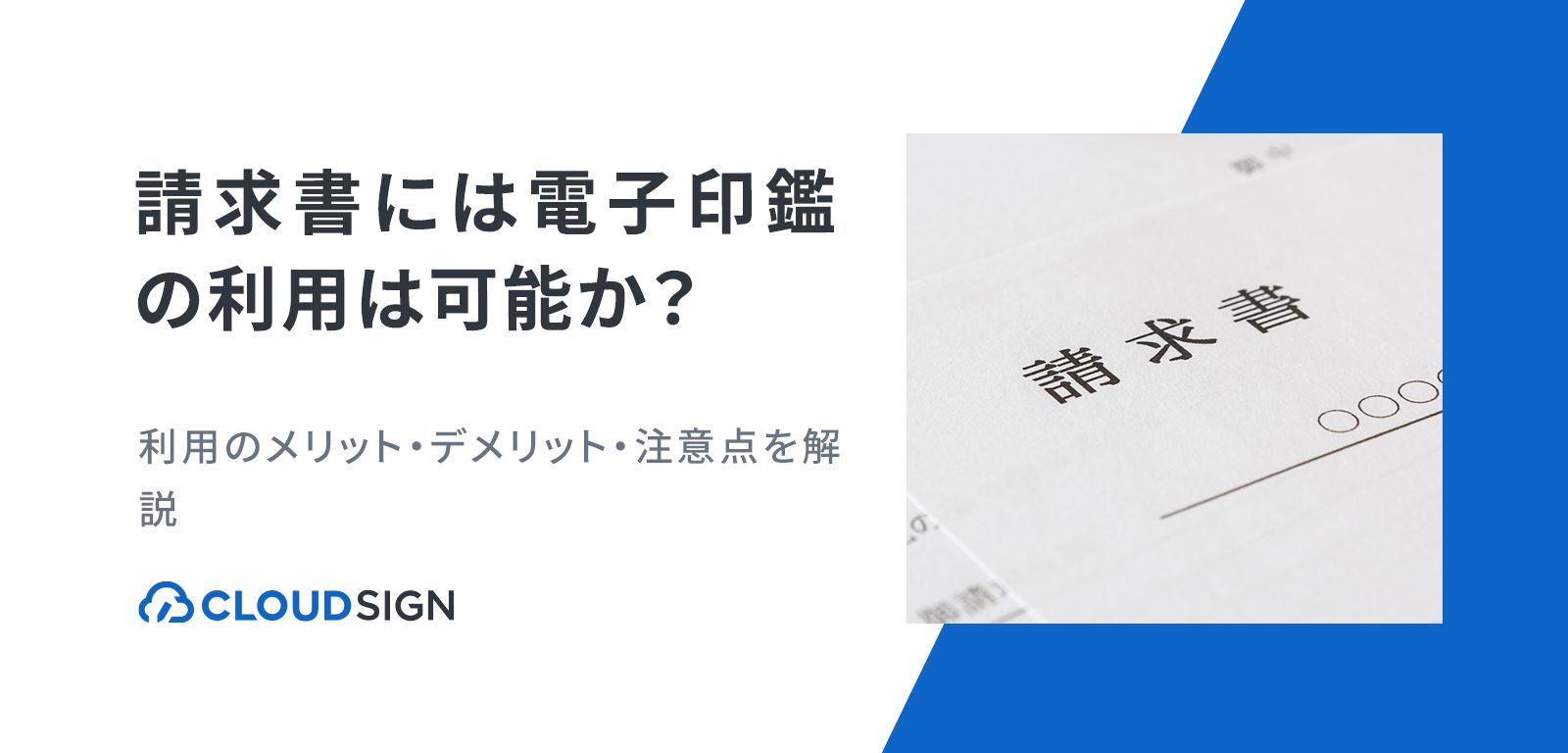請求書はメールで送付可能?請求書に記載すべき内容と注意点を解説
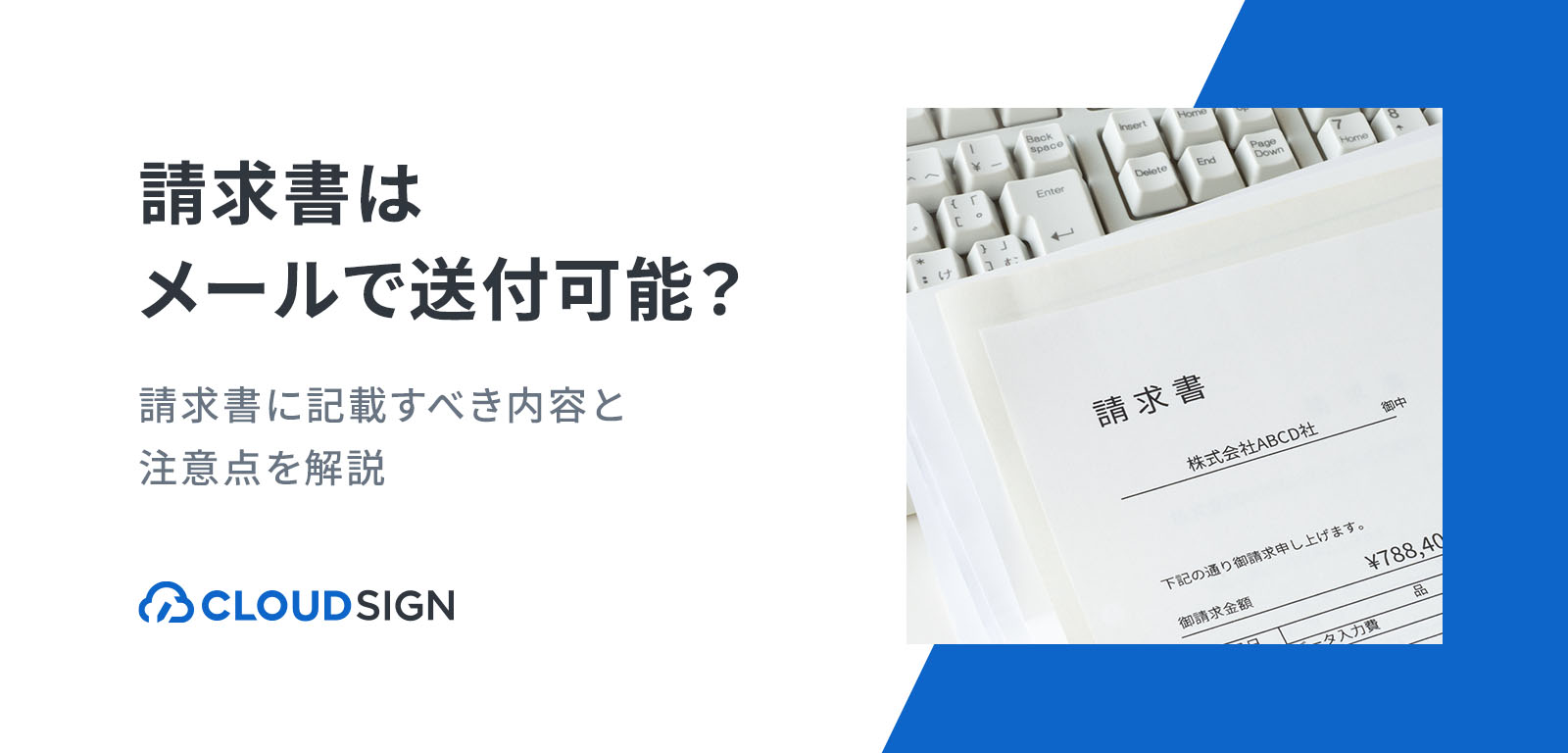
取引先への代金請求時に発行する請求書ですが、最近では紙の書類を郵送するのではなく、PDFなどでメール送付するケースも増えています。
特にテレワークやペーパーレス化の普及により、請求書を電子化するニーズは高まっており、メール送付が正式な請求方法として認められる場面も少なくありません。
本記事では、請求書をメールで送付する際の法的な扱いや、請求書に記載すべき必須項目、送付時の注意点について詳しく解説します。
請求書はメールで送付可能?
従来は、取引先への請求書の送付は元本を郵送で送る形が一般的でした。一方で、現在では多くの企業や事業者が請求書をメールで送付する方法を採用しており、法律上も有効な送付方法として認められています。
特に、電子帳簿保存法やインボイス制度の整備により、PDF形式などの電子データによる請求書のやり取りが普及しつつあります。取引先が了承していることを前提に、請求書をメールに添付して送信することで、紙と同様の証拠力を持つ請求行為が成立します。
ただし、請求書を電子データで送付する際は、税務上の保存要件を満たす必要があります。たとえば、受信者が電子データのまま保存する場合は、検索機能や改ざん防止措置を施すことなどが求められます(参考:「 電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください|国税庁」)。
さらに、取引先が紙での受領を希望している場合には、メール送信のみではトラブルになる可能性もあるため、事前に合意を取っておきましょう。
メール送付は効率的な手段ですが、法令と実務の両面を意識した運用が必要です。
3つの請求書送付方法
請求書を取引先に送付する方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 郵送する
- FAXを送信する
- メールで送信する
それぞれの送付方法について、メリット・デメリットを挙げながら簡潔に紹介します。
郵送する
印刷・押印した紙の請求書を封書に入れて取引先へ直接送付するため、形式的な信頼性が高く、郵送を強く希望する企業もあるでしょう。
| メリット | ・紙の原本として受け取れるため、信頼性が高い ・古くから企業間の正式な書類送付方法として浸透している ・控えを送付元で保管することにより改ざんが困難 |
| デメリット | ・印刷や封入、切手の貼付などに手間がかかる ・郵送費がかかり、コストが高い ・到着まで数日を要する ・請求書自体の紛失・劣化リスクがある |
近年では電子化が進む一方で、公的機関等では郵送での請求書受領を求められる場合もあるため、相手の要望に応じた柔軟な対応が求められます。
FAXを送信する
FAXを使った請求書送付は、相手に即時で内容を伝えられる手段として、今も一部の業種で活用されています。特に不動産業や建設業など、FAXを利用する文化が根強い現場では業務自体に組み込まれているケースもあります。
| メリット | ・送信から受信までが早く、即時性が高い ・相手がFAX機を持っていればすぐに対応できる ・紙で出力されるため、視認性が高い |
| デメリット | ・通信エラーなどによって送信失敗することがある ・内容の鮮明さが保証されず、読みづらいことがある ・検索性が乏しく、管理が非効率 |
FAX送付は書面での郵送と比較すると迅速に送付ができる点が魅力でした。しかし、セキュリティ面や管理のしやすさでは現代の基準に合わなくなりつつあり、将来的には電子化への移行が求められると考えられます。
メールで送信する
メールによる請求書送付は、現在では一般的に広く普及している送付方法です。メールで送付する際は、請求書をPDF形式などのファイルとして添付し、取引先に送信します。低コストかつスピーディーで、在宅勤務にも対応しやすいメリットがあります。
| メリット | ・送付にかかるコストがほぼゼロ ・相手にすぐ届くため、請求処理が迅速に進む ・デジタル形式で保管・共有しやすく、管理が容易 |
| デメリット | ・メールが迷惑フォルダに入るなど、未着のリスクがある ・相手のITリテラシーによっては印刷などの対応が必要 ・改ざんリスクや不正アクセスなどセキュリティ面の注意が必要 |
メール送付は効率的な手段ですが、相手の合意を得たうえで送付すること、そして電子帳簿保存法に基づいた保存要件を満たす運用が必要です。ビジネスのスピード化を図るうえでも、多くの企業にとって今後主流となる手段といえるでしょう。
請求書に記載すべき内容【インボイス制度対応】
請求書をメールで送付する際でも、記載すべき内容は従来の紙面で郵送する際と基本的に変わりません。2023年に開始したインボイス制度に対応した記載内容は、主に以下のとおりです。
・請求書の宛名
・請求書を発行する側の情報
・請求書の作成日
・請求書番号
・取引内容
・請求金額
・消費税と源泉徴収
・支払い期限
・振込先
請求書の宛名
請求書には、誰に対して発行するかを明確にするため、取引先企業の正式名称と部署名・担当者名などの宛名を記載します。
原則として略称や省略名は避け、商業登記簿に記載されている正式な法人名を使用することで、請求の正当性が証明されやすく、誤送付やトラブルの防止にもつながります。
請求書を発行する側の情報
請求書には、発行する側(売り手)の会社名、住所、電話番号、担当者名などの基本情報を必ず記載します。
インボイス制度に対応した適格請求書としては、これに加えて登録番号(Tから始まる13桁)も明記する必要があります。
この情報により、買い手側が適格請求書かどうかを確認できるため、仕入税額控除の要件を満たす上でも重要なポイントとなります。
請求書の作成日
請求書の発行日である作成日は、請求の起点となる日付であり、会計処理や税務処理の基準となる重要な情報です。
作成日が記載されていないと、取引時期が不明確になり、仕入税額控除の対象外と判断されるリスクもあります。年月日まで明記するのが原則です。
請求書番号
請求書番号は、発行された請求書を特定するための管理番号です。
重複のない通し番号や年月日・顧客コードなどを組み合わせた形式が一般的で、後の問い合わせや支払確認時にも役立ちます。
インボイス制度において番号の記載は必須ではありませんが、自社の帳簿管理や相手先の確認作業を効率化するうえでも役立つため、記載するのがおすすめです。
取引内容
請求対象となる商品・サービスの名称、数量、単価、提供日、提供内容の詳細を明確に記載する必要があります。
インボイス制度では「課税対象となる資産の譲渡等の内容」が必要であるため、「業務委託料」や「コンサル費用」と簡略化するのではなく、できるだけ具体的な内容で記載することが求められます。これにより、受け手側も取引の内容を確認しやすくなります。
請求金額
請求書には、取引の金額を「税抜金額」「消費税」「税込金額」に分けて明記するのが基本です。合計金額は明確に記載し、取引先との認識違いを防ぎましょう。
インボイス制度においては、適用税率ごとの税抜金額と消費税額を分けて記載することが義務付けられています。
軽減税率の対象がある場合は、それを区別して記載する必要もあります。正確な金額の内訳を提示することで、相手先の経理処理や税務申告にも対応しやすくなります。
消費税と源泉徴収
インボイス制度に対応するには、請求金額に含まれる消費税額を明確に記載することが求められます。
適用税率が複数ある場合は、それぞれ分けて明記する必要があります。フリーランスや個人事業主が報酬を請求する場合、源泉徴収税額(通常10.21%)を差し引いた金額を記載するケースもあります。
消費税と源泉税は異なる税制であるため、それぞれを明確に区分して表示することが重要です。
支払い期限
請求書には、支払期限(支払期日)を必ず明記しましょう。
「2025年8月31日まで」など、日付を明確に指定することが望ましく、支払い遅延を防ぐうえでも重要です。契約上で「月末締め翌月末払い」といった取り決めがある場合は、それに従って記載します。
振込先
請求書には、振込先の銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義を正確に記載します。
記載に誤りがあると遅延やトラブルの原因となるため、最新の情報を必ず確認しましょう。
請求書をメールで送付する際の文例
請求書をメールで送付する際は、件名・宛名・本文の流れに注意しながら、丁寧かつ簡潔に要点を伝えることが大切です。
件名:請求書送付のご案内(株式会社〇〇/請求No.〇〇)
〇〇株式会社
〇〇部 〇〇様
いつも大変お世話になっております。
株式会社△△の〇〇です。
〇〇〇〇年〇月分の業務に関する請求書をお送りいたします。
添付ファイル(PDF)にてご確認いただき、ご査収のほどよろしくお願いいたします。
お支払いは、請求書記載の期日までに指定口座へご入金をお願い申し上げます。
なお、誠に勝手ながら、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願いいたします。
また、請求書原本郵送の必要がございましたらご連絡ください。
添付ファイルが開封できないなど、不都合やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
――――――――――
株式会社△△
経理担当:〇〇
TEL:03-XXXX-XXXX
Email:xxxx@xxxx.co.jp
――――――――――
実際に送る際は、取引先や担当者との関係に応じて文面を調整しましょう。
請求書をメールで送付する際の注意点
ここでは、請求書をメールで送付する際の、データの取り扱いなどに関する注意しておくべき点について解説します。
ファイル添付があることを本文を明記する
請求書をメールで送る際には、請求書ファイルを添付していることを本文内で明確に伝えることが重要です。
件名や本文にその記載がないと、相手がファイルの存在に気づかずに見落とす可能性があります。迷惑メール対策が強化されている企業では、添付ファイル付きのメールが自動的に除外されることもあるため、本文で「請求書をPDFにて添付しておりますので、ご査収ください」などと明記することで、相手の確認を確実に促すことができます。
ファイル名も「2025年4月分_株式会社○○_請求書」といったように、内容が一目でわかる形式にすることで、誤認防止や管理のしやすさにもつながります。
電子帳簿保存法に対応する
請求書をメールで送付する場合、相手側がそのデータを電子帳簿保存法に則って保存する必要があることを理解しておく必要があります。
2022年の電子帳簿保存法改正以降、電子取引に該当する請求書データは、一定の保存要件を満たす形で保存しなければ税務上の証憑として認められない可能性があります。
たとえば、ファイル名やフォルダの管理ルールに基づいた「検索性の確保」、タイムスタンプの活用、改ざん防止措置などが挙げられます。
請求書を送る側として、相手が制度に対応できているかをあらかじめ確認し、必要に応じて書面や郵送での対応を選ぶ配慮も求められます。発行側も同じく電子帳簿保存法に則りデータを保管する義務がある点も注意しましょう。
請求書はPDFデータで送付する
メールで送る請求書は、PDF形式で作成・添付するのがもっとも一般的で安全な方法です。
WordやExcelのまま送ってしまうと、受け手側の環境によってレイアウトが崩れたり、内容が改変されてしまうリスクが高まります。一方、PDFファイルであれば、書式や表示の崩れを防ぎ、改ざん防止の観点でも安心感があります。
ただし、PDFでも改ざんされる可能性はゼロではないため、PDFにパスワードをかけるなどのセキュリティ対策も忘れず実施しましょう。
クラウド型の請求書管理ツールなどを使えば、自動でPDF形式の請求書を発行・送付する仕組みも構築でき、効率化にもつながります。
原本の郵送が必要かどうか確認する
請求書のメール送付が一般化しているとはいえ、取引先によっては原本の郵送を求めているケースもあります。
たとえば、紙の原本を保管する社内規定がある企業や、電子帳簿保存法への対応が未整備な中小企業などでは、従来どおりの郵送対応が必要です。
メール送付だけで済ませてしまうと、「請求書が届いていない」と誤解されたり、支払いが遅れる原因にもなりかねません。請求書を送る前に、取引先の請求書受領ルールを必ず確認しておくことが大切です。
押印の必要性を確認する
請求書には必ずしも押印が必要というわけではなく、税法上も押印の有無によって請求書の法的効力が否定されることは基本的にありません。
ただし、取引先によっては「社印のある請求書でなければ経理処理できない」といった内部ルールが存在する場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
特に公共団体や伝統的な企業では、押印された紙の請求書が求められる慣習がいまだに存在しているケースもあります。メール送付の場合も、PDFデータ内に電子印鑑を挿入して対応するのが一般的です。
印鑑の有無に関する認識の違いが信頼関係に影響することもあるため、相手の要望や社内の運用方針に沿って柔軟に対応することが望まれます。
請求書の電子化により業務効率アップを
請求書を電子化することで、これまで煩雑だった経理業務の効率が大幅に向上し、紙代や郵送費などのコスト削減にもつながります。さらに、請求書だけでなく契約書などの社内文書もあわせてデジタル化することで、企業全体の業務フローがよりスムーズになり、DX推進につながります。
当社が提供する電子契約サービス「クラウドサイン」では、契約書類をアップロードしメールで送信するだけで、契約締結までのプロセスを簡潔に完了できます。受信者はサービスに登録せずとも内容を確認・対応できるため、取引先にも負担をかけずに導入できるのが特長です。
業務の電子化を検討している方は、このタイミングで電子契約の導入を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
クラウドサインの機能や料金については、概要をまとめた資料をご用意しているので、興味のある方はぜひ下記リンクからご覧ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
この記事を書いたライター