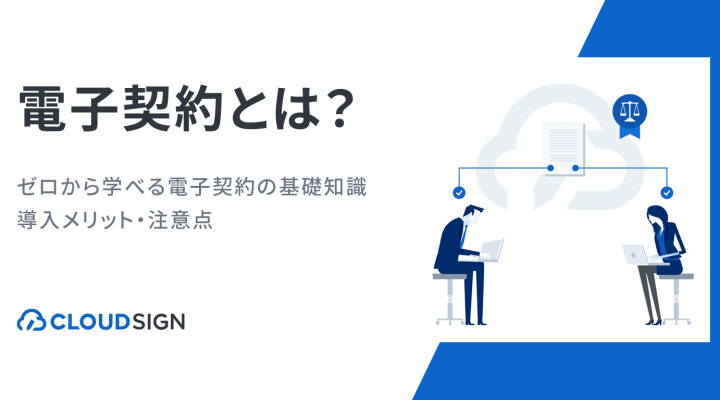検収書とは?発行目的や納品書・受領書との違い、検収書の書き方を解説|テンプレート無料ダウンロード付き
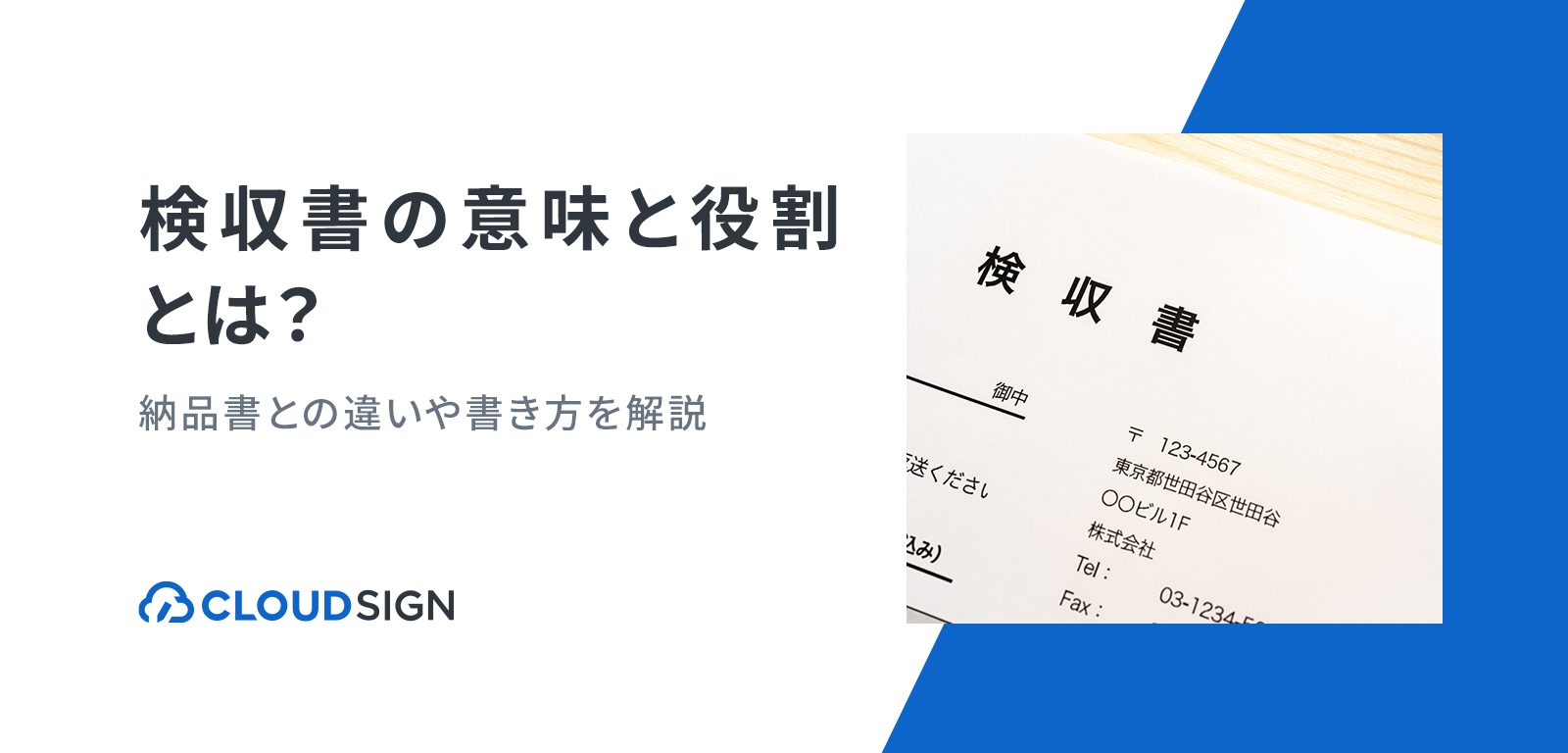
本記事では、建設業や製造業などで利用する機会の多い検収書について解説します。さらに、電子契約を利用した検収書の送付や電子化のメリットについても紹介しますので、ペーパーレスによる業務効率化を図りたい方は受発注業務をスムーズに進めるためのガイドとしてご活用ください。
また、Word版のひな形も無料でダウンロードできますので、検収書作成の手助けにご活用ください。
無料ダウンロード
検収書とは
検収書とは、契約に基づいて納品された納入物や工事の品質、数量等を確認し、受け入れたことを証明する書類です。主に建設業や製造業、システム開発、Webサイト制作、コンサルティングといった、成果物が無形であったり、完成までに複数回のチェックが必要だったりする取引でで利用されることが多く、契約の完了や支払いなどに関わる重要な文書として位置付けられます。
多くの場合、この検収書をもって、取引の一つの区切りとし、検収書の作成・発行後に請求と支払いがされる流れとなります。
検収書の意味と役割
検収書を発行する意味としては、「発注者による成果物の検査が完了し、契約内容に適合していることを承認した」という意思表示をするということにあります。
検収書を発行することで、受注者にとっては、契約通りの義務を果たしたことを客観的に証明する役割、つまり取引完了の証明となる役割があります。また、検収書の受理をもって支払い処理を開始するフローが組まれていることが多く、経理部門にとっては、支払いを行うための正式な根拠となります。ほかにも、発注者が納品された成果物の品質、数量、仕様などを最終確認することで、品質の担保につながるという役割も果たしています。
検収書の重要性
検収書は法的に発行が義務付けられた書類ではありませんが、発行が重要な理由はいくつかあります。
まず、検収書はクレームやトラブル防止のために重要な書類です。発注者は、検収書の発行により、納入物の品質や数量が発注内容と適合していることを認めたことになりますから、検収書の発行後は納入物の不備を指摘しづらくなります。
したがって、受注者の立場から考えると、発注者から検収書を発行してもらうことは、検収書の受領後に発注者からクレームを未然に防ぐことにつながります。
次に、検収書は仕事の完成を裏付ける資料の1つとなります。法律上、検収の効果は定められていないため、検収書の存在によって当然に仕事の完成が証明されるわけではありません。しかし、検収書が発行されている場合、通常は発注者が仕事の完成を確認しているはずですから、検収書は、仕事の完成を推定する証拠となり得ます。したがって、仮に検収書の発行後に仕事が完成しているか否かをめぐってトラブルが生じた場合にも、トラブル解決のために検収書が重要です。
検収書の発行は義務?
原則として、法律で検収書の発行が直接的に義務付けられているわけではありません。 そのため、当事者間の合意があれば、検収書を取り交わさずに取引を進めることも可能です。
ただし、下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)が適用される取引においては、親事業者は下請事業者に対して、実質的に検収に類する行為とその結果の通知が義務付けられています。具体的には、親事業者は物品等を受領した日から起算して60日以内に定めた検査期間内に検査を完了し、不合格の場合は直ちにその理由を通知する義務があります。このプロセスを書面で管理する上で、検収書が利用されるのが一般的です。
検収書の法的効力は?
検収書自体が特別な法的効力を持つわけではありませんが、民法上の承認という意思表示を行った証拠として、法的に重要な意味を持ちます。
検収書に署名・捺印することで、発注者は「納品された成果物が契約内容に適合していることを確認し、承認した」とみなされます。そのため、検収書発行後に、検収時に発見可能であったはずの不備(例:数量が足りない、仕様が違うなど)を理由に支払いを拒否したりすることは原則として困難になります。
ただし、検収時に通常の注意を払っても発見できなかった不備(「隠れた瑕疵」や「隠れた契約不適合」)については、検収書を発行した後でも、受注者に対して修正や損害賠償を請求できる場合があります。
納品書との違い
検収書と納品書はそれぞれ異なるタイプの書類です。
検収書は納入物の品質・数量が発注内容どおりであるか発注者が確認したことを示すために発行される書類です。一方、納品書は商品やサービスの納入を証明するために発行される書類です。
また、検収書は検収完了時に発注者側が発行するのに対し、納品書は商品・サービスの納品時に受注者側が発行する書類のため、検収書と納品書では発行者の立場と発行のタイミングも異なります。
| 検収書 | 納品書 | |
| 目的 | 納品物の中身(品質・数量など)を検査し、受け入れたことを証明する | 商品やサービスを納品した事実を伝える |
| 発行者 | 発注者(購入側) | 受注者(販売側) |
| 発行タイミング | 納品後、検査・検収が完了したとき | 商品やサービスを納品するとき |
受領書との違い
受領書は「受け取った」という事実を証明する点で検収書と似ていますが、確認する範囲の深さが異なります。
受領書が証明するのは、あくまで「物品を物理的に受け取った」という事実のみです。たとえば、宅配便のドライバーから段ボール箱を受け取る際にサインをするのが、この受領書にあたります。この段階では、まだ箱の中身が注文通りのものか、破損していないか、といった点までは確認していません。
一方、検収書は、その段ボール箱を開封し、中にある商品の品番や数量が発注内容と一致しているか、商品に傷や不具合がないかといった、品質や仕様まで含めた詳細なチェックを行なった後で発行します。
したがって、「受領」は検収作業の前段階の行為であり、受領書の発行が必ずしも納品物の受け入れを意味するわけではありません。
| 検収書 | 受領書 | |
| 確認の範囲 | 品質の良否、数量の過不足、仕様との合致など、中身まで確認・承認する | 物品を受け取った事実のみを証明する(中身や内容の確認は含まない) |
| 発行者 | 発注者(購入側) | 発注者(購入側) |
| 意味合い | 「検査の結果、問題なかったので正式に受理します」 | 「確かに受け取りました(中身や内容はこれから確認します)」 |
請求書との違い
請求書は、これまで解説した書類とは目的が根本的に異なり、金銭の支払いを要求するための書類です。検収書は「モノやサービスの取引の完了」を証明する書類であり、請求書は「お金の取引の開始」を依頼する書類であるという、明確な違いがあります。
もう少し具体的に解説をします。取引における一般的な流れとしては、「①納品 → ②検収 → ③請求」です。まず、受注者が成果物を「①納品」し、発注者がその内容を検査し、問題がなければ「②検収書」を発行します。この検収書の受理が、受注者にとって「請求書を発行して良い」という正式な合図になります。
この後、受注者は確定した金額で「③請求書」を発行し、発注者はその請求書に基づいて支払い処理を行います。もし検収書がないまま請求書が送られてきた場合、発注者側は「まだ中身を確認できていないので支払えません」と支払いを保留することが可能です。
| 検収書 | 請求書 | |
| 目的 | 納品物が契約通りであることを承認する | 提供したサービスの代金を要求する |
| 発行者 | 発注者(購入側) | 受注者(販売側) |
| 発行タイミング | 納品 → 「検収」 → 請求 → 支払い | 納品 → 検収 → 「請求」 → 支払い |
検収書に記載する項目
検収書には決まったフォーマットはありませんが、以下のような項目が記載されることが一般的です。
| 検収書に記載する項目 | 概要 |
|---|---|
| タイトル | 何の書類なのかがわかるように冒頭に「検収書」と記載します |
| 検収の日付 | 商品やサービスの検収が完了した日の日付を記載します |
| 納入日付 |
商品やサービスが納入された日の日付を記載します |
| 検収番号 | 検収書の一意の識別番号を付けます |
| 受注先情報 | 受注先の会社名や住所、連絡先などを記載します |
| 発注者情報 | 発注側である自社の情報(企業名、所在地、連絡先など)を記載します |
| 契約内容 | 契約の詳細な内容や納入物や工事の詳細を記載します |
| 数量と品質 | 納入物や工事の数量や品質に関する情報を記載します |
| 検収者の氏名・捺印 | 検収を行った担当者の氏名を記載し、捺印します |
| 備考 | その他の重要な情報や特記事項を記載します |
なお、Word版のひな形はこちらから無料でダウンロードできますので、検収書作成の手助けにご活用ください。
無料ダウンロード
検収書に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、検収書の実務において疑問に思われやすい点について、わかりやすく解説します。
検収書に押印は必要?
法律上の義務はありませんが、実務上は押印するのが一般的です。
法律では、検収書を含む書類の成立に押印を必須とは定めていません。当事者間の合意が確認できれば、押印がない検収書も有効です。
しかし、日本のビジネスシーンにおいて押印は、その書類が正式な手続きを経て発行されたものであることを示す重要な役割を担います。押印があることで、誰が、いつ、その内容を承認したのかが明確になり、書類の証拠能力と信頼性が高まります。
そのため、トラブル防止の観点から、多くの企業では会社印(角印)や、検収担当者の部署印・氏名印などを押印する運用を行っています。
なお、電子契約サービスを利用する場合は、物理的な押印の代わりに、本人性と非改ざん性を担保する「電子署名」がその役割を果たし、書類の証拠能力と信頼性を高く保つことができます。
検収書に収入印紙は必要?
原則として、検収書に収入印紙は不要です。収入印紙の貼付が義務付けられているのは、印紙税法で定められた20種類の「課税文書」に限られます。
検収書は、通常「成果物の内容を確認し、受け入れたこと」を証明する書類であり、金銭の受領事実を証明する「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書、いわゆる領収書)には該当しません。そのため、印紙税の課税対象外となり、収入印紙は不要です。
ただし、検収書の記載内容には注意が必要です。もし検収書に「代金〇〇円を受領しました」「上記金額を相殺しました」といった、金銭の受領事実を示す文言が含まれている場合、それは実質的に領収書や相殺領収書とみなされ、記載金額に応じた収入印紙の貼付が必要になることがあります。意図せず課税文書とならないよう、検収書には検収完了の事実のみを記載するのが賢明です。
出典: 国税庁|No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書 、 国税庁|No.7140 印紙税の課税対象となる文書
検収書を紛失した場合の対処法は?
速やかに取引先に連絡し、再発行を依頼しましょう。検収書は取引完了の証拠となる重要な書類です。紛失に気づいたら、放置せずにすぐ対応することが重要です。対処法は、どちらが紛失したかによって異なります。
- 自身が受注者側で検収書を紛失した場合発注者に正直に事情を説明し、検収書の再発行をお願いしましょう。その際、二重計上などのミスを防ぐため、再発行された検収書には「再発行」と明記してもらいましょう。
- 自身が発注者側で検収書の控えを紛失した場合受注者に連絡し、保管している検収書の控えのコピー(写し)を提供してもらいましょう。
いずれの場合も、まずは取引先に連絡を取り、すぐに相談しましょう。
なお、このような紛失リスクは、紙の書類で起こりがちな問題です。電子契約サービスを利用して検収書をデータで管理すれば、検索性が向上するだけでなく、誤って破棄したり紛失したりするリスクを大幅に低減できます。
検収書は電子契約サービスで送付できる
従来の紙の書類から電子契約に乗り換えることで検収書の作成〜送付〜保管といった一連の業務をスピーディーかつ効率的に行えるようになります。電子契約サービスでは、検収書を保管し、必要な場合に簡単にアクセスできるため、管理や検索の手間も軽減されます。
検収書を電子化するメリット
電子契約サービスで検収書を送付するメリットとして、「業務効率化」「管理の効率化」「環境への貢献」「セキュリティの確保」の4点が挙げられます。検収書の電子化を検討している方はそれぞれの詳細を確認しておきましょう。
業務効率化
電子化により、検収書の作成や送付などの業務プロセスが効率化されます。紙の書類を印刷したり郵送する手間がなくなるため、従来の紙の書類で発生していた時間とコストを節約することができます。
管理の効率化
電子化した場合には、検収書を安全に保存し、必要な時に簡単にアクセスできるようになります。紙の書類の場合、保管場所の確保や整理方法に悩むことがありますが、電子化により検索や整理も簡単に行うことができます。
環境への貢献
単なる業務や管理の効率化だけでなく、環境への貢献も期待できます。電子化により、紙の使用量を減らすことができるためです。紙の製造には多くの資源とエネルギーが必要であり、また廃棄物として処理される際にも環境に負荷がかかってしまうため、環境への貢献の観点でもメリットがあると言えるでしょう。
セキュリティの確保
セキュリティ対策の施された電子契約サービスを利用して電子化した場合には、情報漏洩や紛失のリスクを低減できます。電子契約サービスを検討する際にはデータのセキュリティを確保するための厳しい対策を講じているかどうかも選定基準に含めるとよいでしょう。
検収書の電子化で受発注業務の効率化を
検収書の電子化により、検収書の作成〜送付〜保管といった一連の業務を効率化できます。そこでおすすめなのが電子契約サービスです。電子契約サービスを利用することで、検収書の管理や検索を簡単に行うことができます。必要な情報をすばやく見つけることができるため、受発注業務全体のスピードと正確性が向上します。
さらに、電子契約による検収書の送付は、郵送や手渡しに比べて迅速かつ安全です。紙の書類が紛失したり、届かないといったトラブルも防ぐことができます。
当社の提供するクラウド型の電子契約サービス「クラウドサイン」は導入社数250万社以上、累計送信件数1000万件超の実績を持ち、導入時の課題解決や運用定着化のサポートも充実しています。検収書を作成することの多い製造業や建設業における電子契約システムの導入実績も多数あるため、電子契約の導入を検討中の方はお気軽にご相談ください。
また、電子契約の基礎知識やメリットなどをまとめて知りたい方はこちらの資料をダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)なお、クラウドサインではWord形式の検収書ひな形をご用意しています。無料で入手できますので、検収書のひな形をお探しの方は下記のリンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード
この記事を書いたライター