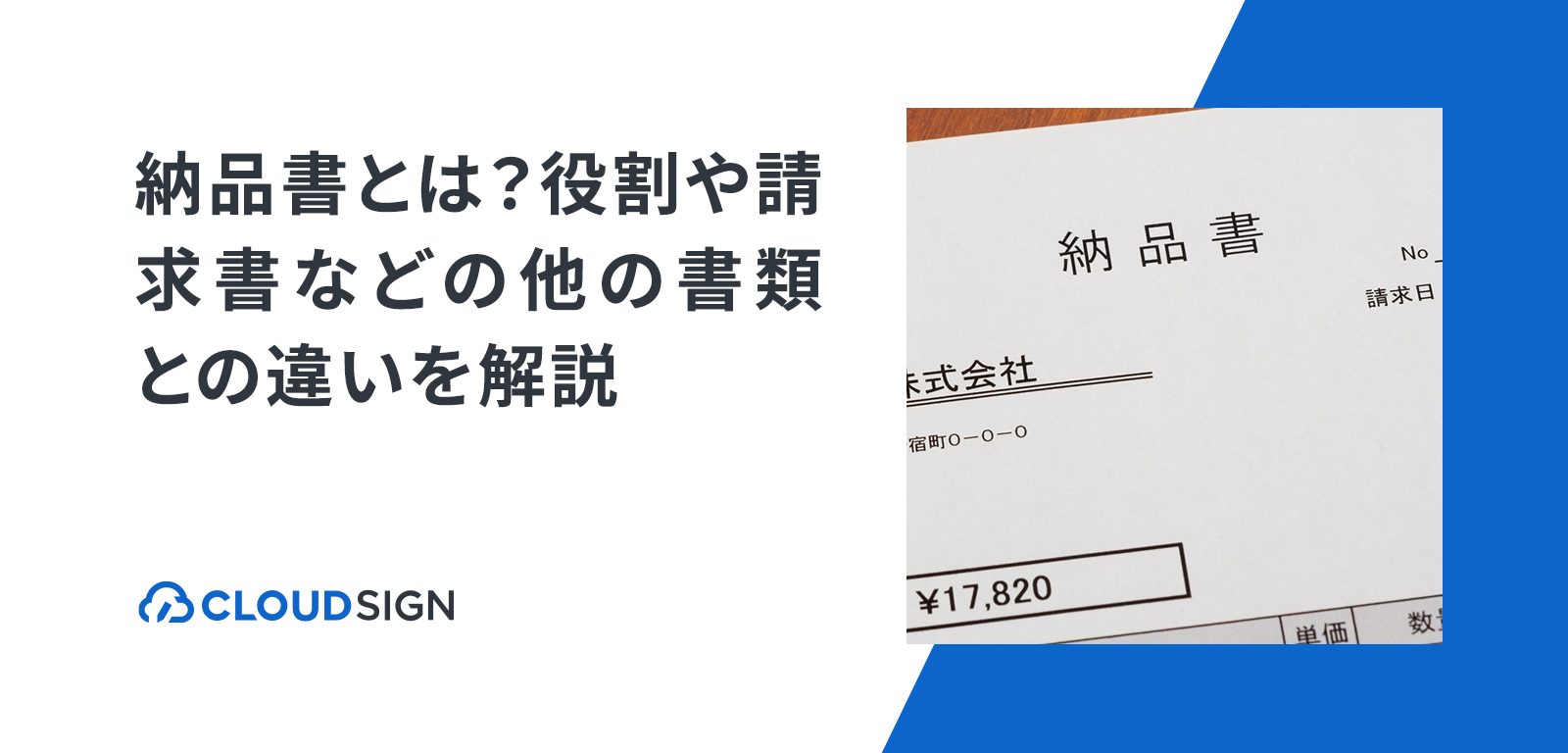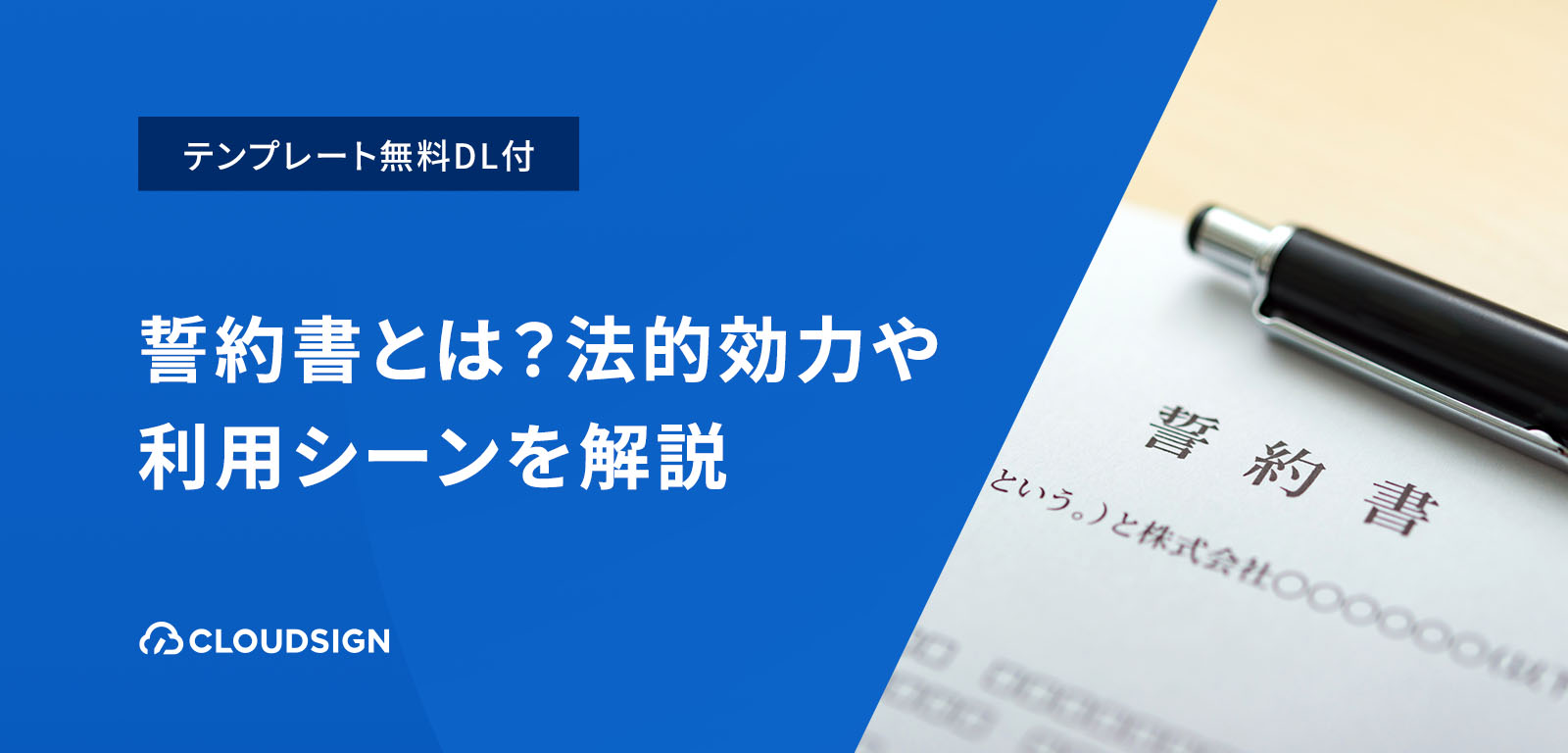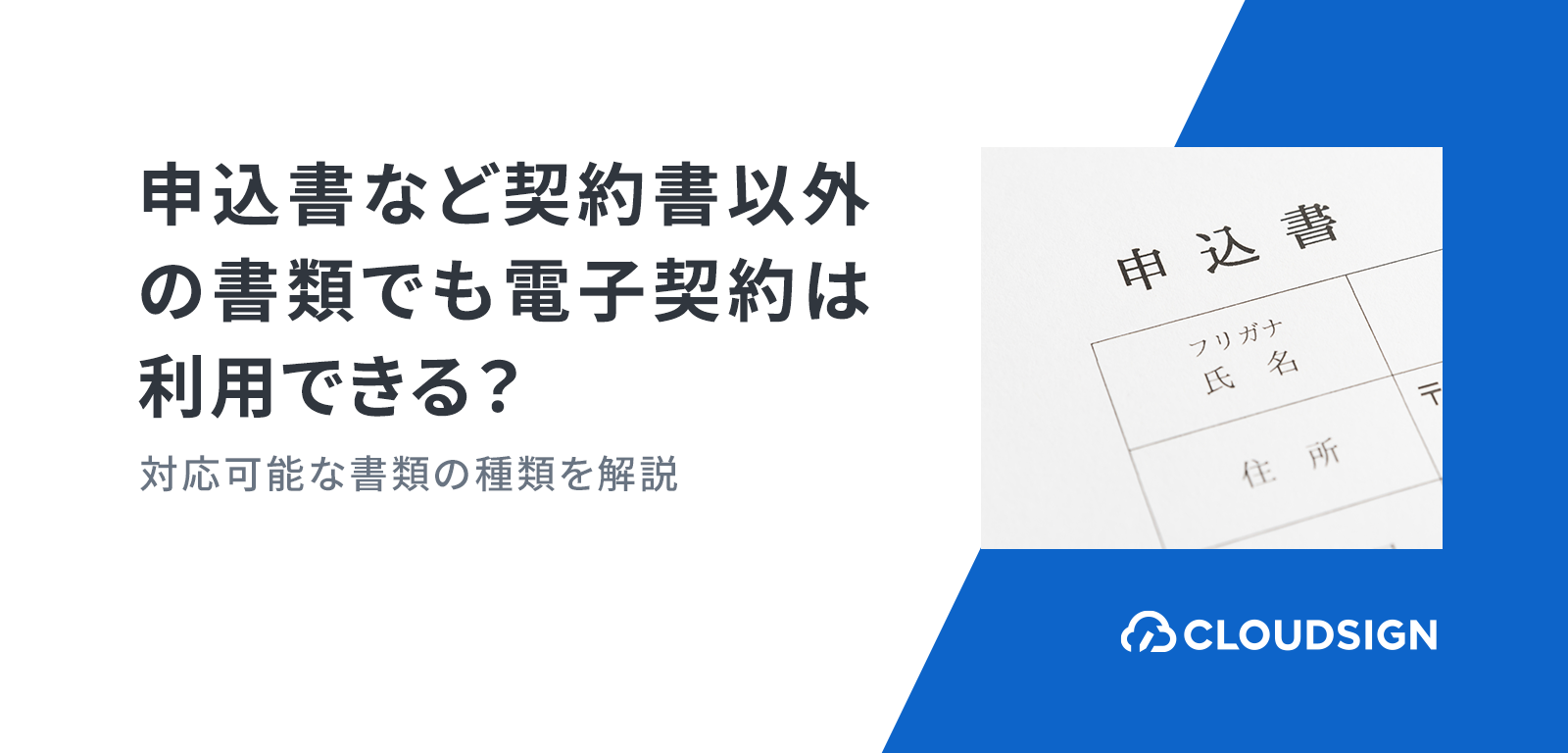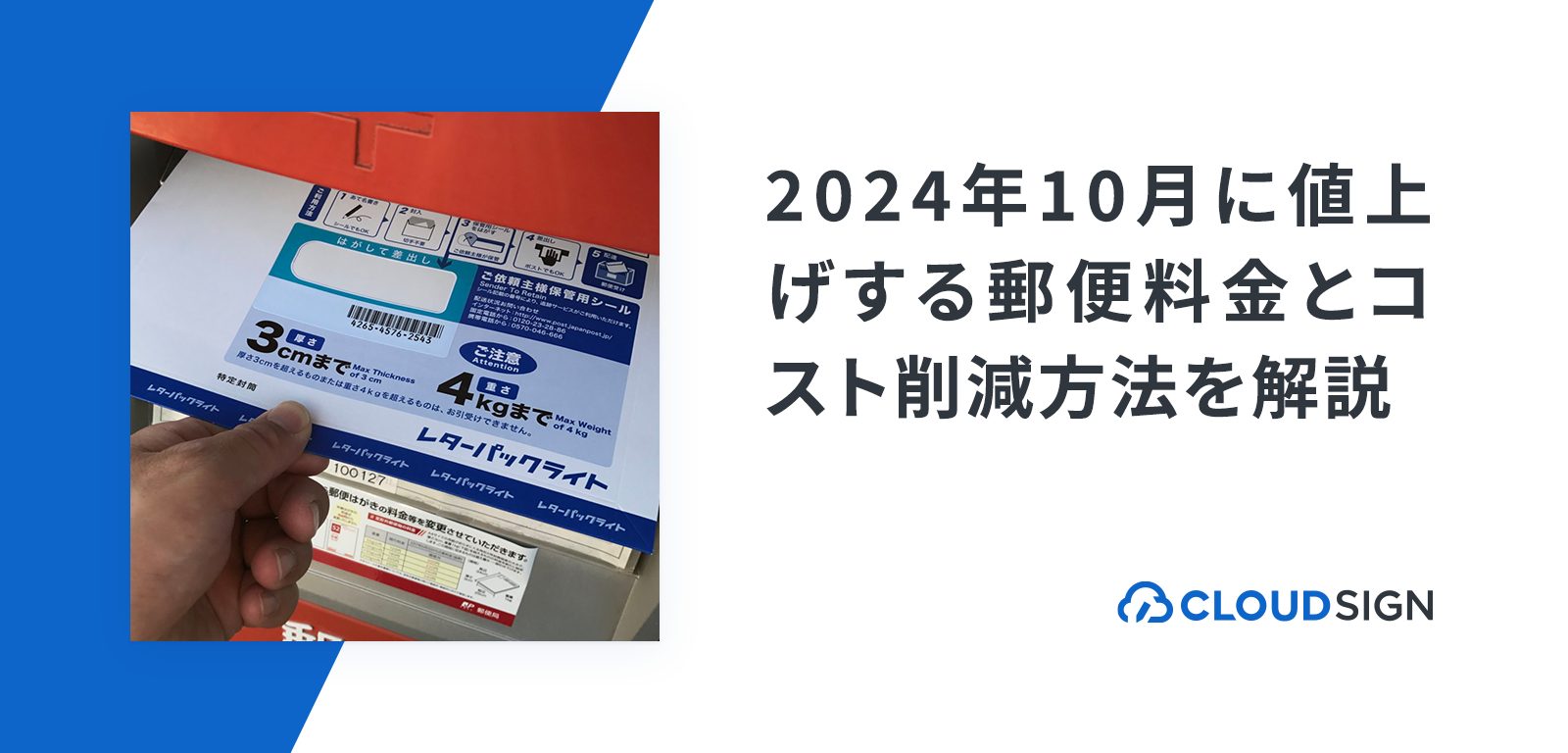同意書とは?契約書や承諾書などの類似する言葉との違いや作成時の注意点を解説

同意書とは、取引や契約において買い手側の意思表示を記録として残すために作成する書類です。
「個人情報に関する同意書」や「医療行為に関する同意書」など、提供するサービスや利用シーンによって同意書の内容は異なるため、どのような項目を盛り込むべきか確認しておく必要があります。
この記事では、同意書の定義・役割や必要項目、作成時の注意点を分かりやすく解説しますので、同意書を作成する前に確認しておきましょう。
同意書とは?
同意書とは、ある行為や情報開示に対して事前に「同意する」という意思を表明するために作成する文書です。 書面に定めた事項について、提出者が同意したことを証明する役割があります。
同意書を作成する主な目的は、同意を得た事実を明確にし後々のトラブルを予防することにあります。 たとえば、個人情報の利用、未成年者の契約、医療行為などのさまざまな場面で利用されます。
同意書はその記載内容によっては法的効力を持つ場合があるため、適切な形式で作成し、保管することが重要です。
契約書・承諾書・誓約書との違い
同意書と混同しやすい書類として「契約書」「承諾書」「誓約書」があります。
これらの書類の大きな違いとして、双方の署名・捺印が必要か、当事者の一方が相手方に差入れるのみのいわゆる「差し入れ形式」(双方の署名・捺印は不要)かという点が挙げられます。
「差し入れ形式」とは契約の一方の当事者が相手先に対して提出する形式のことです。
具体的には、契約書は契約を締結する双方の署名・捺印が必要になります。それに対して、同意書、承諾書、誓約書は契約の一方の当事者が相手先に対して提出する「差し入れ形式」の書類のため、双方での署名・捺印は必要ありません。
【同意書、契約書、承諾書、誓約書の分類と詳細】
| 分類 | 書類名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 契約当事者双方の署名・捺印が必要な書類 | 契約書 | 契約当事者間の合意内容を詳細に定めた文書です。 双方が署名・捺印することで成立し、権利と義務を明確にします。 |
| 相手方の署名・捺印が不要な差し入れ形式の書類 | 同意書 | ある行為や情報開示に対して、事前に「同意する」という意思を表明する文書 |
| 承諾書 | 相手からの申し出や提案に対して、承諾の意思を示す文書です。 契約内容に合意した場合などに作成されます。 一方的な意思表示であり、相手方の行為を認める意味合いが強いです。 |
|
| 誓約書 | 特定の事項を守ることを約束する文書です。 違反した場合の罰則などが明記されることもあります。 行為を約束し、その遵守を誓う場合に用いられます。 |
同意書と承諾書は、何らかの事項について提出者の同意を明確にすることを目的としているため、基本的にはほぼ同じ位置付けの書類になりますが、法令や契約内容で相手方の「同意」が必要であれば「同意書」、「承諾」が必要であれば「承諾書」とするのが一般的です。
また、誓約書は提出者が何らかの行為の実行ないしは行為しないことを約束して、その内容に関連する義務を負う書類です。単に相違を得るだけの同意書に比べると、誓約書はより重い義務を負うという違いがあります。
状況に応じて、これらの書類を使い分けることが重要ですが、書類の命名に関して迷った際には、弁護士等の法律の専門家に相談するのがよいでしょう。
同意書の種類と利用シーン
同意書はさまざまな場面で利用されており、次のような同意書が主な例として挙げられます。
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 未成年者の契約における同意書
- 医療行為に関する同意書
ここでは、よく作成される同意書の種類とそれぞれの利用シーンを解説しますので、自社の状況に適した同意書を作成するための参考にしてみて下さい。
個人情報の取り扱いに関する同意書
個人情報の取り扱いに関する同意書は、企業が顧客や従業員から個人情報を収集、利用する際に必要な書類です。
具体的には、氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどの情報を収集する際に利用目的を明示し、同意を得るために同意書が使用されます。
たとえば、Webサイトの会員登録、メールマガジンの配信、アンケート調査など、個人情報を取り扱うあらゆる場面で必要となる可能性があります。
個人情報の第三者提供について、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の27条1項などで「(一部の例外を除いて)あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」旨が定められています。
(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
出典:個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)|e-GOV 法令検索
このように同意書を作成することで、企業は個人情報を適切に管理し、プライバシーを保護するための努力を示し、利用者側は自身の情報がどのように扱われるかを理解し、安心してサービスを利用できるようになります。
未成年者の契約における同意書
同意書は、契約内容、金額、契約期間などを明記し、親権者が内容を理解・同意したことを証明します。未成年者の契約に関する同意書は、未成年者保護の観点から、非常に重要な役割を果たしています。
たとえば、携帯電話の契約、高額な商品の購入、アルバイトの雇用契約など、未成年者の判断能力を超える可能性がある契約においては、親権者の同意書が必要です。
民法5条1項において「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と定められているため、未成年者が契約を行なう場合、親権者または未成年後見人の同意が必要になるためです。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-GOV 法令検索
未成年者との契約においては必ず親権者または未成年後見人からの同意を得るようにしましょう。
医療行為に関する同意書
医療行為に関する同意書は、患者が治療内容を理解し、同意したうえで医療行為を受けるために必要です。手術、検査、投薬など、身体に負担を与える侵襲的な医療行為を行なう前に、医師は患者に対して治療内容、リスク、代替治療法などを説明した上で患者の同意を得る必要があるためです。
この同意書には、治療内容や期待される効果、リスク、合併症などが記載されます。同意書にサインすることで、患者自身がその内容を理解・同意したことを証明します。
医療行為に関する同意書は、患者の自己決定権を尊重し、患者と医療従事者間の信頼関係を構築するために重要な役割を果たしています。また、医療訴訟のリスクを軽減するためにも、適切な同意書の作成と保管が重要です。
同意書に必要な項目
同意書には決まった形式はなく、必要項目は利用シーンによっても異なります。一般的には下記の項目を記載する場合が多いです。
【同意書に必要な項目の一覧】
| 同意書に必要な項目の例 | 概要 |
|---|---|
| タイトル | 同意書の内容を簡潔に表すもの |
| 掲出先名 | 同意書の提出先(同意を求める側)の氏名または名称 |
| 当事者名 | 同意する側(情報提供者や未成年者など)の氏名または名称 |
| 前文 | 同意書の記載内容に対して同意することの表明 |
| 同意事項 | 個人情報の利用目的、契約内容などを具体的に記載 |
| 日付・署名欄 | 同意書にサインした日付と同意する側の署名 |
インターネット上でもさまざまな同意書のテンプレートが公開されているため、同意書作成時の参考にできますが、権利や個人情報をどのように取り扱うかは明確に記載する必要があります。
どのような記載が法的に適切か判断に迷う場合は、同意書で扱う分野に精通している弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
同意書作成時の注意点
同意書を作成する際にはいくつかの重要な注意点があります。これらの注意点を守ることで、法的リスクを回避しより有効な同意書を作成できます。
必要な同意事項が含まれているかを確認する
まず、同意書に記載されている内容が本当に必要な同意事項を全て網羅しているかを確認しましょう。
個人情報の利用目的、未成年者の契約内容、医療行為の内容など、同意を得るべき事項が漏れなく記載されているかを確認することが重要です。必要な事項が不足している場合、同意が無効となる可能性があります。
また、同意事項が具体的に記述されているか、曖昧な表現になっていないかも確認しましょう。不明確な点があると、後々トラブルの原因となる可能性があります。具体的に記載されているかどうかは、弁護士などの専門家に確認してもらうと安心です。
作成日を記載する
同意書には必ず作成日を記載しましょう。作成日は同意の有効性を判断するうえで重要な要素となるためです。いつ同意が行われたのかを明確にすることで、後日同意の事実を証明する際に役立ちます。
特に、医療行為など時間経過とともに状況が変化する可能性がある内容の場合には作成日の記載が不可欠です。作成日が記載されていないと、同意の成立時期が不明確になり法的紛争に発展するリスクが高まります。
控え(コピー)を保管しておく
同意書は原本だけでなく必ず控え(コピー)を残しておくようにしましょう。控えは万が一原本を紛失した場合や後日同意の事実を証明する必要がある場合に役立つためです。
また、自分自身が同意書を提出する側だった場合、原本は相手方が保管することになり、自分の手元には残りません。相手方に提出した同意書は必ずコピーして保管しておきましょう。
同意書の電子化で送付・締結・管理の効率化を
同意書を電子化することで、送付・締結・管理業務を効率化することが可能です。
紙の書類の場合、印刷や郵送、ファイリングといった事務作業が必要になりますが、電子化することでこれらの事務作業を省略できるメリットがあります。
また、紙の場合は紛失のリスクがありますが、電子化しておけばオンライン上に同意書のデータを保管できるため、無くしてしまうということも避けられます。
ファイル名や日付での検索も可能になり、書類管理の側面でもメリットがあるため、電子化への対応を検討するのも選択肢のひとつです。
電子契約サービスでも同意書を送付・締結・管理できる
2022年の電子帳簿保存法改正以降、各種文書の電子化を促進するために電子契約サービスを導入する企業・個人が増えています。電子契約サービスを利用することで、紙のやり取りが不要になる上、郵送にかかる時間やコストを削減し、迅速な取引が実現できるようになるためです。
電子契約サービスでは、同意書をはじめとする契約書以外の書面の送付ももちろん対応可能です。同意書を紙で提出するためには同意書への記入・印刷・郵送といった手続きが煩雑になりがちですが、電子契約サービスを利用することで同意書をスムーズに提出し、同意完了までのプロセスを迅速に進められます。
関連:申込書など契約書以外の書類でも電子契約は利用できる?対応可能な書類の種類を解説
当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」は導入社数250万社以上、累計送信件数1000万件超の実績を持つ電子契約サービスです。書類の受信者側はクラウドサインに登録する必要がないため、同意書の提出先に準備の負担をかけることなく契約締結が可能になります。
クラウドサインのサービス詳細や特徴を知りたい方は以下のリンクからサービス説明資料をダウンロードしてご検討ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部