代表者名義の押印に慣れ過ぎてしまった日本の商慣習は変わるか
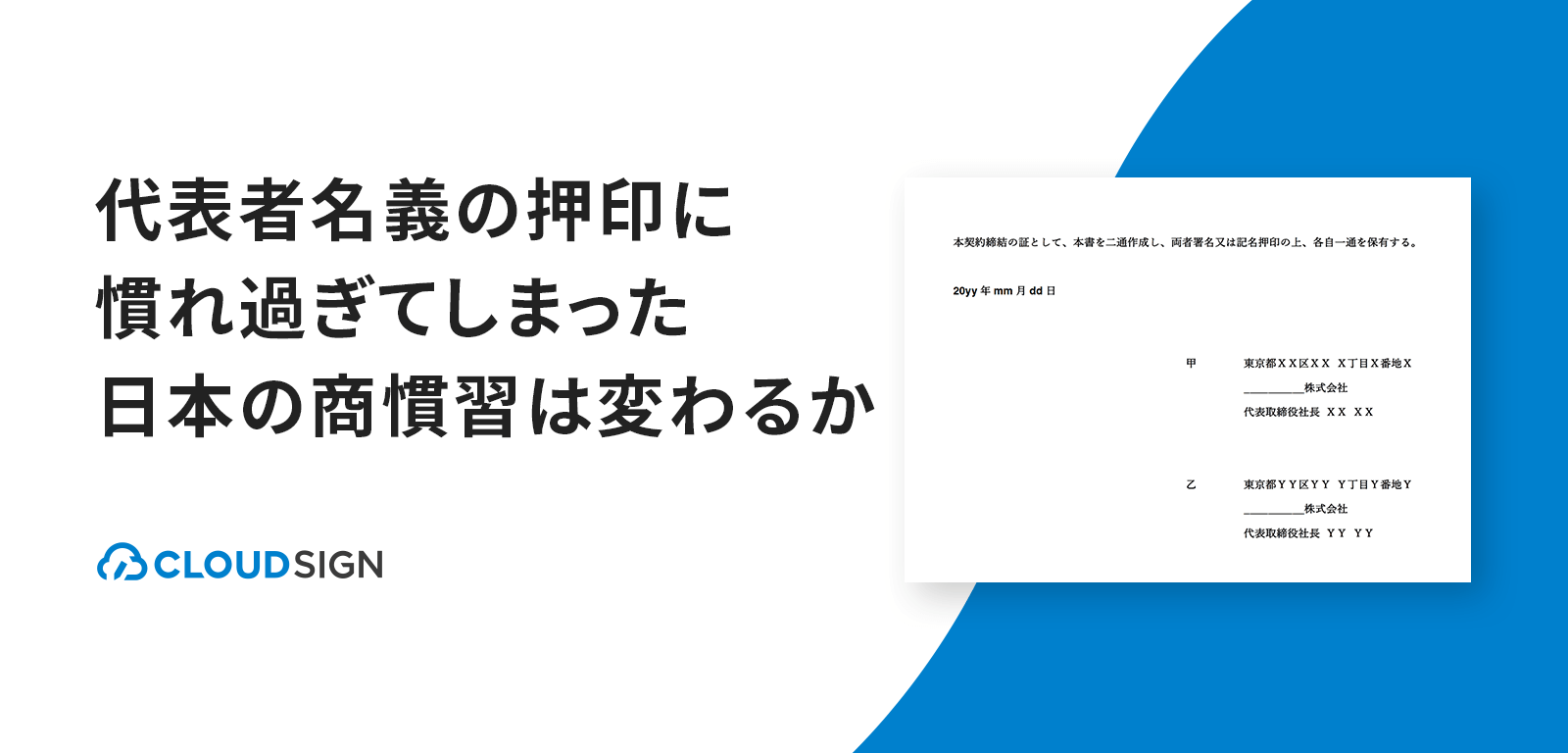
企業にとって電子契約導入の最大の障害は、契約書に代表者名義で押印し続けてきた根強い商慣習からどう抜け出すかにこそあります。
代表者名義の押印文化が根強い日本企業の悩み
行政のハンコ廃止が急スピードに進んでいます。2020年7月から9月にかけて電子署名法に関する法的見解が整理され、これまで一番の障害と言われていた「相手先の理解」も、事業者署名型(立会人型)電子契約の浸透により問題ではなくなりました。
そうして民間のハンコ廃止も進み、電子署名にスムースに移行するだろう…と思われている方も多いでしょう。ところが最近「いざ電子契約を導入しようと運用フローを整理してみたところ、電子署名の作業を誰が行うかという社内事情で悩んでしまって」というご相談が増えつつあります。

このような事情で電子契約サービスの導入につまずいてしまう企業の事情を深掘りしてみると、そこには共通するある「特徴」が浮かび上がってきます。その特徴とは、「一定の従業員数を抱える企業でありながら、ほとんどの契約書を『代表取締役』の名義で記名・押印している」、いうなれば 代表者名義の押印文化が根強い企業 が多くを占めるという点です。
ハンコの代替手段を検討して初めて気づく「代表者押印文化」のカベ
なぜ代表者名義で契約書を作成している企業で導入が滞ってしまうのか? その原因を整理してみましょう。
まず、企業がハンコを廃止しようとするとき、その代替手段としては以下4つの選択肢を挙げることができます。
- 手書き署名する
- 電子署名する
- 署名はしないものの、書面を交付したり電子文書をメールするなど何らかの証憑を残す
- 何も残さない
上記3のようにPDFにPWパスワードを設定し、複数者に電子メールを送信しておくような方法は、政府が6月に発出した「押印についてのQ&A」でもガイダンスがあったところです。リスクが極めて低い取引であれば、いっそ上記4のような思い切った措置もとりうるでしょう。
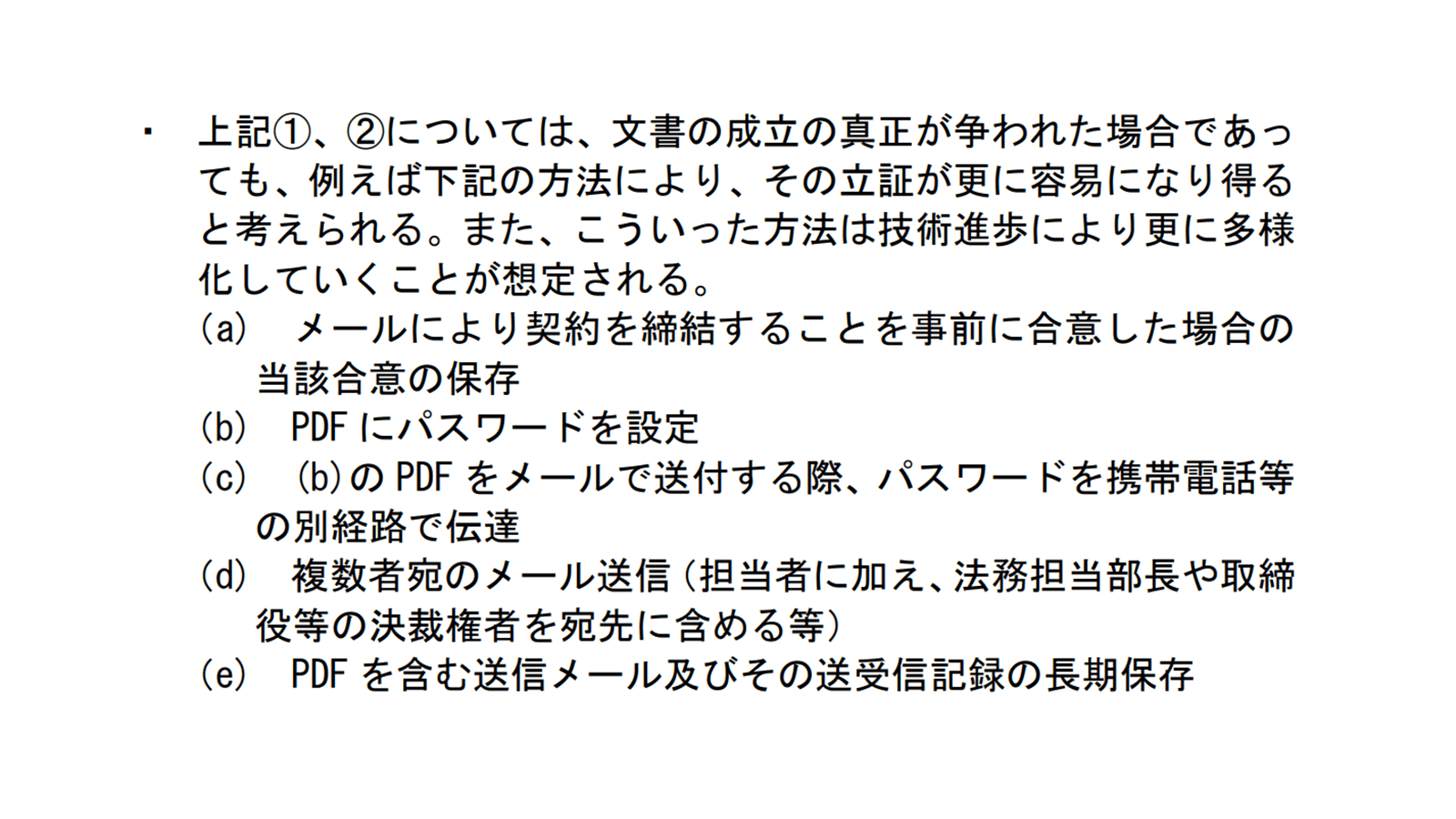
しかし、ある程度の金額を超える取引をするとなれば、ハンコに代わる何らかの証拠を残さないと訴訟の際立証が面倒になります。上場企業であれば、監査上も証憑を求められるでしょう。したがってこの場合の現実的な選択肢は、上記1の手書き署名か2の電子署名となりますが、ここで多くの企業が代表者押印文化のカベにぶつかります。
押印の場合、良くも悪くも誰がハンコを押したかは見た目からは分からないからこそ、従業員が作業を代行できました。一方、1の手書き署名では署名者の筆跡が残り、2の電子署名では作業者の認証情報やアクセスログが残ります。これは本来正しく内部統制を効かせるという点で非常に重要なことなのですが、実務運用上ある意味便利に融通を効かせることができた押印のメリットがいよいよ失われる ということを意味します。冒頭の企業の相談事例のように、「従業員が代表者の署名作業を代行できない」「代表者に手書き署名や電子署名の作業をお願いしなければならない」と悩んでしまうのはそのためです。
もし代表者押印文化が根強い企業がその文化を変えずにハンコだけを廃止し、すべての契約書について代表取締役が手書きサインしたり電子契約のボタンをクリックすることになったら、代表者の貴重な時間を単純事務作業に費やさなければならなくなります。

海外取引におけるサイン文化との違い
1の手書き署名や2の電子署名がすでに当たり前となっている外国企業は、CEOやPresidentといった代表者自身がサイン作業を当然のように行います。といっても、相当な重要取引でなければVice President(当該案件担当部門の責任者)クラスがサイナーとなることも多いため、これを悩みや課題と感じていない(むしろ電子契約で手書きサインの手間が減りラクになったと感じている)のが実態と思われます。
これに対し、先述したような 代表者押印文化が根強く残る日本企業において、あらたに1の手書き署名や2の電子署名を導入する際、この押印カルチャーとのギャップをどうクリアすればよいのでしょうか? これに関し、NBL No.1178(2020年9月15日号)に、横河電機の髙林法務部長のコメントが紹介されていました。
代理署名については、電子署名は押印ではなく署名と同じなので本人に送ることを原則とし、社長名のサインなどでどうしても難しいという場合には、無権代理のリスクを排除すべく、予め代理権限があることを示す書類を出していただく形を取っています。(P17)
先ほど申し上げましたとおり、ドキュサインの場合は本人の署名を原則としていますので、原則は社長本人にサインしていただくことになります。とはいえ、相手方との関係もあり、どうしても社長名でサインせざるを得ないものの、そのために社長の時間を取るのも効率が良くない場合もあると思いますので、それに備えてルール化し、社長が承認した場合、法務部長の確認を経た上で、秘書部長が代理署名をすることができることとしました。当社では従来、社長が契約等の法的文書に署名する場合は、その書類を事前に法務部長が確認して合議した上で、秘書部宛てに署名依頼するというプロセスにしておりますので、これと同様の事前確認プロセスを求めるものです。(P24)
電子契約においても、あくまで 代表取締役本人が自身で署名作業をすることを原則としつつ、どうしてもという場合は秘書部長がこれを代行 することを一定範囲で許容する。そんな折衷案を採用しているというわけです。

一方で、髙林氏はこのカルチャーに対し、未来を見据えこうした見解も添えていらっしゃいます。
そもそも契約締結に関する決裁自体は、社内意思決定ルールに従い、本部長その他の決裁機関が行うことが前提にありますので、決裁後の署名手続上のハードルを上げることで、安易に社長のサインを求めず、当該事案について権限委譲されている人の名前でサインするという、あるべき姿に誘導していければと考えております。(P24)
日本企業においても、「事業部の責任者に決裁権限があるにもかかわらず、ついつい契約書の名義を代表取締役自身にして押印してしまう」カルチャーから脱却し、本来の権限に照らして署名作業自体もしっかりと権限委譲していくべき であろうというわけです。
電子契約の普及を機に日本の商慣習をリ・デザインできるか
代表取締役が取引やその決裁にまったく関与していない、正しく権限委譲がなされていたはずの案件であっても、押印する契約書の調印名義は「代表取締役」と記名してしまうという慣習。
これは「法人では印鑑証明書が唯一入手可能な代表者実印をもらっておいたほうが、いざというときに安心」というマインドからはじまった、日本らしい商慣習です。しかし、印鑑証明書が発行される実印を入手したからといって、その取引の安全が保証されるわけではありません。法務局や認証局が発行する印鑑証明書・電子証明書“だけ”に頼るのではなく、その契約にいたるまでの信用をお互いに積み上げていくことも重要です。
ハンコ廃止を阻もうとするものはいくつかありますが、代表者名義の押印商慣習からの脱却は、日本の民間企業にとって最も根深いレベルで求められる変化 ではないでしょうか。
(橋詰)