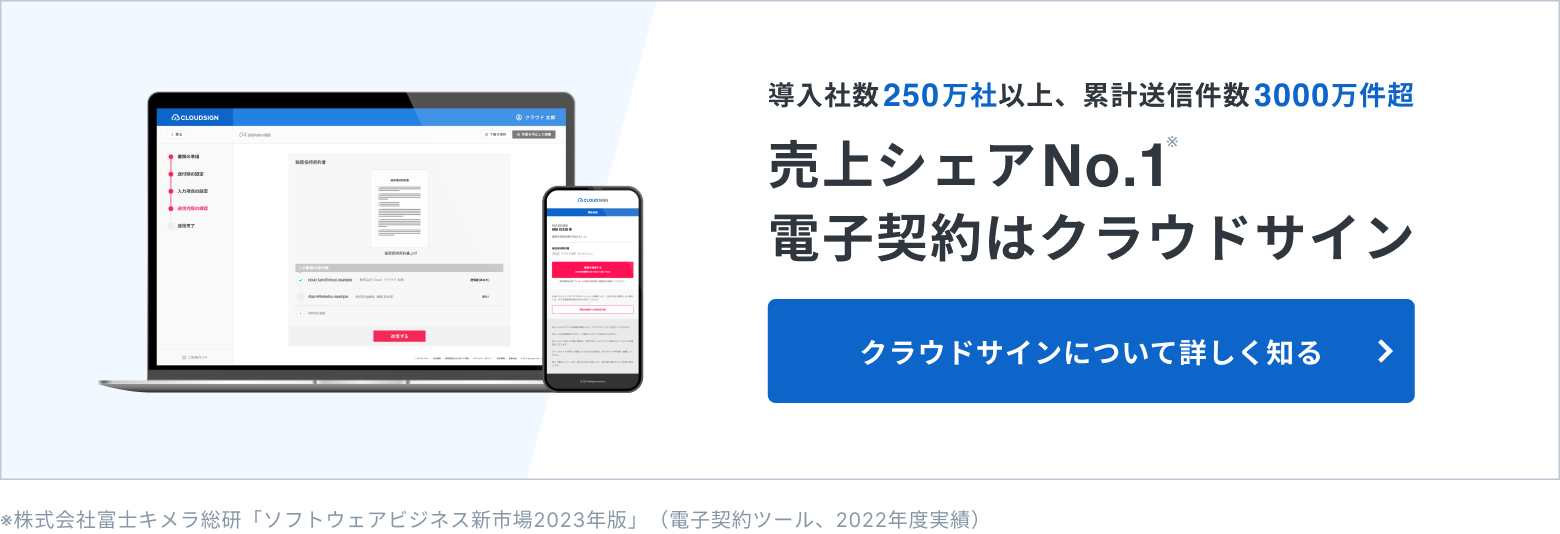実運送体制管理簿とは?義務化の背景と作成方法を解説
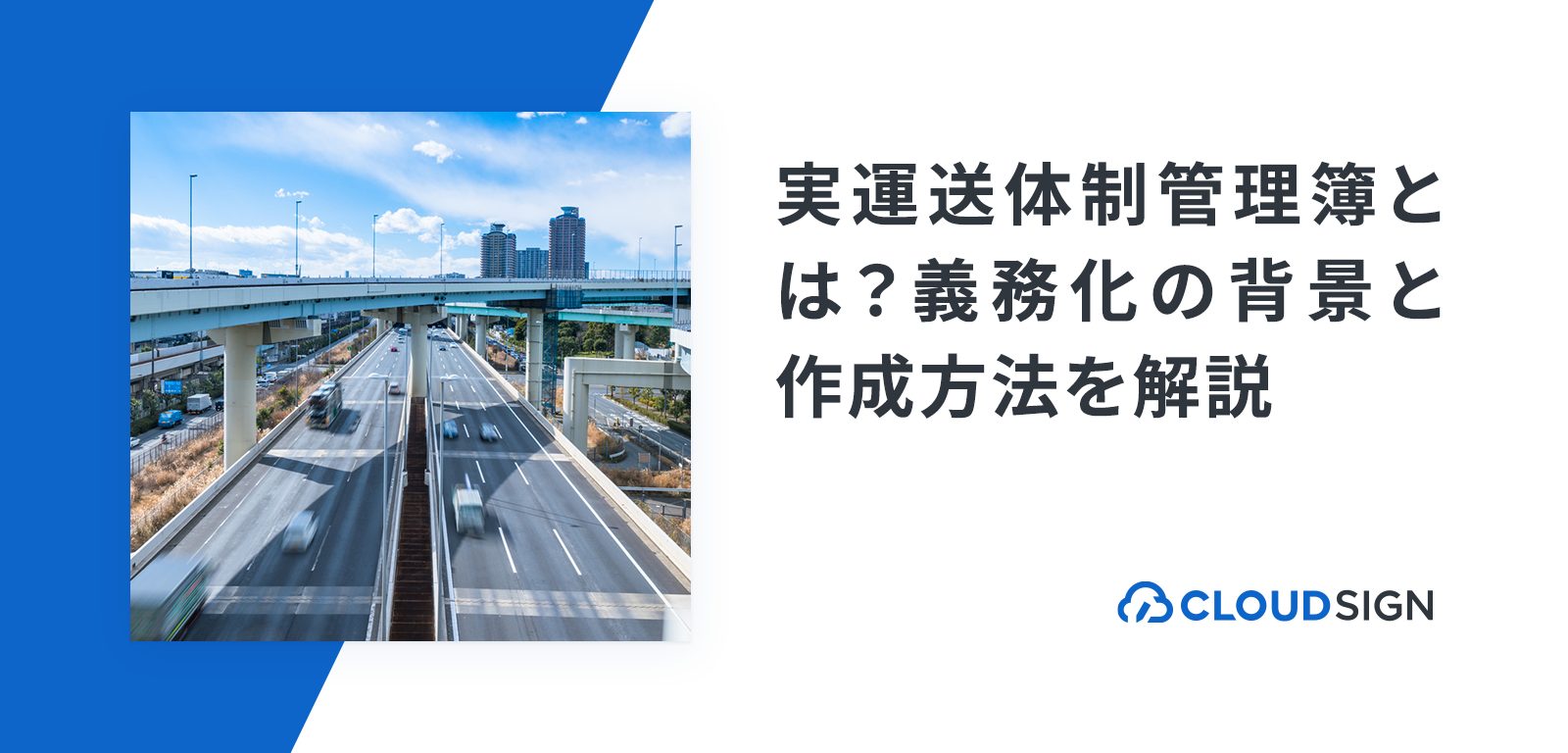
2024年(令和6年)の国会で「貨物自動車運送事業法」の一部改正法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律)が可決・成立し、2025年(令和7年)4月1日から、新たに「実運送体制管理簿」の作成が義務付けられました。物流事業における元請け事業者は、この新しい義務への対応方法を正確に理解する必要があります。
本記事では、実運送体制管理簿の基本的な内容から、その義務化の背景、改正法によって課せられた義務、具体的な作成方法、そして違反した場合のリスクについて詳しく解説します。元請け事業者の方はぜひこの機会に確認しておきましょう。
なお、クラウドサインでは弁護士監修の「運送委託基本契約書」ひな形をご用意しています。無料でダウンロード可能ですので、これから運送委託契約を締結する物流事業者の方はぜひ入手ください。
無料ダウンロード
実運送体制管理簿とは
実運送体制管理簿とは、荷主から運送を委託された元請け事業者が、実際に荷物を運ぶ「実運送事業者」の名称、請負階層、貨物の内容、運送区間などを記録する台帳のことです。
「実運送事業者」とは、貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項までに定められている次に掲げるものをいいます。軽自動車、ロープウェイ、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実運送事業者」には当たりません。
- 船舶運送事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)
- 航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)
- 鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者)
- 貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)
実運送体制管理簿の主な目的は、多重下請構造の可視化を図ることです。これにより、下請け構造の是正に向けた取り組みが進み、最終的に実運送事業者が収受する運賃・料金の適正化につながることが期待されています。
義務化の対象者
実運送体制管理簿の作成は、原則として、利用運送を行う元請け事業者(元請トラック事業者)に義務付けられています。そのため、元請事業者は真荷主から引き受けた貨物の運送について利用運送を行ったとき、貨物の運送ごとに実運送体制管理簿を作成する必要があります。2025年4月の改正貨物自動車運送事業法施行では、ここでいう元請け事業者とは、一般貨物自動車運送事業者として利用運送を行う一番上位の事業者を指します。
ただし、荷主から引き受けた貨物の運送をすべて自社で実運送する場合は、実運送体制管理簿の作成は不要です。
対象となる貨物
実運送体制管理簿の作成対象となるのは、1荷主の1運送依頼あたりの重量が1.5トン以上の貨物です。

この1.5トンの判断は、実運送する際の重量ではなく、真荷主から運送を引き受ける際の貨物の重量で判断します。
参考:実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化(国土交通省)
実運送体制管理簿の義務化の背景
実運送体制管理簿の作成義務化は、物流業界が抱える構造的な課題、とくに「輸送力不足への懸念(物流の2024年問題)」と「多重下請け構造」の是正を目的としています。
輸送力不足への懸念
物流業界では、慢性的なドライバー不足に加え、2024年4月以降の時間外労働規制(いわゆる「物流の2024年問題」)により、輸送能力の低下が懸念されています。
トラック輸送を現場で支えるトラックドライバーを確保するためには、働き方改革の実現により、他産業並みの労働時間への短縮と賃金水準の引上げによりトラックドライバーを魅力ある職業にしていくことが不可欠です。そこで、実運送事業者が収受する運賃・料金の適正化を図るために、実運送体制管理簿の作成が義務化されました。
多重下請け構造の是正
多重下請け構造が一般化している物流業界では、運送を委託する際、下層になるほど報酬が減額され、実運送事業者が労働に見合った適正な運賃を収受できないことが問題視されていました。
実運送体制管理簿の導入は、この多重下請構造の実態を明らかにし、是正に向けた取り組みを促進するための規制的措置としても導入されました。
貨物自動車運送事業法改正のポイント
前述の通り、実運送体制管理簿の作成を義務付けている法律は貨物自動車運送事業法です。多重下請構造を是正し、実運送事業者が適正な運賃を収受できるようにすることを目的として改正されました。
この改正は、令和6年(2024年)4月に成立し、令和7年(2025年)4月1日より施行されており、そのポイントは以下の通りです。
- 実運送体制管理簿の作成の義務付け: 物流事業者のうち、元請け事業者に対し、実運送事業者の名称や請負階層などを記載した実運送体制管理簿の作成が義務付けられました。
- 運送契約の書面・交付等の義務付け: 荷主・物流事業者に対し、役務の内容や対価を明記した運送契約の締結および書面交付が義務付けられました。
- 利用運送の適正化への義務付け: 物流事業者に対し、他の事業者への運送の利用(下請けへの依頼)の適正化に関する努力義務が課されました。また、一定以上の規模の物流事業者に対しては、運送利用管理者の選任・運送利用管理規程の作成が義務付けられました。
また、令和7年(2025年)4月の施行改正以降の動きとして、同年6月には実運送体制管理簿の作成義務を負う事業者の範囲が拡大されました。4月施行時には、最上位の一般貨物自動車運送事業者(元請け事業者)が対象でしたが、令和8年(2026年)度の施行からは「貨物利用運送事業者」も対象となります。
この改正法は2028年6月までの全面施行が予定されているため、詳しく知りたい方は下記記事もご一読ください。
実運送体制管理簿の作成方法と記載事項
実運送体制管理簿には、以下の事項を記載することが義務付けられています:
- 実運送の商号又は名称
- 実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
- 実運送事業者の請負階層(一次請け、二次請け等)
なお、運送区間や貨物の内容について、どの運送について記録されたものであるかが真荷主・元請け事業者ともに分かる状態であれば、記載の粒度は問われません(例:「東京~大阪」「雑貨」のような記載も可能です)。
必要な情報の通知フロー(情報通知の義務)
元請事業者が実運送体制管理簿を作成するためには、下請け事業者が持つ「実運送事業者情報」を把握する必要があります。このため、関係する各事業者に情報通知の義務が課されます。
- 元請事業者から委託先へ(下請情報)
利用運送を行う事業者は、委託先の事業者へ以下の「下請情報」の通知を行う義務があります
・元請事業者の連絡先
・真荷主の名称
・委託先の請負階層(次数)
また、元請け事業者は運送委託を行う際に、当該運送が管理簿の作成対象であることを確実に委託先へ伝達する必要があります。 - 実運送事業者から元請事業者へ(実運送事業者情報)
最終的に実運送を行う事業者は、元請事業者へ以下の「実運送事業者情報」を直接通知する義務があります
・自社の名称
・運送区間
・貨物の内容
・請負階層
元請事業者は、実運送事業者から通知されたこれらの情報(①~③の事項)を取りまとめ、管理簿に記録します。この情報のやり取りが非常に煩雑になるため、システム導入による簡易化が推奨されています。
作成の方式と保管期間
- 作成方式: 書類の様式に指定はありません。既存の配車表を活用するなど、事業者が取り組みやすい形で作成することが可能です。また、電磁的記録(デジタルデータ)での作成も認められています。
- 保管期間: 運送を完了した日から1年間、営業所で保存しなければなりません。デジタル上での保管は、スペース確保や検索の容易性から推奨されています。
- 作成時期: 作成期限について具体的な定めはありませんが、運送完了後、遅滞なく作成することが望ましいとされています。1ヶ月分をまとめて作成することも問題ありません。
真荷主による閲覧請求
荷主(真荷主)は、運送を委託した元請事業者に対して、業務取扱時間内であれば、いつでも実運送体制管理簿の閲覧・謄写(コピー)を請求することができます。これは、荷主が自社の荷物が適正な請負階層のもとに配送され、適正な運賃が請求されているかを把握するために重要です。
実運送体制管理簿の作成や備え付けに違反した際の罰則・リスク
実運送体制管理簿の作成や備え付けに関して、現時点では直接的な罰則は規定されていません。
しかし、実運送体制管理簿の作成や備え付けを怠った場合、トラック法第33条に基づき行政処分の対象となる可能性があります。
行政処分と「トラック・物流Gメン」による調査
行政処分は、まず注意や指導が行われ、これに従わない場合には業務停止等の処分が行われるものと想定されます。
また、行政処分の対象となることから、国土交通省の「トラック・物流Gメン」による是正指導を受けることになる可能性もあります。
情報通知義務違反のリスク
管理簿作成に必要な情報通知を怠った場合、その事業者に対して行政処分が行われる可能性があります。
元請けや一次請けなどの上流事業者が通知義務を怠り、下請け事業者が通知を受け取れなかった場合、下請け事業者に通知義務は課されません。この場合、通知義務を怠った上流事業者に対し、行政処分が下される可能性があります。
実運送事業者からの通知がなかった場合、その不備の原因を作った事業者が責任を問われ、行政処分の対象となる可能性があります。しかし、元請け事業者は、通知の有無にかかわらず、実運送事業者およびその請負階層を把握する努力をする必要があります。
まとめ
実運送体制管理簿の作成義務化は、物流領域の健全化、特にドライバーの所得改善と輸送力不足の解消に寄与する重要な措置です。
多くの配送案件を扱う事業者は、既存の配車表の活用や、電磁的記録での管理(デジタル化)を前提とし、下請け事業者との情報連携をシステム化するなど、法令遵守の体制を確実に運用していくことが重要になります。
また、実運送体制管理簿の作成・管理を滞りなく行うことは、法令遵守はもちろん、真荷主への説明責任を果たす上でも不可欠となりますので、改めて作成の要件を把握し、物流事業者、荷主企業・消費者、経済社会が「三方良し」となる社会を実現していきましょう。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
法律・法改正・制度の解説
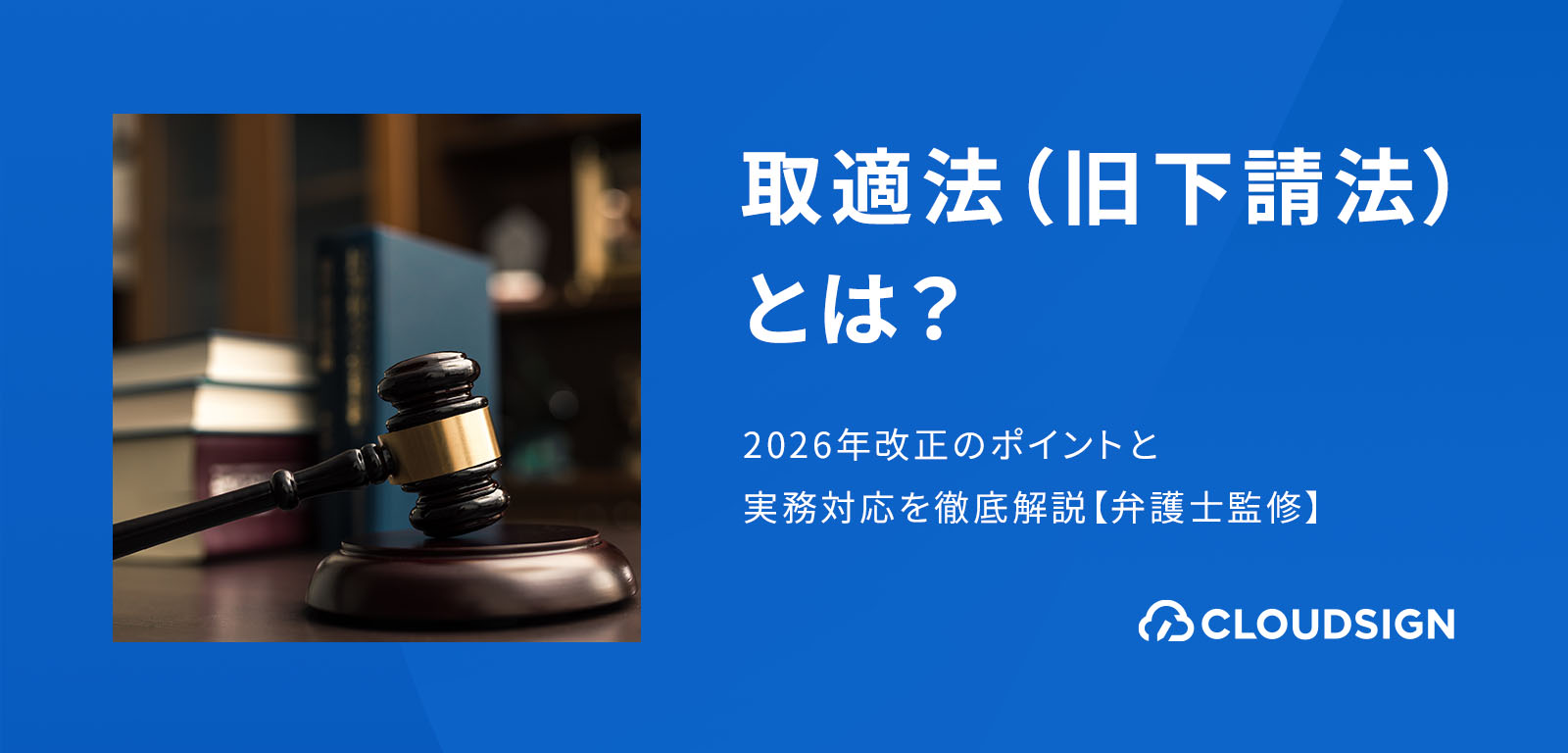
取適法(旧下請法)とは?2026年改正のポイントと実務対応を徹底解説【弁護士監修】
取適法(下請法) -
法律・法改正・制度の解説

【2025年6月公布】貨物自動車運送事業法改正のポイントは?運送事業者の対応事項も解説
取適法(下請法)物流業 -
法律・法改正・制度の解説

【2025年4月・2026年4月施行】改正物流効率化法とは?変更点や運送事業者の対応ポイントを解説
取適法(下請法)物流業 -
法律・法改正・制度の解説

フリーランス新法とは?主な義務や罰則、下請法との違い、相談窓口を解説【弁護士監修】
フリーランス新法 -
業務効率化の成功事例まとめ

Salesforceとクラウドサインを連携し、業務効率化に成功した事例5選
契約書管理インタビュークラウドサインの機能コスト削減電子契約の活用方法電子契約の導入電子契約のメリット業務効率化API連携 -
業務効率化の成功事例まとめ

kintoneとクラウドサインを連携し、業務効率化に成功した事例4選
契約書管理インタビュークラウドサインの機能コスト削減電子契約の活用方法電子契約の導入電子契約のメリット業務効率化API連携