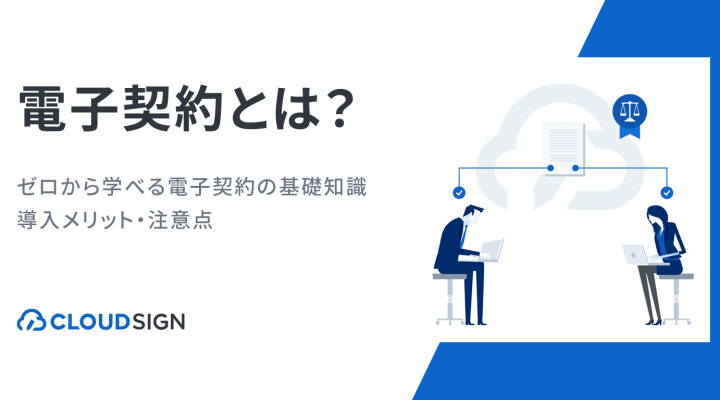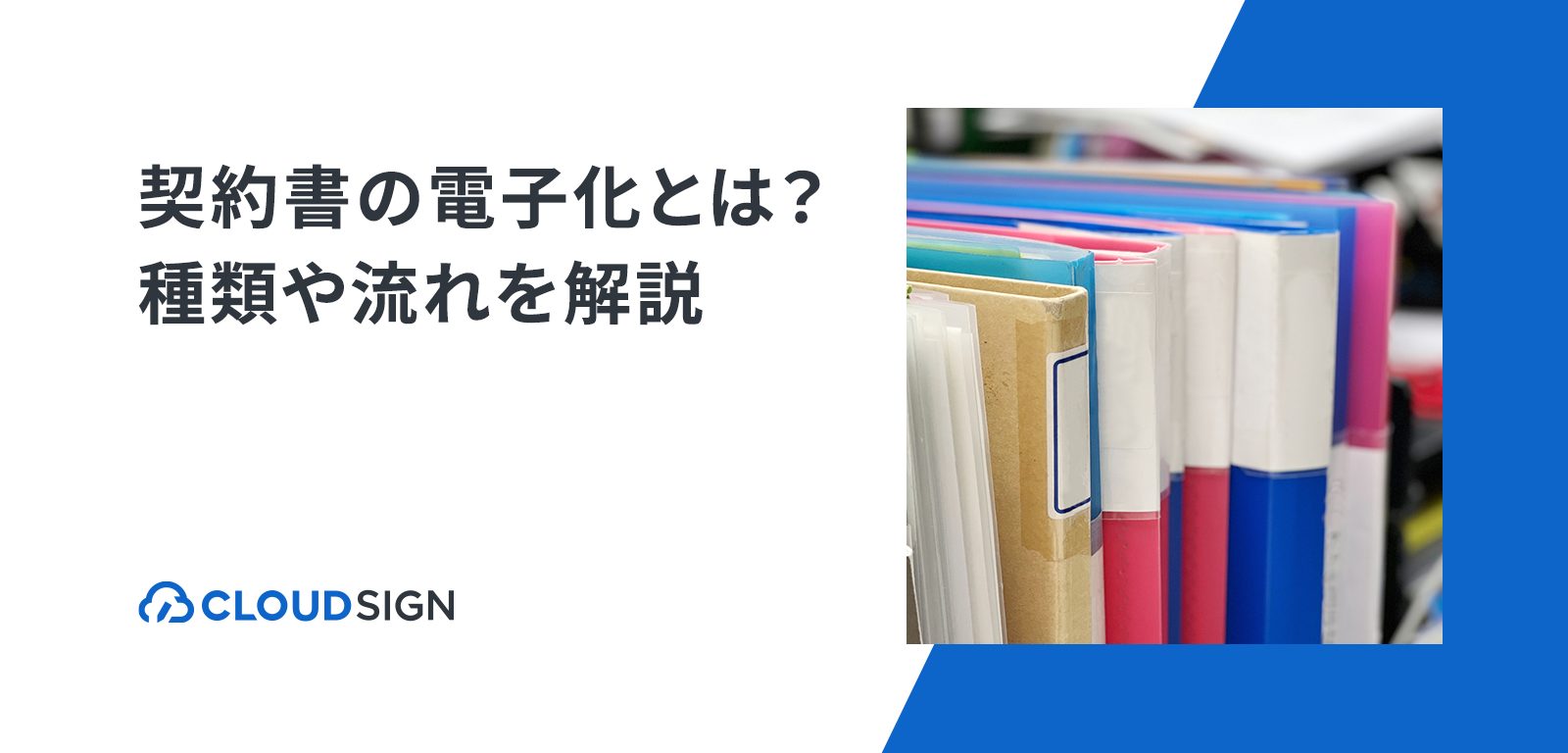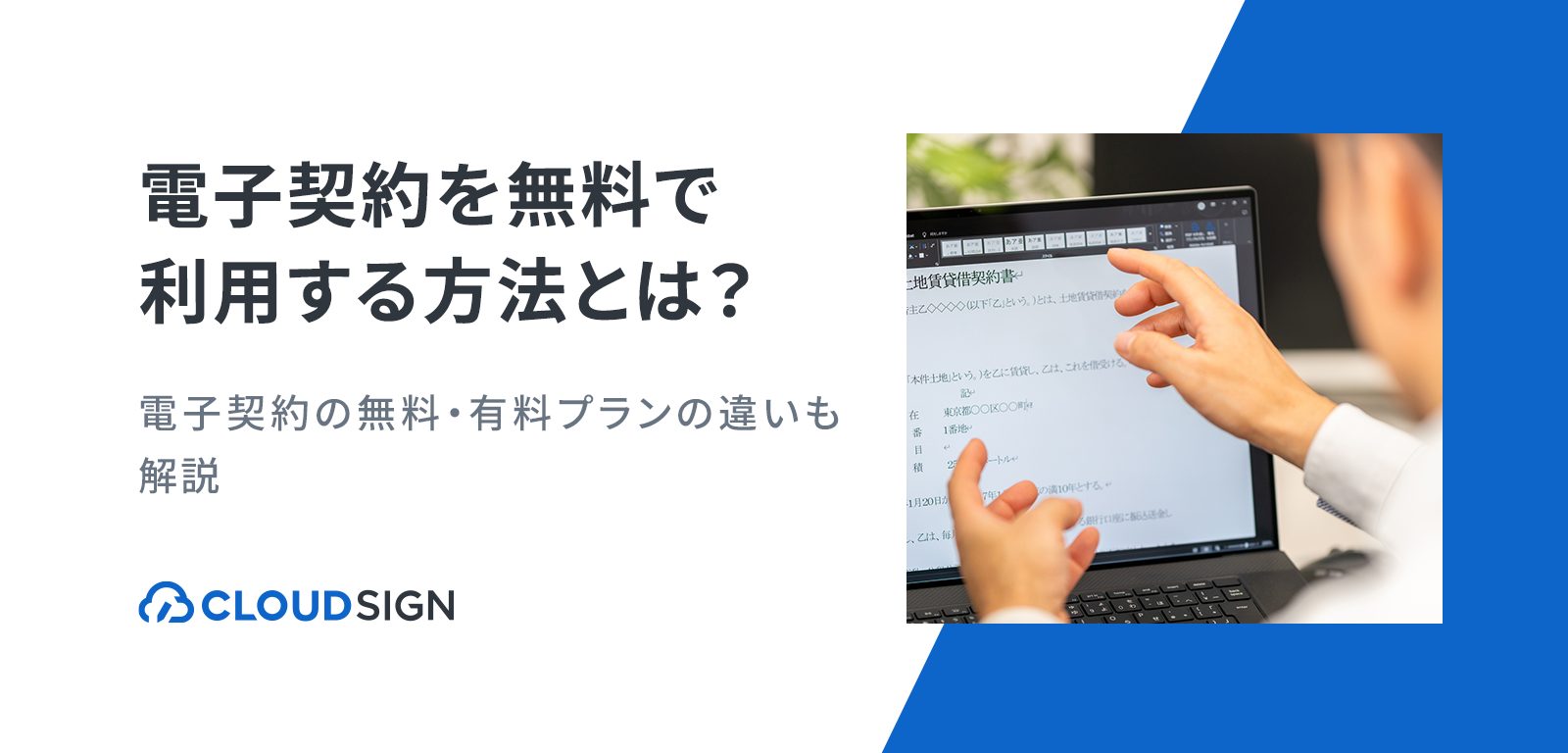EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説

EDI(Electronic Data Interchange)とは、電子データ交換のことです。具体的には、企業間で注文書や納品書、請求書などの取引情報をデジタルでやりとりする仕組みのことをいいます。紙を使わずにやり取りをするため、印刷や郵送の手間が省け、保管などのコスト削減にもつながります。
この記事では、EDIの基本から種類、導入メリット、注意点、電子契約との違いまでをわかりやすく解説します。
EDIの導入は、取引におけるペーパーレス化と迅速化を実現する大きな一歩です。そして、その取引の根幹をなす契約書自体も電子化することで、バックオフィス業務全体のDXが加速します。コンプライアンス強化やさらなるコスト削減を目指すなら、電子契約サービスの活用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。電子契約の基礎知識やメリットなどをまとめた資料をご用意しておりますので、ご興味のある方は無料でダウンロードして活用してみてください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)EDIとは
EDIは、企業同士の取引に関する情報を、紙ではなくコンピュータを通じてやりとりする仕組みです。たとえば、これまでFAXや郵送で送っていた注文書や請求書などを、データとして直接やりとりします。
これによって、作業の手間やコストが減り、やりとりのスピードも格段にアップします。
もともとは大企業を中心に使われてきましたが、最近では中小企業でも導入が進んでおり、さまざまな業界でEDIの活用が広がってきています。
EDIでやりとりされる文書
EDIでは、企業間のやりとりに使われるさまざまな書類をデータで送ります。以下、代表的なものを紹介します。
【注文書】
注文書は、取引先に商品やサービスを依頼する際に使います。「いつ・何を・どれだけ」注文するかを明記することで、発注ミスや納期トラブルを防げます。
仕入れや部品発注など、日常的な企業間取引でよく使われるのが特徴です。
【納品書】
納品書は、注文された商品を取引先に届けたときに提出する書類です。各商品をどれだけ納品したかが記載されており、受取側は納品内容を確認する際に使います。納品時に商品と一緒に渡されるのが一般的です。
【請求書】
請求書は、取引が完了したあとに、代金を請求するために使います。納品した内容や金額、支払期限などを明記し、取引先に「いくら支払ってください」と正式に伝える書類です。
このほかにも、出荷の予定を知らせる書類や、支払いを通知するデータなど、取引に必要な情報がいろいろあります。書類の電子化により作業が効率化され、ミスも減少します。
EDIに関連する言葉の意味
EDIにはさまざまな接続方式やシステムがあります。ここでは、代表的な関連用語について、基本的な意味や違いをわかりやすく解説します。
レガシーEDI
レガシーEDIは、専用回線を使って企業間でデータをやりとりする従来型の方式です。通信が安定しており、高い信頼性を誇ったレガシーEDIですが、その基盤である電話網(PSTN)の設備が老朽化し、IP網へ切り替わることが決定しました。これにより、NTT東日本・西日本はISDN回線のデータ通信サービス(INSネット ディジタル通信モード)を2024年1月に終了し、従来のレガシーEDIの利用が難しくなりました。
これにより、レガシーEDIを利用していた企業が、レガシーEDIからインターネット回線を利用するWeb-EDIなどの新しいシステムへ移行を迫られることをEDIにおける2024年問題と呼んでいます。
WebEDI
WebEDIは、インターネットを使ってWebブラウザ上でEDIを行う方式です。
専用ソフトが不要で、初期費用が抑えられるため、中小企業でも導入しやすいのが特徴です。ただし、手動操作が多く、大量の取引には不向きな面もあります。
メールEDI
メールEDIは、取引データをメールに添付して送受信する方法です。既存のメール環境を使えるため手軽に始められますが、セキュリティや誤送信のリスクがある点には注意が必要です。取引量が少ない企業間でのやりとりに適しています。
EOS
EOS(Electronic Ordering System)は、主に流通業界で使われる発注専用の仕組みです。スーパーやドラッグストアが、取引先に商品を自動的に発注する際などに利用されます。EDIの一種であり、商品補充や在庫管理の効率化に役立ちます。
EDIの種類
EDIには、接続方法や運用体制の違いによっていくつかの種類があります。ここでは「個別EDI・標準EDI・業界VAN」という代表的な3つのタイプについて解説します。
個別EDI
個別EDIとは、取引先ごとに個別に仕様を決めてシステムを構築する仕組みのEDIです。
柔軟なカスタマイズができる半面、接続先ごとに異なる仕様へ対応する必要があるため、開発や保守の負担が大きくなります。複数社と取引する企業の場合、逆に管理が大変になる可能性があります。
標準EDI
標準EDIは、業界や業種で共通の通信仕様やデータ形式を用いて、複数の企業間でEDIを行う方式です。個別に設定を調整する必要がないため、導入や運用の手間が抑えられ、複数の取引先と効率的にデータ連携できます。
業界VAN
業界VANとは、同じ業界の会社どうしが共通のネットワークを使ってEDIを行う仕組みです。
参加企業は、VANと呼ばれるサービス事業者を通じてデータをやりとりするため、取引先ごとに個別の設定をする必要がなくなります。データの形式や通信の仕方が統一されているので、効率よく取引できるのが特長です。
EDIが利用されている主な業界
EDIは多くの業界で活用されています。特に物流・製造・金融・小売などでは特に利用が多いため、それぞれの特徴を紹介します。
物流業
物流業では、出荷指示書や配送依頼書などをEDIでやりとりすることで、輸送管理がスムーズになります。具体的には、メーカーや小売店からの出荷依頼を受けて、物流会社がすぐに対応できるようになるなどです。
製造業
製造業では、部品の発注や納期の確認、生産計画の共有などにEDIが活用されています。メーカーや組立業者など、サプライチェーン全体で情報を共有できるため、タイムリーな生産や在庫管理が可能になります。
特に自動車や家電などの分野では、取引先が多く複雑なため、EDIによる自動化が大きな効果を発揮します。
金融業
金融業では、企業が取引先とお金のやりとりをする際に、EDIが使われています。たとえば、振込データと一緒に「何の支払いか」の情報も送ることで、受け取った側がすぐに内容を確認できるようになります。
これにより、経理担当者が一つひとつ確認する手間が減り、入金のチェック作業が楽になります。
小売業
小売業では、商品の注文や納品、在庫管理などを取引先とやりとりする際にEDIが広く使われています。たとえばスーパーが売れた分だけ商品を自動発注する仕組みなど、日々の仕入れ業務に欠かせません。
取引先ごとに形式が異なると管理が煩雑になりますが、EDIで統一することで在庫確認や仕入れ業務が効率化されます。
EDIを導入するメリット
EDIを導入すると、仕事の流れがスムーズになったり、ミスが減ったりと、さまざまなメリットがあります。ここでは、EDIの導入で得られる主なメリットを紹介します。
業務効率の向上
紙やFAXで行っていた注文や請求のやりとりがEDIで自動化され、業務のスピードが大幅に向上します。手作業で入力したり確認したりする手間が減るため、作業がシンプルになります。
特に取引が多い会社では、毎日の業務が大幅に効率化され、時間にゆとりが生まれることも少なくありません。
コストの削減
EDIを使えば、紙を使った書類の印刷や郵送にかかるお金が必要なくなります。また、手作業での入力やチェックの手間も減るため、人手や時間にかかるコストも自然と少なくなります。
紛失リスクやトラブルも起こりにくくなるため、管理部の負担を全体的に減らすことができます。
人的ミスの軽減
人の手でデータを入力したり、確認したりする作業では、どうしても入力ミスや確認もれが起こりやすくなります。EDIを導入すれば、データが自動でやりとりされるため、そういったミスは起こりにくくなるでしょう。
結果として、取引先とのトラブルが減り、業務に集中しやすくなります。
EDIを導入する際の注意点
EDIはとても便利ですが、導入した日からすぐにすべてがうまくいくわけではありません。実際に運用するには、準備や調整なども必要です。EDIを導入する際は、次の注意点も把握しておきましょう。
【専用のシステムが必要】
EDIを使うには、データのやりとりをするための専用システムやソフトが必要になります。
そのため、最初にある程度の導入費用や社内での環境整備が必要です。ITに不慣れな企業では、操作に慣れるまで時間がかかることもあるので、運用ルールやサポート体制も考えておくと安心です。
【企業間での協議が必要】
EDIは一社だけでは使えません。取引先とEDIの活用を事前に協議しておく必要があります。円滑に運用するには、事前のコミュニケーションが重要です。
【取引効率が下がる場合もある】
EDIは便利な反面、すべての取引に向いているわけではありません。たとえば、相手企業の対応が遅い場合や、システムが合っていない場合は、かえってやりとりがスムーズにいかなくなることもあります。
また、少量の取引にEDIを使うと、コストや手間の方が大きくなるケースもあるため注意しましょう。
代表的なEDIツール3選
これからEDI導入を検討している方のために、おすすめのものを3つ紹介します。
【BtoBプラットフォーム(インフォマート)】
BtoBプラットフォームは、インフォマートが提供するクラウド型のEDIサービスで、主に飲食・小売・卸業などで使われています。画面が見やすく操作も簡単なので、ITが苦手な方でも使いやすいのが特長です。月額数千円から利用でき、問い合わせへの対応も丁寧と評判です。取引先も多く、導入がスムーズに進みやすい点もメリットです。
【EXtelligence EDIFAS(富士通)】
EDIFAS(エディファス)は、富士通が提供するクラウド型EDIで、中小企業でも使いやすいように設計されています。Webブラウザから操作でき、シンプルな画面で初めてでもわかりやすいのが魅力です。
月額料金も比較的安く、必要に応じてサポートスタッフのサポートを受けられる体制も整っています。取引先との接続もスムーズです。
【EcoChange(グローバルワイズ)】
EcoChange(エコチェンジ)は、中小企業向けに作られた使いやすいクラウド型のEDIサービスです。注文や納品、請求などのやりとりをすべてオンラインで行なえるため、紙の書類やFAXを使わずにすみ、業務の手間がぐっと減ります。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しており、法令対応の面でも安心です。
EDIと電子契約の違い
EDIと電子契約は、どちらも企業間の取引を電子化し効率化する仕組みですが、その目的や扱う文書などが異なります。両者の違いを正しく理解することで、自社のデジタル化においてどちらを導入すべきか、あるいは両方をどう使い分けるべきかを判断できます。
ここではEDIと電子契約の違いについて解説します。
目的の違い
EDIは企業どうしが取引に必要な情報をやりとりするための仕組みで、主に業務の効率化を目的としています。企業間で統一されたフォーマットの取引データをシステム間で自動的に交換することで、データ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎ、業務全体のスピードアップを図る役割を担っています。
電子契約は、契約書の作成・締結・保管をデジタル化 し、契約業務の効率化を図る仕組みです。電子契約の目的は、契約締結という法律行為を電子的に完結させ、その証拠を残すことです。紙の契約書への署名や押印の代わりに、電子署名とタイムスタンプを用いて契約内容への合意を証明し、契約書の作成・送付・保管にかかる手間とコストを削減する役割を担っています。
対象・扱う文書の違い
EDIは実務向け、電子契約は法的な意思表示向け といった違いがあります。
EDIでは、主に受発注、出荷、検収、請求、支払といった商取引の一連の流れで発生する帳票をデータとして扱います。主な文書としては、納品書、受領書、請求書、支払通知書などです。
電子契約でも注文書や納品書が扱われるケースはありますが、メインとなるのは契約書や合意書など、法的な合意を交わす文書です。当事者間の権利や義務を法的に証明する必要がある重要な文書を扱うことが多く、主な文書としては業務委託契約書、売買契約書、秘密保持契約書(NDA)、請書、発注書、利用申込書などです。
主な導入部門の違い
EDIは主に、営業・物流・購買・経理といった日々の業務を担当する部門で使われます。一方、電子契約は法務部門や総務部門、または経営層が中心となって導入・運用されることが多いです。
利用シーンの違い
EDIは、商品の注文や納品、請求といった継続的なやりとりに使われます。一方、電子契約は新しい契約を結ぶときや、条件変更の合意を取り交わす場面で使われます。日々使うものなのか、契約時に使うものなのかという点に違いがあります。
電子契約システムは必要?EDIだけ導入しておけばOK?
EDIを導入していても、契約そのものを電子化できるわけではありません。注文や請求といった実務の効率化はEDIが得意ですが、契約書の締結や法的な証明には電子契約システムが必要です。
両方を使い分けることで、よりスムーズな業務運用が可能になります。
まとめ
EDI(電子データ交換)は、企業間の注文書や請求書などをデータでやりとりする仕組みです。紙やFAXを使わずにすむため、業務の効率化やミスの防止、コスト削減につながります。特に、物流・製造・金融・小売など、日々の取引が多い業界で利用されています。
導入にあたって、取引先との調整が必要ですが、使いやすさやサポート体制に優れたサービスを選ぶことで、スムーズな運用が可能になります。
EDIによって受発注や請求業務が効率化されるように、取引の基本となる「契約」も電子化することで、業務プロセスはさらにスムーズになります。取引全体をデジタルで完結させたい方は、電子契約サービスの導入もあわせてご検討ください。
無料ダウンロード
この記事を書いたライター