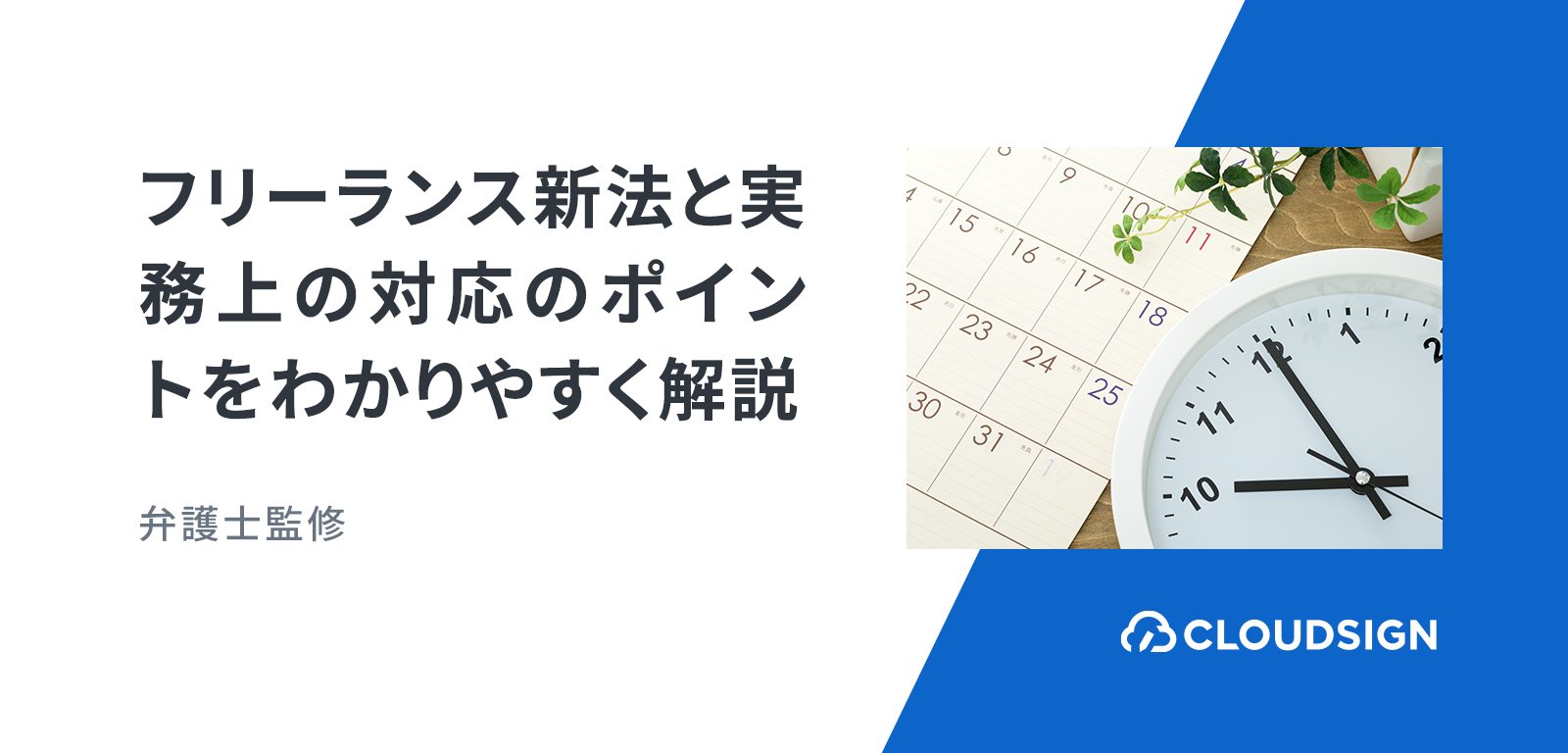フリーランス新法とは?主な義務や罰則、下請法との違い、相談窓口を解説【弁護士監修】

働き方の多様化が進む現代において、フリーランスとして活躍する人々が増えています。その一方で、発注者との力関係の不均衡から、不利な取引条件を強いられたり、報酬の支払いが遅延したりといったトラブルも少なくありませんでした。こうした背景を踏まえ、フリーランスがより安心して働ける環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス新法」(またはフリーランス保護新法)が制定されました。
本記事では、2024年11月1日から施行されたこの法律について、個人事業主や企業担当者の方々にも分かりやすく、その目的、対象者、具体的な義務や禁止事項、違反した場合の罰則、そして下請法との違いなどを徹底的に解説します。
なお、フリーランス新法で義務付けられている取引条件の明示義務を履行するためにも電子契約は有効です。
電子契約において、本人による適切な電子署名が行われた電子文書は、「電子署名法第3条」に基づき、紙の契約書と同様に法的な証拠力が認められています。具体的には、電子署名が本人のものである限り、その電子文書は真正に成立したものと推定されます。
これにより、フリーランスと発注者間の取引条件を明確かつ法的に有効な形で記録・保管することが可能となり、後のトラブル防止に繋がります。
電子契約についてもう少し詳しく知りたい方や導入を検討している方に向け、無料の資料をご用意しております。電子契約の基礎、始め方を知りたい方は下記資料を無料でダウンロードしてみてください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)目次
フリーランス新法の基礎知識
まずはじめに、フリーランス新法が可決され、施行されるまでの経緯、目的や背景の解説をします。フリーランス側も発注事業者側も、この新しい法律の内容を正しく理解し、適切に対応していくことが求められているため、詳細の内容に移る前に理解を深めておきましょう。
2024年に施行されたフリーランス新法とは
フリーランス新法とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、その主な目的は、業務委託の相手方であるフリーランスを保護し、事業者間の取引の適正化とフリーランスの就業環境の整備を図ることにあります。
フリーランス新法は、2023年4月28日に国会で可決・成立、同年5月12日に公布され、2024年11月1日から実際に施行されました。この施行日を境に、フリーランスと取引を行う企業は、新法に定められた義務を遵守し、禁止事項に抵触しないよう注意を払う必要が生じました。
施行まで約1年半の期間が設けられた背景には、企業が新しい法律の要求事項に対応するための準備期間を確保する意図があったことが考えられます。企業側が講じるべき対策は、契約書の見直し、社内体制の整備、従業員への周知徹底など多岐にわたるため、この準備期間が設けられたということです。
フリーランス新法の目的・背景
近年、日本国内におけるフリーランスの数は増加傾向にあり、内閣官房の試算によれば約462万人にものぼるとされています。しかし、フリーランスは企業などの発注者に対して立場が弱くなりがちで、契約条件の不明確さ、報酬の支払い遅延や一方的な減額といったトラブルが後を絶ちませんでした。実際に、「令和4年度フリーランス実態調査」の結果によると、2割強が取引先とのトラブルを経験しており、その内容として最も多かったのが「報酬の支払いが遅れた・期日に支払われなかった」(36.1%)、次いで「あらかじめ定めた報酬を減額された」(21.4%)でした。さらに深刻なのは、トラブルが生じた際に約6割のフリーランスが「そのまま受け入れた」または「交渉したが改善されないまま受け入れた」と回答しており、事実上の泣き寝入りを強いられている状況が浮き彫りになりました。
そのため、フリーランスが安心してその能力を発揮し、創造的な活動に専念できる環境を整えることが、発注側の利益、フリーランスの所得向上、ひいては経済全体の好循環に繋がると考えられており、フリーランス新法は、まさにこのような問題意識から生まれたものです。フリーランスという働き方を選択した人々が公正な条件のもとで安定的に業務に従事できるよう、法的な基盤を整備することを意図しています。
参照:第3章 成長と分配の好循環実現に向けた家計部門の課題(第1節)、令和4年度フリーランス実態調査結果
フリーランス新法の対象・適用範囲
フリーランス新法を理解するうえで、誰がこの法律の保護対象となる「フリーランス」で、誰がこの法律を守る義務を負う「発注事業者」となるのかを把握しておくことが大切です。ここではフリーランス新法における対象者・適用範囲について詳しく解説します。
法律上の「フリーランス(特定受託事業者)」とは?
フリーランス新法では、保護の対象となるフリーランスを「特定受託事業者」と定義しています。具体的には、以下のいずれかに該当する事業者を指します。
- 個人であって、従業員を使用しないもの
- 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役など)がおらず、かつ、従業員を使用しないもの(いわゆる「一人社長」の会社などが該当します)
フリーランス新法第2条では以下のように定義されています。
第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの2 この法律において「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である前項第一号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第二号に掲げる法人の代表者をいう。
3 この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。
一 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。
二 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。4 前項第一号の「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一 プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの5 この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいう。
6 この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用するもの
二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの7 この法律において「報酬」とは、業務委託事業者が業務委託をした場合に特定受託事業者の給付(第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。第五条第一項第一号及び第三号並びに第八条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。
「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない、と記載されており、基本的には、労働契約を締結している者がこれに該当するため、パートタイマーやアルバイトであっても、労働契約を結んでいれば「従業員」となります。
この定義からわかるように、フリーランス新法が対象とするのは、デザイナー、ライター、エンジニア、コンサルタント、カメラマン、イラストレーター、通訳、家庭教師、配達員、インストラクターなど、特定の業種に限定されず、従業員を雇わずに個人で事業を営んでいる幅広い層です。
重要なのは「従業員を使用していない」という点であり、これにより、企業に対して交渉力が弱い立場にある個人や極めて小規模な事業者を重点的に保護しようとする法の意図が読み取れます。フリーランス自身が、自分がこの「特定受託事業者」に該当するかどうかを認識しておくことは、法律による保護を適切に受けるための第一歩となります。
参照:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
発注事業者(業務委託事業者・特定業務委託事業者)とは?
フリーランス新法では、フリーランスに業務を委託する側の事業者を「業務委託事業者」と呼びます。そして、この業務委託事業者のうち、従業員を使用している事業者(個人事業主または法人)を特に「特定業務委託事業者」と定義しています。
フリーランス新法が定める義務の多くは、この「特定業務委託事業者」に対して課せられます。例えば、後述する報酬の60日以内支払いや7つの禁止行為、育児介護等への配慮義務などは、主に特定業務委託事業者が遵守すべき事項です。
一方で、従業員を使用していない個人事業主や一人社長が、他のフリーランス(特定受託事業者)に業務を委託する場合、その発注者は「業務委託事業者」には該当しますが、「特定業務委託事業者」には該当しません。この場合でも、取引条件の明示義務(後述の義務1)といった基本的な義務は負うことになりますが、特定業務委託事業者に課されるような広範な義務の対象とはならない場合があります。
このように、フリーランス新法では発注事業者に対しても責任の階層を設けています。すべての業務委託事業者は取引の透明性を確保する基本的な義務を負いますが、従業員を抱える(=相対的に交渉力が高く、体制整備の能力も高いと見なされる)特定業務委託事業者には、より広範かつ厳格な義務と禁止事項が課されることになります。企業担当者は、自社がどちらのカテゴリーに該当するのかを正確に理解し、求められる義務を把握する必要があります。
発注事業者に課される主な義務と禁止事項
フリーランス新法は、発注事業者に対して、フリーランスとの取引を適正化し、その就業環境を整備するための具体的な義務と禁止事項を定めています。特に「特定業務委託事業者」(従業員を使用する発注事業者)には、より多くの責任が課されます。
具体的には下記の義務および禁止事項が挙げられます。
- 義務1:取引条件の明確な提示
- 義務2:報酬の適切な支払い
- 義務3:禁止行為
- 義務4:募集情報の的確な表示
- 義務5:育児介護等と業務の両立への配慮
- 義務6:ハラスメント対策
- 義務7:契約の中途解除等の事前予告
それぞれの項目を確認しておきましょう。
参照:フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタート
義務1:取引条件の明確な提示
発注事業者は、フリーランス(特定受託事業者)に業務を委託した場合、直ちに、以下の取引条件を書面または電磁的方法(電子メール、SNSのメッセージ、チャットツールなど)で明示しなければなりません。口頭での明示は認められず、必ず記録に残る形で行う必要があります。
明示すべき具体的な内容は以下の9項目です。
- 発注事業者及びフリーランスの氏名または名称
- 業務委託をした日
- フリーランスが行う給付の内容(業務内容)
- フリーランスの給付を受領する期日(納期)または役務の提供を受ける期日
- フリーランスの給付を受領する場所または役務の提供を受ける場所
- フリーランスの給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
- 報酬の額
- 報酬の支払期日
- その他(報酬を現金以外の方法で支払う場合の支払方法に関する事項など、公正取引委員会規則・厚生労働省令で定める事項)
この義務は、フリーランスとの間で「言った、言わない」のトラブルを防ぎ、契約内容の透明性を確保するための基本中の基本です。従来、口頭での依頼やあいまいな条件での取引がトラブルの一因となっていましたが、この法律により、発注の初期段階で双方が合意内容を明確に確認することが求められます。
電子メールやSNSのメッセージといった電磁的方法が認められている点は、現代の迅速なビジネスコミュニケーションの実態を反映したものですが、注意も必要です。これらの方法は手軽である反面、正式な契約書に比べて記録の保存や管理が煩雑になる可能性があります。
発注者・フリーランス双方が、これらのやり取りを契約の証拠として確実に保存・整理しておくことが、後のトラブル防止のために重要となります。
なお、フリーランス新法は電子契約サービスの利用は認めており(義務化はしていません)、同法が定める「取引条件の明示義務」を確実かつ効率的に行い、後のトラブルを防ぐための証拠能力の高い手段として、電子契約サービスの必要性は非常に高いものとなります。
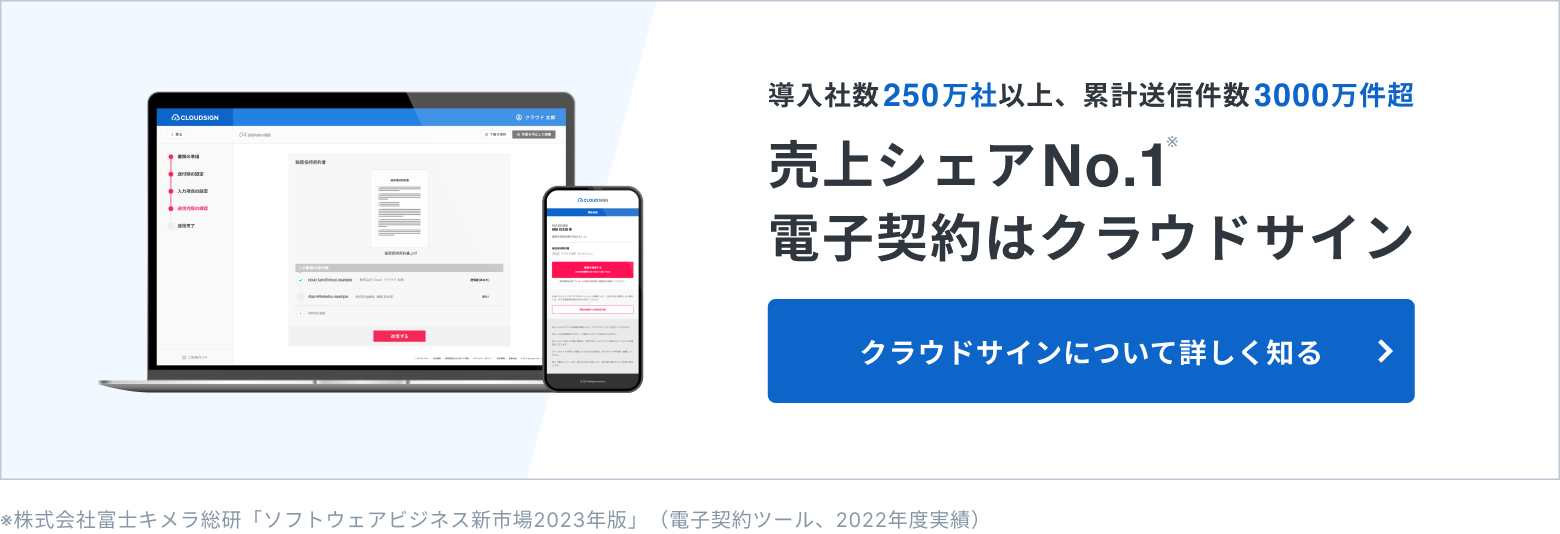
義務2:報酬の適切な支払い
特定業務委託事業者は、フリーランス(特定受託事業者)から給付(成果物やサービス)を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に報酬の支払期日を定め、その期日までに支払わなければなりません。
例えば、フリーランスとの取引で一般的な「月末締め翌々月15日払い」といった支払サイトは、場合によっては納品日から75日程度の期間が空く可能性があり、この60日ルールに違反する恐れがあります。
また、発注事業者が元請けとして受けた業務をフリーランスに再委託した場合には、例外規定があります。元委託者(最初の発注者)から業務委託事業者が支払いを受けた日から起算して30日以内のできる限り短い期間内に、フリーランスへの支払期日を定めることができます。ただし、この例外を適用するには、フリーランスへの取引条件明示の際に、再委託である旨や元委託者の名称、元委託業務の支払期日などを追加で明示する必要があります。
「できる限り短い期間内で」という文言が付されている点は重要です。これは、単に60日という上限を守ればよいというわけではなく、発注事業者の支払いプロセスが許容する範囲で、可能な限り速やかに支払う努力を求めるものです。これは、フリーランスが長年抱えてきた支払い遅延という大きな問題を改善することを意図したものです。
義務3:禁止行為
特定業務委託事業者(従業員を使用する発注事業者)は、フリーランス(特定受託事業者)との契約期間が1か月以上にわたる業務委託(契約更新により通算して1か月以上となる場合を含む。この期間は政令で定められています)に関して、以下の7つの行為を行うことが禁止されています。これらの行為は、フリーランスの正当な利益を不当に害する典型的なものとして法律で具体的に列挙されています。
- 受領拒否:フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、発注した物品や情報成果物の受領を拒むこと。発注を取り消したり、納期を一方的に延期して納品物を受け取らない場合も該当します。
- 報酬の減額:フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、あらかじめ定めた報酬の額を発注後に減額すること。協賛金の名目で差し引くなど、名目や金額の多寡を問いません。
- 不当な返品:フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、受領した物品等を返品すること。
- 買いたたき:通常支払われる対価(市場価格など)に比べて著しく低い報酬の額を不当に定めること。
- 購入・利用強制:正当な理由がないのに、自己の指定する物(製品、原材料など)の購入や役務(保険、リースなど)の利用を強制すること。
- 不当な経済上の利益提供要求:自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を不当に提供させることにより、フリーランスの利益を不当に害すること。
- 不当な給付内容の変更・やり直し要求:フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、給付の内容を変更させたり、受領後にやり直しをさせることにより、フリーランスの利益を不当に害すること(その際にフリーランスが負担する費用を発注事業者が負担しない場合など)。
これらの禁止行為は、フリーランスが直面しがちな不公正な取引慣行に直接対処するものです。契約期間が「1か月以上」という条件が付されている点は注意が必要です。これは、ごく短期間の単発的な業務委託については、これらの特定の禁止行為の直接的な適用対象外となる可能性を示唆しています。ただし、そのような場合でも、下請法(適用される場合)や一般の契約法の原則に基づき、不当な行為が問題視される可能性は残ります。
義務4:募集情報の的確な表示
特定業務委託事業者は、フリーランス(特定受託事業者)を募集する際に、広告やウェブサイト、SNS、クラウドソーシングサイトなどで情報を提供する場合は、その内容を虚偽なく、誤解を招くことのないよう、正確かつ最新の状態に保つ義務があります。
具体的に禁止される表示としては、以下のようなものが挙げられます。
- 虚偽表示:意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示する、実際に募集を行う企業とは別の企業名で募集する、など。
- 誤解を生じさせる表示:報酬額が確約されているかのように表示する(「報酬額の一例」といった注釈がない場合など)、募集が終了しているにもかかわらず情報を掲載し続ける、など。
- 必要な情報の欠如:募集を行う者の氏名・名称、住所・連絡先、業務の内容、業務に従事する場所、報酬といった募集に際してフリーランスが知るべき基本的な情報が欠けている場合も、誤解を生じさせる表示に該当する可能性があります。
これらは、フリーランスが不正確な情報や誤解を招く情報に基づいて不利な契約を結んでしまうことを防ぐためのものです。フリーランスが仕事を探す際に、適切な情報に基づいて判断できるよう保護する狙いがあり、フリーランスが仕事の「買い手」として情報弱者になりやすい状況を考慮した措置と言えるでしょう。
義務5:育児介護等と業務の両立への配慮
特定業務委託事業者は、フリーランスとの契約期間が6か月以上にわたる場合(契約更新により通算して6か月以上となる場合を含む)、そのフリーランスから申し出があったときには、育児や介護と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
配慮の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 妊婦健診のための打ち合わせ時間の調整
- 育児や介護のための在宅勤務やオンラインでの業務遂行の許可
- 子供の急な病気などによる作業時間の確保が難しい場合の納期調整
- 出産に伴う転居の際の成果物の郵送やオンラインでの納品許可
契約期間が6か月未満の場合であっても、同様の配慮をするよう努めなければならないとされています(努力義務)。
義務6:ハラスメント対策
特定業務委託事業者は、フリーランス(特定受託業務従事者)が業務委託に関連してハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントなど)を受けることがないよう、相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。
具体的には、以下のような措置が求められます。
- ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確にし、それをフリーランスにも周知・啓発する。
- ハラスメントに関する相談窓口を設置し、フリーランスに周知する。
- 相談があった場合に、迅速かつ適切に対応できる体制を整備する(事実関係の確認、被害者・加害者への適切な措置、再発防止策など)。
相談したことや事実行為の確認に協力したことなどを理由として、フリーランスに不利益な取り扱いをしない。
これは、従来の「独立した事業者」としてのフリーランスと発注者の関係性に、ある種の社会的配慮の側面を導入するものです。特に長期間にわたり継続的に業務を行うフリーランスに対しては、単なる取引の公正さだけでなく、人間としての尊厳や生活との調和にも目を向けるよう発注事業者に求めている点が特徴的です。
義務7:契約の中途解除等の事前予告
特定業務委託事業者は、フリーランス(特定受託事業者)との契約期間が6か月以上にわたる業務委託契約(契約更新により通算して6か月以上となる場合を含む)について、契約期間の途中で解除する場合や、契約期間満了後に更新しない場合には、原則として、その少なくとも30日前までに、フリーランスに対してその旨を書面または電磁的方法で予告しなければなりません。
さらに、フリーランスから予告期間中に解除または更新しない理由について開示を求められた場合には、遅滞なくその理由を開示する義務も負います。ただし、フリーランス側に契約違反などの帰責事由がある場合や、天災などやむを得ない事由により予告が困難な場合は、この予告義務の例外となることがあります。
これらは、フリーランスが突然の契約終了によって収入を絶たれるリスクを軽減し、次の仕事を探すための時間的猶予を与えることを目的としています。また、理由の開示を求める権利をフリーランスに与えることで、発注事業者側の一方的で不透明な契約終了を防ぎ、より公正な関係構築を促す効果が期待されます。単に30日前に通知すればよいというだけでなく、理由の開示まで求められる可能性がある点は、発注事業者が契約終了の判断をより慎重に行う動機付けとなるでしょう。
発注事業者の主な義務・禁止事項と適用条件のまとめ
フリーランス新法における発注事業者の主な義務と禁止事項、そしてそれらがどのような場合に適用されるのかを一覧表にまとめました。
| 項目 | 内容 | 対象となる発注事業者 | 適用される契約条件等 |
| 義務1:取引条件の明示 | 業務内容、報酬額、支払期日など9項目を書面または電磁的方法で直ちに明示 | 全ての業務委託事業者 | 全ての業務委託契約 |
| 義務2:報酬の適切な支払い | 給付受領日から60日以内(再委託時は元委託支払期日から30日以内)のできる限り短い期間内に支払い | 特定業務委託事業者 | 全ての業務委託契約 |
| 義務3:禁止行為(7項目) | 受領拒否、報酬減額、不当返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益提供要求、不当な給付内容変更・やり直し | 特定業務委託事業者 | 契約期間が1か月以上の業務委託 |
| 義務4:募集情報の的確な表示 | 虚偽表示・誤解を招く表示の禁止、正確かつ最新の情報提供 | 特定業務委託事業者 | フリーランスを募集する全ての情報提供 |
| 義務5:育児・介護と業務の両立への配慮 | フリーランスからの申出に応じ、必要な配慮 | 特定業務委託事業者 | 契約期間が6か月以上の業務委託(6か月未満は努力義務) |
| 義務6:ハラスメント対策 | 相談対応のための体制整備など必要な措置 | 特定業務委託事業者 | 全ての業務委託契約 |
| 義務7:中途解除等の事前予告 | 契約解除・不更新の場合、30日前までに予告、理由開示(フリーランスからの請求があった場合) | 特定業務委託事業者 | 契約期間が6か月以上の業務委託 |
より詳しい実務上の注意点は、こちらの記事で解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。
フリーランス新法において電子契約は必要?
フリーランス新法の施行により、電子契約は発注事業者とフリーランスの双方にとって、法律を遵守し、円滑な取引を行ううえで非常に重要なツールとなりました。以下にその関係性と必要性について事実情報を記載します。以下の項目の対応が重要だと感じられる場合には、電子契約導入の必要性が高いといえます。
電子契約は取引条件の明示義務を履行するために有効
フリーランス新法の第3条では、発注事業者がフリーランスに業務を委託する際、直ちに、書面または電磁的方法により取引条件を明示することを義務付けています。電子契約サービスは、この「電磁的方法」の一つとして明確に認められています。法律では電子契約の利用を義務付けてはいませんが、取引条件の明示義務を履行するための有効な手段となります。
電子契約はメリットが大きく、必要性も高い
口頭での契約が認められなくなるフリーランス新法のもとで、電子契約を利用することには、単なるメールやPDFでのやり取りに比べ、以下のような明確なメリットや必要性があります。
法令遵守の確実性と証明力が向上する
フリーランス新法が求める「給付の内容」「報酬の額」「支払期日」などの明示義務を、抜け漏れなく確実に履行できます。電子契約サービスは、電子署名とタイムスタンプにより「いつ、誰が、どの内容の契約に合意したか」を法的に有効な形で証明します。これにより、「言った言わない」といったトラブルを防止し、契約の存在と内容を客観的に示す強力な証拠となります。また、一度締結された契約書が事後的に改ざんされることを防ぐ技術が組み込まれており、契約内容の信頼性が担保されます。
トラブルを未然に防止できる
新法で禁止されている「報酬の不当な減額」や「不当な給付内容の変更・やり直し」などが発生した際、合意内容が明確に記録されている電子契約書は、フリーランスが自身の権利を主張するための重要な根拠となります。発注事業者側にとっても、明確な合意形成の証拠を残すことで、不当な要求をされたと主張されるリスクを低減できます。
業務効率化とコスト削減につながる
契約書の印刷、製本、押印、郵送といった物理的な手間と時間が不要になり、オンライン上で契約プロセスが完結するため、取引をスピーディーに開始できます。さらに、郵送費や、紙の契約書を保管するためのファイリングや倉庫スペースにかかるコストが削減できます。また、電子契約は印紙税法上の課税文書には該当しないため、収入印紙が不要です。
また、契約書はクラウド上で一元管理でき、検索機能を使えば必要な契約書をすぐに見つけ出せます。契約の更新時期を管理する機能を持つサービスもあり、管理業務が大幅に効率化されます。
電子帳簿保存法に対応できる
電子契約によって授受した契約書データは、電子帳簿保存法が定める「電子取引」に該当します。電子契約サービスを利用することで、同法の要件(真実性の確保、可視性の確保)を満たした形でデータを保存しやすくなります。
なお、当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」に関してご興味のある方に向け、3分でわかる資料をご用意しております。こちらから無料でダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約を検討する方に向け、電子契約の知識を深めるためにすぐわかる資料をご用意しました。電子契約サービスやクラウドサインについて詳しく知りたい方はダウンロードしてご活用ください
ダウンロードする(無料)もし違反したら?フリーランス新法の罰則
フリーランス新法に定められた義務の不履行や禁止行為への抵触があった場合、発注事業者には行政措置や罰則が科される可能性があります。また、フリーランスがトラブルに直面した際の相談窓口も設けられています。
違反した場合の行政措置は?
フリーランス新法に違反する行為があったと疑われる場合、公正取引委員会、中小企業庁長官、または厚生労働大臣は、発注事業者に対して調査を行い、その結果に基づいて段階的な行政措置を講じることができます。
具体的には、まず助言や指導が行われ、それでも改善が見られない場合には勧告が出されます。勧告に従わない場合には、より強制力のある命令が発せられることがあります。そして、この命令にも違反した場合には、事業者名が公表されることもあります。企業名の公表は、社会的な信用失墜に繋がりかねないため、発注事業者にとっては大きなリスクとなります。
違反した場合の罰則は?
行政からの命令に違反した場合や、法律に基づく立入検査を拒否したり妨害したりした場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、フリーランス新法には「両罰規定」が設けられています。これは、違反行為を行った従業員個人だけでなく、その事業主である法人等も罰金の対象となるという規定です。企業としては、従業員による違反行為が自社の責任問題に発展する可能性があることを認識し、コンプライアンス体制の整備と従業員教育を徹底する必要があります。
フリーランス側からの相談窓口は?
フリーランス新法に関連して取引先との間で困ったことが起きた場合、いくつかの方法はありますが、最も代表的な相談窓口について解説します。
相談先は「フリーランス・トラブル110番」へ
フリーランスが契約上のトラブルや仕事上の問題に直面した際に、無料で弁護士に相談できる窓口として「フリーランス・トラブル110番」が設置されています。この相談窓口は、公正取引委員会、厚生労働省、中小企業庁が第二東京弁護士会と連携して運営しており、フリーランスが専門的な法的助言を得るための重要なリソースとなります。ウェブサイト(https://freelance110.mhlw.go.jp/ )から相談の申し込みが可能です。
フリーランス新法の執行は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省がそれぞれの専門分野に応じて担当します。このような複数省庁による連携体制は、フリーランスの取引や就業環境が多岐にわたる問題を抱えていることを反映しています。各省庁が専門性を活かして監督にあたることで、より実効性のある保護が期待される一方で、どの問題についてどの省庁に相談すべきか迷うケースも考えられます。「フリーランス・トラブル110番」のような統一的な相談窓口は、こうした複雑さを軽減する役割も担っていると言えるでしょう。
フリーランス新法と下請法との違いは?
フリーランスとの取引においては、フリーランス新法だけでなく、「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」も関連する場合があります。どちらも取引の適正化を目指す法律ですが、その対象や規制内容にはいくつかの重要な違いがあります。フリーランス新法と下請法の主な違いは以下の通りです。
- 規制対象となる発注事業者(資本金要件など):
・下請法:親事業者(発注者)の資本金規模によって適用対象が定められています(例:資本金1000万円超の法人が個人や資本金1000万円以下の法人に委託する場合など)。
・フリーランス新法:発注事業者の資本金要件はありません。「特定業務委託事業者」(従業員を使用する発注事業者)であれば、資本金規模にかかわらず、より広範な義務や禁止事項が適用されます。 - 保護対象:
・下請法:下請事業者(資本金1000万円以下の法人や個人事業者など)を保護します。
・フリーランス新法:「特定受託事業者」(従業員を使用しない個人事業主や一人社長など)を主な保護対象としています。 - 対象となる取引:
・下請法:製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4類型が対象ですが、建設業法が適用される建設工事や、運送、コンサルティングなど事業者が自ら用いる役務の提供委託の一部は対象外となる場合があります。
・フリーランス新法:「業務委託」全般を対象としており、フリーランスが請け負う多様な業務をより広くカバーする可能性があります。 - 書面交付義務:
・下請法:発注内容、下請代金額、支払期日などを記載した書面(3条書面)の交付が厳格に義務付けられています。電磁的方法による交付には、下請事業者の事前の承諾が必要です。
・フリーランス新法:同様に取引条件の明示義務がありますが、書面に加えて電子メールやSNSなど、より柔軟な電磁的方法による明示が当初から認められています。 - 禁止行為の適用条件:
・下請法:親事業者の11の禁止行為(受領拒否、支払遅延、不当な減額、買いたたき、不当な返品など)は、基本的に契約期間にかかわらず適用されます。
・フリーランス新法:7つの禁止行為は、契約期間が1か月以上の業務委託に適用されるなど、一部の義務や禁止行為が契約期間によって適用条件が異なります。 - 独自の保護規定:
・フリーランス新法:育児・介護と業務の両立への配慮義務やハラスメント対策義務、契約の中途解除・不更新時の事前予告・理由開示義務など、フリーランスの就業環境整備に特化した独自の保護規定が含まれています。これらは下請法にはない特徴です。
下請法の対象となる取引が、同時にフリーランス新法の対象にもなる場合(例えば、資本金1000万円超の企業が個人のフリーランスに委託する場合など)、原則として両方の法律が適用されます。
また、フリーランス新法にしかない育児介護配慮やハラスメント対策などの規定と、下請法にしかない遅延利息の支払義務などは、それぞれ遵守する必要があります。フリーランス新法は、下請法ではカバーしきれなかった、比較的小規模な発注事業者との取引や、特定の取引類型に該当しなかったフリーランスの業務についても保護の網を広げる役割を果たしています。これにより、フリーランスにとってより包括的なセーフティネットが構築されることが期待されます。
フリーランス新法と下請法の主な違い(一覧表)
| 比較項目 | フリーランス新法 | 下請法(下請代金支払遅延等防止法) |
| 保護対象 | 特定受託事業者(従業員を使用しない個人事業主、一人社長など) | 下請事業者(資本金1000万円以下の法人、個人事業主など) |
| 規制対象事業者(主なケース) | 特定業務委託事業者(従業員を使用する発注事業者。資本金要件なし) | 親事業者(資本金1000万円超の法人が資本金1000万円以下の事業者へ委託する場合など、資本金区分による) |
| 主な義務・禁止行為の特色 | 取引条件明示、報酬の60日以内支払、7つの禁止行為(1か月以上の契約)、募集情報適正表示、育児介護配慮・ハラスメント対策(6か月以上の契約)、中途解約時予告など | 発注書面交付(3条書面)、支払期日設定(60日以内)、11の禁止行為(受領拒否、支払遅延、不当減額、買いたたき、不当返品など)、書類作成・保存義務など |
| 取引条件の明示・書面交付 | 書面または電磁的方法(メール、SNS等)で直ちに明示 | 原則として書面(3条書面)を交付。電磁的方法は相手方の承諾が必要 |
| 一部義務・禁止行為の適用される契約期間 | 7つの禁止行為は1か月以上、育児介護配慮・中途解約予告等は6か月以上の契約で適用 | 禁止行為は基本的に契約期間を問わず適用 |
フリーランス・発注事業者が今すぐ準備すべきこと
フリーランス自身も、そして業務を発注する事業者側も、それぞれ準備を進めておくべきことがあります。ここではそれぞれがすべきことを解説します。
フリーランス側がすべきこと
フリーランス新法はフリーランスを保護するための法律ですが、その恩恵を最大限に活かすためには、フリーランス自身も積極的に行動(自己防衛)することが重要です。
取引条件の文書化を徹底する:口頭で依頼を受けることは避け、必ず書面またはメール、チャット、電子契約などの電磁的方法で取引条件を明示してもらいましょう。新法では発注事業者に明示義務がありますが、フリーランス側からも積極的に確認する姿勢が大切です。
- 明示された取引条件をしっかり確認する
特に、業務内容、報酬額、支払期日、納期、検査期間など、法律で定められた9項目が明確に記載されているかを確認しましょう。不明な点や納得できない点があれば、契約締結前に必ず質問し、解消しておくことがトラブル防止に繋がります。 - 自身の権利を理解する
報酬の支払期限(原則60日以内)、発注事業者による一方的な受領拒否や報酬減額の禁止など、新法で定められた自身の権利を把握しておきましょう。 - 証拠を保存する
契約書や発注書はもちろん、メールやチャットでのやり取りなど、取引に関する全ての記録を整理して保存しておくことが、万が一のトラブル発生時に自身を守るための重要な証拠となります。 - 相談窓口を知っておく
厚生労働省の「フリーランス・トラブル110番」のような無料相談窓口の存在を覚えておき、困ったときには専門家の助けを求めることを躊躇しないようにしましょう。 - 積極的に交渉する
不当と思われる条件については毅然と交渉することも時には必要です。取引条件を「自分ごと」として捉えることが、より良い取引関係を築くうえで役立ちます。
発注事業者側が今すぐ準備すべきこと
発注事業者、特に特定業務委託事業者に該当する企業は、新法の施行に合わせて以下の準備を進める必要があります。
- 契約書・発注書テンプレートの見直し
フリーランス新法で定められた9項目の明示事項を網羅できるよう、既存の契約書や発注書のひな形を見直しましょう。 - 報酬支払プロセスの確認・整備
成果物受領日から60日以内(または再委託の場合は元委託支払期日から30日以内)に支払いが行えるよう、社内の経理プロセスやシステムを確認し、必要であれば改修します。 - 社内体制の整備:
・育児・介護配慮への対応
フリーランスから育児や介護との両立に関する配慮の申し出があった場合に、適切に対応できるような手順や方針を定めます。
・ハラスメント相談窓口の設置・周知
フリーランスも利用可能なハラスメント相談窓口を設け、その存在を周知徹底します。相談があった場合の対応フローも整備しておきましょう。
・中途解約・不更新時の手続き整備
契約期間6か月以上のフリーランス契約を中途解約または更新しない場合の事前予告(30日前)や、理由開示請求への対応手順を確立します。 - 従業員への周知・教育
フリーランスとの契約締結や業務指示に関わる購買部門、法務部門、人事部門、そして各事業部門の担当者や管理職に対して、フリーランス新法の内容、特に発注者としての義務や禁止行為について研修を実施するなどして周知徹底を図ります。 - 下請法との関連性の確認
自社が下請法の適用対象でもある場合、フリーランス新法との違いを理解し、両方の法律を遵守できる体制を構築します。
フリーランス新法の施行は、フリーランスとの取引における透明性と公正性を高めることを目的としています。これまでの口頭ベースのあいまいな契約や、力関係に任せた取引慣行から脱却し、より文書化され、ルールに基づいた関係へと移行することが求められています。この変化は、短期的には発注事業者側にとって事務負担の増加や体制整備のコストを伴うかもしれませんが、長期的にはフリーランスとの信頼関係を強化し、より安定した協業関係を築くうえで不可欠な対応と言えるでしょう。
フリーランス新法を理解し、適正な取引を
2024年11月1日に施行されたフリーランス新法は、フリーランスが安心してその能力を発揮できる社会を目指すための重要な一歩です。この法律は、フリーランスと発注事業者双方にとって、取引のルールを明確にし、より公正で透明性の高い関係を築くための指針となります。
フリーランスにとっては、取引条件の明示、適切な報酬支払い、不当な行為からの保護など、自身の権利を守るための強力な法的根拠が得られます。一方、発注事業者にとっては、新たな義務や禁止事項への対応が求められますが、これらを遵守することは、フリーランスとの信頼関係を構築し、質の高い業務成果を得るための基盤となります。また、法令遵守は企業の社会的責任を果たすうえでも不可欠です。
法律の詳細や個別のケースについては、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省といった関係省庁の発表する情報やQ&A、ガイドラインを参照するか、必要に応じて弁護士などの専門家にご相談ください。
記事内でも解説しましたが、フリーランス新法の対応において、電子契約は取引条件の明示義務を履行するための有効な手段となります。電子契約は法令遵守の観点や業務効率化、コスト削減などメリットが大きく、必要性も高いものです。ご興味のある方はこちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード
この記事の監修者
加藤高明
弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部