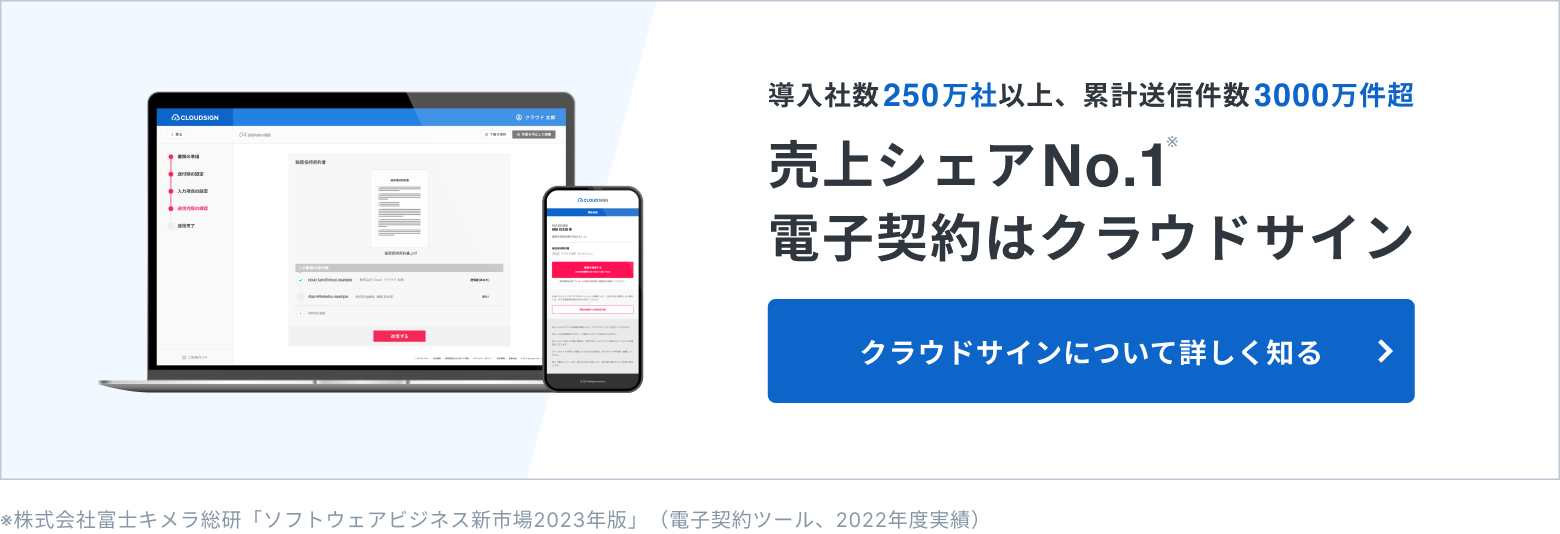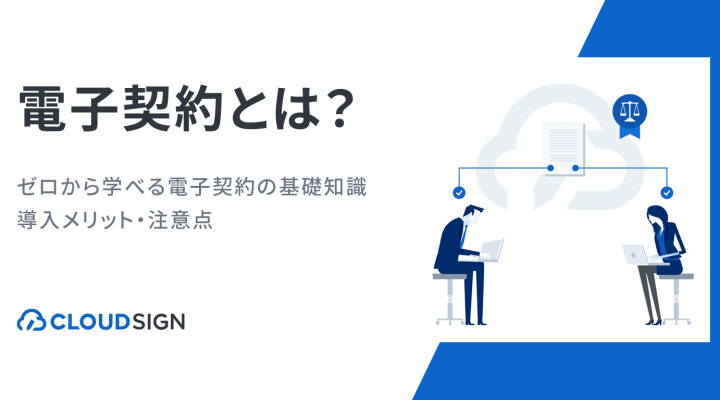新リース会計基準とは?2027年適用開始に向けた基礎知識や対応ポイント、最新動向を解説【税理士監修】

新リース会計基準は、企業の財務報告における透明性と国際的な比較可能性を向上させるために導入される重要な基準です。2027年から適用が開始されるこの基準は、リース契約の資産・負債計上を義務付けることで、企業の財務状況をより正確に反映することを目的としています。
当記事では、新リース会計基準の基本的なポイントや最新の動向、新基準の導入に伴う課題やその解決策について詳しく解説します。
なお、適用は2027年から開始となりますが、2025年4月1日以後に開始する事業年度の期首からの早期適用も可能となっています。2027年が近づいてから対応し始めるのではなく、適用開始まで時間的な猶予がある今から計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。「まだ先の話」と捉えず、まずは自社にどのような影響があるのかを確認し、早めに着手しましょう。
とくに、新基準対応の最大のハードルである「契約の網羅的な把握と一元管理」という課題は、電子契約システムにより解決できるため、この機会にぜひ電子契約サービスの導入を検討してみてください。
なお、当社では電子契約の基礎知識やメリットについてまとめた資料をご用意しておりますので、ご興味のある方は無料でダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)目次
新リース会計基準の基礎知識
2024年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表 )およびその適用指針は、日本におけるリース会計に抜本的な変更をもたらすものです。
ここでは、その新リース会計基準の目的や適用対象について解説します。
新リース会計基準とは?
まず前提として、リース会計基準とは、企業がコピー機や不動産などをリース(賃貸借)するときの会計処理のルールであり、企業の財務状況を適切に表示するための重要な会計ルールのことです。
新リース会計基準とは、これまでのリース会計基準における問題点を変更し、投資家が企業の財政状態をより正確に理解できるようにするために、企業会計基準委員会が公表したリース取引に関する会計処理のルールを新しくするというものです。
新リース会計基準の目的
これまでのリース会計基準では、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの2種類に分けていました。
| ファイナンス・リース |
|
| オペレーティング・リース |
|
この2種類のうち、オペレーティング・リースは費用計上するだけで貸借対照表(B/S)には計上されませんでした。それにより、この「オフバランス」になる取引は、多額のリース契約があっても財務諸表からは実態が見えにくく、「隠れた負債」と見なされることがあったため、問題視されました。
新リース会計基準の主な目的は、国際財務報告基準(IFRS)のIFRS第16号「リース」との整合性を図ることです。これにより、海外の投資家などが日本企業の財務諸表を他国企業と比較しやすくなり、国際的な資本市場における信頼性の向上が期待されるということになります。
また、従来の会計処理では貸借対照表に計上されなかったオペレーティング・リースを原則として資産・負債計上することで、企業がリース契約によって負っている実質的な支払義務を財務諸表に反映させ、情報の透明性を高めることも目的となっています。
これらにより、企業がどれくらいのリースを利用しているかが、B/Sを見れば一目でわかるようになります。
適用開始時期と対象企業
新リース会計基準の強制適用は、2027年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首からと定められています。例えば3月決算の企業であれば、2028年3月期から適用が開始されます。ただし、企業の準備状況に応じて、2025年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首からの早期適用も認められています。
本会計基準の適用対象となるのは、主に金融商品取引法の適用を受ける上場企業およびその連結子会社、ならびに会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)など、会計監査人による監査が義務付けられている企業です。
参考:国税庁 新リース会計基準に対応する改正、e-Gov 会社法
現行の会計基準と新リース会計基準との違い・変更点
新リース会計基準の導入により、企業の財務報告に大きな変化がもたらされます。新リース会計基準がもたらす本質的な変更点としては、会計処理の考え方にあります。これまでリースの種類によって異なっていた会計処理が、原則としてひとつに統一されることとなります。
ここでは、新リース会計基準における変更点について解説します。
原則すべてのリースを資産・負債に計上(オンバランス化)
現行の会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類します。このうち、契約の実態が資産の売買に近いファイナンス・リースのみが資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上(オンバランス)され、一般的な賃貸借契約に近いオペレーティング・リースは、支払リース料を費用計上するのみでした(オフバランス)。 新基準ではこの区分が原則として廃止され、借手は短期・少額の例外を除き、すべてのリース契約について「使用権資産」および「リース負債」を貸借対照表に計上することが求められます。
これにより、これまで費用処理のみで済んでいた多くの契約が企業の資産・負債として可視化されることになります。
対象となる契約・対象外となる契約の具体例
新基準の適用により、従来はオペレーティング・リースとしてオフバランス処理されることが多かった、下記のような契約もオンバランス化の対象となります。
- 対象となる契約例:
オフィスの賃貸借契約、PCやサーバー等のIT機器レンタル、複合機、社用車など。一方で、実務上の負担を軽減するため、例外として以下のリースについては、引き続き費用処理(オフバランス)が認められます。 - 短期リース:
リース期間が12ヶ月以内のリース。 - 少額リース:
企業の事業内容等に照らして重要性が乏しいリースで、契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリースや、原資産の新品価額が5,000米ドル相当額以下の少額なリースなどが該当します。
参考:企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」BC43・45
新リース会計基準がもたらす企業課題とは
新リース会計基準の適用は、単なる会計処理の変更に留まらず、企業の財務戦略や業務プロセスに直接的な影響を及ぼします。本章では、企業が直面する可能性のある主要な3つの経営課題について解説します。
財務指標の悪化リスクがある
すべてのリースがオンバランス化される結果、貸借対照表の資産と負債が同額増加します。これにより、企業の財務体質を示す各種経営指標に影響が及びます。具体的には、総資産が分母となるROA(総資産利益率)は低下する傾向にあります。
また、負債総額が増加するため、自己資本比率の低下や負債比率の上昇を招き、融資契約等における財務制限条項(コベナンツ)に抵触するリスクも考慮する必要があります。これらの指標変動について、金融機関や株主への事前説明が重要となります。
リース契約を網羅的に把握する難易度が高い
新基準への対応におけるハードルとなることとしては、対象となるリース契約を全社的に、漏れなく識別・把握することです。契約は本社経理部門だけでなく、各事業部、支店、工場などが個別に締結しているケースが少なくありません。
さらに、契約書の表題が「業務委託契約」や「保守契約」であっても、その内容に資産を支配して使用する権利が含まれていれば、新基準におけるリースに該当する可能性があります。こうした「隠れリース」の特定には、契約内容の詳細な精査が求められ、多大な労力が必要となります。
複雑化する会計処理と管理工数が増加する
リース負債は、将来支払うリース料総額を、借手の追加借入利子率などを用いて現在価値に割り引いて算定する必要があり、その計算は複雑です。また、計上後も使用権資産の減価償却やリース負債に係る支払利息の計算を毎期行わなければなりません。
さらに、契約期間の変更や重要な経済状況の変化に応じてリース負債を再測定する必要が生じるなど、従来は存在しなかった継続的な管理業務が発生します。これにより、経理部門の業務負荷が大幅に増加することが想定されます。
新リース会計基準への対応策
新リース会計基準への対応は、単なる経理部門のタスクではありません。全社を挙げて計画的に進める必要があります。ここでは、適用開始に向けて企業が実践すべきことについて解説します。
推進体制の構築をする
新リース会計基準への対応は、経理部門だけで完結するものではありません。リース契約は、総務、法務、IT、営業など、社内の様々な部署で個別に管理されているケースが多いためです。
まずはプロジェクトチームの発足を検討しましょう。経理部門が中心となり、関連部署を横断するプロジェクトチームを立ち上げ、全社的な対応方針とスケジュールを策定していきましょう。
同時に役割分担の明確化も進めましょう。各部署の担当者と協力体制を構築し、誰が何の情報を持っているのか、何をすべきかを明確にしていくことが望ましいです。
リース契約を網羅的に把握する
次に、社内に存在するすべてのリース契約を正確に洗い出す必要があります。本社だけでなく、支社や子会社、各部署が個別に結んでいる契約も対象となります。対象となるものの例としては、不動産(事務所、店舗)、車両、コピー機、PC・サーバー等のIT機器などです。
すべてのリース契約を洗い出し、把握する作業は最も時間と手間を要する部分であり、重要な作業となるため、早めに着手することが大切です。具体的には以下の作業を進めましょう。
- 契約書の収集
各部署で保管されている賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書などをすべて収集します。契約書に「リース」と記載がなくても、実態として新基準のリースに該当する可能性があるため注意が必要です。 - 契約内容のリスト化
収集した契約書をもとに、以下の情報をリストアップし、管理台帳を作成します。- 契約対象の資産
- 契約期間(解約不能期間、延長・解約オプションの有無など)
- リース料(月額、支払総額)
- その他契約条件(保守費用などリース料以外の支払いを含むか等)
会計方針を決める
洗い出したリース契約を、新基準に沿ってどのように会計処理するかの社内ルール(会計方針)を決定しましょう。
特に、新基準では短期リース(12ヶ月以内)や少額リース(新品価額が少額な資産)について、オンバランスしない簡便的な処理が認められています。自社として適用するかどうかや、どの範囲までを対象とするか(例:少額リースの金額基準など)を定めておく必要があります。
影響額の試算をする
決定した会計方針に基づき、新基準を適用した場合に財務諸表(特に貸借対照表)へどのような影響が出るかを試算しましょう。
具体的には、オンバランス化されるリース契約についての「使用権資産」と「リース負債」の金額を計算します。この試算結果は、経営陣が財務戦略を立てるうえでの重要な判断材料となるほか、投資家や金融機関といったステークホルダーへの事前説明にも必要となります。
業務フロー・システムの整備をする
最後に、新しい会計処理を継続的に行うための業務プロセスとシステムを整備しましょう。契約件数が多い場合、Excelなどでの手作業による管理には限界があり、ヒューマンエラーのリスクが高まります。効率的かつ正確な処理を行うために、システムの導入や改修を検討し業務フローやシステムの整備をしましょう。業務フローに関しては、リース契約の追加・変更・解約といった情報を、事業部門から経理部門へ確実に連携するルールを構築しましょう。
新リース会計基準の対応はいつから始めるべき?
結論から言うと「今すぐ始めるべき」と言えるでしょう。
2027年4月1日から適用と考えると、まだ時間があるように思えるかもしれませんが、その影響範囲の広さと準備の複雑さを考えると、2025年の今、すでに対応へのカウントダウンは始まっていると言えます。「まだ先の話」と考えていると、あっという間に時間がなくなり、混乱の中で適用日を迎えることになりかねません。
特に、以下の特徴を持つ企業は、特に早期の着手が不可欠です。
- 上場企業やその子会社: 投資家への説明責任があり、財務諸表への影響を早期に開示・説明する必要があるため。
- リース契約数が多い企業: 契約の洗い出しとデータ入力の作業量が膨大になるため。
- 拠点や事業部が多い企業: 契約が社内に分散しており、全体像の把握に時間がかかるため。
- 金融機関から融資を受け、財務制限条項がある企業: 財務指標の変動が契約に直接影響するため。
ここからは新リース会計基準の対応を今すぐ始めるべき理由について解説をします。
影響度評価(PoC)が予想以上に時間がかかるから
新基準対応の第一歩は、自社にどれだけのインパクトがあるかを試算する「影響度評価(Proof of Concept)」です。上記で解説しましたが、これには多くの作業が必要となり、数ヶ月単位の時間が必要になることが考えられます。特に、契約の網羅的把握や会計情報の抽出と計算に時間がかかることが予想されます。
そして、ここでつまずくと後続のすべての計画が遅延してしまうため、早めに着手することが必要となります。
システムの導入・改修には時間が必要だから
新しい複雑な計算や契約管理をExcelなど手作業で行うのは非現実的です。多くの企業でリース管理システムの導入や既存会計システムの改修が必須となります。一般的なシステム導入プロジェクトは、要件定義、ベンダー選定、設計、開発・導入、テスト、担当者への教育といったプロセスを経て、完了までに1年〜1年半かかることも珍しくありません。2025年後半から検討を始めても、決して早すぎることはないでしょう。
関係各所との調整に時間がかかるから
新基準対応は経理部門だけの問題ではありません。契約を管理する各事業部門、法務部門、IT部門、そして経営層や監査法人との連携が不可欠です。全社的なプロジェクトチームを組成し、方針を固め、協力を得ながら進めるには、相応の調整期間が必要です。
新リース会計基準への対応は契約管理のDXが鍵に
新リース会計基準が求める「全てのリース契約の網羅的な把握」と「継続的な情報管理」は、紙やExcel、個人のファイルサーバで契約書を管理する従来の方法では極めて困難であるといえます。この課題を解決する鍵が、契約管理のデジタルトランスフォーメーション(DX)です。
特に、電子契約システムを導入することは、新リース会計基準への課題の解決に直接つながるものです。電子契約を活用することで、手作業によるヒューマンエラーのリスクを低減し、管理工数を大幅に削減するために効果的であるといえます。
電子契約を利用することで、さまざまなメリットが生まれますので、次のパートで詳しく解説します。
新リース会計基準に電子契約が有効な理由・メリット
上記で述べたように、特に契約の網羅的な把握と継続的な管理という難題に対し、テクノロジーを活用したDXが有効な解決策となります。ここでは、電子契約システムの活用すべき理由とそのメリットについて解説します。
契約情報の一元管理による「網羅的な把握」ができる
電子契約システムを導入することで、紙媒体で各拠点に分散保管されがちな契約書を電子データとして集約し、クラウド上で一元管理することが可能となります。
これにより、本社管理部門は全社で締結されたリース契約の全体像を網羅的に把握できるようになります。物理的な保管場所やバージョン管理の問題から解放され、新基準対応の前提となる「全契約の洗い出し」という煩雑な作業を、効率的かつ正確に進めることが可能となります。
検索機能による「会計処理の迅速化」と「監査対応」ができる
電子化・データベース化された契約情報は、契約の相手方、締結日、契約期間、リース料といった多様な条件で瞬時に検索・抽出が可能です。
これにより会計処理に必要な情報を契約書の中から探し出す手間が大幅に削減され、使用権資産やリース負債の算定業務を迅速化します。また、会計監査の際には、監査人から要求される契約書の根拠資料を速やかに提示できるため、監査対応業務の効率化にも直結します。これにより、正確な会計処理とガバナンス強化を両立させることができます。
更新管理の自動化による「管理工数の削減」ができる
多くの電子契約システムは、契約期間の満了日が近づくと事前に担当者へ通知するアラート機能を備えています。この機能を活用することで、契約の更新漏れや意図しない自動更新を防ぐことができます。新リース会計基準では、契約更新の判断がリース負債の再測定といった会計処理に影響するため、計画的な管理が不可欠です。契約のライフサイクル管理を自動化することで、将来にわたって発生する管理工数を削減し、担当者はより付加価値の高い業務に集中することが可能となります。
なお、「クラウドサイン」「クラウドサイン カンリ」を利用することで新リース会計基準の対応を効率的かつ正確に進めることが可能です。ご興味のある方はサービス内容をまとめた資料をご用意しておりますので、無料でダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約を検討する方に向け、電子契約の知識を深めるためにすぐわかる資料をご用意しました。電子契約サービスやクラウドサインについて詳しく知りたい方はダウンロードしてご活用ください
ダウンロードする(無料)新リース会計基準の適用開始は目前。早期着手と契約管理のDXの検討を
当記事では、新リース会計基準の概要から企業が直面する課題、そして具体的な対応策までを解説しました。
最大の変更点は、原則としてすべてのリース契約が貸借対照表に計上されることであり、これにより企業の財務状況は大きく変わる可能性があります。対応の過程では、散在する契約の洗い出しや複雑な会計処理といった、多くのハードルが待ち受けています。
これらの課題を乗り越え、新基準へスムーズに移行するために最も重要なのは「計画的な準備を、今すぐ始めること」です。
特に、全契約を漏れなく把握し、継続的に管理していくためには、従来の紙やExcelによる管理では限界があります。本記事でもご紹介した電子契約システム「クラウドサイン」をはじめとした技術を活用し、契約管理のDXを進めることが、根本的な解決策となります。
今回の基準変更を、単なる会計ルールの変更と捉えるのではなく、自社の契約管理体制を見直し、業務全体の効率化とガバナンス強化を実現する絶好の機会と捉え、第一歩を踏み出しましょう。
なお、当社では電子契約の基本をまとめたお役立ち資料をご用意しております。電子契約を導入すれば、契約の網羅的な把握が容易になるだけでなく、コスト削減や業務効率化といった多くのメリットが生まれます。こちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード
この記事の監修者
末永寛
税理士
一般企業における経理事務を約25年経験した後、税理士事務所開業。フリーランス・中小企業向けの税務業務の他に、「相続税」分野を強みとし、相続や中小企業の事業承継(後継者問題)について、相談に応じたり、セミナーを開催したりするほか、金融機関の勉強会やハウスメーカー主催の相続情報や相続対策の講演なども行っている。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部