【2025年6月公布】貨物自動車運送事業法改正のポイントは?運送事業者の対応事項も解説

2025年(令和7年)の国会で貨物自動車運送事業法の改正法が可決・成立し、同年6月11日付で公布されました。
改正法は2028年6月までの全面施行が予定されています。運送事業者は改正法のポイントを理解し、施行日までに対応できるように準備を進めましょう。
本記事では、2025年6月に公布された貨物自動車運送事業法改正の内容や、運送事業者の対応事項などを解説します。
目次
貨物自動車運送事業法とは
「貨物自動車運送事業法」とは、トラック輸送などの貨物自動車運送事業の運営を適正化・合理化するために、必要な規制を定めた法律です。「トラック法」などと呼ばれることもあります。
トラック輸送などを行う運送事業者は、貨物自動車運送事業法の規制を遵守することが求められます。
【2025年6月公布】貨物自動車運送事業法改正とは
2025年5月27日に貨物自動車運送事業法の改正法が国会で可決・成立し、同年6月11日に公布されました。
貨物自動車運送事業法改正の目的
今回の貨物自動車運送事業法改正の目的は、トラック輸送などの貨物自動車運送事業に関する問題点を解決し、輸送の安全確保と健全な発達を図ることです。
貨物自動車運送事業については、従来より以下のような問題点が指摘されていました。
・下請発注が何重にも行われていて、荷主や元請事業者による管理が行き届きにくくなっていること
・無許可で貨物自動車運送事業を行う者がいること
・許可の有効期限がないため、コンプライアンスが不十分な運送事業者が増えていること
・特に下請事業者における労働環境が劣悪であること
など
今回の貨物自動車運送事業法改正では、上記のような問題点を解決するための変更が行われます。
貨物自動車運送事業法改正の公布日・施行日
今回の貨物自動車運送事業法改正の公布日・施行日は以下のとおりです。
施行日:公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日(一部の規定を除く)
【2025年6月公布】貨物自動車運送事業法改正の全体像
今回の貨物自動車運送事業法改正では、以下の変更が行われます。
・実運送体制管理簿の作成義務の拡大
・多重下請構造の是正|二次請けまでに制限する努力義務
・無許可業者等に対する委託の禁止【2028年6月までに施行】
・適正原価の告示|下回る運賃での受託等の禁止
・貨物自動車運送事業許可の5年更新制
・運送業労働者の適切な処遇の確保
次の項目から、各変更点の内容を解説します。
【2026年6月までに施行】貨物自動車運送事業法改正の内容①
2026年6月までに、以下の変更が施行されます。
・多重下請構造の是正|二次請けまでに制限する努力義務
・無許可業者等に対する委託の禁止
実運送体制管理簿の作成義務の拡大
一般貨物自動車運送事業者は、自社が元請けとして真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送を下請事業者に行わせたときは、以下の事項を記載した「実運送体制管理簿」を作成しなければなりません。実運送体制管理簿は、運送完了日から1年間の保存が義務付けられています。
(b)(a)の実運送を行う貨物の内容および区間
(c)(a)の貨物自動車運送事業者の請負階層
現行法では、実運送体制管理簿の作成義務を負うのは元請けである「一般貨物自動車運送事業者」に限られています。
「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じて有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。典型的には、トラック輸送を行う事業などが該当します。
ただし、以下のものは一般貨物自動車運送事業から除外されています。
・特定の者の需要に応じて貨物を運送するもの(=特定貨物自動車運送事業)
また、「貨物自動車利用運送」を行う事業者が真荷主である場合は、実運送体制管理簿の作成義務が適用されません。「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を経営する者が、下請事業者の自動車運送を利用して行う貨物の運送をいいます。
今回の貨物自動車運送事業法改正では、実運送体制管理簿の作成義務を負う事業者の範囲が拡大されました。
一般貨物自動車運送事業に加えて、貨物軽自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業を行う元請事業者にも実運送体制管理簿の作成義務が課されます。
また、貨物自動車利用運送を行う事業者が真荷主である場合にも、元請事業者は実運送体制管理簿の作成義務を負うようになります。
真荷主は元請事業者に対して、実運送体制管理簿の閲覧・謄写を請求できます。実運送体制管理簿の作成義務が拡大されることにより、真荷主は運送の請負階層を把握しやすくなるでしょう。
実運送体制管理簿の作成・保存義務に違反した運送事業者は、国土交通大臣から事業停止などの行政処分を受けるおそれがあります。
多重下請構造の是正|二次請けまでに制限する努力義務
トラック輸送などの貨物自動車運送事業については、従来から多重下請構造が問題視されていました。下請発注が何重にも行われていると、荷主や元請事業者は実運送の状況を把握するのが難しくなります。
今回の貨物自動車運送事業法改正では、元請けである貨物自動車運送事業者に対して、下請構造を二次請けまでに制限するために必要な措置を講ずる努力義務が課されました。多重下請構造の緩和により、実運送の状況把握が容易になる効果が期待されます。
上記は努力義務に過ぎないため、改正法の施行後に二次請けまでに制限するための措置を怠っても、具体的なペナルティを受けることはありません。
ただし、努力義務を怠ると行政指導を受ける可能性があるほか、今後の法改正によっては義務化されることもあり得るので十分ご注意ください。
無許可業者等に対する委託の禁止
一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を営むには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。また、貨物軽自動車運送事業を営むには、所定の事項を国土交通大臣に届け出なければなりません。
今回の貨物自動車運送事業法改正では、何人も上記の規定に違反する無許可業者等に対し、自動車による貨物の運送を委託してはならないものとされました。
無許可業者等に対して自動車による貨物の運送を委託した場合は「100万円以下の罰金」に処されます。
また、荷主その他の者(=荷主等)による無許可経営等の原因となるおそれのある行為(=無許可経営等原因行為)に対処するため、国土交通大臣は当分の間、以下の対応ができるものとされました。
・無許可経営等原因行為をしているおそれがある荷主等に対して、無許可経営等原因行為をしないよう要請する
・無許可経営等原因行為をしていると疑うに足りる相当な理由がある荷主等に対して、無許可経営等原因行為をしないよう勧告し、その旨を公表する
【2028年6月までに施行】貨物自動車運送事業法改正の内容②
2028年6月までに、以下の変更が施行されます。
・貨物自動車運送事業許可の5年更新制
・運送業労働者の適切な処遇の確保
適正原価の告示|下回る運賃での受託等の禁止
トラック輸送などの貨物自動車運送事業については、事業者間で過当な価格競争が起きやすい傾向にあります。
過度な価格の低下を防いで実運送の事業を持続化させるため、これまでは国土交通大臣が「標準的な運賃」を定めていました。しかし、標準的な運賃は強制力に乏しく、荷主の理解も十分に得られていないという問題がありました。
今回の貨物自動車運送事業法改正では、国土交通大臣が貨物自動車運送事業の適正な運営を図るための原価(=適正原価)を定めることができる旨が定められました。適正原価を定めた場合は、遅滞なく告示するものとされています。
適正原価を定める際に考慮すべき要素として、以下のものが列挙されています。具体的な考慮要素は、今後省令によって定められる予定です。
・全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費
・減価償却費
・輸送の安全確保のために必要な経費
・委託手数料
・事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資
・公租公課
・その他の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用
適正原価の告示があった場合、貨物自動車運送事業者は運送を受注するに当たり、その運賃や料金が適正原価を下回らないようにしなければなりません。
また、自らが引き受けた貨物の運送を別の事業者に行わせる場合も、その運賃や料金が適正原価を下回らないようにする必要があります。
上記の義務に違反して、適正原価を下回る価格での受注または下請発注を行った場合は、国土交通大臣による行政処分を受けるおそれがあります。
なお、本改正の施行に伴い、従来定められていた「標準的な運賃」は廃止されます。
貨物自動車運送事業許可の5年更新制
一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を営むためには、その種類に応じた国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
現行法では、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業の許可に有効期間は設けられていません。一度許可を受ければ、更新することなくずっと営業できるようになっています。
このような制度の下では、最新法令への対応などのコンプライアンスを怠る運送事業者が増えている点が問題視されていました。
今回の貨物自動車運送事業法改正では、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業の許可の有効期間を5年とする旨が定められました。5年ごとに更新を受けなければ、国土交通大臣の許可が失効して営業できなくなります。
許可の更新に当たっては、更新申請時点における許可基準を満たさなければなりません。
許可基準では、業務遂行体制や財務基盤、法令遵守などの要件が掲げられています。5年ごとに許可基準の充足を求めることにより、運送事業者のコンプライアンス向上が期待されます。
運送業労働者の適切な処遇の確保
トラック輸送などの貨物自動車運送事業に関しては、過当競争や価格転嫁の難しさなどが影響して、劣悪な労働条件で働く人が多いことが問題となっています。
今回の貨物自動車運送事業法改正では、貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者に対して、労働者の適切な処遇を確保するために必要な措置の実施が義務付けられました。
対象となる運送事業者は、労働者が有する知識や技能などの能力を公正に評価し、その評価に基づいて適正な賃金を支払わなければなりません。運送事業者が実施すべき労働者の処遇確保措置の詳細は、今後省令によって定められる予定です。
貨物自動車運送事業法に関する運送事業者の対応事項
今回の貨物自動車運送事業法改正について、運送事業者は以下の対応を施行日までに行いましょう。
(a)実運送体制管理簿の作成・保存
以下の元請事業者は、新たに実運送体制管理簿の作成・保存義務を負います。
・貨物軽自動車運送事業を行う元請事業者
・特定貨物自動車運送事業を行う元請事業者
・貨物自動車利用運送を行う事業者が真荷主である場合の元請事業者(b)下請構造の見直し
元請事業者は、下請構造を二次請けまでに制限するために必要な措置を講ずる努力義務を負います。(c)無許可業者等に対して運送委託をしていないかどうかの確認
無許可業者等に対する運送委託は、新たに罰則の対象となります。委託先において許可の取得または届出が済んでいることを必ず確認しましょう。【2028年6月までに施行】
(a)運賃・料金の見直し
施行日までに告示される適正原価を下回らないように、自社が受託または発注する運送の運賃・料金を見直しましょう。
(b)貨物自動車運送事業許可の更新準備
一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の許可は、5年ごとに更新が必要となります。更新時期を確認したうえで、更新手続きの準備を進めましょう。
・運送業労働者の適切な処遇の確保
施行日までに制定される省令を踏まえて、労働者の適切な処遇を確保するために必要な措置を講じましょう。
まとめ
今回の貨物自動車運送事業法改正では、運送事業者のオペレーションに影響を与える様々な変更が盛り込まれました。幅広い運送事業者が改正の影響を受けるため、今のうちから変更内容を把握したうえで対応を進めましょう。
なお、物品などの運送を委託する際に締結する運送委託契約書は、電子契約によって締結することもできます。電子契約で締結することで印紙税を節約できるほか、書類の管理を効率化できます。まだ電子契約を導入していない企業は、ぜひ導入をご検討ください。
クラウドサインでは、電子契約の基礎知識など、契約書のデジタル化を検討する方に向けた資料を無料でご提供しています。ご興味のある方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード
この記事の監修者
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
法律・法改正・制度の解説
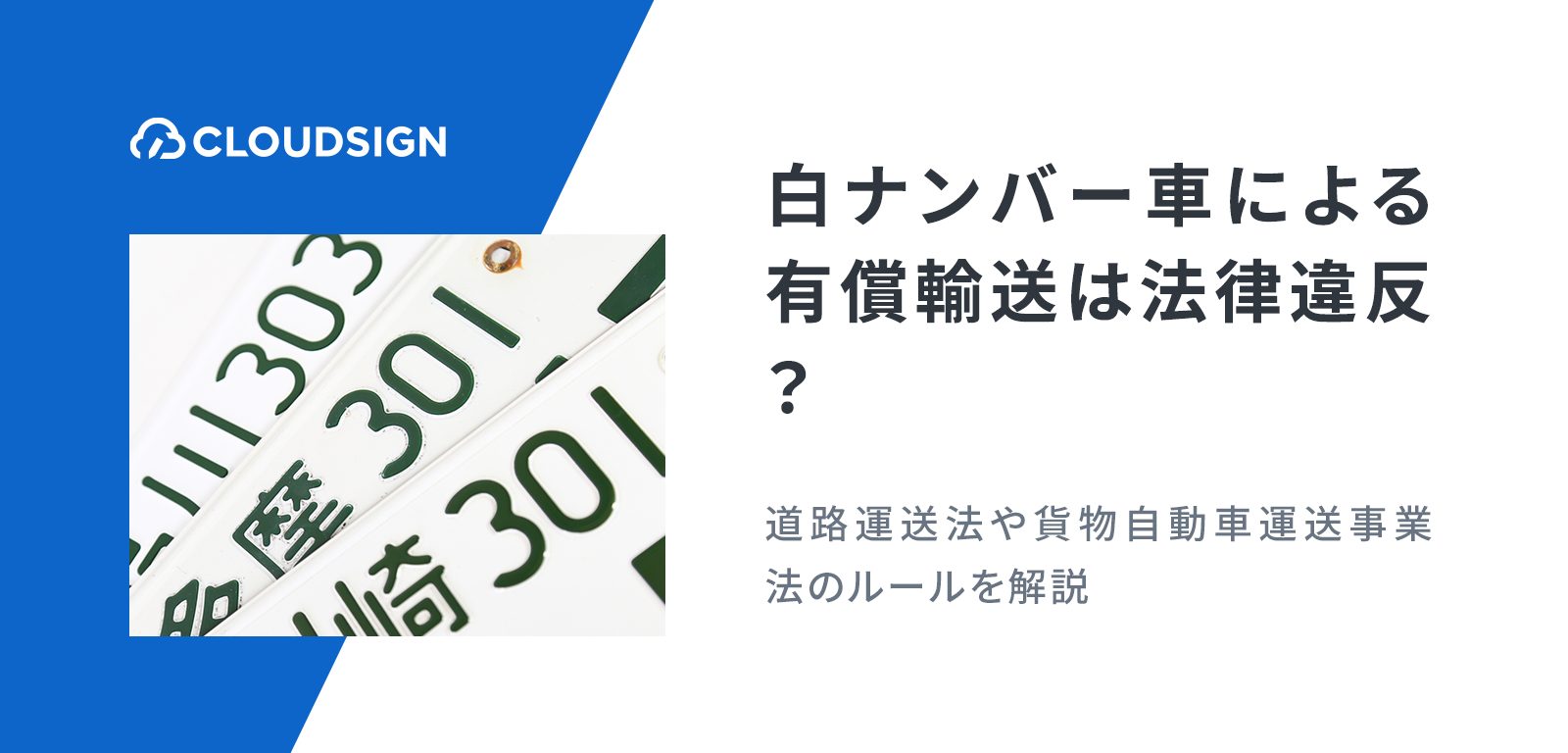
白ナンバー車による有償輸送は法律違反?道路運送法や貨物自動車運送事業法のルールを解説
物流業 -
法律・法改正・制度の解説

【2025年4月・2026年4月施行】改正物流効率化法とは?変更点や運送事業者の対応ポイントを解説
取適法(下請法)物流業 -
法律・法改正・制度の解説

フリーランス新法とは?主な義務や罰則、下請法との違い、相談窓口を解説【弁護士監修】
フリーランス新法 -
法律・法改正・制度の解説

下請法とは?2026年施行の改正内容と実務への影響を解説
取適法(下請法) -
業務効率化の成功事例まとめ

Salesforceとクラウドサインを連携し、業務効率化に成功した事例5選
契約書管理インタビュークラウドサインの機能コスト削減電子契約の活用方法電子契約の導入電子契約のメリット業務効率化API連携 -
業務効率化の成功事例まとめ

kintoneとクラウドサインを連携し、業務効率化に成功した事例4選
契約書管理インタビュークラウドサインの機能コスト削減電子契約の活用方法電子契約の導入電子契約のメリット業務効率化API連携
