【2025年4月・2026年4月施行】改正物流効率化法とは?変更点や運送事業者の対応ポイントを解説

2025年4月1日に施行された法改正により、従来の「流通業務総合効率化法」が「物流効率化法」に改められました。
物流効率化法では、運送事業の効率化に関する新規制が定められており、2025年4月1日と2026年4月1日の2回に分けて施行されます。運送事業者は、新たな規制の内容を理解しておきましょう。
本記事では、2025年4月・2026年4月施行の改正物流効率化法のポイントを解説します。
目次
【2025年4月・2026年4月施行】改正物流効率化法とは
2024年の国会で成立した改正法に基づき、2025年4月1日から、従来の「流通業務総合効率化法」が「物流効率化法」へと改められました。2025年4月と2026年4月の2回に分けて施行が予定されています。
(旧)流通業務総合効率化法……流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
物流効率化法……物資の流通の効率化に関する法律
物流効率化法では、運送事業の効率化や運送業務の適正化などを促すための新たな規制が設けられています。
物流効率化法改正の目的
2025年4月と2026年4月の2回に分けて施行される物流効率化法改正の目的は、いわゆる「2024年問題」による物流の停滞に対処することです。
2024年4月1日から、運送業のドライバーの労働時間規制が厳格化されました。ドライバーの労働時間が短縮されることに伴い、労働力不足によって物流業務が停滞することが懸念されていました。
そこで、事業者に対して物流事業の効率化に関する取り組みを促し、労働力不足を補うことを目的として、2025年4月1日から物流効率化法改正が施行されました。
物流効率化法改正の全体像
2025年4月と2026年4月の2回に分けて施行される物流効率化法改正による変更のポイントは、以下の2点です。
(2)一定規模以上の物流事業者・荷主に対する規制強化(2026年4月~)
次の項目から、各変更点の内容を詳しく解説します。
改正ポイント(1)|物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務(2025年4月~)
1つ目の改正点は、物流事業者や荷主に対して、物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務が課されたことです。本改正は、2025年4月1日から施行されました。
運転者1人当たり・運送1回当たりの貨物重量を増加させて物流業務を効率化するため、運送事業者・荷主・関連事業者・連鎖化事業者は、それぞれ以下の措置を講じるよう努めるものとされました。
運送事業者・荷主・貨物自動車関連事業者・連鎖化事業者が物流効率化のために講ずべき措置については、省令によって判断基準が定められています。
運送事業者が取り組むべき物流効率化措置
トラックなどを用いて物資を運送する貨物自動車運送事業者等(以下「運送事業者」といいます。)は、以下の措置を講ずるよう努めるものとされました。
(a)複数の荷主の貨物の積み合わせ、輸送網の集約
(b)配送の共同化
(c)復荷(帰り荷)の確保による実車率の向上
(d)配車・運行計画の最適化
(e)輸送量に応じた大型車両の導入②実効性確保のための事項
(a)積載効率の状況や取組の効果の把握
(b)取引先に対する標準仕様パレット活用、共同輸配送等の提案実施
(c)関係事業者間での連携推進
(d)物流データの標準化の取組
(e)過積載など関係法令の遵守
参考:貨物自動車運送事業者等の判断基準等|「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
荷主が取り組むべき物流効率化措置
運送事業者に対して荷物の運送を委託する荷主は、以下の措置を講ずるよう努めるものとされました。
(a)リードタイムの確保
(b)繁閑差の平準化、納品日数の集約
(c)発送量等の適正化等に向けた物流・販売・調達等の関連部門の連携②荷待ち時間の短縮
(a)トラック予約受付システムの導入
(b)混雑時間を回避した日時指定③荷役等時間の短縮
(a)パレット等の輸送用器具導入による荷役等の効率化
(b)パレット標準化
(c)出荷荷姿を想定した生産
(d)フォークリフト、作業員の配置
(e)事前出荷情報の活用、タグ導入等による検品の効率化
(f)適正な荷役作業が行える環境確保④実効性の確保のための事項
(a)責任者の選任、社内教育体制
(b)運送者への配慮
(c)積載効率・荷待ち・荷役等時間の状況や取組把握、デジタル技術の活用
(d)物流データの標準化の取組
(e)メニュープライシングの実施
(f)関係事業者間での連携推進
なお物流効率化法では、荷主は「第一種荷主」と「第二種荷主」の2つに区別されています。
第一種荷主は、運送事業者と直接契約を締結して運送を委託し、輸送計画の管理を行います。主に荷物を送る側(発荷主)が第一種荷主に該当します。
第二種荷主は、他の事業者が雇用しているトラックドライバーから貨物を受け取る者、または荷物を引き渡す者です。主に荷物を受け取る側が第二種荷主に該当します。
第一種荷主と第二種荷主は、それぞれの立場に応じて上記の措置を講じることが求められます。詳しくは判断基準をご参照ください。
参考:荷主(第一種・第二種)の判断基準等|「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
貨物自動車関連事業者が取り組むべき物流効率化措置
「貨物自動車関連事業者」とは、トラックドライバーとの間で貨物の受渡しを行う者です。具体的には、倉庫業者・港湾運送事業者・航空運送事業者・鉄道事業者の4つを指します。
貨物自動車関連事業者は、以下の措置を講ずるよう努めるものとされました。
(a)トラック予約受付システムの導入
(b)混雑時間を回避した日時指定②荷役等時間の短縮について
(a)適正な荷役作業が行える環境確保
(b)荷役前後の搬出入の迅速な実施
(c)フォークリフト、作業員の配置
(d)納品先単位の貨物の仕分け
(e)一貫パレチゼーションへの協力
(f)機器の導入による検品の効率化③実効性の確保のための事項
(a)責任者の選任、社内教育体制
(b)荷待ち・荷役等時間の状況や取組把握、デジタル技術の活用
(c)荷主への効率化の提案・協力
(d)物流データの標準化の取組
(e)作業の自動化
(f)関係事業者間での連携推進
参考:貨物自動車関連事業者の判断基準等|「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
連鎖化事業者が取り組むべき物流効率化措置
「連鎖化事業者」とは、フランチャイズ・チェーンの本部です。加盟店(連鎖対象者)と運送事業者の間の貨物の受渡しに関して、本部が運送事業者に指示できる場合は、本部が連鎖化事業者に該当します。
連鎖化事業者は、以下の措置を講ずるよう努めるものとされました。
(a)リードタイムの確保等に関する協力
(b)繁閑差の平準化、納品日の集約
(c)発送量等の適正化等に向けた物流・販売・調達等の関連部門や連鎖対象者間の連携②荷待ち時間の短縮
(a)混雑時間を回避した日時指定③実効性の確保のための事項
(a)責任者の選任、社内教育体制
(b)運送者への配慮
(c)積載効率・荷待ち時間の状況や取組把握、デジタル技術の活用
(d)物流データの標準化の取組
(e)関係事業者間での連携推進
参考:連鎖化事業者の判断基準等|「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
改正ポイント(2)|一定規模以上の物流事業者・荷主に対する規制強化(2026年4月~)
2つ目の改正点は、一定規模以上の物流事業者・荷主が「特定事業者」に指定され、物流事業の効率化に関する所定の対応が義務付けられることです。本改正は、2026年4月1日から施行されます。
特定事業者の指定基準値
2026年4月以降、一定規模以上の運送事業者・荷主・連鎖化事業者・倉庫業者は、国土交通大臣によって「特定事業者」に指定されます。
特定事業者の指定基準値は、以下のとおりです。指定基準値以上である事業者は、事業所管大臣にその旨を届け出なければなりません。
| 特定事業者の種類 | 指定基準値 |
| 特定貨物自動車運送事業者等 | 年度末において保有する事業用自動車の台数が150台以上 |
| 特定第一種荷主 | 取扱貨物の重量が9万トン以上 |
| 特定第二種荷主 | 取扱貨物の重量が9万トン以上 |
| 特定連鎖化事業者 | 取扱貨物の重量が9万トン以上 |
| 特定倉庫業者 | 年度内に入庫された貨物の合計重量が70万トン以上 |
特定事業者には、物流事業の効率化を目的として、次に挙げる対応が義務付けられます。
特定事業者の対応①|中長期的な計画の作成
特定事業者は、その種類(運送事業者・荷主・連鎖化事業者・倉庫業者)ごとに定められた判断基準(前掲)を踏まえて、物流効率化措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、事業所管大臣に提出する必要があります。提出の頻度は5年に1回ですが、計画内容を変更した場合はその都度提出しなければなりません。
特定事業者の対応②|定期報告
特定事業者は毎年1回、以下の事項を事業所管大臣に報告しなければなりません。
・関連事業者との連携状況等の判断基準と関連した取組に関する状況
・荷待ち時間等の状況
特定事業者の対応③|物流統括管理者(CLO)の選任(特定荷主と特定連鎖化事業者のみ)
特定荷主と特定連鎖化事業者は、物流効率化のために必要な業務を統括管理する者(=物流統括管理者)の選任が義務付けられます。物流統括管理者には、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者を充てなければなりません。物流統括管理者の業務内容は、以下のとおりです。
(a)中長期計画の作成
(b)トラックドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備
(c)その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務(以下の業務など)
・定期報告等の作成
・リードタイムの確保
・発注および発送量の適正化等のための連携体制の構築
・効率化のための設備投資、デジタル化
・物流標準化に向けた事業計画の作成、実施および評価
・社内研修の実施
・調達先や納品先などの物流統括管理者や、物流事業者等の関係者との連携、調整
物流統括管理者を選任または解任したときは、その氏名と役職を荷主事業所管大臣に届け出なければなりません。
物流効率化法に違反した際の罰則はあるのか?
2025年4月1日から物流事業者や荷主に対して課された、物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務については、対応する措置を講じなくても罰則の対象にはなりません。
これに対して、2026年4月1日から施行される一定規模以上の特定事業者の義務については、違反した場合には以下の罰則が科されます。
| 違反行為 | 罰則 |
| ・特定荷主または特定連鎖化事業者が、物流統括管理者の選任を怠ったとき | 100万円以下の罰金 |
| ・前年度実績が特定事業者の指定基準値以上であるのに、 所管大臣への届出をしなかったとき、または虚偽の届出をしたとき ・中長期的な計画の作成を怠ったとき ・定期報告をせず、または虚偽の報告をしたとき |
50万円以下の罰金 |
| ・特定荷主または特定連鎖化事業者が、物流統括管理者の選任または解任の届出を怠ったとき | 20万円以下の過料 |
運送業における業務効率化なら電子契約も選択肢のひとつに
これまでみてきたように、運送業においては人手不足による物流業務の停滞が課題になっており、業務効率化が求められています。業務効率化の手段はさまざまありますが、電子契約サービスによる契約業務に係る時間・コストの削減も選択肢のひとつです。
電子契約サービスとは、これまで紙と印鑑で行っていた契約を電子データで締結・管理する仕組みです。電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを付与し、本人による作成と非改ざん性を証明するもののため安全性も高く、電子署名法に基づき、紙の契約書と同等の法的効力が認められているものです。
面倒な印刷や製本、郵送や保管といった一連の事務処理が不要になるため、最近では契約締結までのリードタイム短縮や、締結後の管理の効率化のために物流業で導入する企業が増えています。具体的には、運送契約の電子化に電子契約サービスが利用可能です。
なお、クラウドサインでは契約書の電子化を検討している方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
まとめ
改正物流効率化法により、物流事業者と荷主には、運送事業の効率化に向けたさまざまな取り組みが求められるようになりました。
特に一定規模以上の物流事業者や荷主は、2026年4月1日から特定事業者としての届出を行ったうえで、中長期的な計画の作成と定期報告を行う必要があります。特定荷主と特定連鎖化事業者は、物流統括管理者(CLO)の選任と届出も必要です。
物流に関わる事業者や、物流事業者に対して運送を委託する事業者は、改正物流効率化法による新たなルールの内容をきちんと把握しておきましょう。
この記事の監修者
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
業務効率化の成功事例まとめ
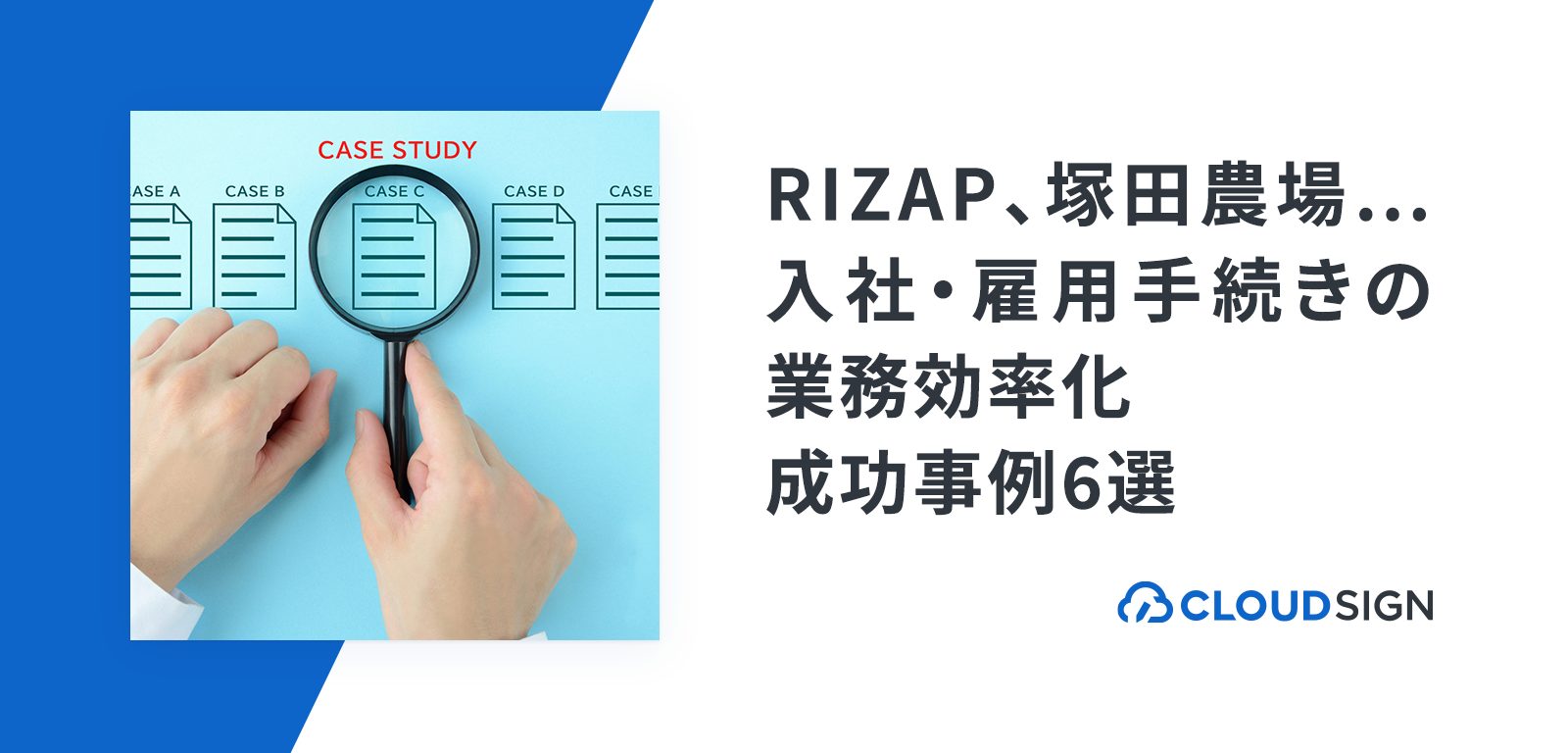
RIZAP、塚田農場…入社・雇用手続きの業務効率化 成功事例6選
インタビュー業務委託契約書電子契約の活用方法電子契約の導入電子契約のメリット雇用契約人事労務業務効率化 -
法律・法改正・制度の解説
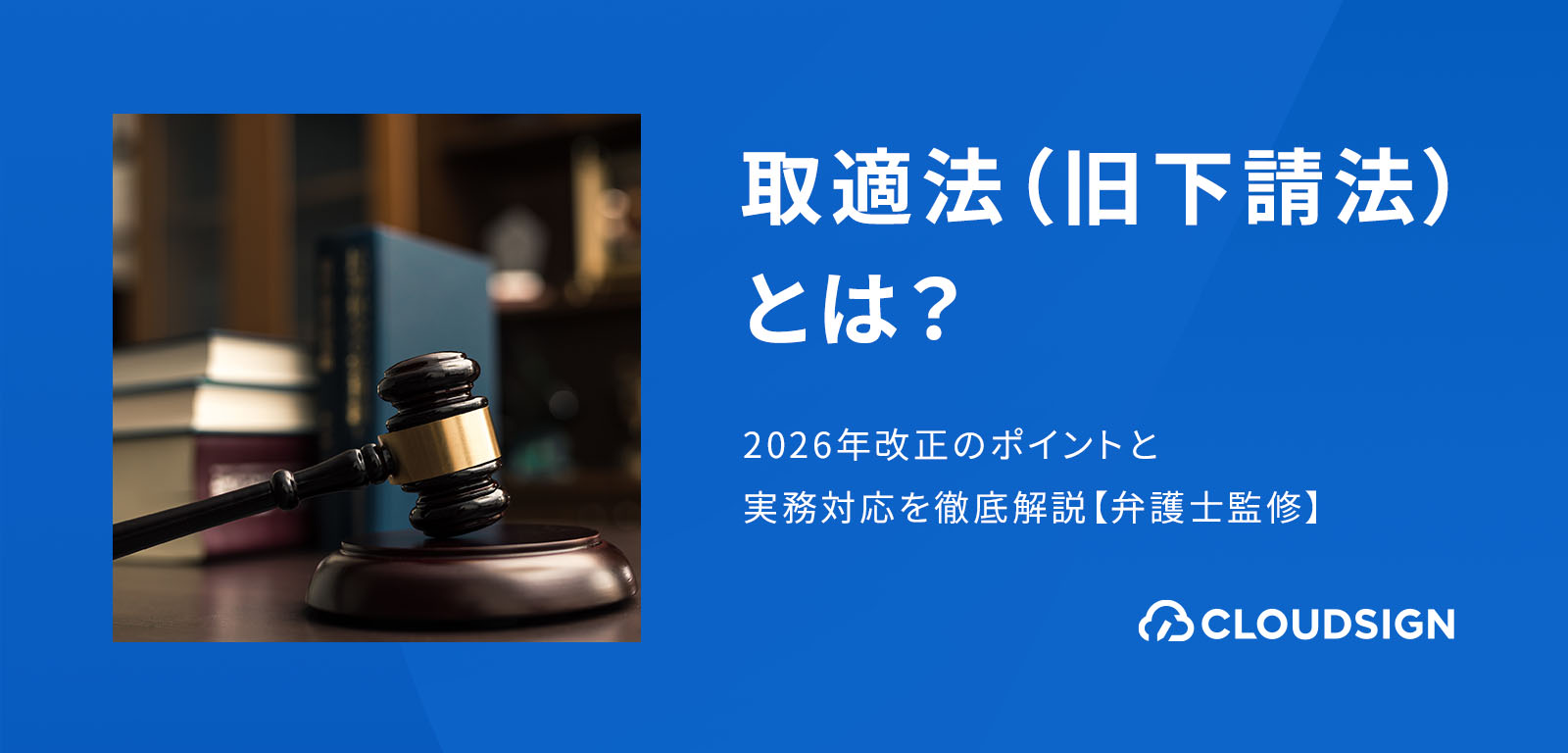
取適法(旧下請法)とは?2026年改正のポイントと実務対応を徹底解説【弁護士監修】
取適法(下請法) -
法律・法改正・制度の解説

フリーランス新法とは?主な義務や罰則、下請法との違い、相談窓口を解説【弁護士監修】
フリーランス新法 -
業務効率化の成功事例まとめ

Salesforceとクラウドサインを連携し、業務効率化に成功した事例5選
契約書管理インタビュークラウドサインの機能コスト削減電子契約の活用方法電子契約の導入電子契約のメリット業務効率化API連携 -
業務効率化の成功事例まとめ

kintoneとクラウドサインを連携し、業務効率化に成功した事例4選
契約書管理インタビュークラウドサインの機能コスト削減電子契約の活用方法電子契約の導入電子契約のメリット業務効率化API連携