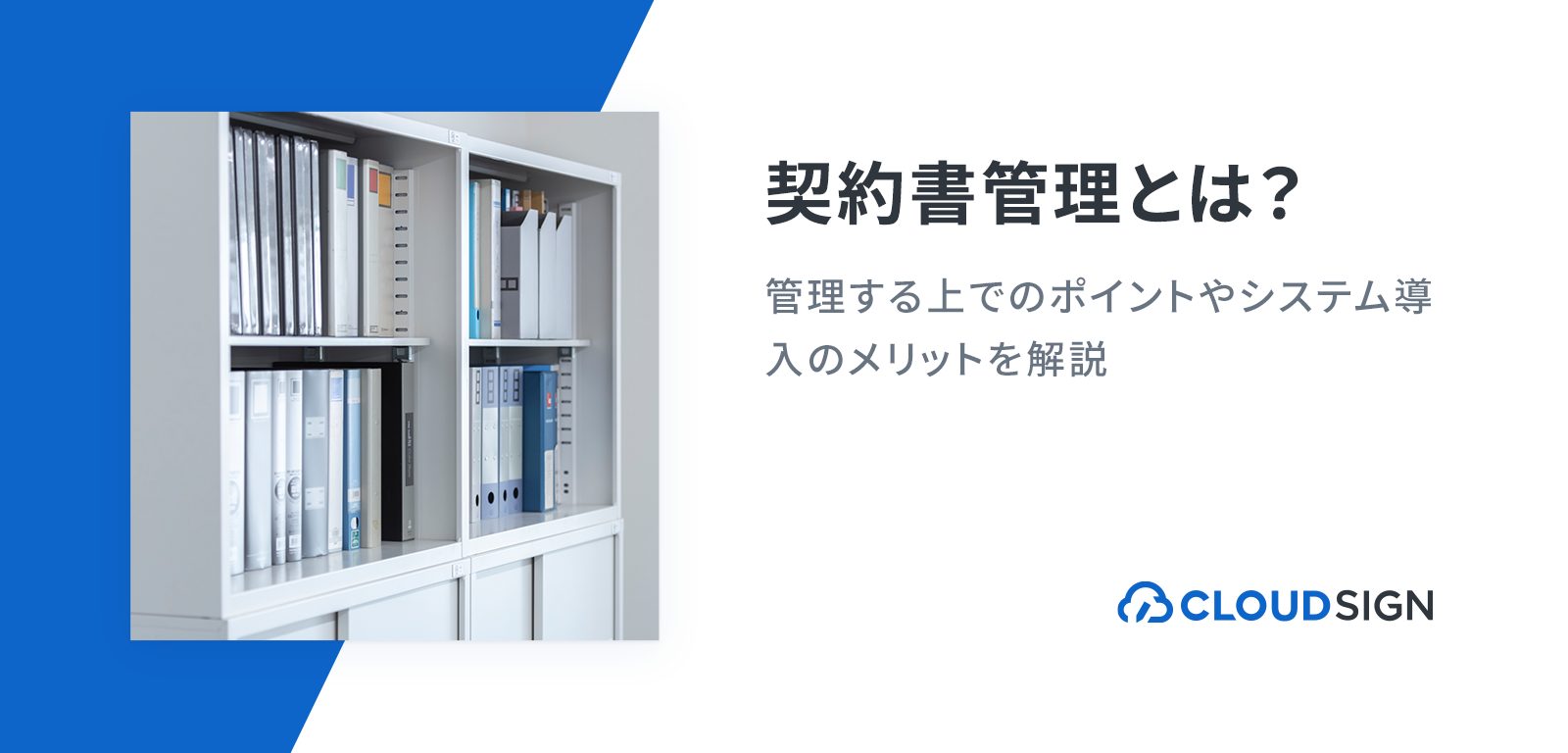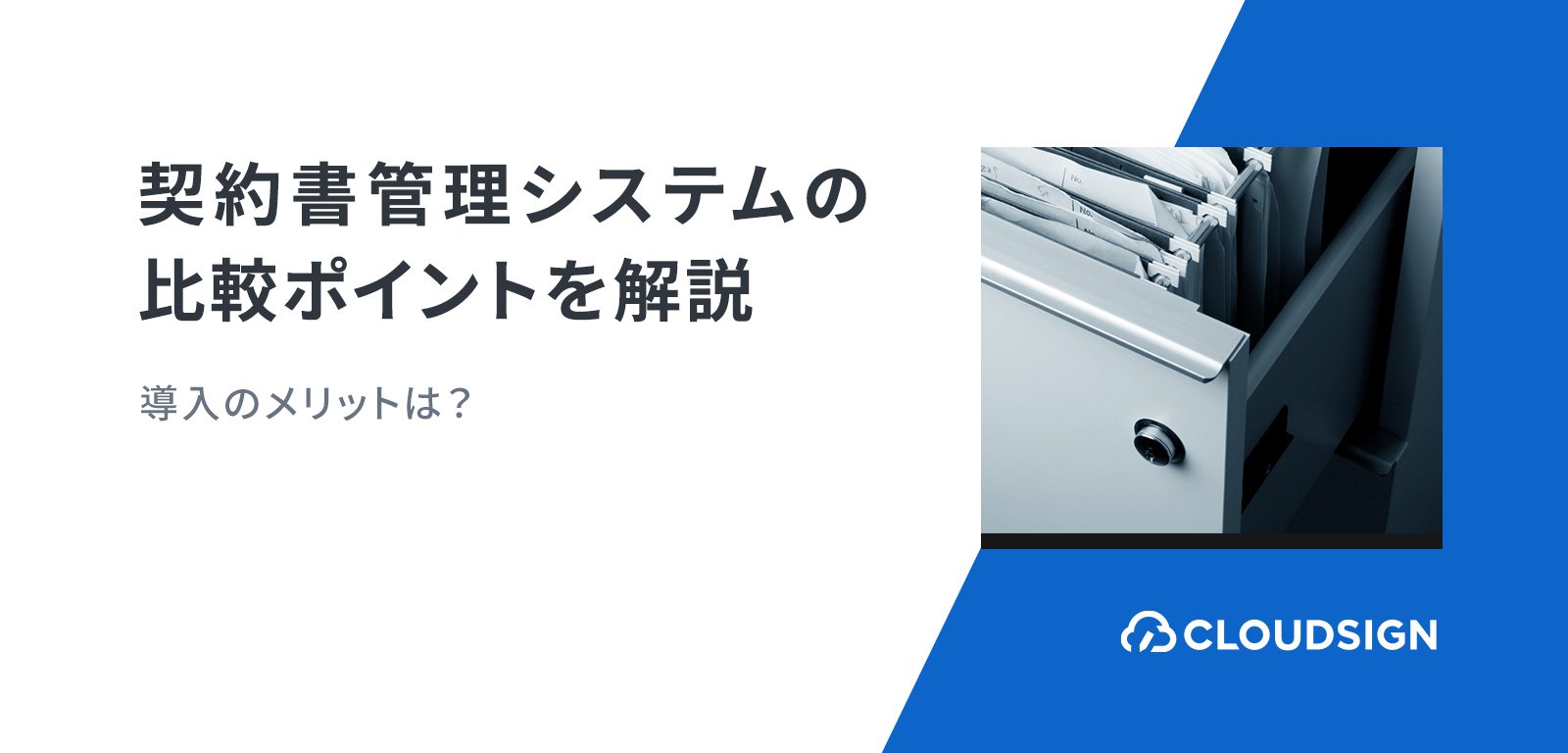遡及効とは?意味・具体例・相続への影響までわかりやすく解説
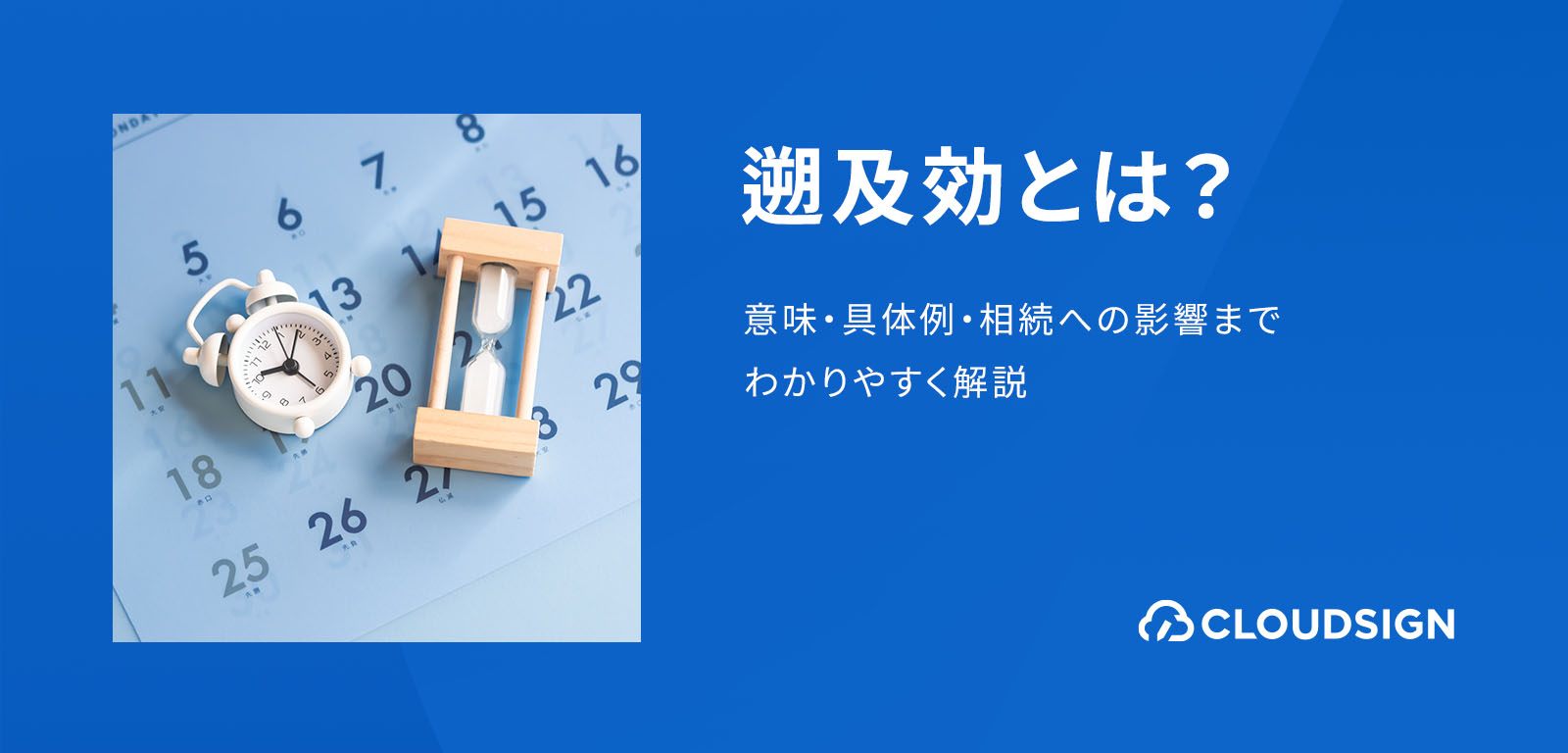
遡及効(そきゅうこう)とは、法律や契約の効力が、発効日より前の時点にさかのぼって適用されることをいいます。相続・契約・法改正など、企業法務や実務の中でも混乱を生みやすい概念のひとつです。
本記事では、遡及効の基本的な考え方と、契約書・法律運用における留意点をわかりやすく解説します。
なお、遡及効のような契約書の効力発生日はトラブルの元になりがちです。電子契約サービスを利用することで、契約締結日を正確に記録してトラブルを防ぎ、契約実務や管理の効率化とコンプライアンス強化が可能になります。電子契約の基礎をまとめた資料を無料でご用意しておりますので、こちらからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード
遡及効とは
遡及効(そきゅうこう)とは、契約や法律の効力が過去にさかのぼって及ぶことを指します。
たとえば企業間の契約などでは、通常「これから」に向けて効力が発生しますが、例外的に「効力発生日からさかのぼって効力が出る」ケースもあります。実務上の混乱を防ぐためにも、遡及効の基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。
過去にさかのぼって法的な効果が生じること
契約や法律の効力が、過去にさかのぼって発生することを「遡及効(そきゅうこう)」といいます。
たとえば、「この契約は2024年4月1日から有効」と定められていれば、実際の締結日が後日であっても、4月1日以降の行為には契約の内容が反映されます。
こうした遡及効は、当事者の合意による契約や、法律の改正、裁判所の判断などにより適用される場合があります。
どのくらい前までさかのぼれるのか
遡及効がどこまで過去に及ぶかは、法律で明確に制限されているわけではありません。
契約であれば当事者の合意により遡及日を定められますが、第三者に不利益が及ぶ場合などは無効とされることがあります。
法律や制度の変更について遡及させる場合には、憲法や法の原則に照らして問題がないか慎重に検討されます。
遡及効の問題点
遡及効には一定の合理性がある一方で、混乱や不公平を招くおそれがあります。
あとから新しいルールができた際に、過去にさかのぼって適用されると、「そのときは認められていたのに」と理不尽に感じられることがあります。
とくに税金、刑罰、行政処分などについては、過去にさかのぼって不利益な扱いをすることは原則として禁止され、憲法でも明記されています。これを「法の不遡及」と呼び、法の安定性を守るための重要な考え方とされています。
遡及効と将来効の違い
法律や契約の効力の発生時期には、「遡及効」と「将来効」という2つのパターンがあります。
・将来効:契約や法律が成立した日から、または未来の特定の日から効力を持つ
たとえば、「この契約は2025年1月1日から効力が生じる」と決めておけば、それ以降に起きたことにのみ契約が適用されます。これが将来効です。
将来効は、適用時期がはっきりしているため、混乱が少なく実務でも一般的です。
一方で遡及効は、過去の出来事に影響を与えるため、適用には十分な合意や法律上の根拠が必要になります。
遡及効は民法で定められている?
民法に遡及効に関する条文はない
民法には「遡及効」という言葉を定義した条文はありません。ただし、無権代理の追認や条件の成就、相殺、時効の完成など、過去にさかのぼって効力が生じる仕組みは一部に認められています。
なお、憲法39条には「不遡及の原則」が定められており、刑罰などについては過去への適用が禁止されています。
実質的に遡及効の効果を持つ条文がある
民法には、「遡及効」という言葉が明示されていなくても、結果として過去にさかのぼる効果を持つ条文がいくつか存在します。代表的なものを以下に紹介します。
【相続放棄の効力(民法939条)】
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。たとえば借金を抱えた被相続人が亡くなった場合、相続放棄すれば、債務の引き継ぎも発生しません。これは、放棄の効果が被相続人の死亡時点までさかのぼって適用される、典型的な遡及効の一例です。
【契約の取消し(民法121条)】
詐欺や脅迫などによって結ばれた契約を取り消すと、契約は最初から無効だったものとみなされます。これは、取り消しによって効力が過去にさかのぼり、契約当初から存在しなかったと扱われるため、当事者の権利・義務もそのように整理されます。
【認知の効力(民法784条)】
父が子を認知した場合、その効力は子の出生時にさかのぼって生じると定められています。これにより、認知された子どもには、生まれたときから親子関係があったとみなされ、相続権などの権利も同様に認められます。
多くの法律では遡及効が認められない理由
法律には「過去にさかのぼらない」という原則があります。とくに刑事罰や税制、行政処分などでは、あとから決まったルールで過去の行為を裁くことは基本的に認められません。ここでは、その背景にある考え方や、例外的に認められるケースについて解説します。
法の不遡及の原則があるから
法律の世界には、「法の不遡及(ふそきゅう)」という基本的な原則があります。これは、新しくできた法律は、それ以降の出来事にしか効力を持たないという考え方です。
たとえば、ある日から喫煙が禁止されたとしても、禁止される前に喫煙していた人がさかのぼって罰せられることはありません。
このように、行為当時に適法だったものがあとから違法とされるような状況は、社会的にも大きな混乱を招くため避けられるべきとされています。
憲法とも関係しているから
日本国憲法39条では、「行為時に適法だった行為は、後から処罰できない」とする刑法の不遡及原則が定められています。
たとえば、当時は合法だった行為が法改正により処罰の対象となると、本人には避ける手段がなく、不当な結果を招くおそれがあるため、この原則はとくに厳格に適用されます。
例外的に遡及効が認められるケース
すべての遡及が禁止されているわけではありません。とくに、契約する人にとって有利な変更あれば、例外的に認められることがあります。
たとえば、過去に課されていた税金があとから軽減される場合や、新たに権利が認められるような法改正があった場合などです。
ただし、遡及効を認めるかどうかは個別の法律や附則に明記されている必要があり、あくまで「例外的な扱い」である点には注意が必要です。
遡及効の具体例
実務では「過去にさかのぼる効力」が問題になる場面が少なくありません。契約、課税、行政処分など、分野によっては例外的に遡及が認められるケースがあります。
以下では、遡及効が具体的にどのような形で現れるのかを、代表的な事例ごとに整理します。
税制改正による課税の遡及
税制改正では、あとから決まった増税が過去にさかのぼって適用されることは基本的にありません。これは、納税する人が事前に税額を見込んで行動できるようにするためです。
一方で、減税については例外的に遡及が認められる場合があります。たとえば、所得税の引き下げが年初までさかのぼって適用される場合などです。
年金・社会保険制度の改正
年金や社会保険の制度改正では、内容によっては過去にさかのぼって適用されることがあります。
たとえば、支給要件の緩和があった場合、過去に資格を持っていた人が対象となるケースも見受けられます。
ただし、財源や制度維持の観点から、原則として将来に向けて適用され、遡及がある場合は法律の附則などで明記されます。
刑事・行政処分のルール変更
刑罰や行政処分に関するルールは、原則として過去にはさかのぼって適用されません。これは憲法39条に基づく「刑罰の不遡及」の原則によるものです。
たとえば、ある行為が法改正によって処罰対象となったとしても、改正前にその行為をしていた人にまで罰則が適用されることはありません。
一方、行政指導や許認可の要件緩和など、処分とは異なる対応については例外が設けられる場合もあります。
離婚後の養育費の支払い命令
家庭裁判所が養育費の支払いを命じる場合、実務では離婚成立時までさかのぼって養育費を請求できることがあります。
これは、子どもの生活保障という観点から、事後的に必要と判断された費用についても一定の遡及を認める考え方によるものです。
ただし、過去分の養育費が常に認められるとは限らず、当事者の生活状況や支払能力なども考慮されて判断されます。
労働条件の変更
就業規則の変更などにより労働条件が見直される際、過去にさかのぼって変更を適用することは原則できません。
たとえば、賃金体系や評価制度の見直しについて、改定前にさかのぼって減給するような運用は、労働契約法や不利益変更の原則に反するおそれがあります。
ただし、従業員の合意がある場合や、有利な変更であれば例外的に遡及が許容されることもあります。
民事訴訟における「契約の無効」の主張
裁判で契約の無効が認められた場合、その契約は「最初から存在しなかった」とみなされるのが原則です。
たとえば、詐欺や錯誤を理由に契約の取り消しが主張され、裁判で認められた場合、当初の契約時点にさかのぼって無効となり、支払済みの代金なども返還の対象になります。
このように、取り消しの主張が認められた結果として遡及的な効果が生じるケースも存在します。
相続問題に遡及効が影響するケース
相続に関連する手続きでは、「過去にさかのぼる効力」が重要になる場面があります。
相続放棄や認知などの法律効果が、被相続人の死亡時点にさかのぼって適用されることで、相続関係や遺産分割の前提が変わるケースも見られます。以下では、代表的な例を紹介します。
相続放棄して最初から相続人ではなくなった場合
相続放棄が認められると、民法上は最初から相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。
これにより、放棄者が遺産分割協議に加わる必要はなく、債務を引き継ぐこともありません。
遡及効によって「初めから相続関係にいなかった」と扱われるため、他の相続人の持分にも影響を及ぼします。
相続欠格・廃除による相続資格を喪失した場合
相続欠格や廃除が認められると、その者は相続の開始時点にさかのぼって相続権を失ったとみなされます。
たとえば、被相続人に対する重大な非行があった場合、家庭裁判所の判断などにより相続人から除外されます。
結果として、当初からその人物は相続人でなかった扱いとなり、遺産分割の内容にも影響します。
認知された子どもに相続権が発生した場合
父から認知を受けた子どもには、出生時にさかのぼって親子関係が認められます(民法784条)。
これにより、相続が発生した際には「子」としての立場を得て、法定相続分に基づいた権利を主張できるようになります。
認知の時期に関係なく、死亡時点で相続人として扱われる点に遡及効の特徴があります。
遺言無効が認められた場合
遺言書が無効と判断されると、その遺言による相続は最初からなかったものとして扱われます。
たとえば、偽造・変造された遺言や、遺言能力が否定された場合などが該当します。
この場合、法定相続に基づいて遺産が再分配されることになり、遡及的に相続関係が見直される可能性があります。
遡及効に関するよくある質問
ここでは、遡及効に関して実務でよく寄せられる疑問について、ポイントを絞って簡潔に解説します。
遡及効についてわかりやすく教えて欲しい
たとえば「この契約は4月1日から有効」と書かれていれば、契約書を結んだのが5月だったとしても、4月にさかのぼって効力が発生します。
こうした、後から決まったことが過去に影響を及ぼすしくみを遡及効といいます。
遡及効はなぜ禁止されている?
法律が過去の行為にさかのぼって適用されると、当時は合法だった行為まで処罰の対象になるおそれがあるためです。
こうした不公平を避けるため、日本国憲法では刑罰について「遡及的な適用」を原則として禁止しています。
遡及効は契約書でも有効?
契約の場合、当事者の合意があれば、効力を過去にさかのぼらせることは可能です。
ただし、第三者の権利を侵害する内容や、公序良俗に反する条項は無効とされる場合があるため、慎重な検討が必要です。
まとめ
遡及効とは、法律や契約の効力が過去にさかのぼって適用されることをいいます。刑法では「事後法による処罰」を禁じる不遡及の原則が憲法で明記されており、厳格に制限されています。
一方、民事の分野では、契約当事者の合意や法令の規定に基づき、一定の範囲で遡及効が認められることもあります。
実務では、契約の効力発生日を明示する、法改正の附則を確認するなど、適用範囲を正しく把握しておくことが、トラブルの予防につながります。
遡及効をはじめ、契約に関する様々なリスクを管理し、トラブルを未然に防ぐためには、契約プロセス全体の可視化と効率化が重要です。 契約書の作成から締結、保管までを一元管理できる電子契約サービスで法務リスクを低減することを検討してみてください。「クラウドサイン」をはじめとする電子契約サービスを利用することで、印紙税や郵送費のコスト削減はもちろん、バックデート(日付の遡り)防止など、コンプライアンス強化にも繋がります。「クラウドサイン」のサービスや電子契約について簡単にまとめた資料もご用意しておりますので、ご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約を検討する方に向け、電子契約の知識を深めるためにすぐわかる資料をご用意しました。電子契約サービスやクラウドサインについて詳しく知りたい方はダウンロードしてご活用ください
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
加藤高明
弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部