【2025年最新】施工体制台帳とは?作成義務・記入例・管理方法を行政書士が解説

建設業においては、許可の有無にはじまり、許可要件、工事種別、会計方法、請負契約の方法、書類作成・保存などさまざまな規制や法的義務があります。その中で、実際の建設現場においても作成が義務付けられている書類が「施工体制台帳」です。
施工体制台帳は、建設業法その他の法令により作成が義務付けられており、工事の進行体制や下請状況を整理した書類で、これらの整備を怠ると指導や処分の対象となります。この記事では、似た言葉である施工管理台帳と施工体制台帳の違いからはじめ、施工体制台帳の記載内容や、保存方法などを詳しく解説していますので、建設業に従事している方はぜひご一読ください。
目次
施工体制台帳とは?
施工体制台帳は、建設業法その他法令により工事を請け負った元請業者に対して、その工事に関わる下請業者も含めた施工体制全体(どの会社がどの範囲を担当し、どのような技術者がどのように配置されているか、どのような保険体制か、etc.)を記録・把握するために作成が義務付けられた台帳です。
俗に言う「グリーンファイル」の一部であり、安全書類類の中に含まれる書類のひとつでもあります。これに加えて施工体系図も作成し、工事現場の見やすいところに掲示しなければなりません。
施工管理台帳と施工体制台帳の違い
施工体制台帳と似たものに、「施工管理台帳」があります。これは、さまざまな作業が必要となる建設工事において、各工事種別の工程・進捗を管理し、建設工事を適切に施工していくための台帳です。進捗管理として、調査、杭打ち、コンクリート敷設など細かく工程を分けて工事完成までをスケジューリングし、工事進行具合を可視化するのに用いられます。
施工体制台帳と施工体制台帳は名前が似ていますが、施工管理台帳は日々変化する工事の状況を予定通りに進捗させるためのものであり、工程の詳細を管理します。一方、施工体制台帳は、その工事がどういった業者によって行われるか、適法に実施されているかをまとめるものです。
したがって、施工管理台帳は実際の工事内容に深く関わる実務的な側面が強く、施工体制台帳はどちらかというとコンプライアンス重視、トラブル回避、安全性確保といった部分に重きを置いています。
両者を混同して作成したつもりになっている、またはそもそもよくわかっていないと、思わぬトラブルを引き起こすため注意が必要です。
誰かわからない人が現場に出入りしている、資格者でない人が特殊な職務に携わっているということが起こらないよう、正確な施工体制台帳の作成が求められます。工事及び完成物の安全性に関わる部分ですので、正確に、実態確認を行ってください。
施工体制台帳の作成目的とは?
施工体制台帳を作成する目的として、次の3点が挙げられます。
- 施工における安全性・品質の確保
技術者の配置、下請構造の見える化、責任の所在を明確にすることで、工事中のトラブル(事故、施工ミス、周辺環境配慮等)の防止。 - 法令遵守(建設業法など)
施工体制台帳は法律で一定の条件で作成義務や保管・提出義務が定められており、それを遵守することで法的リスクを避ける。 - 施工管理・工程管理・コスト管理の効率化
関係者がどの会社・技術者がどこを担当しているかを明示できるので、責任範囲があいまいになりにくい。下請・協力会社との連絡調整、進捗確認もスムーズになる。
施工体制台帳は、建設業法その他の法令により作成が義務付けられている書類のため、作成することが前提ではありますが、上記に挙げた通り、建設業におけるトラブル防止や効率化といったメリットがあるため、確実に準備を進めておきましょう。
施工体制台帳は、誰が義務を負う?対象工事は?
施工体制台帳を作成する上で、「いつ作らなければならないか」「どの工事が対象か」を明確に把握しておくことが重要です。近年法改正等があり、基準額なども変動していますので、細心の注意を払って作成していきましょう。
作成時期は、契約締結後施工開始前です。もし、内容に変更がある場合は、その都度変更して、台帳を最新の状態にしておく必要があります。
また、発注者から直接請け負った建設業者(元請業者)が主として作成義務を負いますが、下請業者が、さらに下請契約を結んだ場合は、元請業者に通知しなければなりません。元請業者から情報提供などの協力を求められるケースもあります。
作成対象の工事は、主に以下の法令に基づいており、工事種別に関係なく発注者・請負形態・金額などによって、義務の有無が変わります。
| 工事区分 | 根拠法令 | 義務が生じる条件 |
| 公共工事 | 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条第1項及び第2項 |
発注者から直接請け負った公共工事で、下請契約を締結した場合は、 下請金額の大小に関わらず施工体制台帳の作成義務あり。 さらに、完成した写しを発注者へ提出する必要あり。 |
| 民間工事 | 建設業法第24条の8 | 特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事で、下請契約を締結しており、 その総額が一定以上である場合に義務が生じる。 最近の法改正でこの金額が5,000万円(建築一式工事では8,000万円)以上 |
公共工事においては、下請契約を締結した場合は、金額の大小に関わらず、必ず施工体制台帳の作成・提出義務を負います。下請契約を締結しない小規模・軽微な工事については、発注者と契約した時点で、施工体制が整理・把握されているため作成は不要です。
たとえば、公共施設の建設などは該当しますが、簡易な空調設備設置工事であって短期間で終わるようなものは該当しないでしょう。
表中の金額以上の工事を請け負う民間工事については、そもそも一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要です。しかし、特定建設業者が下請契約した場合のすべてに必要になるわけではなく、許可基準と同様の工事を請け負う場合に、作成義務を負います。たとえば、戸数の多いマンション建設、区画全体で行う住宅新築などがこれに該当します。
施工体制台帳は、建設業法その他法令で明確に義務付けられています。これを怠ると公共工事の場合は、指名停止、入札参加資格停止などの処分を受けるほか、民間工事も含めて建設業の許可そのものの停止、取消処分を受ける可能性があります。
事前に作成していなかったり、下請業者が追加されたにも関わらず、変更せず最新の状態になっていなかったりすると処分されることがあるためご注意ください。
施工体制台帳の記載項目
施工体制台帳に記載すべき事項は、建設業法施行規則第14条の2第1項で詳細に定められています。
- 作成建設業者に関する事項
イ 許可を受けて営む建設業の種類
ロ 健康保険等の加入状況 - 建設工事に関する事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所等
ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名等
ニ 作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名等
ホ 主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格等
ヘ 監理技術者補佐」を置くときは、その者の氏名及び補佐資格等
ト 主任技術者若しくは監理技術者又は監理技術者補佐以外のものを置くときは、その者の氏名、保有資格等
チ 建設工事に従事者の氏名、生年月日、年齢、職種、健康保険等の加入状況、資格等
リ 入管法上の特定技能、技能実習生の在留資格者の従事の状況 - 下請負業者に関する事項
イ 商号又は名称及び住所
ロ 当該下請負業者の許可番号及び許可種類
ハ 健康保険等の加入状況 - 下請負業者の請け負った工事に関する事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 当該下請負業者が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名等
ニ 下請負業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名等
ホ 下請負業者が建設業者であるときは、主任技術者の氏名、保有資格等
ヘ 下請負業者が主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、保有資格等
ト 当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
チ 建設工事従事者の氏名、生年月日及び年齢、職種、健康保険等の加入状況、資格等
リ 一号特定技能外国人及び外国人技能実習生の従事の状況
このように記載項目は多岐にわたるため、一から自社で作成すると効率が悪くなります。国土交通省で記入例を公開していますので、そちらを基に作成すると便利です。
(国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html)
台帳だけではなく、施工体系図、作業員名簿、台帳等のチェックリストもありますので、上記記載事項だけではわからない事項(主任技術者の専任性について等)も確認できます。
施工体制台帳の添付書類
施工体制台帳に添付すべき書類は、建設業法施行規則第14条の2第2項に詳しく定められています。
- 元請の請負契約及び下請契約に係る契約書(工事内容、請負代金、工期など建設業法第十九条第一項及び第二項に規定された内容記載)
- 主任技術者資格又は監理技術者の資格証の写し及びそれらの者の雇用契約書の写し(雇用期間の定めがないもの)
- 監理技術者補佐を置くときは、資格証の写し及びそれらの者の雇用契約書の写し(雇用期間の定めがないもの)
- 主任技術者若しくは監理技術者又は監理技術者補佐以外のものを置くときは、資格証の写し及びそれらの者の雇用契約書の写し(雇用期間の定めがないもの)
法令には定められていませんが、これら以外にも以下などの写しなどを添付しておくと便利です。記載事項の性質から考えると、これらを添付することで、より正確な台帳を整備できるでしょう。
- 建設業許可証
- 健康保険・雇用保険の加入がわかる書類(保険料納入通知書、概算保険料申告書等)
- 登記事項証明書
- 社員名簿
- 重機、危険物取扱に関する資格証
- 在留資格証
建設業に限らず許可申請等においては、申請書類の記載事項を証明する書類の添付が必ず求められます。これは、記載内容の根拠を明示するということです。施工体制台帳についても記載されている事項を証明する書類は必ず添付することが必要です。
特に公共工事において提出する際は、「根拠を確実に示すことができて」「現在有効なもの」を添付しなければなりません。
記載欄と資格証に齟齬がある、資格証の有効期限が過ぎている、適切な社会保険の加入が証明できる書類でない、一次下請業者に関してしか情報がない、といったことがあると不備として取り扱われます。不備として補正を求められた際に対応できればいいですが、対応できない場合(資格者ではない等)は契約違反となり、請負自体を取り消される可能性があります。
施工体制台帳の管理方法
これまで述べてきたように、施工体制台帳には、膨大な情報と添付書類が盛り込まれています。下請業者が追加されたり、契約内容が変更になったりすると、その都度台帳の内容や添付書類を変更し、常に最新の状態に保たなければなりません。そして、きちんと管理ができていないと、記載漏れや虚偽記載リスクを高めます。
また、現場に保管場所を確保する必要があり、工事完了後も保存期間が定められています。紙書類の場合は、紛失するリスクもあり、こういったリスクは行政処分リスクに直結するため注意が必要です。
施工体制台帳をクラウド管理するメリット
建設業法施行規則第14条の2第3項及び第4項では、施工体制台帳の作成・保管、添付書類の保管が現場で出力できる場合や、パソコン・タブレット上で映像確認できる場合には、電子化して作成・保管することが認められています。
台帳及び添付書類をクラウドで管理すれば、紙ベースで運用することのリスクを回避でき、一元管理できるようになります。またオンライン管理なので、当然現場とのデータ共有が可能となり、即時に変更・更新・出力できます。
施工体制台帳を電子化することは、リスク低減になるだけでなく、業務の効率化においても役立ちます。また、目まぐるしい法令改正を自身で確認・対応し、フォーマットを自分で変更するといった手間も省けるでしょう。結果、記載漏れ防止になるほか、コンプライアンス対応も可能にします。
なお、国土交通省のガイドライン(国不建第46号令和5年5月12日:電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドラインについて)によると、施工体制台帳が書面で作成されている場合であっても、請負契約が電子契約書になっていて、その契約書がパソコン・タブレット上で確認できれば、施工体制台帳に契約書を書面添付は不要とのことです。
また、公共工事において電子契約を締結しており、契約書の写しの提出について発注者が電子的な提出を認めている場合には、その方法で提出することもできます。
まとめ
施工体制台帳を正しく理解し、正確に作成することは、建設業を営んでいくうえで非常に重要です。くわえて、改正が頻繁に行われる法令に則って台帳を自社で作成・管理することの煩雑さ・大変さも実感されている方も、多いかもしれません。
紙の運用からクラウド運用へ移行していけば、業務効率化だけでなく法令遵守、コンプライアンス強化にもつながります。各種法令を踏まえたうえで、業務効率化を行えるよう、検討してみてください。
この記事の監修者
床本渡
行政書士
建設業許可申請・変更届・経営事項審査・入札参加資格審査など300件超の実績を持つ行政書士。制度に基づいた的確な提案と、事業者の状況に応じた柔軟な対応に定評があり、建設業に特化した実務サポートを得意とする。お客様の“今”を支え、“明日”へつなぐことを大切に「企業と事業成功の間」の架け橋になることを目標にしている。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
契約実務

工事請負契約書とは?目的や作成のポイント、締結する際の注意点を詳しく解説
契約書契約書ひな形・テンプレート建設業法工事請負契約書請負契約 -
電子契約の基礎知識
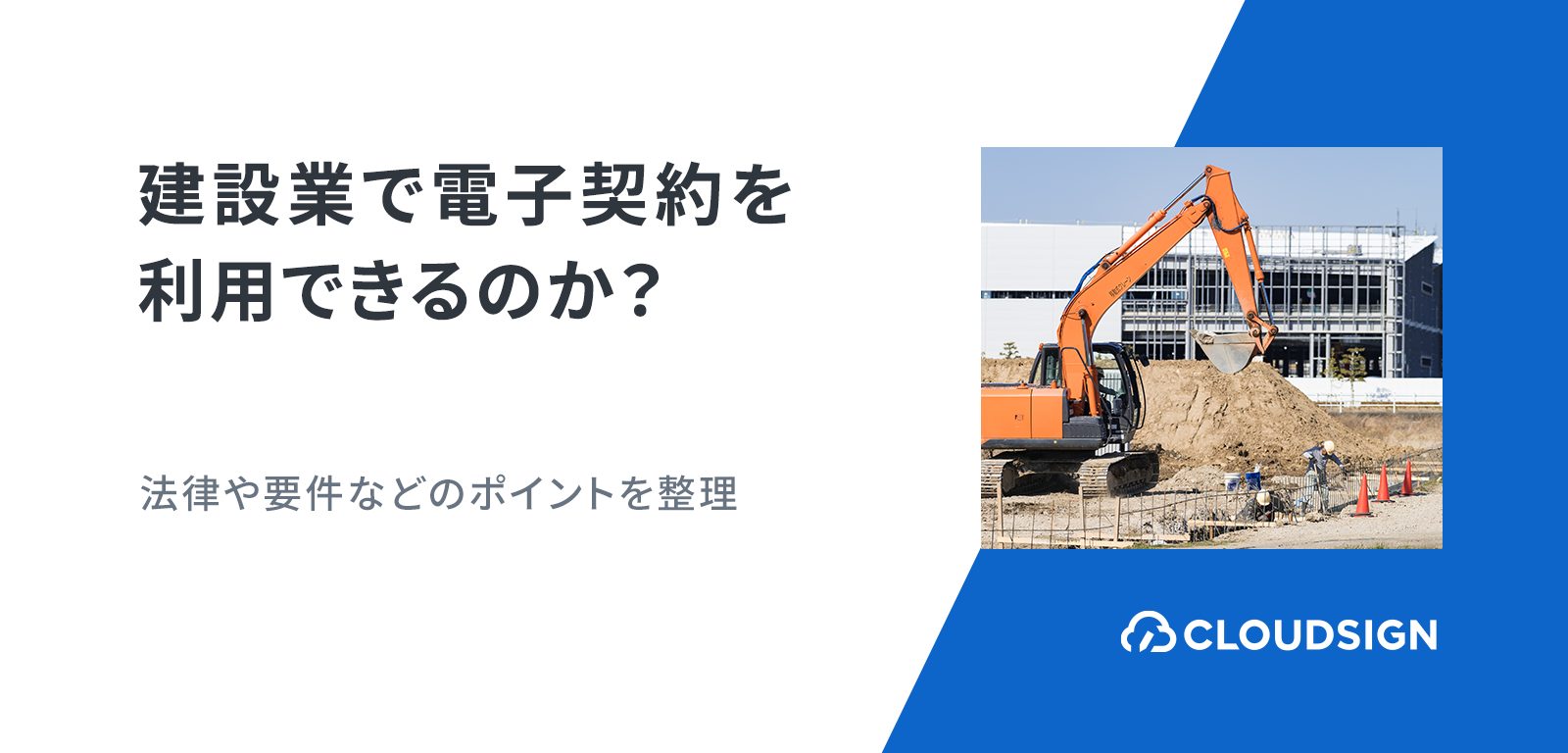
建設業で電子契約を利用できるのか?法律や要件などのポイントを解説
建設業法 -
電子契約の基礎知識

【2025年最新】電子契約サービスのシェアを最新の調査データから解説
電子契約とは -
契約実務

工事請負契約書に収入印紙は必要?例外的に不要なケースや印紙額を解説
契約書建設業法収入印紙工事請負契約書 -
業務効率化の成功事例まとめ

建設・建築業界で業務効率化に成功した事例4選
契約書管理インタビュークラウドサインの機能コスト削減電子契約の活用方法建設業法電子契約の導入電子契約のメリット業務効率化工事請負契約書API連携 -
電子契約の運用ノウハウ

建設業界の2024年問題とは?背景とDXによる業務効率化の方法をわかりやすく解説
電子契約の活用方法建設業法