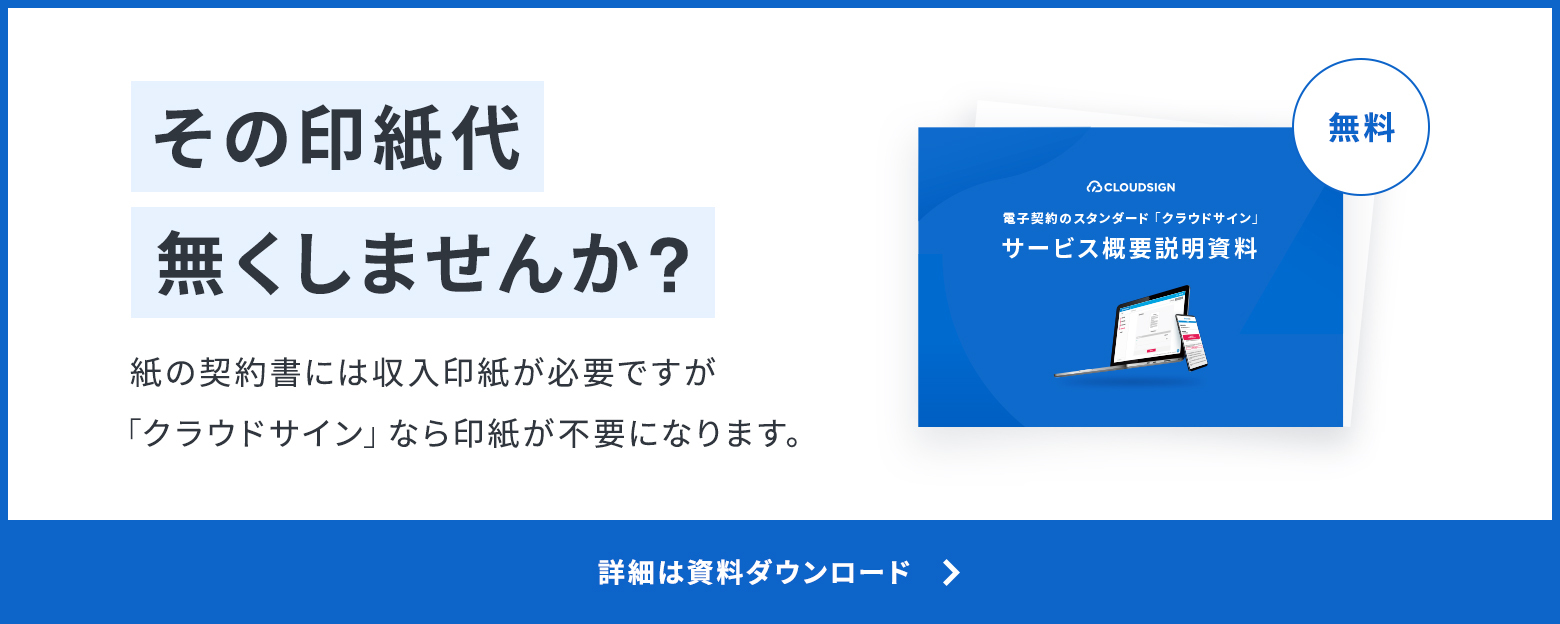工事請負契約書に収入印紙は必要?例外的に不要なケースや印紙額を解説

工事請負契約書とは、建物の新築や増改築などの工事を発注する際に、工事の内容や報酬などについて発注者と請負人のあいだで合意をとるために作成する契約書を指します。
工事請負契約を結ぶ際は、工事請負契約書を作成し発注者と請負人の双方が署名または記名押印する義務が建設業法第19条により定められています。
工事請負契約書は、印紙税の課税文書とされるため、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要となります。ただし、工事請負契約は印紙税額の軽減措置の対象となる可能性があるうえ、電子契約サービスを利用して締結した場合などの一部のケースでは印紙自体が不要になります。本記事では、工事請負契約書と収入印紙税について詳しく解説するので、工事請負契約の締結を控えている方は参考にしてみてください。
無料ダウンロード


クラウドサインでは、契約書の作成に携わる初心者の方に向けて収入印紙の基礎知識をまとめた資料をご提供しています。収入印紙とは何かという基本から、収入印紙を貼るべき文書とそうでない文書の見分け方、購入方法や貼り付ける位置といった情報を知りたい方はぜひご活用ください。
目次
工事請負契約書に収入印紙は原則として必要
工事請負契約書は、印紙税法別表第一の「第2号文書」に該当し、課税文書にあたります。そのため、原則として工事請負契約書を作成した発注者は、契約金額に応じた収入印紙を貼り付ける形により、印紙税を納める必要があります。
(印紙による納付等)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
引用元:印紙税方第8条|e-Gov 法令検索
工事請負契約書に収入印紙が不要となる例外的な3つのケース
工事請負契約書を作成した際は、原則として収入印紙を貼り付ける必要がありますが、以下の3つのケースでは例外的に収入印紙が不要となります。
・契約金額が1万円未満の場合
・申告納付について承認を受けた場合
・電子契約サービスを利用して締結した場合
とくに、電子契約サービスは収入印紙の貼付が不要である他、契約書の管理が容易になるなどさまざまなメリットがあり、近年導入する企業も増えつつあります。
ここでは、工事請負契約書に収入印紙が不要となる3つのケースについて簡単に解説します。
契約金額が1万円未満の場合
工事請負契約書は課税文書にあたりますが、収入印紙の貼付が必要となるのは契約金額が1万円以上の場合に限られます。したがって、契約金額が1万円未満の工事請負契約書は、課税文書に該当せず、収入印紙を貼り付ける必要はありません。
具体的には、例えば小規模な補修工事や点検作業などの契約書が該当する場合が考えられるでしょう。この場合、契約書自体の効力や法的拘束力は収入印紙の有無にかかわらず有効であり、課税対象外であるという理由で印紙税の負担が発生しない仕組みです。
ただし、工事請負において1万円未満のケースはあまり多くはないため、そこまで考慮する必要はないといえるでしょう。
申告納付について承認を受けた場合
工事請負契約書の収入印紙税は、通常、契約書に印紙を貼り付けて納付します。
しかし、一定の条件を満たす企業は、申告納付制度を活用することで、印紙を貼る手間を省き、まとめて印紙税を納付することが可能です。
申告納付制度は、印紙税法に基づき、税務署の承認を得た事業者が対象となります。この制度を利用することで、1年間に作成した課税文書にかかる印紙税を一括で申告・納付でき、契約書ごとに印紙を貼り付ける必要がなくなります。
ただし、収入印紙の貼付が不要となるだけであり、結果として印紙税は納めることになるため注意しましょう。
電子契約サービスを利用して締結した場合
電子契約で工事請負契約を締結した場合、紙の契約書を作成した場合とは異なり、収入印紙を貼る必要がありません。印紙税法における課税対象文書は、紙で作成される文書に限定されているため、電子契約は非課税とされるためです。
電子契約では、契約内容をデータ化し、電子署名やタイムスタンプによって法的な有効性が担保されます。これにより、収入印紙の費用を完全に削減できるだけでなく、書類の保管や管理コストも大幅に削減できます。
また、電子契約はオンラインでの締結が可能であり、契約締結までのスピードが向上し、ビジネス全体の効率化につながります。
さらに、契約書がデジタル化されることで、検索性が向上し、必要な書類を迅速に確認できるといったメリットもあります。
企業担当者は、電子契約の導入が印紙税の節約だけでなく、事務作業全般の効率化に貢献することを十分理解しておくべきといえるでしょう。
工事請負契約書に貼る印紙の金額
工事請負契約書は、印紙税法の課税文書にあたるため、契約金額に応じた額の収入印紙を貼り付ける必要があります。
ここでは、工事請負契約書に貼る印紙の金額を紹介します。各種契約書に貼り付ける収入印紙の金額については、以下の記事も参照してください。
原則として200円〜60万円
工事請負契約書は、課税文書の中の「第2号文書」にあたるため、契約金額に応じて以下の金額の収入印紙の貼付が必要となります。
| 契約金額 | 印紙税額(一通または一冊につき) |
|---|---|
| 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
建設工事請負契約は軽減措置の対象となるケースがある
建物建築工事請負契約書などの建設工事に関する契約書のうち、令和9年3月31日までの間に作成され、契約金額が100万円を超えるものについては、以下の表のとおり印紙税額が軽減されます。
| 契約金額 | 印紙税額(軽減前) | 印紙税額(軽減後) |
|---|---|---|
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
契約金額の記載がないものや、契約金額が100万円以下のものについては軽減措置の対象外となります。
参考:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁
工事請負契約書に収入印紙を貼らなかった場合のペナルティ
工事請負契約書を紙面で発行する場合は、原則として収入印紙の貼付が必要となります。
ここでは、印紙の貼付が必要であるにもかかわらず、適切な印紙を貼らなかった場合のペナルティについて解説します。
過怠税を徴収される
印紙が必要な工事請負契約書を発行したにもかかわらず収入印紙を貼らなかった場合、税務署により過怠税が課されます。過怠税とは、印紙税法違反に対するペナルティとして徴収される追加税で、通常の印紙税額に上乗せして納付しなければなりません。
原則として本来納付すべき印紙税額の2倍が過怠税として課されるため、トータルとして納める税額は本来の印紙税額の3倍となります。
例えば、1〜5億円の工事請負契約書を発行した場合は、本来であれば6万円の印紙税となりますが、印紙の貼付を怠った場合は12万円の過怠税が徴収されるため、本来の税額と合わせて18万円を納めなくてはいけません。
ただし、貼付の漏れに早期に気づき、自ら税務署に申告した場合は過怠税が軽減される可能性もあります。
刑事罰の対象となる
工事請負契約書への収入印紙の貼り付けを意図的に怠った場合、印紙税法に基づく刑事罰が科される可能性があります。
これは、課税文書を作成しながら故意に印紙を貼らずに脱税したり、収入印紙を不正に再利用したりする行為が、税法上の重大な違反とみなされるためです。
刑事罰として科される内容には、懲役刑や罰金刑が含まれます。具体的には、印紙税法第2条に基づき、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
第五章 罰則
第二十一 条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
二偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
引用元:印紙税方第21条|e-Gov 法令検索
これらの刑事罰は過怠税とは別に科されるため、収入印紙の貼付を怠ると経済的損失があるだけでなく、社会的信用の低下につながるリスクがあるといえるでしょう。
契約金額にかかわらず、電子契約であれば収入印紙の貼付は不要となるため、特別な事情がない限り電子契約での請負契約の締結を採用するのがおすすめです。
請負契約書と収入印紙に関してよくある質問
ここでは、工事請負契約書と収入印紙の関係についてよくある質問をいくつか紹介します。
請負契約書の収入印紙税はどちらが負担する?
請負契約書に貼付する収入印紙税は、印紙税法第3条により、契約書の作成者が負担する義務があります。また、複数の当事者が共同して契約書を作成した場合は、連帯して印紙税を納めなくてはなりません。
実務上は、発注者と請負人の双方が契約書を作成し、1部ずつ保管するケースが多いため、各自で自身が保有する契約書に収入印紙を貼る必要があり、それぞれが印紙税を負担することになります。
収入印紙税の配分については、法律上の定めはないため、契約書の作成時にどちらがどの程度を負担するのか、当事者間で納得できる形で取り決めるのが一般的といえます。
印紙税の負担について契約書に明記するのもおすすめです。たとえば、「収入印紙は発注者が負担する」などと取り決めておけば、トラブルを未然に防ぐことが可能でしょう。
収入印紙の貼り付けを怠ると契約自体が無効になる?
収入印紙の貼付を怠った場合でも、契約自体が無効になることはありません。
印紙税法は税務に関する法律であり、契約の有効性を規定するものではないからです。そのため、収入印紙を貼らないまま契約書を作成したとしても、当事者間で合意が成立していれば、契約書は法的に有効です。
ただし、収入印紙の貼付を怠ると税務面でのリスクが生じます。収入印紙を貼らなかったり、所定の額に満たない印紙を貼付したりした場合、税務調査で発覚すると、未納印紙税の納付に加えて過怠税が課されます。さらに、意図的な違反と判断されれば、刑事罰の対象となる可能性もあります。
以上のような事情から、収入印紙は契約の有効性には直結しないものの、適切に貼り付けることで後の問題を防ぐことが重要です。契約締結時には、印紙税の正確な取り扱いを徹底しましょう。
印紙税を節約するにはどうしたらいい?
印紙税を節約するには、電子契約の導入を検討するのがおすすめです。
電子契約は、印紙税法の課税対象である「紙の文書」に該当しないため、印紙税が課されません。これにより、印紙税だけでなく、書類の保管コストや郵送費用も削減できます。
また、書面で契約書を発行する必要がある場合は、契約金額を税抜表示にすることによって節税が可能です。
例えば、契約金額が税込1億1000万円の場合は、通常だと6万円の収入印紙が必要となりますが、税抜の1億円表示とすれば、3万円の収入印紙で済みます。
税抜き表示にしても実際に請負人に支払う金額は変わりませんが、トラブル防止のために事前に相談して承認を得ておくのが良いでしょう。
電子契約で収入印紙が不要となる理由については、下記の記事も参照してください。
無料ダウンロード


下請事業者(中小受託事業者)と取引をしている企業様の間で、意図せず下請法に抵触してしまう事例は少なくありません。そこで本資料では、下請法の中でも特に違反が生じやすい項目をチェックリスト形式でまとめました。本チェックリストを活用することで、下請法違反のリスクを早期に発見し、未然に防ぐことができます。
まとめ
本記事では、工事請負契約書における収入印紙の運用について詳しく紹介しました。
工事請負契約書は印紙税法上の課税文書にあたるため、原則として収入印紙の貼付が必要です。しかし、電子契約で契約書を締結した場合は、印紙税の納付が不要となる上、管理面でも様々なメリットがあります。
信頼性の高い電子契約サービスを利用して、スムーズなDX化を実現すれば、節税対策になると共に、企業の大幅な業務効率化を図れるでしょう。
当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」はアップロードとメール送信のみで契約締結までの作業を完了することができ、取引相手に負担をかけずに電子契約の導入が可能です。契約書の電子化を検討している場合は、ぜひご利用ください。
なお、クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でご入手できますので、ぜひご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
契約実務

【無料ひな形付き】準委任契約とは?請負契約・委任契約との違いを解説
契約書契約書ひな形・テンプレート業務委託契約書準委任契約請負契約 -
契約実務

工事請負契約書とは?目的や作成のポイント、締結する際の注意点を詳しく解説
契約書契約書ひな形・テンプレート建設業法工事請負契約書請負契約 -
契約実務
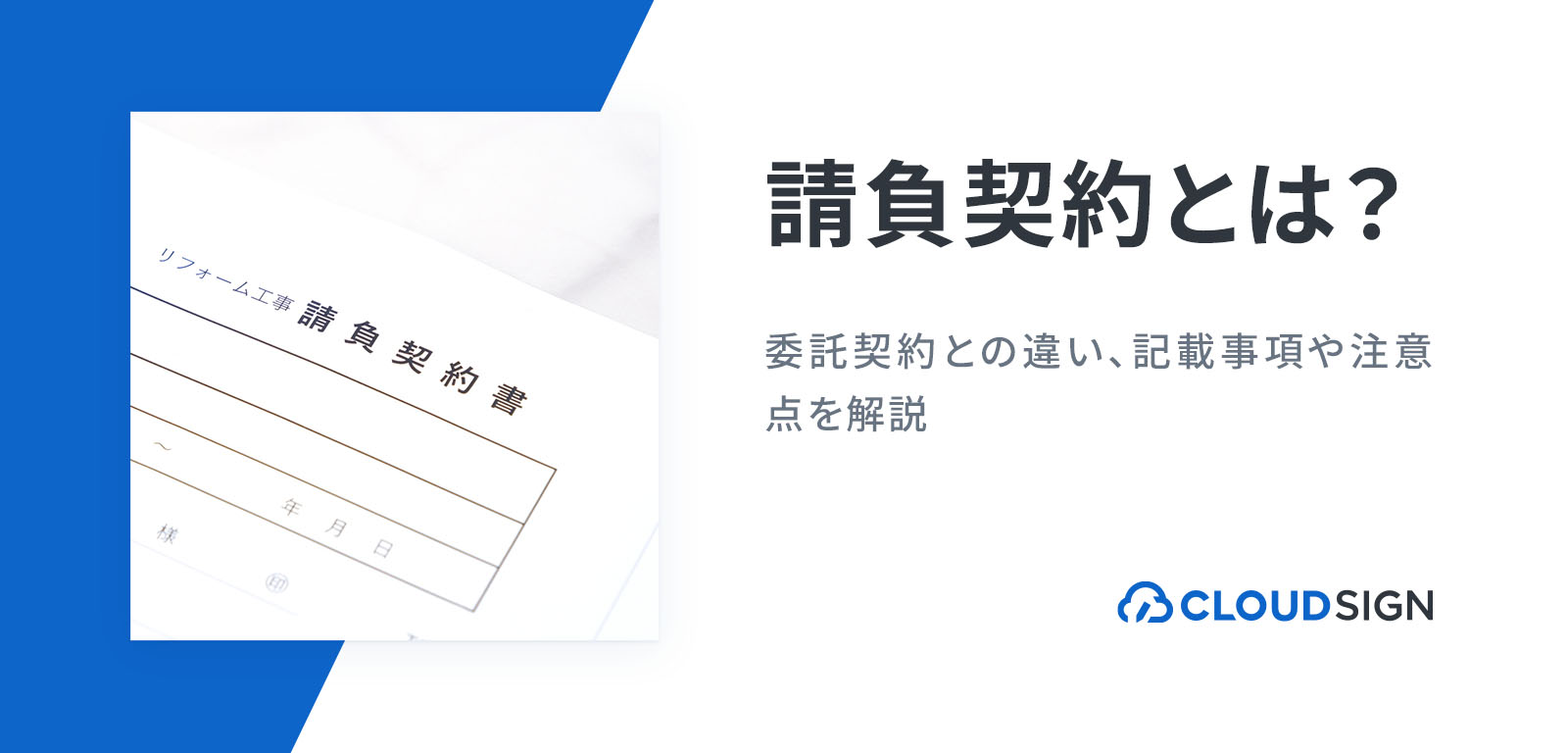
請負契約とは?委託契約との違い、記載事項や注意点を解説 建築工事請負契約書のテンプレート付き
契約書ひな形・テンプレート業務委託契約書請負契約 -
契約実務
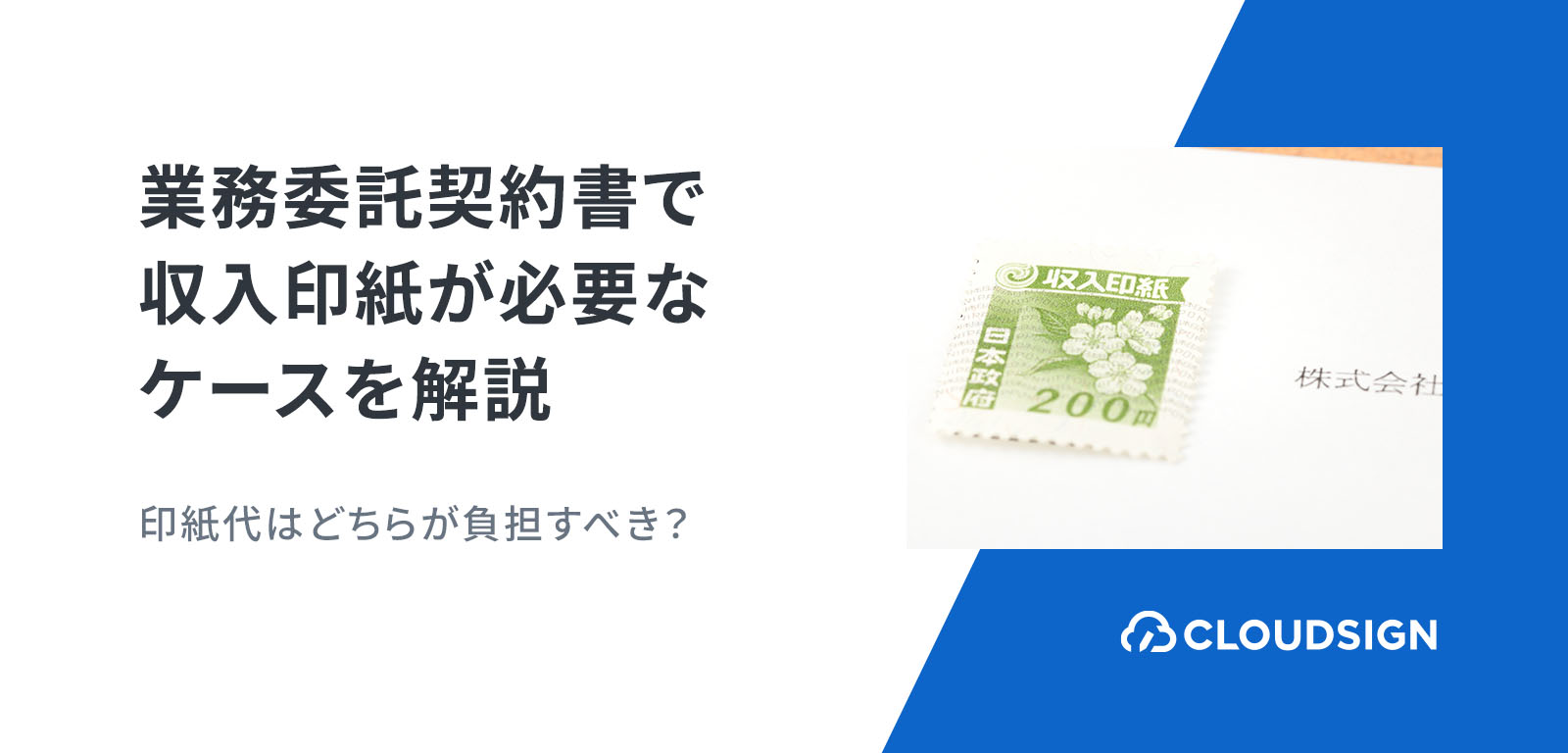
【金額一覧あり】業務委託契約書で収入印紙が必要なケースとは? 印紙代やどちらが負担すべきか解説
契約書業務委託契約書 -

請負契約書とは?委任契約との違いや書き方の解説
契約書業務委託契約書請負契約