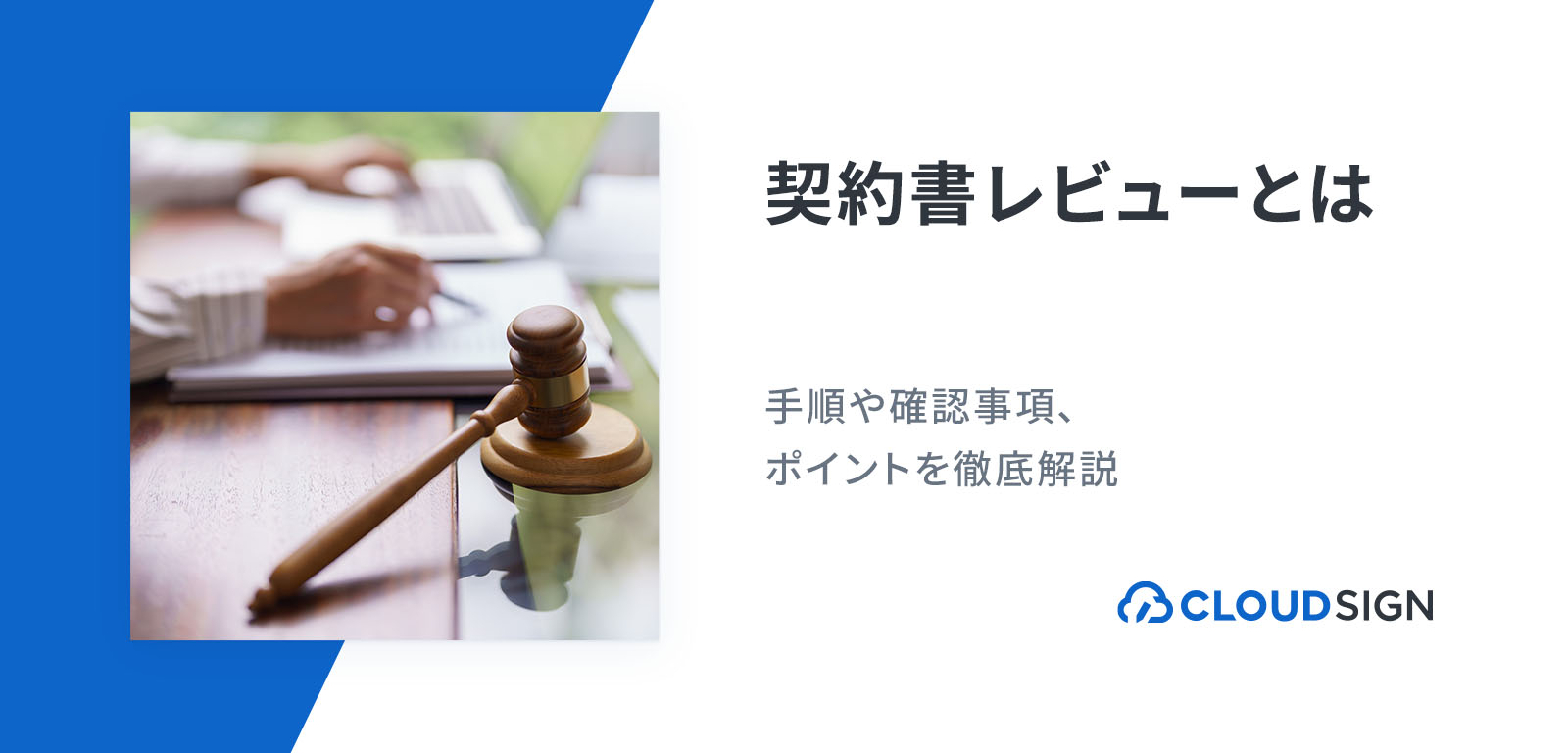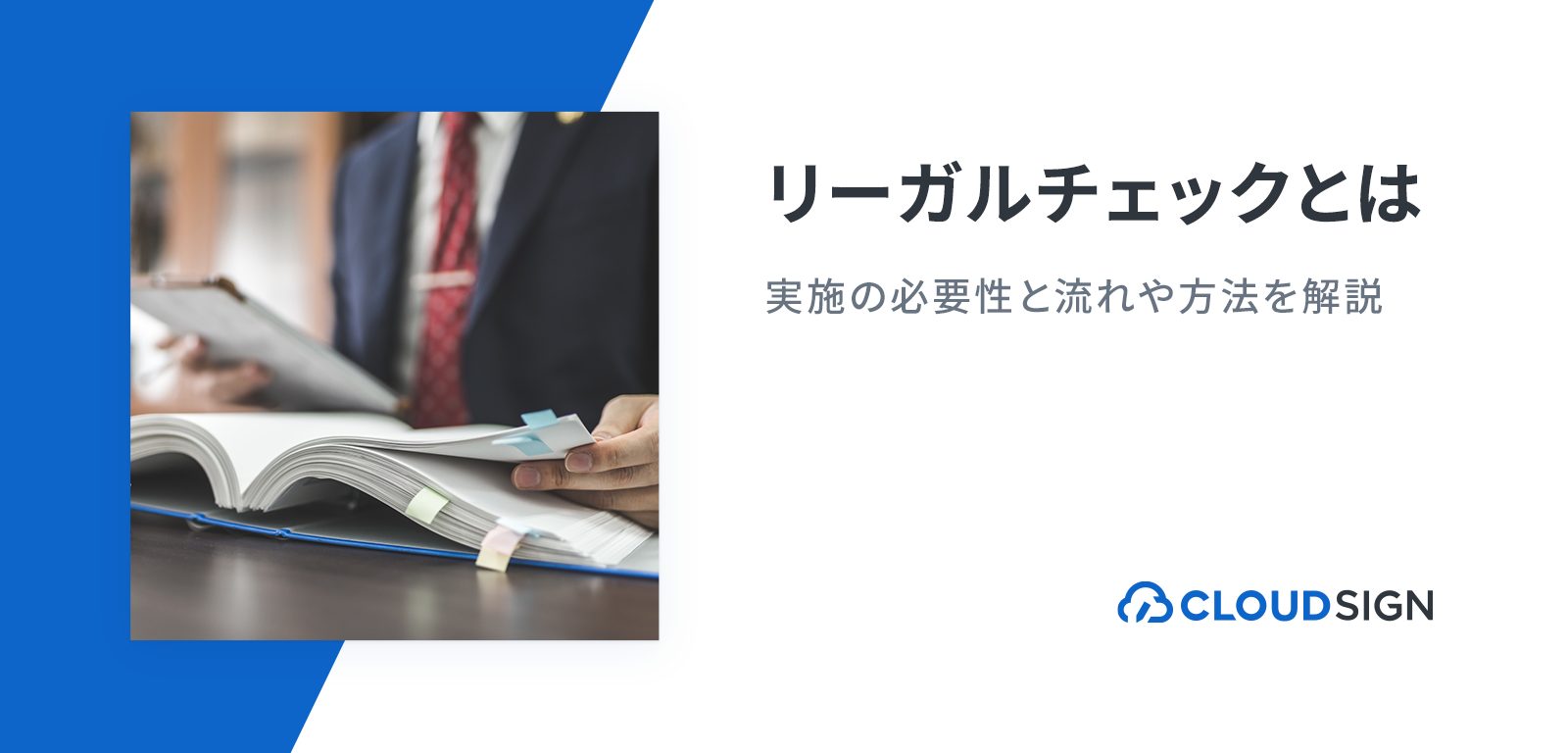契約書にAIは活用できる?作成・レビュー・管理で利用するメリットや注意点を解説

契約書の作成や確認といった業務にAIを取り入れる企業が増えています。近年では、契約書のドラフトをAIが作成したり、条文の表記揺れや抜け漏れを自動でチェックしたりと、実用的な機能が続々と登場しています。
これにより、契約書業務にかかる時間を大幅に短縮できるほか、法務担当者の負担軽減やヒューマンエラーの防止といったメリットも期待できます。
ただし、AIはあくまで補助的なツールであり、すべてを任せきるのは適切ではありません。最終的な判断や修正は、人が責任をもって行う必要があります。
当記事では、契約書業務においてAIができることや導入によるメリット、活用時の注意点などをわかりやすく解説します。
目次
契約書業務にAIを活用する企業が増加している
契約書業務へのAI導入は、もはや一部の先進企業だけの話ではありません。
2020年代に入ってからは、働き方改革やリモートワークの浸透を背景に、契約書の作成・チェック・管理にかかる時間や手間を見直す動きが進んでいます。その中で、AIの力を借りて業務を効率化しようとする企業が増えてきました。
とくに、法務人材の不足や業務の属人化といった課題を抱える現場では、AIの導入が強い関心を集めています。
さらに、こうしたツールは企業だけでなく、契約書を自分で管理しなければならないフリーランスの方にも、便利な存在になりつつあります。
契約書に関してAIでできること
AIは契約書に関するさまざまな作業に活用されています。ここでは、作成・レビュー・管理・分析の4つの観点から、AIにできることを紹介します。
契約書の作成
AIを使うことで、契約書のドラフト作成の負荷軽減が見込めます。テンプレートや過去の契約書のデータをもとに、自動で条文の提案を行ってくれるため、ゼロから文章を考える必要がありません。
契約の種類や内容、業界の慣習に応じた条文を出し分けてくれる機能もあり、たとえば秘密保持契約や業務委託契約などのよくある契約書は短時間で完成できます。
契約書のレビュー
契約書に潜むリスクを事前にチェックする契約書レビューにおいてもAIを活用することができます。たとえば、以下のような指摘をしてくれます。
・責任の範囲が曖昧である
・解除条件が抜けている
契約書の不備を自動で指摘してくれるため、目視での見落としを減らすことができます。
また、法律の観点や業界ごとの基準に基づいた条文改善案を提示してくれることもあり、契約書のクオリティを上げるのに役立ちます。
契約書の管理
AIは契約書の保管や進行状況の管理もサポートしてくれます。
たとえば、当社の提供するクラウドサインでは「AI契約書管理機能」の利用が可能です。これは契約書の合意締結完了後、締結済み書類のPDFファイルをAIが読み取り、契約書情報を自動で解析・入力し、効率的に契約書を管理することができる機能です。
契約書の分析
たくさんの契約書を扱う企業では、AIを使った分析も効果を発揮します。
たとえば、自社の契約条件が過去と比べてどう変化しているか、取引先ごとのリスク傾向はどうかといった点を、AIが自動で抽出・可視化することが可能です。
分析結果を活用することで、今後の契約交渉や社内ルールの見直しにもつなげやすくなります。
契約書業務にAIを使うメリット
契約書の業務にAIを使うメリットとして、「作業時間の短縮」「担当者ごとのスキル差を補える」を具体的に紹介します。
契約書業務にAIを取り入れることで、単なる作業の効率化にとどまらず、業務の質そのものを底上げできるようになります。
作業時間の大幅短縮
AIを活用すれば、数十ページにおよぶ契約書でも、ベースとなるドラフトを数分で自動作成できます。
従来、人の手で何時間もかかっていた契約書のレビューや修正も、AIによって一気に効率化できます。
条文ごとのチェックや、関連条項の整合性確認も自動で行えるため、工数を大幅に削減できます。
これにより、法務担当者は、本来注力すべき業務に集中できるようになります。
担当者ごとのスキル差を補える
AIは、過去の契約書データや法令情報をもとに、一定のレビュー水準を保った提案や修正案を提供してくれます。
これにより、経験の浅い担当者であっても、最低限の法的観点をおさえたレビューが可能になります。
属人化しがちな契約書業務の均一化が進み、チーム全体のクオリティ向上にもつながります。
また、AIによるレビュー結果を通して、法務スキルの教育ツールとしても活用できます。
人手不足の解消
法務担当者の増員が難しい企業や、専任の法務担当者がいない企業が、AI契約書レビューサービスを導入することで、実質的に「AIが法務担当者の一翼を担い」人手不足の解消につながります。
ここでひとつ、「クラウドサイン レビュー」を導入して業務負荷軽減に成功した事例をご紹介します。
学校法人追手門学院様は、法務専門部署がなく「ひとり法務」状態で業務負荷と属人化が課題でしたが、働き方改革の一環でAIレビューツールの「クラウドサイン レビュー」を導入されました。これにより、レビュー時間が大幅に短縮され、担当者の精神的な負担も軽減されるなど、実質的な人手不足の解消につながりました。
コスト削減
AIを契約書業務に導入することは、弁護士費用という直接的なコスト削減につながりますが、それだけではなく、従業員がレビューに費やす時間という間接的なコストも大幅に削減し、企業の利益向上につながります。
こちらも「クラウドサイン レビュー」を導入し、コスト削減をかなえた事例をご紹介します。
テイクアンドギヴ・ニーズ様では、法務専任者がおらず、多くの契約書レビューを顧問弁護士に依頼していたため、業務負荷とコストが課題でした。そこでAI搭載の「クラウドサイン レビュー」を導入されました。これにより弁護士への依頼件数が減り、コスト削減に成功され、現在では全体の2〜4割の契約書をAIのみで処理しているそうです。
契約の管理や比較がしやすくなる
AI搭載の契約管理ツールでは、過去の契約書との比較も簡単に行えます。
たとえば、類似契約との相違点や変更履歴を一目で確認できるため、見直しや再交渉の判断にも役立ちます。
AIは人が気づかないポイントに気づくことができたり、ヒューマンエラーを防いだりできるという点でも有用です。
契約書業務にAIを使う際のポイント・注意点
契約書業務にAIを導入する際は、メリットだけでなく、注意点にも目を向けましょう。
AIは便利ですが、使い方を誤るとリスクが発生します。ここでは、AIを使う際の注意点を紹介します。
AIは補助として使い、最終判断は人間が行うこと
AIは契約書の作成やレビュー作業の効率化に役立つ一方で、最終的な法的判断や責任は人間が担うべきです。
たとえば、契約相手との力関係や、過去の交渉経緯、取引全体のリスクを総合的に判断するのは、AIには難しいです。
AIの提案どおりに契約を締結した結果、取引先との認識にズレが生じてトラブルに発展するケースは十分に考えられます。
とくに、「この記載の仕方できちんと伝わるか、相手に誤解されないか」などの最終判断は、目視で行った方がいいでしょう。
AIに任せる範囲と任せない範囲を明確にすること
AI導入時は、どこまでをAIに任せ、どこからを人が担うのかをあらかじめ線引きしておくことが重要です。
この基準が曖昧だと、担当者ごとに対応が異なり、社内の品質がばらつく要因になります。
【AIに任せてOKな領域】
・定型条文のチェック・修正
・契約書のドラフト作成(初稿レベル)
・誤字脱字や表記ゆれの自動検出
こういった作業はパターンが決まっており、AIが得意とする分野です。事前に用意されたテンプレートや過去事例を学習させることで、作業精度も高まります。
【AIに任せるべきではない領域】
・取引背景に応じた条文の取捨選択
・複雑な契約(M&A、合弁事業など)の構成設計
・戦略的判断や交渉内容を踏まえた意思決定
ビジネス上の判断力や直感、交渉力などは、AIには期待できません。AIに委ねるとリスクを見逃す恐れがあります。これらの判断は、必ず人が行うようにしましょう。
AIを使うことを前提とした業務フローを確立すること
AIを導入する際は、ツールだけでなく業務フロー全体の見直しも重要です。
たとえば、一部の人だけがAIを使っていたり、従来の手作業と併用していたりすると、かえって非効率になりがちです。
AIを活用するなら、全員が共通の流れで作業できるように整えることが大切です。
たとえば、一次レビューをAIに任せ、人はリスク判断などの要点確認に集中すれば、全体の作業時間が大幅に短縮されます。
さらに、AIのチェック結果をもとに修正履歴を記録・共有する仕組みをつくれば、属人化の防止や品質の標準化にもつながります。
生成AIと法務特化AIの違いや使い分けを意識すること
AIと一口にいっても、ChatGPTなどの汎用的な生成AIと、契約書や法律に特化した専門AIとでは、用途も精度も大きく異なります。
生成AIは幅広い言語生成に強みがあり、自然な文章の提案やブレストには向いていますが、法的な正確性や専門用語の扱いには限界があります。
一方、法務特化AIは、契約書の条文構成や法令対応などの分野に最適化されており、契約審査やリスク検出、比較分析といった高度な業務に適しています。
たとえば、同じ「契約書のレビュー」でも、生成AIでは見逃してしまう業界特有の表現ミスを、法務特化AIであれば検出できることもあります。
契約書AIツールを導入する際の選定ポイント
契約書AIツールは便利ですが、どのツールでも同じ効果が得られるわけではありません。自社の契約業務に合ったものでないと、思ったような効果を得られない可能性もあります。
とくに、ツールが対応できる範囲とサポート体制の2点はしっかり確認しましょう。
自社の契約内容に対応した機能があるか
AI契約書ツールには、対応できる契約の種類や条文のレビュー精度に違いがあります。
たとえば、秘密保持契約(NDA)や業務委託契約などの汎用的な契約に強いツールもあれば、M&Aやライセンス契約など専門性の高い分野に特化したものもあります。
自社でよく扱う契約の種類にツールが対応しているか、契約書のチェック項目が業務に見合う深さかを事前に確認しましょう。
サポート・継続的なアップデートがあるか
AIツールは導入後のサポートや継続的なアップデートがあることも非常に重要です。
法改正や契約実務の変化に対応するには、開発側が機能を定期的に更新してくれることが前提となります。
さらに、導入初期のトレーニングや操作説明、ヘルプ対応の充実度も、スムーズな運用に直結します。
特に、法務部門にAIツールの運用経験がない場合は、導入後に質問できる窓口があるか、使い方に関するチュートリアルが整っているかも確認しておくと安心です。
クラウドサインはAI契約書管理機能や契約書レビューなどAI機能も充実
これまで解説してきたように、クラウドサインでは、契約書管理をさらに効率化するための「AI契約書管理機能」やAIで契約書のレビューができる「クラウドサイン レビュー」が提供されています。
クラウドサインのAI契約書管理機能では、さまざまな契約書に対応しており、情報の整理や検索、活用がしやすくなるのが特徴です。
対応可能な書類
クラウドサインのAI契約書管理機能では、以下の2種類の書類に対応しています。
【1.クラウドサインで締結した書類(受信した書類も含む)】
クラウドサイン上で電子契約として締結された書類は、AIによる自動解析の対象となります。契約日や契約金額などの情報が自動で抽出・登録され、手動での入力作業が不要になります。
【2.書類インポート機能を使用してインポートした書類(2023年4月より解析対象)】
過去に紙で締結した契約書や他の電子契約サービスで締結した書類をPDF化し、クラウドサインにインポートすることで、AIによる解析が可能となります。従来の紙ベースの契約書もデジタル管理の対象となり、業務の一元化が図れます。
対応可能な契約類型
クラウドサインのAI契約書管理機能では、以下のような多様な契約類型に対応しています。
・業務委託契約書
・請負契約書
・秘密保持契約書
・サービス利用契約書
・雇用契約書
・賃貸借契約書
・労働派遣契約書
・請求書
・発注書
・受注書
・検収書
・納品書
一般的かつ幅広い類型に対応しているため、多くの人や会社が利用できます。
自動入力される内容について
クラウドサインのAI契約書管理機能では、契約書から主要な情報を自動で抽出・入力できます。対象となるのは以下の7項目です。
・契約締結日
・契約開始日
・契約終了日
・自動更新の有無
・解約通知期限
・取引金額
・契約相手の名称
自動入力された内容は、あとから手動で修正することも可能です。
クラウドサインレビューについて
「クラウドサイン レビュー」は、AIで質の高いレビューを誰でも行える契約書チェック支援サービスであり、リーガルチェックにかかるコストを大幅に削減してくれます。また、契約書ファイルをアップロードするだけで、AIが自社に不利な条項や欠落条項を指摘し、修正・追加すべき文案を提案してくれます。
さらに「クラウドサイン レビュー」は最新の法改正に対応しており、条文の文脈を読み取り、条文ごとのリスクを瞬時に判定・抜け漏れもチェックします。また、自社基準をあらかじめ設定することで、属人化せず誰でも同じ質で契約書チェックをすることが可能です。
無料ダウンロード


クラウドサインでは契約業務を支えるAIアシスタント「クラウドサイン レビュー」の概要をまとめた資料をご用意しました。契約書レビューの自動化を検討している方はぜひダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)まとめ
契約書業務にAIを取り入れる企業が増え、作成・レビュー・管理の効率化が進んでいます。業務効率化や、ヒューマンエラーの防止、属人化の改善など、様々なメリットがあります。
しかしAIは、取引相手との関係性や、ビジネス的な判断は得意としていないため、最終チェックなどは人が目視で確認すべきです。導入時には、任せる業務の範囲や業務フローを明確にして運用することが大切です。
AIを活用し、契約書のレビューから締結までDX化するには「クラウドサイン」と「クラウドサイン レビュー」をぜひご検討ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部