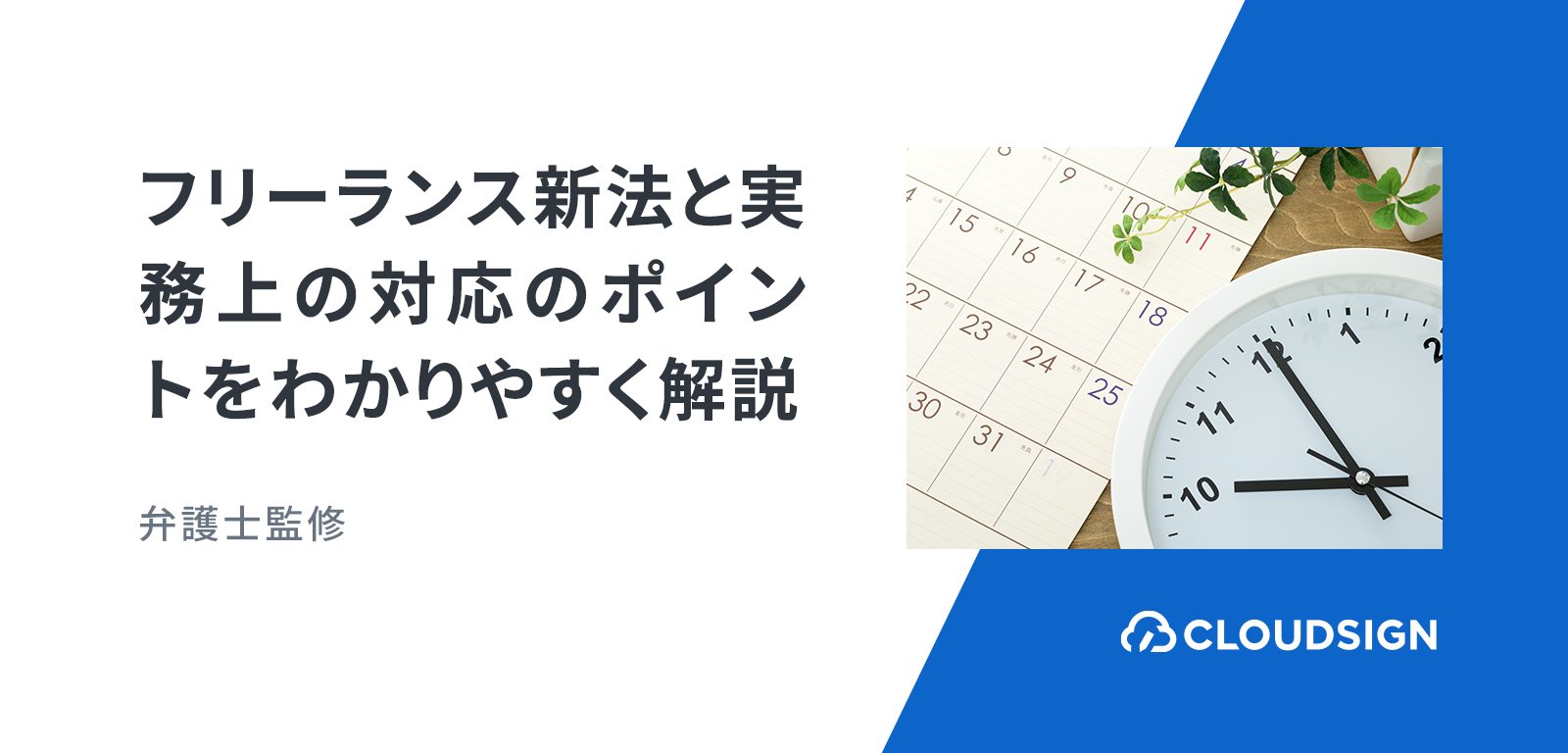下請法とは?2026年施行の改正内容と実務への影響を解説

取引先との契約を結ぶうえで、「下請法」の理解は欠かせません。一見対等に見える取引でも、立場の違いによって不公平が生じることがあります。そうした不当な取引を防ぐために定められたのが下請法です。
この記事では、下請法の基本的な仕組みや対象の判断基準、2026年法改正のポイントまでをわかりやすく解説します。
無料ダウンロード


下請事業者(中小受託事業者)と取引をしている企業様の間で、意図せず下請法に抵触してしまう事例は少なくありません。そこで本資料では、下請法の中でも特に違反が生じやすい項目をチェックリスト形式でまとめました。本チェックリストを活用することで、下請法違反のリスクを早期に発見し、未然に防ぐことができます。ぜひダウンロードし、ご活用ください。
目次
下請法とは
下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、親事業者と下請事業者の間で行われる取引において、不当な取り扱いを防ぐために定められた法律です。中小企業や個人事業主など立場の弱い事業者を守り、公正な取引関係を確保することを目的としています。
下請法の目的・ねらい(背景)
下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者による優越的地位の乱用を防ぎ、下請事業者との取引を公正に保つことを目的とした法律です。
取引構造上、親事業者の立場が強くなりがちな中で、納期変更や代金の減額など不当な扱いを防ぐために制定されました。
親事業者・下請事業者の定義
下請法が適用されるかどうかは、委託内容と当事者双方の資本金規模によって判断されます。主に、以下の2パターンに分類されます。
【①物品の製造・修理、または一定の情報成果物作成・役務提供の委託】
このケースでは、親事業者の資本金が3億円超、下請事業者が3億円以下の場合に適用されます。たとえば、製品製造やソフトウェア開発などが該当します。
【 ②上記以外の情報成果物作成や役務提供の委託】
たとえばデザイン業務やウェブ制作などが含まれます。この場合、親事業者の資本金が1,000万円超、下請事業者が1,000万円以下であれば、下請法の対象になります。
つまり、どのような業務を委託するのか(委託内容)と、委託元・委託先の資本金規模の組み合わせによって、下請法の保護対象となるかどうかが決まります。制度の適用可否は、類型ごとの条件を照らし合わせて個別に確認する必要があります。
下請法が適用される条件
下請法はすべての企業間取引に自動的に適用されるわけではありません。対象となるかどうかは、「資本金の規模」と「取引の種類」の2つの要素に基づいて判断されます。
ここでは、適用条件の基本をわかりやすく整理します。
取引当事者の資本金
下請法が適用されるかどうかは、委託側(親事業者)と受託側(下請事業者)の資本金規模によって決まります。たとえば、親事業者の資本金が1,000万円超で、下請事業者が1,000万円以下の場合は、物品製造委託などで下請法が適用されます。
資本金の区分は、委託の種類によって変動するため、具体的な判断には政令に定められた基準を確認する必要があります。
取引の内容
下請法は、親事業者が下請事業者に対して行う一定の「委託取引」に適用されます。対象となるのは以下の4類型です。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務(サービス)提供委託
単なる売買ではなく、注文に基づき成果物やサービスを提供する関係であることが要件とされます。
下請法が適用される取引の具体例
下請法は、親事業者から下請事業者への一定の委託取引に適用されます。ここでは、実務でよく見られる代表的な取引例を紹介します。
物品の製造
製造委託とは、親事業者が規格やデザインなどを指定し、下請事業者に物品の製造・加工を依頼する取引です。ここでいう「物品」とは動産を指し、建築物などは含まれません。
【具体例】
- 家具ブランドがOEMで木製テーブルの製造を委託
- アパレル企業が指定デザインの衣料品を縫製業者に依頼
- 電機メーカーが家電部品の加工を下請企業に発注
物品の修理
修理委託とは、物品の修理を他の事業者に依頼する取引を指します。自社保有物の修理を外部に任せる場合も含まれます。
【具体例】
- 製造業者が故障した製造装置の修理を専門業者に依頼
- 家電量販店が持ち込み製品の修理を提携業者に外注
- 自動車整備会社が一部の部品交換作業を協力工場に委託
プログラムの作成
情報成果物作成委託の一例として、プログラムやソフトウェアの開発委託が挙げられます。成果物の内容や仕様を指示して、外部に制作を依頼するケースが対象です。
【具体例】
- 家電メーカーが組み込みソフトの開発を外部エンジニアに委託
- ゲーム会社がグラフィック描画用ライブラリの一部開発を外注
- ECサイト運営会社が注文管理システムの開発をソフトウェア制作会社に委託
運送・物品の倉庫保管・情報処理
運送や倉庫保管、情報処理などの役務提供も、一定の条件を満たせば下請法の対象となります。
【具体例】
- アパレルメーカーが、商品の出荷を運送業者に委託
- 食品メーカーが、自社製品の保管を物流倉庫会社に委託
- 通販会社が、顧客データの処理業務をデータ入力専門会社に委託
建設業など一部の業種は対象外ですが、日常的な物流や情報処理の委託が対象になるケースも多く、契約内容と資本金条件をふまえて確認することが重要です。
資料ダウンロード


人手不足等を背景に、物流業界はいま「2024年問題」という大きな転換点に直面しています。この物流クライシスを乗り越えるため、2024年5月に改正物流法が成立しました。本ホワイトペーパーでは、とくに実務への影響が大きい「運送契約締結時の書面交付義務化」に焦点を当て、その具体的な内容や留意点を解説します。コンプライアンス強化を推進する物流関連企業の方はぜひご活用ください。
下請法で親事業者に課される4つの義務と禁止行為
下請法では、親事業者に対して一定の義務が課されています。ここでは、取引時に注意すべき4つの基本的な義務と、併せて禁止されている行為について解説します。
①書面の交付義務
親事業者は、取引の内容を明記した書面を下請事業者に交付する義務があります。口頭の合意では足りず、文書による確認が必要です。
【書面に記載すべき主な項目】
親事業者は、下請事業者に業務を委託した際、書面(発注書等)を交付しなければなりません。記載すべき主な項目は以下のとおりです。
- 委託内容の具体的事項(業務範囲、製品仕様など)
- 下請代金の額と支払期日
- 委託日、納期、受領日
- 不良品・返品の取扱方法
- 支払い遅延時の利息や条件
交付は紙だけでなく、PDFや電子データでも可能です。内容の明記が不十分だと、取引トラブルや法令違反につながるおそれがあります。
なお、書面交付義務や書面を電子化する際の注意点を知りたい方は下記記事もご一読ください。
②書類の作成・保存義務
親事業者は、下請取引に関する書類を作成し、2年間保存する義務があります。保存対象となるのは以下のような書類です。
- 発注書・契約書(書面交付に関するもの)
- 検収記録や納品書
- 支払証明書(振込明細など)
書類は紙だけでなく、電子データでの保存も可能です。不備があると、立入検査での指摘や違反認定につながります。
③下請代金の支払期日を定める義務
親事業者は、商品の納品やサービス提供の検収日から60日以内に支払期日を設定する必要があります。契約書や発注書などに、支払期日を明記しなければなりません。曖昧な記載や期日を超える設定は、違反となるおそれがあります。
④遅延利息の支払義務
親事業者が定めた支払期日を過ぎても下請代金を支払わない場合、遅延利息を支払う義務があります。利率は年14.6%(日割り計算)で、下請事業者に不利な取り決めは無効とされます。利息の記載がなくても、下請法に基づき自動的に適用されます。
禁止されている行為の一覧
下請法では、親事業者による不当な取引行為を防ぐため、禁止されている行為が明確に定められています。ここでは、実務で特に注意すべき代表的な禁止行為について紹介します。
買いたたき
市場価格や原価に比べて著しく低い代金で契約を強要する行為です。下請事業者の利益を不当に圧迫するものとして禁止されています。
受領拒否
正当な理由がないのに、完成品や納品物の受領を拒む行為です。
下請代金の支払い遅延
契約で定めた期日までに代金を支払わない行為です。資金繰りに影響するため、厳しく制限されています。
下請代金の減額
合意した金額を、事後的に一方的に減額する行為です。いかなる理由であっても、下請法上は原則禁止されています。
返品
受領済みの物品について、下請事業者に責任がないのに返品する行為です。費用負担を一方的に押し付けるものです。
購入・利用強制
取引と無関係な物品やサービスの購入・利用を強制する行為です。下請事業者の自由な経済活動を妨げるため禁止されています。
報復措置
下請事業者が公正取引委員会などに通報したことを理由に不利益な扱いをする行為です。通報制度の信頼を損なう重大な違反です。
有償支給原材料等の対価の早期決済
材料や機材の費用を、本来よりも不当に早く支払わせる行為です。資金面での負担を下請事業者に強いるものです。
割引困難な手形の交付
通常よりも期間が長く、現金化が難しい手形で支払う行為です。実質的に代金支払いを遅らせる手段として禁止されています。
不当な経済上の利益の提供要請
金銭や接待、無償作業など、合理的理由のない利益を要求する行為です。優越的地位の濫用とされます。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
契約後に費用を負担せず仕様変更や再作業を強いる行為で、下請事業者に追加負担を与えることから禁止されています。
下請法に違反した場合の罰則やリスク
下請法に違反すると、親事業者は行政処分や罰金、社会的信用の失墜といったリスクを負うことになります。ここでは、実務上とくに影響の大きいと考えられる主なペナルティについて解説します。
勧告や指導を受ける
下請法に違反すると、公正取引委員会や中小企業庁からまず「助言」や「指導」が行われ、必要に応じて「勧告」が出されます。これは法的拘束力のない行政指導ですが、是正措置を求める正式な通知です。内容や対応が不十分であると判断された場合は、罰則や社名の公表といったより重い措置に進む可能性もあります。
罰金が科される
下請法に違反し、勧告に従わなかった場合は、50万円以下の罰金が科されることがあります(下請法第10条)。この罰金は、単なる注意や指導とは異なり、刑事罰として正式に処分されるものです。さらに、違反の内容や対応状況によっては、独占禁止法に基づく命令や課徴金の対象となるケースもあります。
社名の公表による信用の失墜
下請法に違反し、公正取引委員会から勧告を受けた企業は、社名や違反内容が公表されます。これにより社会的な信用を失い、取引先からの信頼を損なう結果につながります。その影響は新規受注の減少、契約の打ち切り、さらには業績悪化など、実務面にも及ぶ可能性があります。
違反の情報は報道などを通じて広まりやすく、企業にとって深刻なダメージとなります。
下請法に違反しないための対策
下請法に違反すると、親事業者は行政処分や信用の低下など、深刻な影響を受けるおそれがあります。こうしたリスクを避けるには、日々の取引において適切な対応を取ることが重要です。
以下では、違反を防ぐために企業が実務で意識すべきポイントを解説します。
下請法をよく理解しておく
下請法は一部の業種・資本金規模にしか適用されませんが、対象事業者である以上、内容を正しく理解しておくことが重要です。とくに親事業者側は、自社がどの取引で下請法の適用を受けるのかを正確に把握したうえで、契約内容や代金の支払い、取引先への対応などを見直す必要があります。
法令に違反すれば、勧告や指導にとどまらず、罰金や企業イメージの低下といった深刻なリスクにもつながるため、関係部署での継続的な研修や情報共有も有効です。
書類の交付や管理を適切に行う
親事業者は、発注書や契約書などに取引条件を正しく記載し、下請事業者に交付する必要があります。さらに、これらの書類は法律により2年間の保存が義務付けられています。
紙ベースでの管理は紛失や検索の手間といった課題があるため、電子化による保管が有効です。電子管理やクラウド型の文書管理ツールなども活用し、確実な記録と迅速な確認が可能な体制を整えることが重要です。
リーガルチェックを導入する
契約内容が下請法に違反していないか、事前にリーガルチェックを行うことも有効です。特に書面交付義務や禁止行為の有無などは、専門的な視点での確認が欠かせません。
契約書レビューサービス「クラウドサイン レビュー」では、法務知識に不安がある企業でも、オンラインで手軽に内容確認が可能です。自社に合った契約書チェック体制を整えることで、下請法違反のリスクを大きく減らせます。
【2025年5月可決・成立、2026年1月施行】下請法で改正されたポイント
2025年5月、下請代金支払遅延等防止法の改正法が国会で可決・成立し、2026年1月1日から施行予定となっています(「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました)。
ここでは、改正の背景と主なポイントを簡潔に整理し、実務対応に必要な視点を解説します。
下請等用語の見直し
今回の改正では、法令上の用語として用いられていた「下請」「下請事業者」などの表記が見直され、「委託」「受託」といったより中立的な用語に変更されました。立場の優劣を前提としない取引関係の明確化を目的としています。
| 改正点 | 概要 |
| 従業員数基準の導入 | 資本金に加え、従業員数(100人・300人)でも適用を判断 |
| 特定運送委託の追加 | 荷主から物流会社への運送委託も対象に |
| 型・治具の追加 | 金型以外の製造委託も下請法の対象に追加 |
適用対象の判断がより複雑になるため、取引先の情報を事前に把握し、体制を整えておく必要があります。
禁止事項の追加
改正下請法では、下請事業者による通報後の報復行為が、法定で明確に禁止されました。違反通報を理由に不利益な取扱いをする行為が、法律上の禁止事項として位置付けられたことにより、違反申告の実効性が強化されています。また、通報先として事業所管省庁も新たに追加され、保護範囲も拡大しました。
執行の強化
改正により、公取委は違反行為が既に是正済みでも勧告できるようになりました。あわせて、事業所管省庁にも指導・助言の権限が付与され、通報先としても明記されるなど、連携体制が強化されます。
その他運用の改定
木型や治具の追加、電磁交付の柔軟化、減額に対する遅延利息の明記、勧告手続の整備など、制度運用の実態に即した複数の見直しが行われました。
まとめ
2026年1月施行の改正下請法では、適用範囲の拡大や禁止事項の明文化、執行強化など、実務に直結する重要な変更が盛り込まれました。
特に、従業員数基準の導入や報復措置の明示的禁止は、多くの事業者に影響を及ぼすと考えられます。各社においては、制度変更の趣旨を正しく理解し、委託先管理や社内フローの見直しを含めた具体的な対応が求められます。
加藤 高明(かとう たかあき)
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部