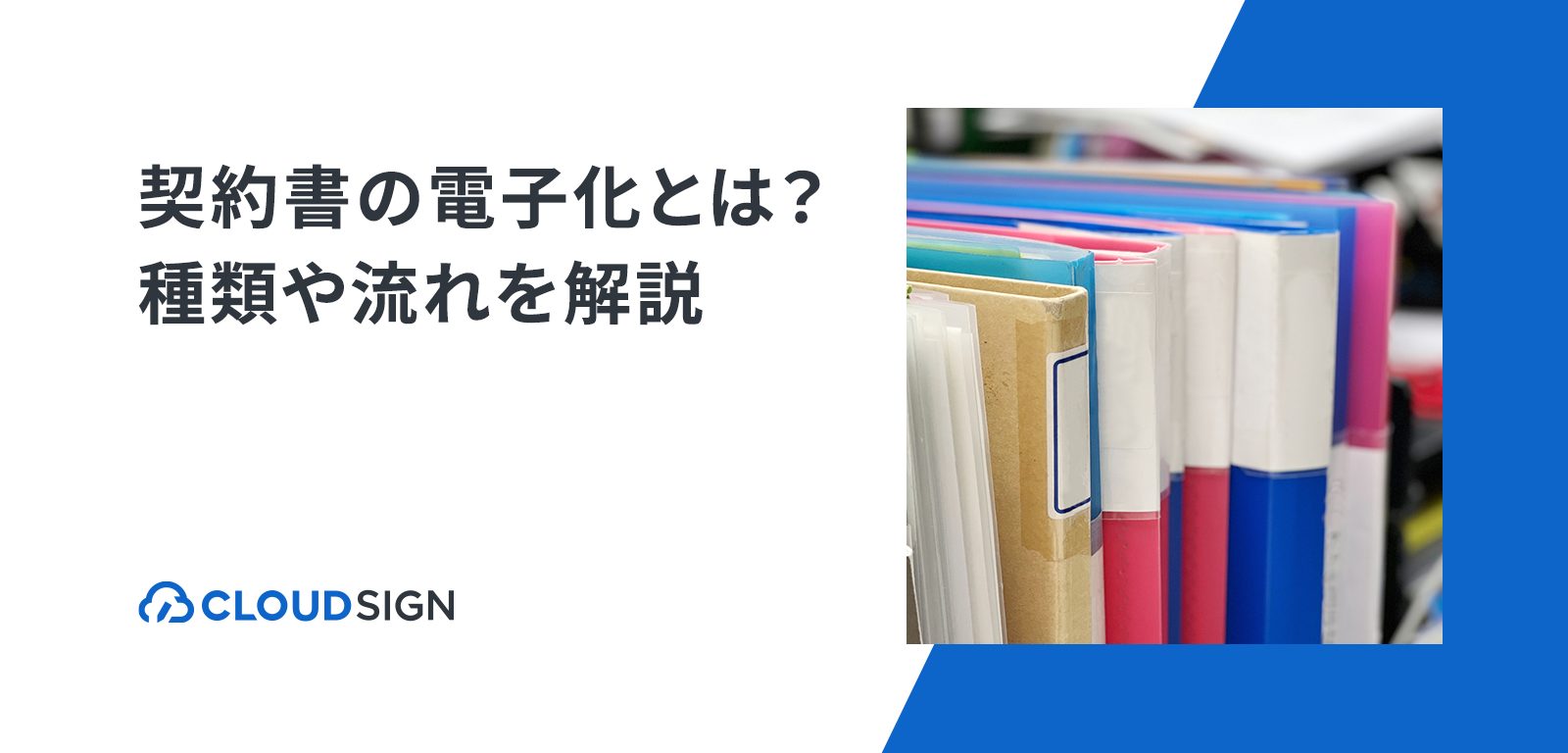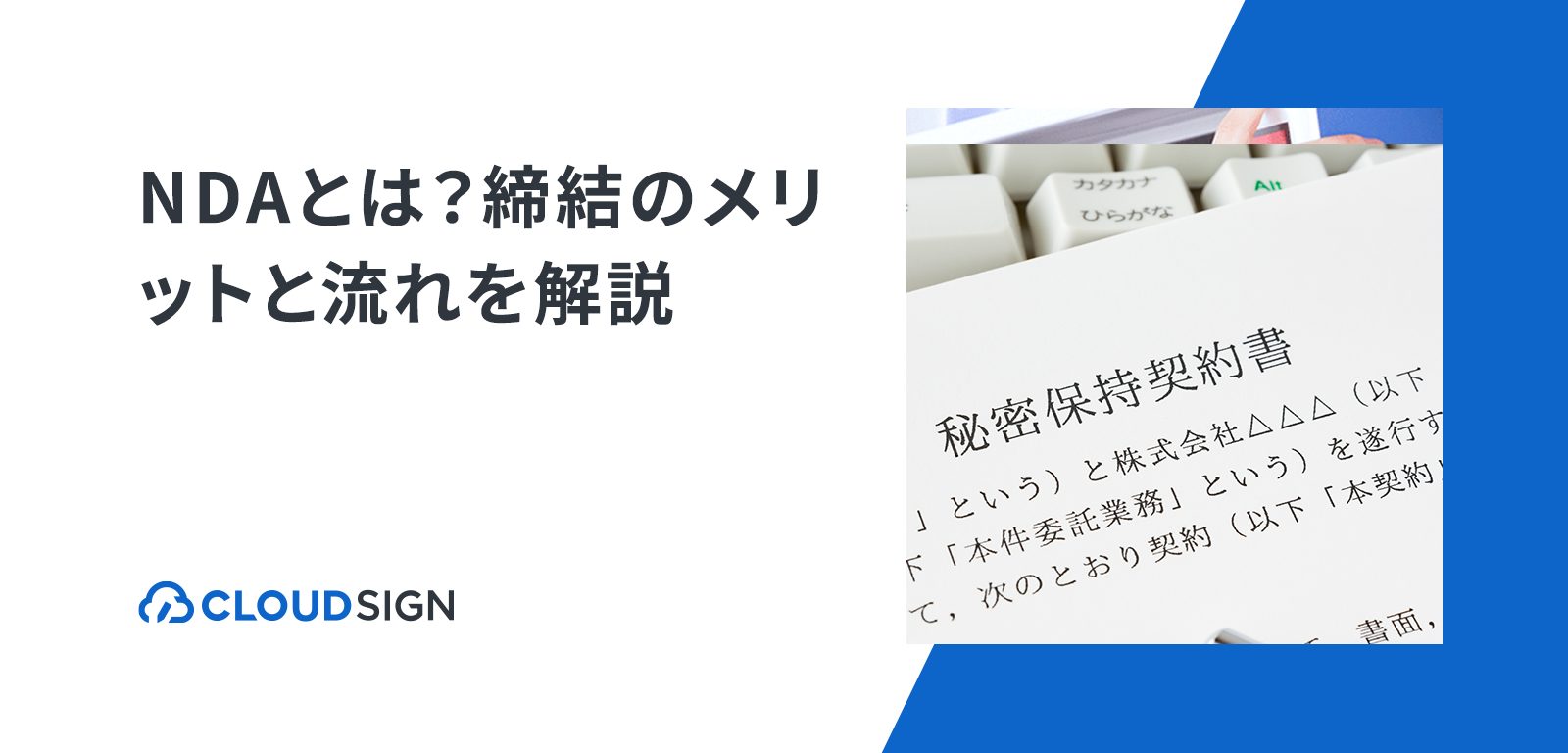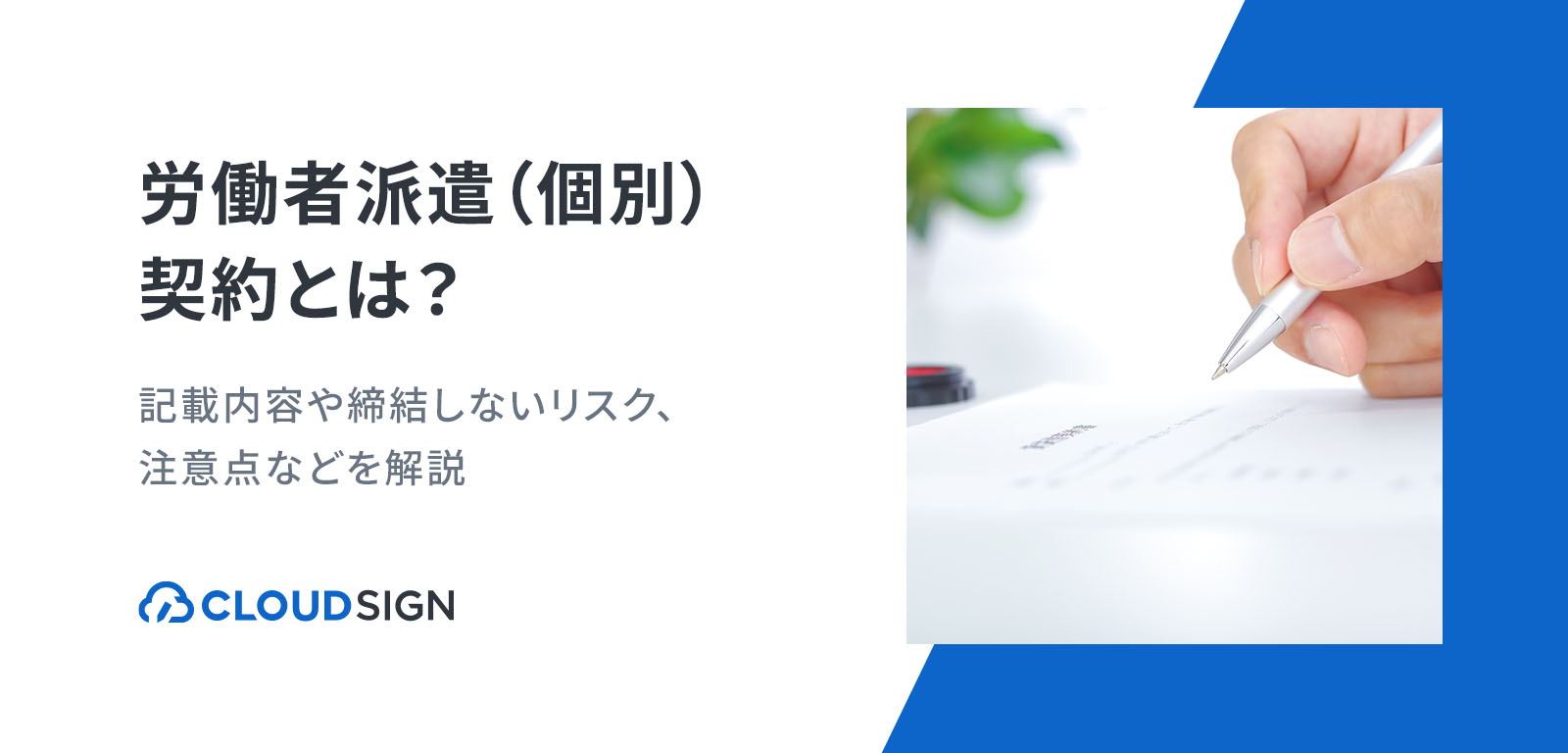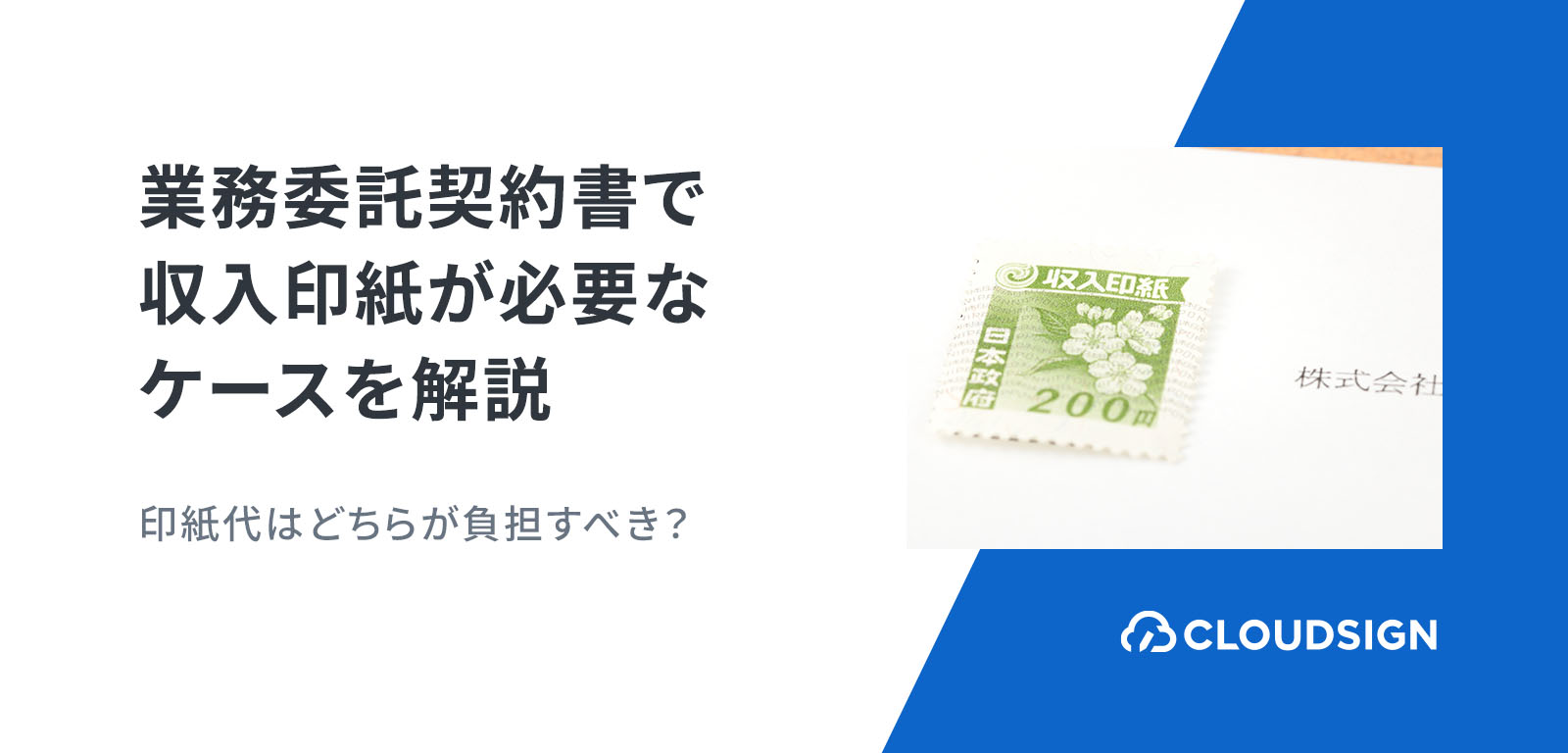取引基本契約書とは?印紙の必要性や記載すべき内容を解説
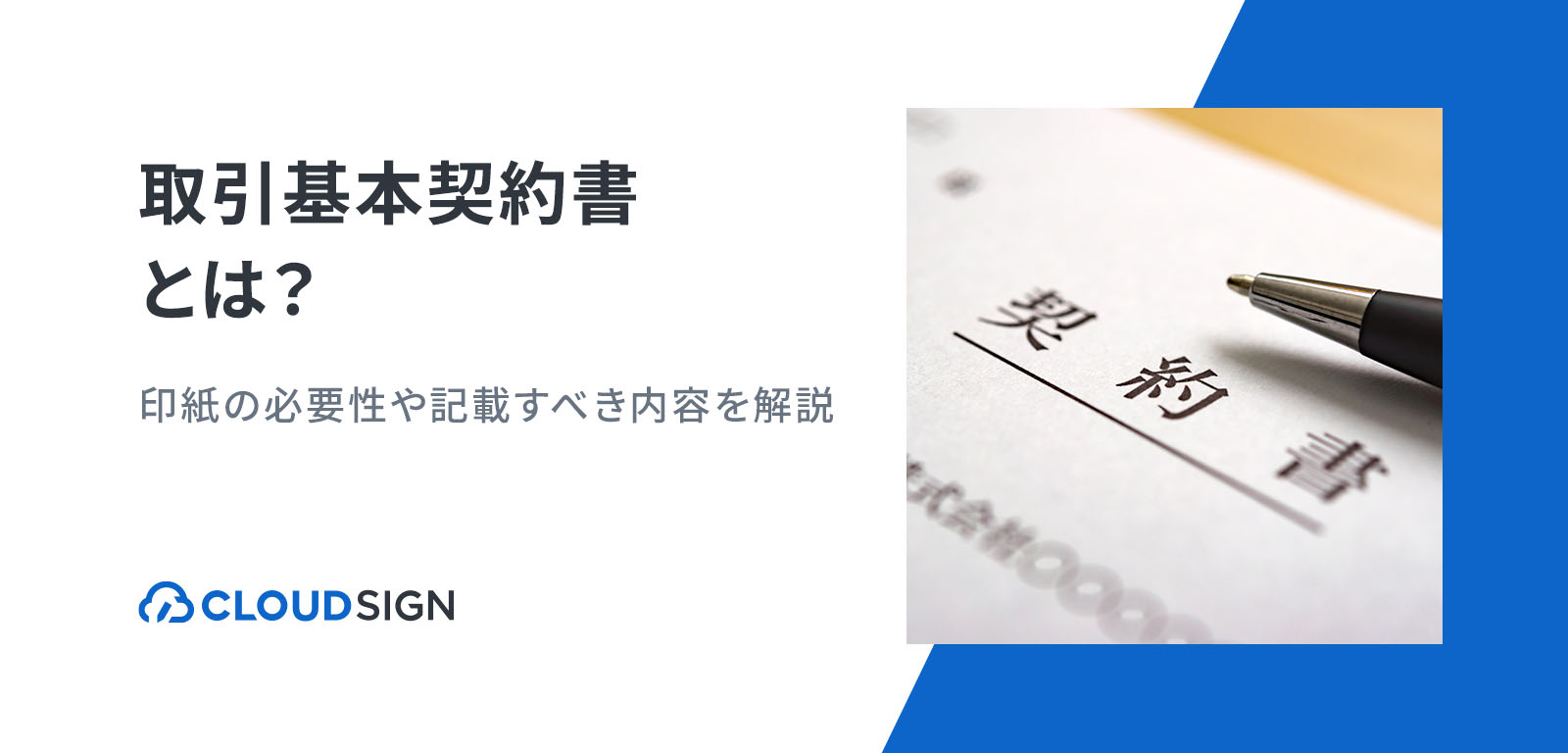
取引基本契約書は、継続的な取引を行う際に、多くの企業で活用されています。たとえば、商品の売買などが代表的です。基本契約と個別契約とあわせて使うことで業務を効率化できますし、締結しないまま取引を始めると、トラブルの原因となることもあります。
この記事では、取引基本契約書の必要性や、契約書に記載すべき内容、電子契約を結ぶメリットなどを解説します。
なお、クラウドサインでは弁護士監修の「売買取引基本契約書」のひな形を用意しました(無料)。売買に関する取引基本契約書のひな形を探している方はぜひ下記フォームからダウンロードしてご利用ください。
無料ダウンロード
目次
取引基本契約書とは
取引基本契約書とは、複数回以上の取引をする際に、取引の基本となる条件をまとめる書類です。
以下は「飲食店が食材や飲み物を仕入れる場合」の、基本契約と個別契約の例です。
- 基本契約:支払い条件・納品方法・契約期間 などの基本部分を定める
- 個別契約:発注する商品や数量、納品日など、個別の契約内容を定める
条件が変わらない部分は基本契約にまとめておき、毎回変わる部分を個別契約でまとめると便利です。
取引基本契約書と売買契約書の違い
売買契約書は、一度きりの取引やスポット契約でよく使われます。たとえば、「機械1台を○円で購入する」「展示会用に商品を100個仕入れる」といった単発の売買では、売買契約書1通のみで取り引きが完結します。
一方、毎月定期的に商品を仕入れるような取引では、「取引基本契約書」と「個別契約書」を組み合わせて使うのが一般的です。
たとえば、商品の所有権がいつ買主に移転するのかを定めた「所有権の移転時期」や納品された商品の検査方法や合格基準を定めた「検収のルール」、代金の締め日や支払日といった「支払条件」、納品物に不具合があった場合の対応を定める「契約不適合責任」といった、売買に関する基本的なルールを基本契約書にまとめておくことで、毎回の発注書(個別契約書)の内容は最低限で済みます。
基本契約書なしで取引はできる?
基本契約書がなくても、取引自体は成立します。しかし、基本契約書がない場合、契約のたびに、契約書にすべての条件を記載しなければなりません。
たとえば、代金の支払条件(締め日・支払日・振込手数料の負担など)や、商品の納品場所、検収の方法と期間、契約不適合責任(商品の不具合への対応)、遅延した場合の損害金の利率といった細かい条件を、取引のたびに毎回協議し、契約書に記載する必要があります。
これは売買契約書を作る人、チェックする人にとっても大きな負担になるため、複数回の取引を行う相手であれば、あらかじめ基本契約を結んでおくのがおすすめです。
なお、取引基本契約自体は、口頭やメールでの合意だけでも成立します。それでも多くの企業が契約書を取り交わすのは、後々の誤解やトラブルを防ぐためです。
たとえば、契約内容が正確に思い出せなかったり、担当者が変わる際に引き継ぎ漏れがあったりするケースは少なくありません。
あらかじめ契約内容を書面に残しておけば、合意事項を明確に残せるうえ、万が一のトラブル時にも法的な証拠として活用できます。
取引基本契約書を締結するメリット
取引基本契約書は、業務の効率化やトラブル防止に欠かせない役割を果たします。
毎回の契約を簡略化できるほか、トラブル時の責任範囲を明確にする効果もあります。ここでは、実務上のメリットを紹介します。
継続的な取引では契約業務の効率化が図れる
毎回同じような条件で取引を行う場合、都度フルセットの契約書を作成するのは手間とコストがかかります。取引基本契約書を結んでおけば、個別契約書には変更がある項目だけを記載すればよいため、業務の効率化につながります。
トラブルが起きた際の対応や責任を事前に明確化できる
支払遅延や納品ミスなど、トラブルが発生したときに、「どちらがどこまで責任を負うのか」が不明確だと、話し合いが長引いたり関係が悪化したりするおそれがあります。
取引基本契約書にあらかじめ責任の所在や対応ルールを定めておくことで、万一のときにもスムーズに対応できます。
取引基本契約書に記載すべき内容
取引基本契約書には、取引全体に関する基本ルールを明確に記載します。以下は、契約書に盛り込むべき内容をまとめた表です。
盛り込むべき内容をまとめた表です。
| 項目 | |
| 基本合意 | 継続的な取引の基本方針や、個別契約がこの基本契約に従うことを確認する条項 |
| 適用範囲 | 契約がどの取引や商品、サービスに適用されるかを明確にする |
| 個別契約の成立 | 注文書やメールなど、どの手段で個別契約が成立するかを取り決める |
| 納期について | 発注から納品までの期間や納品日の指定方法など、納期に関する基準を定める |
| 支払い条件 | 支払い方法や期限、通貨、遅延時の対応など、金銭のやりとりに関する条件を明記する |
| 所有権の移転時期 | 商品の所有権がいつ買い手に移るのかを定め、責任の所在を明確にする |
| 検収と不良品対応 | 納品後の検品方法や不良品発見時の返品・交換の対応について取り決める |
| 秘密保持 | 業務上知り得た情報の外部漏洩を防ぐため、秘密情報の取扱いについて定める |
| 契約期間と終了条件 | 契約の有効期間、終了方法、中途解約の条件や通知期間などを規定する |
| 損害賠償責任の範囲 | 契約違反時の損害賠償の範囲や上限金額をあらかじめ設定し、リスクを抑える |
| 契約の解除条件 | 支払い遅延や倒産など、契約解除が可能となる具体的な条件を定める |
| 準拠法と裁判管轄 | トラブル発生時に適用する法律や、管轄となる裁判所を明記する |
なお、クラウドサインでは弁護士監修の「売買取引基本契約書」のひな形を用意しました(無料)。売買に関する取引基本契約書のひな形を探している方はぜひ下記フォームからダウンロードしてご利用ください。
無料ダウンロード
取引基本契約書の締結で注意すべき主なポイント
契約書を交わす際は、内容を十分に確認しましょう。きちんと確認せずに署名してしまうと、後々不利な条件に縛られるおそれがあります。
ここでは、取引基本契約書を締結する際に特に注意すべきポイントを5つ紹介します。
契約の解除が一方に限定されていないか
「○日以内に納品されなかった場合は解除できる」など、解除の条件が公平かを確認しましょう。解除権が一方にしかないと、不利な立場に置かれるおそれがあります。
また、「催告なしで解除できる」条文がある場合は、その範囲が妥当かどうか注意が必要です。
損害賠償の上限が定められているか
契約違反や不具合が起きた場合に、どこまで損害賠償の責任を負うのかを明確にしておく必要があり、賠償範囲の認識にズレがあると争いに発展する原因になります。
たとえば、売主側は「賠償の上限は取引金額まで」と定めることがありますが、買主側は間接損害(二次損害の発生など)も含めるかどうかに注意が必要です。
個別契約と内容が矛盾していないか
基本契約書と個別契約書に記載された内容に矛盾があると、どちらを優先するかで揉める原因になります。
基本契約書には「基本(個別)契約を優先する」などの、優先準備を定めを必ず盛り込みましょう。条文ごとの整合性にも目を通すことが大切です。
民法改正を踏まえた内容になっているか
2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変更されるなど、契約条文の見直しが必要になっています。
古い契約書の雛形を使いまわしていると、現行法とずれた内容が含まれてしまうことがあります。最新の法改正を踏まえた契約文面になっているか確認しましょう。
自社にとって一方的に不利な内容はないか
契約書のドラフトをどちらが作成するかによって、条文の構成や内容に偏りが出やすくなります。
相手側が用意した契約書であっても、すべての条項を自社の立場から丁寧に読み込み、必要があれば修正や交渉を行いましょう。一見公平であっても、実質的に不利な内容であれば、見直しが必要です。
取引基本契約書に収入印紙は必要?
取引基本契約書に収入印紙が必要かどうかは、印紙税法別表第二の第7号文書に該当するかどうかで判断されます。第7号文書とは、継続的な取引を前提とした契約書のうち、一定の要件を満たすものを指し、印紙税の課税対象となります。
第7号文書に該当する要件は、以下の通りです。
- 営業者同士の契約であること
- 売買、売買の委託、運送、運送取扱、または請負のいずれかに関する契約であること
- 契約書に「目的物の種類」「取扱数量」「単価」「対価の支払方法」「再販売価格」のいずれかが記載されていること
- 電気・ガスの供給契約でないこと
これらの要件を満たす場合、取引基本契約書であっても印紙税の対象となり、所定の収入印紙を貼付する必要があります。
ただし、契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新条項が明示されていない場合など、一部例外もあります。
そのため、実務上は印紙税のリスクを避けるために、商品名や金額などの具体的な記載は個別契約書に分け、基本契約書には記載しないのが一般的です。
なお、取引基本契約書を電子契約で締結した場合には印紙税は課されません。印紙税は「紙に出力された課税文書」にのみ適用されるためです。
取引基本契約書は電子化できる?
取引基本契約書は、電子契約で締結が可能です。
電子契約とは、従来のように紙に署名・押印して締結するのではなく、オンライン上で契約を交わす方法のことです。現在では、法令で書面の作成が義務付けられている一部の契約(事業用定期借地契約など)を除き、当事者間の合意があれば電子データを用いて契約を締結することが法的に有効とされており、多くの企業が電子契約を導入しています。そして、取引基本契約書はこの書面作成義務の対象ではないため、電子化が可能です。
次のパートで詳しく解説しますが、電子化によって得られるメリットは多いです。たとえば、印紙代や郵送費の削減、契約手続きの短縮、保管スペースの不要化などが挙げられます。さらに、契約書をクラウドで管理できるため、検索性やセキュリティ面でも優れています。
とくに取引基本契約書のように、複数回にわたって利用される契約書は、電子化との相性が良いです。複数の取引先と並行して契約を結ぶ場面でも、作業負担を大きく軽減できます。
電子契約を導入するには、事前準備が必要です。使用するサービスの選定や、法的な対応、社内フローの整備など、検討すべきポイントがいくつもあります。「電子契約をしたいけど、何からはじめていいかわからない」そんな方のために、「電子契約の初め方ガイド」をご用意しました。これから電子契約の導入を検討している方は、下記のリンクからダウンロードして活用してください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)取引基本契約書を電子化するメリット
取引基本契約書を電子化することで、従来の紙契約では避けられなかったコストや手間を大幅に削減できます。
また、契約締結までのスピード短縮、安全性なども向上させることができます。ここでは、基本契約書を電子化するメリットを紹介します。
コストの削減が図れる
紙の契約書では、印紙税・郵送費・印刷代・保管コストなどが発生します。電子契約に切り替えることで、これらの直接的な費用をほぼすべて削減することが可能です。
印紙税が不要になるため、1件あたりの契約コストが大幅に下がり、継続的な取引が多い企業ほど効果を実感しやすくなります。
取引を迅速に進められる
紙の契約は印刷・押印・郵送・返送と多くの工程を要し、締結までに数日以上かかることもあります。一方、電子契約であればオンライン上ですぐに契約のやりとりができるため、最短即日で締結が可能です。
改ざんや紛失のリスクを軽減できる
電子契約では、契約データが暗号化された状態でクラウドに保管されるため、紙のように紛失したり、第三者に改ざんされる心配がありません。
また、アクセス履歴や承認記録も残るため、内部統制や監査対応にも強くなります。契約情報を管理するにおいて、信頼性が向上するのもメリットの一つです。
取引基本契約書を電子化して契約業務をスピードアップ
取引基本契約書は、ビジネスの現場でよく使われる契約書の一つです。具体的には、複数回にわたる継続的な取引を行う場合に、契約の基本ルールをまとめるのが「基本契約書」、取引ごとに異なる部分は、「個別契約書」にまとめるのが一般的です。
一般的には、「基本契約」と「個別契約」はセットで運用されるのが通例です。一度基本契約書を作成してしまえば、個別契約書には最低限の情報を記載するだけで済みます。
そのため、契約書の作成・確認にかかる時間が大幅に短縮され、契約業務そのものの立ち上がりもスピードアップします。さらに、基本契約書を電子契約で交わすことにより、印紙税の負担が不要になります。加えて、郵送や印刷、契約書の保管にかかるコストも削減でき、コスト面でも契約のハードルがぐっと下がります。
業務の効率化だけでなく、新たな取引の立ち上げや拡大も、よりスムーズに進められるようになるでしょう。ただし、電子契約にはメリットが多い一方で、導入には事前の準備も欠かせません。どのサービスを選ぶか、社内のフローをどう整えるかなど、考慮すべき点もいくつかあります。
電子契約の導入を検討している場合は、下記の「電子契約の始め方ガイド」をぜひダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)加藤 高明
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部