下請法(中小受託取引適正化法)の違反に該当する親事業者の行為とは?具体的な事例やペナルティ・通報先を弁護士が解説
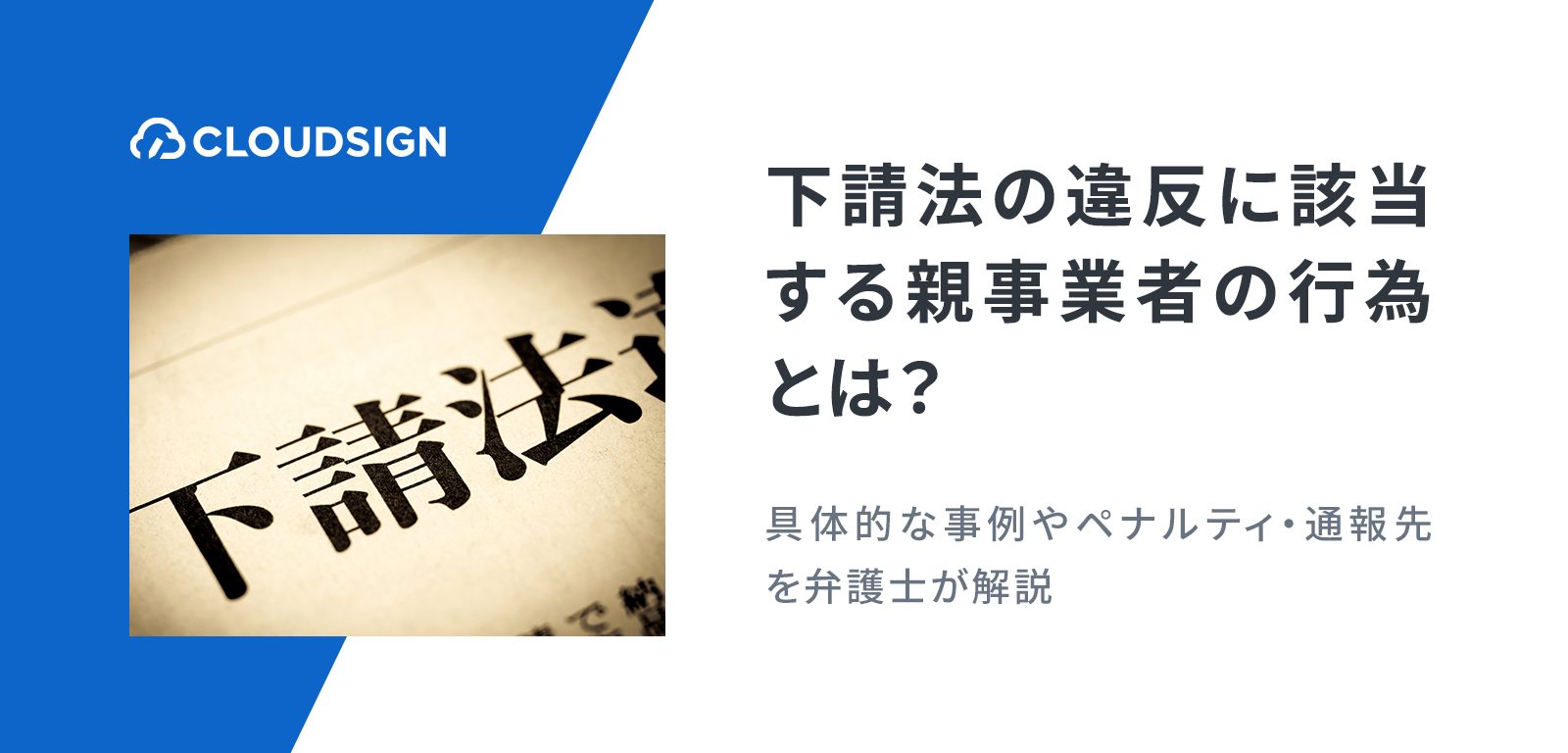
「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」は、親事業者から受注した業務を行う下請事業者を保護する法律です。親事業者が遵守すべき規制を定めることにより、下請事業者に対する搾取の防止を図っています。
2026年1月1日からは改正法が施行され、「中小受託取引適正化法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」に改められます。
親事業者としてはペナルティを受けないように、下請法の遵守を徹底しなければなりません。下請事業者としては、もし親事業者から下請法違反の不当な取扱いを受けたら、公正取引委員会への通報などを検討しましょう。
本記事では、下請法(中小受託取引適正化法)に違反する親事業者の行為、違反した親事業者に課されるペナルティ、下請法違反に関する通報先などを解説します。
無料ダウンロード


下請事業者(中小受託事業者)と取引をしている企業様の間で、意図せず下請法に抵触してしまう事例は少なくありません。そこで本資料では、下請法の中でも特に違反が生じやすい項目をチェックリスト形式でまとめました。本チェックリストを活用することで、下請法違反のリスクを早期に発見し、未然に防ぐことができます。ぜひダウンロードし、ご活用ください。
ダウンロードする(無料)目次
下請法が適用される取引
下請法は、親事業者が下請事業者に対して行う「製造委託等」について適用されます。
「製造委託等」とは、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4つを指します。また、2026年1月1日以降は「特定運送委託」が加わって5つになります。
| 委託の種類 | 概要 |
| 製造委託 | 製品や物品などの製造を委託すること |
| 修理委託 | 物品の修理を委託すること |
| 情報成果物作成委託 | ソフトウェア、映像、デザイン、プログラムなどの情報成果物の作成を委託すること |
| 役務提供委託 | 親事業者が他人から請け負ったサービスの提供を、下請事業者に委託すること |
| 特定運送委託 | 製品・物品・情報成果物の記録媒体などの運送を委託すること |
上記の製造委託等について下請法が適用されるのは、親事業者と下請事業者の資本金の額または出資の総額が以下の要件を満たす場合です。
| 委託の種類 | 資本金の額または出資の総額 |
| 製造委託 修理委託 情報成果物委託(プログラムの作成に限る) 役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管および情報処理に限る) 特定運送委託(2026年1月1日以降) |
以下のいずれか ・親事業者が3億円超、かつ下請事業者が3億円以下 ・親事業者が1000万円超3億円以下、かつ下請事業者が1000万円以下 |
| 情報成果物委託(プログラムの作成を除く) 役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管および情報処理を除く) |
以下のいずれか ・親事業者が5000万円超、かつ下請事業者が5000万円以下 ・親事業者が1000万円超5000万円以下、かつ下請事業者が1000万円以下 |
さらに2026年1月1日以降は、以下の従業員数に関する要件を満たす場合も、中小受託取引適正化法(下請法)が適用されるようになります。
| 委託の種類 | 常時使用する従業員の数 |
| 製造委託 修理委託 特定運送委託 |
委託事業者(親事業者)が300人超、かつ中小受託事業者(下請事業者)が300人以下 |
| 情報成果物委託 役務提供委託 |
委託事業者(親事業者)が100人超、かつ中小受託事業者(下請事業者)が100人以下 |
なお、2026年1月1日に施行される法改正により、法令の名称および用語が以下のように改められます。本記事では特に断らない限り、改正前の法令名および用語(下請法、親事業者、下請事業者、下請代金)を用います。
| 旧 | 新 |
| 下請代金支払遅延等防止法 ※略称:下請法 |
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 ※略称:中小受託取引適正化法、中小受託法など |
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 下請代金 | 製造委託等代金 |
【事例解説】下請法違反に当たる親事業者(委託事業者)の行為一覧
下請法では、下請事業者を保護するため、親事業者が遵守すべき規制を定めています。
具体的には、親事業者による以下の行為は下請法違反に当たります。
②受領拒否
③下請代金の支払遅延
④下請代金の減額
⑤返品
⑥買いたたき
⑦購入・利用強制
⑧報復措置
⑨有償支給原材料等の対価の早期決済
⑩割引困難な手形の交付
⑪不当な経済上の利益の提供要請
⑫不当な給付内容の変更・やり直し
⑬下請発注に関する記録を作成・保存しない
契約書面を交付しない
親事業者は、下請事業者に対して製造委託等をした場合は、直ちに契約事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません(下請法3条1項)。したがって、親事業者が下請事業者に契約書面を交付しないことは下請法違反に当たります。
契約書面に記載すべき事項は、委託業務の内容や下請代金の額・支払期日・支払方法などです。詳しくは「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」で定められています。
参考:下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則|公正取引委員会
なお上記の契約書面は、条文番号をとって「3条書面」と呼ばれています。ただし2026年1月1日以降は、法改正により条文番号が変更されて「4条」となります。
下請事業者の承諾を得た場合は、3条書面に記載すべき事項を電子データで提供することも認められています。この場合、契約書面を交付したものとみなされます(同条2項)。
また2026年1月1日以降は、中小受託事業者(旧:下請事業者)の承諾の有無にかかわらず、書面・電子データのいずれかによって契約事項を明示すれば足りるようになります。ただし、中小受託事業者から書面の交付を求められた場合は、原則として遅滞なく交付しなければなりません。
受領拒否
親事業者は、下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請事業者の給付の受領を拒んではなりません(下請法4条1項1号)。
たとえば、下請事業者から納入された製品や物品の受け取りを拒否することは下請法違反に当たります。
下請代金の支払遅延
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内、かつできる限り短い期間内において定めなければなりません(下請法2条の2第1項)。
親事業者が下請事業者に対して、支払期日が経過しても下請代金を支払わないことは下請法違反に当たります(同法4条1項2号)。「納品検査(検収)」が終わっていないなどの理由があっても、支払期日までに下請代金を支払わないのは違法です。
下請代金の減額
親事業者は、下請事業者に責任がないのに、下請代金を減額してはなりません(下請法4条1項3号)。たとえば「売上が伸びないから値引きしろ」などと要求することは下請法違反に当たります。
返品
親事業者は、下請事業者に責任がないのに、納入された物を下請事業者に引き取らせてはなりません(下請法4条1項4号)。
たとえば、製品に何ら欠陥がないにもかかわらず、「売れ残って余ったから」という理由で下請事業者に返品することは下請法違反に当たります。
買いたたき
親事業者は、通常の対価よりも著しく低い下請代金の額を不当に定めてはなりません(下請法4条1項5号)。
たとえば「不景気だから」「業績が厳しいから」などの理由で、下請事業者に安すぎる額で受注するよう強制することは下請法違反に当たります。
購入・利用強制
親事業者は原則として、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、または役務(サービス)を強制して利用させてはなりません(下請法4条1項6号)。
ただし例外的に、以下のいずれかに該当する場合には、下請事業者に対して物の購入や役務の利用を強制することが認められます。
・下請事業者の給付内容を改善するため必要がある
・その他正当な理由がある
報復措置
親事業者は、下請事業者が自社の下請法違反の事実を公正取引委員会や中小企業庁長官に知らせたことを理由に、下請事業者に対して以下の取扱いをしてはなりません(下請法4条1項7号)。
・取引を停止する
・その他不利益な取扱いをする
有償支給原材料等の対価の早期決済
親事業者は、下請事業者に責任がないのに、自社から購入させている原材料等の対価を、その原材料等を用いる給付の下請代金の支払期日より早い時期に控除しまたは支払わせることにより、下請事業者の利益を不当に害してはなりません(下請法4条2項1号)。
たとえば、下請事業者X社が親事業者Y社から原材料Aを購入し、それを用いて製造した製品BをY社に納入したケースを考えます。製品Bに係る下請代金の支払期日は2025年11月30日であるとします。
Y社は2025年11月30日より前に支払期日が来る下請代金の額から、原材料Aの代金を控除してはなりません。Y社がX社に対して原材料Aの代金の支払いを請求できるのは、早くとも製品Bの下請代金を支払った日以降です(製品Bの下請代金から控除することは認められます)。
割引困難な手形の交付
親事業者は下請事業者に対し、下請代金の支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付して、下請事業者の利益を不当に害してはなりません(下請法4条2項2号)。
たとえば、下請代金の支払期日が2025年11月30日であるのに、2026年以降でなければ割引を受けられない手形を交付して支払いに代えることは下請法違反に当たります。
不当な経済上の利益の提供要請
親事業者は下請事業者に対し、自己のために金銭やサービスなどの経済上の利益を提供させて、下請事業者の利益を不当に害してはなりません(下請法4条2項3号)。
たとえば、自社が開催するイベントの手伝いを強制したり、製品サンプルを無償で提供するよう要求したりすることは下請法違反に当たります。
不当な給付内容の変更・やり直し
親事業者は、下請事業者に責任がないのに、下請事業者の給付内容を変更させたり、納入後に給付をやり直させたりして、下請事業者の利益を不当に害してはなりません(下請法4条2項4号)。
たとえば、一方的な仕様変更を理由に無償で納品をやり直させることは下請法違反に当たります。
下請発注に関する記録を作成・保存しない
親事業者は、下請事業者に対して製造委託等をした場合は、発注に関する事項を記載・記録した書面または電磁的記録を作成し、保存しなければなりません(下請法5条)。
この書類は、条文番号をとって「5条書類」と呼ばれています。ただし2026年1月1日以降は、法改正により条文番号が変更されて「7条書類」となります。
5条書類(7条書類)に記載・記録すべき事項は、下請事業者の給付や下請代金に関する事項などです。詳細は公正取引委員会規則によって定められています。
参考:下請代金支払遅延等防止法第五条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則|e-gov法令検索
5条書類(7条書類)は、作成後2年間にわたって保存しなければなりません。5条書類(7条書類)の作成または保存を怠った場合は、下請法違反に当たります。
【2026年1月~】法改正によって追加される委託事業者(親事業者)の禁止行為
2026年1月1日から施行される改正法(中小受託取引適正化法)により、委託事業者(旧:親事業者)の禁止行為が新たに1つ追加されます。
具体的には、中小受託事業者(旧:下請事業者)の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が求めた価格転嫁に関する協議に応じることなく、または必要な説明や情報の提供をせず、一方的に製造等委託代金(旧:下請代金)を決定することが禁止されます。
上記の改正は、近年の物価高の状況を踏まえて、適切な価格転嫁が行われるような取引環境を整えるために行われるものです。
下請法に違反した親事業者に課されるペナルティ
下請法に違反した親事業者は、公正取引委員会から勧告を受けることがあります(下請法7条)。
勧告を受けた場合は、その勧告に従って是正措置をとることが求められます。また、勧告の内容は公正取引委員会のウェブサイトで公表されるため、レピュテーションへの悪影響が懸念されます。
また、3条書面の交付や5条書類の作成・保存を怠った者は「50万円以下の罰金」に処されます(下請法10条)。また、法人にも同様に「50万円以下の罰金」が科されます(同法12条)。
下請法の違反事例
直近(令和7年度)の下請法違反事例の一部を紹介します。
| 勧告を受けた事業者 | 勧告が行われた日 | 違反行為の概要 |
| 株式会社ジェイテクト | 令和7年9月19日 | 振込手数料として実際の支払額を超える額を控除し、下請代金を不当に減額した。 |
| 株式会社Olympic | 令和7年9月29日 | 「割戻し」や振込手数料の名目で、下請代金を不当に減額した。 |
| リョーノーファクトリー株式会社 | 令和7年10月9日 | 金型・木型・治具を下請事業者に無償で長期間保管させ、下請事業者の利益を害した。 |
親事業者から下請法違反の扱いを受けた場合の通報先
下請法違反に関する通報は、公正取引委員会と中小企業庁が受け付けています。親事業者から不当な扱いを受けていると感じた下請事業者は、通報をご検討ください。
参考:下請法に関する相談窓口|公正取引委員会
参考:下請代金支払遅延等防止法概要・相談窓口|中小企業庁
まとめ
親事業者が下請法に違反すると、公正取引委員会から勧告を受け、その事実がウェブサイト上で公表されるおそれがあります。レピュテーションの毀損を防ぐためにも、親事業者は下請法の遵守を徹底しましょう。
下請事業者としては、親事業者の不当な扱いに対して泣き寝入りする必要はありません。公正取引委員会や中小企業庁に通報するなど、是正を求めて行動することをお勧めします。
なお、下請事業者から事前に承諾を得ることで、3条書面を適法に電子化することができます。そこで、電子契約クラウドサインを活用した、下請法3条書面をはじめとする請負契約の全面電子化を検討してみてはいかがでしょうか。
クラウドサインは、クラウド上で契約書のPDFに電子署名を施し、スピーディーかつ安全に当事者間の合意の証拠を残すことのできる電子契約サービスです。これまでに250万社以上の導入実績があり、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。
当社ではクラウドサインの機能や料金をコンパクトにまとめた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しています。クラウドサインを導入するメリットや導入までの流れ、お客様の声などクラウドサインの導入検討するために知っておきたい情報を網羅的に解説していますので、クラウドサインのサービスの詳細について知りたい方は、下記リンクからご入手ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
法律・法改正・制度の解説
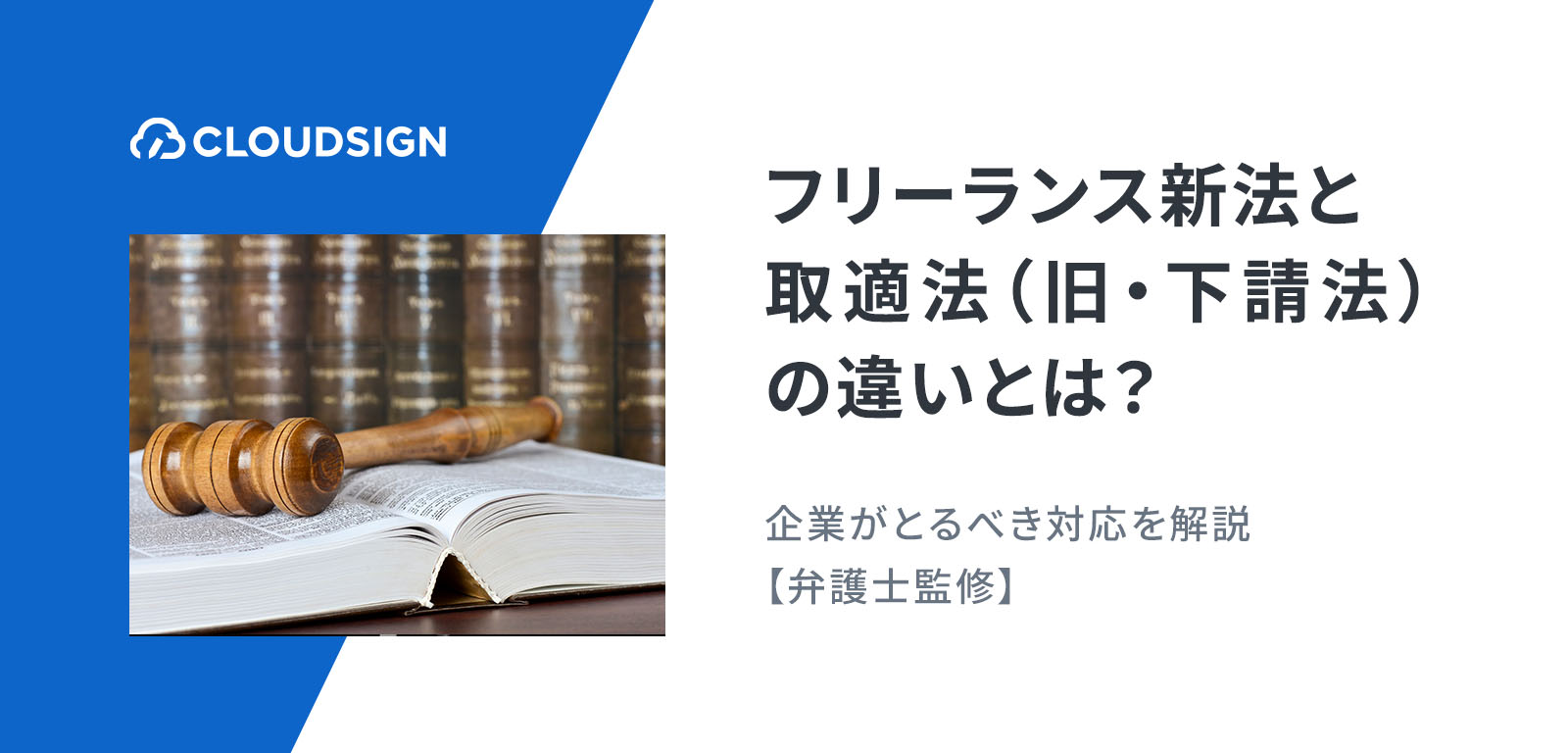
【弁護士監修】フリーランス新法と取適法(旧・下請法)の違いとは?企業がとるべき対応を解説
法改正・政府の取り組み弁護士解説取適法(下請法)フリーランス新法 -
法律・法改正・制度の解説

フリーランス新法とは?主な義務や罰則、下請法との違い、相談窓口を解説【弁護士監修】
フリーランス新法 -
法律・法改正・制度の解説

下請法とは?2026年施行の改正内容と実務への影響を解説
取適法(下請法) -
契約実務

【無料ひな形付き】準委任契約とは?請負契約・委任契約との違いを解説
契約書契約書ひな形・テンプレート業務委託契約書準委任契約請負契約 -
契約実務

工事請負契約書とは?目的や作成のポイント、締結する際の注意点を詳しく解説
契約書契約書ひな形・テンプレート建設業法工事請負契約書請負契約 -
契約実務

委任契約とは? 準委任契約・請負契約との違いや締結時の注意点を解説
契約書