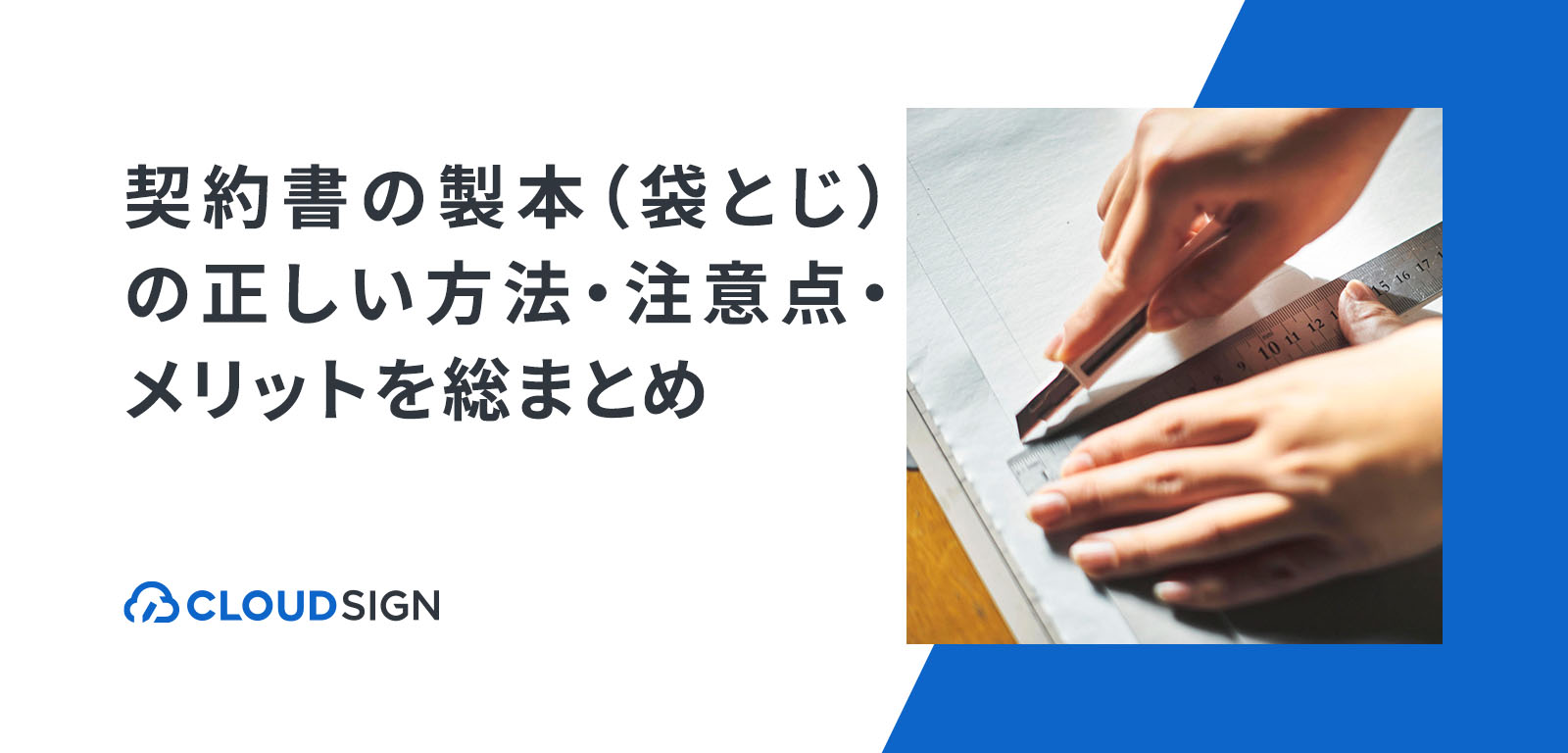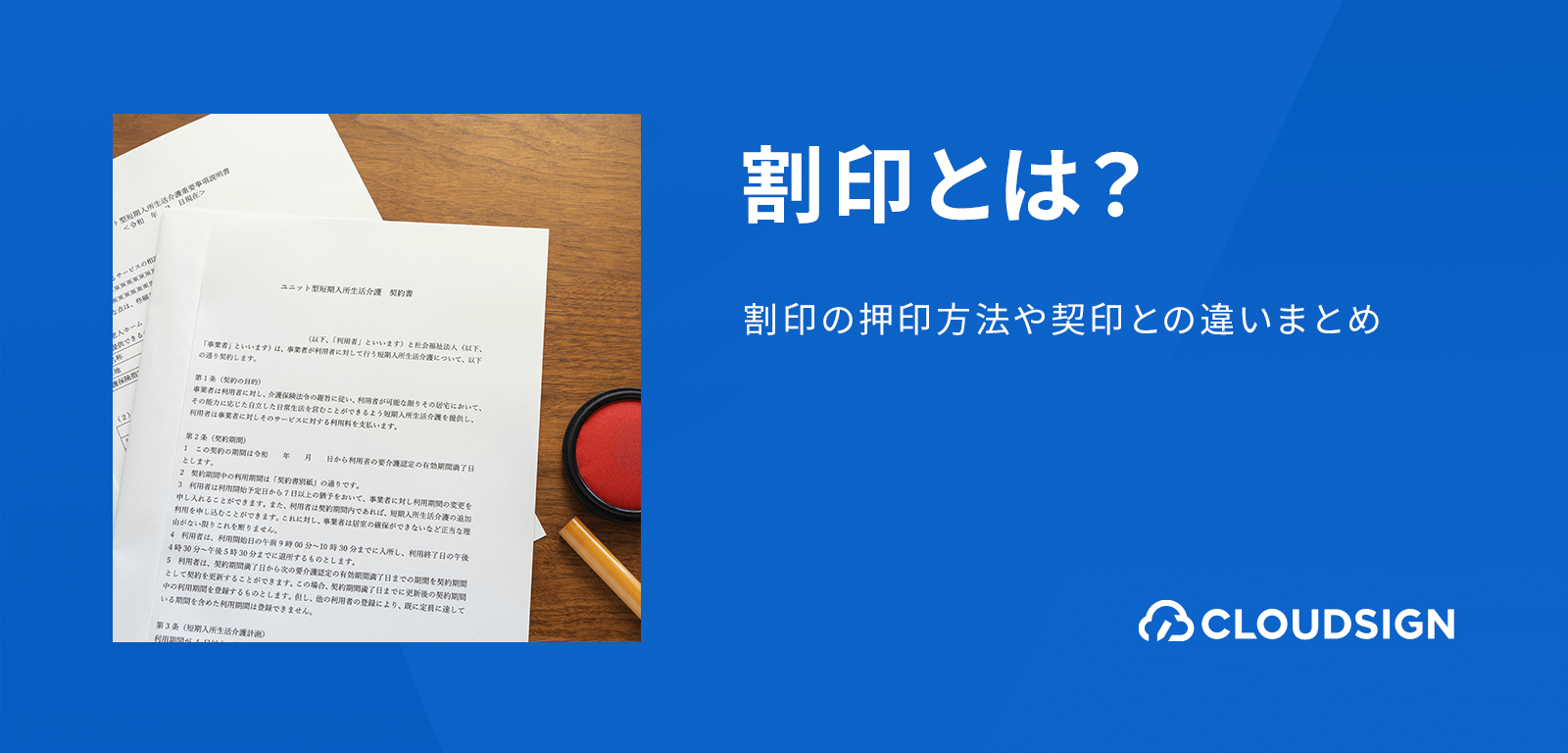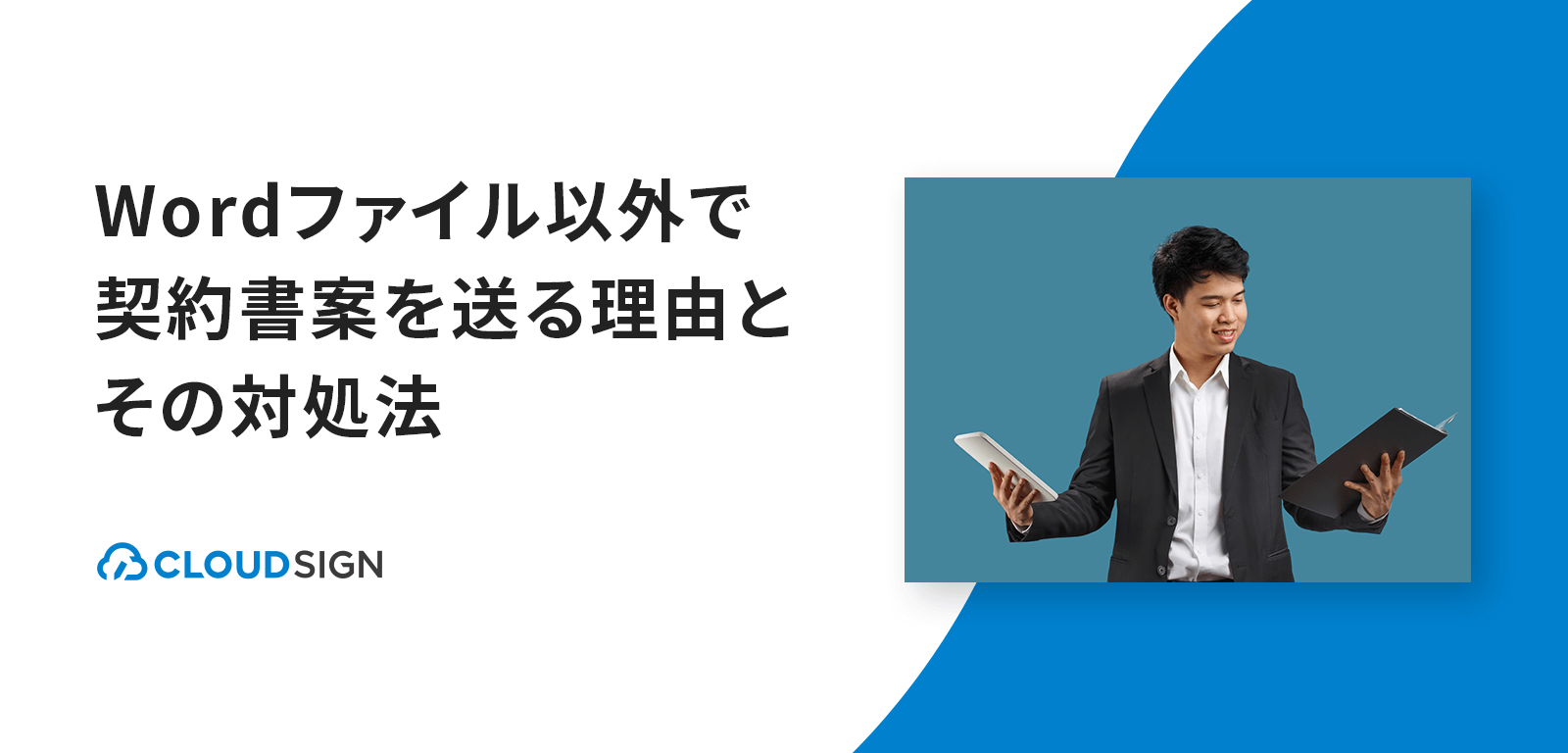地方自治法上の契約書締結義務とバックデート(契約日の遡及)問題

民間企業と同様に、地方公共団体の契約実務でも問題になるのが、契約書を作成していなかった日に遡って契約を締結したこととする「バックデート」です。紙と印鑑の時代には暗黙の了解で通用したことが、デジタル化によって透明化されたことで法令違反かのように見えてしまうこの状態を、どのように解消すればよいでしょうか。
ダウンロード


この資料では、電子契約サービス「クラウドサイン」を導入した茨城県笠間市、奈良県生駒市、千葉県浦安市の事例を紹介します。各自治体における電子契約サービス選びのポイントや、活用シーンを知りたい方はぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
電子契約実務における「バックデート(契約日の遡及)問題」
契約書のバックデートとは
契約条件を交渉し、お互いの合意事項を書面や電子ファイルに文字や図表で契約書に書き記し、押印もしくは電子署名で両者合意の証を残す。
法律上、契約は書面や電子ファイルにする必要はなく、口頭でも成立するのはよく知られています。とはいえ、両者の合意事項に齟齬のないようにし、トラブルの発生確率が低い状態で取引を開始するためには、契約書の作成が事実上必須であり、実際の合意の日から数日内に契約書を作成し押印する企業がほとんどです。
しかし、実務上、こうした契約書の作成にかかる時間や手間が取引スピードを妨げるのも事実。そこで、リスクのそれほど高くない契約においては、実態としての取引行為を先に実施しつつ、契約書作成を後回しにして、あとで日付を遡らせて取引当初から契約書が存在したかのように「偽装」することがしばしば行われます。いわゆる契約書のバックデートです。
電子契約ではバックデートが第三者にも「見える化」され筒抜けになる
紙の契約書と印鑑で契約をしていた時代には、いわば暗黙の了解でこのバックデートを当たり前のように行っている企業も少なくありません。しかし、電子契約導入時には、しばしば「問題」として取り沙汰されます。
それはなぜかというと、電子署名ととともに付与される「タイムスタンプ」によって、電子署名を実施した作業日時が克明に電子ファイル上で「見える化」されてしまうためです。
ハンコで印影を押印しても、ハンコにその作業日を記録する機能はありません。すると、契約書の日付がハンコを押した作業日なのだろうと推定されます(企業実務では実際には多くの場合でバックデートが発生しているにもかかわらず)。一方、電子署名を契約書ファイルに付与するときには、タイムスタンプによって厳密な日時が記録されます。本来は2023年1月1日付で契約書を作成したことにしたくても、1月18日に電子署名作業をしたことがタイムスタンプによって「見える化」されてしまうわけです。
電子署名作業日時についてウソがつけないことは、民間企業内のコンプライアンスという点では不正が起きにくくなり非常に有用です。しかし、契約を文書化することが契約の成立要件にかかわる場合には、このバックデート問題がとたんにヘビーな問題となります。
民間にはない法的制約を課されている地方公共団体
地方自治法による契約確定条件の制約
そのような、契約の成立要件としての契約書の作成について、問題となる法律があります。地方公共団体における契約行為を規律する地方自治法です。
第二百三十四条 (1から4項省略)
5 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
上記条文に記載のあるとおり、地方公共団体においては、契約書(または契約内容を記録した電磁的記録)に記名押印(または総務省令に定める電子署名)を講じなければ契約が確定しない、すなわち、口頭等契約書以外での契約成立は認められないことが明文化されています。
しかし、実際には年度終わり・年度初めなど、契約書を短期間で大量に作成しなければならない繁忙期は民間企業同様に発生するはずです。このような規律が100%遵守できるとは到底考えられません。
それにもかかわらず、口頭契約を認めている民法を上書きするような、このような厳しい法律が定められているのには、何か理由があるのでしょうか。
契約書による確定原則の契機となった最高裁判例
地方自治法234条5項において、契約書作成時成立の原則が定められた契機として、国の契約が入札承諾によって成立するのでなく、契約書作成をもって成立するとした最高裁判例があります。
以下、成田頼明ほか編著『注釈地方自治法』(第一法規)より引用します。
契約は、相互に対立する意思表示の合致により成立する法律行為であり、契約書は、一般には、契約の成立の証拠手段にすぎないと解せられている。ところが、国が締結する契約について、最高裁判所は、「国が当事者となり売買等の契約を競争入札によって締結する場合に、落札者があったときは、国及び落札者は互に相手方に対し契約を締結する義務を負うにいたるが、この段階では予約が成立するにとどまり、本契約は、契約書の作成によりはじめて成立すると解すべきである」と判示した(最判昭和三五年五月二四日民集一四巻七号一一五四頁)。これは、国の場合に、契約書の作成を契約の効力発生要件と解したものであり、民法の原則の例外であるとしたものである(これに対する反対説として、田中二郎・新版行政法下巻二二八頁)。
この判決が出されるまでの通説としては、入札承諾説がとられていたといってよいが(大審判明治三四年五月三一日民録七輯五巻一五七頁)、右の最高裁判所の判決が出たことにより、国の場合には、予算決算及び会計令旧六八条に代えて、会計法二九条の八第二項の規定が新設され、これにより、同判決の趣旨が明文化されたのである。
この経過をうけて、昭和三八年の地方自治法改正に際して、同法では、契約書作成を義務付ける規定は設けられるに至らなかったが、本条五項は、契約につき契約書を作成する場合における契約の確定の規定が設けられ、契約書作成の場合の契約成立の時期が明定されるに至ったのである。
本件は国の契約における判例ですが、この判例を踏まえて国の契約を規律する会計法29条の8が、地方公共団体については前述の地方自治法234条5項が整備された経緯があります。
地方公共団体との契約にバックデートの代替策はあるか?
「フォワードデート」を否定する見解
このように、法律および上バックデートが許されない中、年度会計での発注・契約締結が原則となる地方公共団体においては、どのように大量の契約書実務をまわしていたのでしょうか。
考えられる方策として、後日付の契約書を事前に作成しておき、押印・電子署名作業をすませてしまっておけば、問題はなさそうです。
しかし、このようなバックデートならぬ「フォワードデート」も問題があるとする見解があります。 埼玉県草加市からの提案と、これに対する総務省回答です。
構造改革特区提案における総務省からの回答にもあるとおり、機会均等、公正性、競争性及び経済性を確保する観点から、国、地方を含め、公共調達の契約方法は一般競争入札によることを原則としており、随意契約はその例外として位置付けられている。
しかしながら、現実には、いまだ多くの随意契約が残る。その理由の一つが入札手続きの年度規制にあることから、これまでに草加市は、その規制改革を求めてきた。具体的には、契約の競争性、公正性の確保はもちろんのこと、契約事務や工期の集中などの弊害、更には年度事業であるのに入札のために債務負担行為を多用することで予算審議が形骸化する懸念も理由に挙げ、年度開始前に入札等契約準備行為を行えるようにすることによって随意契約を減らしていくという提案をしているが、認められていない。
確かに、地方公共団体の会計年度は毎年4月1日が始期とされ、予算の執行は年度開始前にはできないこと、入札の執行は、特別の理由による以外、落札者と契約を結ぶことを前提にしている。しかし、入札の執行は契約の準備行為であり、予算の成立を条件に入札を行えば、問題は回避できる。このことは、予算議決された契約案件であっても、予め公告することにより、入札、仮契約後に議会で契約締結議案が否決された場合は契約が成立せず、落札者は求償できないことからも明白と考えられる。
本提案については、これまでの本市提案への全国の自治体からの問い合わせも多く、規制改革が強く望まれている。今一度、実現に向けてご尽力をお願いしたい。
草加市は総務省に対し、「契約事務や工期の分散のため、新年度の4月1日にこだわらず、予算成立を停止条件として、先日付で入札・契約を行わせてほしい」と要望しています。
これに対する総務省の回答は、以下のとおり四角四面な見解となっています。
支出負担行為、すなわち支出の原因となる契約その他の行為は、法令又は予算の定めるところによりしなければならない(自治法232条の3)。 また、普通地方公共団体の会計年度が毎年4月1日から翌年3月31日(自治法208条)とされており、予算の執行は、年度開始前には行うことができない。入札を執行し、落札者の決定があった場合には、地方公共団体と落札者との間には、本契約の予約が成立し、地方公共団体は、法令に定める特別の場合に該当する以外は、落札者と必ず契約を結ぶ義務を負うこととなることから、入札の執行は、支出負担行為(契約)の一連の手続きであり、予算執行に含まれると解すべきである。よって、年度末において、翌年度に係る契約その他の行為をすることは債務負担行為として議会の議決を経た場合のほかは、これをすることはできないものである。
契約締結日を遡及させる条項を置いても非債弁済と解釈せざるをえない問題は残る
では、民間企業の実務でもよく採用されるような、契約締結日・有効期間の遡及条項、すなわち
「この契約の有効期間は、電子署名付与のタイムスタンプに記録される日時にかかわらず、令和◯年四月一日から令和△年三月三十一日までとする」
を置くことではどうでしょうか。
これについて、地方自治制度研究会編『地方財務実務提要』(ぎょうせい)2巻五八二九・108頁では、給付の開始日の4月1日が休日にあたる場合に、遡及条項を置くことについて、以下のような見解が述べられています。
地方公共団体の契約もその基本は私法上の契約ですので、原則的には契約自由の原則が適用され、(中略)契約成立前において既に行われた特定の行為を当該契約上の行為とみなして契約条項を適用するという内容の特約をすることも法律上可能ではありますが、これもこのような契約条項の効果として、そのように取り扱われるに過ぎないものですから、当該特約条項がない場合は、民法705条の非債弁済として取り扱わざるをえないものと考えます。
「バックデートOK」とも「バックデートNG」ともはっきり述べておらず、煮え切らない整理ではあるものの、「理屈上は非債弁済でも契約(書)上の整理としてはありなんでしょうね」とは述べられており、一つの見解として参考になります。
押印の時代の「負の遺産」をデジタルに持ち越さないために
この地方自治法のバックデート問題は、実は今になってはじまった話でも、電子化によって新たに生みだされた問題というわけでもありません。
たんに、これまでの紙とハンコの押印実務で行われていたバックデートという名の現実的対応策が、デジタル化という光を浴びて明るみになっただけのことです。
地方自治事務のデジタル化にあたっては、本音と建前の使い分けでやり過ごしてきたこうした負の遺産についても、一つ一つ丁寧に解消していく必要があります。
ダウンロード


この資料では、電子契約サービス「クラウドサイン」を導入した茨城県笠間市、奈良県生駒市、千葉県浦安市の事例を紹介します。各自治体における電子契約サービス選びのポイントや、活用シーンを知りたい方はぜひダウンロードしてご活用ください。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司
弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。