示談書とは?書き方やテンプレート、注意点を紹介【弁護士監修】
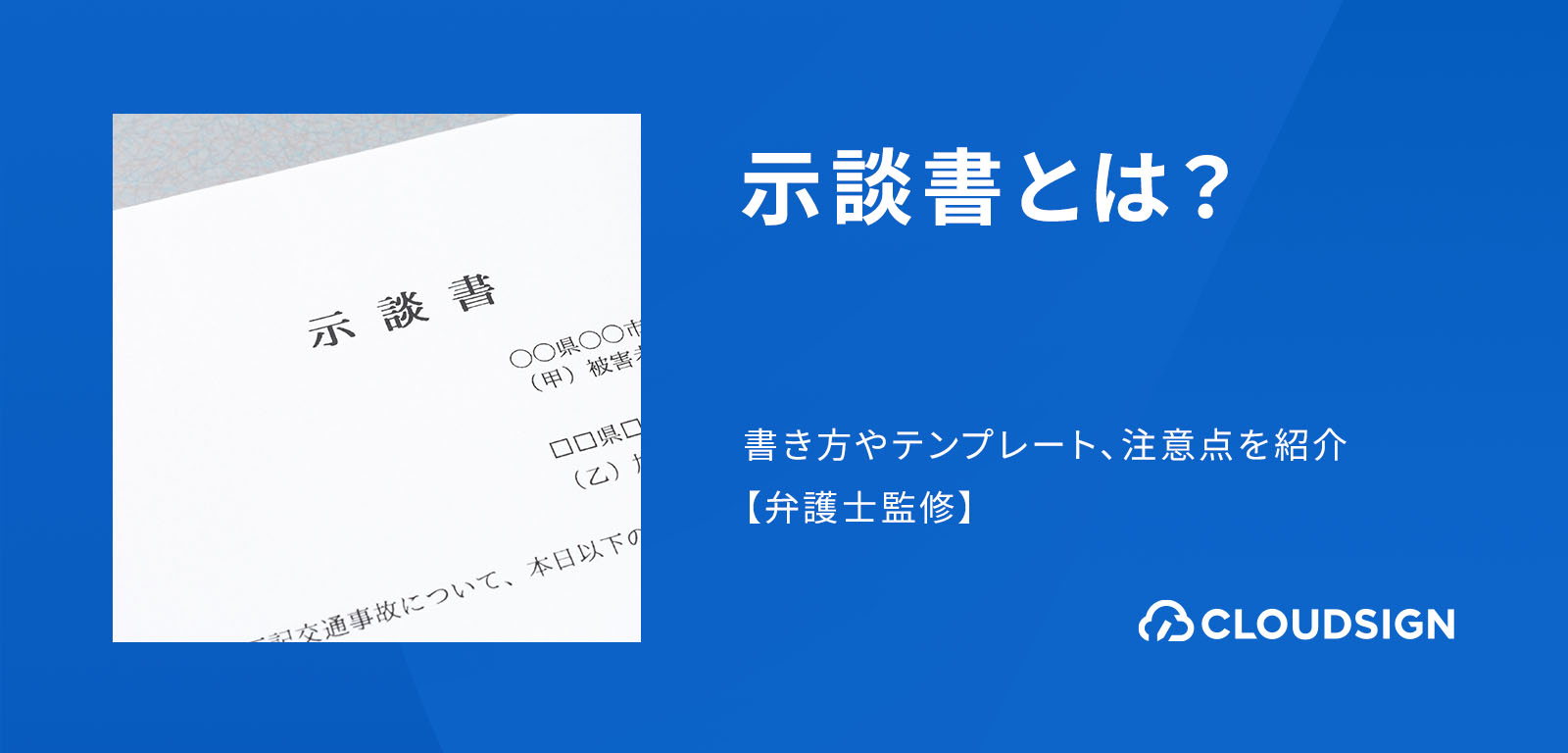
トラブルを円満に解決する手段として使われるのが「示談書」です。
口頭の約束では不安が残る場合でも、示談書を作成すれば、合意内容を明確に残し、後日起こりうる「言った・言わない」のトラブル防止に役立ちます。ただし、正しい形式で作らなければ法的効力が認められないこともあります。
この記事では、示談書の基本的な役割や書き方、作成時の注意点について、わかりやすく解説します。示談書の書き方がわからない方はぜひご一読ください。
示談書は従来、紙で作成・押印するのが一般的でしたが、近年ではより迅速かつ安全に手続きを進められる「電子契約の活用」が広がっています。特に、遠方の相手とのやり取りや、内容の改ざん防止といった観点からも、電子契約は有効な手段です。電子契約の基本から導入方法までを解説したガイドをご用意しましたので、示談書作成の効率化に関心のある方はぜひご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)示談書とは
示談書とは、トラブルや紛争が起きた際に、当事者同士で合意した解決内容をまとめた書類です。
たとえば交通事故や不倫、金銭トラブルなどで、加害者と被害者が話し合いによって解決に至った場合に、その合意事項を示談書として記載し、記録に残しておきます。
合意内容には、損害賠償や謝罪、再発防止に関する取り決めなどが含まれます。示談書を作成しておくことで、当事者双方の「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、合意が成立した証拠として後日の紛争回避の証拠としても役立ちます。
公正証書との違い
示談書は当事者間で作成できるのに対し、公正証書は公証役場で公証人の関与のもとに作成されます。
また、公正証書には執行力を持たせることが可能な点が大きな違いです。
たとえば金銭の支払いに関する条項を含む場合、あらかじめ執行受諾文言を入れておけば、支払いが滞った際に裁判を経ずに財産の差押えを行なうことも可能になります。
示談書の主な目的
示談書を作成する最大の目的は、当事者間での合意内容を文書という形式で明確に残しておくことで、後のトラブルを防ぐことです。
たとえば、加害者が被害者に対して損害賠償を支払う、あるいは謝罪文を提出するなど、具体的な対応内容を文書に残すことで、口約束による誤解や認識違いを防げます。
また、「一度は示談に応じたが、やはり納得できない」と後になって言い出されるリスクも軽減できます。
示談書には再請求を禁じる「清算条項」を入れるのが一般的で、これにより同じ事案についての再請求や裁判提起を防ぐ効果も期待できます。
さらに、万が一裁判に発展した際には、示談書が有力な証拠資料として機能します。自筆で署名押印された示談書があれば、裁判所でも合意が成立していた事実を証明しやすくなります。
ごくまれに、錯誤・詐欺・脅迫などで示談を取り消されたりすることがあります。それを防ぐ場合には、示談前後の様子を録画などしておくとさらによいでしょう。
示談書の法的効力
示談書は、当事者間で起きたトラブルや紛争について話し合いで解決した内容を文書化したものです。この示談書は、民法上の契約として扱われ、当事者の間で法的な拘束力を持ちます。
たとえば、不倫や交通事故などのトラブルにおいて、損害賠償や謝罪、再発防止の約束といった合意内容を示談書に明記すれば、その内容に従う義務が双方に生じます。
万が一、一方が示談内容を履行しなかった場合、もう一方は裁判を通じて損害賠償を請求したり、約束の履行を求めたりすることが可能です。
ただし、示談書を作成するだけでは、すぐに強制執行ができるわけではありません。たとえば「示談金の支払いが滞った場合に、給料や財産を差し押さえる」といった手続きを取るためには、示談書の内容を公正証書にしておく必要があります。
公正証書に「強制執行認諾条項」が含まれていれば、裁判を経ずに差し押さえなどの強制執行が可能になります。
また、示談書の内容が公序良俗に反する場合(たとえば、刑事事件における被害届の取り下げと引き換えに過度な金銭を要求するなど)は、無効とされることもあります。
法的効力を持たせるには、当事者双方の自由な意思に基づき、適法かつ具体的な内容で作成されていることが必要です。
このように、示談書には一定の法的効力がありますが、確実にその効力を発揮させるためには、公正証書化や内容の適切な設計が重要になります。
示談書を作成する際は、法的トラブルを未然に防ぐためにも、必要に応じて弁護士に相談することが望ましいでしょう。
示談書がよく用いられる場面の例
示談書は、裁判に持ち込まず早期解決を目指したい多くの法的トラブルで用いられます。
話し合いによる合意を文書に残すことで、当事者間の争いが再燃するリスクや証拠不在の不安を低減できます。以下に代表的な場面を紹介します。
交通事故
交通事故では、損害賠償や示談金の支払い、責任割合などを当事者間で合意し、示談書にまとめるケースが一般的です。
示談書により支払条件が明確になり、後の未払いトラブルを防止できます。また、保険会社が示談書をサポートすることもあります。
刑事事件
刑事事件では、被害者との示談が不起訴を導く要素になることがあります。
加害者が被害者へ謝罪や損害賠償を約束し、その内容を示談書として文書化することで、検察判断に影響を与えることもあります。
示談書には被害届の取り下げや口外禁止の条項が含まれることがあります。さらに宥恕文言(許すという意味)で被害届を出さない、今後提出しない、などの約束を交わすこともあります。
不倫(不貞行為)
不貞行為では、被害者が加害者に対し慰謝料や今後の関係清算を約束させる目的で示談書を作成します。
多くの場合、示談書には謝罪、慰謝料の額と支払い条件、再発防止や連絡禁止などの合意内容が記載され、双方の納得を明確に残します。
金銭トラブル
貸し借りや契約違反による未払いなど、金銭トラブルの解決にも示談書はよく用いられます。
債務者が返済する額や期限、遅延時の対応などを明記し、再請求を防ぐ意味合いもあります。書面化することで、証拠としても有用です。
労働問題
残業代未払い・退職トラブルなど、雇用における労働紛争でも示談書は活用されます。
双方が合意した条件を書面に残すことで、後に労働基準監督署や訴訟に発展しないように配慮できます。
未払い賃金の清算方法や和解内容を明示する形が一般的です。
名誉棄損・誹謗中傷
SNSやネット上の中傷による名誉侵害では、投稿削除や謝罪、慰謝料請求の条件を示談書でまとめることがあります。
示談により投稿者との合意が文書化されれば、証拠として残ると同時に、再投稿や報復から防衛する効果が期待できます。
示談書のテンプレート
以下は、一般的な示談書のテンプレートです。あくまで、記載例になりますので、実際に利用する際は個別の事案に応じて、金額や具体的な合意内容を調整してください。必要に応じて弁護士のチェックを受けるのがよいでしょう。
〇〇(以下「甲」という)と、△△(以下「乙」という)は、下記のとおり示談することに合意し、本書を作成する。第1条(示談の原因)
甲と乙は、以下のトラブルについて協議を行い、円満に解決することで合意した。【例:乙が甲に対して不貞行為を行った件】
※示談すべき行為の内容を明確にすること
第2条(示談金の支払い)
乙は甲に対し、本件に関する解決金として金○○円を支払う。
支払期日:令和○年○月○日
支払方法:甲が指定する銀行口座に振込むものとする。
第3条(秘密保持)
甲および乙は、本件示談の内容について正当な理由なく第三者に口外しないことを約する。
第4条(清算条項)
甲及び乙は、本件につき、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。
※示談後に再請求をしたり、法的措置を取ったりしないことを約束する
第5条(その他)
本示談書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ誠実に解決を図る。
以上、示談の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名・押印のうえ、各1通を保有する。
令和○年○月○日
【甲】
住所:
氏名: (署名・押印)
【乙】
住所:
氏名: (署名・押印)
このテンプレートは私文書形式ですが、必要に応じて公正証書化することも検討してください。
示談書の記載事項
示談書を有効なものとするためには、記載すべき基本的な要素を正確に盛り込むことが重要です。
ここでは、一般的な示談書に必要とされる主な項目について説明します。
タイトル
文書の冒頭には「示談書」「合意書」「和解契約書」などのタイトルを明記します。
文書の性質を明らかにし、第三者が見ても示談の記録であることが一目でわかるようにするためです。
前文
前文では、当事者の氏名や住所、立場(例:加害者・被害者)を記載し、何についての示談であるかを簡潔に述べます。
例:「甲と乙は、以下の事案に関し協議のうえ、以下のとおり合意した」など。
示談の原因
示談の対象となる事実関係を記載します。
たとえば「令和〇年〇月〇日に発生した交通事故について」や「不貞行為に基づく慰謝料請求に関して」など、紛争の原因や背景を明示しておくことで、誤解や解釈の相違を防げます。
合意内容
示談書の中心となる部分です。トラブルの内容や目的に応じて、以下のような内容を盛り込むことが一般的です。
- 事実の確認:当事者間で争いのない事実を明記
- 損害賠償金について:支払金額・支払期限・振込先などを明記
- 接触禁止:今後一切の連絡を禁止する場合などに明記
- 守秘義務:内容を第三者に漏らさない旨の条項
- 清算条項:「本件に関し、当事者間に一切の債権債務がないことを相互に確認する」など、トラブルの完全な終結を明記
- その他:必要に応じて、準拠法や管轄裁判所の指定などを加える
具体的であればあるほど、後のトラブル防止につながります。
日付
合意した日付を明記します。示談の効力がいつから発生するのかを示す意味でも重要です。基本的に元号を使用し、書類内の他の日付と表記を統一しましょう。
当事者の署名・押印
最後に、合意した当事者の氏名・住所を記載し、直筆で署名し押印します。署名・押印により、当事者が内容に同意した意思が明確になります。
法人の場合は、代表者名と社印を記載します。
示談書を作成する際の注意点
示談書はトラブルを円満に解決する有効な手段ですが、内容によっては後々トラブルの火種になることもあります。作成時には、次のような点に注意が必要です。
内容を十分に確認し、安易にサインしない
その場の雰囲気に流されて、よく読まずにサインするのは避けましょう。
示談書に一度サインすると、原則としてその内容に拘束され、後から「やっぱり納得していない」と言っても効力を覆すのは困難です。
特に、金銭の支払いや損害賠償請求の放棄などに関する条項は慎重に確認する必要があります。
不利な内容になっていないか確認する
示談書の内容が一方に著しく不利な場合、思わぬ損失を被るおそれがあります。
たとえば、過剰な損害賠償義務や将来にわたる請求権の放棄などが含まれていないか注意が必要です。
専門用語や複雑な表現がある場合には、その意味を明確にしてから合意しましょう。
重要な示談は専門家(弁護士)に相談する
特に、金額が大きい案件や刑事事件に関わる示談は、弁護士に内容を確認してもらうのが安心です。
法的な抜け漏れを防ぐだけでなく、万が一トラブルが再燃した場合にも示談書が有効な証拠として機能するように整えてもらえます。
自分で作成する場合でも、内容のチェックのみを専門家に依頼する方法もあります。
示談内容を公正証書化するかどうか検討する
示談内容に金銭の支払いが含まれる場合、トラブルの再発防止や未払いリスクの低減を目的として、公正証書化を検討するのが有効です。
特に「強制執行認諾条項」を記載した公正証書は、民事執行法第22条に基づき、裁判を経ずに強制執行(例:差押え)を行うことが可能です。
示談金が高額な場合や確実な履行を求める場合には、公証役場での手続きを視野に入れましょう。
【参考:e-Gov 民事執行法 第二章 強制執行 (債務名義)第二十二条 第五号】
相手に強制された形跡がないようやり取りの記録を残す
示談が有効と認められるには、当事者双方の自由な意思に基づいて合意されたことが前提です。
たとえば「脅されたからサインした」といった主張が後から出されると、示談書が無効とされる可能性もあります。
口頭だけのやり取りではなく、メールや書面、録音などを通じて交渉の経緯を残しておくと安心です。
示談書に関するよくある質問
示談書は手書きでも作れる?
手書きでも問題ありません。パソコン作成でもよく、どちらも法的効力に差はありません。
ただし、修正のしやすさや誤記防止の観点から、パソコンでの作成が便利です。署名欄は直筆で記入し、捺印も行いましょう。
示談書は公正証書にした方がいい?
示談金などを確実に支払ってもらいたい場合、公正証書にするのは有効です。
公正証書には「強制執行認諾条項」を付すことで、裁判なしに差し押さえなどの強制執行が可能になります。特に示談金が高額なケースでは検討すべき手段です。示談金が高額になる場合、強制執行時の財産を調査しておくことも大切です。
示談書は自分で作れる?
示談書は法律の専門家でなくても作成可能ですが、内容に不備があったり不利な条件になっていたりするリスクもあります。
自作する際は、テンプレートやひな形を参考にしつつ、必要に応じて弁護士にチェックを依頼するのがおすすめです。
示談書は電子契約でも送信できる?
示談書は電子契約でも送信・締結可能です。電子契約を利用することで、紙の書類で必要だった郵送費や印刷費などの経費を削減できるため、コストカットの効果があります。
また、電子契約の場合、PDF化した示談書の電子ファイルに電子署名を付与することで、示談書の改ざんができないようになるため、証拠としても信頼性の高いものになります。
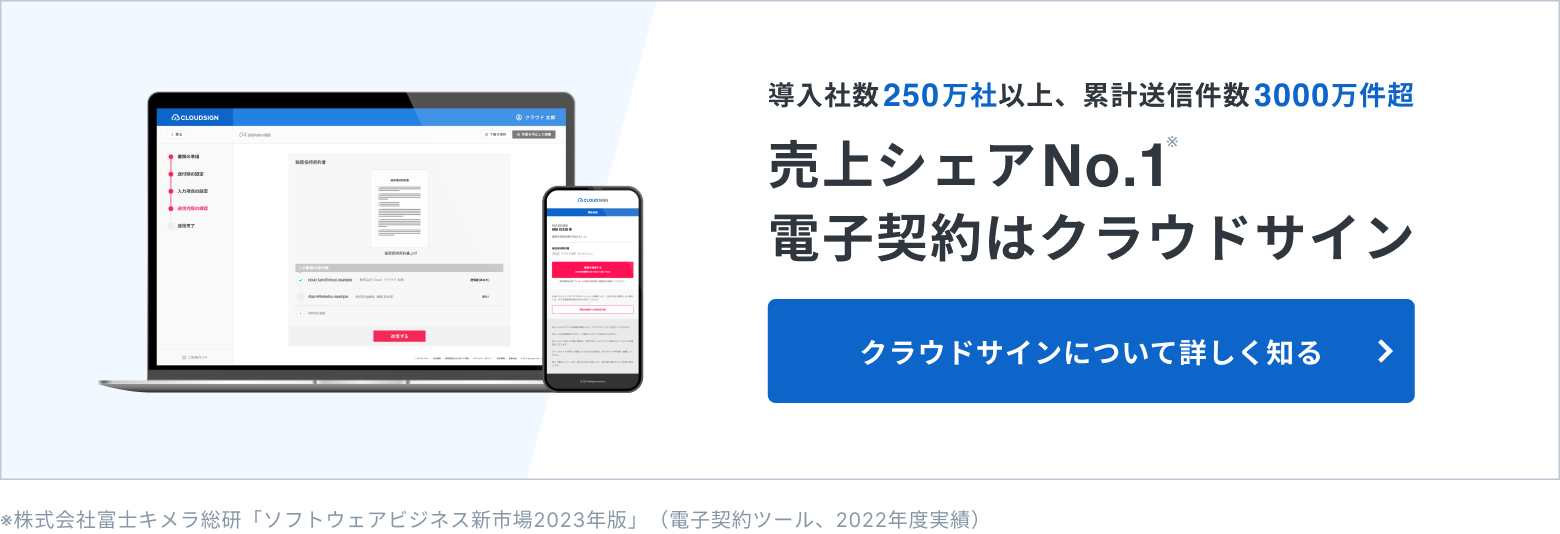
電子契約の基礎知識やメリットなどをまとめて知りたい方はこちらの資料をダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード
まとめ
示談書は、トラブル解決の合意内容を明確に残す重要な文書です。
金銭の支払いや接触禁止などを具体的に記載し、双方が納得のうえで署名・押印することで、法的な効力を持ちます。強制力を高めたい場合は、公正証書化も検討しましょう。作成時は内容を慎重に確認し、必要に応じて弁護士へ相談することが大切です。
近年では示談書を電子契約で締結するケースも増えています。電子契約サービスを利用すれば、遠方の当事者とも迅速に合意内容を取り交わすことができ、郵送の手間やコストを削減できます。さらに、電子署名によって本人性が担保され、改ざん防止にも繋がるため、より安全かつ効率的に示談手続きを進めることが可能です。
示談書をはじめ、契約業務全般の効率化やDX推進に関心をお持ちの方は、各種契約に利用できるクラウドサインのサービス概要がわかる下記資料もぜひご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
加藤高明
弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
契約実務
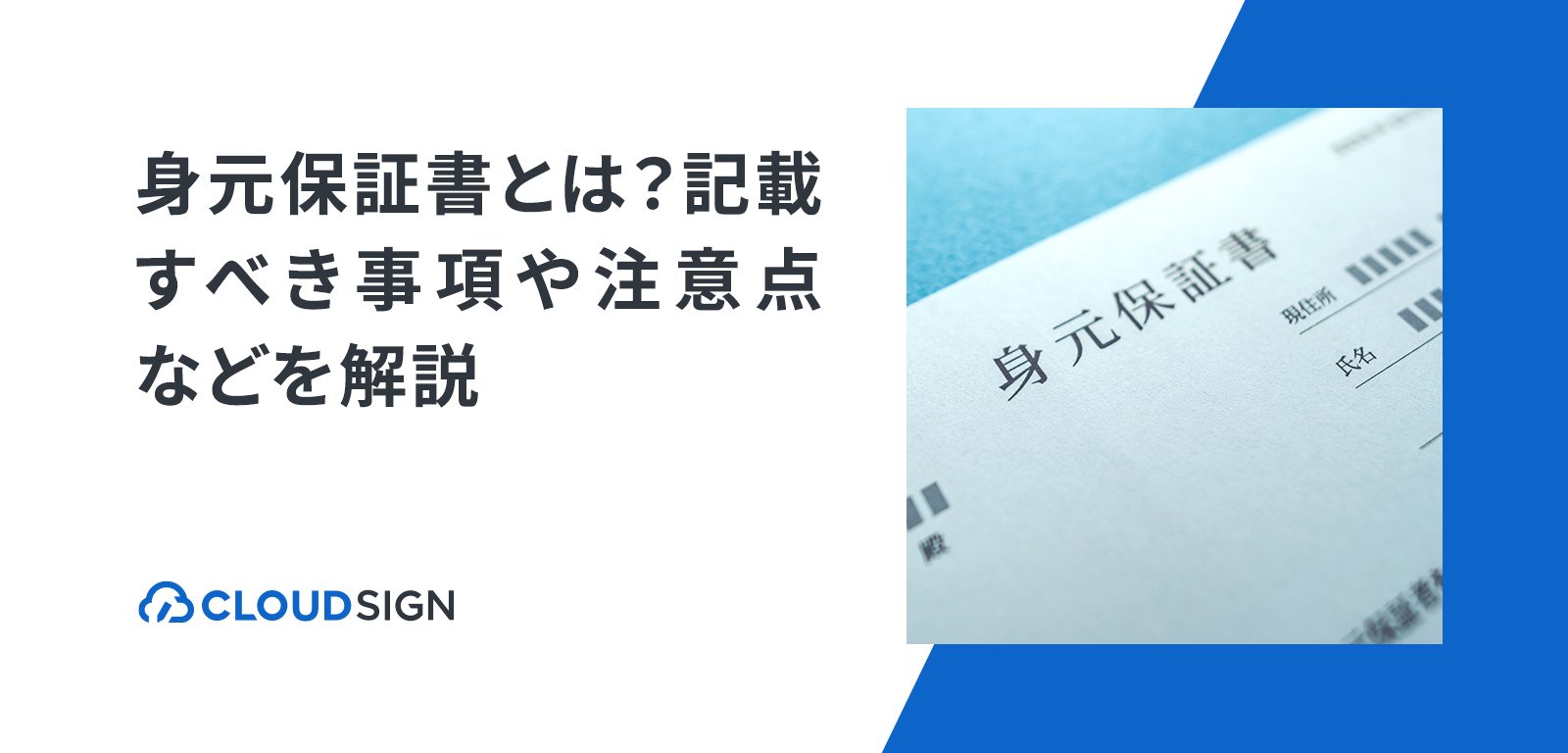
【弁護士監修テンプレートあり】身元保証書とは?記載すべき事項や注意点などを解説
契約書電子契約書 -
契約実務
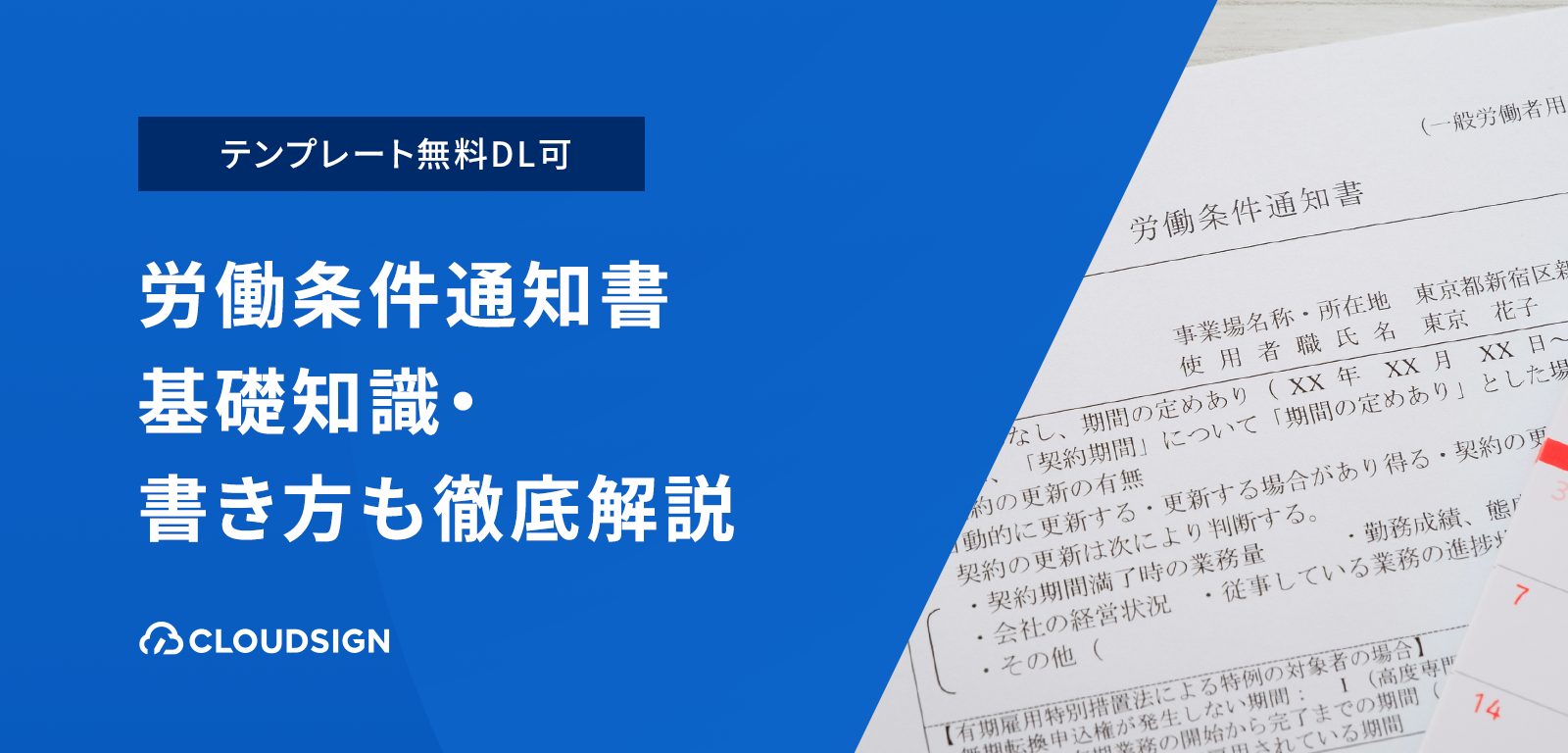
【無料DL可】労働条件通知書のテンプレート 基礎知識と書き方も徹底解説
契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -
電子契約の運用ノウハウ
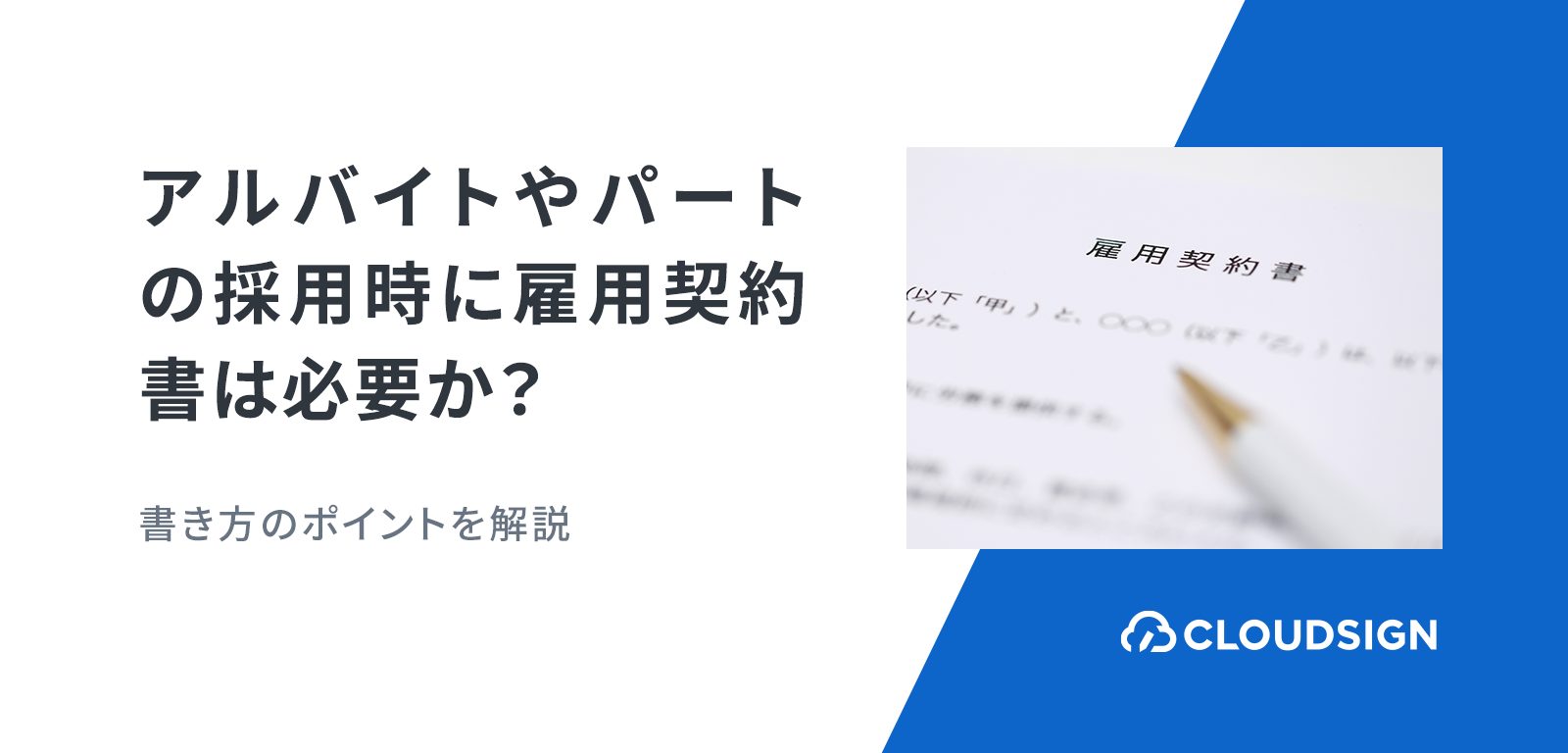
アルバイトやパートの採用時に雇用契約書は必要か?書き方のポイントを解説
雇用契約 -
契約実務
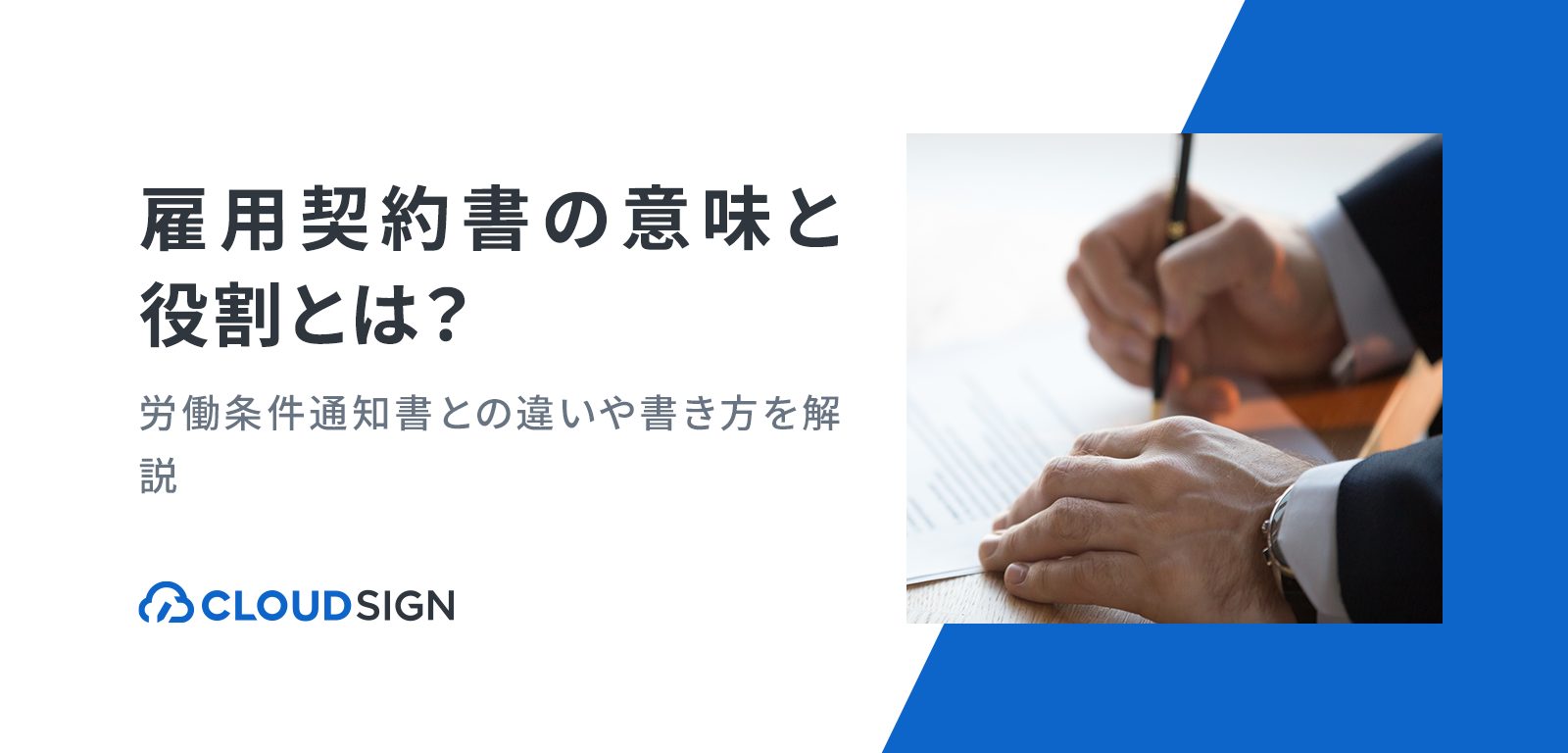
雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや書き方と記載項目を解説
雇用契約 -
電子契約の運用ノウハウ
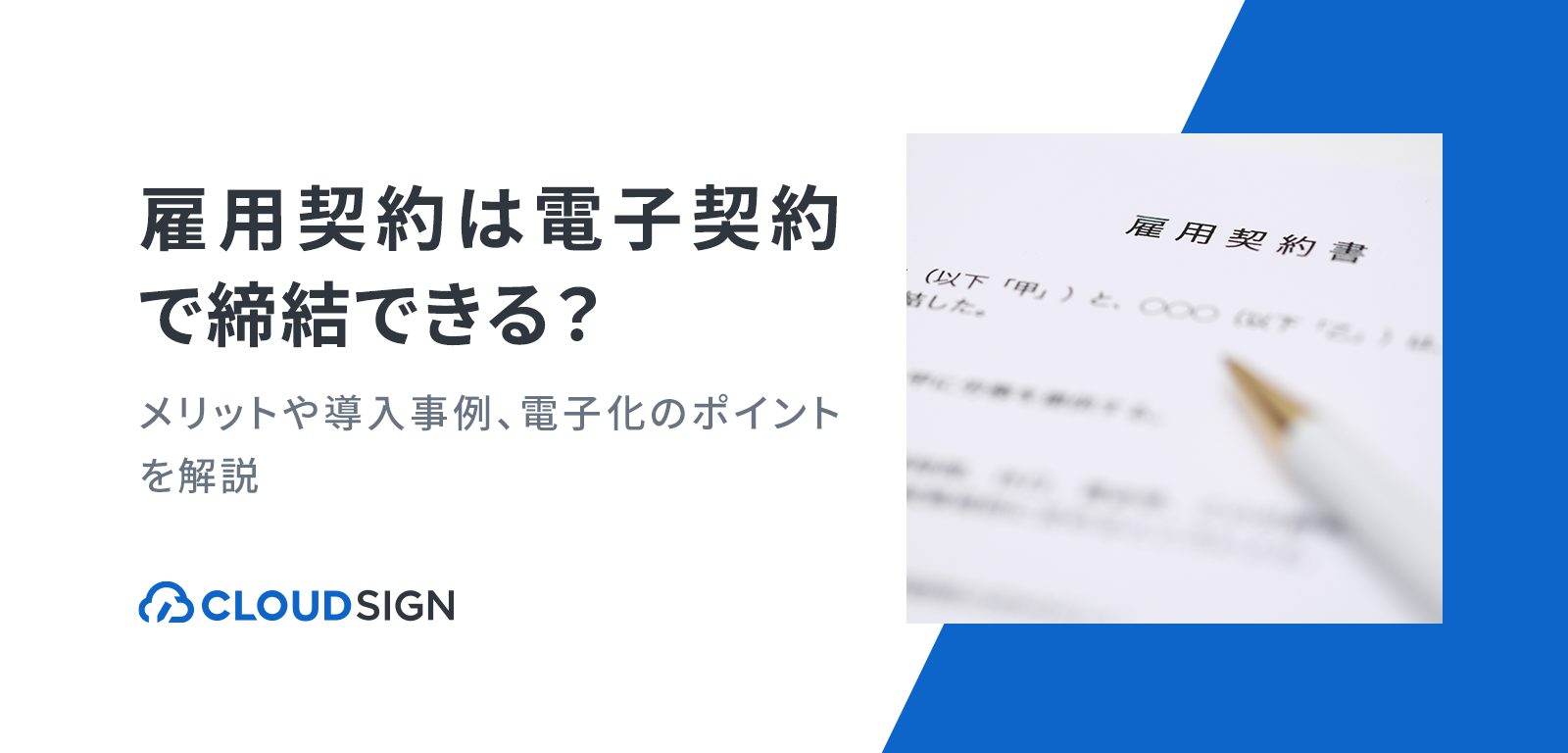
雇用契約は電子契約で締結できる?メリットや事例を解説【Word版ひな形ダウンロード付】
電子契約の活用方法雇用契約 -
電子契約の運用ノウハウ

なぜ今「人事労務に電子契約」か?雇用契約を電子化するメリットと実務的Q&Aを解説
雇用契約人事労務