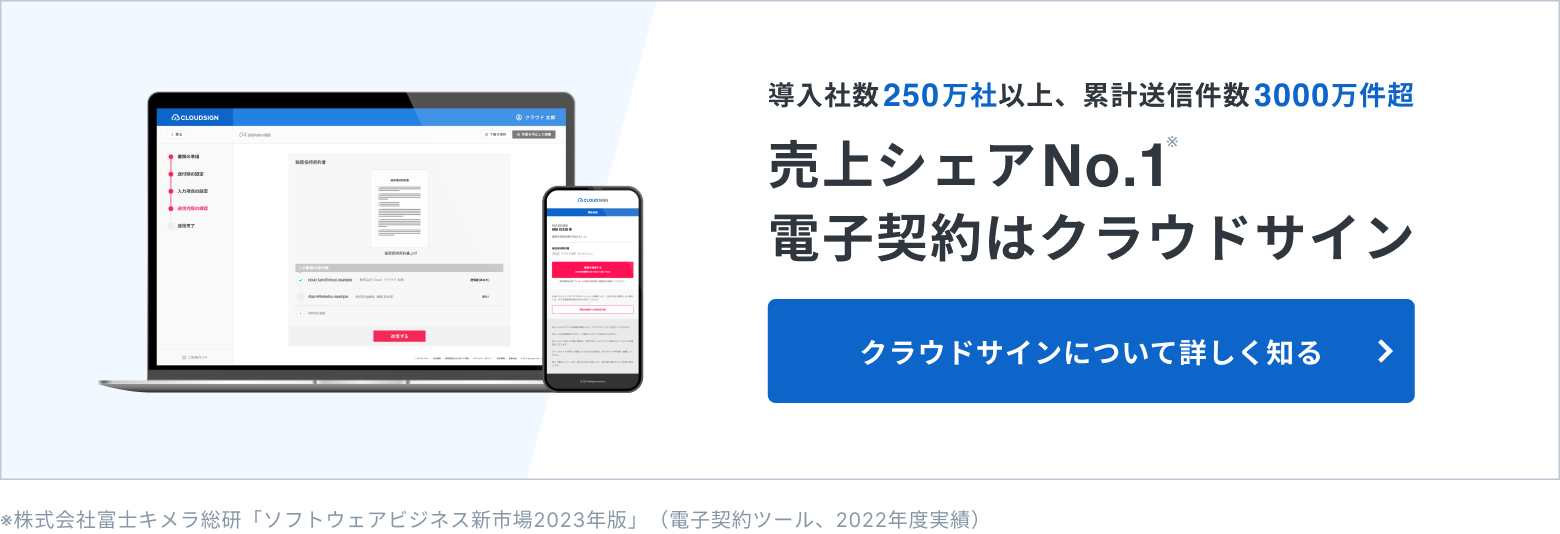労働基準法とは?代表的なポイント・よくある違反例について解説【弁護士監修】
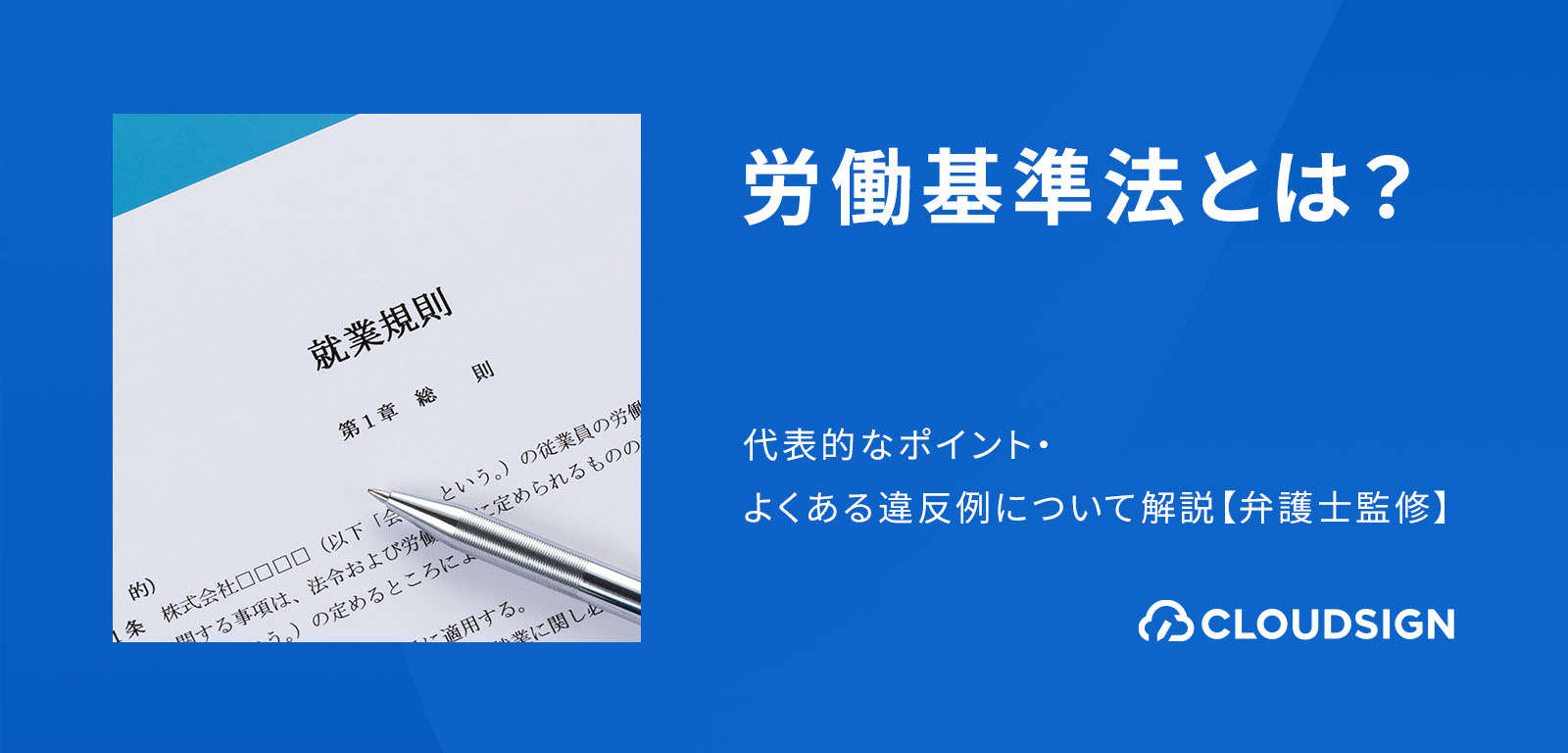
企業が人を雇ううえで、必ず押さえておきたいのが「労働基準法」です。
働く時間や休みの取り方、賃金の支払い方など、すべての労働者に共通する“最低限のルール”を定めた法律であり、たとえ合意があってもこの基準を下回る契約は無効とされます。
ここでは、労働基準法の基本的な仕組みとよくある誤解、違反のリスクについてわかりやすく解説します。
なお、当記事で解説する労働基準法の遵守には、適切な雇用契約書や労働条件通知書の管理が必要です。コンプライアンス強化と業務効率化を両立できる方法として電子契約があげられます。電子契約について、基本から分かる資料を無料でご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード
目次
労働基準法とは?わかりやすく解説
労働基準法は、すべての労働者のために設けられた「最低限のルール」を定めた法律です。ここでは、基本的な仕組みや適用対象についてわかりやすく解説します。
労働基準法の目的
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めることで、労働者の健康・生活を守ることを目的としています(第1条)。
一人ひとりが安心して働ける環境を保障するための法律であり、企業側の裁量に任せきりにしないよう、労働時間や賃金、休日などのルールを国が定めています。
この法律があることで、働く人の基本的な権利が守られています。
労働基準法の対象となる労働者と適用除外のケース
労働基準法は、会社などに雇用されて賃金を受け取って働く「労働者」すべてに適用されます。
雇用形態に関係なく、正社員、契約社員、パート、アルバイト、外国人労働者などが対象です。
労働基準法が適用されない人には、「使用者」に該当する経営者や役員・個人事業主など、そして一部の公務員や船員が挙げられます。また、農業・畜産・養蚕・水産業従事者や、労働時間・休憩・休日に関する適用除外となる管理監督者、そして監督官の許可を受けた監視・断続的労働に従事する者も、労働時間・休憩・休日については適用されません。?
労働基準法の基本原則(労働憲章)
労働基準法には「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むためのものでなければならない」(第1条)という大原則があります。
これを含む基本的な考え方は「労働憲章」とも呼ばれ、労使対等・労働契約の明示・不当解雇の禁止など、法律全体に通底する7つの原則が定められています。
この基本原則は、後の条文で繰り返し具体化されており、労働者保護の出発点となる考え方です。
労働基準法の代表的な部分をわかりやすく解説
ここでは、雇用契約の締結時や日々の勤務に関わる重要なルールを解説します。
労働条件の明示(第15条)
労働基準法第15条では、使用者は労働契約を結ぶ際に、労働者に対して労働条件を明示しなければならないと定めています。
第15条第1項:「労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」
【引用】e-GoV第二章労働契約(労働条件の明示)第十五条
特に、賃金や労働時間、就業場所、業務内容などの「絶対的明示事項」は、書面(または電子的手段)で交付する義務があります。
条件が曖昧なまま雇用が始まると、のちのトラブルにつながるため、契約時の確認が重要です。
労働時間・休憩・休日のルール
労働基準法では、以下のような時間に関するルールが明確に定められています。
・1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならない(第32条)
・6時間超の勤務で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩を与える(第34条)
・毎週少なくとも1日の休日を与える(第35条)
【引用】e-GoV第四章労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(労働時間)
第三十二条、(休憩)第三十四条、(休日)第三十五条
これらの基準は最低ラインであり、労使の合意があっても下回ることはできません。
業種や就業形態に応じて「変形労働時間制」や「フレックスタイム制」もありますが、導入には就業規則での定めや労使協定の締結が必要です。
賃金支払いの原則(第24条)
労働基準法第24条では、賃金の支払いに関して以下の原則が設けられています。
第24条第1項:「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」
【引用】e-GoV第三章賃金(賃金の支払)第二十四条
この「通貨払い」「直接払い」「全額払い」「毎月1回以上・一定期日払い」の原則は、いずれも労働者の生活安定を目的としたものです。
なお、近年は労使間の同意や一定の条件のもと、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座へ送金)も認められるようになっています。
時間外・休日・深夜労働の割増賃金(第37条)
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働には、割増賃金の支払いが義務付けられています(第37条)。
・時間外労働:25%以上の割増
・休日労働:35%以上の割増
・深夜労働(22時~5時):25%以上の割増
【引用】e-GoV第三章賃金(賃金の支払)第三十七条
また、時間外労働をさせる場合には、労使間で36協定(サブロク協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定がない状態での時間外労働は、たとえ労働者の同意があっても違法です。
なお、2023年4月1日より、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、大企業・中小企業を問わず50%以上に統一されています。
出典:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
年次有給休暇(第39条)
労働基準法第39条では、一定の条件を満たす労働者に年次有給休暇(年休)を与える義務が定められています。
第39条第1項:「使用者は、継続勤務6か月以上かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日以上の有給休暇を与えなければならない。」
【引用】e-GoV第四章労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(年次有給休暇)
第三十九条
付与日数は最低10日で、勤続年数に応じて増加し、最大20日まで付与されます。
さらに、2019年の法改正により、年5日の年休を確実に取得させることも義務化されました。
有休の取得時期や方法は、就業規則であらかじめ定めておくとトラブルを防げます。
解雇のルール(第20条・第21条)
労働者を解雇する際には、労働基準法第20条に基づき30日前の予告が必要です。
予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う義務が発生します。
また、第21条では、予告や手当が不要とされる「例外規定」も設けられていますが、その適用には労働基準監督署長の認定が必要です。
不当解雇があった場合には、民事上の損害賠償責任を問われるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
なお、労働契約法第16条では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇は、権利の濫用として無効になります。つまり、予告や手当を支払えば自由に解雇できるわけではありません。
最低賃金法との連動(第28条)
労働基準法第28条では、「最低賃金の定めを下回る労働契約は無効」と明記されています。
最低賃金は都道府県ごとに定められ、地域別・産業別に異なる場合があります。
第28条:「賃金の最低基準は、最低賃金法の定めるところによる。」
【引用】e-GoV第三章賃金(最低賃金)第二十八条
このため、労働基準法と最低賃金法はセットで理解する必要があります。
最低賃金額は毎年見直されているため、最新の金額を把握し、契約条件が下回っていないかを確認することが重要です。
就業規則の作成と届出
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準法第89条に基づき、就業規則の作成と所轄労働基準監督署への届出が義務付けられています。
就業規則には、始業・終業時刻、休日、休暇、賃金、退職など、労働条件の基本的な事項を明記します。
また、変更を行う際も、労働者の意見を聴取したうえで届け出る必要があります。
企業が労働基準法を守らないとどうなる?
労働基準法は「最低限守るべきルール」であり、違反すれば行政処分や刑事罰、損害賠償などの重大なリスクが生じます。
ここでは、企業側が法令違反によって直面する3つの代表的な責任について解説します。
刑事罰を受ける
労働基準法に違反した場合、企業や経営者に対して罰金刑や懲役刑が科されるケースがあります。
たとえば、労働者に危険な業務をさせて死亡事故が発生した場合や、賃金不払いや解雇制限違反などは、重大な法令違反とみなされます。
2025年9月時点における労働基準法第120条以下では、違反内容ごとに刑事罰の内容が明記されています。
・賃金支払い義務違反→6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(第120条)
・解雇予告義務違反→同上(第120条)
・労働条件の明示義務違反→30万円以下の罰金(第120条)
・就業規則の届出義務違反→10万円以下の罰金(第121条)
【引用】e-GoV第十三章罰則第百二十条第百二十一条
これらの罰則は、実際に送検され報道されるケースも少なくありません。
法令を遵守しなかった場合、「知らなかった」では済まされないリスクがあることを認識しておく必要があります。
行政指導や是正勧告を受ける
企業が労働基準法に違反していると、労働基準監督署から行政指導や是正勧告を受けることになります。
調査は、労働者からの申告や定期監督(立ち入り調査)などをきっかけに行われます。
違反が認められた場合、まずは口頭または文書による指導や是正勧告書が交付され、改善期限が設けられます。
期限内に改善が行われなければ、再指導や書類送検の対象となることもあります。
是正勧告は法的強制力を持つものではありませんが、従わない場合は刑事罰に発展するおそれがあります。
また、厚生労働省は毎年、監督指導の結果や送検事例を公表しており、企業名が明記されることもあります。
こうした情報が公開されることで、企業の信用や採用力にも悪影響が及ぶ可能性があるため、行政対応も無視できないリスクのひとつです。
民事上のリスク
労働基準法違反は、民事上の責任を問われるリスクにもつながります。主なトラブル例は以下のとおりです。
・精神的損害に対する慰謝料請求:長時間労働やハラスメントが原因でうつ病を発症した場合、企業の安全配慮義務違反が認定されれば損害賠償が命じられます。
・不当解雇に対する損害賠償請求:解雇理由が不明確・不合理だった場合、解雇無効と判断され、賃金支払義務が継続するケースもあります。
さらに最近では、SNSや口コミサイト、メディアを通じて、企業の法令違反が告発されるケースも増えています。
「炎上」や信用失墜によるreputationaldamage(評判リスク)は、金銭的損害以上に深刻な経営課題になりかねません。
企業が違反しがちな労働基準法の(チェック)ポイント
労働基準法には多くのルールがありますが、なかでも現場で見落とされやすいポイントには注意が必要です。
ここでは、企業がついやってしまいがちな違反例を7つに絞り、実務上のチェックポイントとして整理します。
時間外労働の上限を超えていないか?
36協定を締結しても、時間外労働は原則月45時間・年360時間までです。臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)でも、以下の上限をすべて遵守する必要があります。
- 時間外労働の上限は年720時間
- 時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計は、複数月平均(2~6か月)で80時間以内
- 月45時間を超える時間外労働は、年6か月まで
これらの複雑な上限規制を正しく理解し、遵守しているか確認が必要です。
残業代は正しく支払われているか?
時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合には、労働基準法第37条に基づき、法定の割増率に応じた残業代の支払いが必要です。
「みなし残業制」「固定残業代制」を導入している場合でも、制度の設計や運用が適切でなければ無効とされるリスクがあります。
実際の労働時間に応じた計算ができているか、あらためて確認が必要です。
労働条件を明示しているか?
雇用契約を結ぶ際、使用者は賃金・労働時間・業務内容などの労働条件を明示する義務があります(第15条)。
特に「賃金・就業場所・始終業時刻・休日」などの項目は書面または電子的手段での交付が必須とされています。
口頭での説明や、曖昧な契約内容ではトラブルにつながるため、雇用契約書や労働条件通知書を正しく整備しておきましょう。
有給休暇の取得をさせているか?
年次有給休暇(年休)は、6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日以上の付与が義務付けられています(第39条)。
さらに、2019年からは年5日の有休取得を確実に行わせる義務も加わりました。
取得の申請があった場合に「繁忙期だから」と拒否し続ける対応は違法となる可能性があります。
解雇予告は適切に行なっているか?
労働者を解雇する場合、30日前の予告または30日分以上の平均賃金の支払いが必要です(第20条)。
「急に辞めさせたい」といった理由で即日解雇を行うと、不当解雇として無効と判断されるおそれがあります。
試用期間中の解雇であっても14日を超えている場合には予告義務が生じるため、制度の誤解には注意が必要です。
最低賃金の違反はしていないか?
最低賃金は、都道府県ごとに定められた額以上の時給を支払う義務があります(第28条)。
支給する賃金には、基本給だけでなく手当や残業代の扱いも関係するため、単純な時給計算では不足が生じることもあります。
最低賃金は毎年見直されており、最新の金額と合致しているか定期的な確認が必要です。
休憩時間を正しく、自由に利用させているか?
労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える義務があります(第34条)。
この休憩は「一斉に」「自由に利用できる」ことが原則とされています。
休憩中も電話番や来客対応などの業務を命じている場合、休憩として認められない可能性があり、隠れた労働時間とみなされることもあります。
「労働基準法をわかりやすく」に関するよくある質問
労働基準法に関しては、「何を定めている法律なのか」「どこまで適用されるのか」といった素朴な疑問も多く寄せられます。
ここでは、よくある質問を整理し、基本をおさらいします。
労働基準法の基本7原則とは?
労働基準法の第1章「総則」では、労使対等・最低基準の保障・契約条件の明示など、法律全体の土台となる7つの原則が示されています。これらは「労働憲章」とも呼ばれています。
労働基準法はなぜできた?
戦後の混乱期に、労働者の過酷な労働環境を改善し、生活の安定を図ることを目的として制定されました(1947年施行)。労働者保護の理念が強く反映されています。
労働基準法と厚生労働省の関係は?
労働基準法の所管官庁は厚生労働省です。法改正やガイドラインの策定、運用指針の公表など、制度全体の企画・管理を担っています。
労働基準監督署とは?
労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関として各地域に設置されており、法令違反の調査・是正指導・送検業務などを担当します。現場での監督実務を担う重要な機関です。
労働基準法の基礎知識は?
労働基準法は、労働時間・賃金・休暇・解雇など、雇用に関する最低限のルールを定めています。
違反すると行政処分や刑事罰、民事上の損害賠償が発生する可能性があります。
パートやアルバイトにも労働基準法は適用される?
労働基準法は、雇用形態にかかわらず「労働者」に該当する人すべてに適用されます。パート・アルバイト・外国人労働者も例外ではありません。
まとめ
労働基準法は、すべての労働者を対象に、雇用の現場で守るべき最低限のルールを定めた法律です。
労働時間や賃金、有給休暇、解雇のルールなど、実務に直結する項目が多く、企業には正確な理解と運用が求められます。
違反すれば、行政指導や刑事罰、損害賠償だけでなく、企業の信用を大きく損なう可能性もあります。
法令順守を徹底し、働きやすい環境づくりを進めることが、組織の持続的な成長にもつながります。
なお、労働基準法をはじめとする法令遵守には、雇用契約書や労働条件通知書といった書類の適切な管理が必要です。電子契約サービス「クラウドサイン」を導入すれば、これらの書類をオンラインで迅速かつ安全に締結・保管できます。書類の作成から送付、保管までを一元管理することで、人的ミスを防ぎ、管理コストを削減。テレワークなど多様な働き方にも対応しやすくなります。
当社では「電子契約の始め方」の資料を無料でダウンロードいただけます。ぜひ、貴社のコンプライアンス強化と業務効率化にお役立てください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
加藤高明
弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
契約実務
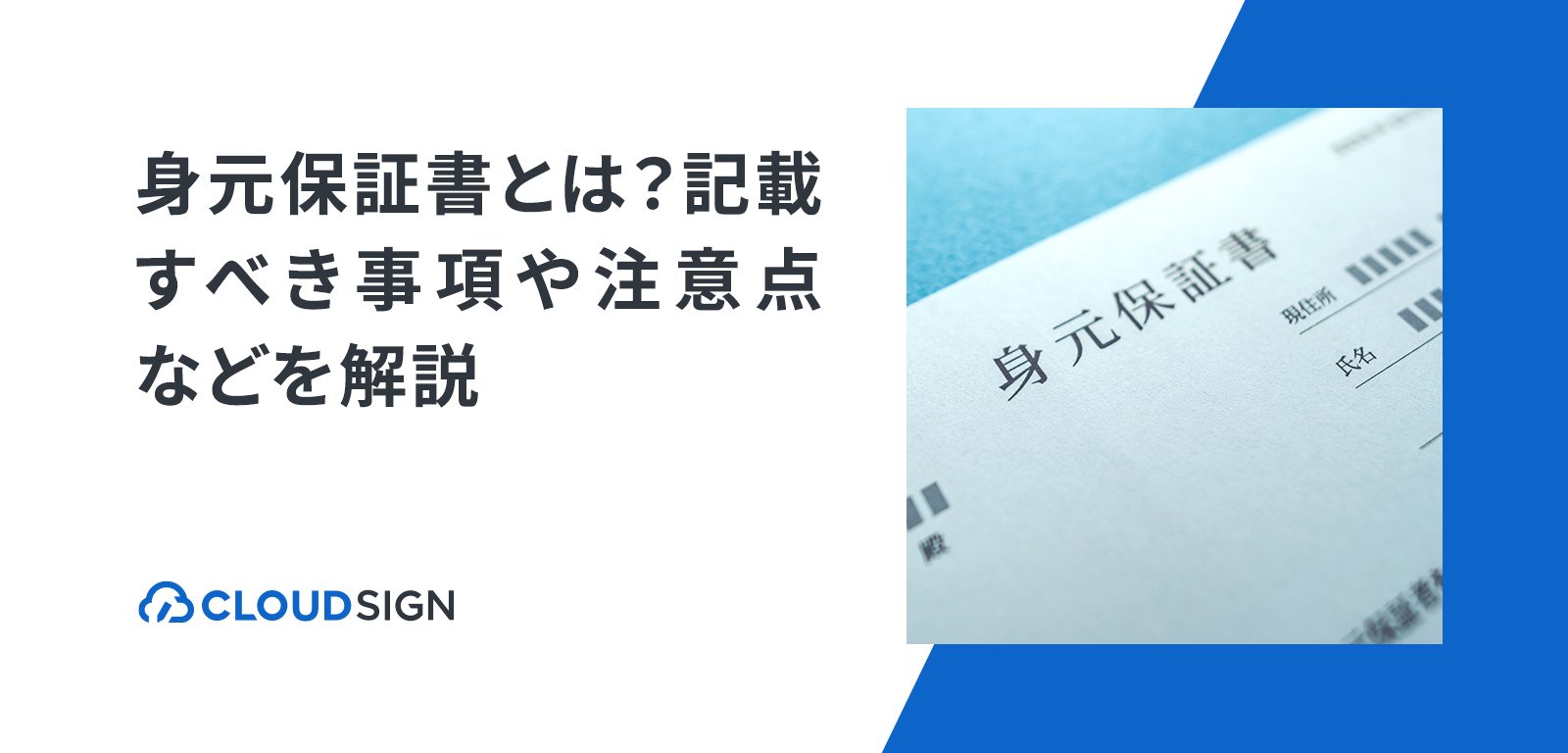
【弁護士監修テンプレートあり】身元保証書とは?記載すべき事項や注意点などを解説
契約書電子契約書 -
契約実務
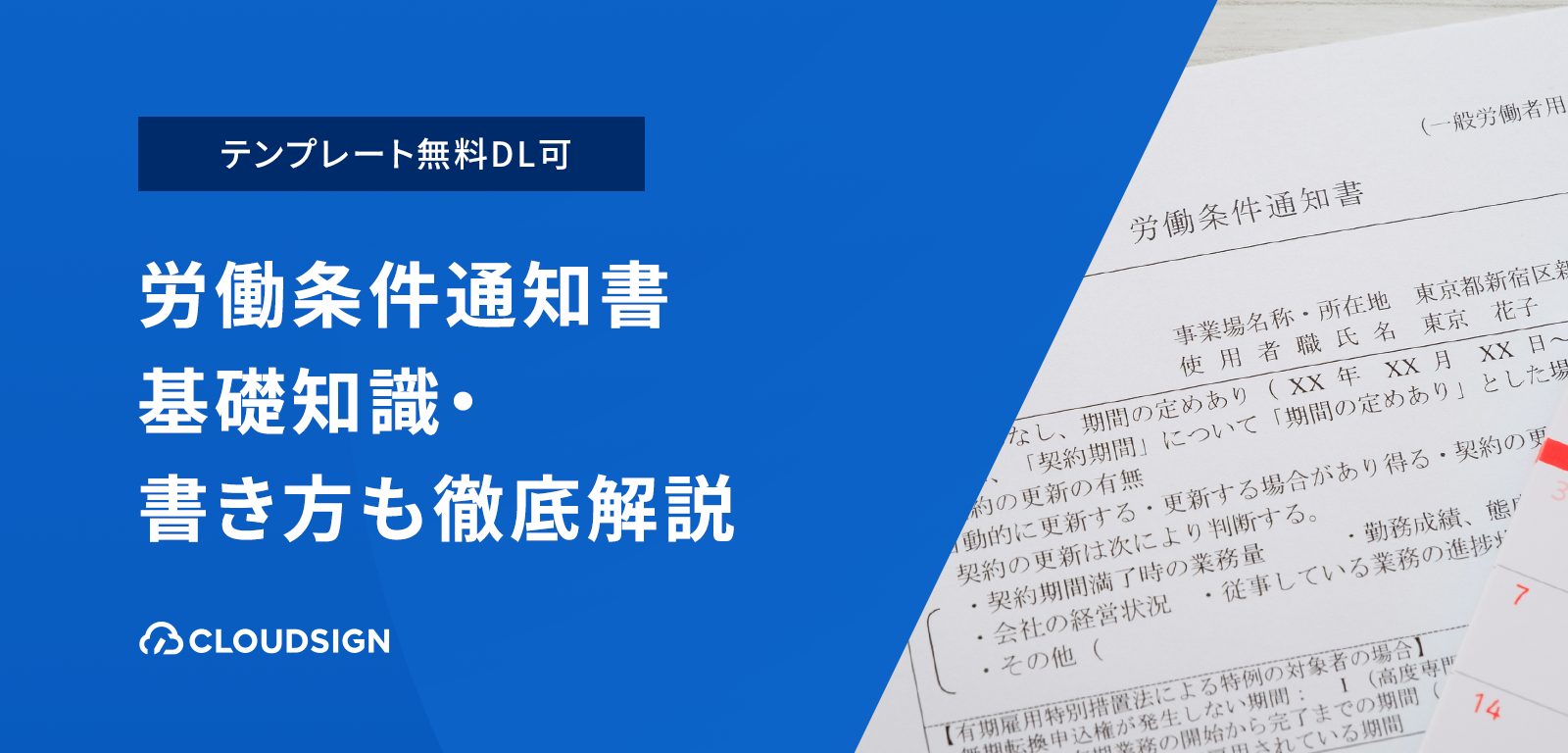
【無料DL可】労働条件通知書のテンプレート 基礎知識と書き方も徹底解説
契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -
電子契約の運用ノウハウ
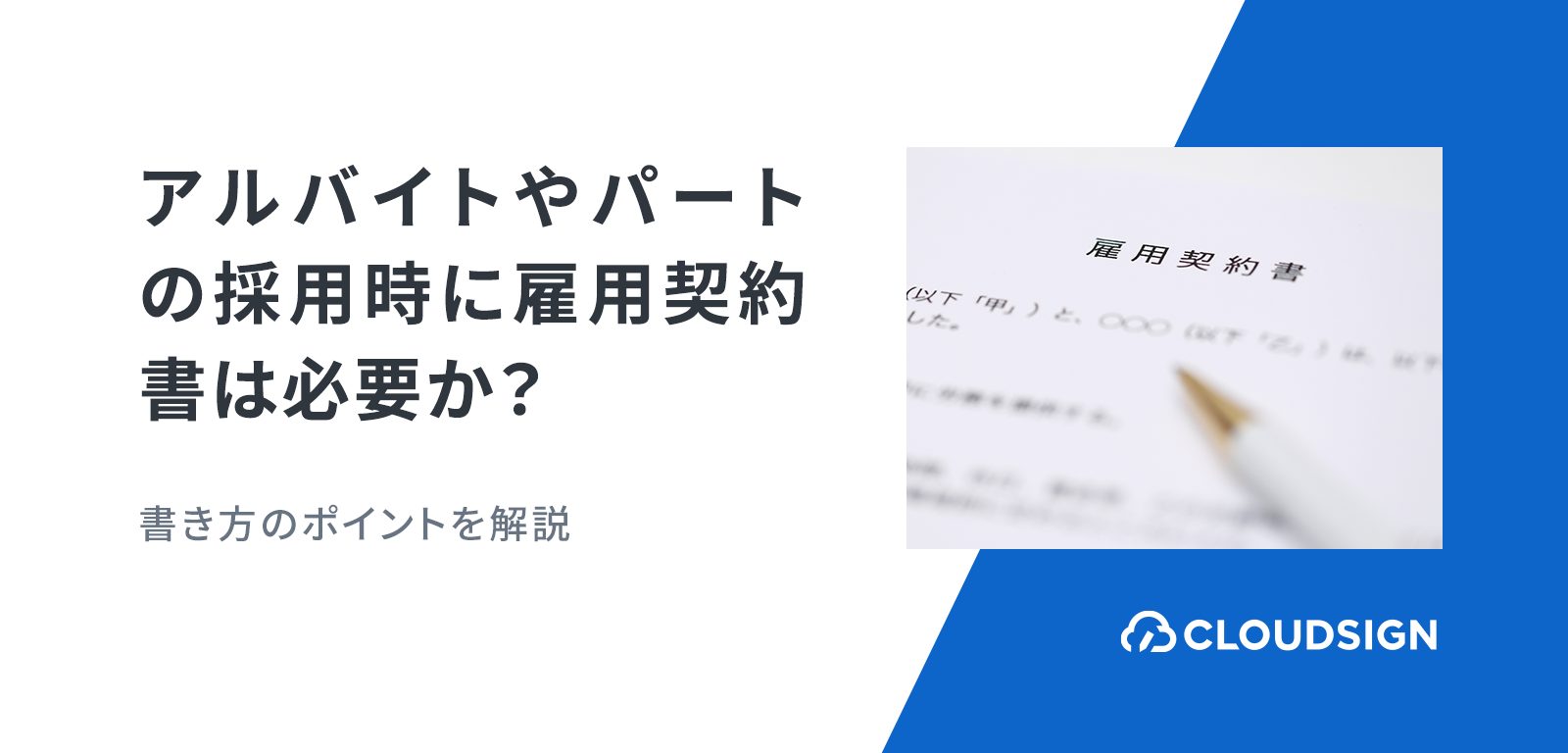
アルバイトやパートの採用時に雇用契約書は必要か?書き方のポイントを解説
雇用契約 -
契約実務
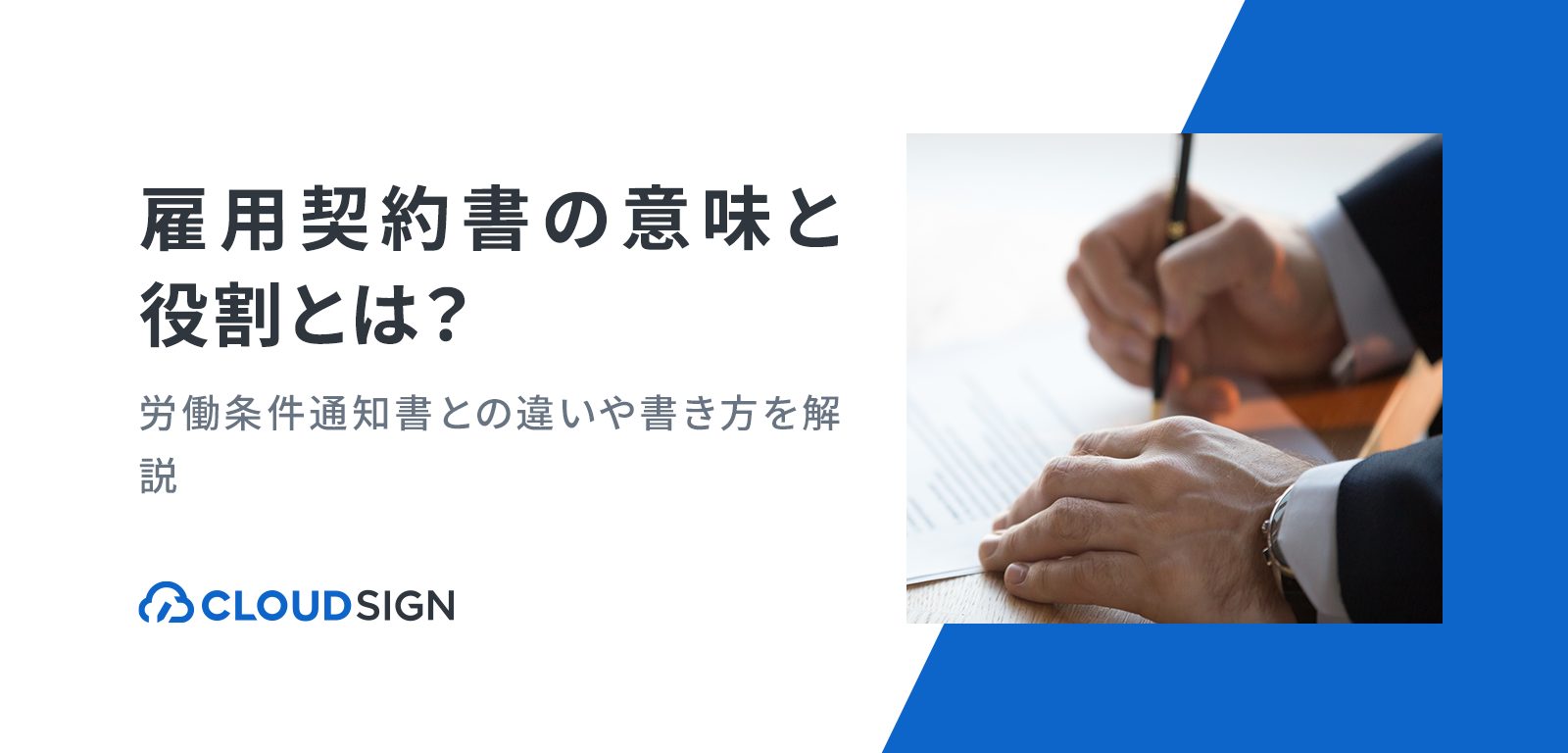
雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや書き方と記載項目を解説
雇用契約 -
電子契約の運用ノウハウ
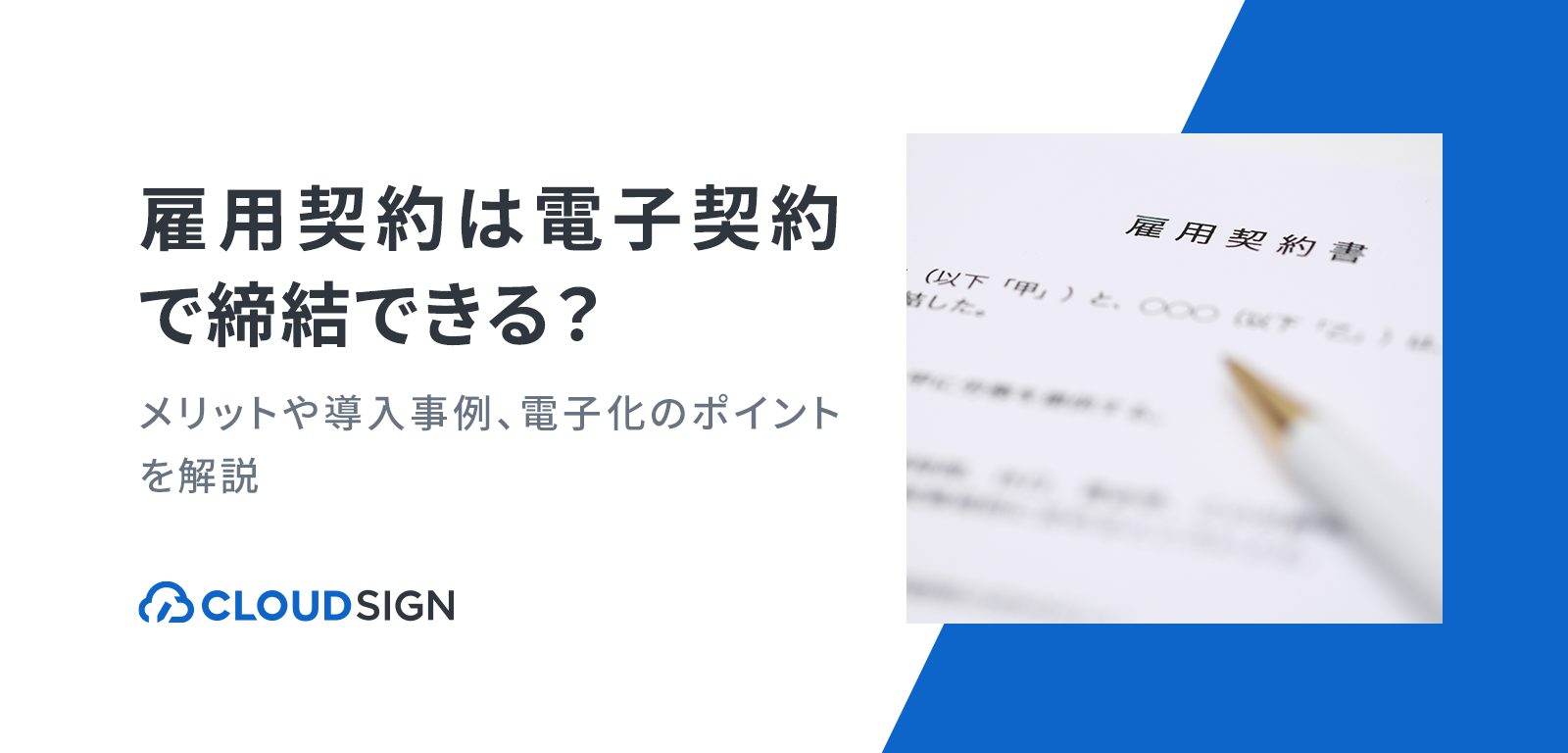
雇用契約は電子契約で締結できる?メリットや事例を解説【Word版ひな形ダウンロード付】
電子契約の活用方法雇用契約 -
電子契約の運用ノウハウ

なぜ今「人事労務に電子契約」か?雇用契約を電子化するメリットと実務的Q&Aを解説
雇用契約人事労務