建設業で電子契約を利用できるのか?法律や要件などのポイントを解説
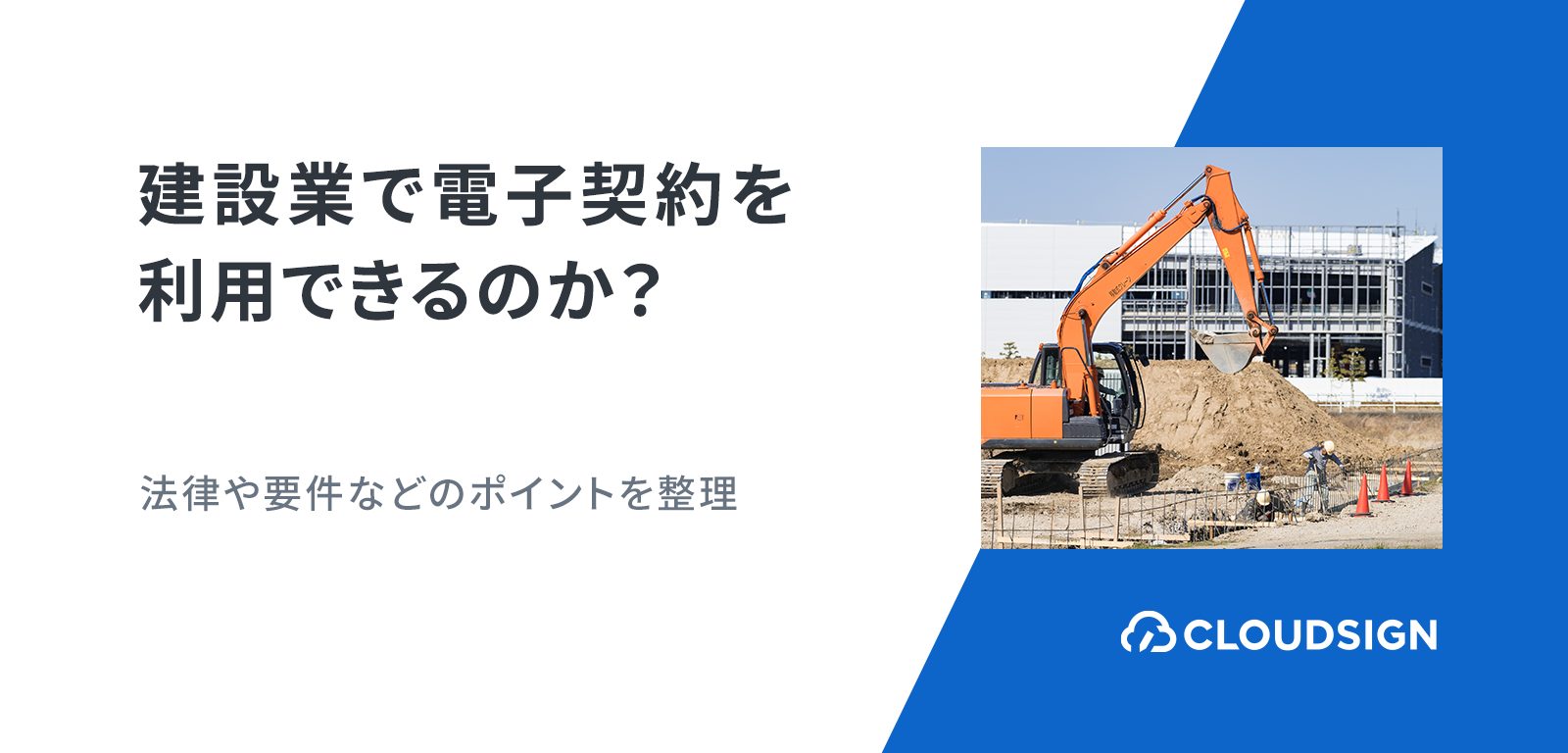
建設業で契約書の電子化を検討している方のなかには「建設業法上、電子契約サービスを利用できるのか」という点を疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
当記事では建設業で電子契約サービスが利用できるのかどうかを実際の事例を紹介しながら解説していますので、建設業で契約書の電子化を検討している方は参考にしてみてください。
資料ダウンロード


クラウドサインでは、電子契約の基礎知識、メリットや注意点、電子署名法や電子帳簿保存法等の法令など、電子契約についてゼロから学べる資料を無料で公開しております。文書のペーパーレス化、業務のデジタル化を推進したい方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。
ダウンロード(無料)目次
建設業で電子契約は利用できる?
結論から言えば、建設業でも電子契約を利用することは可能です。平成13年4月の建設業法改正を受けて、建設工事の請負契約の締結は従来の書面交付だけでなく電子契約でも行えるようになりました。
建設業法では、後日の紛争防止や、発注者と受注者の力関係が一方的になりがちな「片務性」の改善を目的として、当事者間で工事内容や請負金額などを記載した書面を相互に交付することが義務付けられていました。さらに、書面による手続きに代えて、一定の基準を満たす場合には、電磁的措置による契約締結も認められ、現在、建設工事の請負契約は従来の書面交付だけでなく電子契約でも締結できるようになっています。
電子契約とは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で公開して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておく契約方式です。
従来の紙の書面による契約締結作業が不要になるため、電子契約には事務作業で発生していたコストの削減や業務効率化などさまざまなメリットがあります。電子契約を利用することで、建設業においてもそれらのメリットを得られるため、電子契約の導入を検討する価値は十分にあるでしょう。
建設業で電子契約を利用できる書面の例
建設業において電子契約を利用できる書面の例を下記にまとめました。
| 書面の種類 | 概要 |
| (建設)工事請負契約書 | 注文者が工事を発注する際に、受注する際に作成する契約書。 建設業法では、工事請負契約に定めるべき条項や、当事者が負う義務などが定められているため、 同法を踏まえた作成が必要になる |
| 発注書・発注請書 | 協力会社へ工事発注を行う際には、工事請負契約書ではなく注文書・注文請書のみで対応する場合もある。 この場合、基本契約または基本契約約款を取り交わしたうえで、注文書・注文請書で対応できる。 |
| 賃貸借契約書 | 事務所として利用している場所が賃貸物件である場合には、 賃貸借契約書の締結が必要になる。 |
| 売買契約書 | 建設資材の売買の際に締結される契約書。 売買契約書の印紙税は種類によって有無・金額が変わるが、 電子契約の場合、課税文書でも印紙税が不要になる。 |
建設業で頻繁に作成する工事請負契約書(建設工事請負契約書)や発注書・発注請書などを電子化することで、郵送や社内回覧、返送などにかかる時間を削減し、契約締結までのプロセスを大幅に効率化できます。
また、電子化により各種書面の検索や管理が容易になり、事務作業の負担軽減にも繋がります。この他にも建設業で電子契約を利用するメリットはさまざまありますので、「建設業で電子契約を利用するメリット」の項目で確認してみてください。
なお、工事請負契約書は、建設業法19条3項、施行規則13条の2により、電子化にあたって相手方の同意・承諾が必要となる点に注意が必要です。相手方からの同意・承諾を得る方法としては、電子メール、Webページ上の回答フォーム、USBメモリ等の受領のいずれかで対応可能で、電子契約でも行なうことができます。
無料ダウンロード
建設業法において電子契約が認められるようになった背景
「建設業法」は建設業に適用するルールとして1949年に施行された法律です。
建設業法において、建設業は元請、下請その他いかなる名義であるかは問わず「建設工事の完成を請け負う営業」のことを指しており、建設業法には建設工事の請負契約の適正化など、建設業の健全な発達を促進するための規定が定められています。

建設業法において電子契約が認められるようになった経緯を確認しておきましょう。
2001年の建設業法の改正
IT革命が叫ばれていた2000年代初頭、従来は書面の交付が義務付けられていた文書を電子メールや電子ファイルなどの電磁的手段で交付できるようにするために「IT 書面一括法」が施行されました。それに伴い2001年4月に建設業法も改正施行され、建設業の請負契約では以下の条件を満たすことで電子契約が利用できるようになりました。
・相手方の事前の承諾を得ること
・技術的基準に適合すること
相手方から事前に得るべき承認の内容については、コンピュータ・ネットワークと電子記録媒体のどちらを利用するのかや利用する媒体の種類などが該当します。
以上のように、法律の改正により一定の条件をクリアしていれば建設業における電子契約の利用は可能になったものの、どの電子契約システムが技術的水準を満たしているかの判断は難しく、建設業における電子契約の利用が進まない状況がありました。
2018年のグレーゾーン解消制度に基づく回答
どのような電子契約サービスが建設業法の定める技術的水準を満たしているかという問題を解決したのが、政府が民間事業者をサポートするために設けている「グレーゾーン解消制度」です。
「グレーゾーン解消制度」とは、産業競争力強化法に基づき、事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても安心して新事業活動が続けられるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。この制度を活用し、電子契約サービスを提供するさまざまな事業者が自社の電子契約システムの適法性を確認しています。
クラウド型の電子契約サービス「クラウドサイン」を提供している当社においても、2018年1月に建設業法グレーゾーン解消制度に基づく回答を経済産業省から受理し、クラウド型電子契約としてはじめて適法と認められました。詳しい回答内容を確認したい方は経済産業省のニュースリリース「電子契約サービスに係る建設業法の取扱いが明確になりました(経済産業省)」をご覧ください。
建設業で電子契約を利用する際に押さえるべき要件
建設業で電子契約を利用する際は「見読性」「原本性」「本人性」の3つの要件を押さえる必要があります。
| 建設業で電子契約を 利用する際の要件 |
概要 |
| 見読性 | 当該記録をディスプレイ、書面などに速やかかつ整然と表示できるようにシステムを整備しておくことが必要である。 また、電磁的記録の特長を活かし、関連する記録を迅速に取り出せるよう、適切な検索機能を備えておくことが望ましい |
| 原本性 | 契約内容の改ざんを防止可能な措置をとる。また、契約事項などの電磁的記録を適切に保存しておく必要がある |
| 本人性 | 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。 なお「契約当事者による本人確認措置」がなされれば事業者署名型でも問題なく利用可能 |
3つの要件のうち「見読性」「原本性」については2001年4月に施行された建設業法改正で定められていましたが、「本人性」は2020年10月1日に見直された建設業法施行規則で追加された比較的新しい要件となっています。
また、2022年に入ってから新たに申請された建設業グレーゾーン解消申請に対する回答によれば、電子署名法上の電子署名を利用しない、いわゆる「電子印鑑」や「電子サイン」と呼ばれる簡易な電子契約サービスであっても、建設業法上適法な電子契約が締結できることが確認されました。
なお、建設業における電子契約の適法性についてより詳しく知りたい方は「建設業法グレーゾーン解消制度による電子契約の適法性確認—建設工事請負契約の電子化がさらなる規制緩和」も参考にしてみてください。
建設業で電子契約を利用するメリット
建設業で電子契約を利用する主なメリットとして以下3点が挙げられます。
・収入印紙代や郵送費が削減できる
・業務効率化につながる
・コンプライアンスを強化できる
実際に電子契約サービスを導入した企業の事例とあわせて紹介していますので、導入を検討されている方は参考にしてみてください。
収入印紙代や郵送費が削減できる
電子契約には収入印紙代や郵送費などのコストを削減するメリットがあります。
従来の紙の契約では、収入印紙を購入する必要があり、それに加えて契約書類の印刷や郵送に伴う費用も必要でした。しかし、電子契約を導入することで、これらのコストを大幅に削減できます。
実際に、当社の電子契約サービス「クラウドサイン」を導入したタマホーム株式会社の導入事例では、工事請負契約の締結時に発生していた毎年8000~9000万の収入印紙代が電子契約の導入によって削減できるという試算に言及いただいています。電子契約の導入によるコスト削減を期待している方はぜひご一読ください。
>お客様の手間や印紙代の負担を省き、契約書類の管理を簡単、確実に。(タマホーム株式会社)
なお、人件費、郵送費、保管費用など、紙の契約書類1件あたりにかかるコストは、1,200円程度という算出結果が出ています(弊社試算による)。

さらに、契約の種類によっては収入印紙代も発生するため、契約件数が増えれば増えるほど、そのコストは無視できない金額になります。電子契約サービス「クラウドサイン」を導入することで、これらのコストを削減できるため、サービスについて詳しく知りたい方は下記フォームからサービス説明資料をダウンロードしてみてください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)業務効率化につながる
電子契約には、紙での契約と比べて業務プロセスが効率化されるメリットがあります。紙での契約には、印刷、製本、袋とじ、押印、送付といった一連の手順が発生しますが、電子契約ではこれらの手順が不要となります。また、契約書のやりとりも電子ファイルで完結するため、紙の契約に比べて時間的なコストも削減できます。

紙の契約書で締結した場合と電子契約サービス「クラウドサイン」で締結した場合のリードタイムの比較イメージ
具体的には、紙での契約締結が完了するまでにかかっていた数日〜1週間という期間が、電子契約では数分程度で済むことが挙げられます。契約締結までの時間が短縮されることで、取引先とのコミュニケーションもスムーズになり、業務プロセス全体のスピードアップにつながります。
また、建設業では工事請負契約書に図面を添付して取引先へ送信するケースがありますが、電子契約では契約書に図面のPDFを添付して送信することが可能です。利用する電子契約サービスによって添付できるデータの容量が異なるため、事前に確認しておくのがよいでしょう。弊社の電子契約サービス「クラウドサイン」の場合は1ファイルあたり50MBまで(1書類合計200MBまで)送信可能です。
コンプライアンスを強化できる
電子契約の場合、契約内容に応じてアカウントの閲覧権限を設定できるため、契約に関係する社内メンバーのみが契約内容を確認可能です。契約書を書き換えたり、流出させたりといった不正行為も防げるため、コンプライアンスの強化も期待できます。
また、電子契約では契約書の締結状況をクラウド上で一元管理できるため、「誰が・何を・どこまで」進めていたかを把握するのが簡単です。業務の透明性の向上も期待できるうえ、契約や更新の抜け漏れ防止にもつながるでしょう。
建設業における電子契約サービス導入事例
当社が提供しているクラウド型の電子契約サービス「クラウドサイン」は、建設業(または建築業)のお客様にも導入いただいています。建設業においては、工事請負契約はもちろん、売買契約、賃貸借契約、保証契約、同意書、発注書などのさまざまなシーンで電子契約サービスが利用可能です。クラウドサインを実際に導入いただいた企業の事例を以下で紹介しますので、検討の際の参考にしてみてください。
契約書の電子化により業務効率化を実現した事例

株式会社技研製作所は、人件費や郵便代、印紙代などのコスト削減と業務効率化のためにクラウドサインを導入し、機械のユーザーとのメンテナンス契約において契約書の電子化に取り組みました。その結果、契約書を郵送する必要がなくなったうえ、部門をまたいだ確認もできるようになり、保管作業も簡単になるといった業務効率化を実現しています。
電子契約による単純作業の削減で働き方改革を実現した事例

リノべる株式会社の場合には、当初目的としていた事務作業の工数削減だけでなく、紙の書類を持ち歩くことによる紛失リスクがなくなったという点も電子契約導入のメリットとして挙げられており、物理的な紙の書面管理が不要になることでさまざまな恩恵を受けられることがわかっています。
リフォーム工事請負契約書の電子化で営業担当者の移動コストを削減した事例

BXゆとりフォーム株式会社の場合には、紙書類が多く保管場所のコストがかさんでおり、首都圏のみとはいえ営業担当者1人が広い地域をカバーするため、現地で契約締結するのにも客先までの長い移動時間がかかるという課題がありました。そこで、リフォーム工事請負契約書を電子化したことで、各拠点の営業担当者の移動コストを削減に成功。トップセールスマンが積極的に電子契約を利用し、一部拠点では電子化率50%まで達成しています。
建設業における契約電子化の今後の動向
建設業において、今後も契約の電子化が進むことが予想されます。その理由として、政府も電子契約の普及に向けて取り組みを強化していることがうかがえるためです。ここでは、国土交通省が令和7年3月に公開した資料「建設工事請負契約における「署名又は記名押印」規制について」をもとに、今後建設業における電子契約の普及に向けて政府がどのような取り組みを予定しているかを解説します。
電子契約普及に向けた政府の取り組み
政府は、建設業の生産性向上が非常に重要であると考えており、電子契約の普及促進に向けた取り組みを強化する方針を示しています。

出典:「建設工事請負契約における「署名又は記名押印」規制について」P3(国土交通省)
一方で、契約における署名・押印の義務付けについては、慎重な議論が行われています。規制緩和によって生産性向上が期待される一方、立場の弱い受注者が不利な契約を結ばされたり、契約内容を十分に理解しないまま高額な契約をしてしまったりするリスクが懸念されているためです。
また、政府は、発注者と建設業者がパートナーとして適正な価格転嫁を実現できる取引環境の整備を進めており、署名・押印規制の見直しについても、こうした取引適正化の動きを阻害しないよう慎重に検討されています。
技術的基準ガイドラインの改定
現在、電子契約の技術的基準の指針となっているガイドラインは2001年(平成13年)に策定されたもので、その後の技術進展に対応しきれていない点が指摘されています。例えば、ブロックチェーン技術のような最新技術や、現在広く利用されている「立会人型電子署名」に関する記述が反映されていません。
この状況を受け、国土交通省は令和7年(2025年)内にガイドラインを早急に改正することを検討しており、最新の技術や社会情勢を踏まえた内容に見直される予定です。これにより、事業者にとって制度の透明性が高まり、契約のデジタル化がさらに進むことが期待されます。
電子契約システムの導入により業務効率化の推進を
建設業では、政府が労働環境や労働条件の改革を進めるために施行された「働き方改革関連法」の適用が2024年4月から開始され、36協定の特別条項における残業の上限規制に対応する必要があります。そのため、建設業においても今後業務の効率化を推進する必要に迫られることが考えられます。
業務効率化の手段としては基幹システムや会計システムの入れ替えなどさまざまな方法が考えられますが、導入までのハードルが高く、利用開始までの時間もかかるという懸念点があります。そこで、業務効率化を検討している方におすすめなのが、クラウド型の電子契約サービスの導入です。
電子契約サービスは一部署または一契約類型から試験的に導入可能なため、他の種類の業務効率化サービスよりも比較的簡単にご利用いただけます。
当社の提供するクラウド型の電子契約サービス「クラウドサイン」は導入社数250万社以上、累計送信件数3000万件超の実績を持ち、導入時の課題解決や運用定着化のサポートも充実しています。建設業での電子契約システムの導入実績も多数あるため、業務効率化のための電子契約導入を検討中の方はお気軽にご相談ください。
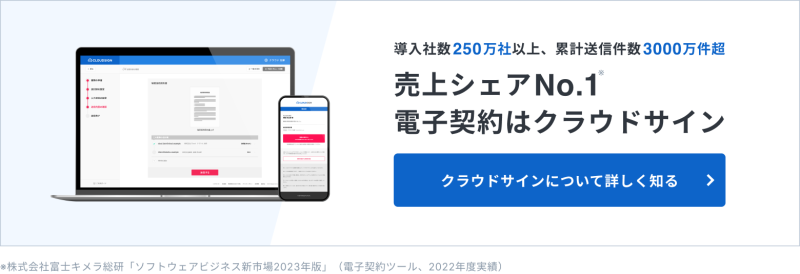
なお、クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
こちらも合わせて読む
-
契約実務

工事請負契約書とは?目的や作成のポイント、締結する際の注意点を詳しく解説
契約書契約書ひな形・テンプレート建設業法工事請負契約書請負契約 -
契約実務

工事請負契約書に収入印紙は必要?例外的に不要なケースや印紙額を解説
契約書建設業法収入印紙工事請負契約書 -
電子契約の運用ノウハウ法律・法改正・制度の解説

不動産業における電子契約導入のメリット、解禁の経緯とは?電子化の成功事例を交えて解説
不動産宅地建物取引業法 -
業務効率化の成功事例まとめ

建設・建築業界で業務効率化に成功した事例4選
契約書管理インタビュークラウドサインの機能コスト削減電子契約の活用方法建設業法電子契約の導入電子契約のメリット業務効率化工事請負契約書API連携 -
電子契約の運用ノウハウ

建設業界の2024年問題とは?背景とDXによる業務効率化の方法をわかりやすく解説
電子契約の活用方法建設業法
