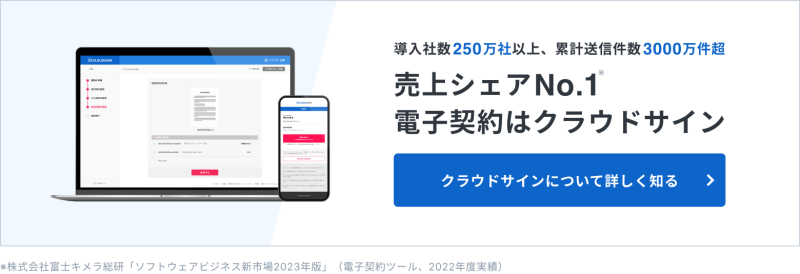【2025年施行】建設業法改正とは?主な変更点や建設業者の対応ポイントを解説

2024年6月に成立・公布された建設業法改正は、2025年中の全面施行が予定されています。
本記事では、2025年中に施行される建設業法改正の変更点や、建設業者の対応ポイントなどを解説します。建設業に従事している方や、取引先に建設業関連の業者がいるという方は、建設業法改正による変更点や対応のポイントを正しく理解しておきましょう。
目次
【2025年施行】建設業法改正とは
2024年6月7日に建設業法の改正法が国会で成立し、同月14日に公布されました。改正法はすでに一部の規定が施行されており、残る規定も2025年中には全面施行される予定となっています。
建設業法改正の目的
2025年中の施行が予定されている建設業法改正の背景には、建設業の担い手を確保する必要性が高まっている事情があります。
建設業者は、住居やオフィス・商業施設・インフラ施設などの重要施設の建設を担っており、その役割は社会に欠かせません。しかし、建設業は低賃金かつ長時間労働となる傾向にあるため、近年では担い手を確保することが難しくなりつつあります。
そこで今回の建設業法改正では、建設業に従事する労働者の処遇改善と働き方改革、さらに建設業の生産性向上を促すための規制変更が盛り込まれました。建設業の職場の魅力が高まり、十分な担い手を確保できるようになることが期待されています。
建設業法改正の主な内容
今回の建設業法改正による主な変更点は、以下のとおりです。
(a)「建設工事の労務費の基準」の作成・勧告(2024年9月1日~)
(b)労働者の処遇確保に関する建設業者の責務・取組状況の調査(2024年12月13日~)
(c)著しく低い材料費等による見積りや見積り変更依頼の禁止(2025年中施行予定)
(d)請負人による不当に低い請負代金の設定の禁止(2025年中施行予定)
(a)契約前|リスク情報の提供義務・請負代金の変更方法を明記(2024年12月13日~)
(b)契約後|請負代金等の変更に関する協議(2024年12月13日~)③働き方改革と生産性向上
(a)働き方改革|請負人による工期ダンピングの禁止(2025年中施行予定)
(b)生産性向上|現場技術者の専任義務の合理化・ICTを活用した効率化(2024年12月13日~)
次の項目から、各変更の具体的な内容を解説します。
改正ポイント①|労働者の処遇改善
低賃金かつ長時間労働になりがちな建設業の労働者の処遇を改善するため、以下の変更が行われました。
「建設工事の労務費の基準」の作成・勧告(2024年9月1日~)
中央建設業審議会は、建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるものとされました(建設業法34条)。
上記改正の施行に伴い、中央建設業審議会にワーキンググループが設置され、基準の作成に関する検討が重ねられてきました。その結果、2025年中には「標準労務費」と呼ばれる基準が公表される見込みとなっています。
建設業者においては、公表された標準労務費を参考にして、労働者の賃金などを適正に定めることが求められます。
労働者の処遇確保に関する建設業者の責務・取組状況の調査(2024年12月13日~)
建設業者は、雇用する労働者の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払い、その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めるものとされました(建設業法25条の27第2項)。
建設業者による上記措置の実施状況については、国土交通大臣が必要な調査を行い、その結果を公表するとともに、中央建設業審議会に報告します(同法40条の4)。
中央建設業審議会は、国土交通大臣の報告内容を、標準労務費に関する基準を作成する際の参考とします。
著しく低い材料費等による見積りや見積り変更依頼の禁止(2025年中施行予定)
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに当たり、工事の種別ごとの以下の経費(=材料費等)の内訳などを記載した見積書を作成するよう努めなければなりません(改正建設業法20条1項)。
・労務費
・建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの
・その他当該建設工事の施工のために必要な経費
見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであってはならないとされました(同条2項)。不当に低い請負代金が設定されると、低賃金化や労働環境の悪化に繋がりかねないためです。
また、建設工事の注文者においても、建設業者から提示された見積りについて、材料費等が当該建設工事を施工するために通常必要と認められる額を著しく下回るような変更を求めてはならないものとされました(同条6項)。
建設工事の注文者・請負人のどちらの立場でも、契約締結前の見積りの金額が合理的なものとなっているかどうかをきちんと確認することが求められます。
請負人による不当に低い請負代金の設定の禁止(2025年中施行予定)
従来から、注文者が自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事の施工のために通常必要な原価に満たない請負代金を設定すること(=原価割れ契約)は禁止されていました(建設業法19条の3)。
今回の建設業法改正では、請負人である建設業者に対しても、原価割れ契約の締結が原則として禁止されました(改正建設業法19条の3第2項)。建設業者は、受注を確保したいなどの意図があるとしても、請負代金が原価割れしてはいけないことに留意する必要があります。
ただし、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができるなどの正当な理由がある場合は、原価割れ契約の締結が例外的に認められます。具体的な例外事由は、今後国土交通省令で定められる予定です。
改正ポイント②|資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
資材価格の高騰によって労務費が圧迫される事態を防ぐため、契約締結の前後について以下のルール変更が行われました。
契約前|リスク情報の提供義務・請負代金の変更方法を明記(2024年12月13日~)
建設工事の請負人(受注者)は、以下の事象が発生するおそれがあると認めるときは、その旨および当該事象の状況の把握のため必要な情報を、契約締結前に注文者へ通知しなければならないとされました(建設業法20条の2第1項、第2項)。
(例)自然災害によって資材工場が被災し、資材の需給バランスが崩れる可能性がある。・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足または価格の高騰
(例)特定の種類の工場の建設需要が急激に増加し、必要不可欠な専門工事を担当する技能者の獲得競争によって労務費が上昇したため、請負代金の増額を要する可能性がある。
このとき、請負人が注文者に通知すべき情報は「おそれ情報」と呼ばれています。
また、資材価格の高騰などをスムーズに請負代金へ反映できるように、請負代金を変更する際の金額の算定方法を建設工事の請負契約に定めることが義務付けられました(同法19条1項8号)。
建設工事を受注する建設業者は、契約締結前の段階で資材価格の高騰などのリスクを適切に見積もり、必要に応じて注文者へ伝えなければなりません。
また、建設工事請負契約のひな形を用いている場合は、請負代金を変更する際の金額の算定方法が明記されているかどうかを確認しましょう。
契約後|請負代金等の変更に関する協議(2024年12月13日~)
請負人は、おそれ情報を注文者に通知したうえで契約を締結した後、実際にその事象が発生したときは、注文者に対して工期・工事内容・請負代金額の変更について協議を申し出ることができます(同条3項)。
注文者は、その申出が根拠を欠くなど正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応じるよう努めなければなりません(同条4項)。
改正ポイント③|働き方改革と生産性向上
建設業に従事する労働者の働き方改革を促すとともに、建設業の生産性を向上させるため、以下のルール変更が行われました。
働き方改革|請負人による工期ダンピングの禁止(2025年中施行予定)
建設工事について著しく短い工期が設定されると、工期に間に合わせるために長時間労働をするなど、建設業の労働環境の悪化につながります。
従来から、注文者側が通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期を設定すること(=工期ダンピング)は禁止されていました(建設業法19条の5)。
その一方で、請負人側が自発的に著しく短い工期を設定することは禁止されていませんでした。実際には、発注を打ち切られることを恐れているなどの理由から、請負人側が著しく短い工期を設定する例がしばしば見られ、問題視されていました。
そこで今回の建設業法改正では、請負人である建設業者の側からの提案であっても、通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期を設定することが禁止されました(改正建設業法19条の5第2項)。
工期ダンピングが注文者・請負人の双方について禁止されることにより、合理的な工期の設定を促す効果が期待されます。
建設工事を受注する建設業者は、たとえ注文者の評価を上げたい、契約を切られたくないなどの意図があるとしても、短すぎる工期の設定は避ける必要があります。
生産性向上|現場技術者の専任義務の合理化・ICTを活用した効率化(2024年12月13日~)
建設業者が請け負った建設工事を施工するときは「主任技術者」、特定建設業者が元請負人として5000万円以上(建築一式工事なら8000万円以上)の下請発注を行うときは「監理技術者」を置く必要があります(建設業法26条1項、2項)。
※「特定建設業」とは、建設業のうち、発注者から直接(元請負人として)請け負った建設工事について、下請代金5000万円以上(建築工事業の場合は8000万円以上)の下請契約を締結するものをいいます。「一般建設業」とは、建設業のうち、特定建設業に当たらないものをいいます。
公共工事などのうち、1件の請負代金の額が4500万円以上(建築一式工事なら9000万円以上)のものについては、原則として、工事現場ごとに設置する主任技術者と監理技術者を専任としなければなりません。しかし、専任者の設置にはコストを伴うため、建設業者にとって大きな負担となります。
そこで、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については、主任技術者・監理技術者が2現場まで兼務できるものとされました(同条3項、建設業法施行令28条)。
なお、営業所における専任の技術者(=営業所技術者等)については、主任技術者・監理技術者と同様の条件の下で、営業所に加えて1現場を兼務することが認められました。
工事現場や営業所に専任者を置いている建設業者は、上記の変更を踏まえた配置転換の可能性を検討してみましょう。コスト削減や業務の効率化に繋がる可能性があります。
さらに特定建設業者には、建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関する措置を講じる努力義務、および下請負人が同様の措置を講ずることができるように指導する努力義務が課されました(建設業法25条の28)。
建設工事請負契約書などの書類の電子化で業務効率化を
平成13年4月の建設業法改正を受けて、建設工事の請負契約の締結は従来の書面交付だけでなく電子契約でも行えるようになりました。
電子契約とは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で公開して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておく契約方式です。
従来の紙の書面による契約締結作業が不要になるため、電子契約には事務作業で発生していたコストの削減や業務効率化などさまざまなメリットがあります。電子契約を利用することで、建設業においてもそれらのメリットを得られるため、電子契約の導入を検討する価値は十分にあるでしょう。
建設業における電子契約の活用方法や実際の導入事例を知りたい方は下記記事もご一読ください。
なお、電子契約サービス「クラウドサイン」では工事の受発注時に利用する「建築工事請負契約書」のひな形(テンプレート)をご用意しました。無料でご入手できますので、建築工事請負契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方は下記リンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード
まとめ
2025年中に全面施行が予定されている建設業法改正では、建設業者が留意すべきさまざまなルール変更が盛り込まれました。
建設業者は、請負代金の決め方や使用中の契約書ひな形、人材配置などを総点検し、必要に応じて見直すことをお勧めします。
また、当社が提供しているクラウド型の電子契約サービス「クラウドサイン」は、建設業(または建築業)のお客様にも導入いただいています。建設業においては、工事請負契約はもちろん、売買契約、賃貸借契約、保証契約、同意書、発注書などのさまざまなシーンで電子契約サービスが利用可能です。
クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
契約実務
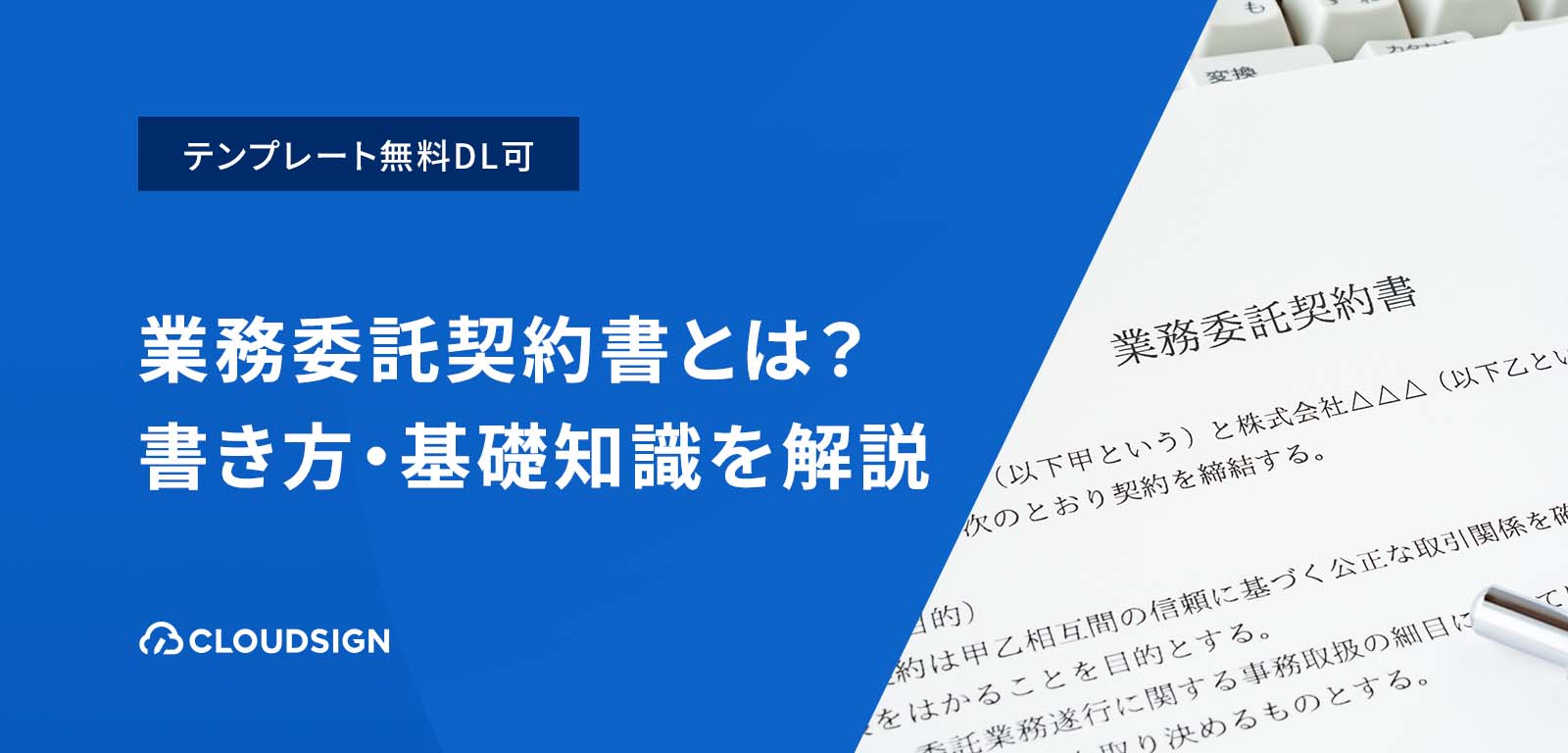
【無料DL可】業務委託契約書とは?テンプレート付きで書き方と基礎知識を徹底解説
コスト削減契約書ひな形・テンプレート業務委託契約書 -
法律・法改正・制度の解説
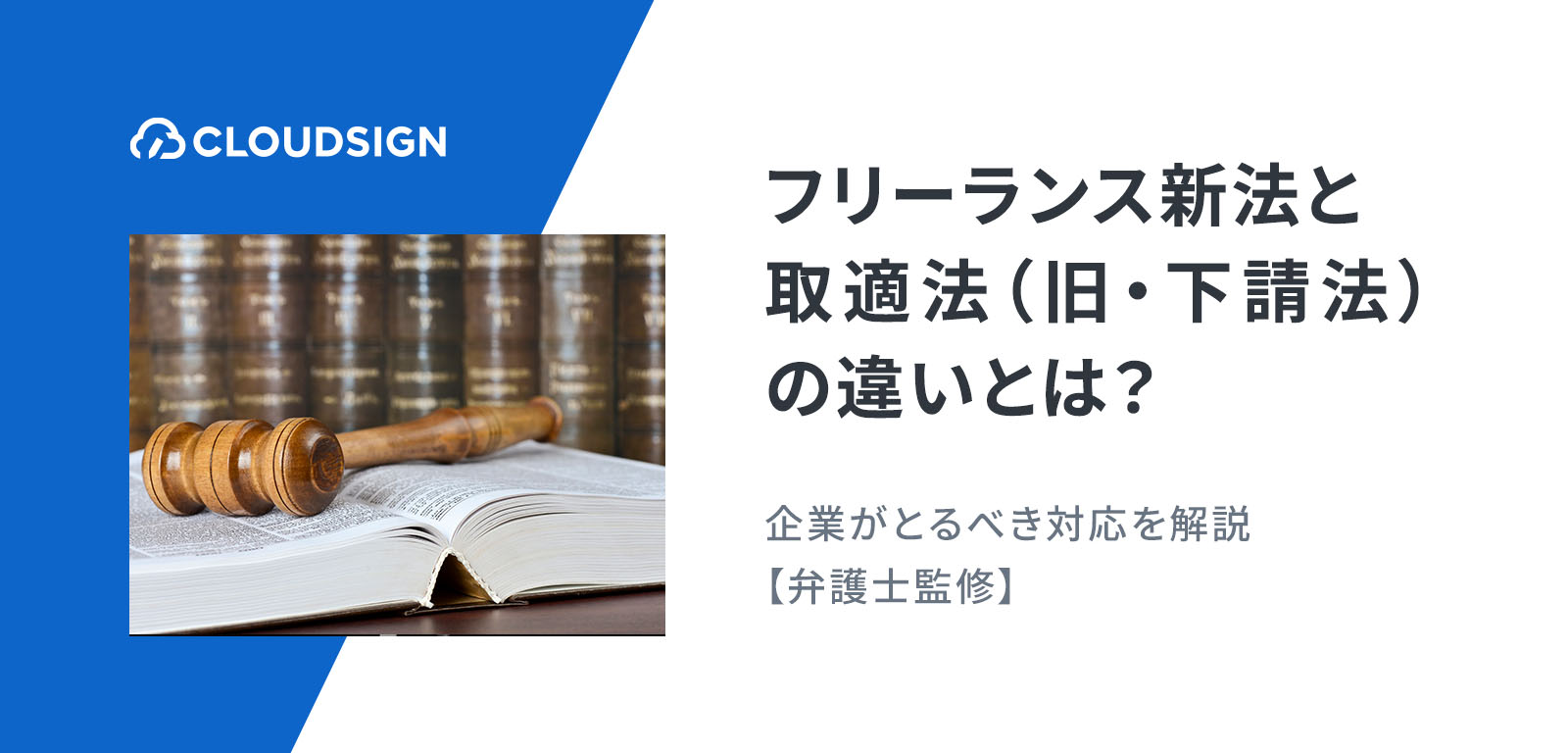
【弁護士監修】フリーランス新法と取適法(旧・下請法)の違いとは?企業がとるべき対応を解説
法改正・政府の取り組み弁護士解説取適法(下請法)フリーランス新法 -
契約実務

工事請負契約書とは?目的や作成のポイント、締結する際の注意点を詳しく解説
契約書契約書ひな形・テンプレート建設業法工事請負契約書請負契約 -
契約実務

請負契約書に収入印紙は必要?課税文書の判断基準や必要金額を解説
印紙税と収入印紙収入印紙請負契約 -
契約実務

工事請負契約書に収入印紙は必要?例外的に不要なケースや印紙額を解説
契約書建設業法収入印紙工事請負契約書 -
契約実務

業務委託とフリーランスの違いとは?業務委託契約を締結するメリットや注意点を解説
業務委託契約書