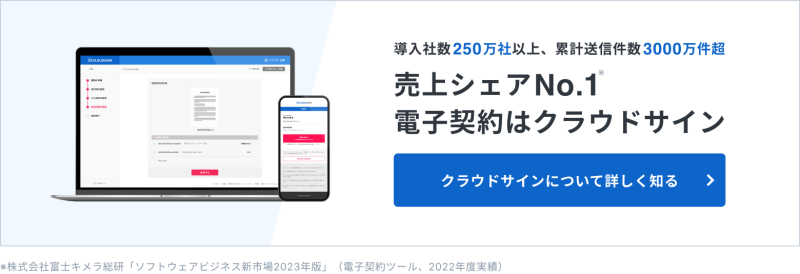建設業法とは?規制の全体像や内容、建設業者の対応ポイントなどを解説

建設業法は、建設業者や建設工事請負契約に適用される法律です。建設業者が業務を行う際には、建設業法のルールを遵守しなければなりません。
本記事では建設業法について、規制の全体像や内容、建設業者の対応ポイントなどを解説します。どのようなルールが定められているのか、全体像や対応のポイントを把握しておきましょう。
建設業法とは
建設業法とは、建設業者が遵守すべき規制や、建設工事請負契約に適用されるルールなどを定めた法律です。特に建設業者は、業務を行うに当たって建設業法の規制に留意する必要があります。
建設業法の目的
建設業法では、建設業者の資質向上および建設工事請負契約の適正化などを図るための規制が定められています。
建設工事の適正な施工を確保して発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することが目的とされています。
建設業法による主な規制の全体像
建設業法によって定められている主な規制としては、以下の3点が挙げられます。
(2)建設工事の請負契約
(3)主任技術者と監理技術者の設置
次の項目から、各規制の具体的な内容を解説します。
建設業法のポイント1|建設業の許可制
建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣、1の都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要です(建設業法3条1項)。
また、建設業の許可は5年ごとに更新が必要とされており、更新しなければ失効します(同条3項)。
建設業とは
「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。元請や下請などの名義が何であるかを問いません(建設業法2条2項)。
建設業の種類|対応する許可が必要
建設業の種類は細分化されており、その種類に対応する許可を得なければ営業することができません。具体的には、以下の29種類に分かれています。
| 建設業の種類 |
| ①土木工事業 ②建築工事業 ③大工工事業 ④左官工事業 ⑤とび・土工工事業 ⑥石工事業 ⑦屋根工事業 ⑧電気工事業 ⑨管工事業 ⑩タイル・れんが・ブロック工事業 ⑪鋼構造物工事業 ⑫鉄筋工事業 ⑬舗装工事業 ⑭しゅんせつ工事業 ⑮板金工事業 ⑯ガラス工事業 ⑰塗装工事業 ⑱防水工事業 ⑲内装仕上工事業 ⑳機械器具設置工事業 ㉑熱絶縁工事業 ㉒電気通信工事業 ㉓造園工事業 ㉔さく井工事業 ㉕建具工事業 ㉖水道施設工事業 ㉗消防施設工事業 ㉘清掃施設工事業 ㉙解体工事業 |
また上記の分類とは別に、建設業は「特定建設業」と「一般建設業」の2つに分かれています。元請負人として一定額以上の下請発注を行う場合は特定建設業、それ以外の場合は一般建設業に分類されます(建設業法3条6項・1項、建設業法施行令2条)。
| 特定建設業と一般建設業 |
| ①特定建設業 建設業のうち、発注者から直接(元請負人として)請け負った建設工事について、下請代金5000万円以上(建築工事業の場合は8000万円以上)の下請契約を締結するもの ②一般建設業 建設業のうち、特定建設業に当たらないもの |
建設業の許可も、特定建設業の許可と一般建設業の許可の2つに大別されます。
特定建設業の許可を受けていれば、特定建設業と一般建設業の両方を営むことができます。一方、一般建設業の許可を受けている場合は、特定建設業を営むことができず、一般建設業のみ認められます(建設業法16条)。
建設業許可の申請方法
建設業の許可を受けようとするときは、許可行政庁に対して許可申請書と添付書類を提出する必要があります。申請先と費用は以下のとおりです。
| 申請先 | 費用 | |
| 国土交通大臣の許可 | 本店の所在地を管轄する地方整備局長等 | ①新規許可 登録免許税15万円 ②許可の更新 許可手数料5万円 ③同一区分内における許可の追加 許可手数料5万円 |
| 都道府県知事の許可 | 都道府県知事 | ①新規許可 許可手数料9万円 ②許可の更新 許可手数料5万円 ③同一区分内における許可の追加 許可手数料5万円 |
建設業許可申請の手続きの詳細は、国土交通省のウェブサイトで案内されています。
建設業法のポイント2|建設工事の請負契約
建設業法では、建設工事の請負契約について以下のルールが定められています。
②現場代理人・監督員の選任に関する通知
③注文者の禁止行為
④建設工事の見積り等
⑤工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等
⑥契約の保証
⑦下請発注に関する規制
⑧工事監理に関する報告
各項目について次項で詳しく確認していきましょう。
建設工事の請負契約の内容
建設工事の請負契約を締結する際には、以下の事項を記載した書面を作成し、当事者双方が署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません(建設業法19条1項)。
(b)請負代金の額
(c)工事着手の時期および工事完成の時期
(d)工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容
(e)請負代金の前払いまたは出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期および方法
(f)当事者が設計変更、工事着手の延期、工事の中止を申し出た場合における以下の定め
・工期の変更
・請負代金の額の変更
・損害の負担
・変更後の請負代金額や損害の負担額の算定方法
(g)天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担、負担額の算定方法に関する定め
(h)価格等の変動や変更に基づく、請負代金の額または工事内容の変更
(i)工事の施工に起因して第三者に支払う賠償金の負担に関する定め
(j)注文者が資材の提供や機械の貸与をするときは、その内容や方法に関する定め
(k)注文者が工事の完成を確認するための検査の時期および方法、引渡しの時期
(l)工事完成後における請負代金の支払の時期および方法
(m)契約不適合責任について保証保険契約の締結その他の措置を定めるときは、その内容
(n)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(o)契約に関する紛争の解決方法
また、請負契約における上記の事項を変更するときも、締結時と同様に書面の作成・交付が必要です(同条2項)。
ただし相手方の承諾を得ていれば、書面に代えて電子データを作成し、電子署名を付したうえで相手方に交付することもできます(同条3項)。
国土交通省のウェブサイトでは、建設業法に基づく記載事項が網羅された「建設工事標準請負契約約款」が公表されています。
現場代理人・監督員の選任に関する通知
請負人が工事現場に現場代理人を置くときは、現場代理人の権限に関する事項と、現場代理人の行為について意見を申し出る方法を注文者に通知しなければなりません(建設業法19条の2第1項)。
また、注文者が工事現場に監督員を置くときも、監督員の権限に関する事項と、監督員の行為について意見を申し出る方法を請負人に通知しなければなりません(同条2項)。
上記の通知は原則として書面で行いますが、相手方の承諾を得ていればメールなどの情報通信によって行うことも認められます(同条3項、4項)。
注文者の禁止行為
下請事業者など立場の弱い請負人を保護するため、建設工事の注文者による以下の行為が禁止されています(建設業法19条の3~19条の5)。
・自己の取引上の地位を不当に利用して、工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定し、請負人に購入させてその利益を害すること
・通常必要な期間と比べて、著しく短い工期を設定すること
これらの禁止行為をした注文者は、国土交通大臣または都道府県知事による勧告や公表処分を受けることがあります(同法19条の6)。
建設工事の見積り等
建設業者は、建設工事の請負契約を締結する際、以下の事項を明らかにした見積りを行うよう努めなければなりません(建設業法20条1項)。
・工事の工程ごとの作業およびその準備に必要な日数
また建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、契約締結前に見積書を交付しなければなりません(同条2項)。見積書は書面による交付が原則ですが、注文者の承諾を得ていればデータで提供することも認められます(同条3項)。
工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等
建設工事の注文者と請負人はそれぞれ、以下のいずれかの事象が発生するおそれがあると認めるときは、その旨および当該事象の状況の把握のため必要な情報を、契約締結前に相手方に対して通知しなければなりません(建設業法20条の2第1項、第2項)。
・地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
・騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象<請負人が注文者に通知すべき事項>
・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延、または資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足または価格の高騰
また、請負人が注文者に上記の事項を通知したうえで契約を締結した後、実際にその事象が発生したときは、請負人は注文者に対して工期の変更、工事内容の変更または請負代金額の変更について協議を申し出ることができます(同条3項)。
協議の申出を受けた注文者は、その申出が根拠を欠くなど正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応ずるよう努めなければなりません(同条4項)。
契約の保証
建設工事の請負代金の全部または一部を前払いする場合、注文者は建設業者に対して、支払いの前に保証人を立てるよう請求できます(建設業法21条1項)。建設業者が保証人を立てないときは、注文者は請負代金の前払いを拒否することができます(同条3項)。
ただし、保証事業会社による工事と1件の請負代金額が500万円未満の工事は、上記の対象外とされています。
下請発注に関する規制
建設業者が請け負った建設工事を、一括して他人に請け負わせること(いわゆる「一括下請負」)はできません(建設業法22条1項)。また、他の建設業者が請け負った建設工事を、自社が一括して請け負うこともできません(同条2項)。
ただし、多数の者が利用する施設または新築共同住宅の建設工事を除き、元請負人が発注者の事前承諾を得たときは、一括下請負も認められます(同条3項、4項)。
建設工事の施工について著しく不適当と認められる下請負人があるときは、注文者は請負人に対して下請負人の変更を請求できます。ただし、注文者の事前承諾を得て請負人が選任した下請負人については、この限りではありません(同法23条)。
工事監理に関する報告
建設工事の施工につき、工事を設計図書のとおりに実施すべき旨の建築士の指示に従わない理由があるときは、請負人は注文者に対して直ちにその理由を報告しなければなりません(建設業法23条の2)。
建設業法のポイント3|主任技術者と監理技術者の設置
建設業者が請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置く必要があります(建設業法26条1項)。
また、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請代金の額が5000万円以上(建築一式工事なら8000万円以上)となるときは、監理技術者を置く必要があります(同条2項)。
なお、公共工事などのうち1件の請負代金の額が4500万円以上(建築一式工事なら9000万円以上)のものについては、主任技術者と監理技術者は原則として、工事現場ごとに専任の者としなければなりません(同条3項)。
主任技術者とは
「主任技術者」は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を担当します。
大学などの教育課程を修めているか、建設工事について10年以上の実務経験を有するか、またはこれらと同等以上の知識や技術・技能を有すると国土交通大臣に認定された者でなければなりません。
監理技術者とは
「監理技術者」も主任技術者と同じく、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を担当しますが、比較的大規模な下請発注の監理業務が発生するのが特徴的です。
所定の検定試験の合格もしくは免許の取得、該当する建設工事についての2年以上の指導監督経験、またはこれらと同等以上の知識や技術・技能の国土交通大臣による認定が要件とされています。
建設工事請負契約書などの書類の電子化で業務効率化を
平成13年4月の建設業法改正を受けて、建設工事の請負契約の締結は従来の書面交付だけでなく電子契約でも行えるようになりました。
電子契約とは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で公開して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておく契約方式です。
従来の紙の書面による契約締結作業が不要になるため、電子契約には事務作業で発生していたコストの削減や業務効率化などさまざまなメリットがあります。電子契約を利用することで、建設業においてもそれらのメリットを得られるため、電子契約の導入を検討する価値は十分にあるでしょう。
建設業における電子契約の活用方法や実際の導入事例を知りたい方は下記記事もご一読ください。
なお、電子契約サービス「クラウドサイン」では工事の受発注時に利用する「建築工事請負契約書」のひな形(テンプレート)をご用意しました。無料でご入手できますので、建築工事請負契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方は下記リンクからダウンロードしてご活用ください。
まとめ
近年ではコンプライアンスの重要性が高まっているうえに、建設業法の内容も法改正によってアップデートされているので、最新の情報を常に把握しておきましょう。
また、当社が提供しているクラウド型の電子契約サービス「クラウドサイン」は、建設業(または建築業)のお客様にも導入いただいています。建設業においては、工事請負契約はもちろん、売買契約、賃貸借契約、保証契約、同意書、発注書などのさまざまなシーンで電子契約サービスが利用可能です。
クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
契約実務
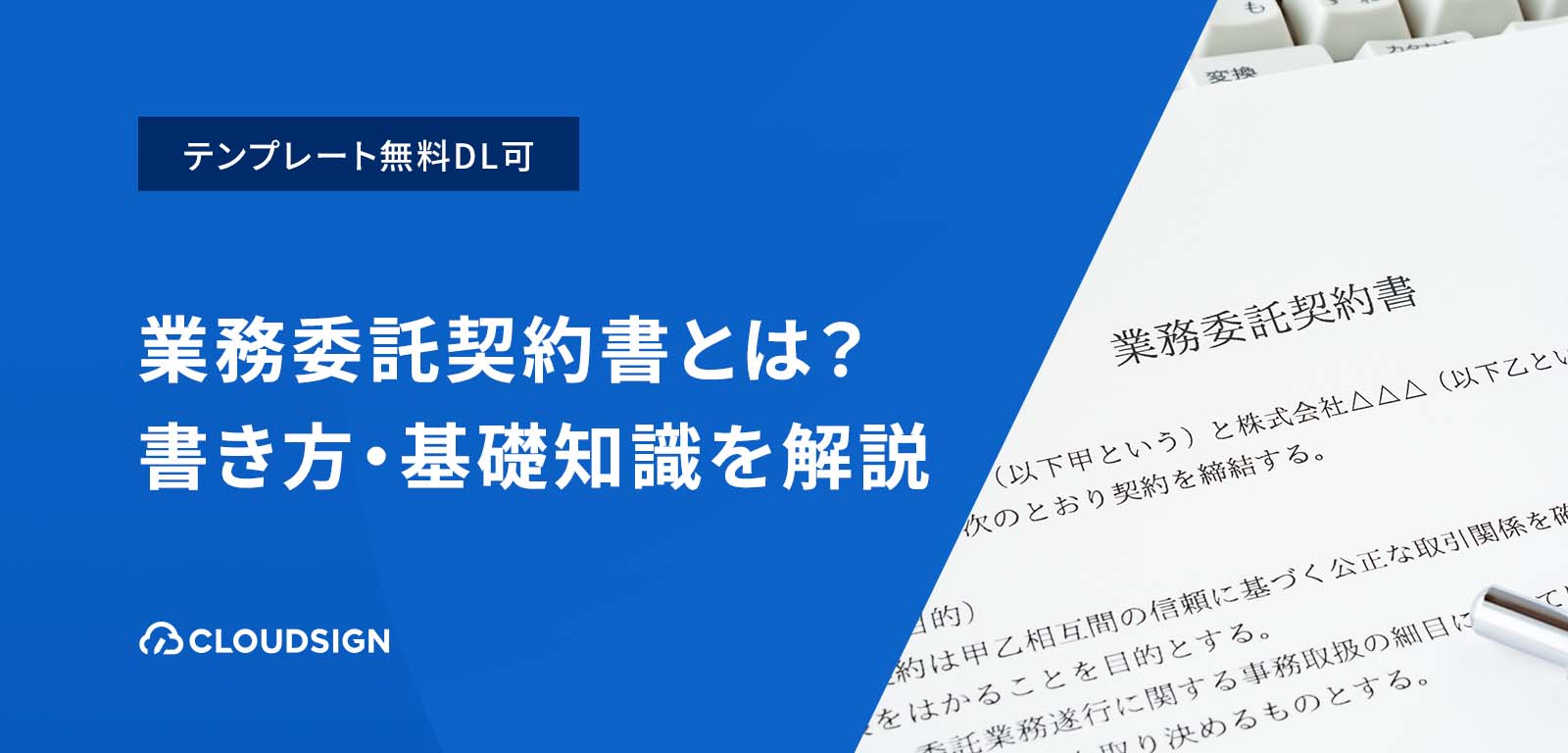
【無料DL可】業務委託契約書とは?テンプレート付きで書き方と基礎知識を徹底解説
コスト削減契約書ひな形・テンプレート業務委託契約書 -
法律・法改正・制度の解説
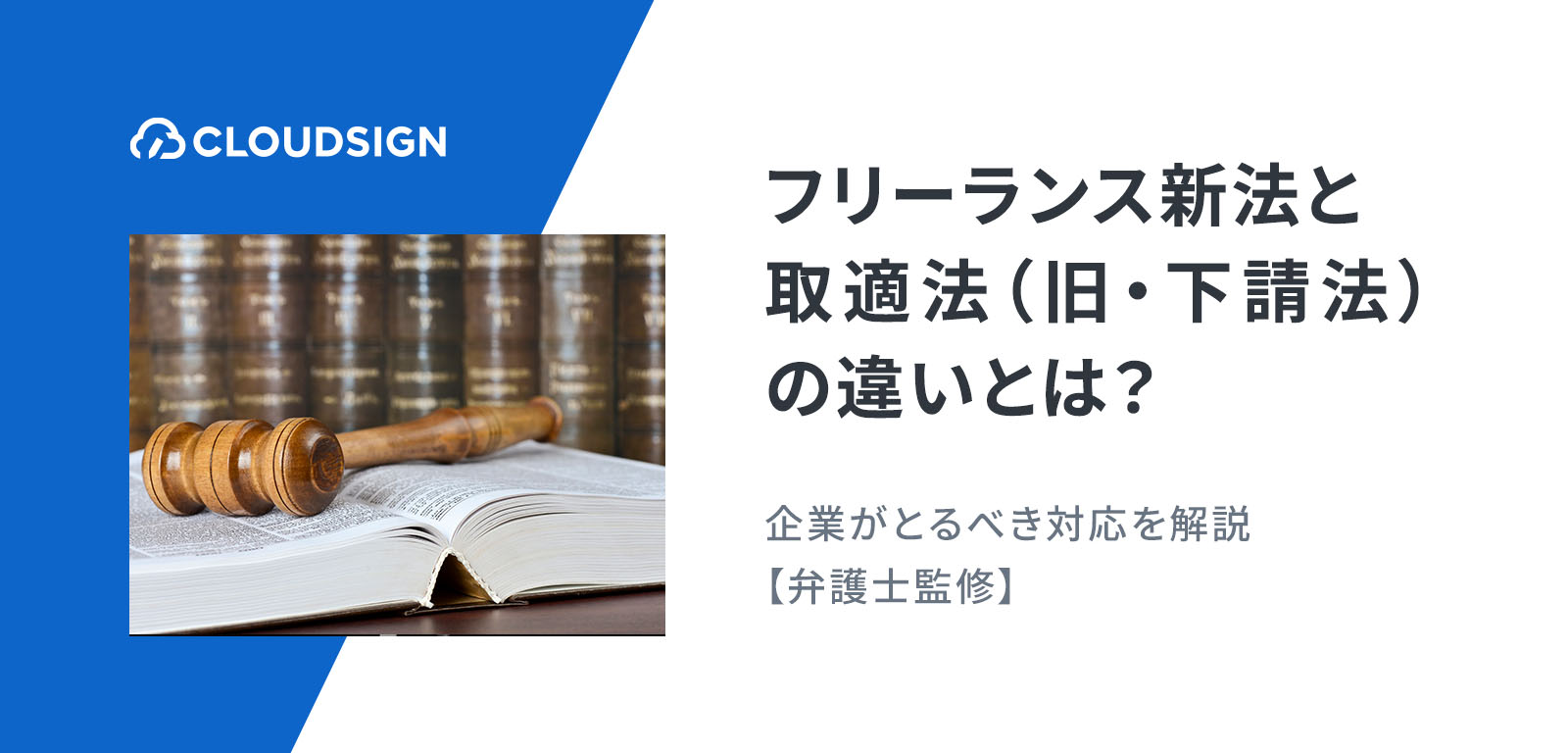
【弁護士監修】フリーランス新法と取適法(旧・下請法)の違いとは?企業がとるべき対応を解説
法改正・政府の取り組み弁護士解説取適法(下請法)フリーランス新法 -
契約実務

工事請負契約書とは?目的や作成のポイント、締結する際の注意点を詳しく解説
契約書契約書ひな形・テンプレート建設業法工事請負契約書請負契約 -
法律・法改正・制度の解説

取適法(旧下請法)改正で「3条書面」は「4条書面」へ。承諾不要などの変更点と契約巻き直し・電子化実務を解説【2026年1月施行】
契約書電子契約の活用方法取適法(下請法)電子契約のメリット業務効率化 -
契約実務

工事請負契約書に収入印紙は必要?例外的に不要なケースや印紙額を解説
契約書建設業法収入印紙工事請負契約書 -
契約実務

業務委託とフリーランスの違いとは?業務委託契約を締結するメリットや注意点を解説
業務委託契約書