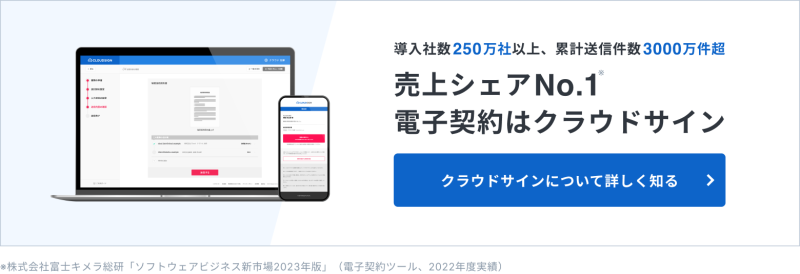電子署名と電子サインの違いとは?法的根拠やそれぞれのメリットを比較して解説
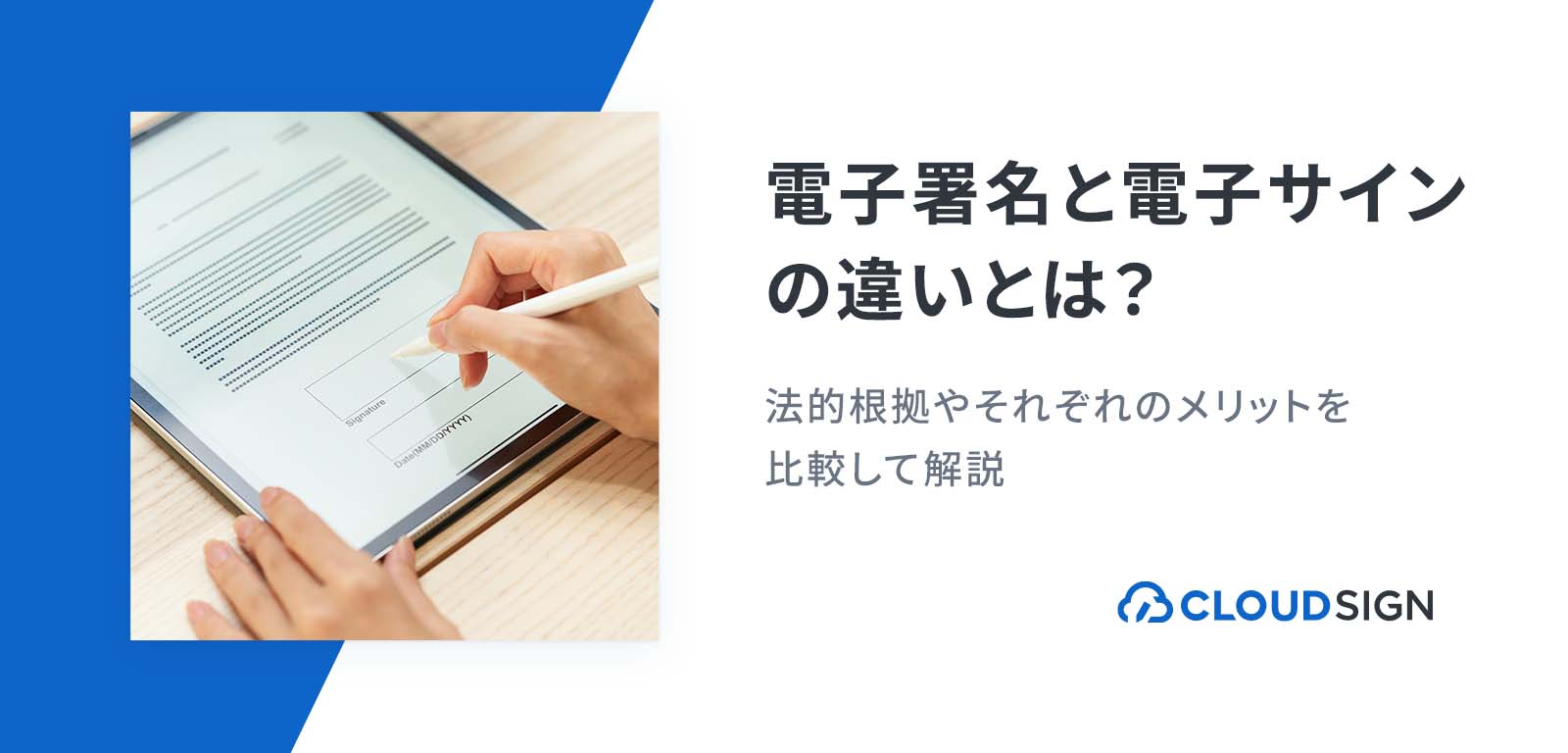
現代ではビジネスのやり取りの中心がデジタルに移行しつつあるため、契約業務も紙書類からデジタルに切り替え、電子契約サービスを導入する企業が増えています。そのなかで「電子署名」と「電子サイン」という用語を見かける機会もありますが、これらは混同されがちな言葉です。しかし、この二つの用語には法的リスクと信頼性において決定的な違いが存在するため、しっかりと理解しておくことが大切です。
当記事では、電子署名と電子サインの明確な違い、法的根拠、そしてビジネスシーンにおける実践的な選択基準について、専門的な見地から解説します。
なお、電子契約とはどのようなものなのかを知りたい方は、電子契約の基礎知識をまとめた下記の資料をご活用ください。フォームに必要情報をご入力いただくと、無料でダウンロード可能です。
無料ダウンロード
電子署名と電子サインの違いを比較
それぞれの定義や内容について詳しく解説する前に、電子署名と電子サインの違いについて最初に表で確認しておく方がわかりやすいと思いますので、まずはこちらをご覧ください。
以下に、電子署名と電子サインの違いを比較し表にまとめました。
| 比較項目 | 電子署名 | 電子サイン |
| 法的定義 | あり(電子署名法で厳密に定義) | なし(広義のビジネス用語) |
| 本人証明の強度 | 高(第三者機関=認証局が介在) | 可変的(メール認証、IPアドレス等) |
| 改ざん検知機能 | 必須(暗号技術で保証) | 多くの場合、ないか脆弱 |
| 法的効力(推定効) | あり(電子署名法第3条) | なし(他の証拠で立証が必要) |
| 紙の契約書の場合にたとえると | 実印 + 印鑑証明書 | 認印や手書きサイン |
電子署名と電子サインの決定的違いは「法的効力」と「信頼性」
それぞれの詳しい内容については次のパートで解説しますが、端的に電子署名と電子サインの違いについてまとめて解説します。広い意味では電子サインという枠組みの中に、電子署名が含まれるという関係性ですが、以下のような違いがあります。
- 電子署名は、「本人が作成したこと(本人性)」と「改ざんされていないこと(非改ざん性)」を証明できる、法律(電子署名法)で定められた特別な技術要件を満たした、高い信頼性があるもののことを指します。
- 電子サインは、同意した意思を示す電子的なプロセス(例:メールでの承諾、同意ボタンをクリックする)を指す「広い言葉」を指すものです。そのため、使われる技術は広く、特定の技術に限定されません。
電子署名と電子サインの大きな違いとして、法的な証拠能力があげられます。法律が定める要件を満たす電子署名には、裁判で「本人が押印した実印付きの契約書」と同じように、契約が本人の意思で正しく結ばれたと推定される「推定効」という強力な法的効力が認められています。「クラウドサイン」をはじめとする現在主流の(立会人型)電子契約サービスの多くも、適切な本人確認を行えば、この電子署名に該当します。
一方で、メールでの同意など、より簡易な「電子サイン」にはこの推定効が働かないため、万一の裁判では、契約の有効性を証明する負担が重くなる可能性があります。
このように、電子サインの中でも特にセキュリティが高く、法的な効力が担保されているものが電子署名である、と理解すると良いでしょう。
電子署名とは?

電子署名とは、電子文書の内容を保証・保護するために使用される技術の一種で、署名者が誰であるかを表示し、文書の改ざんを防止するために使用されます。ここからは電子署名と電子サインの理解を深めるために詳しく解説をしていきます。まずは電子署名について解説しますが、その根拠となる法律の理解をすることから始めましょう。
電子署名法が定める2つの要件、「本人性」と「非改ざん性」について
日本の法律において「電子署名」は、「電子署名及び認証業務に関する法律」(以下、電子署名法)第二条第一項で、以下の二つの要件を満たす措置として厳密に定義されています。
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov法令検索
これらの要件は、実務上、公開鍵基盤(PKI)という暗号技術によって実現され、電子文書における署名者本人による作成の証明と、署名後の改ざんの検知が可能となります。
なお、電子署名の定義や、法的な有効性についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご確認ください。
電子署名のメリット・デメリット
電子署名のメリットは、法的な証拠能力があることです。電子署名法における最も重要な点として、第3条で定められている「推定効」があります。これは、特定の条件下で作成された電子署名が、本人が署名したものとして法的に推定される、という効力のことを指します。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(…)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(…)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
これはつまり、必要な条件を満たした電子署名が付与されている電子文書は、裁判で「本人の意思に基づいて作成されたもの」と認められやすくなる、という効果です。この効果の最大のメリットは、裁判になったときに「どちらが証拠を出す責任を負うか」が変わる点です。
通常、契約が有効だと主張する側がその証拠を出す責任がありますが、推定効がある電子署名付きの文書の場合、それを無効だと主張する相手側が「この署名は本人の意思ではない」ことを証明する責任を負います。これは、争いごとになったときのリスクを大きく減らす、非常に強力な法的保護となります。
一方でデメリットもあります。電子署名は高い安全性を確保するため、サービスの利用料などの費用が必要になることがあります。無料で使える簡易な電子サインに比べると、コストがかかることはデメリットともいえるでしょう。他にもサービスによっては、自社だけでなく、契約の相手方にもサービスへの登録や、アプリのインストールといった操作を依頼する必要が出てくる場合があります。相手のITリテラシーによっては、これが契約締結のハードルになる可能性も考慮しなくてはなりません。
なお、「クラウドサイン」は相手方に登録してもらうことはなく、メールアドレスとパソコン・スマートフォンがあれば問題ありません。シンプルな操作性で、送信者側も受信者側にも使いやすいデザインとなっています。
電子サインとは?

一方で、電子サインは電子署名とは異なり、より広範な概念を指します。電子サインも、電子文書を保護するために使用される技術の一種である点は、電子署名と変わりません。しかし一般的には、公開鍵暗号方式を用いずに、その他の技術的手段による電子文書保護の方法を総称した呼び名として使われます。
電子サインの具体例
電子サインには、さまざまな具体例があります。以下に挙げる行為はすべて電子サインに該当します。
- ウェブサイトの利用規約同意画面で「同意する」ボタンをクリックする行為
- 手書き署名のスキャン画像や印影の画像を文書に貼り付けること
- タブレット端末上でスタイラスペン(タッチペン)を用いて署名すること
- 電子メールの文末に名前を入力し、承諾の意思を示すこと
これらの行為も契約の証拠となり得ますが、前述の通り、電子署名法第3条の推定効は働きません。
電子サインは法律に定義がない広範な概念
日本には「電子サイン」という言葉を直接定義する法律がありません。電子サインはビジネスシーンでよく使われる言葉ですが、その法的な効力は、電子署名法のような特別な法律で守られているわけではなく、それぞれのケースごとに、一般的な契約のルールに基づいて判断されます。
参考として、米国のESIGN法106条(電子署名に関する連邦法)では、電子サインを「契約書や他の記録物に添付され、論理的に関連付けられた電子的な音声、記号、またはプロセス」と広範に定義しており、署名者の「意図」が重視される非常に幅広い解釈の余地を持たせた定義となっています。
The term “electronic signature” means an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record.(訳:「電子サイン」とは、契約書や他の記録物に添付され、論理的に関連付けられた電子的な音声、記号、またはプロセスであり、当該記録物にサインする意図を持って、人によって実行され採用されたものを指す。)
電子サインのメリット
電子サインのメリットは、主にコストと手軽さにあるでしょう。電子サインは、上記のように「メール文末に名前を入力して承諾の意思を示す」「タブレットにスタイラスペンで署名をする」といったシーンで利用するものです。利用者が個人の電子証明書を取得する必要がないなど、手軽な仕組みで利用できるため、厳格な電子署名に比べて導入・利用コストを抑えられます。
もうひとつは、その手軽さです。「クラウドサイン」のような電子契約サービス(電子署名)も、サービスにログインして契約書を送るだけで契約が完了するため、非常に簡単で手軽です。電子サインが電子契約サービスよりも「手軽」といえる部分としては、専用のサービスやシステムを介さず、日常的なツールで完結できる点が挙げられるでしょう。
一方で、電子サインにはその手軽さゆえの注意点も存在します。最大のデメリットは、法的な証拠能力が厳格な電子署名に比べて弱い点です。また、印影の画像を文書に貼り付けるだけやメール認証のみといった手軽さの裏返しで、なりすましのリスクがゼロではない点もデメリットです。例えば、メールアカウントが第三者に乗っ取られてしまった場合、本人の意思に基づかない同意がなされる可能性も否定できません。
電子サインの手軽さは魅力的ですが、取引相手との信頼関係や、契約の重要度に応じて使い分けることが肝心です。
無料ダウンロード
電子署名と電子サインの用語法に関する注意点
電子署名と異なり、電子サインは法律上定義が明確ではない
これまで述べたように、電子署名の語は電子署名法において明確に定義されている一方で、電子サインは法律上定義が明確ではありません。
そのため、電子サインという用語が使われている場面では、それが使用されている場面や、当該電子サインが依拠している技術を正確に把握した上で評価を行うことが必要となります。
クラウド技術を活用した事業者署名型(立会人型)=電子サインとする考え方は誤り
電子署名が使われ出した2000〜2010年前後まで、電子契約業界では、認証局が利用者の身元を確認し電子証明書を発行して利用する当事者署名型の電子署名しか存在しませんでした。これを受けて、当事者署名型によるもののみを電子署名と呼び、それ以外の文書保護技術を下に位置付ける形で電子サインと呼び分けていた時代があります。
その後、クラウド技術を活用した新しい事業者署名型(立会人型)サービスが提供され始めましたが、当初はこれを電子サインにグルーピングし、従来型の電子署名とは異なるものと位置付けられていた時代がありました。
しかし、2020年に政府が電子署名法Q&Aを発信し、事業者署名型(立会人型)についても電子署名法が定義する電子署名に該当することが確認され、こうした従来の誤った認識が改められました(関連記事:デジタル庁の「電子契約サービスQ&A」を解説 —電子署名が法律上有効となる条件の政府見解とは)。
現在では、クラウド技術を活用した事業者署名型(立会人型)=電子サインとする考え方は誤りと言えますが、古い電子署名の専門書やWeb上の記事の記載には、そうした誤った認識に基づいて書かれたものもいまだに散見されるため、注意が必要です。
電子契約サービスの種類
市場に流通する電子契約サービスの多くは、その仕組みによって「立会人型」と「当事者型」に大別されます。この違いは、自社に適したサービスを選定するうえで知っておくべき内容です。
立会人型(事業者署名型)電子署名
これは、クラウド型の電子契約サービスでよく使われる方法です。契約する人は自分で電子証明書を持たず、サービス提供者(立会人)のシステムにアクセスし、メール認証などで本人確認を行います。その後、サービス提供者がその人の指示に基づいて、事業者自身の電子署名を文書につけます。
- メリット
契約相手はメールアドレスとブラウザがあればすぐに使え、手軽に契約ができます。 - 証拠の強さ
サービス提供者が安全に保管する「監査証跡」(誰が、いつ、どの文書にアクセスして同意したかなどの記録)によって、署名した人の意思が証明されます。
当事者型電子署名
これは、契約する人自身が、公的な認証局による厳格な本人確認を経て、自分名義の電子証明書(マイナンバーカードなど)を取得し、その証明書と連携した秘密鍵を使って直接文書に署名する方法です。
- メリット
「誰が署名したか」という本人確認が最も強力で、法的な効力が非常に高いです。 - デメリット
契約に関わる全員が事前に電子証明書を取得する必要があるため、時間も費用もかかります。
この署名方式の信頼性を支える電子証明書の役割について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
まとめ
電子署名と電子サインは、両方とも電子文書に署名をし文書の内容を保証・保護するために使用される技術です。
電子署名は、公開鍵暗号技術に基づいており、署名者が誰であるかを確認し、文書の改ざんを防止するために使用されます。一方、電子サインは、公開鍵暗号技術を使用しないため、電子署名ほどの厳密な仕組みを採用していないものを含みます。
電子署名よりも電子サインは常に機能が劣る、というわけではありませんが、電子サインを利用する際は、公開鍵暗号の代わりにどのような技術を利用しているのか検証が必要となります。
どちらの用語を使用するにせよ、その違いについて十分に理解し、誤った用語法とならないよう注意することが重要です。
これまで解説してきたように、重要な契約であるほど、電子署名法に準拠した「電子署名」の利用が不可欠です。万が一のトラブルに備え、法的証拠能力の高い電子契約サービスで、自社のビジネスを守ることが大切です。
当社の提供する「クラウドサイン」は契約書の送信から締結、保管までを一元管理できる電子契約サービスです。導入社数250万社以上の実績を持ち、多くの企業や官公庁で選ばれている「クラウドサイン」も、電子署名法に準拠した「法的な証拠能力」があるため、安心して契約締結が可能です。ご興味のある方は、3分でわかる電子契約・サービス説明資料をご用意しておりますので、無料でダウンロードしてご活用ください。
参考文献
この記事を書いたライター
橋詰卓司
弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム
弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。
こちらも合わせて読む
-
電子契約の基礎知識
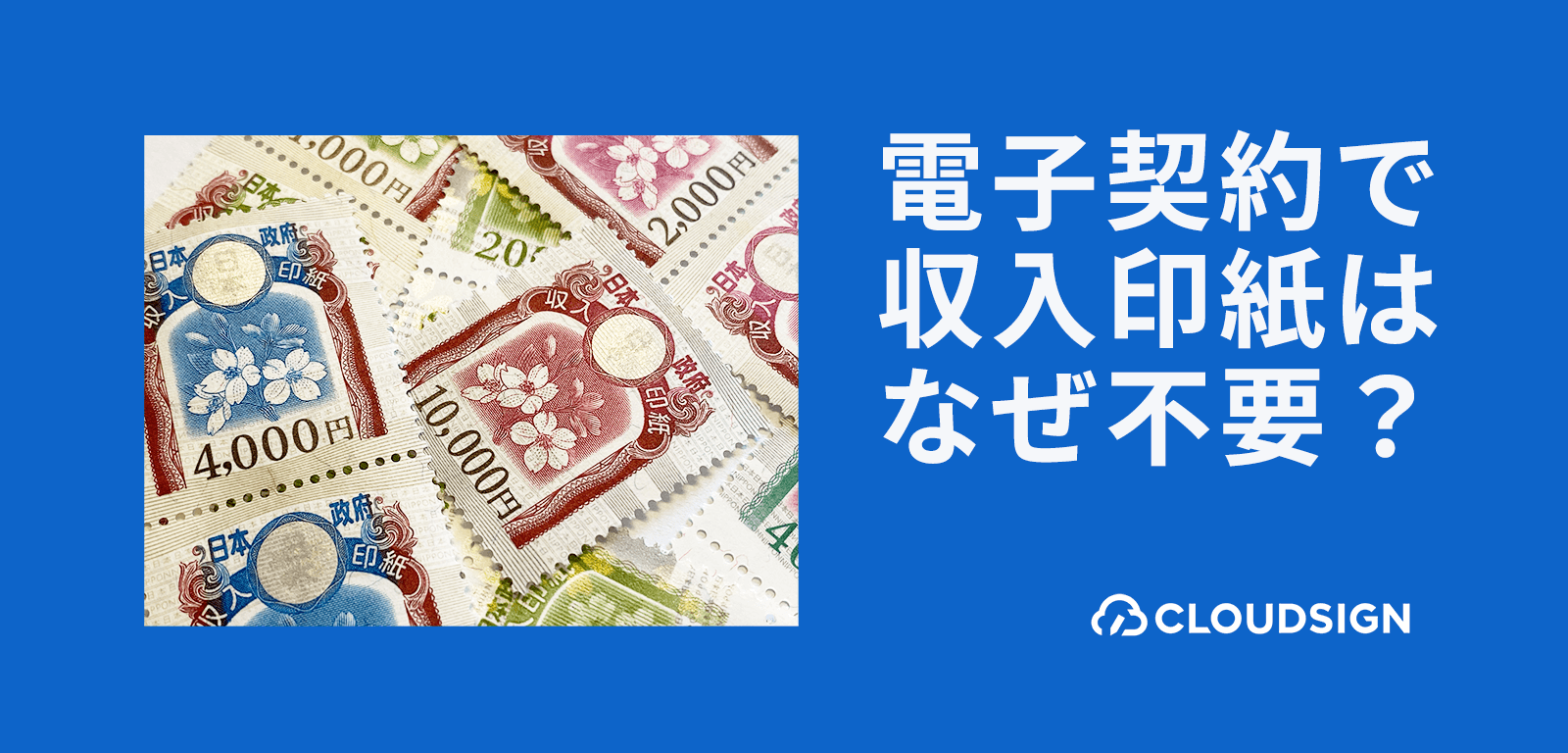
電子契約で収入印紙が不要になるのはなぜか?
印紙税と収入印紙 -
契約実務
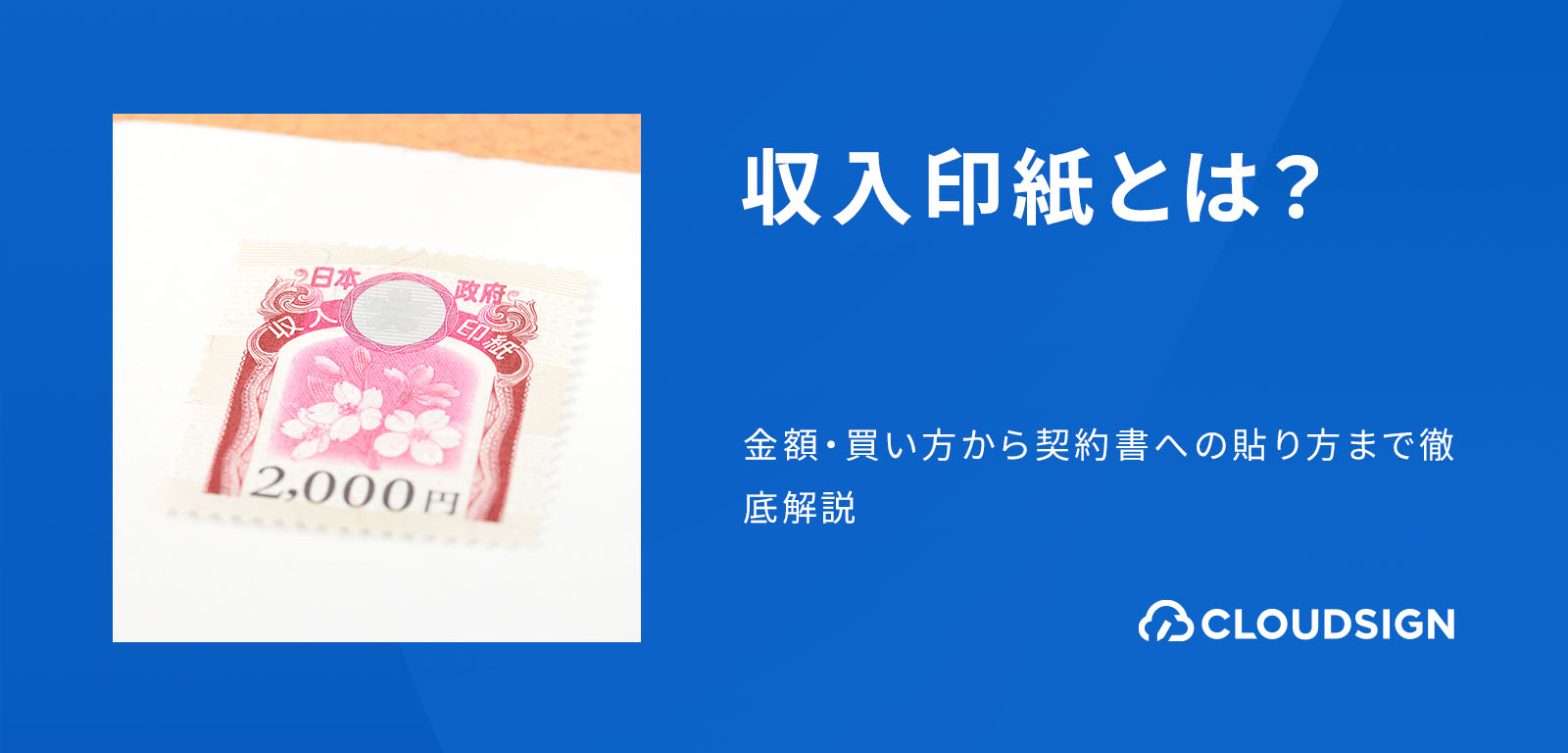
収入印紙とは?必要な金額・買い方・貼付位置まで初心者向けに完全解説
印紙税と収入印紙コスト削減 -
電子契約の基礎知識

電子帳簿保存法で定められた契約書の「データ保存」要件とは 適法な保管・保存方法を解説
契約書管理電子帳簿保存法 -
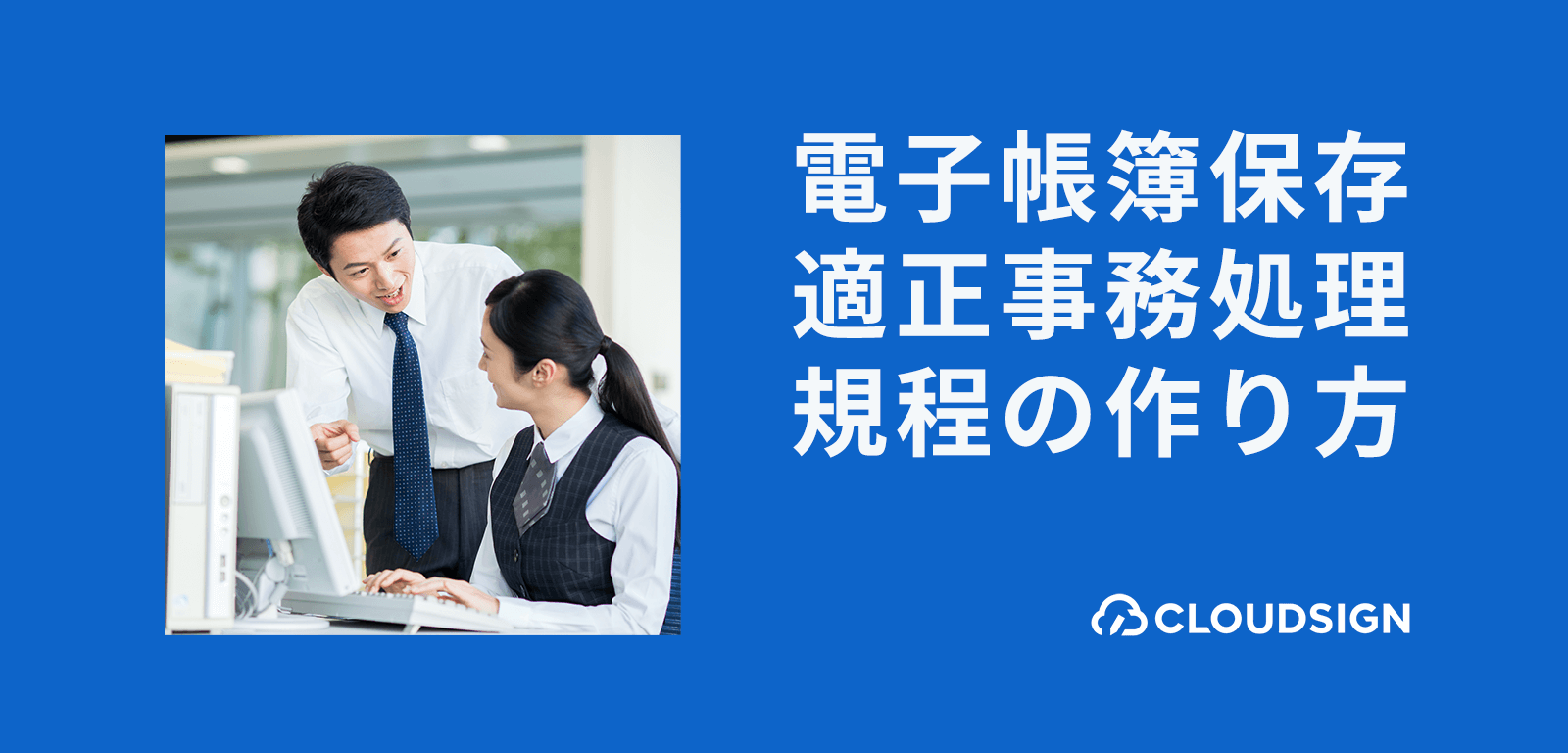
電子帳簿保存法対応のための「適正事務処理規程」の作り方ポイント解説
電子帳簿保存法 -
電子契約の基礎知識
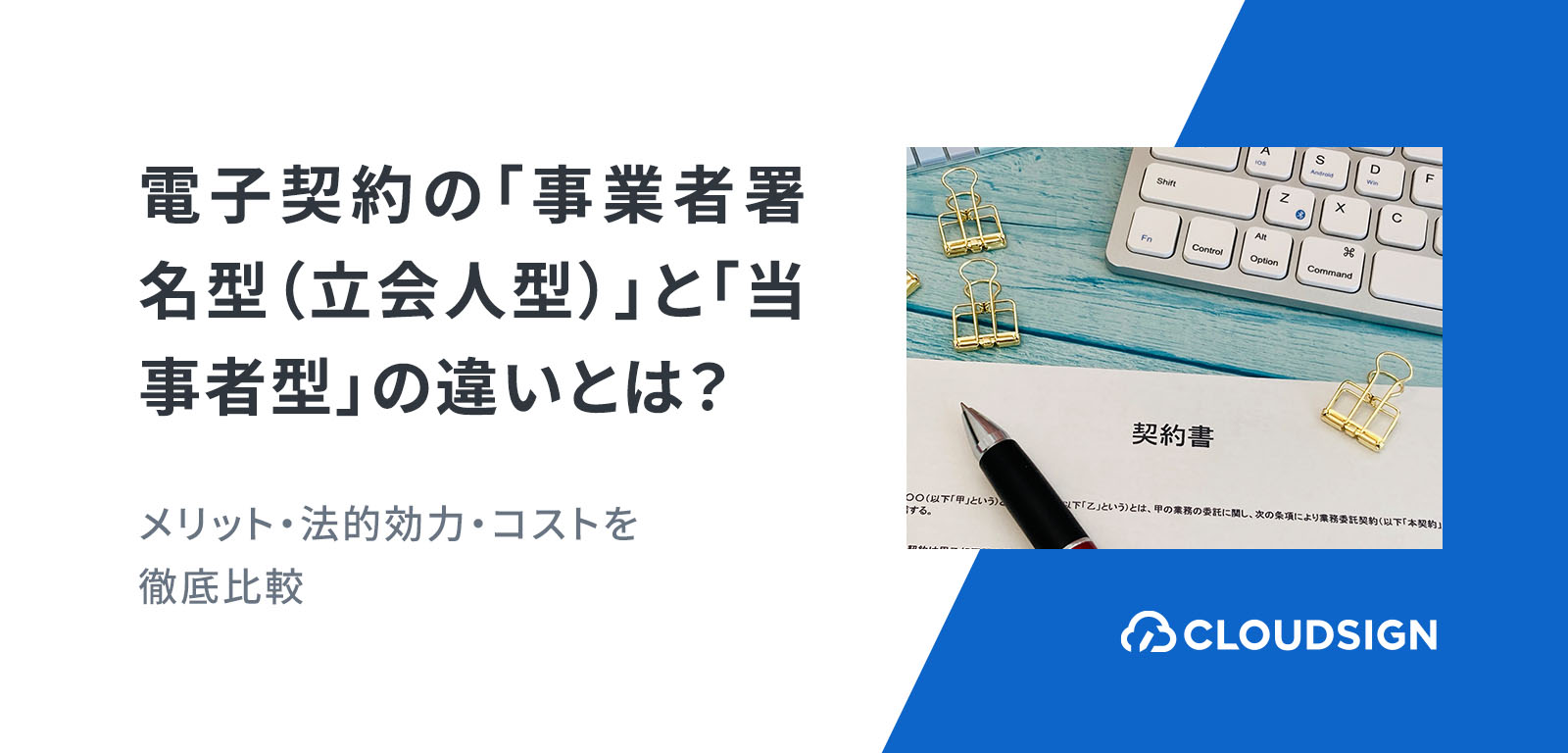
電子契約の「事業者署名型(立会人型)」と「当事者型」の違いとは?メリット・法的効力・コストを徹底比較
事業者署名型(立会人型) -
電子契約の基礎知識
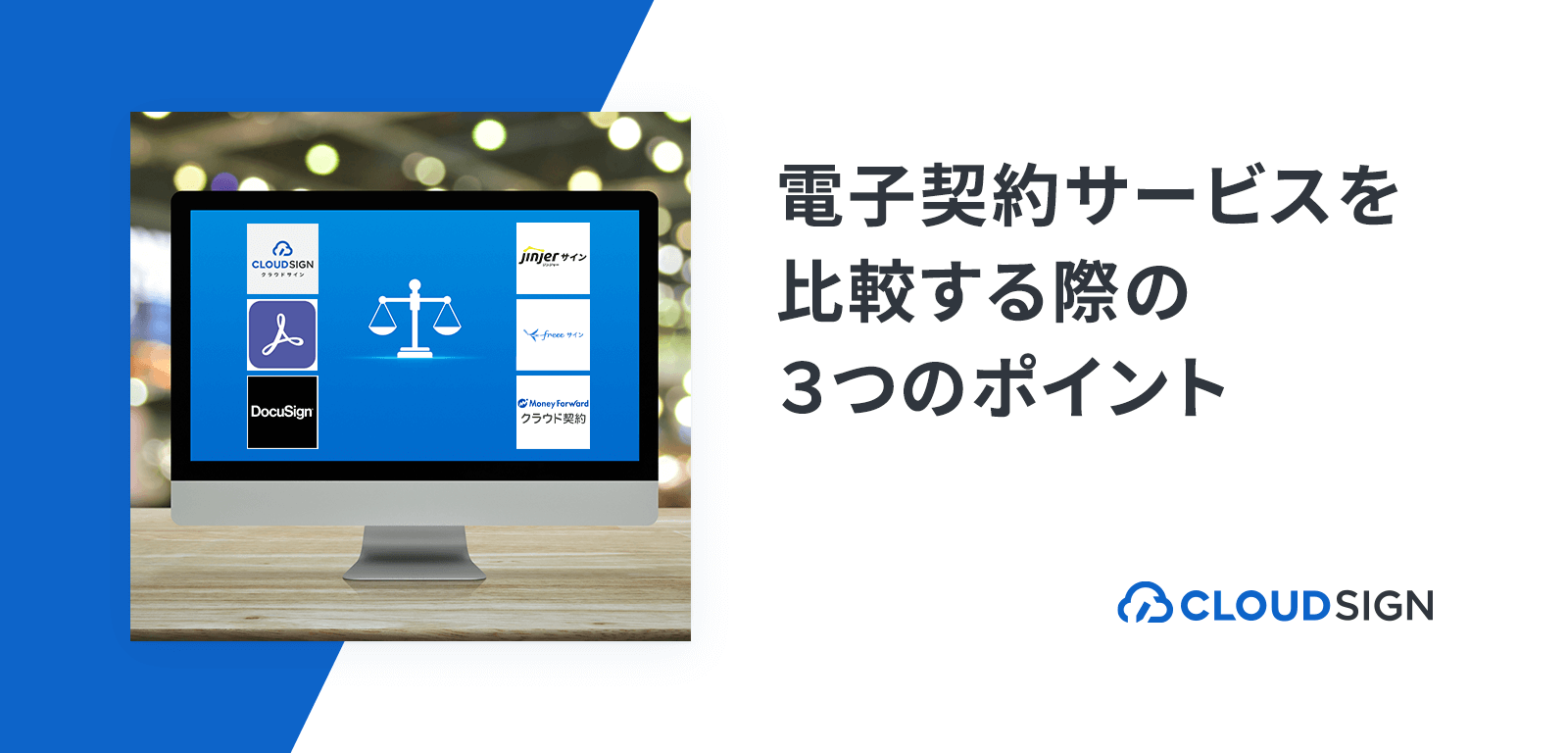
電子契約サービスを比較する際の3つのポイント おすすめの電子契約サービス比較サイトも紹介