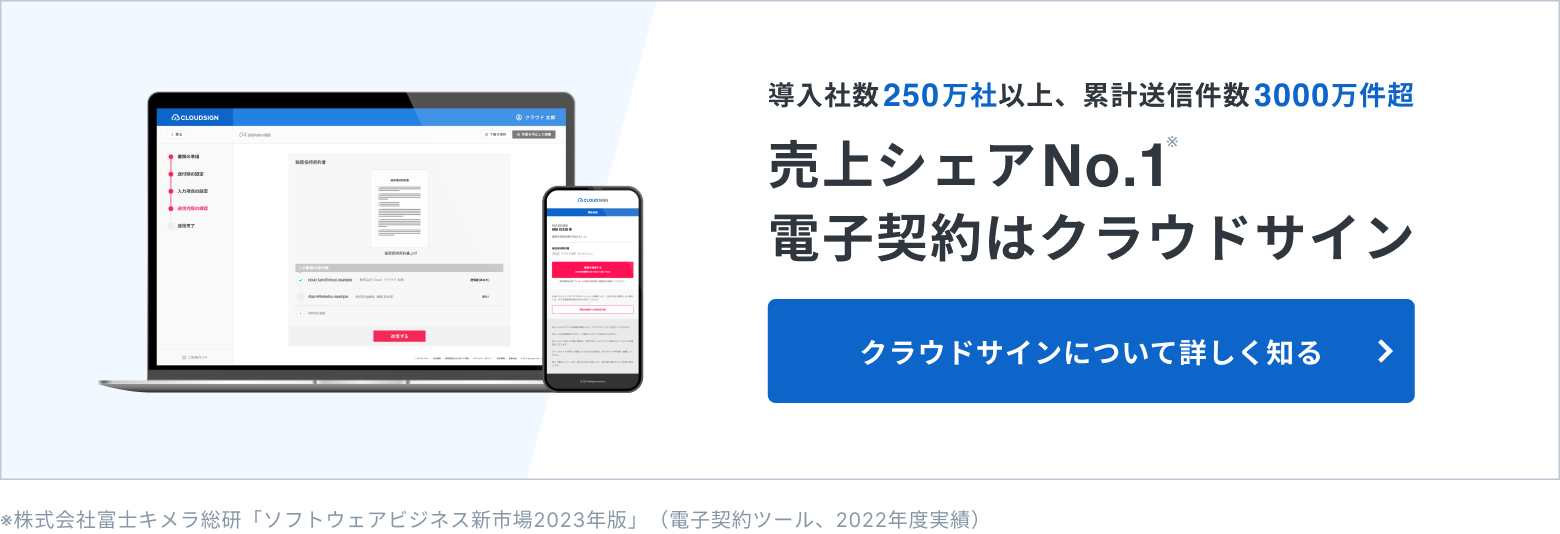外国人雇用の契約書とは?必要な記載内容や注意点をわかりやすく解説【弁護士監修】
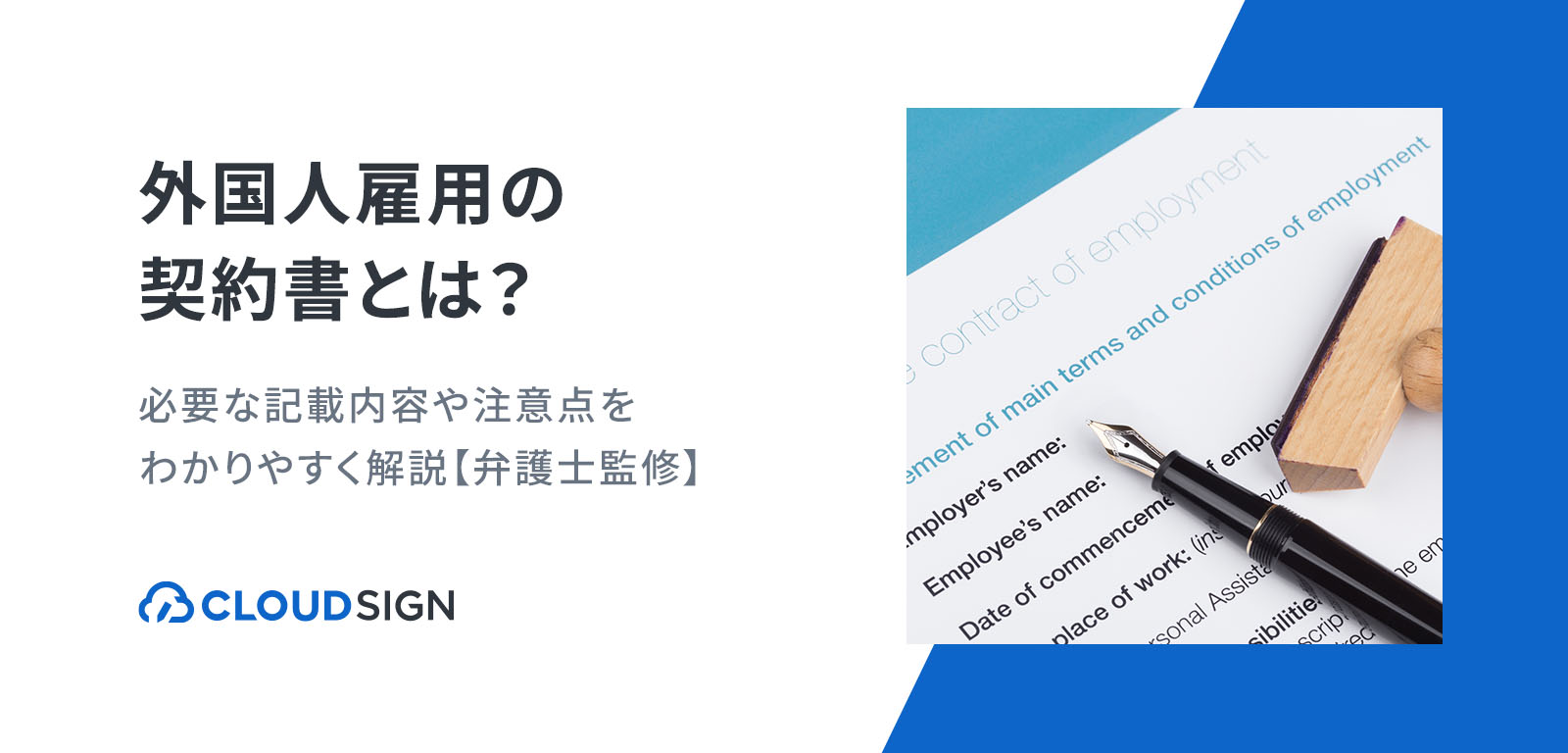
従業員を雇用する際は、労働条件や契約内容を正しく書面で交わすことが重要になりますが、外国人雇用においても同様です。
とくに、外国人労働者の雇用の場合には、言語や制度の違いによる認識のズレが起こりやすく、契約書の不備がトラブルにつながるケースも少なくありません。
ここでは、外国人雇用時に作成する契約書のポイントや注意点をわかりやすく解説します。
なお、外国人との契約手続きは、言語の壁や在留資格の確認など、日本人を雇用する場合よりも複雑になりがちです。こうした手続きをスムーズかつ安全に進める手段として、近年は「電子契約」が注目されています。採用候補者がまだ海外にいる段階でも迅速に契約を締結できるため、外国人雇用を検討する上で有効な選択肢となります。
当社では、電子契約の基礎をまとめた資料をご用意しておりますので、本記事で解説する契約書のポイントとあわせて、無料でダウンロードしていただき、ご活用ください。
無料ダウンロード
目次
日本人と外国人の雇用において異なる点・対応すべきこと
外国人雇用は日本人と同じ対応がベースになりますが、在留資格や言語理解など特有の確認事項があります。ここでは、外国人雇用前に企業が対応すべきことを解説します。
日本人と外国人の雇用契約書は基本的に同じ
労働基準法第15条により、雇用時には賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があり、これは国籍にかかわらずすべての労働者に共通です。そのため、雇用契約書の作成は、日本人と外国人で区別されていません。
【参考:e-Gov 第二章 労働契約 (労働条件の明示)第十五条】
ただし、外国人労働者の場合、日本語を十分に理解できない可能性もあるため注意が必要です。
契約内容を理解していない状態での同意は無効とされるリスクがあるため、母国語または英語での併記や、通訳を交えた説明などの配慮が必要になります。
雇用前に確認すること
外国人を雇用する前に、必ず確認すべきなのが在留資格の種類と就労制限の有無です。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のように就労が認められている資格もあれば、「留学」や「家族滞在」などでは資格外活動許可が必要となります。
雇用主は、在留カードで以下の3点を必ず確認しましょう。
- 在留資格の種類
- 在留期限
- 就労制限の有無(「就労不可」とあれば雇用不可)
これらを確認せずに雇用した場合、たとえ本人の提示した書類が偽造であっても、事業主側が不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われる可能性があります。
【参考:法務省:在留カード・就労資格の確認手続き】
【参考: 法務省公式動画|在留カードの確認方法(YouTube)】
雇用前に必要な書類について
日本人雇用と同様に外国人を雇用する際も、労働条件を明確に示し、本人が理解・同意していることを確認する必要があります。
労働基準法第15条により、事業者には労働者に対する労働条件通知書の交付が義務付けられている一方、雇用契約書の作成に関しては法的義務はありません。しかし、外国人雇用の場合、お互いが合意した証拠を残すために「雇用契約書」を交わすことが推奨されます。日本語の読み書きが難しいケースもあるため、内容を正確に説明した上で、本人が理解・納得したうえで署名することが重要です。
また、「労働条件通知書兼雇用契約書」として1通にまとめる形式も認められています。労働契約は口頭でも成立しますが、労働条件などをめぐる後のトラブルを防止するため、書面で合意内容を明確にし、記録を残すことが重要です。外国人の場合は押印の慣習がないことも多いため、署名(サイン)によって合意の意思を確認することが一般的です。
外国人の雇用契約書で配慮すべきポイント
外国人労働者との雇用契約では、日本人と同じ書式をそのまま用いるのではなく、法的な確認事項や言語の工夫など、特有の配慮が求められます。
以下では、契約書を作成する際に注意すべき具体的なポイントを紹介します。
契約書の言語
契約書は、日本語だけでなく、相手の理解できる言語(英語や母国語)でも作成するのが望ましいです。日本語のみの契約書では、内容を誤って理解されるリスクがあります。
とくに労働条件に関する誤解はトラブルに直結するため、翻訳版を併せて用意し、両者が同内容であることを確認することが重要です。ただし、翻訳の正確性には注意し、誤訳がないか確認することも大切です。
在留資格の確認
雇用前に、外国人の「在留カード」などを通じて、就労が認められる在留資格かを必ず確認する必要があります。
在留資格が就労可能でない場合、その外国人を働かせることは「不法就労助長罪」に該当する可能性があり、雇用主側も処罰対象となるからです。
在留期間の管理
契約期間が在留資格の期限を超えないように注意が必要です。
たとえば、在留期限が1年であるにもかかわらず、2年契約を結んだ場合、在留資格の更新ができないと契約を履行できないリスクが生じます。
在留期限は契約締結時と継続雇用時に必ず確認し、必要に応じて更新の手続きをサポートする体制も整えておくと安心です。
制度による書式の違い
外国人の雇用制度によって、契約書の書式や必要書類が異なります。
たとえば「技能実習」や「特定技能」の場合には、制度に応じた雇用条件書や定められた様式を用いる必要があります。
これらは法令や出入国在留管理庁の定めに基づくため、適切な書式で作成しなければ在留資格の認定が下りないこともあります。
文化・慣習の説明
日本の労働文化や職場慣行に不慣れな外国人労働者に対しては、契約書の内容だけでなく、職場内のルールや礼儀・マナーについても丁寧な説明が求められます。
たとえば「定時後の残業」「昼休憩の取り方」「あいさつ・報告の仕方」など、暗黙の了解で済ませず、明文化または口頭でしっかりと説明することで、認識のズレを防げます。
家族や生活支援の内容
外国人の受け入れ制度によっては、雇用契約に生活支援や家族への配慮に関する項目を盛り込むことが求められる場合があります。
たとえば「住居の確保」「生活オリエンテーションの実施」「日本語学習支援」などです。
とくに特定技能制度では「支援計画」の策定と実施が義務づけられており、契約書にもその概要を反映する必要があります
特定技能外国人とは?雇用する場合の契約上の義務・注意点
特定技能制度とは、深刻な人手不足が続く14業種において、一定の専門性・技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れる制度です。
2019年に新設された在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」に基づき、介護・建設・外食など即戦力人材の雇用が可能になりました。
ここでは、特定技能外国人を雇う際の契約上の義務と注意点を解説します。
業務内容が特定技能14分野の範囲内であること
特定技能外国人を雇用できるのは、以下の14分野に限られます。対象外の職種に従事した場合は在留資格に違反するため、契約書には業務内容を明確に記載する必要があります。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業(鋳造、鍛造、仕上げ等)
- 産業機械製造業
- 電気/電子情報関連産業
- 建設業
- 造船/舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
出典:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)|出入国在留管理庁
これらの業種に該当しない業務内容を記載した場合、在留資格の認定や更新が下りない可能性があります。
日本人と同等以上の報酬であること
特定技能外国人には、日本人と同等以上の報酬(給与)を支払うことが法律で義務づけられています。これは、雇用の公平性を確保するための規定であり、業務内容や経験が同程度であれば、賃金も同等である必要があります。
契約書には、賃金の額・支払い方法・支払い時期を具体的に記載するとともに、社内で同様の職種に就く日本人との待遇に差がないことを確認する必要があります。
勤務時間、休日、残業代の支給など労基法準拠
特定技能外国人も、日本人と同様に労働基準法の対象となります。したがって、契約内容には法令に基づいた労働条件(所定労働時間、休日、休憩時間など)を記載し、時間外労働が発生する場合は、残業代・休日手当・深夜割増賃金を適切に支払う必要があります。
契約書上にも、これらの支払い基準や発生条件を明記し、本人に十分説明することが求められます。
契約終了時の帰国費用負担の明記
特定技能1号の在留資格は「通算5年まで」とされており、契約満了時には原則として帰国が前提となります。このときの帰国費用(航空券など)を誰が負担するかについては、契約書に明示する必要があります。
厚生労働省の指針では、原則として企業が負担することが望ましいとされています。
【記載例】
本契約終了後の帰国にかかる費用は、原則として受入れ企業が負担するものとする。
生活支援・相談体制の記載
特定技能1号外国人を雇用する企業には、「生活支援」を行う義務があります。これは職場だけでなく、生活全般にわたる支援を通じて、円滑な就労環境を整える目的があります。支援の具体例には以下が含まれます。
・住居の確保支援
・生活に必要な情報の提供(交通機関、銀行口座開設など)
・日本語学習機会の提供
・各種相談窓口の案内や通訳対応
これらは「支援計画書」として文書にまとめる必要があり、契約書には実施主体(自社 or 登録支援機関)と支援内容を明記しておくと安心です。
保証金・違約金は取らない旨の記載
特定技能制度では、人権保護の観点から違約金や保証金の徴収が禁止されています。
たとえば「1年未満で退職したら○万円を請求する」「就労のために保証金を預けさせる」といった条件は無効であり、記載されていた場合でも法的効力はありません。
制度上もこれらの取り決めが確認されると、在留資格の認定や更新に影響する可能性があるため、「保証金や違約金は徴収しない」旨を明記しておくことが重要です。
外国人の雇用契約書のひな型
外国人を雇用する際は、雇用契約書の締結が推奨されます。
厚生労働省や出入国在留管理庁では、外国人向けの契約書ひな型や作成例を公開しており、これらを参考にすることで、必要事項の漏れを防げます。
たとえば、厚生労働省愛知労働局の「外国人労働者の雇用契約書(モデル)」では、労働条件の明示項目(勤務時間、賃金、休日、契約期間など)が多言語で整理されています【参考※1】。
また、在留資格「特定技能」の対象者向けには、法務省・出入国在留管理庁が専用の雇用契約書様式を公開しています【参考※2】【参考※3】。
業種や在留資格によって記載内容に違いが出るため、行政が提供する最新の書式を参考にしながら、個別の雇用条件に応じて適切に作成・運用することが重要です。
【参考※1】厚生労働省 愛知労働局|外国人の雇用契約書モデル(Word形式)
【参考※2】出入国在留管理庁|特定技能 雇用契約書例①(日本語版)
【参考※3】出入国在留管理庁|特定技能 雇用契約書例②(多言語対応版)
雇用契約は「電子契約」でスムーズかつ安全に
外国人労働者との雇用契約にも、近年は紙の契約書に代わって電子契約を活用する企業が増えています。
電子契約であれば、遠方に住む外国人とのやりとりもスピーディに進められ、契約の締結や管理もクラウド上で一元化できます。
たとえばクラウドサインでは、契約書の送信・締結を英語や中国語でも対応可能です。日本語に不安がある外国人との契約にも柔軟に対応でき、法的効力も紙と同等です(電子署名法に準拠)。
外国人雇用においては、労働条件通知書などの交付義務もあるため、書面管理の効率化・コンプライアンス対応の両面から、電子契約の導入は有効な選択肢となります。
なお、「クラウドサイン」は法的効力を認められた電子契約サービスとなります。システムから送信されるメールを英語または中国語(繁体字・簡体字)で送信したり、書類確認のガイダンスを英語で表示できるようになっているため、英語でコミュニケーションを行う外国企業や外国人の方々とのスムーズな契約締結が可能です。(クラウドサインヘルプページ:英語で書類送信、合意締結を行う)
「クラウドサイン」のサービスの詳細について知りたい方はこちらの資料を無料ダウンロードしてご覧ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)まとめ
外国人を雇用する際の契約書は、言語の壁や在留資格特有の要件など、日本人雇用とは異なる配慮が求められるため、トラブル防止の観点から非常に重要です。契約内容の曖昧さはもちろん、特定技能制度のように定められた書式が必要なケースや、相手の母国語への翻訳対応など、細やかな注意点がコンプライアンス遵守の鍵となります。
こうした複雑な手続きを効率化し、安全に契約を進めるためには、「クラウドサイン」をはじめとする電子契約サービスの活用が有効です。クラウドサインでは多言語対応や書類の一元管理といった機能があり、外国人雇用の課題解決を力強くサポートします。
なお、当社では電子契約のメリットから始め方についてまとめた資料を無料でダウンロードが可能ですので、ぜひご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
加藤高明
弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
電子契約の運用ノウハウ
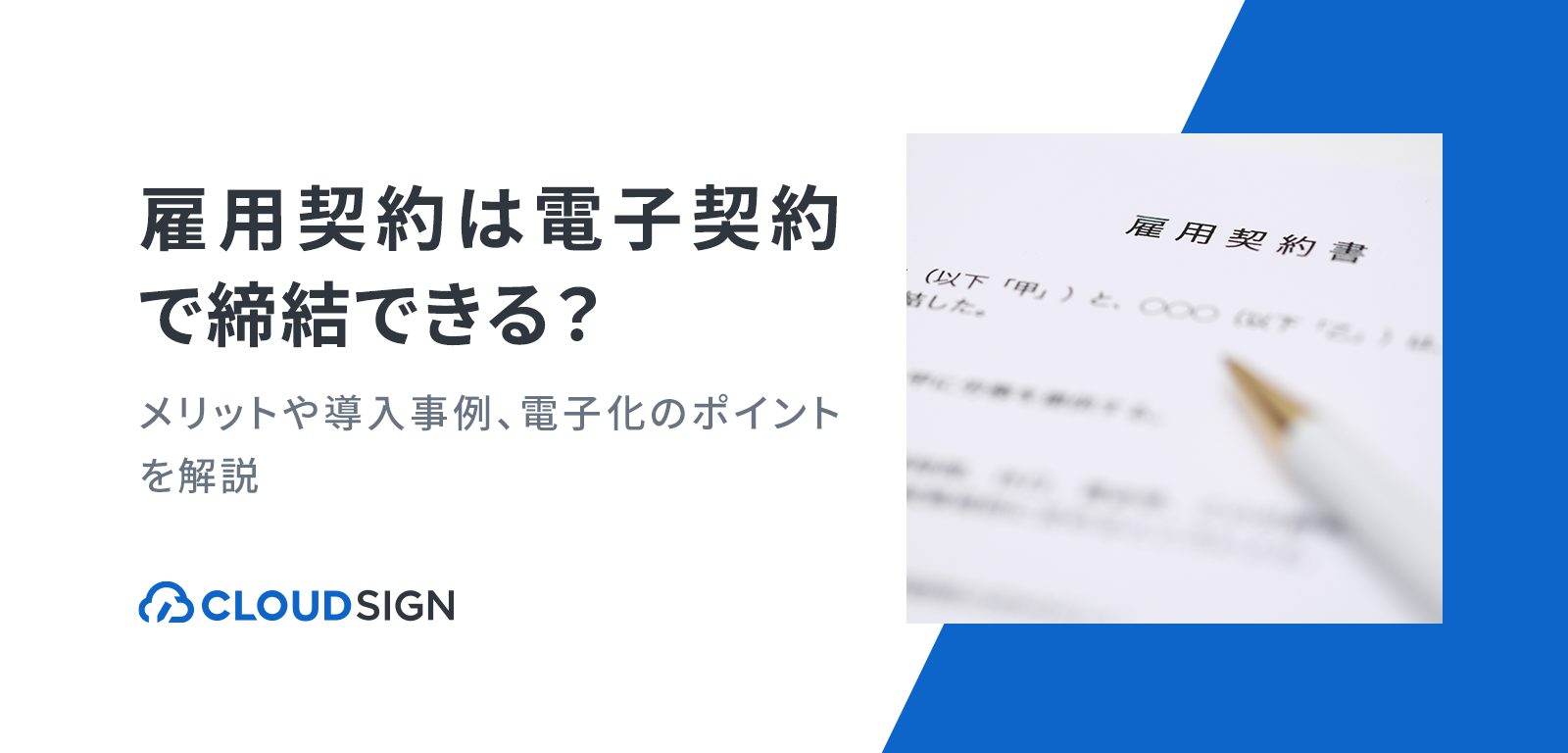
雇用契約は電子契約で締結できる?メリットや事例を解説【Word版ひな形ダウンロード付】
電子契約の活用方法雇用契約 -
電子契約の運用ノウハウ
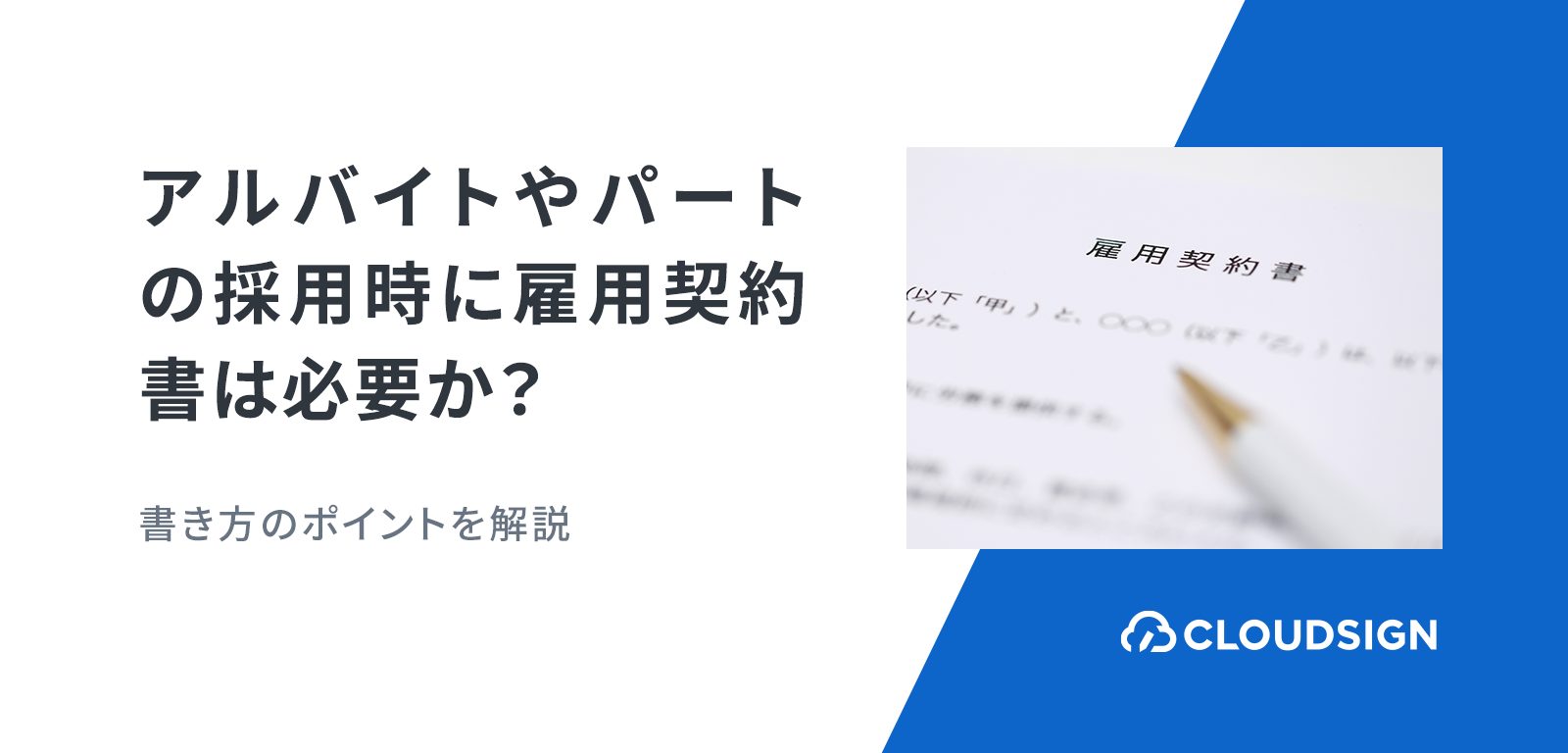
アルバイトやパートの採用時に雇用契約書は必要か?書き方のポイントを解説
雇用契約 -
契約実務
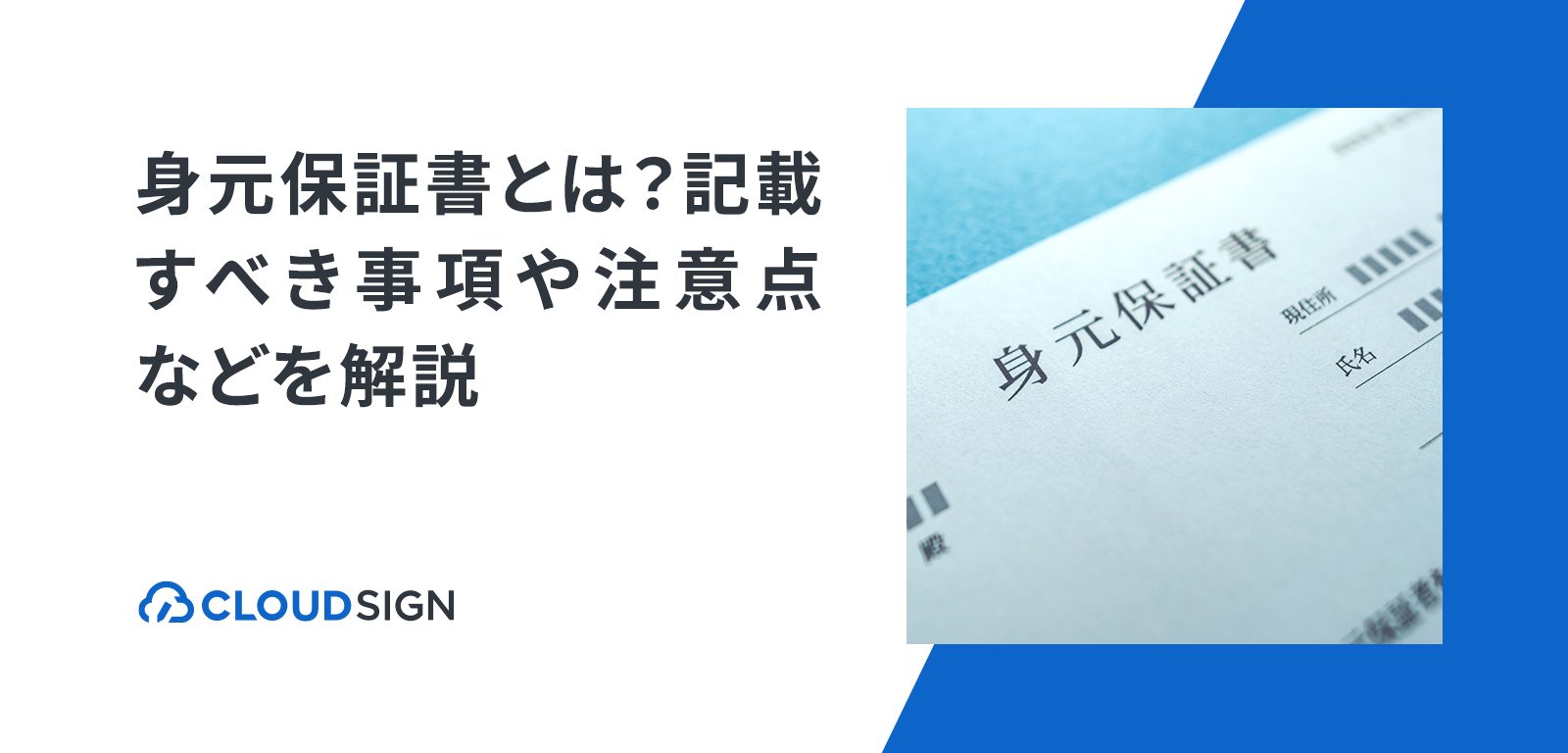
【弁護士監修テンプレートあり】身元保証書とは?記載すべき事項や注意点などを解説
契約書電子契約書 -
契約実務
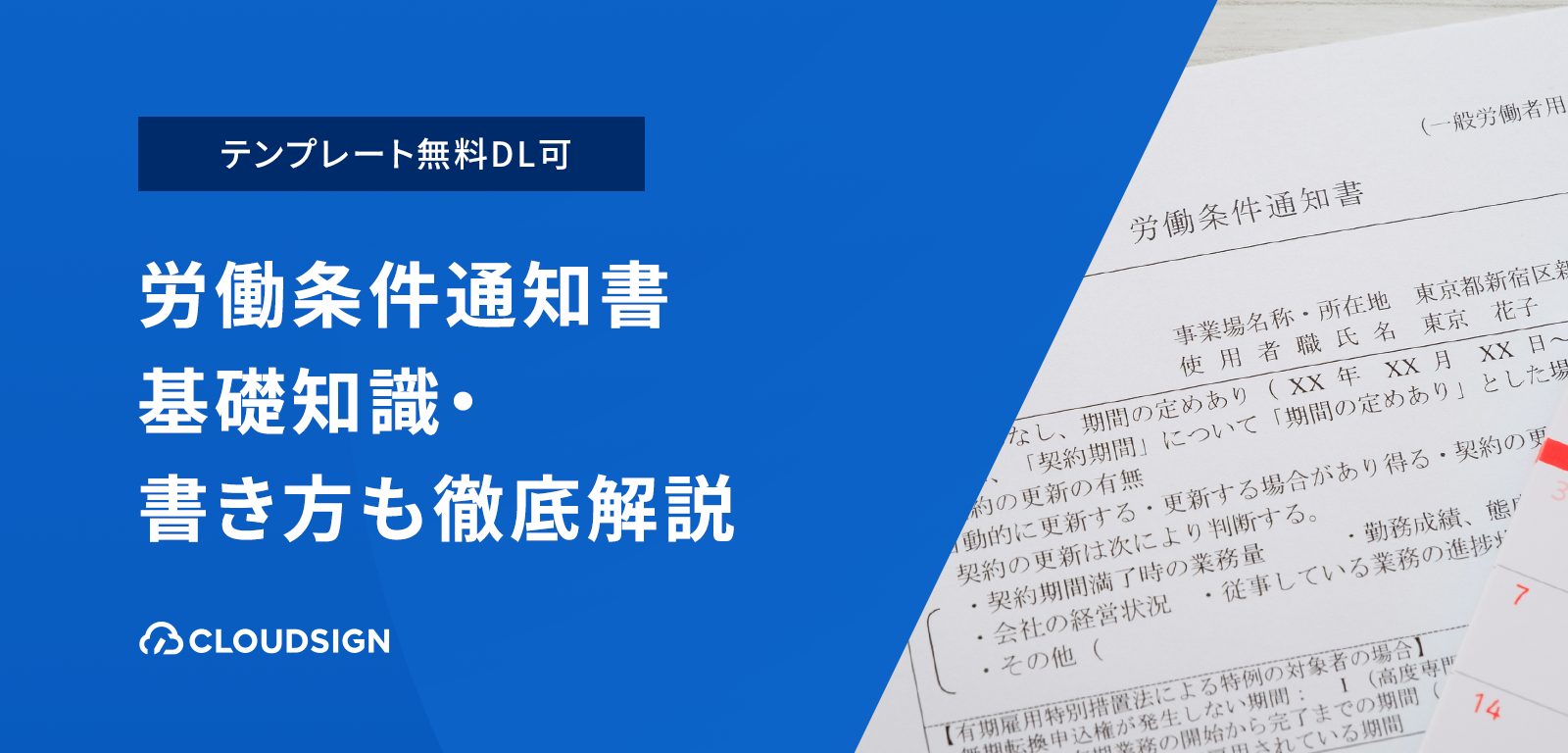
【無料DL可】労働条件通知書のテンプレート 基礎知識と書き方も徹底解説
契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -
契約実務
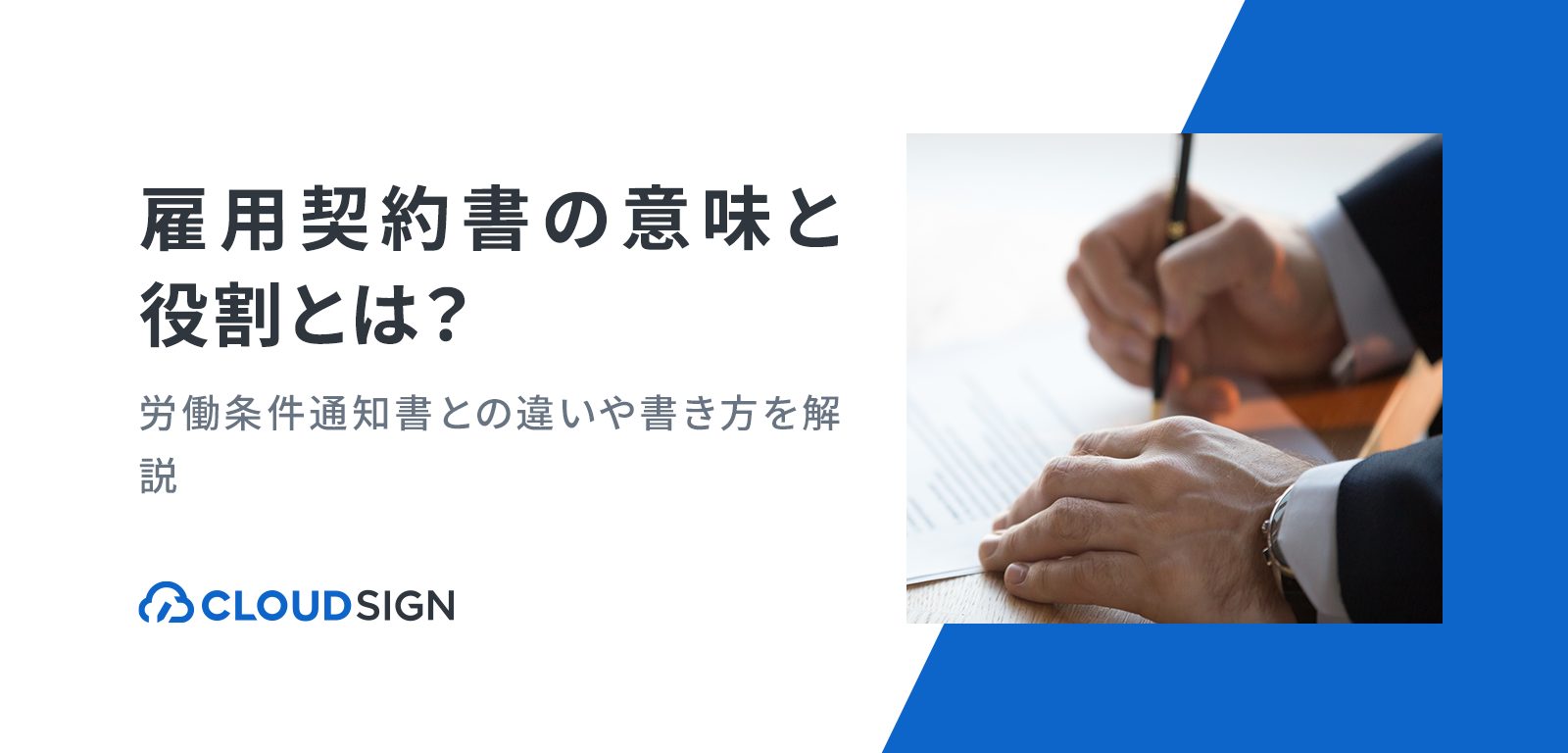
雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや書き方と記載項目を解説
雇用契約 -
電子契約の運用ノウハウ

なぜ今「人事労務に電子契約」か?雇用契約を電子化するメリットと実務的Q&Aを解説
雇用契約人事労務