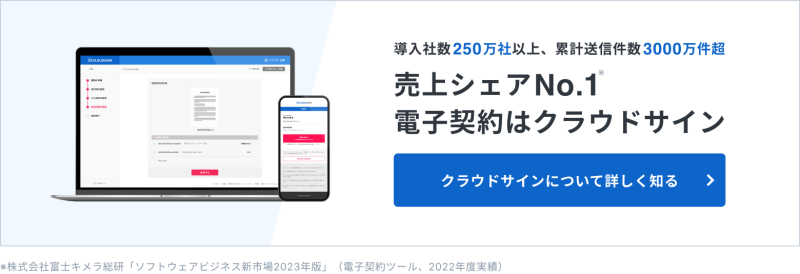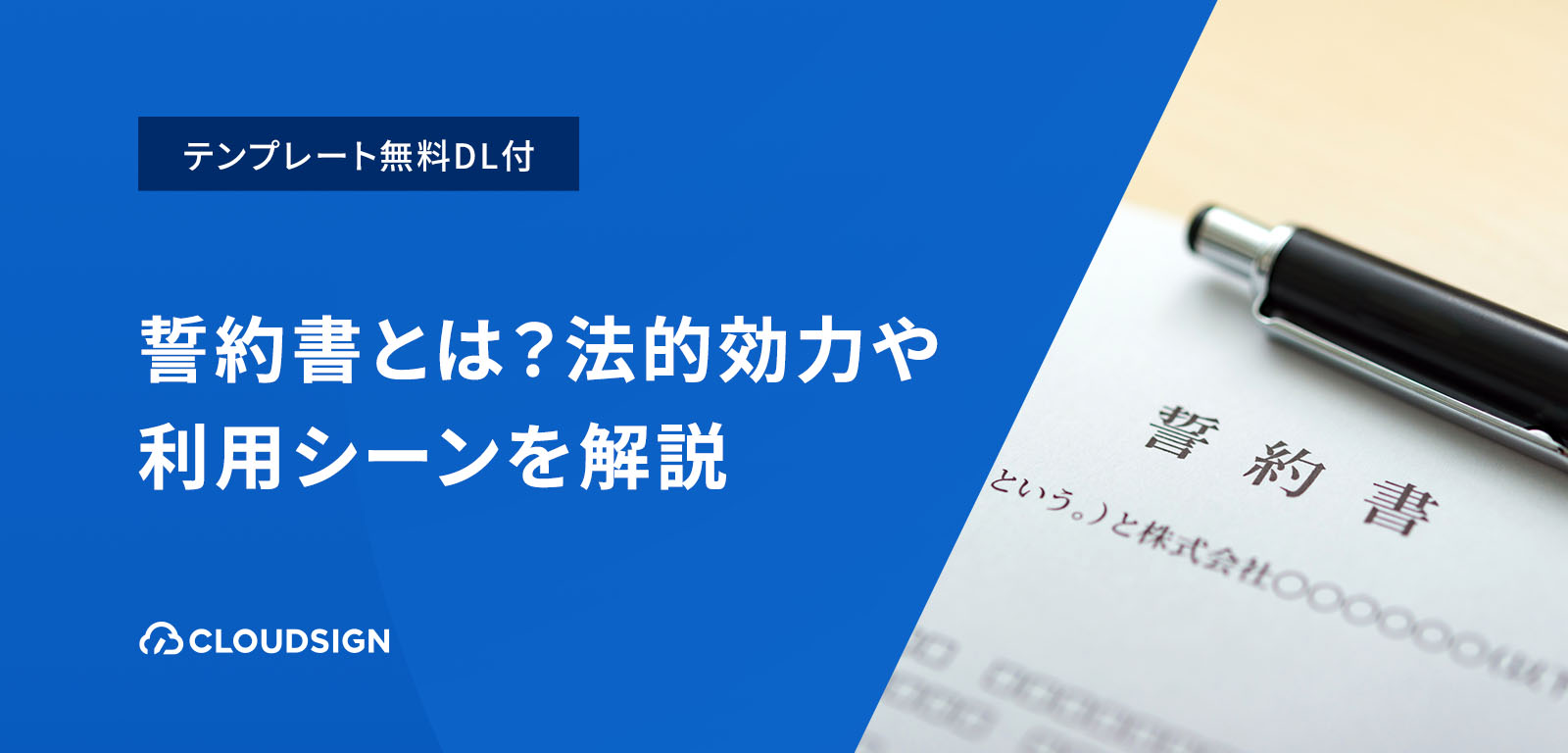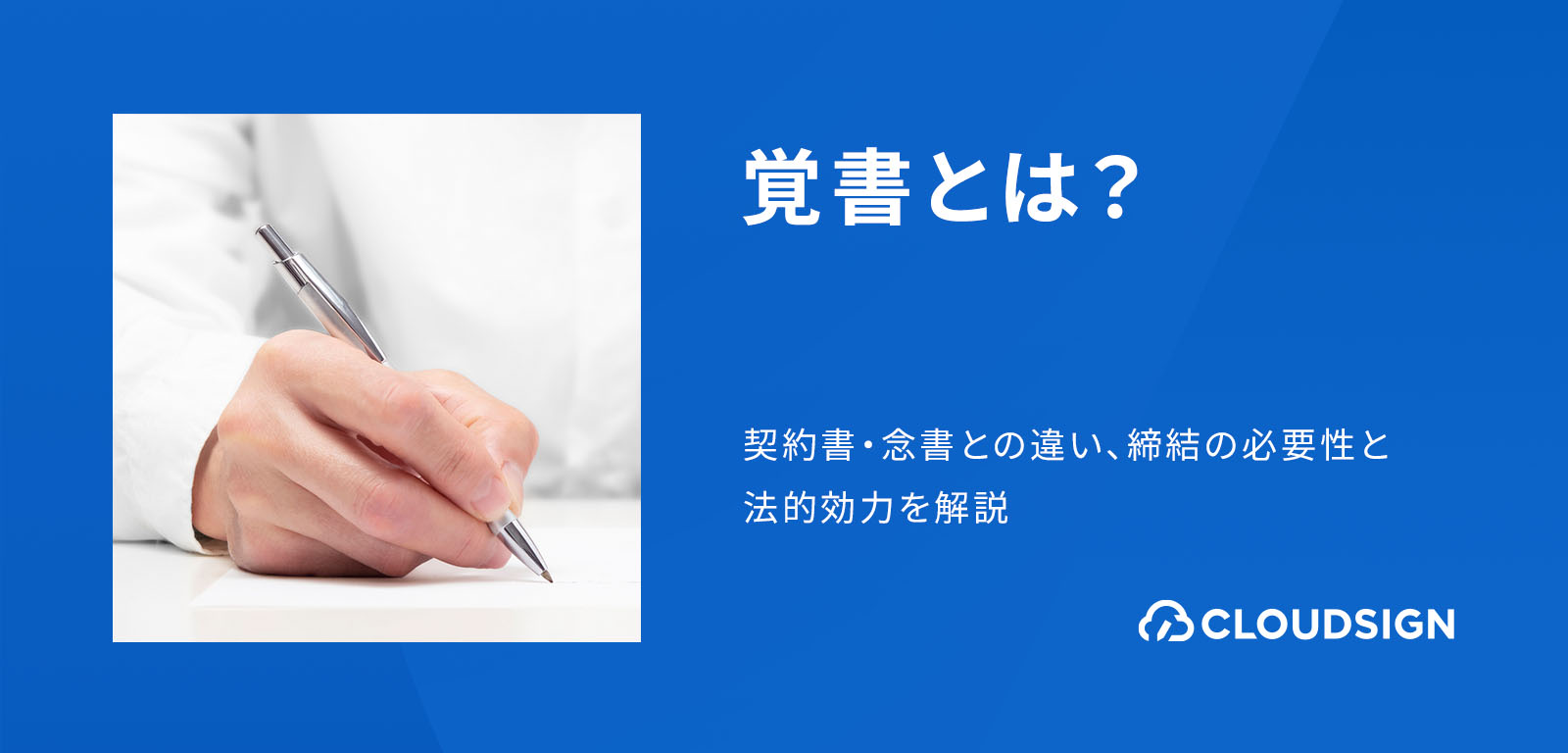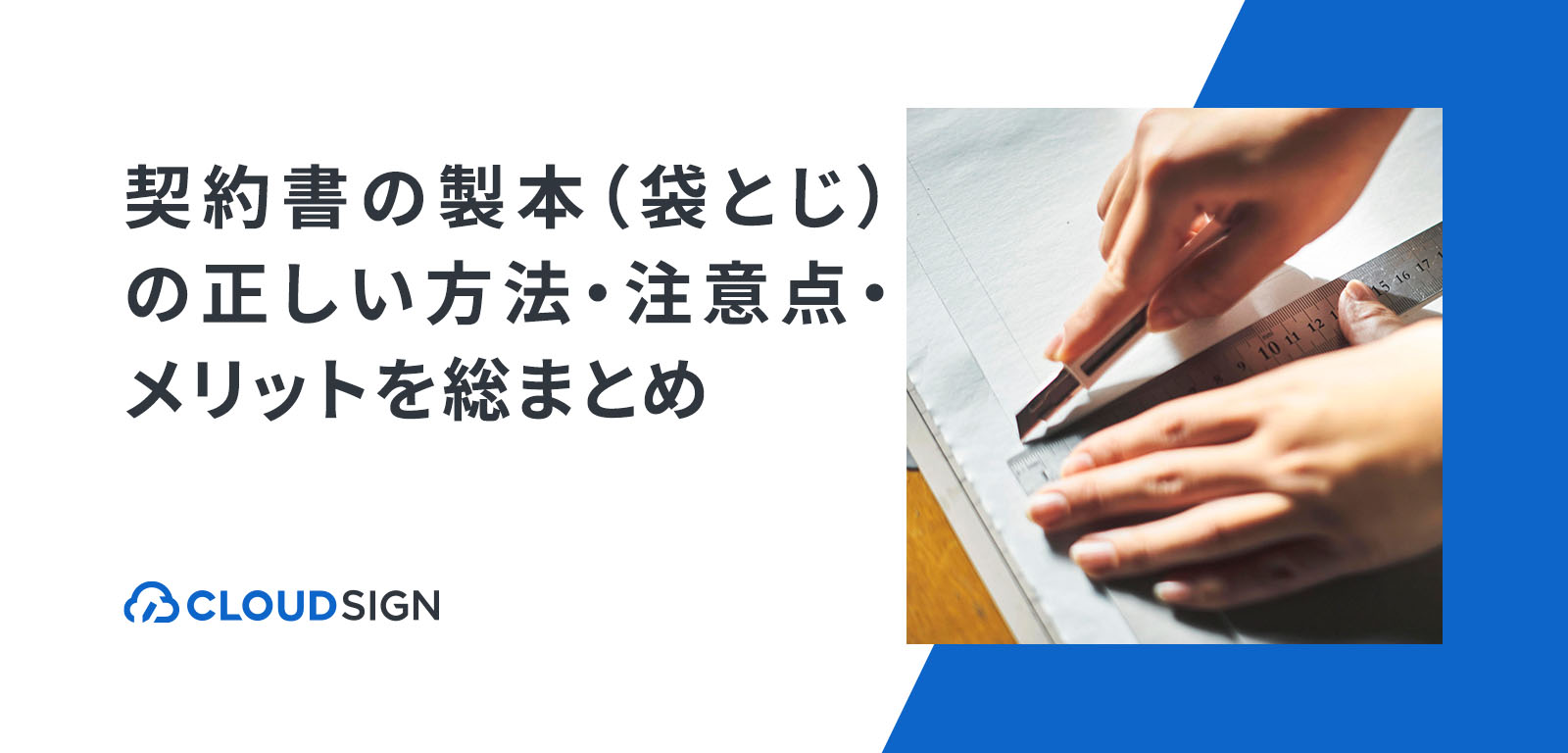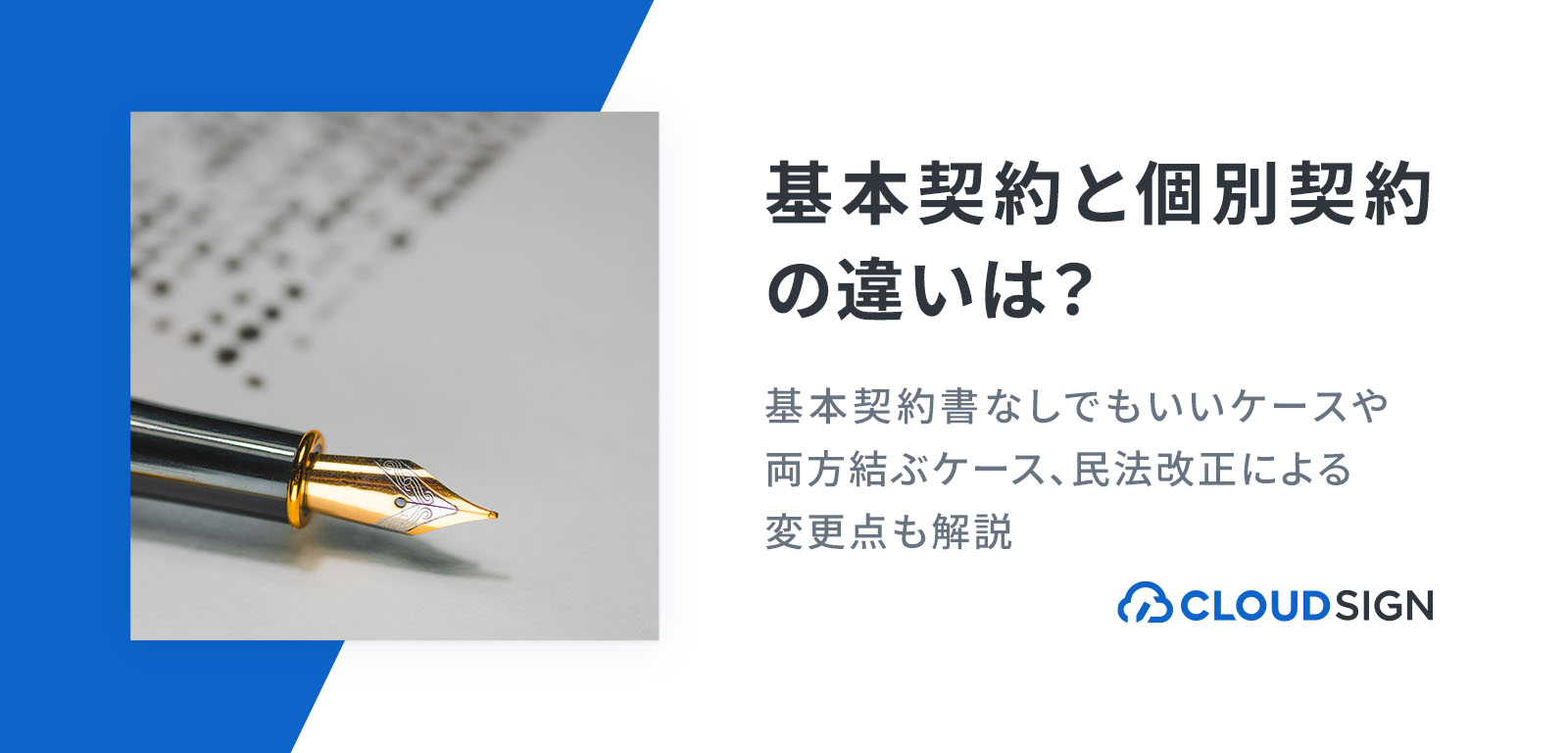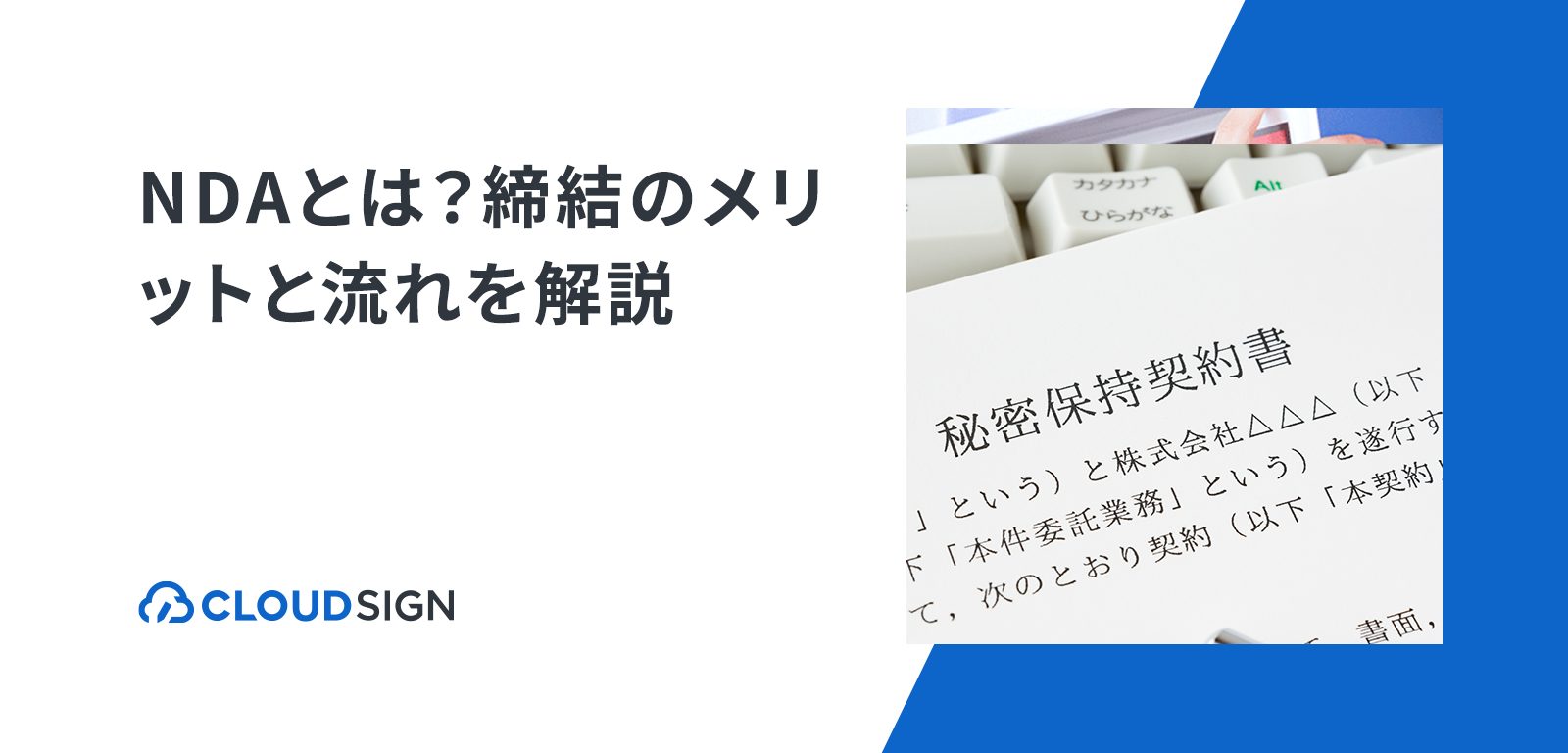契約書の書き方|作成手順や全体的な構成、作成時の注意点などを解説
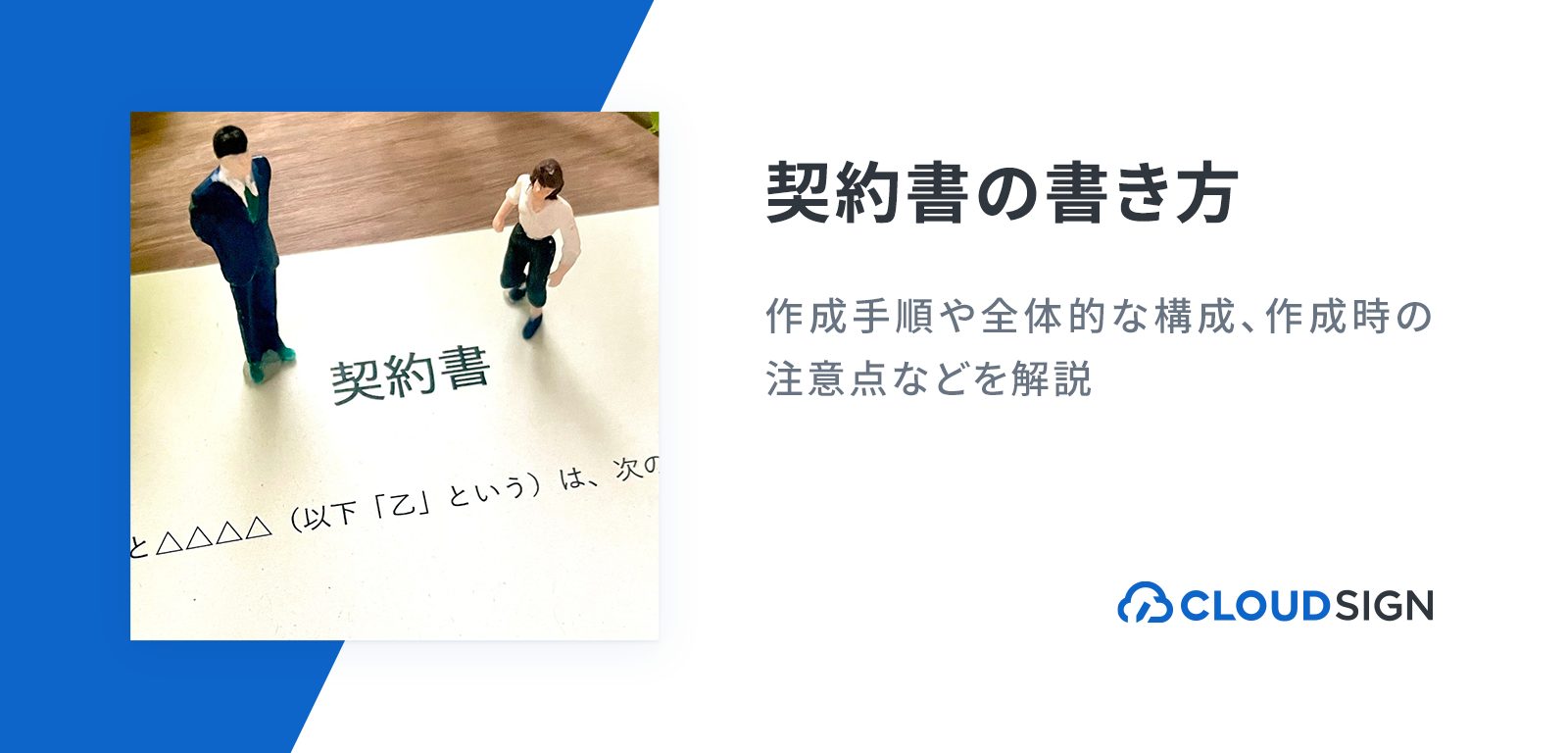
契約書は、取引を行う当事者同士の合意内容を明確化する重要な書面です。契約トラブルによって予期せぬ損害を被る事態を防ぐためにも、内容をよく検討したうえで契約書を作成しましょう。
本記事では契約書の書き方について、作成手順や全体的な構成、作成時の注意点などを解説します。
なお、クラウドサインでは「知っておくべき紙の契約書マナー」を解説するマナーBOOKをご用意しております。印刷・製本・郵送に関する情報をまとめていますので、気になる方はぜひ下記フォームからダウンロードのうえ、ご活用ください。
無料ダウンロード

この資料では「知っておくべき紙の契約書マナー」を解説します。取引先との良好な信頼関係を築くために知っておきたい、紙の契約書の印刷・製本・郵送に関わる知識やマナーを解説しますので、気になる方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。
ダウンロードする(無料)契約書とは
「契約書」とは、取引などに関する当事者間の合意内容をまとめた書面です。個人事業主や会社が事業に関する合意をするときは、契約書を作成することが推奨されます。
契約書を作成する目的
契約書を作成することの主な目的は、取引の条件や業務のフローなどを明確化するとともに、将来のトラブルに備えることです。
取引に関する合意は、法律上「契約」と呼ばれています。契約は口頭の合意によっても成立しますが、口頭では細かい条件を具体的に取り決めることや、当事者間の認識のずれを完全に解消することは困難です。
契約書を作成すれば、当事者間で取り決めた細かい条件を、漏れなく文章として残すことができます。ドラフト(草案)について契約交渉を行う過程で、当事者間の認識のずれも解消され、契約関係が安定します。
また契約書には、将来トラブルが発生した際の処理手順や解決基準も書き込むことができます。これらの事項をあらかじめ定めておけば、トラブルの複雑化を防ぎやすく、予期せぬ損害を被るリスクも抑えられます。
契約書と覚書・誓約書の違い
契約書と並び、取引などについて作成される文書としては「覚書」や「誓約書」などが挙げられます。
「覚書」は契約書と同じく、取引当事者の間の合意内容をまとめた法律文書です。名称は異なりますが、契約書と覚書の法的な位置づけは同じで、実質的な違いはありません。
ただし覚書は、比較的簡潔な内容の合意をする場合や、すでに締結している契約書を補完する内容の合意をする場合などに作成されるケースが多いです。
「誓約書」は、取引の一方当事者が、相手方に対して何らかの事項を誓約する書面です。たとえば、秘密保持に関する誓約書などが挙げられます。
契約書や覚書は当事者双方が共同で作成するのに対し、誓約書は提出者が単独で作成するものです。
契約書の書き方|作成手順を紹介
契約書を作成する際の全体的な流れは、大まかに以下のとおりです。
(1)取引の主要な条件を決める
(2)契約書のドラフトを作成する
①自分でゼロから条文を作成する
②テンプレートをベースに調整する
③弁護士や行政書士に依頼する
(3)契約交渉をする
(4)調印する
次項から、各手順を細かく確認していきましょう。
(1)取引の主要な条件を決める
まずは取引の相手方と話し合い、取引の主要な条件を決めます。たとえば業務委託契約を締結するときは、委託する業務の内容や報酬などを決めておきます。
細かい取引条件の交渉は、契約書のドラフト上で行えばよいので、この段階では大まかな条件を決めておけばよいでしょう。
(2)①自分でゼロから条文を作成する
取引の主要な条件を決めたら、実際に契約書のドラフトを作成します。契約書のドラフトは、契約交渉のたたき台となるものです。
契約書のドラフトを作成する際には、自分でゼロから条文を作成することも考えられます。しかし法律や契約、詳細な取引条件についての知識がなければ、適切に条文を作成することは難しいです。基本的には、自分でゼロから条文を作成することはお勧めできません。
(2)②テンプレートをベースに調整する
過去に同種の取引を行ったことがある場合は、その際に締結した契約書をベースにしてドラフトを作成するのが便利です。手間が省けるうえに、過去の取引との整合性を保つことができます。
また、インターネット上に掲載されている同種の契約書のテンプレートや、生成AIツール(ChatGPTなど)が出力したテンプレートをベースにドラフトを作成することも考えられます。
ただし、テンプレートが取引の実態に適しているとは限りません。テンプレートをそのまま利用すると、必要な事項の定めが漏れていたり、不適切な条項が残ってしまったりして、予期せぬ結果を招くおそれがあるので注意が必要です。
テンプレートを用いる際には、実際に行う取引と照らし合わせて、内容を適切に調整することが求められます。
(2)③弁護士や行政書士に依頼する
契約書のドラフト作成を専門家に依頼するなら、依頼先は弁護士または行政書士となります。
契約書の作成に関する弁護士と行政書士の違いは、複雑な事柄についての相談を受けられるか否かの点です。
弁護士には、契約書の内容が決まっていない場合や、高度な法律的検討を要する場合でも依頼できます。
これに対して行政書士は、すでに契約内容の大部分が決まっていて、それを契約書にまとめてもらえば足りるという場合に限って依頼できます。
契約書の作成依頼にかかる費用は、弁護士だから高い、行政書士だから安いとは限らず、依頼先の事務所によって異なります。事前に見積もりを取得し、必要に応じて比較したうえで依頼先を決めましょう。
(3)契約交渉をする
契約書のドラフトが出来上がったら、そのファイルを当事者同士でやり取りして、細かい契約条件を詰めていきます。
意味が不明確な内容や、自社が不当な不利益を被るおそれのある内容が含まれている場合は、理由を示して修正を求めましょう。
契約交渉に関するコメントのやり取りは、Wordファイルの変更履歴やコメント機能を用いて行う例がよく見られます。
(4)調印する
交渉を通じて契約の内容が固まったら、最終版のファイルを作成し、当事者双方が調印します。
契約書の調印方法は、紙の契約書を作成する場合と、電子契約を締結する場合で異なります。
紙の契約書を作成するときは、最終版のファイルの印刷物を、当事者の数と同じ部数準備します。複数ページに及ぶ場合はバラバラにならないように、ホチキス止めまたは袋とじによって製本を行うのが一般的です。
印刷した契約書の調印ページに、当事者双方が調印します。当事者が個人の場合は署名と押印を行い、法人の場合は名称をあらかじめ印字したうえで押印を行うのが通例です。
また、ホチキス止めで製本した場合はページ間にまたがるように、袋とじで製本した場合は袋とじ部分に割印を押すと、ページの抜き取りなどのリスクを抑えられます。
電子契約を締結するときは、各種の電子契約サービスを用いるのが便利です。電子署名によって契約の有効性が担保されることに加えて、契約書ファイルの管理もしやすいという利点があります。
締結した契約書は、必要なときに参照できるように、整理した状態で保管しておきましょう。
契約書の全体的な構成
契約書の全体的な構成は、以下のとおりです。
②本文|取引の条件を詳しく記載する
③後文|契約書の部数と保有者を記載する
④調印欄|日付・当事者・署名押印など
⑤別紙|細かい条件などを本文から切り出す
次項で各項目に記載する内容を確認しておきましょう。
なお、基本契約と個別契約の違いを知りたい方は下記記事も参考にしてみてください。
タイトル・前文|基本的な情報が分かるように記載する
契約書の冒頭には、タイトル(表題)を記載します。たとえば「売買契約書」「建物賃貸借契約書」「業務委託契約書」「秘密保持契約書」などが挙げられます。契約書の内容を一言で言い表したタイトルを付けましょう。
タイトルの直後には、前文を記載します。
前文は、契約書に関する基本的な情報を明らかにするものです。具体的には、当事者の氏名(名称)や取引の内容、契約締結日などを明記します。
○○(以下「甲」という。)と△△(以下「乙」という。)は、……の取引に関して、×年×月×日付で、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本文|取引の条件を詳しく記載する
前文に続いて、契約書の本文を記載します。
本文には、契約の対象となる取引の具体的な条件を条文形式で定めます。定めるべき事項は取引の内容によって千差万別なので、個別の検討を要します。
本文の条文は「条」「項」「号」などとレベルを分けて記載するのが一般的です。
第1条(委託業務の内容)
1. 甲は乙に対して以下の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)……
(2)……
2. 本件業務の追加、変更及び削除は、甲乙間の合意により行うものとする。
上記は業務委託契約書を想定した条文例です。「条(=第1条)」「項(=1.2.)」「号(=(1)(2))」とレベルを分けて記載しています。
後文|契約書の部数と保有者を記載する
本文をすべて記載したら、その後に後文を記載します。
後文に記載する事項は、契約書の部数や保有者などです。たとえば、以下のように記載します。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印又は署名捺印の上、各自1通ずつを保有する。<電子契約の後文例>
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙それぞれ電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
調印欄|日付・当事者・署名押印など
契約書の調印欄は、後文の直後に設けるのが一般的です。
調印欄には、契約締結日と当事者の情報を明記します。当事者の情報として必要なのは、個人の場合は住所と氏名、法人の場合は住所・名称・代表者の肩書と氏名です。
契約書の有効性を担保するため、調印欄には署名や押印を行いましょう。通例では、個人は氏名を自書したうえで押印し、法人は名称をあらかじめ印字したうえで押印を行います。
別紙|細かい条件などを本文から切り出す
契約書には別紙を付けることがあります。
別紙には、本文として書くには細かすぎる条件を切り出して定めるケースが多いです。別紙に切り出すことで、本文が読みやすくなる利点があります。
別紙を付ける場合は、本文の条文において、別紙を参照する旨を定める必要がある点に留意しましょう。
本契約に基づいて乙が製作すべき製品の仕様は、別紙1に定めるところによる。
契約書を作成する際の注意点
契約書を作成する際には、特に以下のポイントに注意しましょう。
明確な文言で記載する|曖昧だとトラブルの原因になるので要注意
契約書の条文は、明確な文言で記載することが大切です。
日本語としての意味が不明確な文言や、2通り以上の意味に解釈し得る文言が残っていると、契約トラブルの原因になります。条文を隅々までチェックして、曖昧な文言があれば修正しましょう。
自社のリスクを考慮する|不当な条項は修正を求めるべき
法律上の原則や実務慣行などに照らして、自社が不当に不利と思われる条項や、実務上対応困難と思われる条項が含まれている場合は、理由を示して修正を求めましょう。
1. 乙は、甲から本件製品の納品を受けたときは、当該納品の日の翌日(以下「検品期日」という。)までに検品を行い、その結果を甲に通知しなければならない。
2. 検品期日までに、前項に基づく検品結果の通知が甲に到達しないときは、当該本件製品は検品に合格したものとみなす。乙のコメント:納品日の翌日までに検品を完了することは、業務の状況等によっては困難な場合があります。検品期日は納品日の1週間後とさせてください。
修正コメントの理由は、合理的かつ明確に示すことが大切です。現場担当者とも必要に応じて連携し、適切な内容になるまで相手方とコメントをやり取りしましょう。
バックデートはできる限り避ける
契約締結日を、実際に契約書を作成した日よりも後の日付とすることは「バックデート」と呼ばれています。たとえば、すでに始まっている取引について後から契約書を作成する場合などには、バックデートを行うケースが見られます。
しかしバックデートを行うと、契約締結の経緯が不明確となり、トラブルの原因になるおそれがあります。基本的にはバックデートを避け、取引開始と同じタイミングで契約書を作成するよう努めましょう。
契約書を作成する前に取引を始めてしまった場合は、バックデートを避けて実際に契約書を作成した日を締結日としつつ、効力発生日を過去に遡らせる方法が考えられます。
本契約は、×年×月×日(=契約締結日より前の日)に遡って効力を生じるものとする。
収入印紙が必要かどうか確認する
契約書の種類によっては、締結時に収入印紙を貼る必要があります。
印紙税法の第1号文書から第20号文書までのいずれかに該当する場合は、収入印紙の貼付が必要です。各文書の具体的な種類は、国税庁のウェブサイトに掲載されています。
参考:「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」(国税庁)
参考:「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(国税庁)
なお、収入印紙を貼る必要があるのは、紙の契約書を作成する場合のみです。電子契約を締結する場合は、契約内容にかかわらず、収入印紙を貼る必要はありません。
契約書は電子契約サービスで送信・締結がおすすめ
当記事では、契約書の書き方を詳しく解説してきました。契約書を作成した後は、電子契約サービスで送信〜締結を進めるのがおすすめです。電子契約サービスとは、これまで紙と印鑑で行っていた契約を電子データで締結・管理する仕組みのことを指します。
電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを付与し、本人による作成と非改ざん性を証明するもののため安全性も高く、電子署名法に基づき、紙の契約書と同等の法的効力が認められているものです。
面倒な印刷や製本、郵送や保管といった一連の事務処理が不要になるため、最近では契約締結までのリードタイム短縮や、締結後の管理の効率化のために物流業で導入する企業が増えています。
なお、契約書の電子化は、企業全体の業務効率化やリスク管理に大きく貢献する一方で、一元化された業務フローの策定や、適切なセキュリティ対策など、運用上の注意点は複数存在します。
そのため、信頼性の高い電子契約サービスを利用すれば、スムーズなDX化が実現するはずです。電子契約サービス「クラウドサイン」はPDFのアップロードとメール送信のみで契約締結までの作業を完了することができ、取引相手に負担をかけずに電子契約の導入が可能です。契約書の電子化を考えている場合は、ぜひクラウドサインの利用を検討してください。
クラウドサインのサービス詳細や特徴を知りたい方は以下のリンクからサービス説明資料をダウンロードしてご検討ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)まとめ
契約書は重要度の高い文書であるため、作成に当たっては注意深い検討を要します。
契約内容が取引の実態に沿っているか、自社が大きすぎるリスクを負うことにならないかなどの観点から、ドラフトの作成や契約交渉を慎重に進めましょう。
この記事の監修者
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部