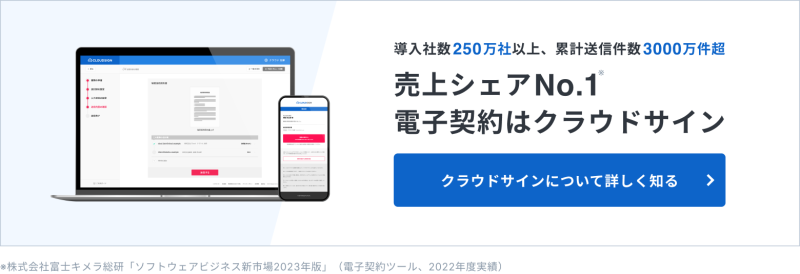雇用契約とは?請負や業務委託などとの違いや締結の手順・注意点などを弁護士が解説
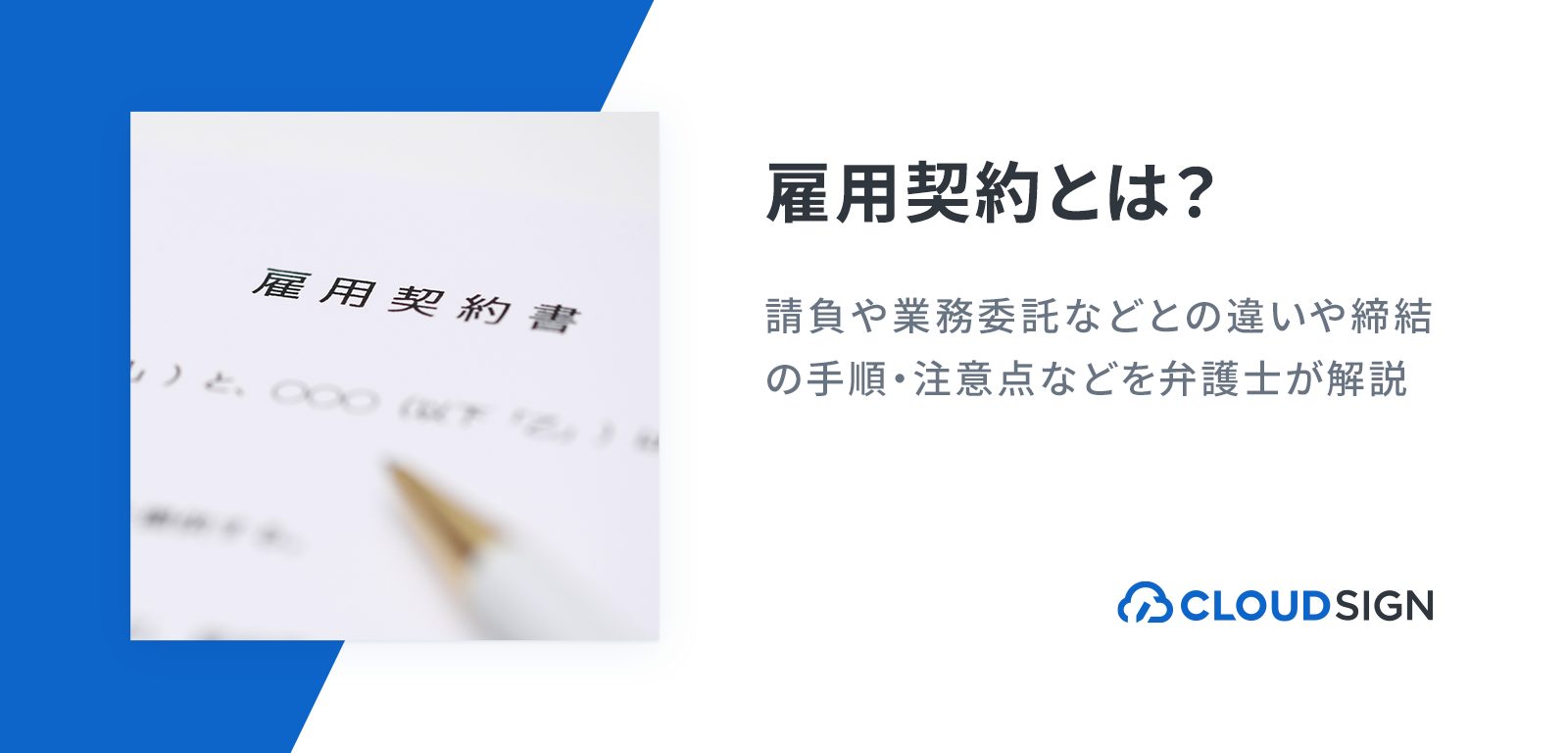
雇用契約は、企業などの使用者が労働者(従業員)を雇用する際に締結する契約書です。請負や業務委託などとは異なり、使用者が労働者に対して指揮命令権を行使できる点に特徴があります。
雇用契約には、労働基準法をはじめとする各種の労働法令が適用されます。企業は法令のルールを踏まえつつ、従業員とのトラブルのリスクを抑えられるように、雇用契約の内容を慎重に検討しましょう。
本記事では雇用契約について、請負や業務委託などとの違い、締結の手順や注意点などを弁護士が解説します。
ひな形無料ダウンロード


クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)雇用契約とは
「雇用契約」とは、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約する契約です(民法623条)。当事者のうち、労働をする側は「労働者」、労働に対して報酬を支払う側は「使用者」と呼ばれます。
企業などが従業員を入社させる場合は、雇用契約を締結するのが一般的です。企業は使用者、従業員は労働者に当たります。
雇用契約を締結した労働者(従業員)は、使用者(企業など)の指揮命令下で働き、使用者から賃金を受け取ります。
雇用契約と他の契約類型との違い
個人が企業のために業務を行うのは、雇用契約を締結している場合に限りません。締結している契約の種類は「請負契約」「委任契約」「準委任契約」「業務委託契約」などの場合もあります。
また、雇用契約と類似した言葉として「労働契約」も用いられています。
これらの契約類型と、雇用契約がどのように違うのか(あるいは同じであるのか)を解説します。
| 業務を行う側の義務 | 当事者間の指揮命令関係 | 労働法令の適用 | |
| 雇用契約(=労働契約) | 労働(=使用者の指揮命令下で業務を行うこと) | あり | あり |
| 請負契約 | 仕事の完成 | なし | なし |
| 委任契約 | 法律行為をすること | なし | なし |
| 準委任契約 | 法律行為でない事務を行うこと | なし | なし |
| 業務委託契約 | 仕事の完成、または業務を行うこと ※契約内容による |
なし | なし |
雇用契約と請負契約の違い
「請負契約」は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約です(民法632条)。仕事を完成する側は「請負人」、報酬を支払う側は「注文者」と呼ばれます。
建設工事やコンテンツ制作など、何らかの成果物を生み出す仕事を委託する場合には、請負契約が締結されます。
雇用契約と請負契約の違いは、主に以下の3点です。
雇用契約の労働者の義務は、使用者の指揮命令下で業務を行うことです。業務を行うだけで足り、仕事を完成させることまでは要求されません。これに対して、請負契約の請負人は、契約で定められた仕事を完成させる義務を負います。たとえば、建物の建設工事請負契約であれば、工事を完了して建物を完成させることが「仕事の完成」に当たります。②当事者間の指揮命令関係
雇用契約の労働者は、使用者の指揮命令に服する義務を負います。たとえば、勤務時間や業務の進め方を具体的に指示されたり、人事異動を命じられたりした場合は、原則としてそれに従わなければなりません。就業規則などで定められる服務規程も適用されます。これに対して、請負契約の請負人は、注文者の指揮命令に服する義務を負いません。注文者と請負人は対等であり、請負人は業務を行う時間や進め方などを自由に決められます。注文者が定めている服務規程も、請負人には適用されません。③労働法令の適用
雇用契約の労働者は、労働基準法などの労働法令によって保護されます。労働者は使用者の指揮命令に服し、使用者よりも弱い立場にあると考えられるためです。
たとえば労働条件の最低ラインや、不当解雇の無効などが適用されます。
これに対して、請負契約の請負人には労働法令が適用されません。請負人と注文者と対等であり、労働法令によって保護する必要はないと考えられるためです。
雇用契約と委任契約・準委任契約の違い
「委任契約」は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを受託して法律行為をする内容の契約です(民法643条)。委託する側は「委任者」、受託して法律行為をする側は「受任者」と呼ばれます。
たとえば、弁護士に訴訟の提起を依頼する場合は委任契約を締結します。
「準委任契約」は、当事者の一方が法律行為でない事務を相手方に委託し、相手方がこれを受託して事務を行う内容の契約です(民法656条)。委任契約と同じく、委託する側は「委任者」、受託して事務を行う側は「受任者」と呼ばれます。
たとえば、システムの保守に関する客先常駐については準委任契約を締結します。
委任契約と準委任契約は、受委託する行為・事務の内容が異なるだけで、基本的には同じルールが適用されます。
雇用契約と委任契約・準委任契約の違いは、主に以下の2点です。なお、仕事を完成する義務を負わない点は、雇用契約と委任契約・準委任契約で共通しています。
雇用契約の労働者は、使用者の指揮命令に服します。これに対して、委任契約・準委任契約の受任者は、委任者の指揮命令に服する義務を負いません。②労働法令の適用
雇用契約の労働者には、労働基準法などの労働法令が適用されます。
これに対して、委任契約・準委任契約の受任者は、委任者と対等であるため、労働法令が適用されません。
雇用契約と業務委託契約の違い
「業務委託契約」は、当事者の一方が相手方に何らかの業務を委託し、相手方がこれを受託してその業務を行う契約です。委託する側は「委託者」、受託して業務を行う側は「受託者」と呼ばれます。
雇用契約・請負契約・委任契約・準委任契約などとは異なり、業務委託契約は民法によって定められた契約(=典型契約)ではありません。
業務を外注する契約の名称には「業務委託契約」が広く用いられていますが、具体的な業務の内容や受託者の義務(仕事の完成の要否を含む)などは、契約の定めによって異なります。
したがって、雇用契約と業務委託契約の違いもケースバイケースですが、以下の2点は常に異なります。
雇用契約の労働者は、使用者の指揮命令に服します。これに対して、業務委託契約の受託者は、委託者の指揮命令に服する義務を負いません。②労働法令の適用
雇用契約の労働者には、労働基準法などの労働法令が適用されます。
これに対して、業務委託契約の受託者は、委託者と対等であるため、労働法令が適用されません。
雇用契約と労働契約の違い
「労働契約」は、雇用契約と同じと理解して問題ありません。民法では「雇用(契約)」、労働契約法などの労働法令では「労働契約」の用語が用いられています。
雇用契約と就業規則の関係
労働者を雇用している使用者(企業など)は、雇用契約とは別に「就業規則」を定めることがあります。
就業規則とは、事業場の労働者に共通して適用される事項を定めたものです。たとえば労働条件や労働者が遵守すべき事項(=服務規程)、懲戒処分などが定められます。
雇用契約(労働契約)のうち、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めている部分は無効です(労働契約法12条)。この場合、無効となった部分については就業規則上で定める基準が適用されます。
なお、雇用契約を締結した後で使用者が就業規則を変更しても、それによって労働者の不利益に労働条件を変更することは、労働者と合意しない限り原則として認められません(同法9条)。
ただし例外的に、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ変更が合理的なものであるときは、就業規則の変更による労働条件の不利益変更が認められます(同法10条)。
雇用契約を締結する際の手順
企業が雇い入れようとする労働者と雇用契約を締結するときの手順は、以下のとおりです。
②雇用契約書への調印
労働条件の明示・労働条件通知書の交付
企業が労働者を雇い入れるときは、労働者に対して以下の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条1項・5項)。
(b)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限がある場合は、その上限を含む)
(c)就業の場所、従事すべき業務(これらの変更の範囲を含む)
(d)以下の事項
・始業、終業の時刻
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間
・休日
・休暇
・就業時転換(労働者を2組以上に分けて就業させる場合)
(e)以下の事項
・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。以下同じ)の決定、計算、支払の方法
・賃金の締切り、支払の時期
・昇給
(f)退職(解雇の事由を含む)
(g)以下の事項
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲
・退職手当の決定、計算、支払の方法
・退職手当の支払の時期
(h)以下の事項
・臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)
・賞与
・精勤手当(1か月を超える期間の出勤成績によって支給されるもの)
・勤続手当(1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給されるもの)
・奨励加給または能率手当(1か月を超える期間にわたる事由によって算定されるもの)
・最低賃金額
(i)労働者に負担させるべき食費、作業用品など
(j)安全、衛生
(k)職業訓練
(l)災害補償、業務外の傷病扶助
(m)表彰、制裁
(n)休職
(o)以下の事項(有期労働契約の期間内に、無期転換申込みができるようになる見込みの場合)
・無期転換の申込み
・無期転換後の労働条件に関する、上記(a)と(c)~(n)の事項
(a)~(f)と(o)の事項については、原則として労働者に書面を交付して明示しなければなりません(労働基準法施行規則5条3項・6項)。これは「労働条件通知書」と呼ばれるものです。
ただし労働者が希望した場合に限り、労働条件通知書に記載すべき事項をファクシミリや電子メールなどで明示することもできます。
雇用契約書への調印
雇用契約は口頭でも締結できますが、契約内容を明確化するためには書面(雇用契約書)を作成することが望ましいです。
契約内容を記載したドラフトを準備し、当事者双方が署名と押印(法人の場合は記名と押印)を行って締結しましょう。合意した内容が漏れなく反映されているか、誤りがないかなどをきちんと確認することが大切です。
なお、雇用契約書は電子契約の方式で締結することもできます。紙の契約書に比べて、電子契約は管理がしやすいなどのメリットがあります。
雇用契約に関する注意点
企業が従業員と雇用契約を締結する際には、特に以下に挙げるポイントに十分ご注意ください。
②解雇は厳しく制限されている
③有期雇用の場合は「雇い止め法理」と「無期転換ルール」に注意
④業務委託などが雇用とみなされることもある|偽装請負に注意
労働基準法の最低ラインが適用される
雇用契約に定める労働条件は、最低でも労働基準法に定められた基準以上でなければなりません。労働基準法の基準に達していない労働条件の定めは無効となります(同法13条)。
労働基準法では、以下の事項などについて最低ラインが定められています。企業が雇用契約を締結する際には、これらの事項に関する基準を確認したうえで、それ以上の労働条件を定めましょう。
・労働時間
・休憩
・休日
・有給休暇
など
解雇は厳しく制限されている
労働者をいったん雇用すると、企業側の都合によって解雇することは厳しく制限されます。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効です(労働契約法16条)。
労働者が悪質な非違行為をした場合や、極度の経営不振に陥った場合などを除き、労働者の解雇は難しいと考えておきましょう。
解雇できない労働者に退職してもらうためには、その労働者の同意を得る必要があります。その代償として、企業が多額の解決金を支払うケースも少なくありません。
解雇は難しいことを念頭に置いて、雇用する労働者は慎重に選ぶことをお勧めします。
有期雇用の場合は「雇い止め法理」と「無期転換ルール」に注意
雇用契約には期間を定めることもできますが、その場合は「雇い止め法理」と「無期転換ルール」に注意すべきです。
有期労働契約が過去に反復して更新されており、雇い止め(=使用者が期間満了に伴って有期労働契約を終了させること)が解雇と同視できるなどの条件を満たす場合は、雇い止めが無効となります。②無期転換ルール(同法18条)
有期労働契約の通算期間が5年を超えており、すでに契約が1回以上更新されている労働者には、無期労働契約への転換を申し込む権利が与えられます。使用者は無期転換の申込みを拒否できません。
特に長期間にわたって有期雇用している労働者については、雇い止め法理や無期転換ルールが適用されるかどうかを確認し、適用される場合は対応を検討しましょう。
業務委託などが雇用とみなされることもある|偽装請負に注意
業務委託・請負・委任(準委任)などの名目で業務を外注していても、業務を行う者に対して企業が具体的な指揮命令を行っている場合は、実質的に雇用であるとみなされます(=偽装請負)。
偽装請負に当たる場合は、労働基準法を含む労働法令が適用されるなど、企業にとって予期しない事態を招くおそれがあります。
特に、業務の進め方や時間配分を具体的に指示したり、服務規程の遵守を求めたりすると、偽装請負のリスクが高まる点に十分ご注意ください。
雇用契約締結後に行うべき手続き
雇用契約を締結した後は、雇用した労働者の情報を法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)に記録しましょう。また、社会保険や労働保険の対象となる労働者については、その加入手続きを行う必要があります。
法定三帳簿への記録|労働者名簿・賃金台帳・出勤簿
労働者を雇用する企業は、以下の3つの帳簿(=法定三帳簿)を作成しなければなりません。
日雇い労働者を除くすべての労働者について、氏名・生年月日・雇入れ年月日などの基本的な事項を記載します。②賃金台帳
雇用するすべての労働者について、賃金の支払いに関する事項を記載します。③出勤簿
雇用するすべての労働者について、出勤状況を記載します。
厚生労働省のウェブサイトに掲載されている様式などを参考にして、法定三帳簿をきちんと作成しましょう。
参考:主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)|厚生労働省
社会保険・労働保険の加入手続き|適用要件を要確認
企業が労働者を雇用する際には、その労働者が各種社会保険・労働保険の対象であるかどうかを確認し、対象であれば加入手続きを行いましょう。
使用者が法人である場合、各種社会保険・労働保険の加入要件と手続先は以下のとおりです。
| 加入要件 | 手続先 | |
| 厚生年金保険・健康保険 | 以下の①または②のいずれかに該当すること
①以下のいずれかに該当すること ②以下の要件をすべて満たすこと ※日雇い労働者など、一部例外あり |
日本年金機構 |
| 介護保険 | 40歳以上65歳未満である
※65歳以上の人は介護保険の被保険者となるものの、 |
日本年金機構 |
| 雇用保険 | 以下の要件をいずれも満たすこと ・週の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上継続して雇用される見込みがある ※臨時の日雇い労働者など、一部例外あり |
労働基準監督署
※以下の事業についてはハローワーク |
| 労災保険 | 船員保険の被保険者を除くすべての労働者 | 労働基準監督署 |
電子契約で採用業務の効率化が可能
電子契約の導入により、雇用契約や労働条件通知書といった採用業務に必要な書類を電子化することで、採用時や契約更新時にかかる事務作業の時間を大幅に節約できるようになります。また、紙の書類が発生しないため印刷費や郵送費といったコストも削減することができます。
電子契約サービス「クラウドサイン」であれば、労働者側が電子メール等の電磁的方法による送信を希望すれば、法的要件を満たして労働条件通知書を電子化することが可能です。人事採用業務の効率化を図るために、労働条件通知書と雇用契約書をひとつに統合するという工夫も考えられます。
なお、労働条件通知書兼雇用契約書のひな方をお探しの方は以下のリンクから無料で入手可能ですので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
ひな形無料ダウンロード


クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)
まとめ
雇用契約は、企業などが労働者(従業員)を雇い入れる際に締結します。
請負や業務委託などと異なり、使用者は労働者に対して業務の進め方や時間配分を指定したり、服務規程の遵守を求めたりするなど、具体的な指揮命令権を行使できます。
雇用契約の締結に当たっては、労働基準法の最低ラインが適用される点や、解雇が厳しく制限されている点など、さまざまなポイントに注意しなければなりません。
労働法令のルールを踏まえつつ、労働者とのトラブルをできる限り避けられるように、十分に内容を検討したうえで雇用契約を締結してください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
契約実務
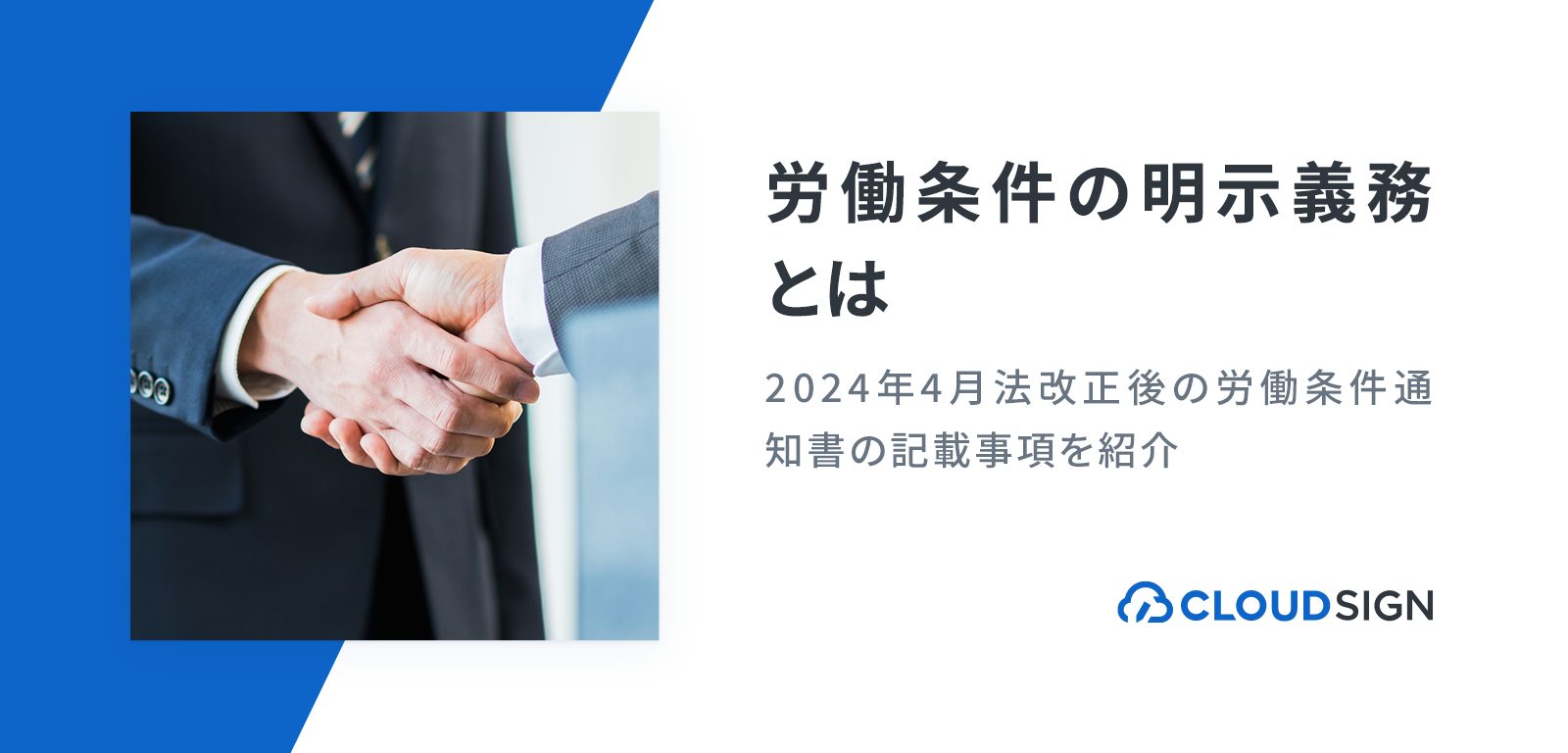
労働条件の明示義務とは|2024年4月法改正後の労働条件通知書の記載事項を紹介
契約書雇用契約人事労務 -
電子契約の運用ノウハウ
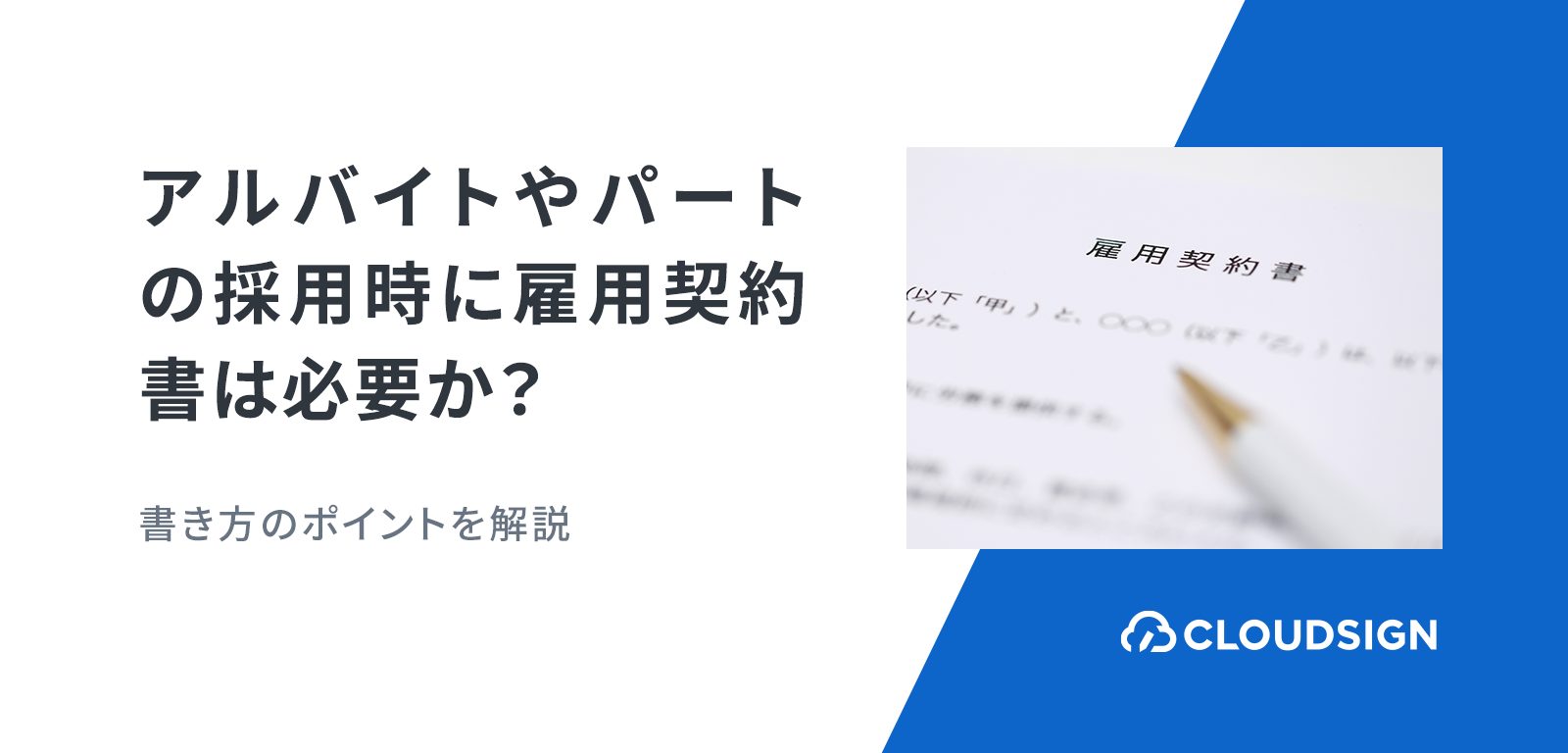
アルバイトやパートの採用時に雇用契約書は必要か?書き方のポイントを解説
雇用契約 -
契約実務
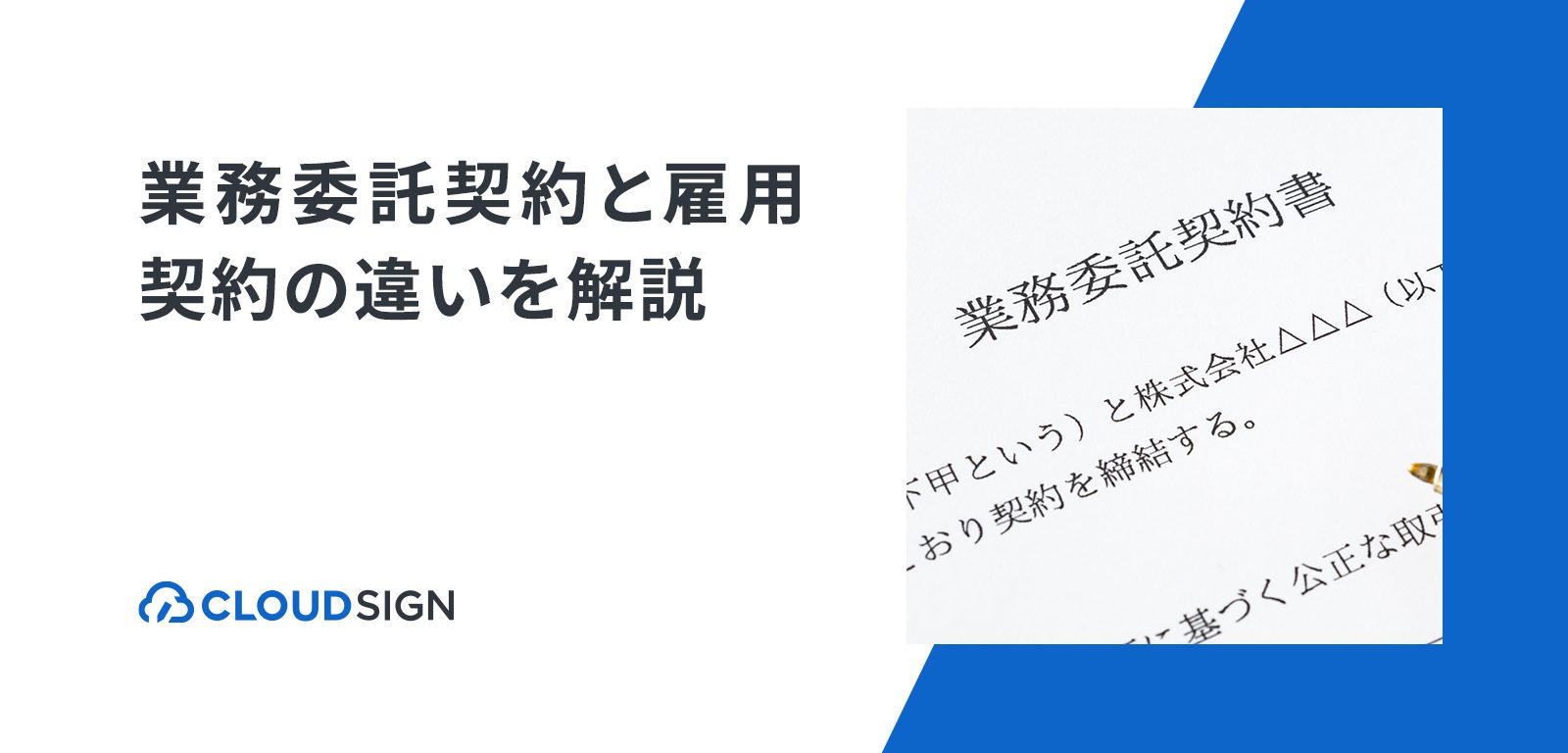
業務委託契約と雇用契約の違いを解説
業務委託契約書雇用契約 -
業務効率化の成功事例まとめ
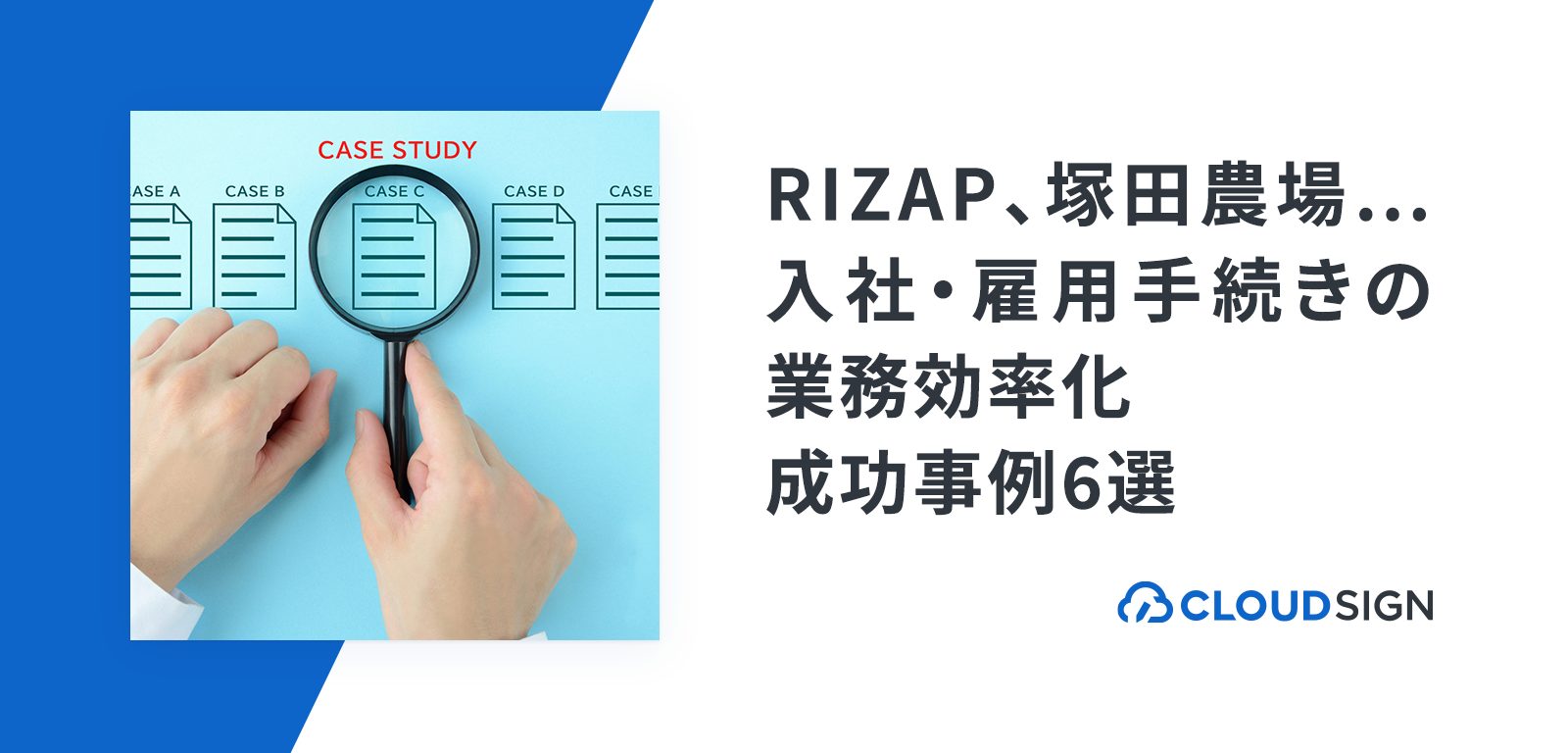
RIZAP、塚田農場…入社・雇用手続きの業務効率化 成功事例6選
インタビュー業務委託契約書電子契約の活用方法電子契約の導入電子契約のメリット雇用契約人事労務業務効率化 -
電子契約の運用ノウハウ

なぜ今「人事労務に電子契約」か?雇用契約を電子化するメリットと実務的Q&Aを解説
雇用契約人事労務