偽装請負とは?具体例・問題点・判断基準・リスク・予防策などを解説
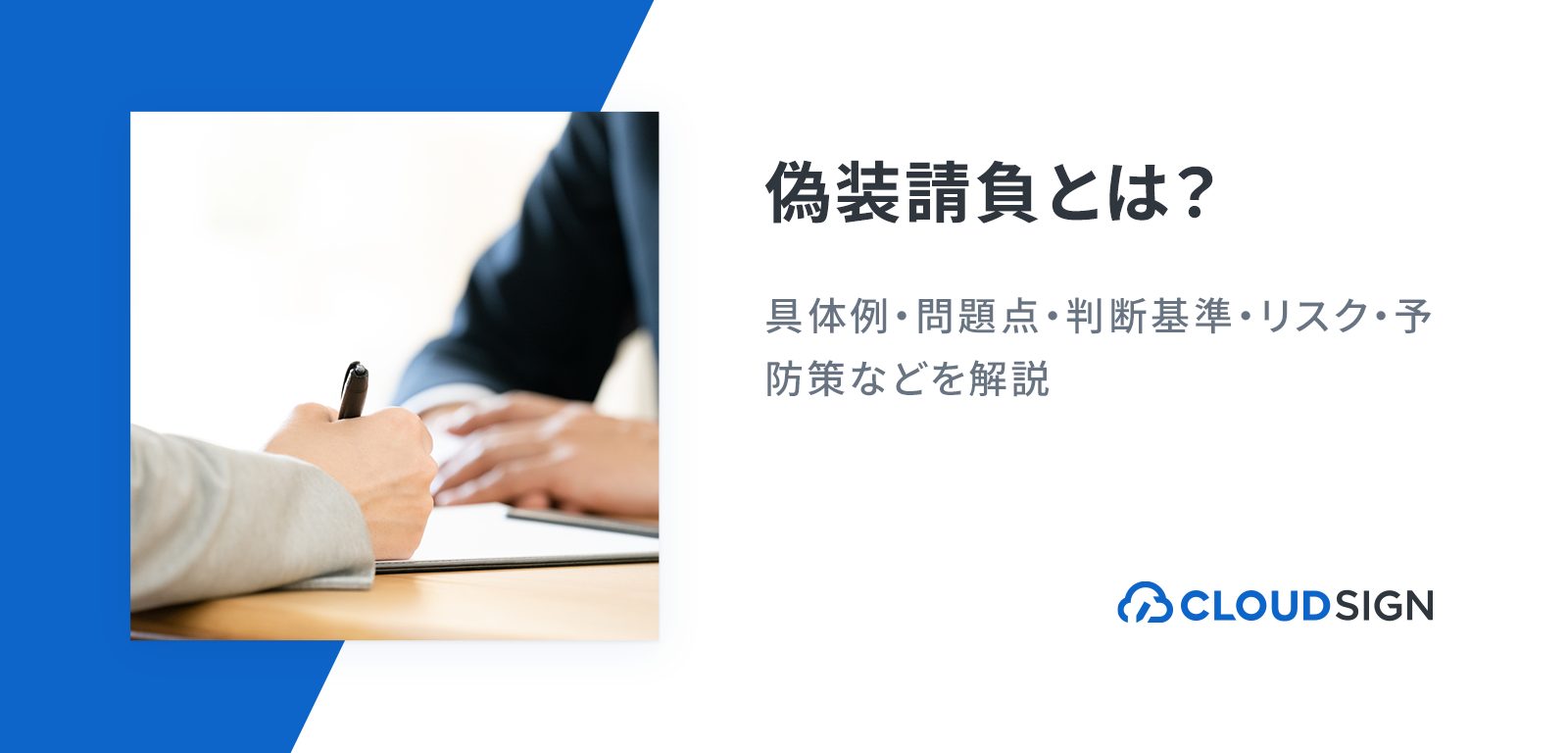
「請負」や「業務委託」の名目で来てもらっている人に対して、自社の従業員と同じように指揮命令を行うと「偽装請負」と判断されるおそれがあります。客先常駐している自社の従業員が、常駐先の指揮命令を受けている場合も同様です。
偽装請負は違法行為に当たり、法的なペナルティの対象となります。契約内容と業務の実態の両面から、偽装請負になっていないかどうかをよく確認しましょう。
本記事では偽装請負について、具体例・問題点・判断基準・リスク・予防策などを解説します。業務委託や請負など、外注先との契約を担当している方は確認しておきましょう。
偽装請負とは
「偽装請負」とは、請負や業務委託などの名目で契約を締結しているにもかかわらず、実質的に労働者派遣または労働者供給となっている状態です。言い換えれば、請負や業務委託によって取引先から来ている人を、あたかも自社の従業員(労働者)であるかのように取り扱うことを意味します。
請負や業務委託の当事者は互いに対等であり、注文者(委託者)が請負人(受託者)に対して具体的な指揮命令を行うことはできません。
もし具体的な指揮命令を行いたいなら、自社の労働者として雇用するか、または他社から労働者派遣をしてもらう必要があります。偽装請負はそれを怠り、業務の実態に反して請負や業務委託などを偽装するもので、違法行為とされています。
偽装請負の具体例
偽装請負の典型例としては、請負や業務委託の名目で来てもらっている他社の従業員に対し、業務の進め方や時間配分を具体的に指示したり、自社の服務規程に従うことを要求したりすることが挙げられます。
請負や業務委託の場合、業務の進め方は請負人(受託者)の裁量によって決めるべきもので、注文者(委託者)が具体的に指示することはできません。
また、服務規定は注文者(委託者)の指揮命令に服する従業員を対象とするものであって、自社と対等である請負人(受託者)の従業員に遵守を強制してはなりません。
上記のような状態が発生している場合は、偽装請負と判断されるおそれがあります。
偽装請負の問題点
偽装請負の問題点としては、主に2点が挙げられます。
1点目は、労働者の待遇が悪化し、または不安定となるおそれがあることです。
たとえば、A社の従業員XがB社の指揮命令下で働くことは「労働者派遣」に当たります。XがB社に直接雇用される場合に比べると、A社がマージン(取り分)を得るため、Xの待遇は低く抑えられてしまいがちです。さらに、A社またはB社の都合によって派遣契約が打ち切られると、Xの意思にかかわらず職場環境が変わるなど、その待遇は不安定になります。
このような弊害のリスクを抑えるため、労働者派遣は労働者派遣法によって規制されています。しかし、請負や業務委託が実質的に労働者派遣である場合は、労働者派遣法を遵守していないことになり、労働者の待遇確保の観点から大いに問題があります。
2点目は、作業従事者が労働法令の保護を受けられないおそれがあることです。
先ほど挙げた労働者派遣の例では、Xは派遣元事業主のA社に雇用される労働者でした。
これに対して、たとえばA社に雇用されているわけではなく、単にA社のデータベースに登録されているだけのYがB社に派遣され、B社の指揮命令下で働くとします。YはA社にもB社にも雇用されていません。このようなケースは「労働者供給」と呼ばれています。
労働者は使用者に対して弱い立場にあることを踏まえ、労働基準法や労働契約法などの労働法令によって保護されています。しかし労働者供給の場合、作業従事者はどの事業主にも雇用されていないので、労働法令の保護を受けることができません。その結果、労働法令の最低ラインを下回る劣悪な条件で働かされるなど、作業従事者が搾取されてしまうおそれがあります。
こうした問題点を避けるため、偽装請負は各種の法律によって禁止されています。
偽装請負を禁止する法律
偽装請負はその実態に応じて、労働者派遣法・職業安定法・労働基準法との関係で違法となります。下記の表で偽装請負を禁止する法律と、各法律で禁止されている違反の内容をまとめましたので、確認しておきましょう。
| 違反する法令 | 違反に当たる場合 |
| 労働者派遣法 | 偽装請負が無許可での労働者派遣に当たる場合 |
| 職業安定法 | 偽装請負が労働者供給に当たる場合 |
| 労働基準法 | 偽装請負が労働者供給による中間搾取に当たる場合 |
偽装請負に該当するかどうかの判断基準
請負や業務委託が偽装請負に当たるかどうかは、契約の定めと現場における職務の実態の両面から判断されます。
契約の定め
契約において、注文者(委託者)と請負人(受託者)の関係性がどのように定められているかは、偽装請負に当たるかどうかを判断するに当たって重要な考慮要素の一つです。
契約の名称が「請負契約」や「業務委託契約」であっても、注文者(委託者)が請負人(受託者)に対して具体的な指揮命令を行う権利を有する場合は、偽装請負と判断されるリスクが高くなります。
反対に、注文者(委託者)は具体的な指揮命令を行わず、業務の進め方などを請負人(受託者)の裁量に委ねる旨を明記しておけば、少なくとも契約の定めから偽装請負と判断されるリスクは低くなります。
現場における職務の実態
契約上は指揮命令関係がない旨が明記されていても、実際の現場で注文者(委託者)が請負人(受託者)に対して具体的な指揮命令を行っている場合は、偽装請負と判断されるリスクが高くなります。
たとえば、注文者(委託者)の管理職などが請負人(受託者)の従業員に対して、業務の進め方や時間配分などを具体的に指示したり、服務規程に従うように要求したりするケースが見られます。
このような指示は、契約上の根拠に基づかず、現場限りの判断で行われている場合が多いです。また、不当な指揮命令を受けた請負人(受託者)の従業員も、そのことについて問題意識を持たず、上司に報告しないケースがしばしば見受けられます。
上記のような事情から、現場で偽装請負の実態が生じていても、注文者(委託者)や請負人(受託者)の経営者はそのことを把握していないケースが多いように思われます。経営者としては、請負や業務委託に関する職務が現場でどのように行われているのか、実態を把握するよう努めなければなりません。
偽装請負に関与した事業者に課されるペナルティ(罰則など)
偽装請負に関与した事業者は、刑事罰や行政処分の対象となるほか、作業従事者に対して残業代の支払義務を負う可能性もあります。
刑事罰
偽装請負に関与した事業主に対しては、以下の罰則が科されることがあります。
| 違反の内容 | 罰則の対象者 | 法定刑 |
| 無許可での労働者派遣 | 派遣元事業主 (請負契約の注文者、または業務委託契約の委託者) |
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(労働者派遣法59条1号)
※法人に対しても、両罰規定により100万円以下の罰金が科されます(同法62条)。 |
| 労働者供給 | 供給元・供給先双方の事業主 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(職業安定法64条10号)
※法人に対しても、両罰規定により100万円以下の罰金が科されます(同法67条)。 |
| 中間搾取 | 供給元の事業主 (請負契約の注文者、または業務委託契約の委託者) |
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働基準法118条1項)。
※法人に対しても、両罰規定により50万円以下の罰金が科されます(同法121条1項)。 |
行政指導・行政処分
法律の規定に違反して偽装請負に関与した事業者は、厚生労働大臣から指導や助言、改善命令等を受けることがあります。改善命令等に従わなかった場合は、公表処分の対象となります(労働者派遣法48条~49条の2、職業安定法48条の2、48条の3)。
上記の行政指導や行政処分を受けると、是正のための対応に多くの労力やコストを要します。また、公表処分に至った場合は、企業としての評判が大幅に低下してしまうおそれがあるので要注意です。
残業代の支払い
請負や業務委託が偽装請負に当たる場合、作業従事者は労働者に該当するため、労働基準法が適用されます。労働基準法では、時間外労働・休日労働・深夜労働をした労働者に対し、各種手当(残業代)を支給することを使用者に義務付けています。
特に問題となるのは、作業従事者が注文者(委託者)と請負人(受託者)のどちらにも雇用されていないケースです。この場合に偽装請負と判断されると、注文者(委託者)と請負人(受託者)のいずれかが、作業従事者に対して残業代の支払義務を負う可能性があります。
作業従事者が労働者に当たらないことを前提として報酬などの条件を定めていたのに、偽装請負によって労働者扱いになると、予期せぬコストが増えてしまいます。また、労働基準法違反によって労働基準監督署から是正勧告を受けるリスクもある点に注意が必要です。
偽装請負を避けるための対策
請負や業務委託によって他社から人材を受け入れるときは、偽装請負の状態が生じないように注意しなければなりません。そのためには、以下のような対策を行いましょう。
契約上、指揮命令関係がないことを明確化する
契約において、注文者(委託者)と請負人(受託者)の間に指揮命令関係がないことを明確化しておけば、契約の定めから偽装請負と判断されるリスクは低くなります。
偽装請負のリスクを避けるためには、たとえば以下のような内容を契約に定めておくとよいでしょう。
・勤務時間を具体的に定めず、請負人(受託者)の裁量に委ねる旨を明記する
・業務の進め方や時間配分などを具体的に定めず、請負人(受託者)の裁量に委ねる旨を明記する
など
現場担当者に対するヒアリングを行う
契約上は注文者(委託者)と請負人(受託者)の間に指揮命令関係がないことが明記されていても、現場の実態で具体的な指揮命令が行われていると、偽装請負と判断されてしまうおそれがあります。
注文者(委託者)と請負人(受託者)の双方の経営者は、現場での職務の実態を把握することが大切です。その方法の一つとして、現場担当者に対するヒアリングを行うことが考えられます。
注文者(委託者)側では現場の管理職、請負人(受託者)側では現場へ派遣されている従業員に対して、指揮命令の有無や職務の状況などを質問するため、定期的に1on1ミーティングなどを行いましょう。
ヒアリングに当たっては、対象者が嘘をついたり、事実を隠したりする可能性にも注意を払う必要があります。対象者の立場を保護する旨を伝えて安心感を与えたり、複数の従業員から事情を聞いて照らし合わせたりする工夫が求められます。
不定期に現場視察を行う
現場担当者に対してヒアリングをするだけでは、現場の実態を十分に把握することは難しく、隠された事実や嘘を見抜けないこともあります。そのため、経営者が自ら現場視察を行い、現場における職務の実態を確認することが望ましいです。
普段からの職務の様子を観察するためには、事前に予告せず抜き打ちで、不定期に現場視察を行うのがよいでしょう。そうすれば、現場担当者にも危機意識が生まれて、偽装請負に当たる行為をしにくくなります。
従業員に対して、偽装請負の注意点を理解させる
偽装請負が違法であることや、どのような行為が偽装請負に当たるのかなど十分に理解している従業員は少ないと思われます。
偽装請負のリスクを避けるためには、従業員の偽装請負に対する理解を深めることが欠かせません。定期的に従業員研修を行う、日々の業務の中で上司から注意喚起をするなどの対策を講じましょう。
まとめ
「請負」や「業務委託」の名目で作業に従事する人に対し、自社の従業員であるかのように具体的な指揮命令を行うと、偽装請負と判断されるおそれがあります。たとえば、業務の進め方や時間配分を具体的に指示したり、服務規程の遵守を求めたりすることは、偽装請負に当たる可能性があるので要注意です。
偽装請負のリスクを防ぐには、契約において指揮命令関係がないことを明記するとともに、職務の現場でも具体的な指揮命令が行われないようにすることが大切です。
担当者へのヒアリングや現場視察を通じて職務の実態を把握しつつ、従業員研修を通じて偽装請負のリスクを周知するなどの対策を行いましょう。
なお、電子契約サービス「クラウドサイン」では「業務委託契約書」のひな形(テンプレート)をご用意しました。無料でご入手できますので、業務委託契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方は下記リンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインでは業務の一部を外部に委託する場合に利用できる、弁護士監修の「業務委託契約書」ひな形を作成しました。業務委託契約の締結に今すぐ使えるWord形式のテンプレートをお探しの方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事の監修者
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
契約実務
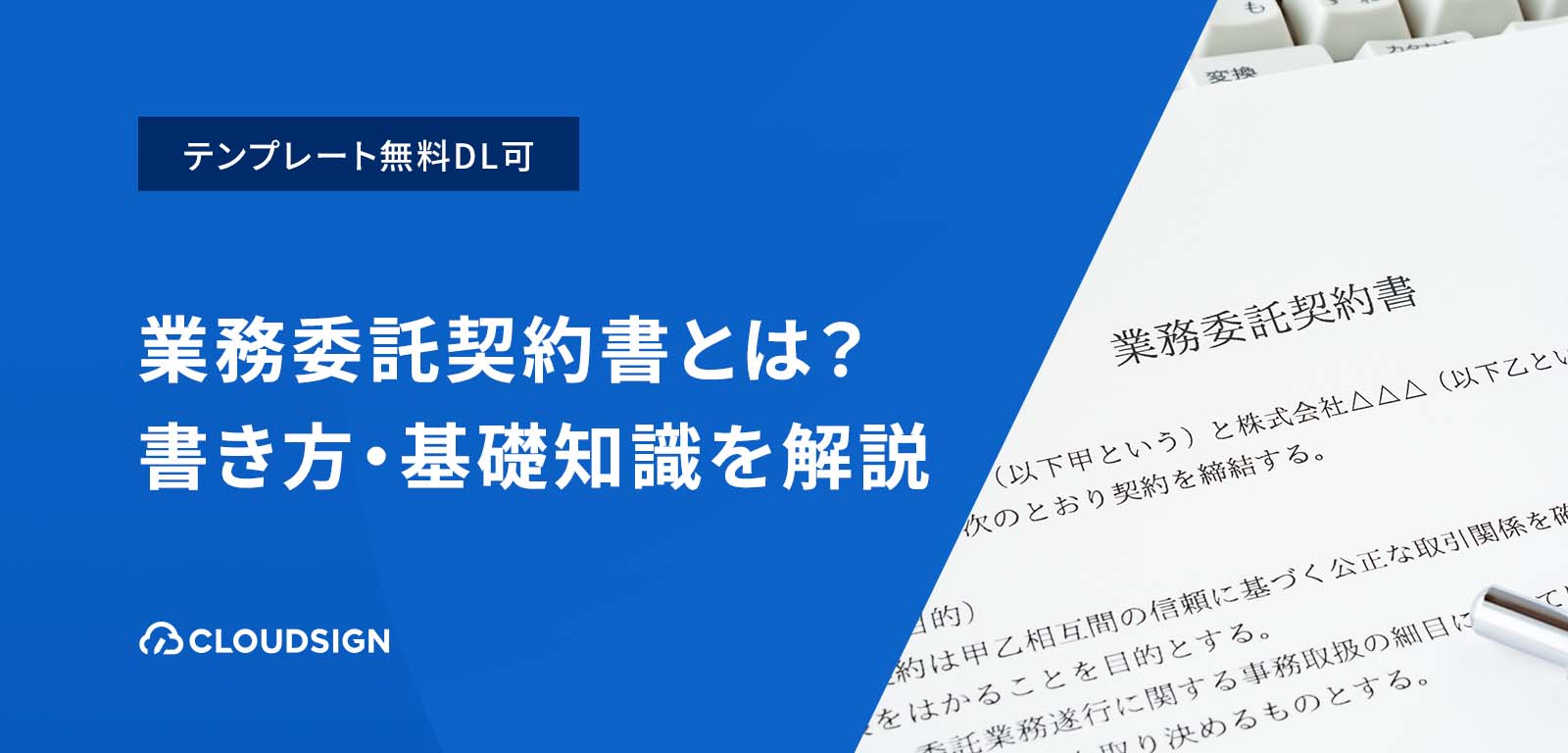
【無料DL可】業務委託契約書とは?テンプレート付きで書き方と基礎知識を徹底解説
コスト削減契約書ひな形・テンプレート業務委託契約書 -
法律・法改正・制度の解説
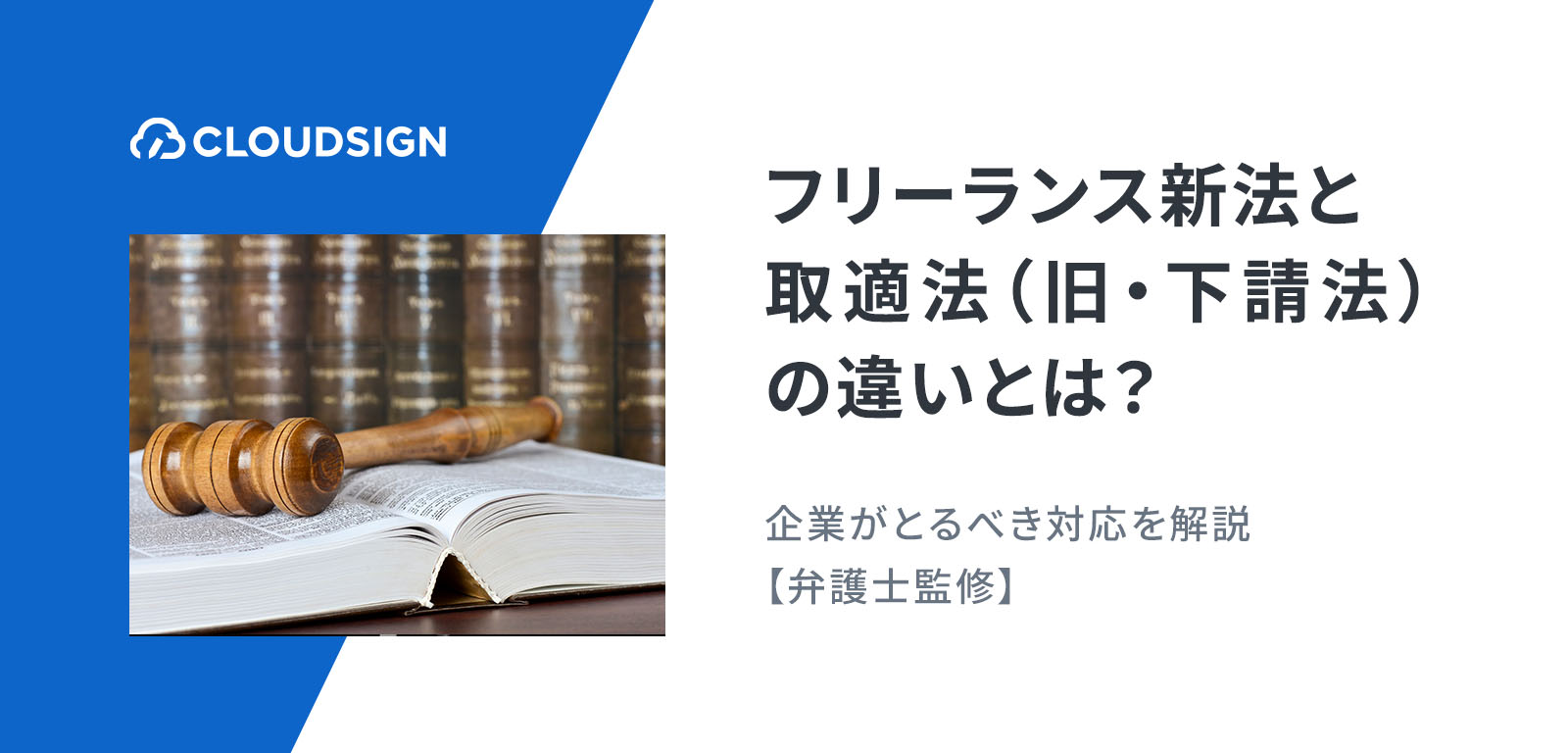
【弁護士監修】フリーランス新法と取適法(旧・下請法)の違いとは?企業がとるべき対応を解説
法改正・政府の取り組み弁護士解説取適法(下請法)フリーランス新法 -
契約実務

工事請負契約書とは?目的や作成のポイント、締結する際の注意点を詳しく解説
契約書契約書ひな形・テンプレート建設業法工事請負契約書請負契約 -
法律・法改正・制度の解説

取適法(旧下請法)改正で「3条書面」は「4条書面」へ。承諾不要などの変更点と契約巻き直し・電子化実務を解説【2026年1月施行】
契約書電子契約の活用方法取適法(下請法)電子契約のメリット業務効率化 -
契約実務

請負契約書に収入印紙は必要?課税文書の判断基準や必要金額を解説
印紙税と収入印紙収入印紙請負契約 -
契約実務

工事請負契約書に収入印紙は必要?例外的に不要なケースや印紙額を解説
契約書建設業法収入印紙工事請負契約書 -
契約実務

【無料ひな形付き】準委任契約とは?請負契約・委任契約との違いを解説
契約書契約書ひな形・テンプレート業務委託契約書準委任契約請負契約 -
契約実務

業務委託とフリーランスの違いとは?業務委託契約を締結するメリットや注意点を解説
業務委託契約書 -
契約実務
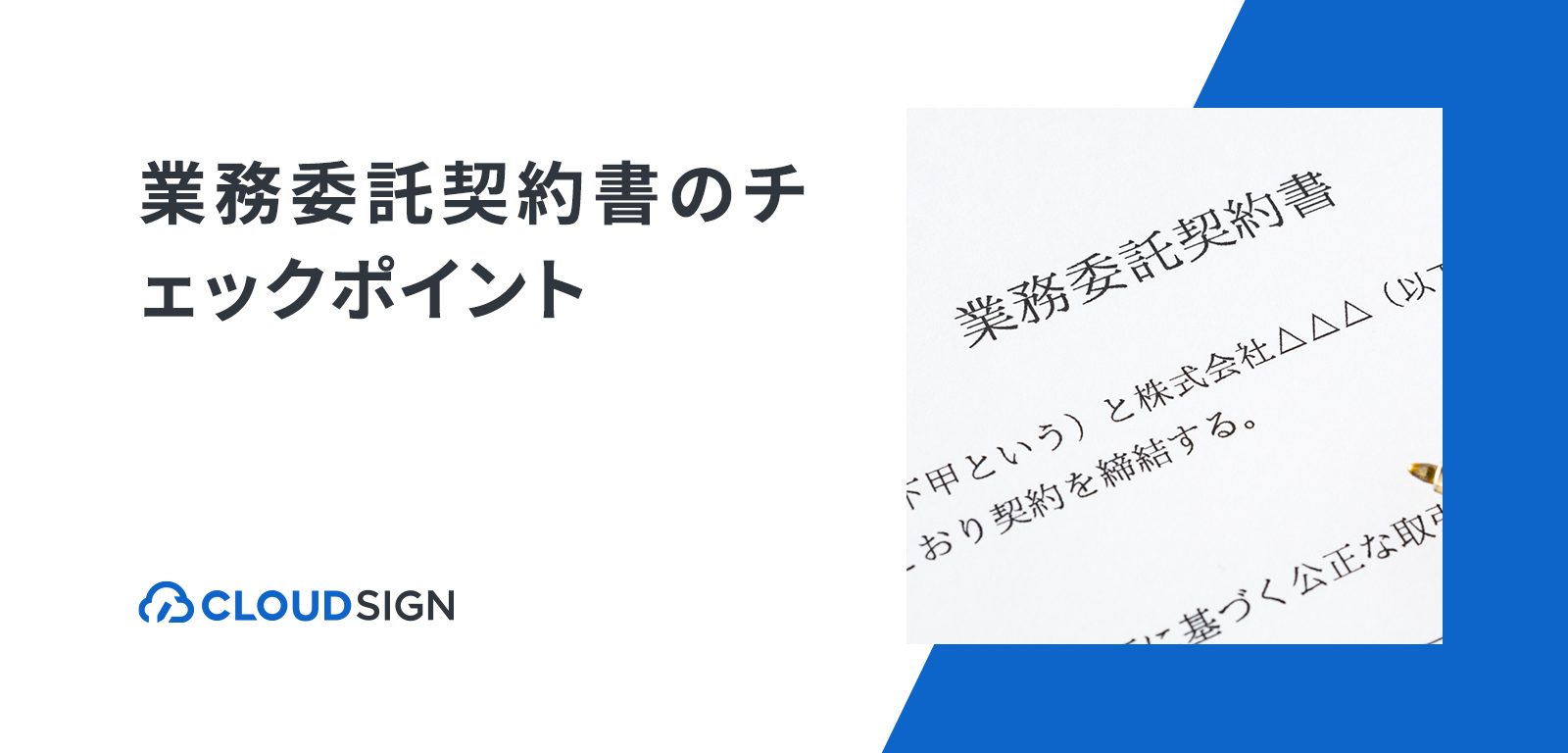
業務委託契約書のチェックポイント
契約書業務委託契約書