電子契約の利用可能範囲と改正民法522条 —契約方式自由の原則とその例外

目次
1. 電子契約を利用して締結可能な契約の範囲・種類に制限はあるか
お客様からよくいただく質問の一つに、「ハンコを使わず、電子契約のような電磁的方法で契約を締結しても本当に大丈夫なのか、どんな契約書でも問題にならないのか」というものがあります。
たしかに、日本のように100年以上にわたって紙とハンコによる契約締結の商慣習が確立している国で、ハンコによらない方法で締結すると、不安になるのは無理もありません。
この点、日本においては、民法522条2項に契約締結方式の自由を認める条文が明記されており、原則として、どのような契約でも電子契約で締結が可能です。ただし例外として、いくつかの契約類型について、若干の制約があることも合わせて知っておくと良いでしょう。
本記事では、この民法が定めている契約の自由の原則と例外について整理をしていきます。
2. 契約自由の原則—相手方選択・締結・内容決定・方式の自由
2020年4月に改正された民法には、企業と企業、企業と個人といった私人間の関係を規律するルールが定められています。契約に関するルールもそのうちの一つ。特に、電子契約との関係では、契約自由の原則が重要です。
契約とは、目的が対立する複数の意思表示が合致したときに成立する法律行為のことを言い、売買・贈与・賃貸借などが例として挙げられます。具体的には、当事者(甲)が申込みを行い、反対当事者(乙)が承諾を行うことで、契約は成立します。
このことを定めている民法522条を見てみましょう。
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
(2項省略)
私人である当事者の衝突を自主的に調整する手段が契約であり、日本においては、その締結や内容について、問題が起きない限りは国家権力は介入せず、当事者同士の私的自治に任せればよいとして、広範な自由が認められています。
以下、その契約自由の原則の具体的な中身について、4点に分けて解説します。
2.1 契約締結の自由(改正民法521条1項)
まず前提として、契約を締結し、または締結しない自由があるという点が大切です。
たとえば、働ける状態ではないのに、労働契約の締結を強制されたとしたら、それは強制労働になってしまいます。そのようなことを断る権利があるということは、私的自治の大前提となります。
第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
(2項省略)
2.2 契約相手方選択の自由(改正民法521条1項)
次に、契約の相手方を選択する自由があります。
さきほどの強制労働の例で言えば、A社では働きたくないが、B社でならぜひ働きたいというように、労働契約の相手を選べることは重要です。
改正民法の条文上、これが保障されていることが読み取りにくいかもしれませんが、2.1で引用した521条1項に含意されると解釈されています。
2.3 契約内容決定の自由(改正民法521条2項)
これも文字通りではありますが、契約当事者は、合意によって契約の内容を自由に決定することができます。
売買契約ならば、同じ物を1万円で売ろうが10万円で売ろうが、それは当事者間の合意に委ねられますし、業務委託契約を締結する際に、委託する業務について何をどこまで達成すべきか、達成しなかったときにどのようなペナルティを課すかといった取り決めを、自由に結ぶことができます。
第521条 (1項省略)
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
2.4 契約方式の自由(改正民法522条2項)
最後が、電子契約にも大いに関係する、契約締結の方式を自由に決定することができる、という原則です。
一般に「契約」と聞くと、「契約書」の文字が表すとおり、書面による契約を想像しがちです。しかし、よく知られているとおり、契約の方式としては、
- 口頭による契約
- 書面による契約
- 電磁的記録による契約
と、書面以外にも、口頭や電磁的記録によるものが増えています(場合により、黙示の契約も成立しますが、ここでは除きます)。たとえば、ウェブサービスを利用する際の利用規約への同意ボタンクリックは、電磁的記録によって契約を行っていると言えるでしょう。
電子契約は、このうちの電磁的記録を使った意思表示による契約にあたります。この条文を根拠に、原則としてあらゆる契約が電子契約で締結できることが明らかになりました。
第522条 (1項省略)
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
3.改正前の民法には契約自由の原則は明文化されていなかった
こうした契約自由の原則は、私的自治を支える基本原則であるにもかかわらず、2020年の改正民法施行まで明文化はされていませんでした。
そのような状況からわざわざ条文に明記されるようにまでなった理由には諸説ありますが、1990年代までは、契約自由の制限を積極的に評価する学説が有力であったところ、1990年代以降、新自由主義的な政策・思想や、憲法13条による自己決定権を根拠として、契約の自由が強調されるようになったと言われています(中田裕康『契約法〔新版〕』(有斐閣、2021)28頁)。
確かに、1999年の借地借家法改正により導入された定期借家制度を例に挙げると、「公正証書による等書面によって契約をするときに限り」という制限付きではあったものの、かつて正当な事由がない限り契約の更新を拒否できなかった賃貸借契約において、貸主の都合でこれを拒絶できるようになりました。
このように、近年、制定法レベルで契約自由の拡大を認めるようになってきたことが影響し、民法改正を機に条文化されたと考えられます。。
4. 契約自由の原則に対する例外—契約方式に対する制約
さて、以上みてきたように、契約はその締結、相手方、内容決定、方式のそれぞれについて自由が認められているわけですが、いくら私的自治が原則と言っても、その自由の範囲に限界はあり、別の法令によって制約が課される場合もあります。
契約自由の原則に制約が課される代表的なケースとして、以下のような契約が挙げられます。
- 水道事業者は、正当の理由がなければ給水契約の申込みを拒んではならない(水道法15条1項)
→契約締結の自由に対する例外 - NHKとの受信契約締結義務(放送法64条1項)
→契約相手方選択の自由に対する例外 - 30年より短い借地権の存続期間の定めは無効(借地借家法3条、9条)
→契約内容決定の自由に対する例外
このような例外の一つとして、契約方式自由の原則に対する制約、たとえば、口頭で締結した場合は取消しが可能になる契約や、書面でなければそもそも効力を生じないといった制約が課されるケースもあります。
5. 現時点で電子契約が認められていない契約類型・文書に注意
2022年時点で、電磁的記録を利用して行う電子契約について、一定の範囲で規制されるケースをまとめてみました。
紙の契約書が主流だった時代と比較すれば種類は少なくなったものの、逆に落とし穴にはまらないように、確かな知識を身に付けておくことが必要です。
5.1 電子契約を利用した契約締結を行う際に事前に相手方の承諾が必要なもの
たとえば、以下のような契約は、電子契約で締結するために、事前に相手方の承諾が必要となります。
- 建築請負契約の契約書
- マンション管理業務委託契約書
- 下請会社に対する受発注書面
5.2 電子契約を利用した契約締結が認められず、書面での締結が必要なもの
また、そもそも電磁的記録による契約が認められない類型も、ごく一部ですが存在します。代表的な契約類型は、以下の通りです。
- 不動産売買・交換の媒介契約書
- 事業用定期借地契約
- 特定商取引(訪問販売等)の契約等書面
こうした規制がある契約類型については、別途解説した記事があります(関連記事:電子化に規制が残る文書と契約類型のまとめリスト)。
5.3 契約方式自由の原則に対する規制と、その緩和動向
いまは電子契約の利用に規制が存在する契約書についても、2022年5月以降に規制が緩和され、電子契約が利用できるようになることが決定している契約類型もあります(関連記事:不動産DX法改正で始める不動産契約電子化のメリットとデメリット)。
2020年以降、リモートワークの要請が高まっていることから、デジタル庁をはじめとする政府が書面・対面・押印慣行の廃止・見直しを行っています。いずれは規制が撤廃され、100%電子化が可能となる時代を見据えて、今から準備を進めておくことが重要です。
こちらも合わせて読む
-
電子契約の基礎知識法律・法改正・制度の解説
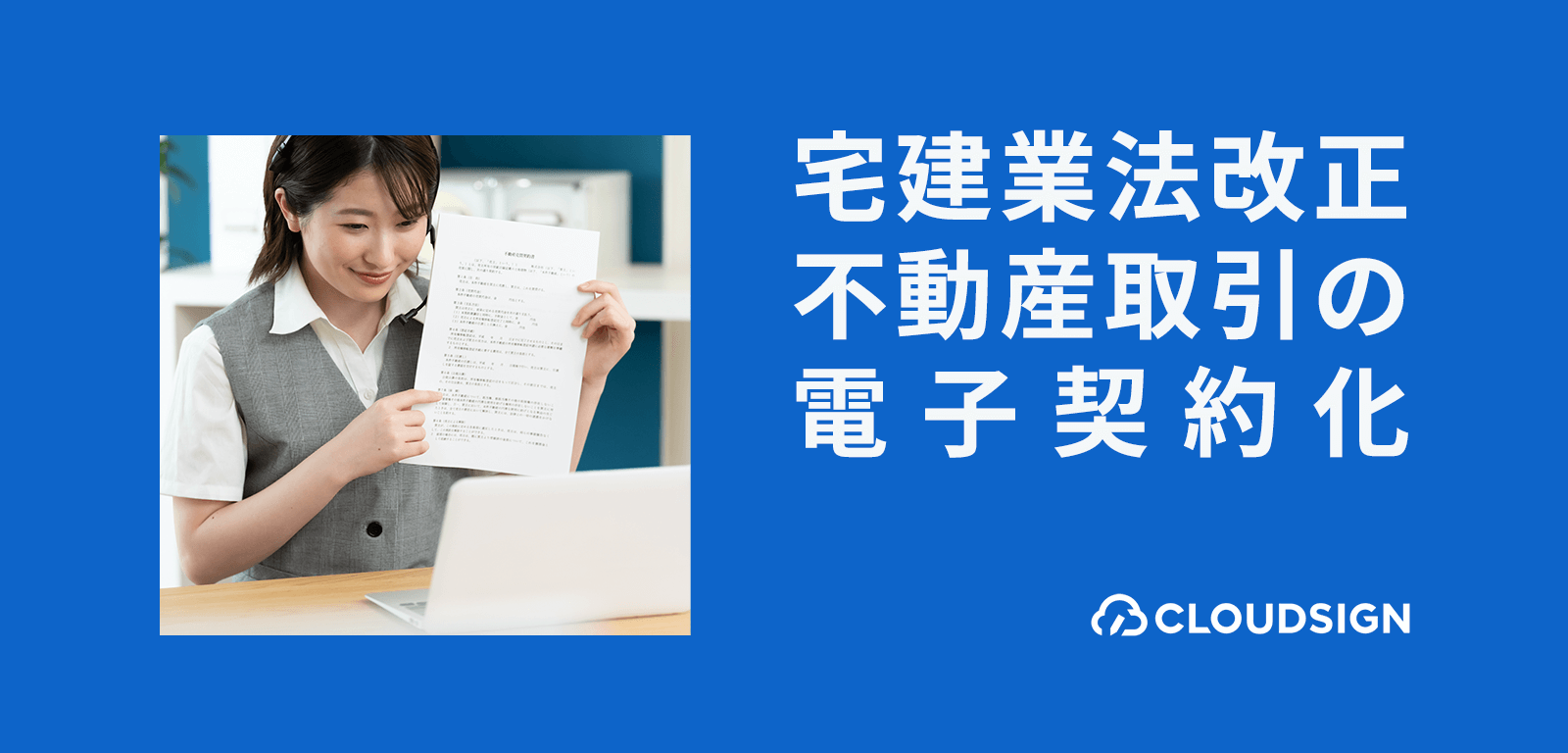
【2023年10月最新】不動産取引の電子契約化はいつから?宅建業法改正で重要事項説明書等の押印廃止・電子交付が可能に
法改正・政府の取り組み不動産コスト削減宅地建物取引業法 -
電子契約の運用ノウハウ電子契約の基礎知識

【日本初の不動産電子契約事例も紹介】デジタル法改正で始める不動産契約電子化のメリットとデメリット
不動産借地借家法宅地建物取引業法 -
リーガルテックニュース
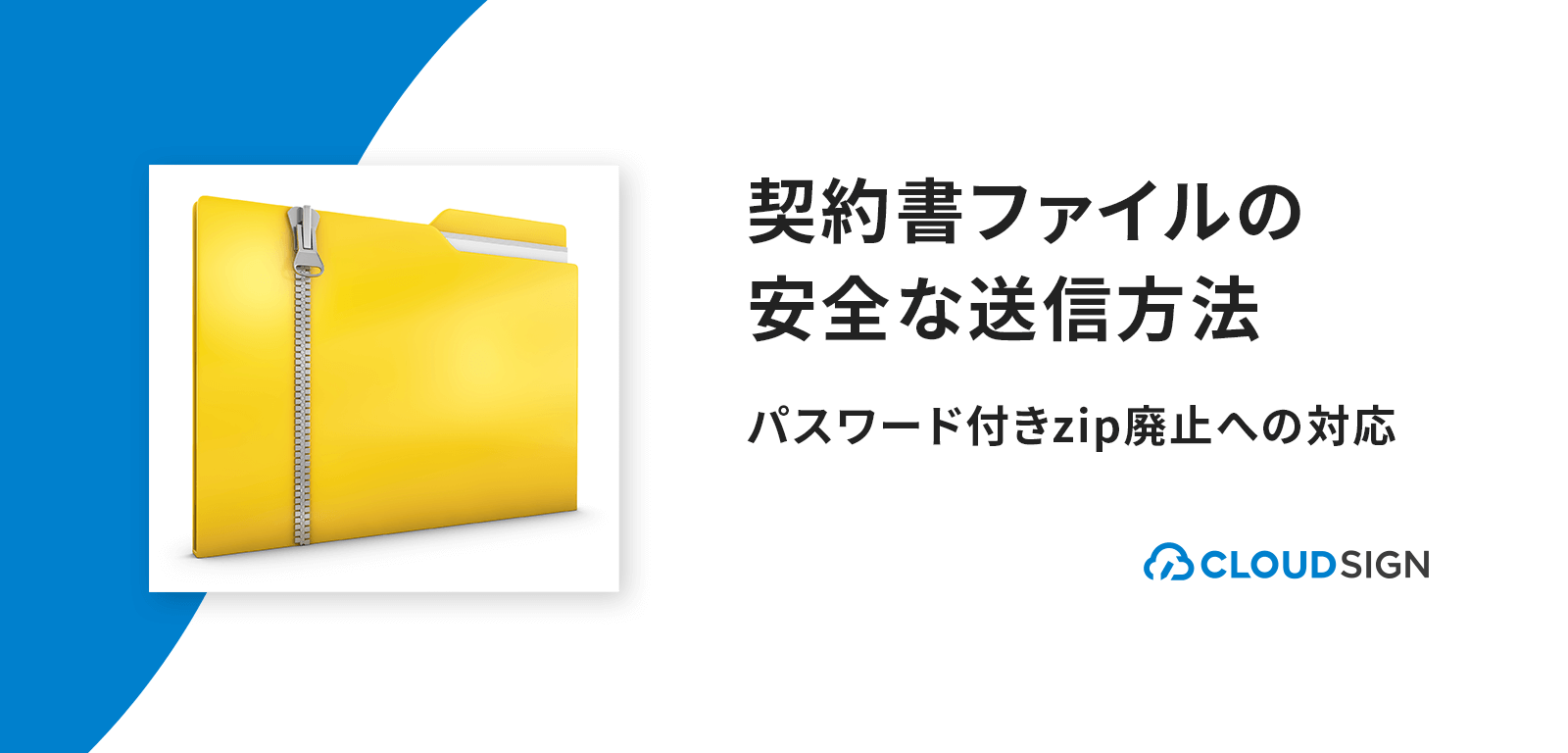
契約書ファイルの安全な送信方法—パスワード付きzip廃止への対応
-
リーガルテックニュース
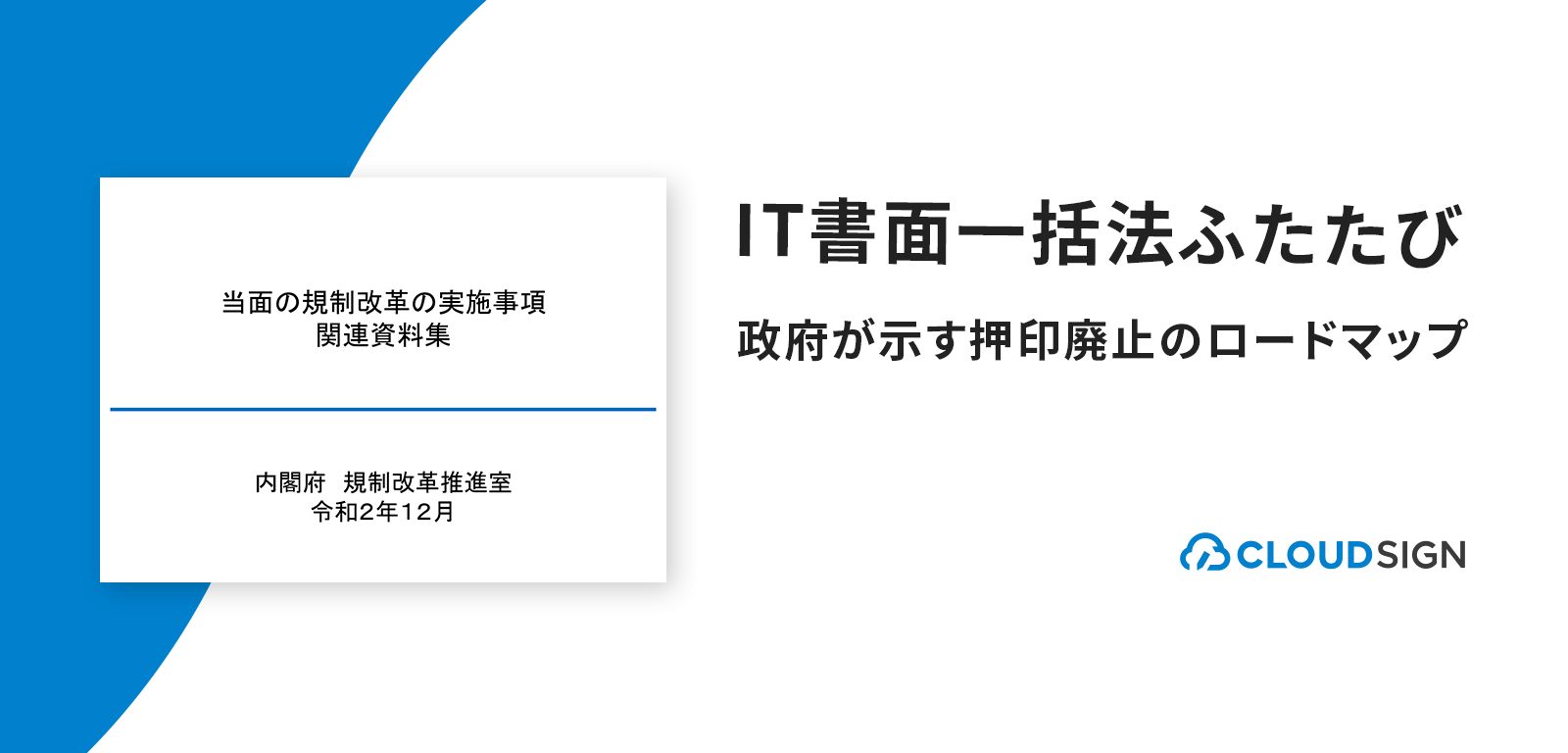
IT書面一括法ふたたび—政府が示す押印廃止のロードマップ
押印・署名電子署名 -
リーガルテックニュース
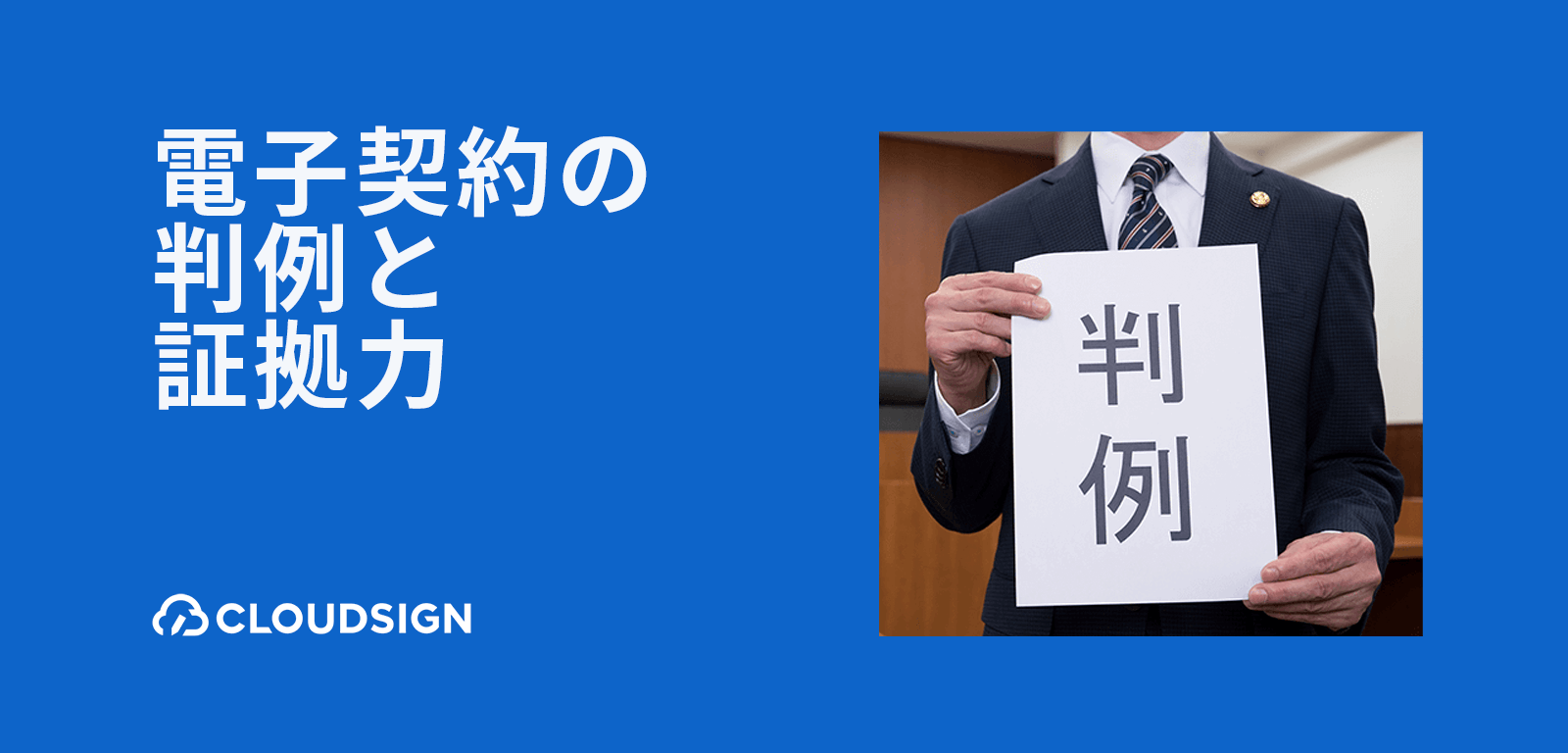
電子契約の有効性が争われた裁判例はあるか?民事訴訟法における電子署名入りデータの証拠力を解説
民事訴訟法 -
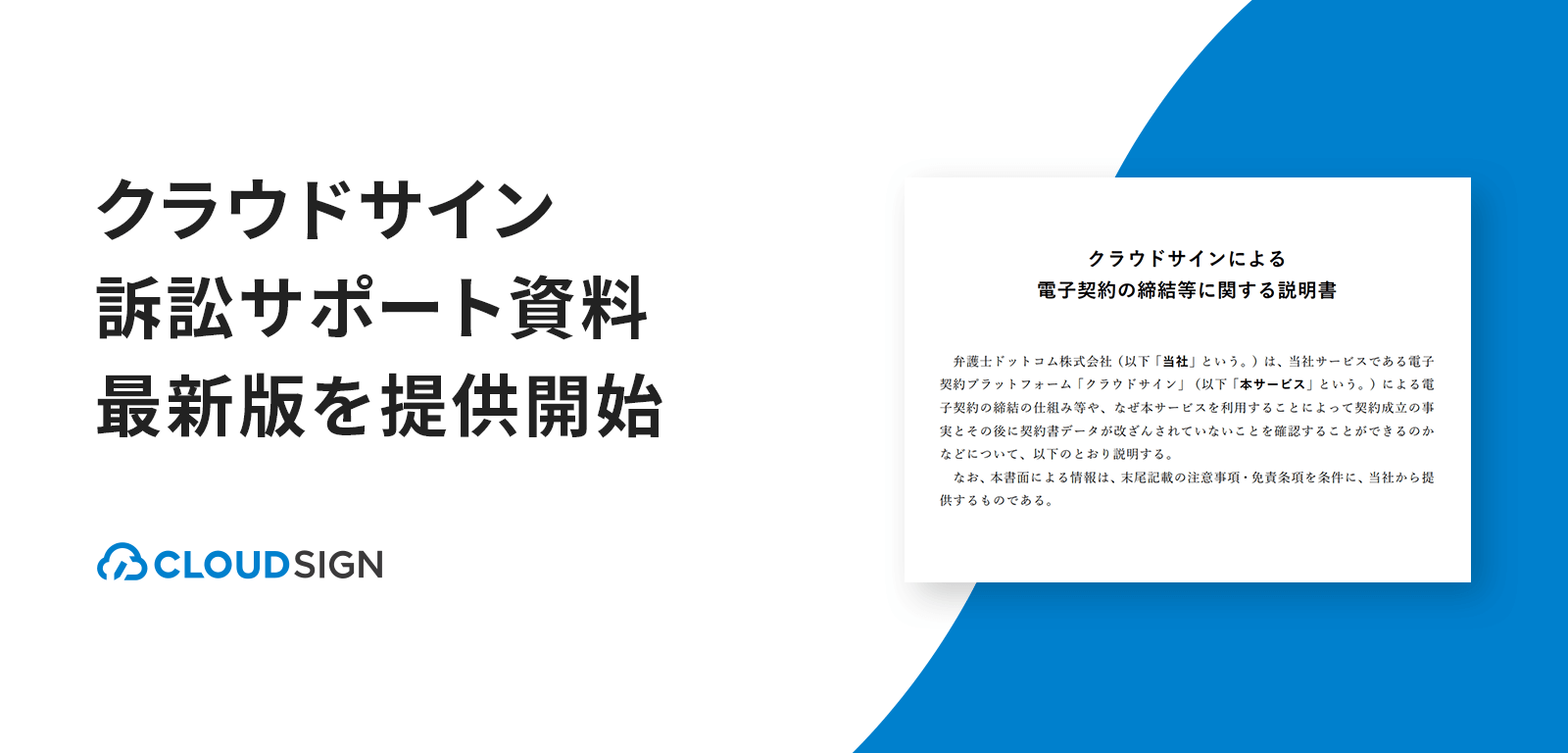
クラウドサイン訴訟サポート資料最新版を提供開始
弁護士解説