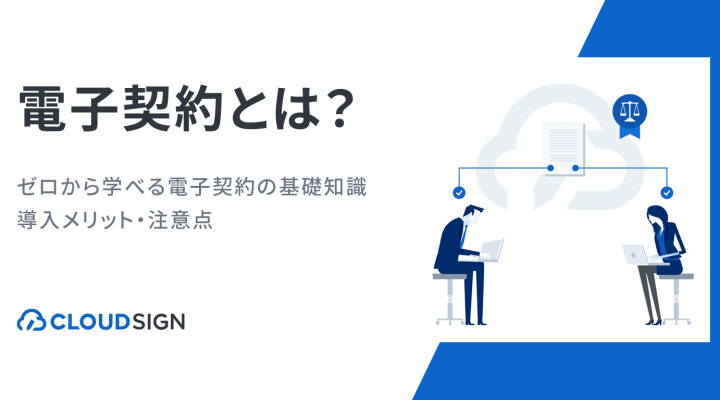【2025年2月最新】電子契約にできない契約書とできる契約書の違いとその見分け方

電子署名法、IT書面一括法およびデジタル社会形成整備法等の施行により、ほとんどの契約書について電子契約化できるようになりました。しかし、ごく一部の契約類型で、電子契約にできない契約書が残っています。本記事では、電子契約にできない契約書とできる契約書の違いとその見分け方についてまとめました。
目次
法改正によりほとんどの契約書が電子契約化できるようになったが、できない契約書も一部残っている
かつては押印が原則であった日本でも、電子署名を押印と同等に通用させる電子署名法が2001年に施行されて以降、IT書面一括法(2001年施行)、e-文書法(2005年施行)、電子帳簿保存法(1998年施行、2005、2015、2016、2020、2022年改正)そしてデジタル社会形成整備法(2021年施行)が施行され、現在では以下のように、企業が取り交わす文書・契約書のほとんどが電子契約で締結可能です。
これらに加え、長らく電子化が認められてこなかった不動産売買・賃貸借等に関する契約書や重要事項説明書についても、宅地建物取引業法・借地借家法等の改正により、2022年5月18日以降は電子契約による完全電子化が可能となりました。

しかしながら、ごく一部の文書について、書面が必須、または電子化に相手の承諾や希望が必要となる類型が存在するのも事実です。以下では、そのような例外的な契約書をリストアップした上で、見分け方をレクチャーします。
電子契約にできない契約書
現時点では電子化できない契約書について紹介します。
電子契約にできない契約書リスト(2025年現在)
法律により書面化が必須の義務とされ、電子契約を利用できない契約書は次のとおりです。
| 文書名 | 根拠法令 | 改正法施行予定 |
|---|---|---|
| 事業用定期借地契約 | 借地借家法23条 | — |
| 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約 | 企業担保法3条 | — |
| 任意後見契約書 | 任意後見契約に関する法律3条 | — |
電子契約にできない理由—「公正証書」化する義務が残るため
上記リストの通り、
- 事業用定期借地契約
- 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約
- 任意後見契約書
については、それぞれ公正証書によって契約を締結すべきことが法律で定められているために、現状は書面での締結が必要となります。
公正証書とは、公証人が公証人法等の法令に従って法律行為その他私権に関する事実について作成した証書のことを言います。(有斐閣「法律学小辞典」)
なお、公正証書については、規制改革推進会議において電子化を認める範囲や、その時期について検討が進められており、これらの契約書についても電子署名によって作成することが認められる可能性があります。
電子契約にできるが、契約相手方の承諾等が必要な契約書
電子契約の利用は可能なものの、契約相手方の承諾・希望・請求が必要な契約書についても、主なものをまとめて紹介します。
- 電子契約の利用に承諾・希望・請求が必要な文書・契約書リスト
- 電子契約の利用に相手方の「承諾」が必要なもの—建設工事の請負契約・下請との受発注書面など
- 特商法改正により2023年6月1日から訪問販売などの特定商取引でも電子化可能に
- 電子契約の利用に相手方の「希望」が必要なもの—労働関連の条件書類
電子契約の利用に承諾・希望・請求が必要な文書・契約書リスト
| 文書名 | 根拠法令 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 事業者が交付する申込書面、契約書面、概要書面 | 改正特商法第4条第2項、第13条第2項、第18条第2項、第20条第2項など | 承諾 |
| 建設工事の請負契約書 | 建設業法19条3項、施行規則13条の2 | 承諾 |
| 設計受託契約・工事監理受託契約の重要事項説明書 | 建築士法24条の7第3項 | 承諾 |
| 設計受託契約・工事監理受託契約成立後の契約等書面 | 建築士法24条の8第2項 | 承諾 |
| 下請事業者に対して交付する「給付の内容」等記載書面 | 下請法3条2項 | 承諾 |
| 定期建物賃貸借契約の際の説明書面 | 借地借家法38条3項、同4項 | 承諾 |
| 宅地建物の売買・交換の媒介契約書 | 宅建業法34条2第11項、同12項 | 承諾 |
| 宅地建物の売買・交換の代理契約書 | 宅建業法34条3 | 承諾 |
| 宅地建物の売買・交換・賃借の際の重要事項説明書 | 宅建業法35条8項、同9項 | 承諾 |
| 宅地建物取引業者の交付書面 | 宅建業法37条4項、同5項 | 承諾 |
| 不動産特定共同事業契約書面 | 不動産特定共同事業法24条3項、25条3項 | 承諾 |
| 投資信託契約約款 | 投資信託及び投資法人に関する法律5条2項 | 承諾 |
| 貸金業法の契約締結前交付書面 | 貸金業法16条の2第4項 | 承諾 |
| 貸金業法の生命保険契約等に係る同意前の交付書面 | 貸金業法16条の3第2項 | 承諾 |
| 貸金業法の契約締結時交付書面 | 貸金業法17条7項 | 承諾 |
| 貸金業法の受取証書 | 貸金業法18条4項 | 承諾 |
| 割賦販売法の契約等書面 | 割賦販売法4条の2、割賦販売法35条の3の8・同条の3の9第1項、同3項 | 承諾 |
| 旅行契約の説明書面 | 旅行業法12条の4、12条の5、施行令1条等 | 承諾 |
| 労働条件通知書面 | 労働基準法15条1項、施行規則5条4項 | 希望 |
| 派遣労働者への就業条件明示書面 | 派遣法34条、施行規則26条1項2号 | 希望 |
| 金銭支払の受取証書 | 民法486条2項 | 請求 |
電子契約の利用に相手方の「承諾」が必要なもの—建設工事の請負契約・下請との受発注書面など
建設工事の請負契約・下請との受発注書面 などは、締結件数も多く、また書面では印紙税が課税されるのに対し電子化すれば印紙税が不要となることもあり、電子化の効用が高い契約類型です。
相手方の承諾が必要とあるものの、むしろ承諾さえ確保できれば法的にはなんら問題はないとも言え、積極的に電子契約を活用すべき領域でしょう。
特商法改正により2023年6月1日から訪問販売などの特定商取引でも電子化可能に
2023年6月以前の特商法では、以下の特定商取引については消費者保護のため、事業者には紙媒体の契約書面等を交付する義務が課せられていたため、電磁的方法で交付することはできませんでした。
- 訪問販売電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
しかし、特商法の改正により、2023年6月1日からは事業者が消費者に対して交付すべき契約書面等について「消費者から事前の承諾を得ること」を前提に電磁的方法による交付が可能になりました。この電磁的方法の具体例としては、電子メールのほかクラウドサインのような電子契約サービスも含まれます。
また、消費者によるクーリングオフ通知書面に関しても電磁的方法によることが可能になりました(根拠法令:改正特商法9条1項など)。消費者庁の運営する「特定商取引法ガイド」の「Q&A」によれば、電磁的方法によるクーリングオフの代表的な例として、電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。
特定商取引法についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
電子契約の利用に相手方の「希望」が必要なもの—労働関連の条件書類
また、労働条件通知書や派遣社員に対する条件明示書面 については、電子化について「承諾」ではなく「希望」を確認するというプロセスが必要とされています。
なお、クラウドサインでは、労働条件通知書の交付時に労働者へ電子化についての希望を確認できるひな形をご用意しています。ぜひダウンロードの上、ご活用ください。
電子契約にできない契約書・できる契約書の見分け方
以上をまとめると、電子契約にできる契約書とできない契約書を見分けるポイントは、契約当事者の力関係・パワーバランス・情報格差に著しい有利不利が生じがちな契約締結の場面かどうかにある、といえます。
具体的には、契約当事者が
- 賃貸人と賃借人
- 親事業者と下請事業者
- 企業と消費者
- 雇用主と労働者
といった関係性にある場合、電子契約の利用ができない、または相手方の承諾が必要などの制限が設けられています。
逆に言えば、一般的な対等関係で結ばれる契約については、電子契約が問題なく利用できるということでもあります。上記表も参考に関連法令をご確認の上、電子契約のご利用をご検討ください。
電子契約を導入してコスト削減や業務効率化の実現を
電子契約サービスの導入により、印紙代や郵送費などのコスト削減や、締結完了までにかかるリードタイムの削減といったさまざまなメリットが得られます。
当社の提供する「クラウドサイン」は、電子署名を電子ファイルに施し、スピーディーかつ安全に当事者間の合意の証拠を残すことのできる電子契約サービスです。導入社数250万社以上、累計送信件数 1000万件超の国内シェアNo1の電子契約サービスとして、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。

電子契約サービス「クラウドサイン」のサービスイメージ
電子契約サービス「クラウドサイン」の「契約書の準備から送信」までの流れが気になる方は下記バナーからサービスのデモを体験してみてください。
なお、クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でご入手できますので、ぜひご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター
弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司
弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。