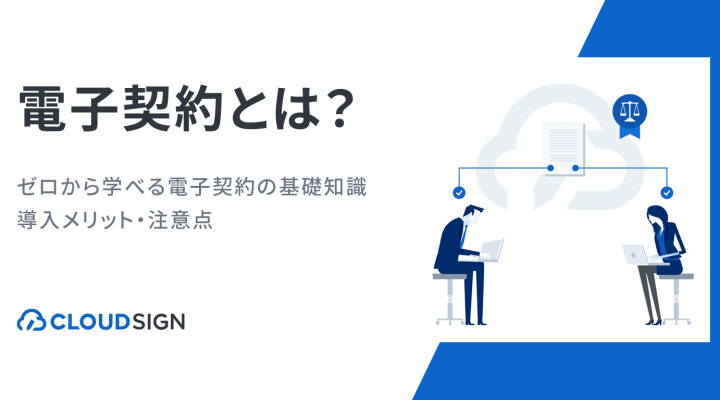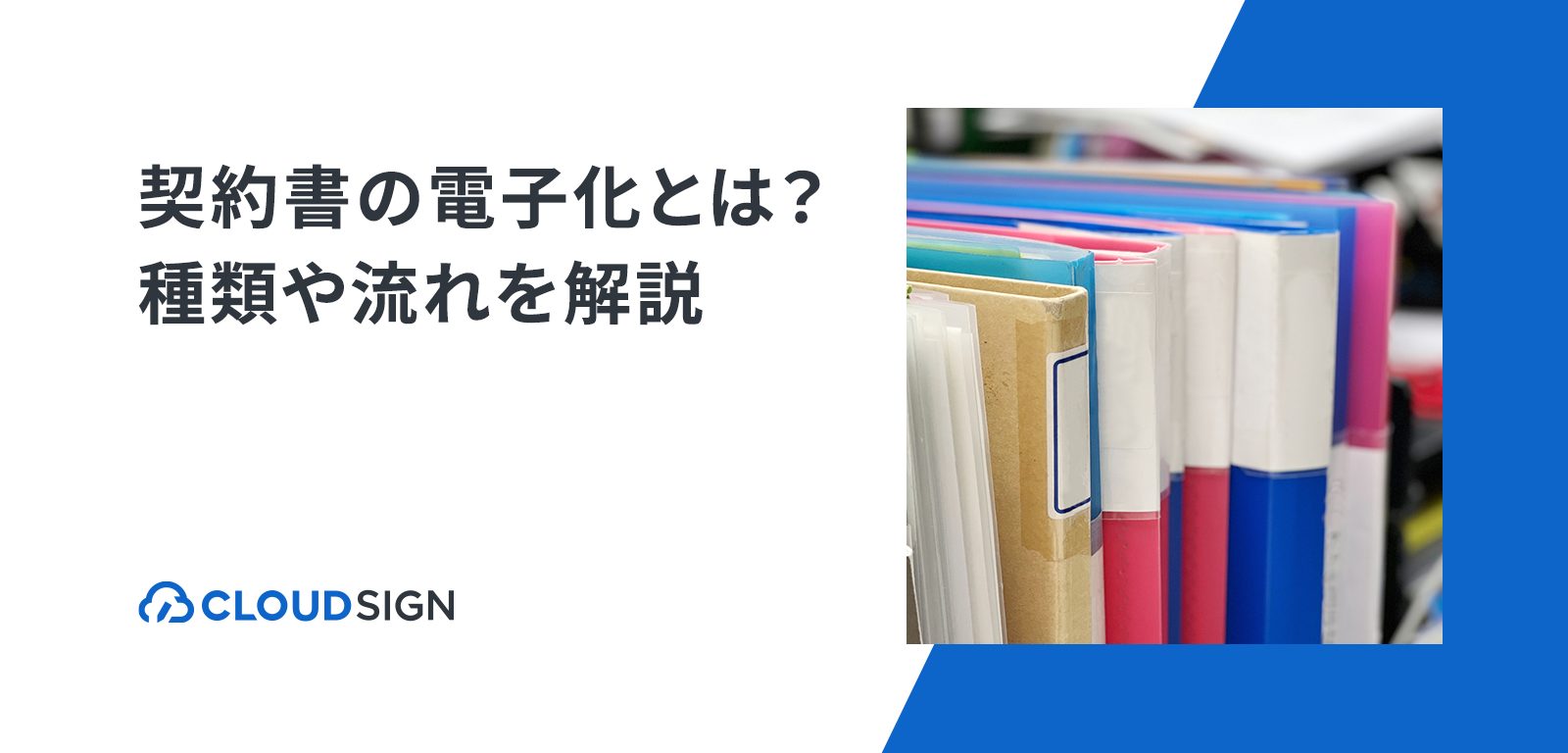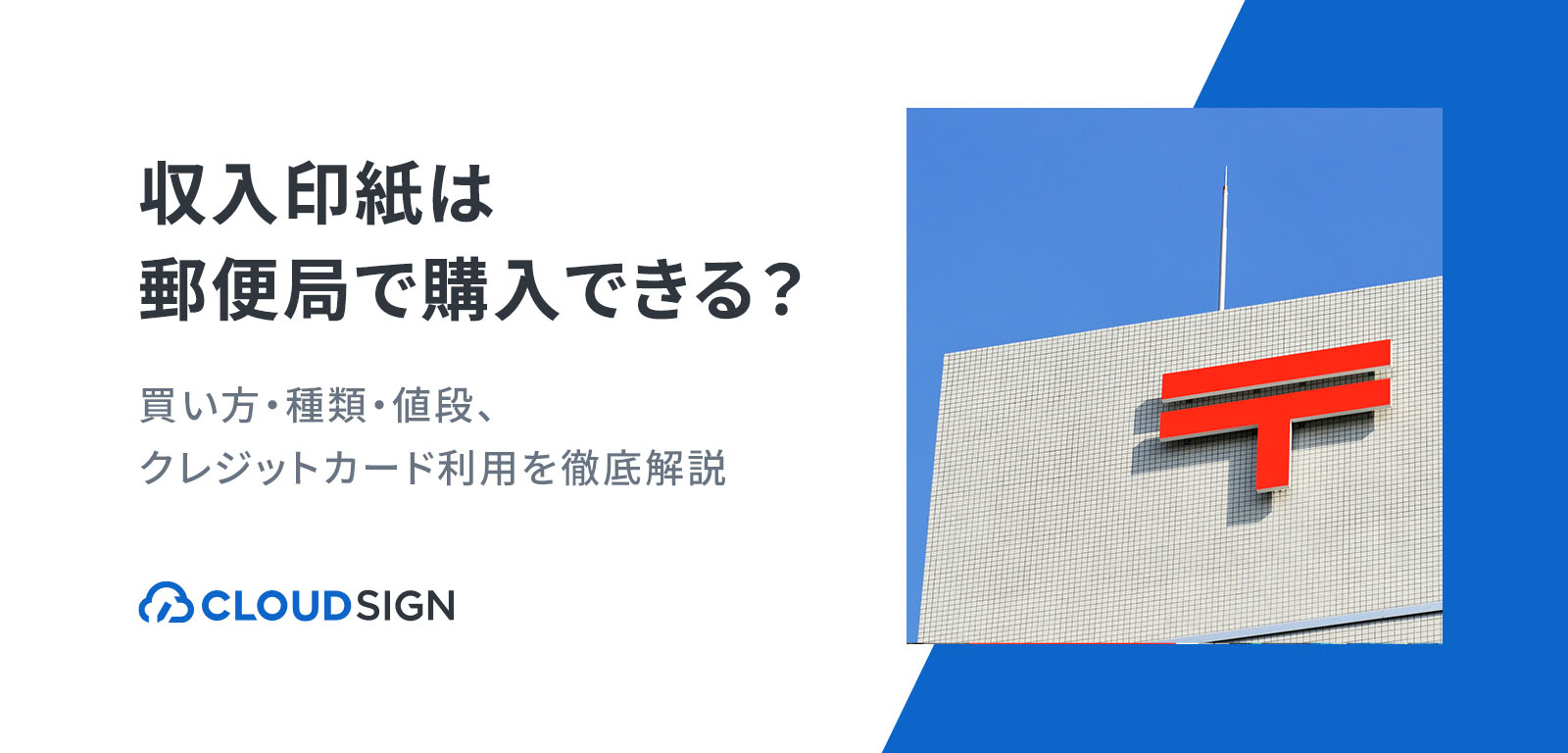契約書の適切な郵送方法は?法的ルールや最新料金まで解説

契約書などの重要書類を適切に郵送することは、ビジネス上の取引において不可欠であると同時に、十分な配慮と正確さが求められます。
当記事では、重要書類を適切かつ安全に郵送する方法を詳しく解説します。重要書類を郵送する前に知っておきたい法的ルールや郵送時の注意点など、様々なポイントを押さえながら適切な郵送方法を確認しておきましょう。
一方で、郵送にかかるコストや時間、書類の紛失といったリスクをなくし、契約締結までのプロセスを劇的に改善する電子契約という選択肢も広がっています。当記事では、従来の郵送方法を解説するとともに、より効率的で安全な電子契約のメリットについても触れていきます。双方を比較検討し、自社に最適な契約業務の進め方を見つけていきましょう。
なお、クラウドサインでは「知っておくべき紙の契約書マナー」を解説するマナーBOOKをご用意しております。印刷・製本・郵送に関する情報をまとめていますので、気になる方はぜひ下記フォームからダウンロードのうえ、ご活用ください。
無料ダウンロード

この資料では「知っておくべき紙の契約書マナー」を解説します。取引先との良好な信頼関係を築くために知っておきたい、紙の契約書の印刷・製本・郵送に関わる知識やマナーを解説しますので、気になっている方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。
ダウンロードする(無料)目次
契約書を郵送するために最適な方法とは?
契約書をはじめとする重要書類を郵送する場合、万が一の紛失や誤配を防ぐため、配送過程を記録・追跡できるサービスの利用が最適です。
具体的には、日本郵便が提供する以下のサービスがおすすめです。
- 書留(一般書留・簡易書留)
- レターパックプラス
これらのサービスは、引受けから配達までの過程が記録され、受取人から受領印または署名をもらう形で配達が完了するため、安全性が高い郵送方法と言えます。ただし、2024年以降、条件により置き配がされる場合がありますので注意しましょう。詳しくは後述する「書留・レターパックプラスの配達方法に関する注意点」のパートで解説します。
一方で、追跡サービスや損害賠償制度がなく、郵便受けに投函される普通郵便は重要書類の郵送には適していません。
信書を送れるサービスと送れないサービス
次の項目で詳しく解説しますが、法的ルールに基づき、信書を送れるサービスと送れないサービスは明確に区別されています。
【信書を送れるサービス】
- 日本郵便のサービス
- 定形郵便、定形外郵便(手紙)
- はがき
- レターパック(プラス、ライト)
- スマートレター
- 上記に書留、速達、特定記録などのオプションを付けたもの
- 信書便事業者のサービス
- 総務省の許可を得た事業者が提供する信書便
【信書を送れないサービス】
- 宅配便サービス
- ゆうパック(日本郵便)
- ゆうパケット(日本郵便)
- 宅急便(ヤマト運輸)
- 飛脚宅配便(佐川急便)など
- 荷物や印刷物を対象とするメール便サービス
- クロネコDM便(ヤマト運輸)
- 飛脚メール便(佐川急便)
- ゆうメール(日本郵便)※ただし、内容物に関する例外規定あり
- クリックポスト(日本郵便)
(出典:総務省|信書の送達について)
重要書類の送付時に知っておきたい法的ルール

送付したい重要書類が「信書」に該当する場合は、法律で定められた方法で送付する必要があります。
信書とは、契約書や納品書、履歴書、見積書のような書類に代表される「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」が当てはまります(郵便法第4条第2項、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第1項)。送付したい書類が信書に該当するかどうかを知りたい場合には日本郵便のQ&Aページ「信書に該当するものを教えてください」を確認しましょう。
出典:郵便法 第四条、民間事業者による信書の送達に関する法律 第二条
この信書の送達は、日本郵便株式会社および総務大臣の許可を得た信書便事業者のみが行うことができると、法律で定められています。許可を得ていない事業者が他人の信書を送達することや、それに委託することは郵便法違反となり、郵便法第76条で定められた3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
【郵便法(昭和22年法律第165号) (抜粋)】
第二条(郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。
第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
(2) 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなされる。
(3) 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
(4) 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(2) 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
なお、上記(3)(4)にある通り、郵便法では運送営業者の信書の送達を禁じているため、宅配便に信書を含めることはできない点に注意しましょう。
契約書の郵送方法の比較【2025年最新料金】
契約書を送付する際は、その重要性に応じて適切な郵送方法を選ぶ必要があります。ここでは、追跡サービスがあり、安全性の高い「簡易書留」「一般書留」「レターパックプラス」の3つのサービスを、現在の最新料金と共に比較します。
| 簡易書留 | 一般書留 | レターパックプラス | |
| 料金 | 基本郵便料金 + 350円 | 基本郵便料金 + 480円 | 全国一律 600円 |
| 配達方法 | 原則対面手渡し・要受領印
(※条件を満たす宅配ボックスへの配達も可) |
原則対面手渡し・要受領印
(※条件を満たす宅配ボックスへの配達も可) |
原則対面手渡し・要受領印 (不在時、受取人による事前の置き配依頼がある場合は指定場所へ配達) |
| 追跡サービス | あり | あり | あり |
| 損害賠償 | あり(上限5万円) | あり(上限10万円~) | なし |
| こんな時におすすめ | コストを抑えつつ確実に届けたい | 高額な契約など、より高い安全性を求める | スピードを重視し、全国一律料金で送りたい |
ではそれぞれについてもう少し詳しく解説をしていきます。
簡易書留
簡易書留は、基本的な郵便料金に350円を追加することで利用できます。引受けから配達までの過程が記録され、万が一郵便物が破損したり届かなかったりした場合、原則として5万円までの実損額が賠償されます。コストを抑えつつ、書留としての基本的な安全性を確保したい場合に適しています。ただし、2024年以降、受取人が専用の依頼書を提出し、一定の条件を満たす宅配ボックスを設置している場合は、対面ではなく宅配ボックスへ配達されることがあります。
一般書留
一般書留は、簡易書留よりも高い安全性を求める場合の最適解と言えるでしょう。基本料金に480円の追加で利用できます。簡易書留との大きな違いは、手厚い損害賠償制度にあります。申し出た損害要償額に応じた賠償が行われ、標準で10万円まで、さらに追加料金を支払うことで上限500万円まで補償の範囲を広げることが可能です。高額な取引の契約書や、再発行が困難な重要書類など、最大限の安全を確保したい場合に最適です。ただし、一般書留も簡易書留と同様に、受取人側の事前の手続きと条件を満たす宅配ボックスがある場合には、宅配ボックスへの配達が行われる可能性があります。
レターパックプラス
レターパックプラスは、A4サイズ・4kgまでなら全国一律600円で送れるサービスで、手軽さとスピードを両立できる方法です。専用封筒を購入すれば切手は不要で、郵便ポストへの投函も可能です。配達は速達に準ずるスピードで、土日祝日も配達されます。ただし、最も重要な注意点として、追跡は可能ですが損害賠償制度はありません。送付する契約書の重要度と緊急性に応じて、他の書留サービスと比較検討しましょう。
なお、レターパックには、全国一律430円で送れる「レターパックライト」もあります。レターパックプラス同様に信書の送付や追跡サービスは可能ですが、厚さ3cm以内という制限があり、配達先では郵便受けへの投函となります。
書留・レターパックプラスの配達方法に関する注意点
書留やレターパックプラスは、受取人への対面手渡しが原則ですが、2024年以降、受取人側の事前の手続きや、宅配ボックスの有無によっては、必ずしも対面で渡されるとは限らないという点に注意が必要です。
書留の場合は、 受取人が専用の依頼書を提出し、一定の条件を満たす宅配ボックスを設置している場合、不在時に限らず宅配ボックスへの配達が行われます。レターパックプラスの場合は、 受取人がWeb等で「指定場所配達に関する依頼書」を提出している場合や、宅配ボックス・鍵付き容器が設置されている場合、不在時には玄関前など指定場所への「置き配」が行われます。
このように、送り主が対面での受け渡しを意図していても、受取人側の設定によっては置き配や宅配ボックスへの配達となり、紛失や情報漏洩のリスクが生じる可能性があります。
紙の契約書を確実に本人へ対面で届けたい場合は、一般書留にさらに270円を追加で支払う「本人限定受取郵便」の特殊取扱を付加する方法が確実です。このサービスを利用すると、郵便物に記載された受取人の本人に限り、運転免許証などの本人確認書類を提示することで郵便物が渡されるため、第三者による受け取りを防ぐことができます。契約書の重要性を鑑み、取引相手の状況も考慮した上で、一般書留や簡易書留、本人限定受取郵便といった選択肢を適切に使い分けることが重要です。
一方で、こうした物理的な郵送に伴う配達方法の複雑さや、意図しない置き配・誤配といったリスクを根本から解消する手段が「電子契約」です。オンライン上で契約締結が完結するため配送自体が不要となり、配達状況の確認や紛失のリスクからも解放されます。郵送が抱えるこれらの課題を解決する電子契約のメリットについては後半で詳しく解説します。
出典:日本郵便株式会社|書留、日本郵便株式会社|レターパック、日本郵便株式会社|本人限定受取郵便、日本郵便株式会社|置き配
重要書類を郵送する際の注意点
契約書を郵送する際は、単に書類を送るだけでなく、ビジネスマナーと確実性を両立させることが、相手方との信頼関係の構築に必要です。発送前と発送後、それぞれの段階で以下の点を確認しましょう。
発送前の注意点
- 契約内容の最終確認
発送する前に、契約書に署名・捺印漏れはないか、日付や金額、条項に誤りがないかを必ず再確認しましょう。内容の正確性は、後のトラブルを避けるための大前提です。 - 添え状(送付状)の同封
ビジネスマナーとして、何の書類を(契約書原本2通など)、誰が、何のために送ったのかを明記した添え状を同封します。これにより、相手方は内容物をすぐに把握でき、送り先に対して丁寧な印象を抱きます。 - 書類の保護と封筒の書き方
雨や汚れから守るため、書類はクリアファイルに入れてから封筒に入れます。
封筒の表面には、宛名(会社名、部署名、担当者名)を正確に記載し、左下に赤字で「契約書在中」と明記します。これにより、社内で重要書類として扱われやすくなり、開封までの流れがスムーズになります。 - (任意)返信用封筒の準備
相手方に記名・押印後に返送してもらう場合は、相手方の手間を省くため、返送先の住所を記載し、適切な料金の切手を貼った返信用封筒を同封するとより丁寧です。
発送後の注意点
書留やレターパックで発送した後は、必ずその控え(追跡番号)を保管しましょう。そして、日本郵便の「郵便追跡サービス」のウェブサイトやアプリを利用し、配達状況を必ず確認しましょう。特に重要なのは、「配達完了」のステータスを確認することです。万が一、相手からの返送が遅れるような場合でも、この追跡記録を元に「〇月〇日頃に到着しているかと存じますが、ご確認いただけましたでしょうか」と、丁寧かつ具体的な状況確認が可能になります。
こうした丁寧な手続きが、郵送ミスを防ぐだけでなく、取引相手に対する誠意の表明となり、円滑で信頼性の高いビジネス関係を築くことにつながります。
契約書の郵送に潜む「隠れたコスト」と「リスク」
契約書を1通郵送する、という日常的な業務には、普段意識している以上の「コスト」と「リスク」が潜んでいます。書留やレターパックの料金だけでなく、契約締結と全体でかかる負担を可視化してみましょう。契約書の郵送の課題としては大きく以下の3つに分けられますので、それぞれ詳しく解説します。
- 金銭的コスト
- 時間的コスト
- 紛失・情報漏洩のリスク
「金銭的コスト」は最もわかりやすい負担であり大きな課題と言えるでしょう。郵便料金(例:基本郵便料金(定形郵便物、長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内、50g以内なら140円)+350円=490円)に加え、封筒代、書類の印刷代、インク代などがかかります。相手方の返信を求める場合は、返信用封筒と切手の同封も必要です。さらに、契約金額によっては数千円から数万円以上にもなる「印紙税」の負担が発生します。これらが契約の都度、継続的に発生するコストです。
そして意外と見落とされがちな負荷としては「時間的コスト」です。契約締結までにはざっと洗い出すだけでも「書類の印刷、製本、送付状の作成、押印、封入、宛名書き、収入印紙の購入、郵便局窓口での発送手続き、相手方への郵送にかかる日数、相手方での確認、押印、返送準備、自社への返送にかかる日数」というように相当な時間がかかります。すべてがスムーズに進んでも、契約締結完了までに1週間以上かかることは珍しくありません。そして時間的コストだけではなく、締結準備をしている間に、顧客や取引先の気が変わって大切なビジネスチャンス自体を逃してしまったというケースも耳にします。
また、郵送には「紛失・情報漏洩のリスク」もゼロではありません。書留を利用しても、輸送中の事故による遅延や、人的ミスによる誤配・紛失のリスクはあります。契約書という企業の機密情報が物理的に移動すること自体が、情報漏洩のリスクを内包していると言えます。
これらのコストとリスクは、ひとつひとつは小さく見えても、積み重なることで企業全体の生産性に大きな影響を与えます。
契約書の郵送に対する課題は電子契約で解決を
前述した郵送における様々な課題を、根本から解決する手段として導入が加速しているのが「電子契約サービス」です。郵送と電子契約を比較すると、その違いは一目瞭然です。
| 郵送(書留) | 電子契約(クラウドサイン) | |
| コスト | 郵便料金、印紙代、印刷費などが発生 | 郵送費・印紙代0円。サービス利用料のみ |
| スピード | 数日~1週間以上 | 数分~即日で締結完了 |
| 手間 | 印刷・製本・押印・封入・投函 | アップロードして送信するだけ |
| 保管・管理 | ファイリング、保管スペースが必要 | クラウド上で一元管理・検索も容易 |
| セキュリティ | 紛失・誤送付のリスク | 通信の暗号化、アクセス制限で高い安全性を確保 |
電子契約について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
電子契約を導入することで、具体的に以下4つのメリットが生まれます。
- 圧倒的なコスト削減ができる
- 契約締結スピードの向上
- 業務プロセスの効率化
- 内部統制・コンプライアンスの強化
それぞれのメリットについて詳しく確認していきましょう。
圧倒的なコスト削減ができる
郵送費や印刷費が不要になるだけでなく、電子データでの契約は印紙税法上の課税文書に該当しないため、高額な印紙税も0円になります。
契約締結スピードの向上
契約書ファイルをアップロードし、相手方の情報を入力して送信するだけで手続きは完了。相手方もオンライン上で内容を確認し、数クリックで同意(締結)できるため、契約業務のリードタイムを劇的に短縮します。実際に、電子契約を導入して契約スピードが上がった成功事例も増えています。
業務プロセスの効率化
製本・押印・送付状作成・封入・投函といった一連の物理的な作業が不要になり、契約担当者の負担を大幅に軽減します。創出された時間で、より付加価値の高い業務に集中できます。
内部統制・コンプライアンスの強化
締結済みの契約書はクラウド上に自動で保管され、ファイリングの手間や保管スペースを削減します。「いつ」「誰が」「どの契約に」合意したかという証拠(ログ)も電子的に記録されるため、内部統制やコンプライアンスの強化にも繋がります。
これらのメリットから、契約業務のDXの第一歩として、多くの企業が電子契約サービスを導入しています。ペーパーレス化の進んでいる昨今、従来の郵送方法だけでなく、電子契約サービスも選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。
重要書類を送る際には、法令の順守や郵送コストなどさまざまな観点で注意が必要になりますが、電子契約サービスを利用した場合は、郵送ではなくオンライン上での送信になるため、それらに注意する必要が限りなく少なくなります。
電子契約サービスを導入する場合には、社内に存在する課題の整理や運用の定着化も重要になってきます。
当社の提供するクラウド型の電子契約サービス「クラウドサイン」は、導入時の課題解決や運用定着化のサポートも充実しています。

幅広い業界での導入実績があるため、コスト削減や業務効率化のための電子契約導入を検討中の方はお気軽にご相談ください。
電子契約はメリットが大きいですが一部デメリットも存在しますので、気になる方はこちらの記事や電子契約についてまとめた資料をダウンロードしてご覧ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)なお、クラウドサインでは、電子契約で実現するコスト削減の方法を知りたい方にぜひご一読いただきたい資料「業務プロセスの無駄をなくすには?電子契約の導入からスタートする戦略的コスト削減」をご用意しています。
DXの観点からある程度早期に効果を出す短期的なコスト削減を「契約書類・事務のデジタル化」からスタートし、成功させる方法を事例を参考にしながら解説していますので、以下のリンクからダウンロードの上、ぜひ参考にしてみてください。
無料ダウンロード


本資料では、DXの観点からある程度早期に効果を出す短期的なコスト削減を解説します。企業におけるDXをどのように始めようかお悩みの方はダウンロードしてご活用ください。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部