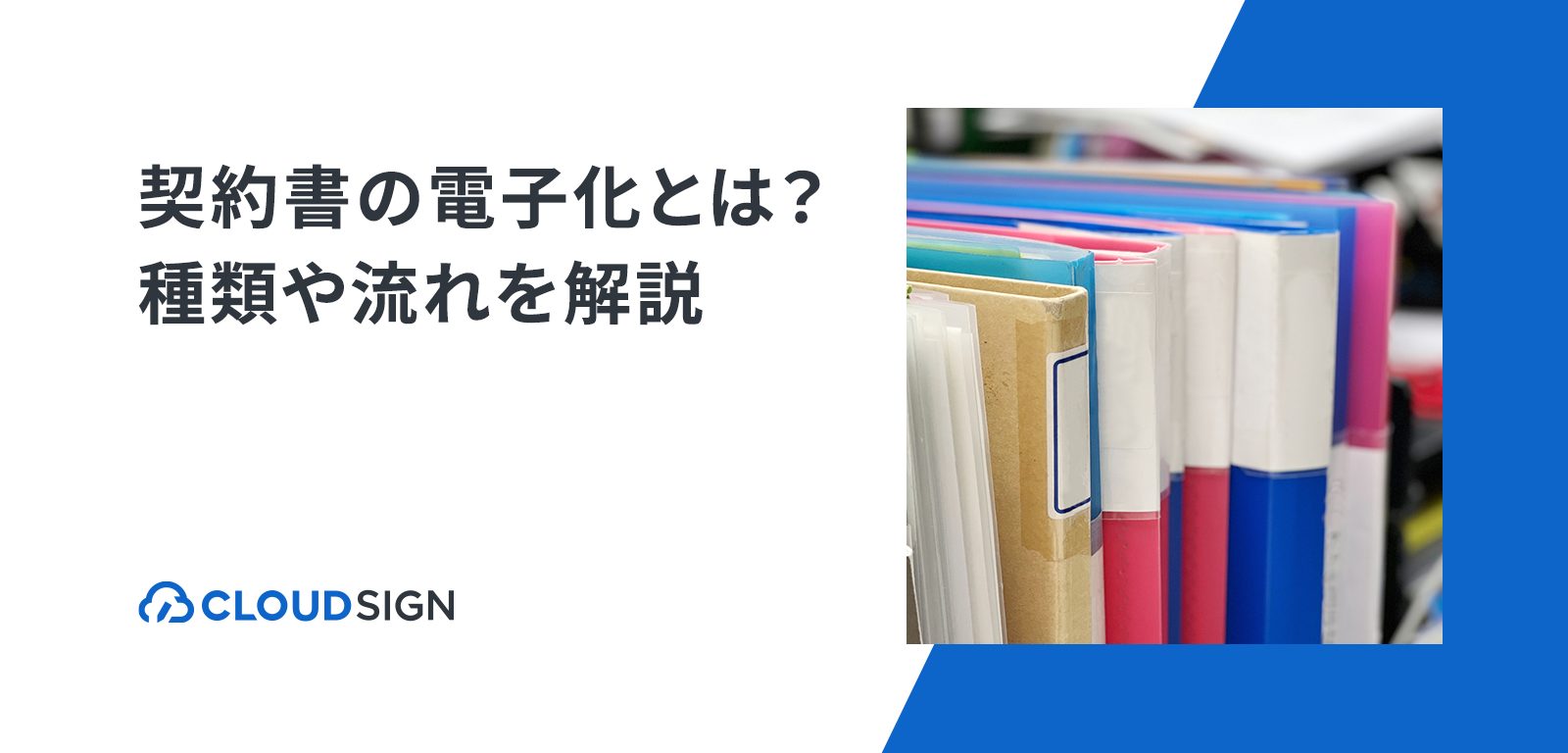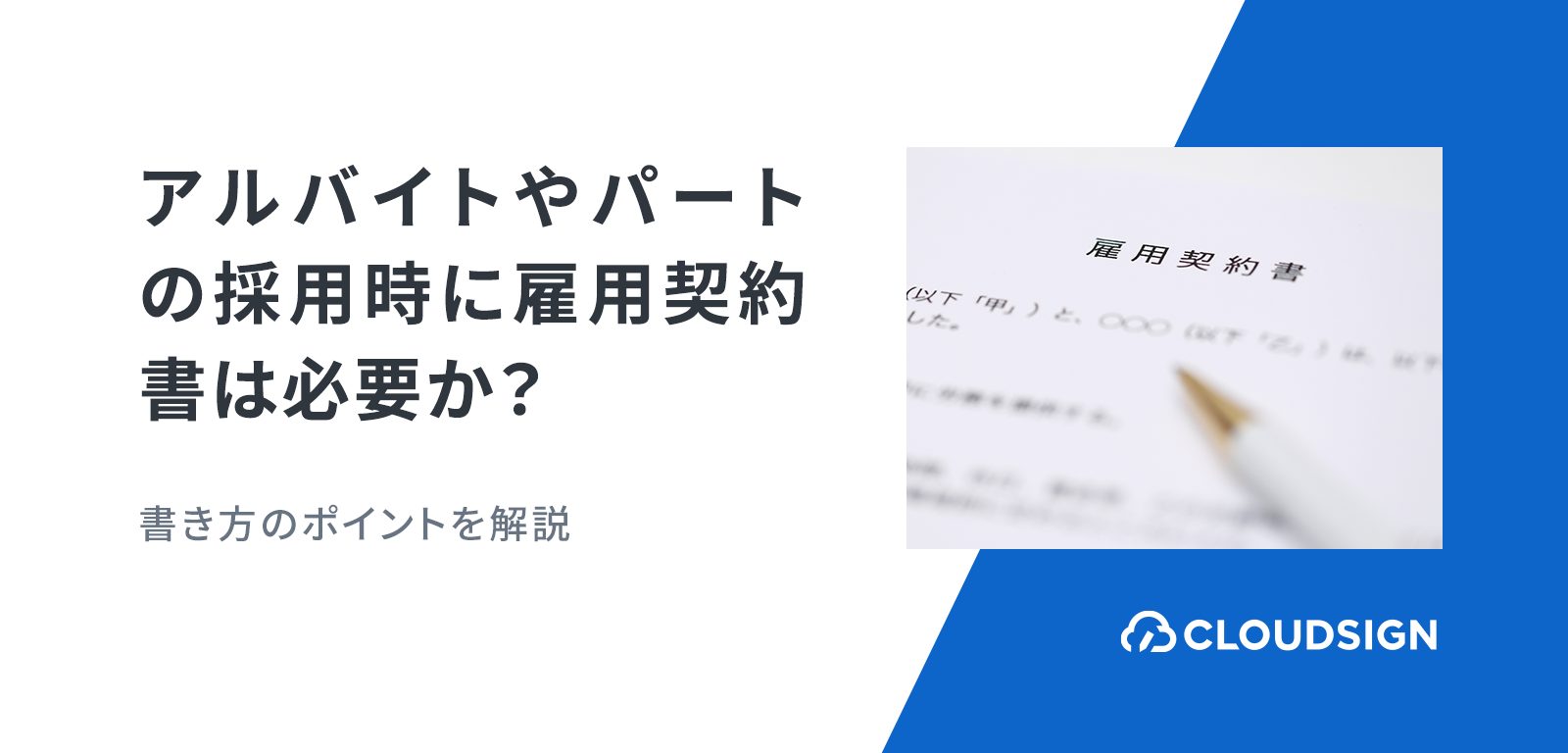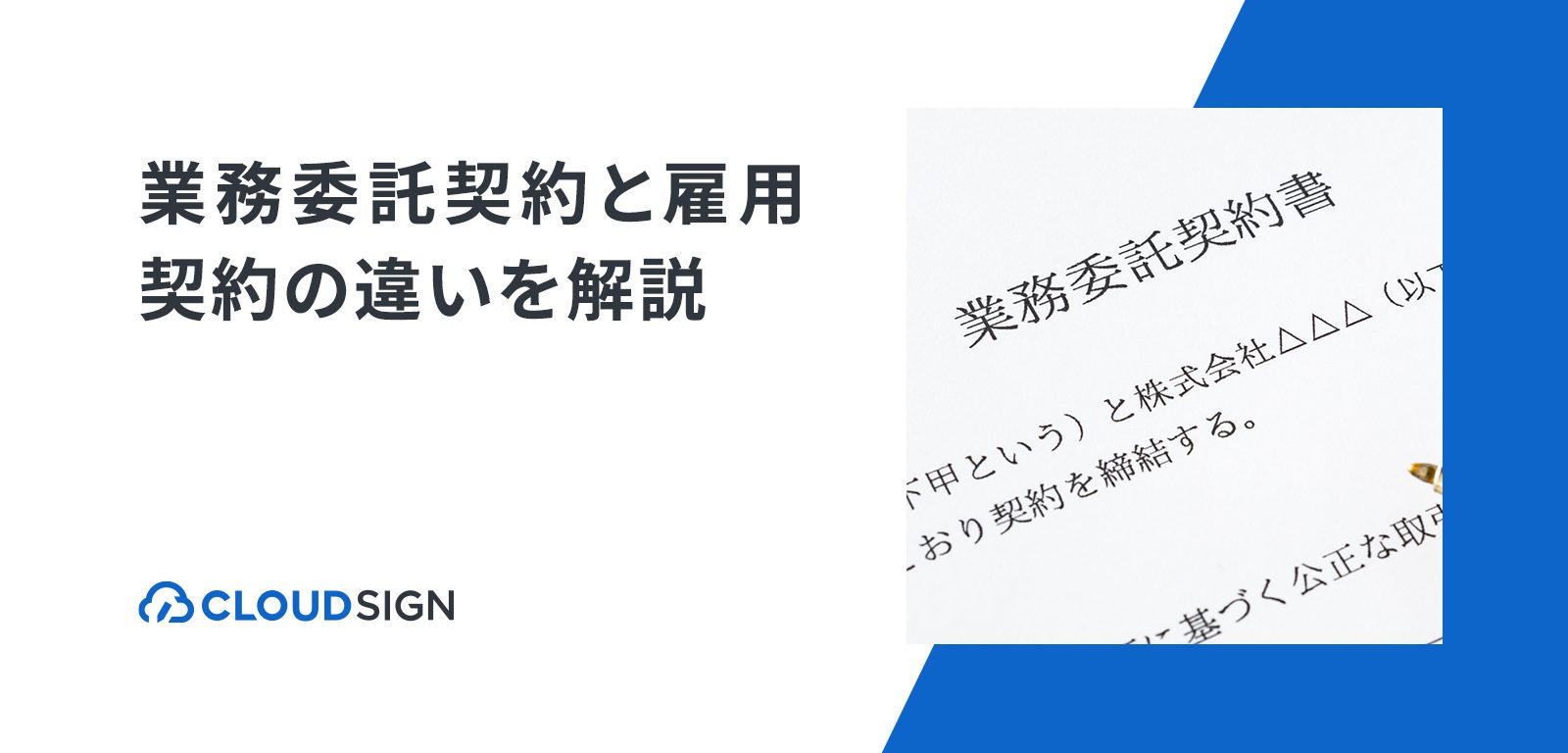採用内定通知書とは?法的効力や記載内容・送付時の注意点を解説
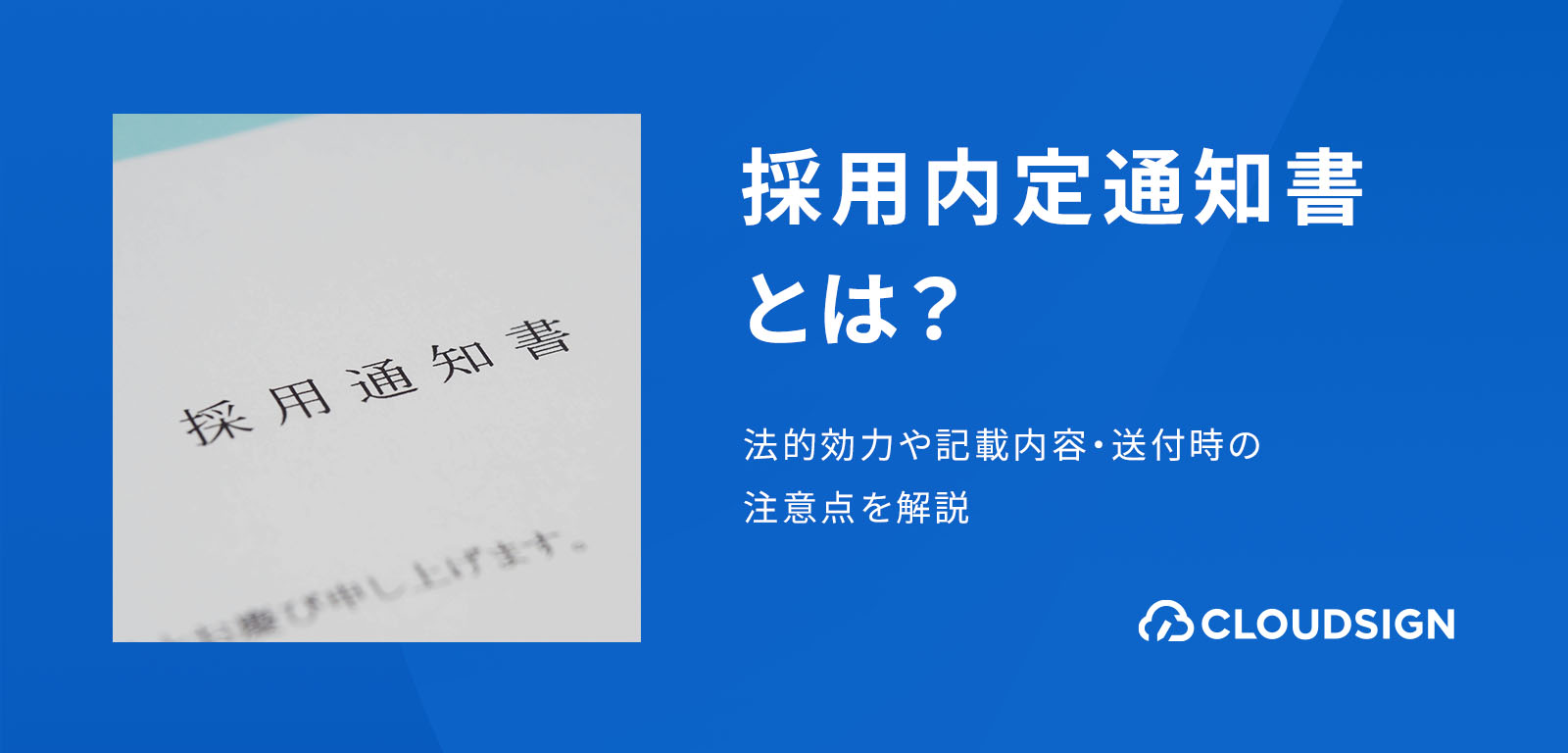
採用活動の終盤で企業から応募者へ送られるのが「採用内定通知書」です。内定を伝える大切な書類ですが、取り扱いを誤ると、法的トラブルに発展するおそれもあります。
たとえば、通知後の取り消しには慎重な対応が求められ、記載されている内容によっては労働契約が成立したと見なされることもあります。
この記事では、採用内定通知書の位置づけや法的な効力、記載事項、送付時の注意点を整理し、電子化による運用の効率化についても解説します。新卒や中途採用の準備を進めている方は、内定通知を適切に行なうためにご一読ください。
なお、採用内定通知書を電子化するなら、法的効力と実務性を兼ね備えた「クラウドサイン」の活用が有効です。クラウドサインは、採用通知書の作成・送信・署名の一連のプロセスをすべてオンラインで完結でき、紙での管理に比べて格段に手間を減らせます。電子契約について詳しく知りたい方はこちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)目次
採用内定通知とは
採用内定通知書は、企業が応募者に「内定」を正式に伝えるための書類です。法的に送付が義務づけられているわけではありませんが、内容を明確にし、トラブルを防ぐ目的で書面で交付するのが一般的です。
内定通知を受け、応募者が入社の意思を示した場合、企業とのあいだに「解約権留保付きの労働契約(=条件付き契約)」が成立すると見なされることがあります。
そのため、企業が内定後に一方的に取り消すと、正当な理由がない限り「解雇」とみなされ、解雇権の濫用と判断されるおそれがあります。
採用や内定に関する書類の意味や違い
採用活動では、複数の書類が使われます。それぞれに目的や効力があり、混同しないように違いを整理しておくことが大切です。
なお、内定後の入社手続きに必要な書類を詳しく知りたい方は下記記事も参考にしてみてください。
採用通知書
採用通知書は、「この応募者を採用します」と企業が一方的に伝える書類です。選考結果としての採用の意思表示であり、入社の条件や今後の連絡方法などが簡潔に記載されます。
ただし、採用通知書だけでは雇用契約が成立するわけではありません。あくまで「採用の意思がある」ことを伝えるもので、採用と見なされる可能性がある採用内定通知書とは性質が異なる点に注意が必要です。
内定通知書
内定通知書は、採用内定通知書とほぼ同じで、正式に内定を伝えるときに企業から応募者へ送付される書類です。
法的な役割などを見てもほとんど違いはありませんが、一般的には、「採用内定通知書」のほうが丁寧で形式的な表現として好まれる傾向があります。書類の名称よりも、記載内容や発行のタイミングが重要です。
内定承諾書
内定承諾書は、内定者が企業の内定を受け入れ、入社の意思を伝えるための書類です。企業によっては「内定誓約書」や「入社承諾書」といった名称を使うこともあります。
この書類を提出することで、企業と内定者のあいだに「労働契約の予約」が成立したと考えられますが、法的な効力が完全に発生するのは入社日以降です。
なお、内定が承諾された後に、企業側が内定を取り消す場合は、「経営悪化で採用枠がなくなった」「重大な経歴詐称があった」といった客観的に納得できる事情が必要です。
労働条件通知書
労働条件通知書は、従業員を採用する際に企業が交付すべき書類です。労働基準法第15条により、働くうえでの重要な条件を事前に書面で示すことが義務づけられています。
たとえば、契約期間・就業場所・給与・労働時間・休日・試用期間の有無などが、主な記載項目です。
なお、採用内定通知書は、内定を出したことを伝えるための書類であり、法的な交付義務はありません。一方、労働条件通知書は、実際に雇用契約が成立する際に交付が必要となる法定書類であり、役割もタイミングも異なります。
労働条件通知書の書き方を知りたい方やひな形を入手したい方は下記記事も参考にしてみてください。
雇用契約書
雇用契約書は、企業と従業員のあいだで労働条件を確認・合意したことを記録する書類です。契約自体は民法上、口頭でも成立しますが、労働契約法では「できる限り書面で確認すること」が望ましいとされています。
労働条件通知書が、企業から一方的に条件を伝えるものなのに対し、雇用契約書は双方が納得のうえでサインし、内容に合意したことを示す証拠になります。
法律上の義務はありませんが、条件の認識違いや入社後のトラブルを防ぐ目的で、実務では書面で取り交わすケースが一般的です。
雇用契約書の基礎知識や書き方を知りたい方は下記記事もご一読ください。
採用内定通知書の効力
採用内定通知書そのものには、法律上の発行義務や直接的な法的効力はありません。ただし、企業が内定通知書を交付し、応募者がそれを受けて入社の意思を示した場合、労働契約が成立したと見なされる可能性があります。
ここでは、採用内通知書が企業側、応募者側にどのような効力があるのかを説明します。
企業側|応募者が承諾した後の内定取り消しは不可
採用内定通知書には発行義務はありませんが、企業が何らかの方法で内定を伝え、応募者が入社の意思を示した時点で、法的には「始期付き・解約権留保付きの労働契約」が成立したとみなされます。
このため、応募者が承諾した後に企業が一方的に内定を取り消すことは、労働契約法第16条により、原則として認められていません。
取り消しが認められるのは、たとえば経歴詐称や重大な非行が判明した場合など、客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上も相当と認められる場合に限られます。
応募者側|応募者が承諾した後の内定取り消しは可能
内定通知書を受け取ったあと、応募者が入社の意思を示せば、企業とのあいだに労働契約が成立したと見なされます。そのうえで応募者が内定を辞退すること自体は、法律上認められています。
民法627条第1項では、雇用契約は「期間の定めがない限り、退職の申し出から2週間で終了できる」とされており、入社前の辞退もこの考え方に基づいて可能です。
ただし、これはあくまで法的な話であり、「気軽に辞退しても問題ない」という意味ではありません。企業は入社に向けて準備を進めているため、辞退する際はできるだけ早く、誠意ある対応を心がけることが大切です。
採用内定通知書を送る主な目的
採用内定通知書は、単に内定を伝えるだけでなく、入社意思の確認や人材確保、条件のすり合わせといった目的を持つ重要な書類です。
ここでは、その主な役割を整理します。
入社意思の確認
採用内定通知書は、内定の事実を明確に伝え、応募者の入社意思を正式に確認するための書類です。
口頭やメールだけでは行き違いが起きやすいため、書面にすることで企業の意思を正確に伝えられ、応募者も返答しやすくなります。
お互いの認識を揃えることで、後のトラブル防止にもつながります。
人材の早期確保
優秀な人材を確保するには、内定通知書をできるだけ早く、正式な形で送ることが効果的です。
選考後すぐに書面で内定を伝えることで、応募者に企業の本気度や誠意が伝わり、「この会社に決めよう」と感じてもらいやすくなります。
応募者の多くは複数社に同時応募しているため、通知が遅れると他社へ入社してしまう可能性があります。
トラブルの防止
採用内定通知書は、入社後のトラブルや認識のズレを防ぐためにも役立ちます。
通知書には、入社日や勤務地、給与などの労働条件が明記されており、口頭でのやり取りによる行き違いを避けることができます。
あらかじめ書面で条件を共有しておくことで、企業と応募者のあいだに誤解が生まれにくくなります。
採用内定通知書に記載すべき事項
内定通知書に明確な形式の決まりはありませんが、以下のような基本項目を記載するのが一般的です。
【採用内定通知書に記載すべき事項】
| 項目 | 内容 |
| 内定日・通知日 | 書類右上に記載。内定確定日または通知書送付日を明記 |
| 応募者氏名 | 左詰めで氏名を記載。履歴書に基づき正確に |
| 会社名・代表者名 | 企業名と代表取締役(または代表社員)の氏名を明記 |
| 内定の通知文 | 内定決定の旨を簡潔に伝える |
| 入社予定日 | 入社する予定の年月日を記載 |
| 労働条件 | 賃金、勤務時間、勤務地などの概要を記載 |
| 内定取り消し事由 | 入社に支障がある行為など、取消しの可能性を明記 |
| 提出書類・期限 | 必要な書類と提出期限、送付先などを記載 |
| 問い合わせ先 | 連絡事項があった場合の担当者情報を記載 |
新卒採用と中途採用では記載項目が異なる場合もあるため、採用内定通知書を作成する前に必要項目を確認しておくのがよいでしょう。
採用内定通知書を送る際の注意点
採用内定通知書は、単なる形式的な書類ではなく、後のトラブルを防ぐための重要な文書です。内容や送付のタイミング、運用方法に気を配ることで、スムーズな採用につながります。
正確・具体的な内容を記載する
内定通知書には、入社日・勤務地・仕事内容・雇用形態などをはっきり書くことが大切です。通知書に書かれた内容と実際の条件が違うとトラブルにつながることもあります。
誤解を防ぐためにも、事前にしっかり確認して、正しい情報を伝えましょう。
できるだけ早く送付する
採用内定通知書は、内定を出すと決まった段階で速やかに送付するのが基本です。送付の目安としては、面接通過から7〜10日以内がひとつの目安とされています。
通知が遅れると、応募者が他社への応募を進めたり、入社への意欲が下がってしまうこともあります。せっかく確保した人材を逃さないためにも、できるだけ早く通知書を送りましょう。
内定承諾書などとセットで運用する
内定通知書を送るだけでは、応募者が採用条件に同意したことにはなりません。
明確な意思確認を行うためには、「内定承諾書」や「入社誓約書」などをあわせて用意し、通知書に同封して返送を求める運用が有効です。
特に、条件面や就業意思の食い違いが後になって判明するケースもあり、文書で双方の合意を残しておくことでトラブルの予防につながります。採用に関する認識をすり合わせるうえでも、承諾書の運用は欠かせないステップです。
採用内定通知書を電子化するメリット
採用通知書を紙で送るケースもありますが、電子化には多くの利点があります。スピードやコスト、事務負担の面で、導入を検討する企業が増えています。
スピーディーに通知書を送れる
電子化の最大の利点は、通知書をすぐに送れることです。
紙の通知書では、印刷・封入・郵送といった手間がかかり、届くまでに数日かかることもありますが、電子通知であれば作成後すぐに送信でき、当日中に応募者へ届けることも可能です。
採用時期が迫っている場合や、複数名に一斉に通知したいときでも、すばやく対応できます。
やり取りに時間がかからないことで、応募者が他社に決めてしまうといった採用のチャンスを逃すことも防ぎやすくなります。
事務作業の負担を軽減できる
通知書を紙で運用していると、印刷・封入・郵送といった手間が都度発生し、担当者の作業負担が大きくなります。
とくに採用数が多い企業や選考のペースが早い企業では、事務対応が追いつかず、送付ミスや対応遅れのリスクも高まります。
電子化によってこうした作業を大幅に効率化できれば、本来注力すべき採用戦略や候補者対応に時間を割くことが可能になります。人事業務の質を落とさずに、全体の業務負担を軽くできる点も、電子化の大きなメリットといえるでしょう。
印刷費や郵送費を削減できる
通知書を紙で送る場合、印刷用紙や封筒、切手代など、件数が増えるほどコストも積み重なっていきます。さらに、書類の保管や管理にもスペースや人的コストがかかります。
こうした費用は一つひとつは小さく見えても、年間を通じてみると無視できない額になることもあります。
電子化することで、これらの印刷・郵送にかかるコストを大幅にカットでき、採用にかかる間接費の最適化にもつながります。とくに複数拠点で採用活動を行う企業にとっては、コスト削減効果がより実感しやすいでしょう。
採用内容通知書の電子化はクラウドサインがおすすめ
採用内定通知書を電子化するなら、法的効力と実務性を兼ね備えた「クラウドサイン」の活用が有効です。クラウドサインは、採用通知書の作成・送信・署名の一連のプロセスをすべてオンラインで完結でき、紙での管理に比べて格段に手間を減らせます。
タイムスタンプや閲覧履歴のログ機能が備わっており、誰が・いつ確認し、署名したかが記録に残るため、通知書の紛失・改ざんを防止でき、コンプライアンス強化にもつながります。
さらに、労働条件通知書のような書類の保存義務にも対応しており、電子帳簿保存法に準拠した形での長期保存も可能です。
社内の運用フローを統一し、人事担当者ごとのばらつきを抑えることで、トラブルや誤送信のリスクも軽減できます。採用業務の効率化と法令遵守を両立する手段として、クラウドサインの活用は非常に有効です。
なお、クラウドサインについて簡単にまとめた資料をご用意しておりますので、無料でダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)まとめ
採用内定通知書は、入社の意思確認や条件の明示といった役割を担う、採用プロセスの重要な一手です。記載内容が曖昧だったり送付が遅れたりすると、内定者との認識のずれや思わぬトラブルにつながるおそれがあります。
入社予定日や勤務地、雇用形態などは明確かつ正確に記載し、内定承諾書などとセットで運用することが大切です。
また、通知書の電子化によって、送付のスピード向上や業務負担の軽減、コスト削減が期待できます。さらに、改ざんや誤送信リスクを低減できる点から、法的リスクや情報漏えいリスクの対策にもつながり、コンプライアンス強化にも寄与します。
当社の運営する「クラウドサイン」は、採用内定通知書の電子化に対応したクラウド型の電子契約サービスです。導入社数250万社以上、累計送信件数 1000万件超の国内シェアNo1の電子契約サービスとして、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。
クラウドサインのような電子契約サービスを導入することで、電子署名を電子ファイルに施し、スピーディーかつ安全に当事者間の合意の証拠を残すことが可能になります。日々の採用業務を効率化したい方はぜひ電子契約サービスを導入し、書類の電子化を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、クラウドサインでは契約書の電子化を検討している方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)加藤 高明
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部