注文請書(発注請書)とは?注文書(発注書)との違い・記載事項・テンプレート・印紙税まで徹底解説

注文請書(発注請書)とは、受注側が業務を引き受ける際に、それを引き受けることを証明するために作成する文書のことを示します。
当記事では、注文請書と注文書(発注請書と発注書※)の違いや契約書の違いを説明した上で、注意すべきポイント、主な記載事項・印紙税等の作成コストについて解説します。
また、注文請書のひな形(テンプレート)を探している皆様のために、無料でダウンロードできるWordファイルも提供いたしますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
ひな形無料ダウンロード


クラウドサインでは注文書 兼 注文請書(発注書 兼 発注請書)のひな形をご用意しました。サービス等のお申し込みおよび承諾時に使える注文書 兼 注文請書(発注書 兼 発注請書)のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)目次
注文請書とは? 発注請書・注文書・契約書との違い
ここでは、注文請書の定義や、注文請書と発注請書、注文書や契約書との違い、注文請書の法的効力について詳しく解説していきます。
注文請書とは?
注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは、発注元の注文に対して、受注側がこれを引き受けたことを意思表示するために作成される文書をいいます。法的な作成義務はありませんが、発注内容について「言った」「言わない」といった後のトラブルを防ぐ役割があります。
通常、発注元が「注文書」を発行した後、その注文内容を引き受けたことの意思表示として受注者が「注文請書」を発行します。
発注者と受注者の情報や注文内容、数量、金額、納期などが記載されることが一般的です。
注文請書と発注請書の違い
注文請書と似たような言葉に「発注請書」(はっちゅううけしょ)があります。注文請書と発注請書はそれぞれほぼ同じ意味であり、法律上の違いはありません。このため、当記事では、注文請書(発注請書)と記載しています。
あえて違いを挙げるなら、一般的には商品など有形のものを受け取る際には「注文請書」を用いて、サービスなど無形のものを受け取る際には「発注請書」を用いるケースが多いです。
注文請書と発注請書のどちらの名称を用いても法律上問題はありませんが、企業内や取引先同士で表記揺れがあると、混乱を招く恐れがあります。チームやプロジェクトごとにどちらの名称を用いるか統一するようにしましょう。
注文請書と注文書の違い
注文請書と注文書との違いは、作成する主体や、作成する目的にあります。
注文請書が受注側の意思表示をする文書であるのに対し、注文書は商品やサービスなどを注文する際に、発注者側が発行する文書です。
商品またはサービスの数量や納期、金額などを記載し、「たしかに注文を行った」という意思表示のために発行します。
両者の違いをまとめると次のとおりになります。
注文請書と注文書の違い
| 注文請書 | 注文書 | |
| 作成する主体 | 受注側 | 発注側 |
| 作成する目的 | 注文を引き受けたという意思表示をし、その証拠とする | 注文をしたという意思表示をし、その証拠とする |
なお、注文書がどのような書類なのかや他の書類との違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご一読ください。
注文請書と契約書の違い
契約書は双方の合意のもと作成し、双方が署名押印することによって契約の成立を証明する文書となります。対して注文書・注文請書は、発注側や受注側の一方的な意思表示のために発行する書類であるという違いがあります。
注文請書は、先述してきたように受注者が相手方に対して「注文を受ける」という意思表示を示す文書です。
一方、契約書は発注者と受注者双方の「商品・サービスの注文をする」「商品・サービスの注文を受ける」という意思を表す文書です。
注文請書に法的効力はあるのか
民法上、契約は申し込みと承諾によって成立するため、注文書が発行された上で注文請書が発行されることで、注文者と受注者の間に売買契約などの契約が成立します。このため、注文請書の発行は契約成立を明確にする上で非常に重要です。注文書・発注書の発行のみで、相手側の了承を取らずに契約が成立することは基本的にありません。
また、下請法では、親事業者が下請事業者に製造委託等をした場合、ただちに下請事業者に一定事項を記載した発注書や注文書を交付する義務があります。下請法の適用がある場合には、この発注書や注文書には、注文内容や金額などを記載する必要があることになります。
下請法の違反があった場合には、公正取引委員会による勧告や指導を受けることがあります。場合によっては、罰金を科される可能性もあるので注意しましょう。
無料ダウンロード


下請事業者(中小受託事業者)と取引をしている企業様の間で、意図せず下請法に抵触してしまう事例は少なくありません。そこで本資料では、下請法の中でも特に違反が生じやすい項目をチェックリスト形式でまとめました。本チェックリストを活用することで、下請法違反のリスクを早期に発見し、未然に防ぐことができます。ぜひダウンロードし、ご活用ください。
注文請書を発行するメリット・デメリット
受注者側は、注文書を受け取った後、注文の受諾を口頭で意思表示することでもよく、必ずしも注文請書を発行しなければならないわけではありません。
しかし、注文請書を発行することで、企業間のやり取りに関するトラブルを防げるというメリットもあります。
ここでは、注文請書を発行するメリット、発行しないリスク、リスクに対する打ち手を詳しく解説していきます。
注文請書を発行するメリット
あらためて注文請書を発行するメリットをまとめると、次のようになります。
注文請書を発行するメリット
- 契約の成立を明確にし、トラブルを防止する
- 業務フローを可視化し、取引を円滑に進める
また、注文書や注文請書には、契約書と違っていちいち製本する必要がなく、取引にまつわる書類の作成を効率化できるというメリットもあります。
基本的に、注文請書や発注請書を作成するメリットは、注文書や発注書を作成するメリットと同様なので、詳しくはこちらの記事もご覧ください。
注文書・注文請書を発行しないリスク
注文書・注文請書を発行しない最大のリスクは、契約の成立や契約条件があいまいになり、トラブル発生時にそれぞれの主張を証明する手立てがなくなることです。
注文書・注文請書を発行しないということは、書面(証憑)が存在しないということであり、口頭で合意した内容は証明が困難です。そのため、契約内容について、発注側と受注側で認識のずれが生じやすくなるということです。
もし、この認識のずれが大きくなってしまった場合、結果的として「商品が納品されない」「代金が支払われない」といった事態に陥るリスクがあるということになります。
こうしたリスクを避けるためにも、注文書・注文請書の発行は取引において非常に重要な手続きであることを認識しておきましょう。
また、より高額な取引や重要な取引の場合には、注文請書だけでなく、契約書を作成することが推奨されます。
注文請書に記載すべき事項
注文請書には、注文書に記載された契約条件で受託したことがわかるよう、注文書の記載内容と同じ事項を記載しましょう。
なお、注文書の記載事項は、下請法第3条に必要的記載事項として定められている12項目が参考になります。下請法の適用のない契約でも、契約条件を明確にするため、3条書面の必要的記載事項を参考にするのがよいでしょう。
下請法第3条上には、必要記載事項として次の12項目が記載されています。
-
- <3条書面に記載すべき具体的事項>
- 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)
- 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
- 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう,明確に記載する。)
- 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間)
- 下請事業者の給付を受領する場所
- 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期日 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが,算定方法による記載も可)
- 下請代金の支払期日
- 手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
- 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
- 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
- 原材料等を有償支給する場合は,品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日,決済方法
出典:公正取引委員会公式サイト
下請法は、もともと下請事業者とのトラブル防止のために制定された法律です。下請取引に該当しない契約であっても、これらを明文化して定めておくことにより、トラブルを回避するのに役立ちます。
なお、注文書・注文請書を作成する際、次のような注意点もあります。
- 「備考欄」記載事項に潜むリスク
- 保管忘れに注意
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
注文請書の書式とテンプレート(ひな形)
注文請書を作成する時は、上述の書き方・記載項目および以下を参考にしながら 自社の書式とテンプレート(ひな形)を作成しておくと便利 です。
なお、クラウドサインでは電子契約の締結にも適した「注文書兼注文請書のひな形」を無料配布しております。入手したい方は下記のダウンロードフォームから必要情報を入力の上、ダウンロードしてご活用ください。
ひな形無料ダウンロード


クラウドサインでは注文書 兼 注文請書(発注書 兼 発注請書)のひな形をご用意しました。サービス等のお申し込みおよび承諾時に使える注文書 兼 注文請書(発注書 兼 発注請書)のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)そのほかにも、以下のようなサイトから注文書のテンプレート(ひな形)をダウンロードできます。
- 公正取引委員会による発注書書式
- ビジネス文書のテンプレートサイト
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
注文請書の保管方法と保管期間
注文書や注文請書の保存期間は、税法上は原則7年です(法人税法施行規則59条1項柱書、67条2項)。欠損金が生じる事業年度については、保存期間が10年に延長されます(法人税法施行規則26条の3第1項)。
一方、会社法には、「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。」という定めがあります(会社法432条2項)。
一般的には、日常の取引の注文書や注文請書は「事業に関する重要な資料」とまではいえず、税法上の保存期間をクリアすれば足りる(そのための法人税法である)と考える企業が多いでしょう。
しかし、注文書や注文請書を「事業に関する重要な書類」と考える場合、会社法上の規定に忠実に、10年保存を原則にするという考え方も十分にあり得ます。
注文請書の保管期限については、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
注文請書と印紙税
注文請書を作成し実際に取引先に対して発行する場合、印紙税を納付するための収入印紙の添付が必要となる場合と必要ない(印紙税が非課税・不課税となる)場合があります。
以下、その判定基準を確認しましょう。
収入印紙を貼付すべきは注文請書
まず、注文書と注文請書により取引を行う場合、収入印紙を貼付する必要があるのは注文請書のみ です。
注文請書は、注文書によって契約の申込みを受けた当事者がその申し込みを承諾した事実を証明する目的で作成し、注文者に交付するものです。こうして作成され交付される注文請書は、常に「契約の成立を証明する契約書」すなわち課税文書となる可能性があります。
一方で、注文書を作成した段階では契約は成立していないため、通常発注書は課税文書とはなりません。
売買か請負かを確認
次に、売買の発注請書か、請負の発注請書かで、収入印紙の要否と金額が変わります。
モノ(動産)を売買するための注文請書の場合、原則として収入印紙による印紙税の納税は必要ありません。ただし、印紙税法が規定する「土地、建物、借地権、著作権、船舶、航空機」の売買を行う際の注文請書は、第1号文書に該当し、所定の印紙を貼る必要があります(特定の業界に限定されるため、ここでは割愛します)。
サービス(仕事)の提供を請け負い、それが仕事の完成に重きを置く請負契約の注文請書の場合は、原則として第2号文書に該当し、記載された契約金額に応じて下表の収入印紙による納税の必要があります。
貼付すべき収入印紙の金額は、注文書・注文請書に記載された契約金額によって変化します。
| 記載された契約金額 | 税額 |
| 1万円未満のもの | 非課税 |
| 1万円〜100万円以下 | 200円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超〜以下 | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
第2号文書の「請負」に該当するかどうかの基準は、印紙税法基本通達の「別表第1 第2号文書」において、以下の通り例とともに詳細に記載されています。
(請負の意義)
1 「請負」とは、民法第632条《請負》に規定する請負をいい、完成すべき仕事の結果の有形、無形を問わない。 なお、同法第648条の2《成果等に対する報酬》に規定する委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約する契約は「請負」には該当しないことに留意する。(平18課消3-36、令2課消4-16改正)
(請負に関する契約書と物品又は不動産の譲渡に関する契約書との判別)
2 いわゆる製作物供給契約書のように、請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書又は不動産の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物品又は不動産の譲渡に重きをおいているかによって、そのいずれであるかを判別するものとする。
なお、その具体的な取扱いは、おおむね次に掲げるところによる。(昭59間消3-24改正)
(1) 注文者の指示に基づき一定の仕様又は規格等に従い、製作者の労務により工作物を建設することを内容とするもの 請負に関する契約書 (例)家屋の建築、道路の建設、橋りょうの架設
(2) 製作者が工作物をあらかじめ一定の規格で統一し、これにそれぞれの価格を付して注文を受け、当該規格に従い工作物を建設し、供給することを内容とするもの 不動産又は物品の譲渡に関する契約書 (例)建売り住宅の供給(不動産の譲渡に関する契約書)
(3) 注文者が材料の全部又は主要部分を提供(有償であると無償であるとを問わない。)し、製作者がこれによって一定物品を製作することを内容とするもの 請負に関する契約書 (例)生地提供の洋服仕立て、材料支給による物品の製作
(4) 製作者の材料を用いて注文者の設計又は指示した規格等に従い一定物品を製作することを内容とするもの 請負に関する契約書 (例)船舶、車両、機械、家具等の製作、洋服等の仕立て
(5) あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするもの 物品の譲渡に関する契約書 (例)カタログ又は見本による機械、家具等の製作
(6) 一定の物品を一定の場所に取り付けることにより所有権を移転することを内容とするもの 請負に関する契約書 (例)大型機械の取付け
ただし、取付行為が簡単であって、特別の技術を要しないもの 物品の譲渡に関する契約書 (例)家庭用電気器具の取付け
(7) 修理又は加工することを内容とするもの 請負に関する契約書 (例)建物、機械の修繕、塗装、物品の加工
電子契約(電磁的方法)なら収入印紙は不要・保管の手間もなし
書面(紙)で発行した注文請書は課税文書に該当しますが、電子契約等電子ファイル(電磁的方法)で発行した場合には印紙税が発生しません。
印紙税法の第3条第1項には、「文書(略)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」との規定があるのですが、電子契約を締結することは、この課税文書の「作成」に該当しないためです。
詳しくはこちらの記事で解説していますので参考にしてみてください。
また、クラウドサインのようなクラウド型の電子契約を利用していれば、締結後は自動的にクラウド上に保存され、紛失リスクもなく安心です。
当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」はアップロードとメール送信のみで契約締結までの作業を完了することができます。さらに、書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がないため、取引相手に準備の負担がかかることなく契約締結が可能です。
この機会にぜひ電子契約サービスを導入し、発注書(注文書)の電子化を進めることでペーパーレス化・DX化を推進してみてはいかがでしょうか。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)<参考文献>
- 近藤圭介『業務委託基本契約書作成のポイント(第2版)』(中央経済社、2022)
- 佐藤明弘編『印紙税実用便覧』(法令出版、2021)
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
こちらも合わせて読む
-
電子契約の基礎知識
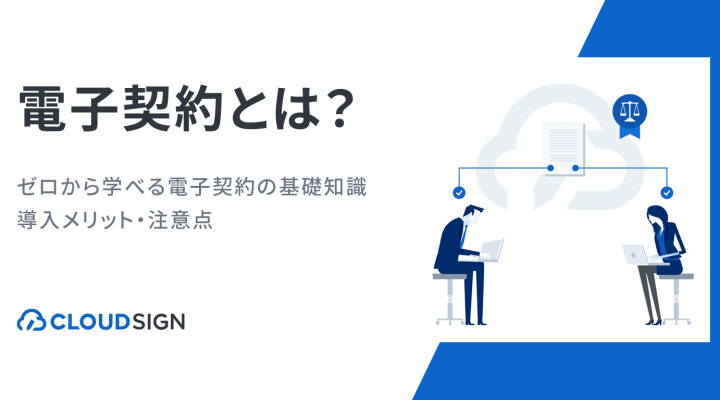
電子契約とは?仕組みと導入のメリットや注意点をわかりやすく解説
電子署名法民法電子署名電子帳簿保存法事業者署名型(立会人型)電子契約サービスQ&A -
契約実務
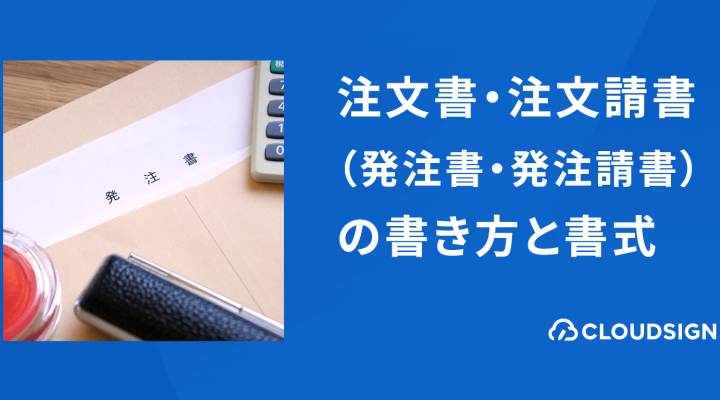
発注書・発注請書(注文書・注文請書)の書き方と書式|テンプレートあり
契約書ひな形・テンプレート発注書 -
契約実務
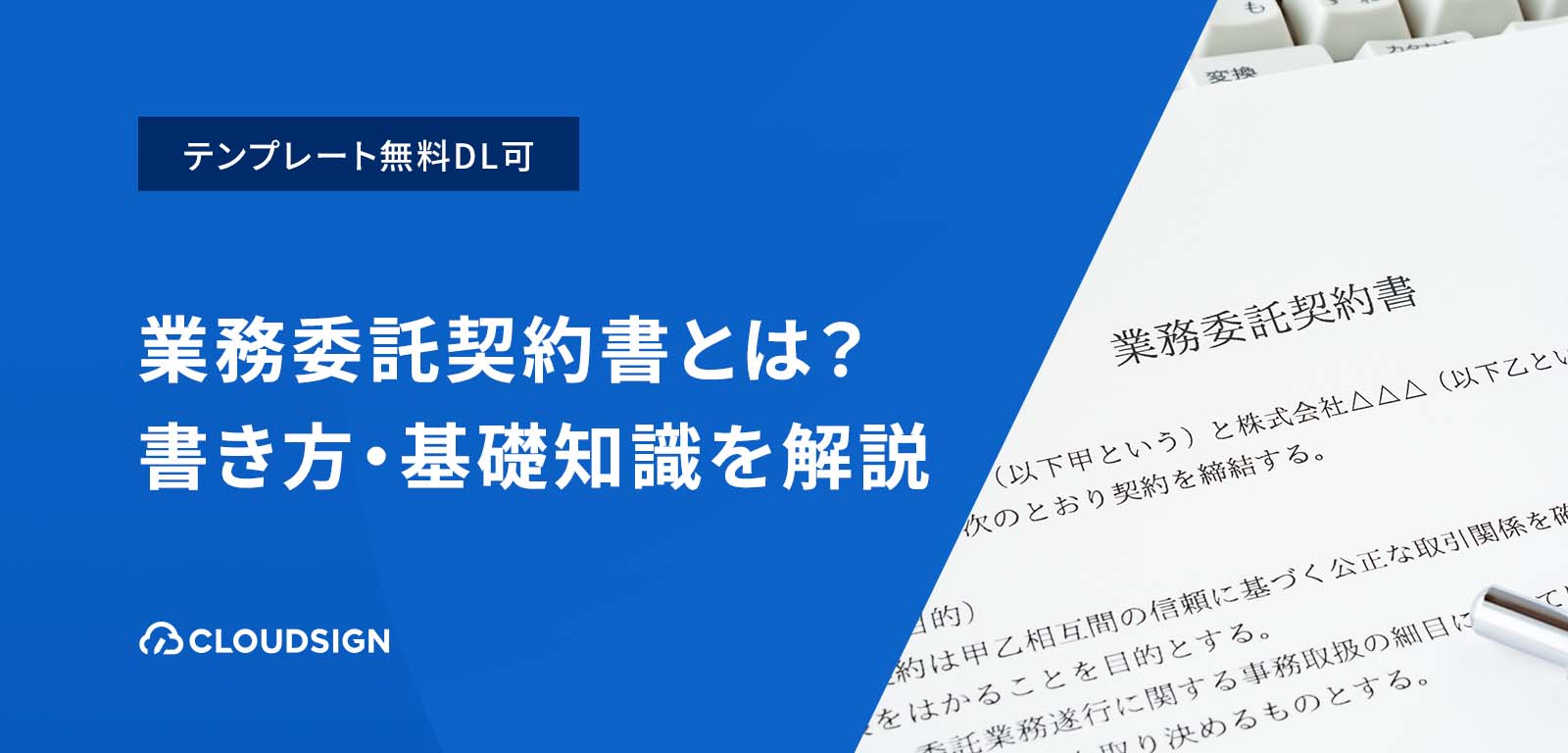
【無料DL可】業務委託契約書とは?テンプレート付きで書き方と基礎知識を徹底解説
コスト削減契約書ひな形・テンプレート業務委託契約書 -
電子契約の運用ノウハウ
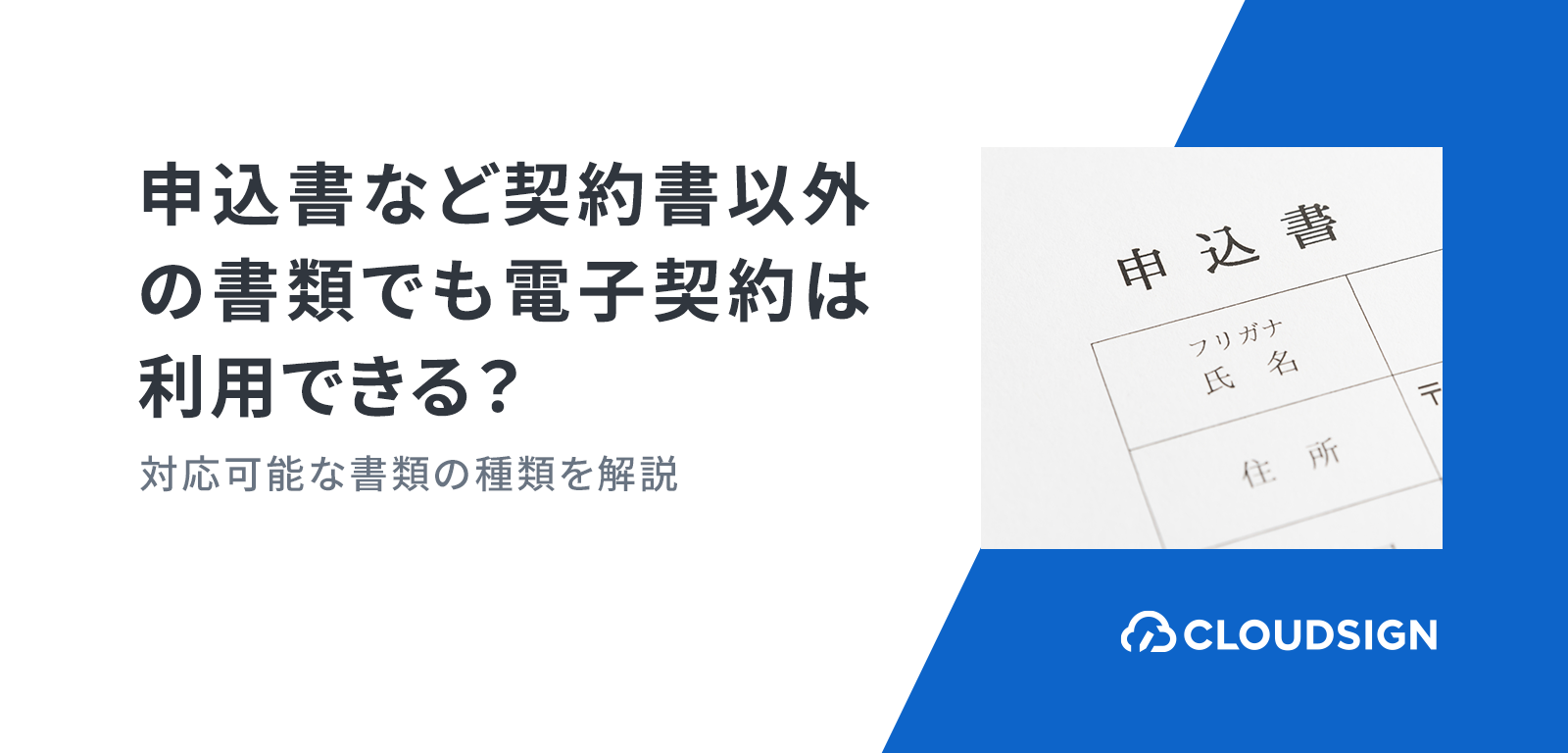
申込書など契約書以外の書類でも電子契約は利用できる?対応可能な書類の種類を解説
電子契約の活用方法 -
業務効率化の成功事例まとめ

紙も電子もクラウドで 契約書のデジタル化・管理効率化に成功した事例4選
契約書管理インタビューコスト削減業務効率化 -
契約実務
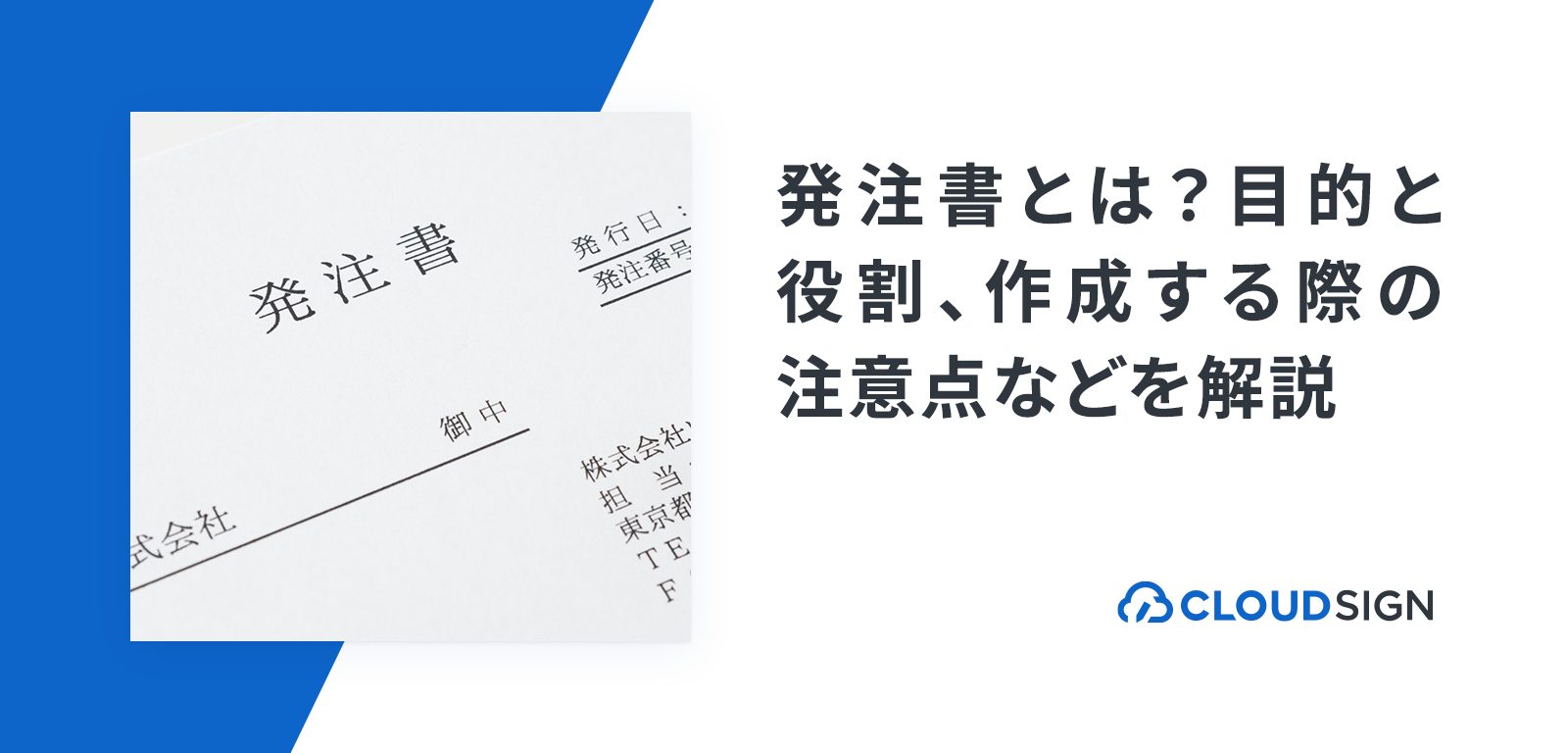
発注書とは?目的と役割、作成する際の注意点などを解説
契約書ひな形・テンプレート業務効率化発注書 -
契約実務
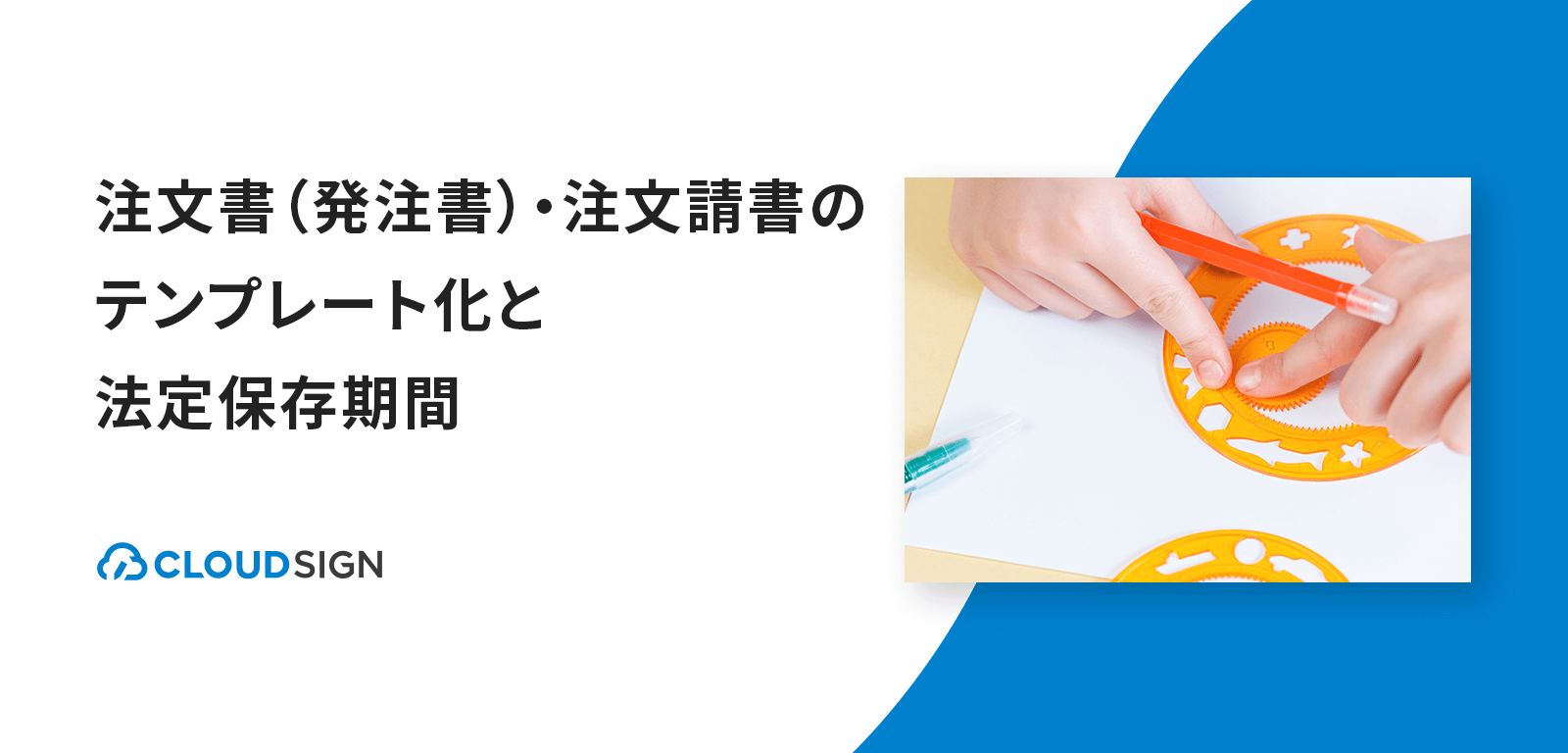
注文書(発注書)・注文請書のテンプレート化と法定保存期間|Word版ひな形ダウンロード付
発注書 -
契約実務
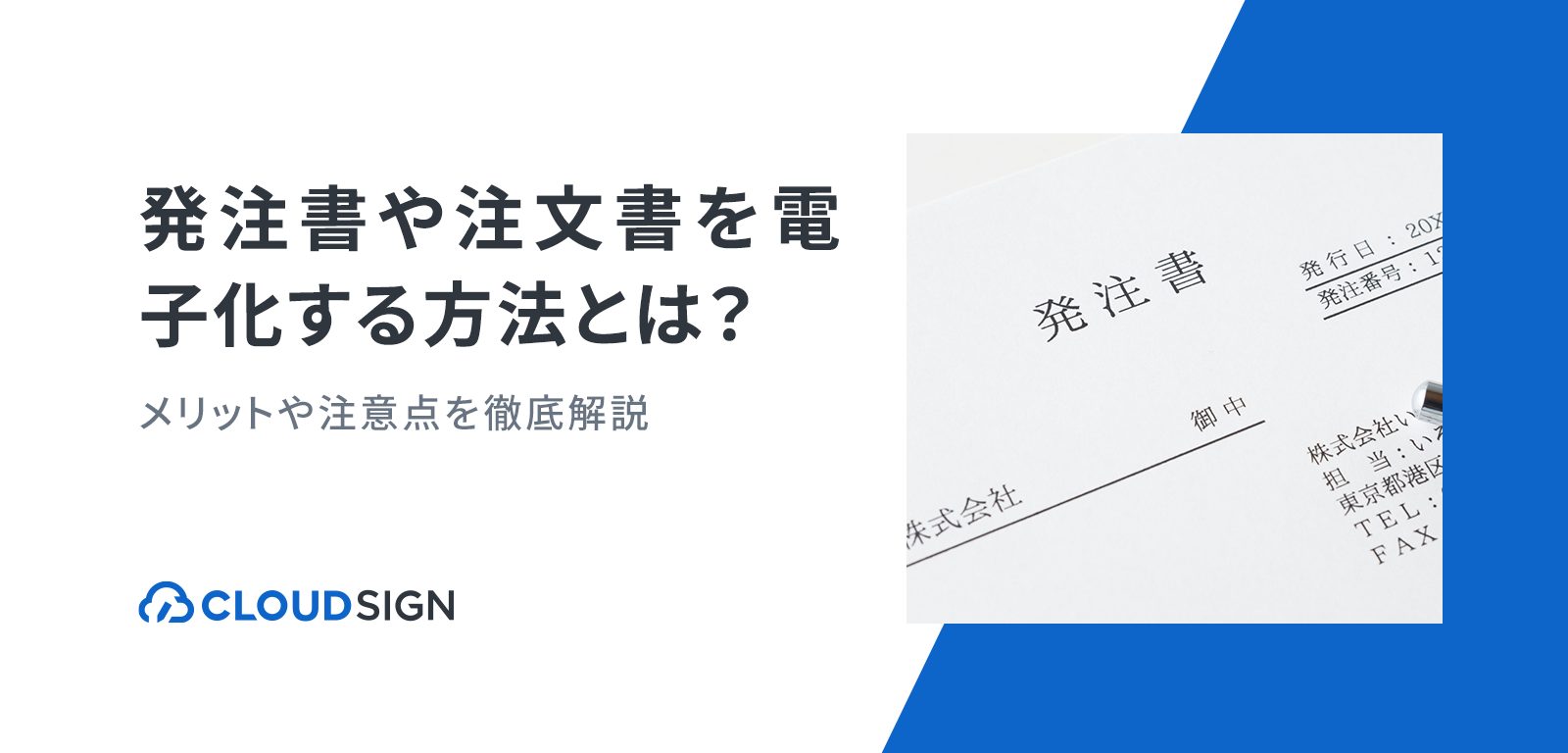
発注書や注文書を電子化する方法とは?メリットや注意点を徹底解説
契約書ひな形・テンプレート業務効率化発注書 -
契約実務
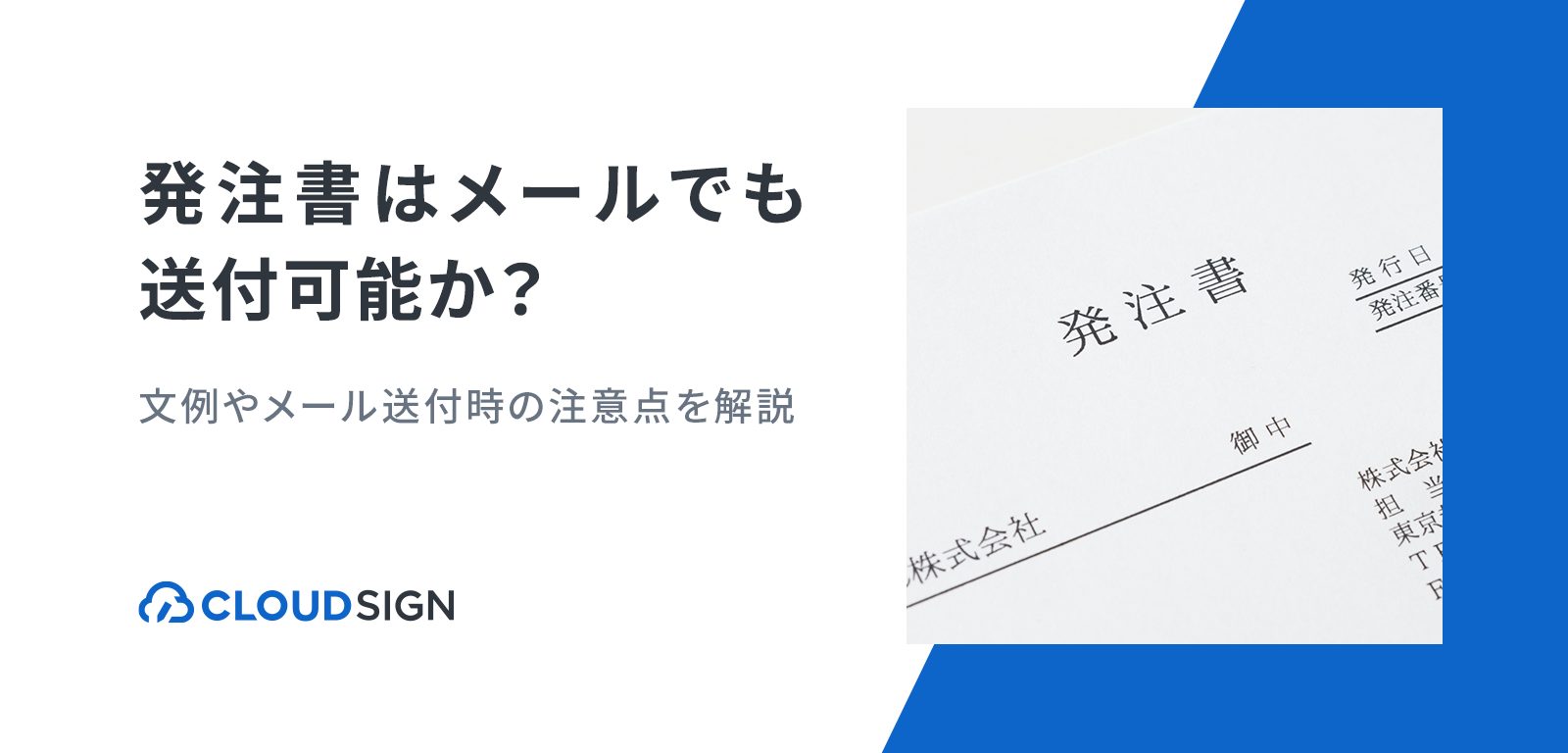
発注書はメールでも送付可能か?文例やメール送付時の注意点を解説
契約書ひな形・テンプレート発注書 -
リーガルテックニュース
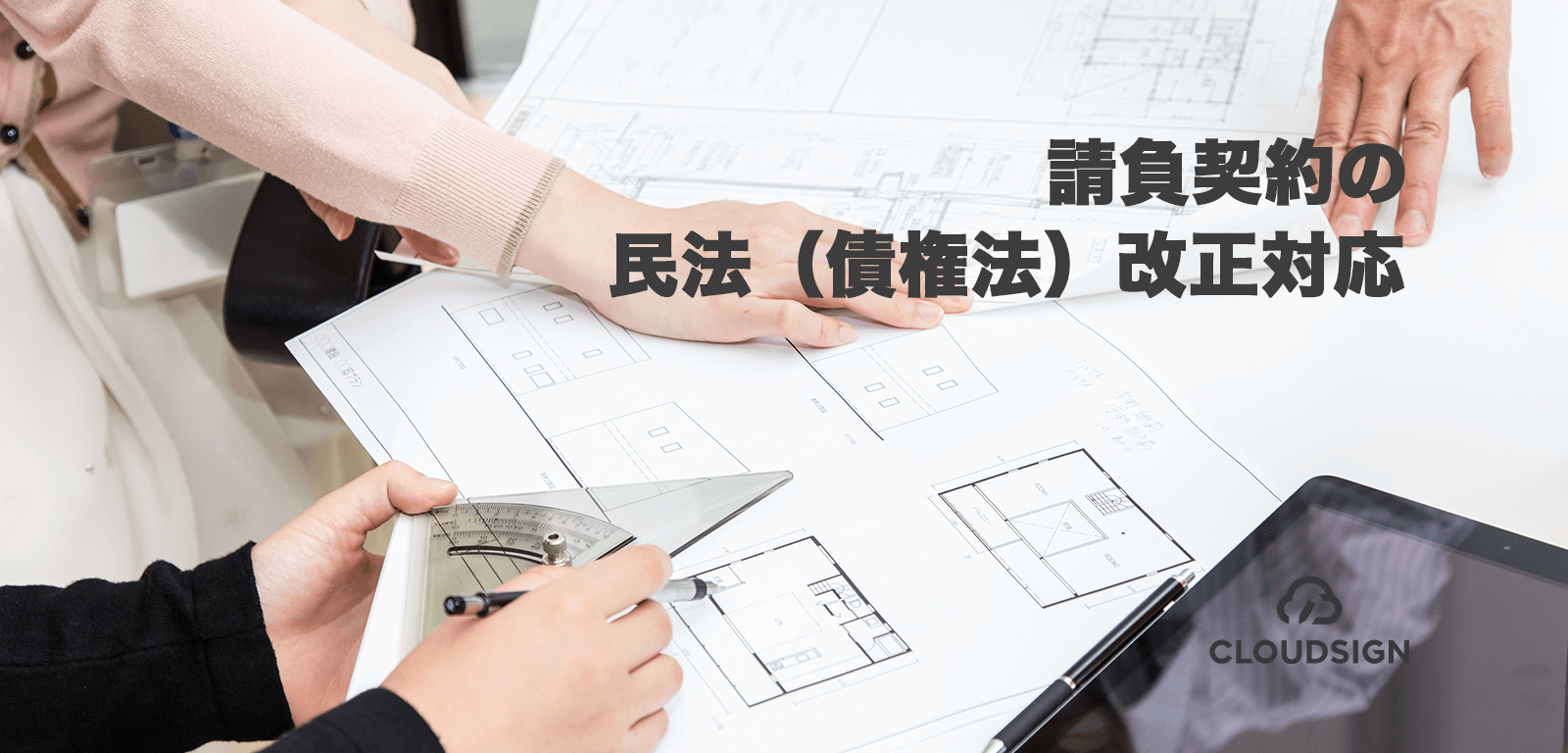
請負契約の民法(債権法)改正対応
法改正・政府の取り組み契約書民法請負契約