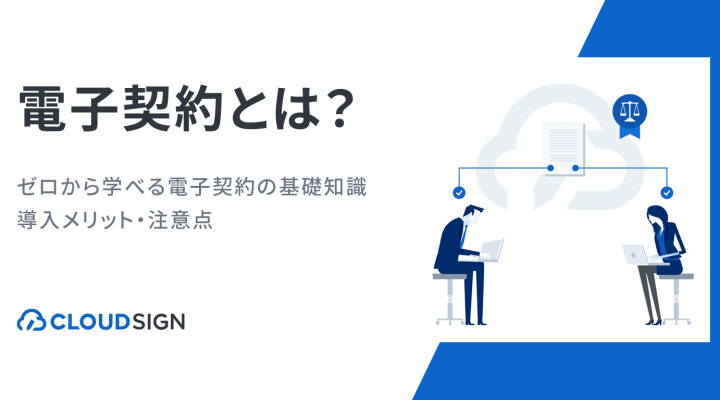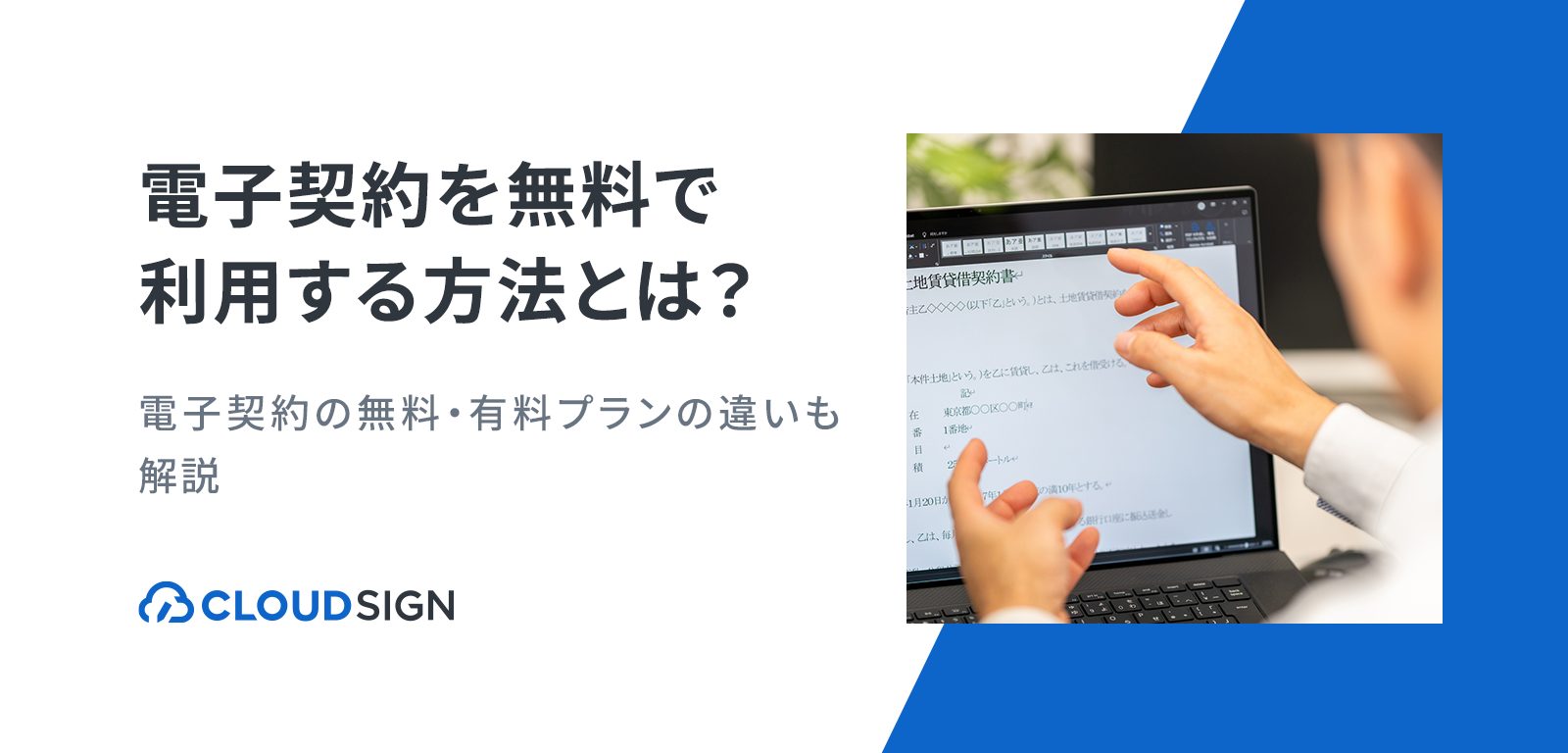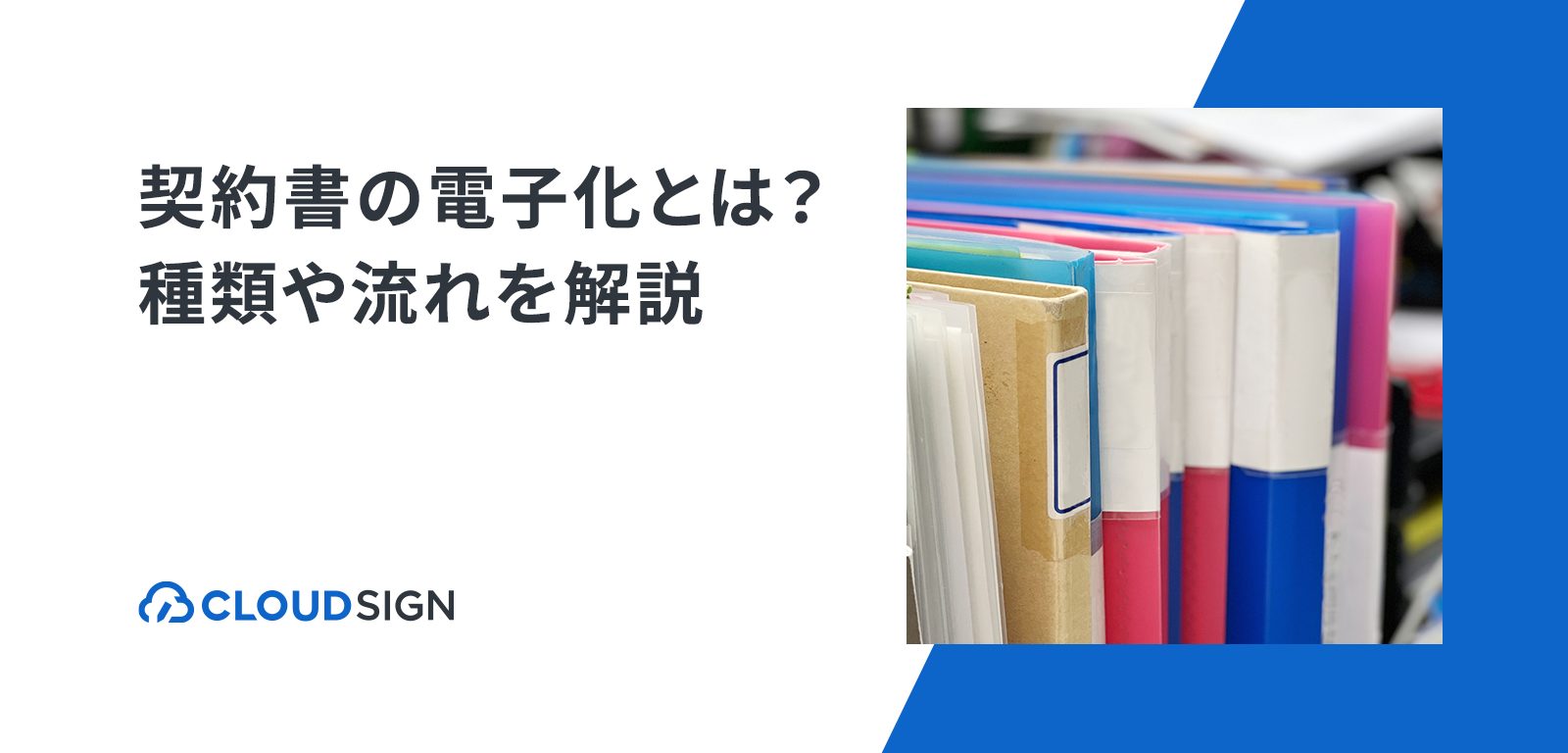契約とは?契約の基礎知識と重要ポイントを解説

契約は、個人や企業が法的な約束を交わすための重要な手段です。そもそも契約とはどのようなものなのか理解することは相手方とのトラブルを未然に防ぐためにも欠かせません。
この記事では、契約の基本的な知識から、その重要なポイントまでわかりやすく解説します。契約の基本的な内容を確認し、今後の契約締結業務に役立てていきましょう。
目次
契約とは何か?基本的な意味と重要性
契約とは、簡潔に言うと「当事者間の意思表示が合致することで成立する約束」のことです。民法522条1項では、契約が成立する条件を下記の通り定めています。
【民法522条1項】
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-GOV 法令検索
身近な例で例えるとするならば、「このリンゴを100円で売ります」という売り手の意思表示に対して、「このリンゴを100円で買います」という買い手の意思表示が合致することで売買契約が成立します。
契約の重要性は、相手との関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐことにあります。契約が存在することで、双方の権利と義務が明確になり、信頼関係の構築が可能になります。契約の役割を理解することは、健全な取引関係を築くための第一歩です。

ビジネスシーンにおいて適切な契約締結が健全な取引関係の鍵を握る
なお、契約は書面を残さずに口頭だけで約束した場合でも成立します(民法522条2項)。書面の契約書を締結する意味については次項を参考にしてみてください。
契約書を締結する意味とは
契約書を締結することは、口頭での約束を法的に裏付けるための重要な手段です。契約書は、合意内容を文書化し、後の誤解や紛争を避けるための証拠となります。
契約書があることで、双方の合意内容が明確になり、責任の所在がはっきりします。これにより、契約違反が発生した際に、法的な措置を取る際の基盤となります。さらに、契約書は信頼性を高め、ビジネスパートナーシップの強化にも寄与します。
契約自由の原則とは
民法では、公序良俗(公の秩序・善良の風俗) 等に反しない限り、だれを相手に、どのような内容の契約を、どのような方式で行おうと自由であるとしています。当事者間で結ばれた契約に対しては、国家は干渉せず、その内容を尊重しなければなりません。
このルールは「契約自由の原則」と呼ばれています。
契約自由の原則は、以下の4つの自由で構成されます。
- 契約締結の自由
- 相手方選択の自由
- 内容決定の自由
- 方式の自由
各項目の詳細を確認しておきましょう。
契約締結の自由
契約締結の自由とは、契約を締結すること自体が自由であるということです。つまり、契約を結ぶかどうかの選択が個人に委ねられており、裏を返せば誰とでも契約を結ぶ義務がないことを意味します。
相手方選択の自由
相手方選択の自由は、契約を結ぶ際に誰を相手に選ぶかを自由に選択できる権利です。これは、取引相手を選ぶ際に、個人の判断に基づいて相手方を選択できることを意味します。
例えば、商品を購入する際に、どの店から購入するか、誰から購入するかを自由に選択できます。
なお、「相手方」には個人だけでなく、企業や団体・組織も含まれます。
内容決定の自由
内容決定の自由とは、契約の具体的な内容を自由に決めることができる権利です。契約の条件や条項を契約の当事者間で交渉し、合意に基づいて決定することが許されています。
たとえば、売買契約においては「製品Aを5,000円で売る(または買う)」「サービスBを1年間提供する(または提供を受ける)」といったさまざまな内容が含まれますが、これらの条件を自由に決定し、選択することができます。
方式の自由
方式の自由とは、契約を書面で締結するか、口頭で締結するか等、契約締結の方式を自由に決定することができることを意味します。
例えば、友人同士の貸し借りにおいて、口頭での約束のみで契約するのか、契約書や覚書を締結するのかを自由に決定できます。
ただし、契約の種類によっては法律で特定の形式があらかじめ決められている場合もあるため、契約前に関連する法令を確認しておくのがよいでしょう。
契約自由の原則の例外
個人が自由に契約を締結できる権利を保障するための「契約自由の原則」には、いくつかの例外もあります。契約を結ぶ当事者の関係性には「雇用主と労働者」「事業者と消費者」のように、必ずしも対等な関係とはいえないケースがあり、力関係が上の者に有利な契約を結んでしまうと、一方が大きな不利益を被る可能性があるためです。
ここでは、「公序良俗」と「強行法規(強行規定)」という2つの例外を解説します。
公序良俗
公序良俗とは、「公共の秩序や善良な風俗」を意味し、社会一般で通用する常識やルールのことをいいます。契約内容等が社会的な妥当性を欠く場合、当事者あるいは第三者の権利を侵害する恐れがあることから、民法90条により公序良俗に反する契約は無効です。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-GOV法令検索
公序良俗に反する例として挙げられる行為・契約内容は次の通りです。
- 高利貸しなどの暴利行為
- 愛人契約のような倫理に反する行為
- 金銭の支払いを対価として犯罪の実行を要求する行為 など
なお、公序良俗違反になるかどうかの判断基準は必ずしも明確に規定されているわけではないため、その判断に迷う場合には法律の専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。
強行法規(強行規定)
強行法規(強行規定)とは、公の秩序に関する規定のことをいいます。より具体的に言い変えれば、当事者の意思に左右されずに強制的に適用されるのが強行法規です。強行規定に反するような契約をした場合には、その契約はその部分について無効とされます。
強行法規の例として、消費者契約法が挙げられます。この法律は消費者を契約トラブルから守るために施行され、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。
例えば、「重要事項について事実と異なることを告げられた」「消費者が通常必要とする分量以上のものの購入をすすめられた」「退去困難な場所に移動させて、逃げられない場所で購入をすすめた」など、不当な勧誘により締結させられた契約は後から取り消すことが可能です(参考:「知っていますか?消費者契約法|消費者庁」)。
このように、強行法規は立場の弱い人が不当な不利益を被る事態を防ぐ防波堤としての役割を担っています。
民法で定められている契約の種類
民法には13種類の契約に関する規定が存在します。これらの契約は「典型契約(有名契約)」とも呼ばれています。
典型契約に含まれるのは次の13種類の契約です。
- 贈与
- 売買
- 交換
- 消費貸借
- 使用貸借
- 賃貸借
- 雇用
- 請負
- 委任
- 寄託
- 組合
- 終身定期金
- 和解
ここでは、13種類の契約を4グループに分けて解説しますので、各契約の概要をおさえておきましょう。

民法では日常生活に関わるさまざまなルールを規定している
贈与・売買・交換
贈与契約、売買契約、交換契約は、いずれも物や権利の所有権を移転する契約形態です。
贈与契約は、無償で物を渡す契約で、贈与者が受贈者に対して物を与えることを約束します。売買契約は、物やサービスを対価と引き換えに提供する契約で、売主と買主の間で価格が合意されることが重要です。交換契約は、物と物を交換する契約で、双方が提供する物の価値が等しいことが基本となります。
これらの契約は、日常生活の中で頻繁に行われるものであり、契約内容や条件を明確にしておくことが重要です。特に売買契約では、価格や支払い方法、引き渡しの時期などを詳細に取り決めることで、後々のトラブルを避けることができます。
なお、売買契約について詳しく知りたい方は下記記事もご一読ください。
消費貸借・使用貸借・賃貸借
消費貸借契約、使用貸借契約、賃貸借契約は、物や金銭の貸し借りに関する契約です。
消費貸借契約は金銭や消耗品を借りて、同等のものを返す契約で、利息の有無が重要なポイントとなります。なお、金銭の貸し借りが対象となる場合には「金銭消費貸借契約」と呼ばれます。
使用貸借契約は、物を無償で借りて使用し、返却する契約で、貸主と借主の信頼関係が基盤となります。
賃貸借契約は、物を一定期間貸し、賃料を受け取る契約です。賃貸借契約では、契約期間や賃料、物の使用目的などを明確にし、双方が納得した上で締結することが求められます。これにより、契約期間中のトラブルを未然に防ぐことができます。
金銭消費貸借契約や賃貸借契約について詳しく知りたい方は下記記事も参考にしてみてください。
雇用・請負・委任・寄託
雇用契約、請負契約、委任契約、寄託契約は、何らかのサービス(役務)を提供する際に締結する契約であることから「役務提供型契約」とも呼ばれます。
雇用契約は、労働者が使用者に対して労働を提供し、対価として賃金を受け取る契約で、労働条件の明確化が重要です。請負契約は、特定の仕事を完成させることを目的とした契約で、成果物の品質や納期が重視されます。
委任契約は、特定の事務処理を他者に依頼する契約で、信頼関係が基盤となります。寄託契約は、物を預ける契約で、受託者が物を適切に管理する義務を負います。
いずれの契約も、業務の効率化や専門性の活用に寄与するため、企業内では締結する機会が比較的多いといえるでしょう。
なお、雇用契約、請負契約、委任契約については下記記事で詳しく解説していますので、気になる方はあわせてご一読ください。
その他(組合・終身定期金・和解)
その他の契約には、組合契約、終身定期金契約、和解契約があります。これらの契約は、特定の状況や目的に応じて活用され、適切に締結することで、関係者間の信頼を構築します。
組合契約は、共同で事業を行うための契約で、メンバー間の役割や責任を明確にします。終身定期金契約は、当事者の一方(定期金債務者)が、相手方(定期金権利者)または第三者の死亡に至るまで、定期的に金銭その他の物を給付することを内容とする契約です。
また、和解契約は、紛争を解決するための契約で、双方が妥協点を見つけることが目的として締結するものです。
未成年者の契約の取り消しとは
未成年者が契約を締結する場合、法律上の特別な保護が与えられています。これは、未成年者が十分な判断能力を持たない可能性があるため、誤った判断で不利益を被ることを防ぐための対応です。
具体的には、未成年者が親権者や法定代理人の同意を得ずに契約を結んだ場合で、以下の要件にすべて当てはまると、その契約は「取り消し可能」となります。取り消し可能とは、後から契約を無効にできるという意味です。
【未成年者契約の取消しの要件】
- 契約時の年齢が18歳未満であること
- 契約当事者が婚姻の経験がないこと
- 法定代理人が同意していないこと
- 法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
- 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
- 未成年者が「成年者である」「親の同意を得ている」などと偽っていないこと
- 法定代理人の追認がないこと
- 取消権が時効になっていないこと
この取り消し権は、未成年者自身やその親権者、法定代理人によって行使できます。取り消しが行われると、契約は初めから存在しなかったことになります。これにより、未成年者は不利な契約から解放され、元の状態に戻ることができるのです。
ただし、取り消しが可能な期間には制限があり、通常は成人に達するまで、または契約締結後一定期間内に行使する必要があります。
なお、未成年者の契約について、専門家に相談したい場合には、全国の消費生活センター等に問い合わせるのがよいでしょう。消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。詳しい問い合わせ先については下記リンクを参照してください。
>全国の消費生活センター等(独立行政法人 国民生活センター)
契約に関するトラブルが起きた場合はどうする?
契約に関するトラブルが発生した場合、まずは契約書を再確認することが重要です。契約書には、双方の権利や義務が明記されていますので、問題の原因を特定する手がかりとなります。特に、契約書に記載された条項や条件がどのように解釈されるべきかを理解することが、問題解決への第一歩です。
次に、当事者間での話し合いを試みましょう。誤解やコミュニケーション不足が原因でトラブルが発生している場合も多いので、冷静に状況を確認し、お互いの立場を理解することが大切です。
それでも解決しない場合は、第三者の専門家に相談することを検討します。弁護士や公正証書役場の専門家に相談することで、法的な視点からのアドバイスを受けることができます。
それでも解決が難しい場合、調停や仲裁といった法的手段を考慮することも選択肢のひとつです。これにより、裁判を避けつつ問題解決を図ることができます。
電子契約で実現できる契約業務の効率化
ここまで契約の基礎知識と重要なポイントについて解説してきましたが、日々の契約業務には、紙の契約書ならではの課題も少なくありません。例えば、印刷、押印、郵送、そして保管場所の確保や、必要な書類を探す手間など、意外と多くの時間とコストがかかっているのではないでしょうか。
こうした課題を解決し、業務効率を飛躍的に向上させるのが「電子契約」です。
電子契約とは、インターネットを介して契約を締結する方法であり、紙の契約書をデジタル化することで業務の効率化を図る手段です。
具体的には、契約書の作成から送付、締結、そして保管までの一連のプロセスをデジタル化できるため、「印刷・郵送コストの削減」「契約締結までの時間の短縮」「保管スペースの不要化と検索性の向上」「押印や郵送といった物理的な手間の削減」といったメリットが期待できます。
現在の契約業務に非効率さを感じているのであれば、電子契約による契約書の電子化は、まさに検討すべき選択肢のひとつになるでしょう。まずは関連情報を集め、電子契約が現状の業務にもたらす具体的なメリットを考えてみてはいかがでしょうか。
なお、クラウドサインでは契約書の電子化を検討している方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部