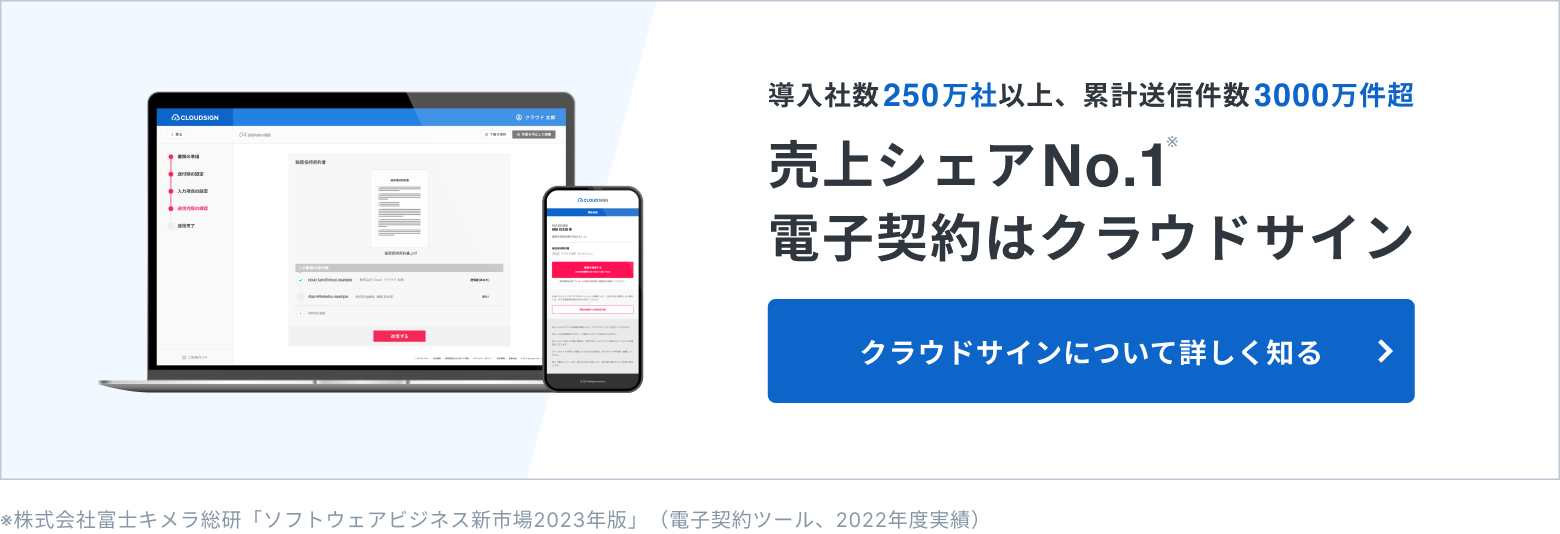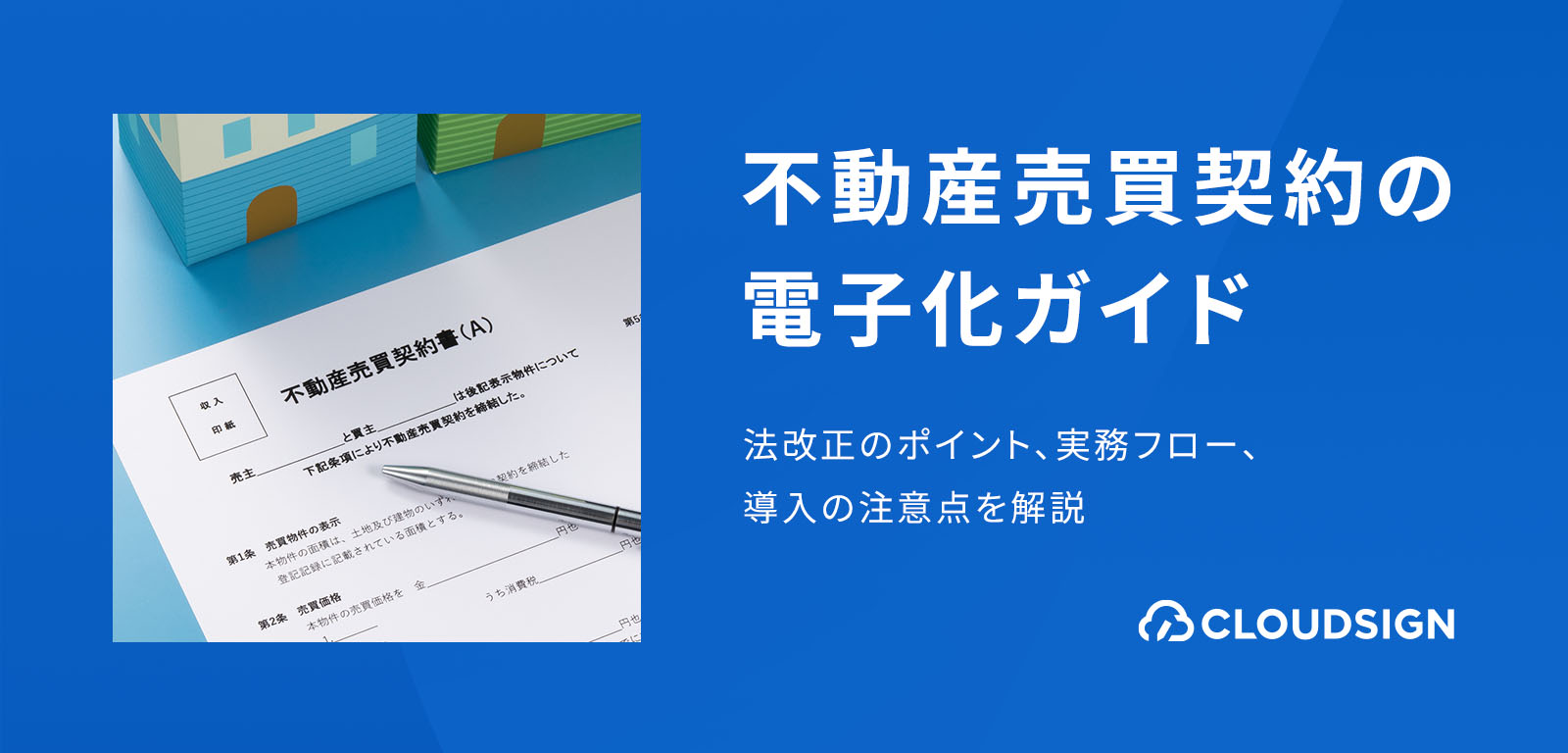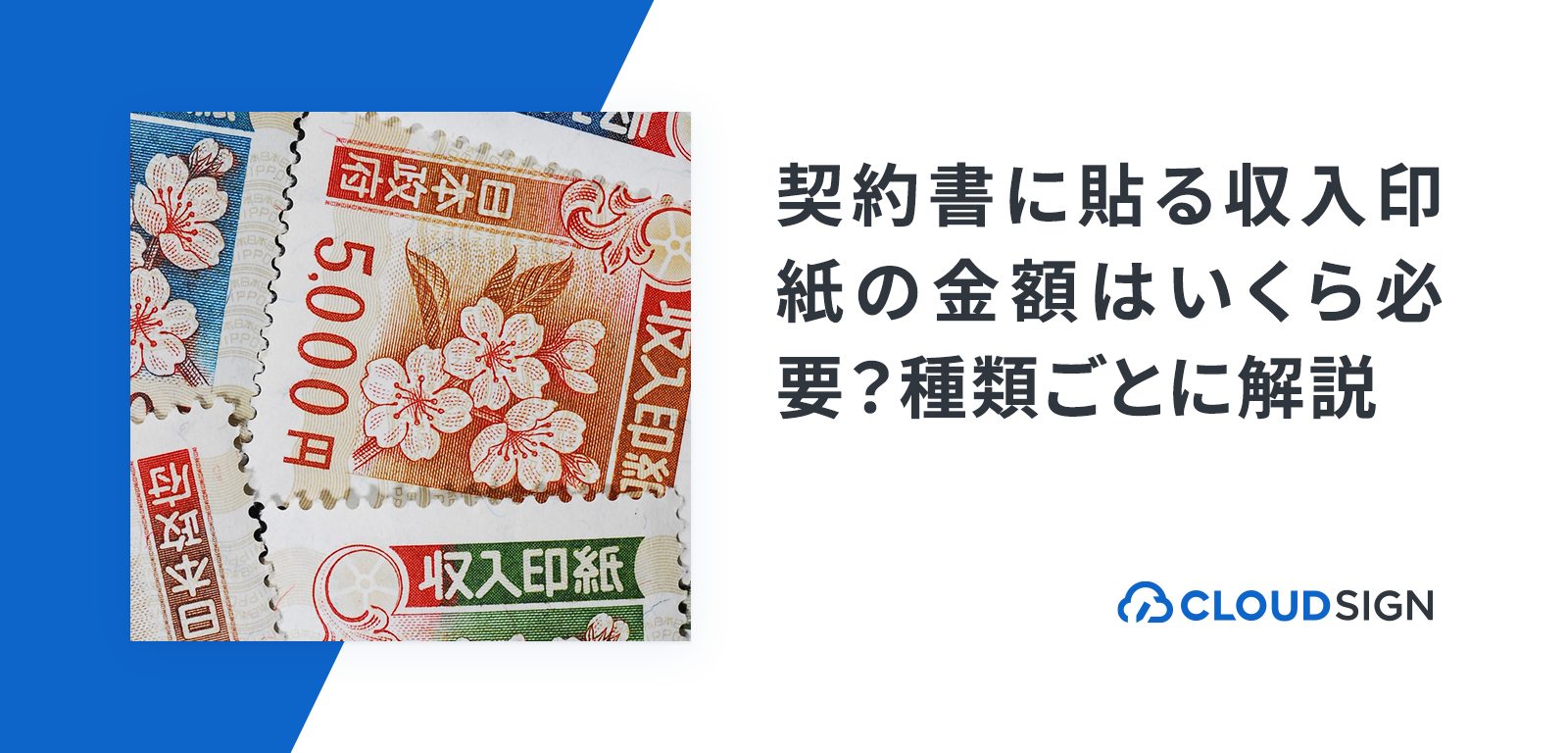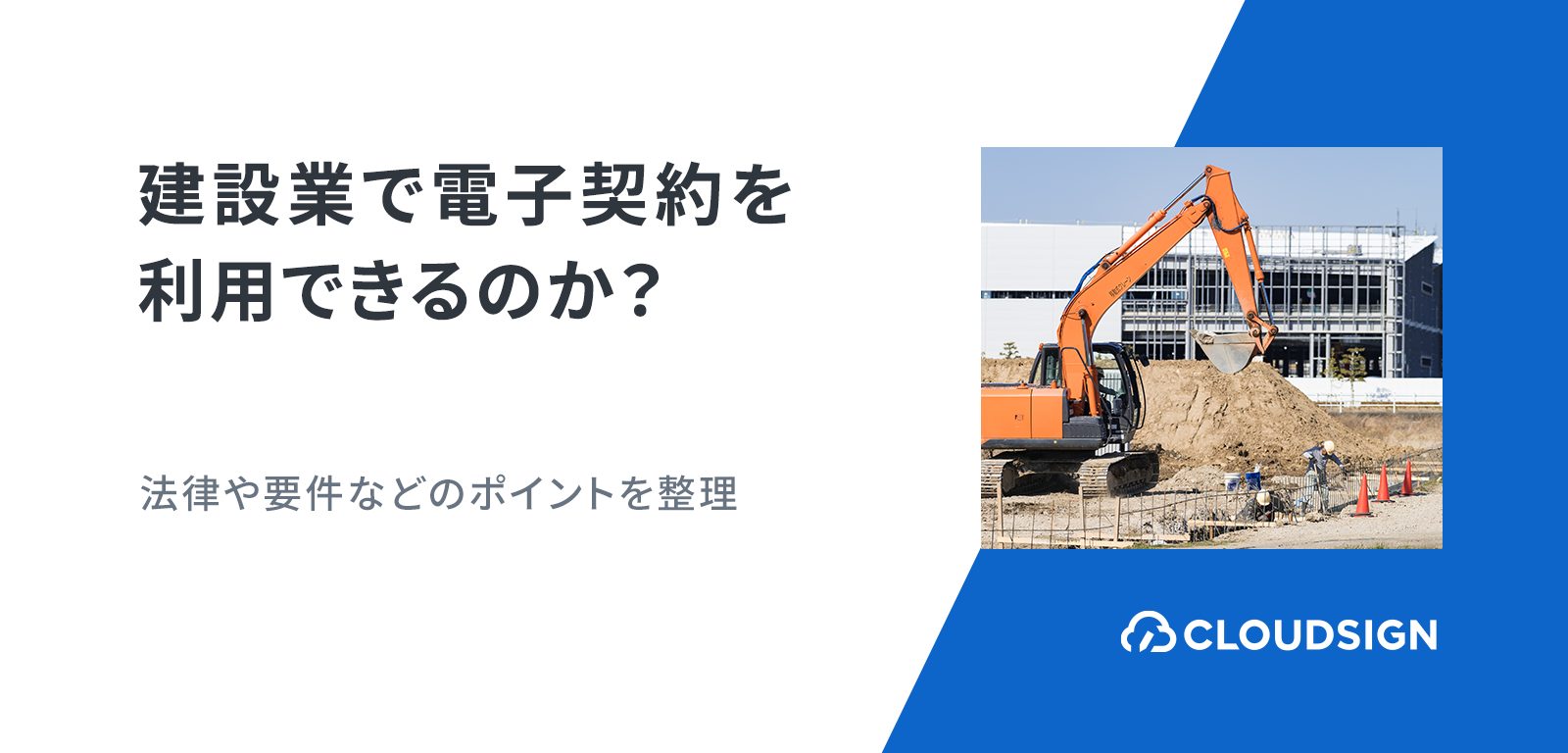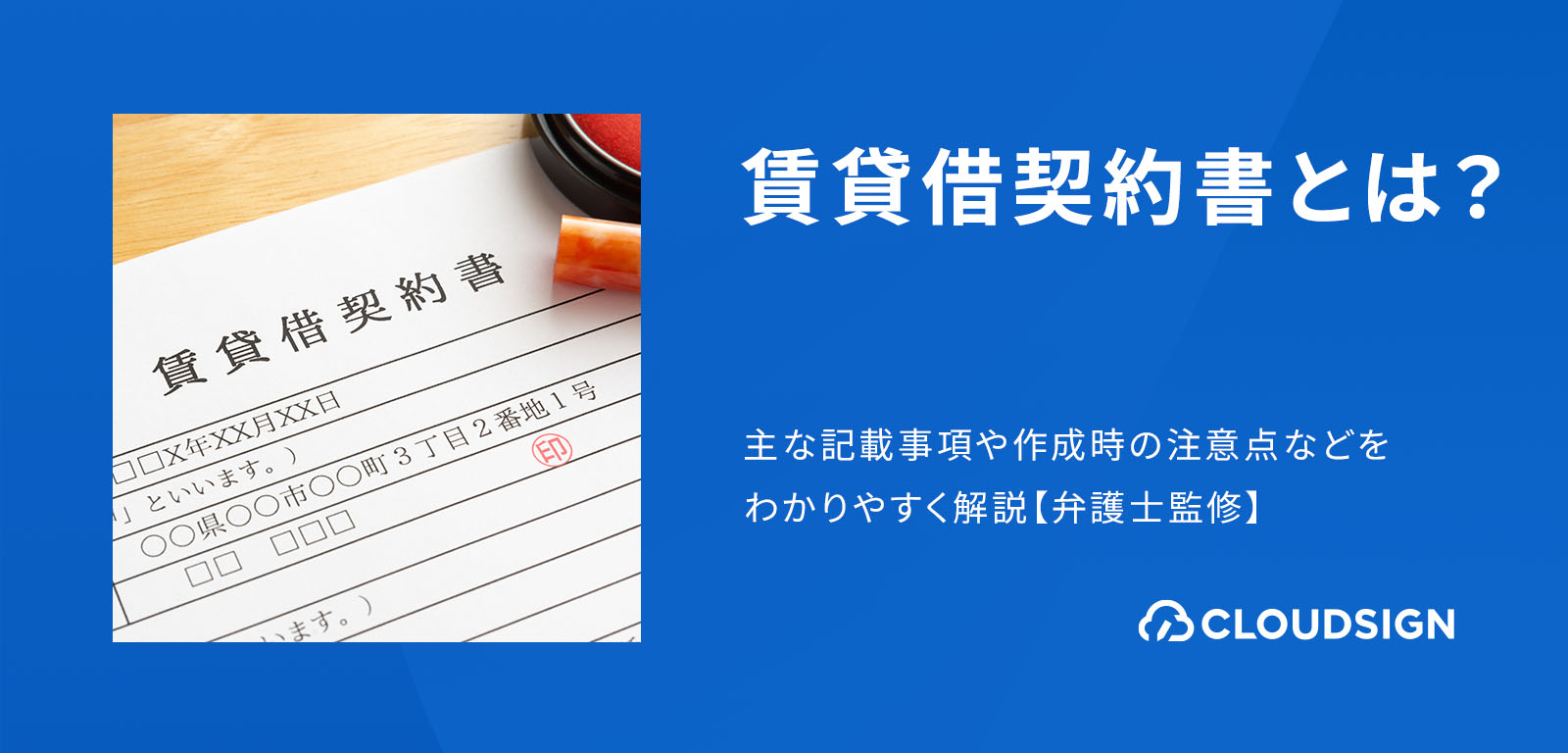賃貸借契約書はいつまで保管すべき?保管期間や保管方法などを解説【弁護士監修】
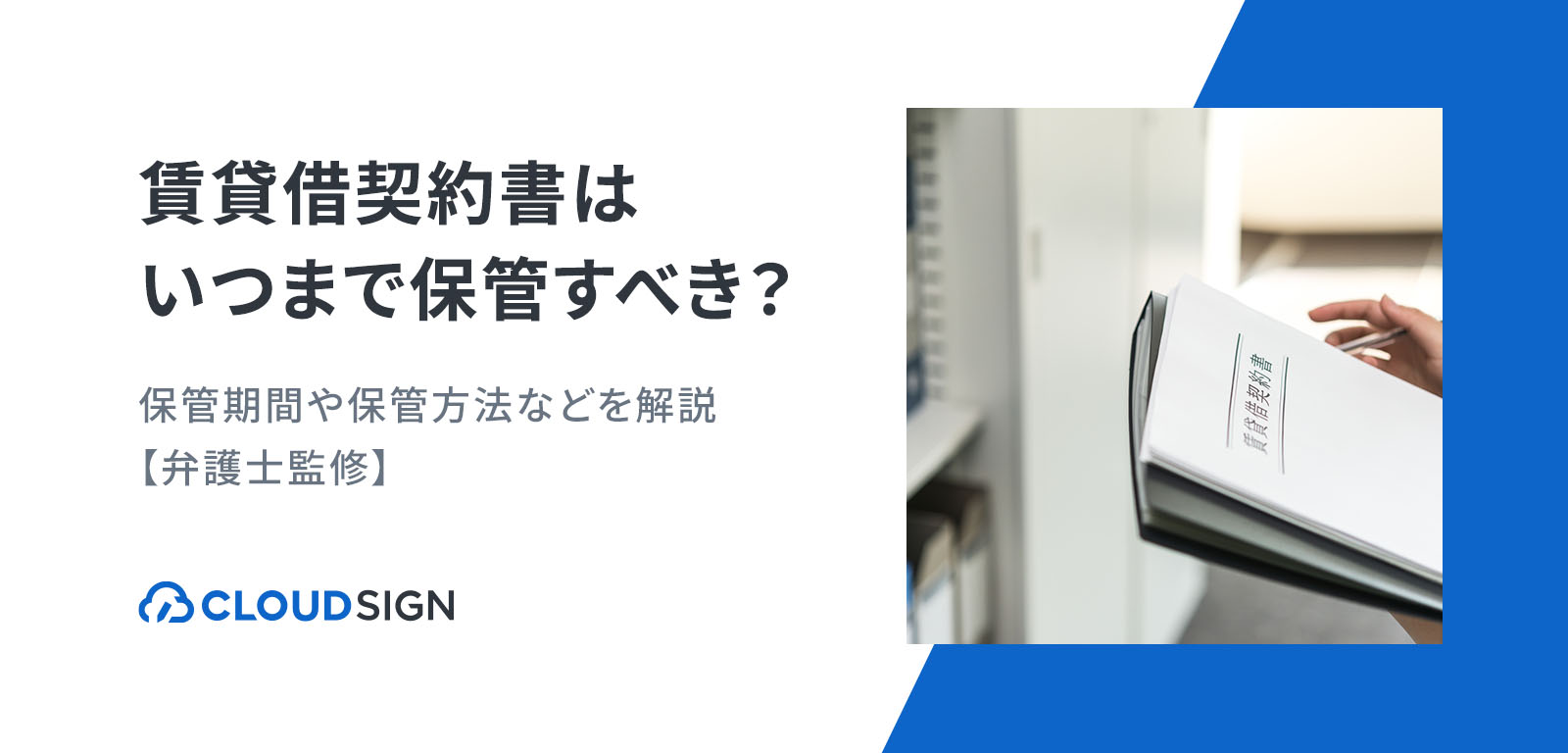
賃貸借契約書は、主に不動産の貸し借りをするときに締結する契約書です。不動産を所有している事業者や、店舗・事務所などとして建物を借りている事業者は、賃貸借契約書を締結する機会があります。
締結した賃貸借契約書は、適切な形で保管しておきましょう。しかし、永遠に保管するわけにもいかないため、どこかの段階で破棄することになります。いつまで賃貸借契約書を保管すればよいのでしょうか?
当記事では、賃貸借契約書の保管期間や保管方法などを解説します。
なお、契約書の保管期間は法律で定められていますが、その管理には手間もコストもかかります。こうした課題は、電子契約サービスを利用することで解決が可能です。電子契約なら、保管スペースは不要になり、検索も容易になります。電子契約について詳しく知りたい方は、こちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード
目次
賃貸借契約書の保管期間はいつまで?
賃貸借契約書は、締結したら長期間にわたって保管する必要があります。保管すべき期間は法人と個人のどちらであるかや、経理の状況などによって5年・7年・10年などと異なります。
賃貸借契約書を保管すべき理由
賃貸借契約書を保管すべき理由としては、主に以下の3点が挙げられます。
契約条件をいつでも確認できるようにするため
賃貸借の期間や更新の時期、賃貸物件の使用に関するルールなどの契約条件は、賃貸借契約書に記載されています。賃貸借契約書をきちんと保管しておくことで、契約条件をいつでもスムーズに確認することができます。
契約トラブルに備えるため
賃貸借について契約トラブルが発生した場合、契約条件は賃貸借契約書の記載によって証明します。裁判所で訴訟が行われる際にも、賃貸借契約書を証拠として提出することができます。
税務調査に備えるため
納税が正しく行われているかどうかを確認する税務調査では、事業に関する書類のチェックが行われることもあります。
賃貸物件を事務所や店舗などとして使用している場合は、事業に関する書類として賃貸借契約書もチェックの対象となるため、きちんと保管しておかなければなりません。
賃貸借契約書の保管期間を決める際の着眼点
賃貸借契約書の保管期間を決める際には、主に以下の2点に着眼するとよいでしょう。
法律上の保存義務がある期間
法人税法や所得税法では、事業に関する帳簿書類を一定期間保存することが義務付けられています。少なくとも、保存義務がある期間は賃貸借契約書を保管しなければなりません。
契約トラブルが発生し得る期間
契約トラブルが発生し得る期間は、賃貸借が終了した後でも賃貸借契約書を保管しておくことが望ましいです。債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効期間が参考になります。
なお、賃貸借契約書の保管について詳しく解説する前に「そもそも賃貸借契約書とは何か、どうやって作るのか」といった基本的な内容を知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
【法人の場合】賃貸借契約書の保管期間は「契約終了後7年2か月」以上
法人(会社など)が締結した賃貸借契約書は、少なくとも契約終了後7年2か月が経過するまで保管を続ける必要があります。また、経理や契約トラブルなどの状況によっては、さらに長期間保管すべきケースもあります。
賃貸借契約書は税務上の帳簿書類|7年2か月間は保存が必要
会社を含む普通法人等は、以下の書類を保存しなければなりません(法人税法施行規則67条2項)。賃貸借契約書は①の書類に該当します。
②棚卸表、貸借対照表および損益計算書ならびに決算に関して作成されたその他の書
上記の帳簿書類の保存期間は、事業年度終了日の翌日から2か月後の日から起算して7年間です。
たとえば、2025年3月31日に終了する事業年度に関する帳簿書類は、2025年6月1日から7年後の2032年5月31日まで保存する必要があります。「事業年度終了後7年2か月」は保存が必要ということです。
賃貸借契約書を締結した事業年度だけでなく、契約期間が含まれる全ての事業年度が保存義務の対象となります。
したがって、賃貸借が終了した事業年度が終了した後、7年2か月が経過するまでは賃貸借契約書を保存しなければなりません。
欠損金の繰越控除を受ける場合は、10年2か月間の保存が必要
青色申告を行った事業年度において生じた欠損金は、その後10年にわたって繰り越して損金に計上することが認められています(法人税法57条)。
欠損金の繰越控除を受ける場合には、事業年度終了日の翌日から2か月後の日から起算して10年間、事業に関する帳簿書類を保存しなければなりません(法人税法施行規則26条の3)。原則である「7年2か月」ではなく、「10年2か月」の保存が必要です。
賃貸借契約書についても、契約期間が含まれる事業年度について欠損金の繰越控除を受ける場合は、その事業年度が終了してから10年2か月間は保存を続ける必要があります。
実際には、欠損金の繰越控除を受ける事業年度(のうち最も遅いもの)の終了から10年2か月後と、賃貸借が終了した事業年度の終了から7年2か月後を比較して、いずれか遅い方まで賃貸借契約書の保存義務が続きます。
賃貸借期間は2020年8月1日~2025年7月31日の5年間
事業年度は4月1日~翌年3月31日
①2020年4月1日~2021年3月31日の事業年度のみ、欠損金の繰越控除を受けた場合
→賃貸借契約書の保存義務は2033年5月31日まで(=2026年3月31日の7年2か月後)②2024年4月1日~2025年3月31日の事業年度のみ、欠損金の繰越控除を受けた場合
→賃貸借契約書の保存義務は2035年5月31日まで(=2025年3月31日の10年2か月後)
参考:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁
契約トラブルが発生している間は、引き続き賃貸借契約書を保管すべき
税務上の帳簿書類の保存義務とは別に、賃貸借契約に関するトラブルが発生している間は、賃貸借契約書を引き続き保管すべきです。
たとえば以下のようなケースでは、トラブルが収束するまで賃貸借契約書を保管しておきましょう。
・貸主から未払い賃料を請求されている場合(借主に対して未払い賃料を請求している場合)
・無断転貸や用法違反などを理由に、貸主から損害賠償を請求されている場合(借主に対して損害賠償を請求している場合)
・敷金の返還や原状回復についてトラブルが発生している場合
など
【個人の場合】賃貸借契約書の保管期間は「契約終了後5年3か月」以上
個人が締結する賃貸借契約書については、法人とは保存期間が異なります。少なくとも契約終了後5年3か月は保管が必要ですが、トラブルのリスクがある場合はさらに長期間の保存しておきましょう。
個人事業主の場合、税務上5年3か月間は保存が必要
個人事業主は、事業所得に関する帳簿書類を一定期間保存しなければなりません。
賃貸借契約書を含む書類の保存期間は、当該年の翌年3月16日から5年間とされています(所得税法施行規則102条4項)。
たとえば、2025年の事業所得に関する書類は、2026年3月16日から5年後の2031年3月15日まで保存する必要があります。おおむね「年度終了後5年3か月」は保存が必要と理解しておきましょう。
個人事業主の場合も法人と同様に、賃貸借契約書を締結した事業年度だけでなく、契約期間が含まれる全ての事業年度が保存義務の対象となります。
したがって、賃貸借が終了した年が終わってから5年3か月が経過するまでは、賃貸借契約書を保管しておきましょう。
なお、事業所得がある場合と同じく、不動産所得がある場合も上記のルールが適用されます。所有している不動産を貸して賃料収入を得ている場合などには、税務調査に備えて賃貸借契約書を保管しなければなりません。
事業所得や不動産所得がなくても、トラブルに備えて契約終了後一定期間は保管すべき
事業所得や不動産所得がない場合(例:給与所得者で自宅を借りている場合など)でも、トラブルに備えて賃貸借契約書を保管しておくべきです。
契約トラブルのリスクがなくなる時期がいつかは一概に言えませんが、債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効期間が参考になります。時効期間が過ぎれば、何らかの理由で損害賠償を請求されても、時効を援用すれば債務を免れる可能性が高いです。
債務不履行に基づく損害賠償請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効によって消滅します(民法166条1項)。
②権利を行使できる時から10年※最後に賃貸借が更新された日(一度も更新されていない場合は賃貸借の開始日)が2020年3月31日以前の場合は、(一律で)権利を行使できる時から10年
少なくとも賃貸借が終了してから5年、できれば念のため10年は、賃貸借契約書を保管し続けることが望ましいです。
なお、時効期間の途中で相手方から内容証明郵便が送られてきたり、賃料や損害賠償を支払ったりすると、時効が完成しなくなることがあります。その場合は、賃貸借契約書をさらに長期間保管する必要が生じるのでご注意ください。
賃貸借契約書の主な保管方法
賃貸借契約書の保管方法は、主に以下の3つです。
①紙のまま保管する
紙で締結した賃貸借契約書は、紙のまま保管するのが最も一般的です。なお、紙の契約書には印紙税がかかります。賃貸借契約書に印紙がかかるのかどうかについてはこちらの記事もご覧ください。
②マイクロフィルムで保管する
紙で締結した賃貸借契約書は、マイクロフィルム化して保管する方法もあります。マイクロフィルムは紙よりも長期保存が可能で、保管スペースを節約でき、改ざんが難しいなどのメリットがあります。
③電子データで保管する
賃貸借契約書を電子データで保管すると、管理や検索がしやすくなって便利です。紙の賃貸借契約書をスキャンして保存する場合と、最初から電子契約を締結してデータを保存する場合の2パターンがあります。
賃貸借契約を電子契約にする方法について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
賃貸借契約書を電子データで保管する際の注意点
事業所得や不動産所得がある法人や個人が、その所得に関して税法上保存義務を負う賃貸借契約書を電子データで保管する場合は、電子帳簿保存法のルールを遵守しなければなりません。
電子帳簿保存法では、紙の賃貸借契約書をスキャン保存する場合と、電子契約のデータを保存する場合のそれぞれについて満たすべき要件が定められています。
スキャン保存する際に満たすべき要件
紙の賃貸借契約書をスキャン保存する場合は、以下の要件を満たさなければなりません。
- 書類の受領等後または業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかにスキャンする。
- 一定水準以上の解像度(200dpi以上)によってスキャンする。
- カラー画像(赤、緑、青それぞれ256階調(約1677万色)以上)によってスキャンする。
- タイムスタンプを付与する。
- 解像度および階調情報を保存する。
- 大きさ情報を保存する。
- ヴァージョン管理を行い、訂正または削除の事実および内容を確認する。
- 入力者等情報を確認する。
- 書類の受領等からスキャンまでの各事務を適正に処理するための要件を満たす。
- スキャン文書と帳簿との相互関連性を保持する。
- 見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)を備え付け、スキャンデータを整然かつ明瞭に出力できるようにする。
- 電子計算機処理システムのマニュアルなどを備え付ける。
- 検索機能を確保する。
電子契約のデータを保存する際に満たすべき要件
賃貸借契約書を最初から電子契約として締結し、そのデータを保存する際には、「真実性」と「可視性」の要件を満たさなければなりません。
真実性
データの改ざんを防ぐため、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
- タイムスタンプを事前に付与する。
- 契約締結後、おおむね7営業日以内(事務処理規程を定めている場合は+2か月)にタイムスタンプを付与する。
- 訂正や削除の履歴が確認できるシステム、または訂正や削除ができないシステムを通じてデータを授受する。
- 正当な理由のない訂正や削除を防ぐための事務処理規程を定め、その規程を適切に運用してデータを保存する。
可視性
データをスムーズに出力して確認できるように、以下の措置を講じなければなりません。
- 出力用の機器(PC、ディスプレイ、プリンターなど)と、その機器の操作説明書を備え付ける。
- 検索機能を確保する。
- 自作のプログラムを用いている場合などには、電子計算機処理システムの概要書や操作説明書を備え付ける。
- データの保存などに関する事務処理規程を定め、備え付ける。
ただし、可視性の要件の一つである検索機能の確保は、免除される場合もあります。検索機能の確保が免除される場合については、国税庁の資料をご確認ください。
まとめ
賃貸借契約書は、契約トラブルや税務調査に備えるため、契約期間中はもちろん、契約終了後も一定期間は保管するしなければなりません。
法人の場合は契約終了後7年2か月以上、個人事業主の場合は契約終了後5年3か月以上の保管が必要です。状況によっては、さらに長期間の保存が必要になります。
賃貸借契約書を電子データで保存する際には、電子帳簿保存法の要件を満たさなければならない点にもご注意ください。
ここまで解説してきたように、賃貸借契約書をはじめとする各種契約書は、法律で定められた長期間の保管が義務付けられています。
「紙の契約書が多くて保管場所に困っている」
「過去の契約書を探すのに時間がかかる」
「電子帳簿保存法の要件が複雑で、正しく対応できているか不安」
このような課題は、電子契約サービスを導入することで解決できます。
電子契約なら、物理的な保管スペースは不要になり、検索機能で必要な契約書をすぐに見つけ出すことが可能です。また、電子帳簿保存法の要件に対応したサービスを選べば、法改正を気にすることなく、安心して契約書の管理を行えます。「クラウドサイン」はこれらに対応しているため簡単かつ安心してご利用いただけます。
なお、電子契約サービスに興味がおありの方に向け、3分でわかるサービス説明資料をご用意しておりますので、無料でダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約を検討する方に向け、電子契約の知識を深めるためにすぐわかる資料をご用意しました。電子契約サービスやクラウドサインについて詳しく知りたい方はダウンロードしてご活用ください
ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。